| 第二十番 善峯寺 野をも過ぎ 山路に向かう雨の空 善峯よりも晴るる夕立 |
善峯寺へはバイクのタンデムで参詣した。
バイクに乗るには少し暑い日でバイク用のジャケットを着ると汗ばんだ。
名神高速道路を大山崎で下り川に沿って左折をし、珍しく余り迷わないで行き着いた。
途中の道は竹の町にふさわしくきれいな竹林が続いている。道は普通車がすれ違うのがやっとで、バイクのありがたさを感じた。
山の下に広い駐車場があり、境内に近いところには有料の駐車場がある。いったんその駐車場に入りかけたがこちらはバイクであり、また戻って無料駐車場に置いた。
駐車場から程なく小さな赤い橋があり、そこから曲がりくねった急坂を登っていく。かなり急勾配の石段の参道を上がると、大きな山門が眼前に現れる。
非常に複雑な造りであり、由緒正しい寺の感じがする。現存の山門は元禄5年(1692年)桂昌院によって再建されたものといわれ、山門両脇の金剛力士像は運慶の作という。
パンフレットでは、
「善峯寺は、長元2年(1029年)に源算上人が開山した。源算上人は、因幡生まれで恵心僧都の高弟であり、47歳の時この山に小堂を結んだ。
長元7年9月後一条天皇より、鎮護国家の勅願所と定められ良峯寺の寺号と詠を賜わった。
長久3年、後朱雀天皇の時に洛東鷲尾寺より仁弘法師作の十一面千手観音像を当山に遷して本尊とした。
室町時代の最盛期には僧坊も52及び隆盛を極めたが、応仁の乱の兵火により焦土と化した。
その後徳川五代将軍の生母である桂昌院が復旧し、石高二百石及び山林42万5千坪を寺領とし明治に至った。重要文化財として、多宝塔・大元師明王軸 その他文化財多数」とある。京都の西に位置し、現在でも雰囲気のいい境内であるが、往時には今以上に広くいい建物があったに違いない。
ここで面白かったのは松で、「遊龍の松」と名付けられており、その名の通り龍がこれから飛び上がろうとするような形で太い幹が水平に延び、貫禄があった。樹齢600年を五葉松で天然記念物に指定されているという。
これまであちこちの松を見てきたが、この松はすごい。
またこの寺は京都の紅葉の隠れ名所らしく、まだ緑のカエデが境内一面にあったが秋にそれらが紅葉すれば見事であることが想像できた。
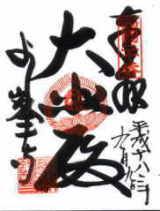
朱印をもらうとき社務所を見ると阪神大震災のバスが落ちかけている写真があり、なんだろうとよく読むと、墜落を免れたバスの運転手さんがここ善峯寺のお守りを持っていたことで「落ちない」御守りとして、その後受験生に人気が広まったという。
九死に一生のあの瞬間、たまたま提げていたお守りがここのものだったのである。
昔であれば、猛獣に遭遇したがお守りを持っていたおかげで助かったという物語ができそうであるが、現在では物語にするのは難しい。やはりこうした幸運のあやかろうというのはいつの時代でも同じである。
もともとは、神経痛や腰痛を取ってくれるお寺として有名らしい。あの震災以来、命を守ってくれるという御利益が増えたのである。
境内の各建物に行くには案内板に沿ってアップダウンを繰り返す。
釈迦堂の隣には薬湯場があり、神経痛、腰痛は勿論諸病に特効がありという。
5月と10月の第2日曜日の8時より午後3時まで入浴が可能と言うことで、一度入ってみたいものである。
境内もよく整備されており、なかなかいいお寺である。
境内からは京の街並が一望できる。

(前を行く親子連れバイク) |
 |
 |
 |

(複雑な作りの山門) |

(本堂は割にシンプル) |
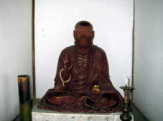
(びんづるさま) |
 |
 |

(天然記念物 「遊龍の松」) |
 |
 |

(京都が一望できる) |
|
|