久しく33カ所巡りをしていなかった。
しかしどうも寝覚めが悪いので、連休明けに走ることにした。
5月8日の仏の舞の日にあわせた。和歌山を朝、9時に出発した。
仏の舞開始は12時頃と聞いていたので、間に合うか少し心配だったが、走った。
舞鶴には11時半頃ついた。
我が家からふるさとの串本までは3時間半だからそれより早い時間で日本海に着くことになる。
こんな時、高速道路のありがたさを感じる。
食事をしたかったが、時間がないのでそのまま案内表示の通りに松尾寺まで坂を登った。
道は狭くすれ違いが困難な場所もあった。
寺に着くとちょうど僧侶軍団が歩き始めたところで、何とか間に合った。
ちょうど3時間で到着したことになる。
寺へはすぐ下の駐車場に車を駐め、200mほど歩いた。
駐車場では核兵器撲滅のための署名活動をしていた。
私たちも署名をした。
松尾寺本堂へは少し急な石段があり、登り切ると仁王門がある。
江戸中期の建造ということだがなかなかの威厳でたっている。
門の下の空間には牡丹が咲いていた。
境内には巨大な銀杏の木があり、木陰でお年寄りが根っこに腰をかけ憩っていた。
鳥羽天皇お手植えと伝わる。
松尾寺は、宗派は真言宗醍醐派、本尊は座像馬頭観世音菩薩、開基は威光上人という。
西国33カ所で馬頭観音を本尊としているのはここだけである。
パンフレットには、
「中国から渡来した威光上人が、青葉山中の松の大木の下で修行中に馬頭観音像を感得し、慶雲5年(708年)にこの松の木の下に草庵を造り、観音像を安置したのが松尾寺の創始とされている。このことが都に伝わり、8世紀初頭に元明天皇(707~715年)が藤原武智麻呂に命じ、本堂を建立させ、馬頭観音を刻ませたという。戦国時代には大寺となっていたが、織田信長の攻めにあい全焼、復興したのは享保15年(1730年)という」
といったことを書いている。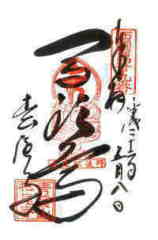 ここ松尾寺では、毎年卯月8日(現5月8日)には今日の参詣のもう一つの目的である、仏の舞(国重要無形民俗文化財)が行われる。 ここ松尾寺では、毎年卯月8日(現5月8日)には今日の参詣のもう一つの目的である、仏の舞(国重要無形民俗文化財)が行われる。
ここでは花祭りの一環としてこの時期に奉納されるという。
そのためかお釈迦様にお茶をかける。
仏の舞は、大日如来・阿弥陀如来・釈迦如来のそれぞれの面をつけた6人の檀家が、舞楽にあわせて優雅に舞う。仏の舞の起源は不詳であるが、「楽舞の菩薩」といわれるものを基本としたゆったりとしたな旋律の舞楽で、奈良の宮廷舞楽が遠く日本海側まで広がり民間芸能として、ここ松尾寺に定着したものかもしれない。
一年一度のイベントに出会えたことがうれしい。
いずれにしろ、当時の人が田植えなどの前に行う、豊作を願う娯楽だったのではないかと思う。
仏の舞は、僧侶が10人ほど2列に並び、その後を檀家の方が続く。
本堂でのひとしきりの読経があり、舞楽の演奏とともに仏様が厳かに出てくる。
これはお面をかぶっているので、前が見えないために早く歩けないせいでもある。
建物の角にくると介添えの方が仏様の体を回してガイドしていた。
舞楽のリズムは単調であるが、退屈でない響きでその音と舞に引き込まれた。
西国三十三霊場の中では唯一観音像を本尊とするというが、馬頭観音は片膝をたてて座っていた。 。 。
馬頭観音は、農耕や牛馬畜産、車馬交通の守り仏として広く信仰されていたが、最近は競馬関係者や万馬券に夢を賭ける参拝者もいるらしい。そんな濡れ手に粟を期待する人には霊験を与えなくてもよろしいね。
境内には資料館があるがそこには、国宝の仏画「普賢延命菩薩像(平安時代)」をはじめとして、重文の仏像「阿弥陀如来坐像 (快慶作)」、重文の仏画「孔雀明王像(鎌倉時代)」、「法華曼荼羅(鎌倉時代)」、「如意輪観音像(鎌倉時代)」などが展示されている。入館には800円必要である。
資料館の中で、ご住職が新聞記者のような人に語っているのをそばで聞いていたが、結論的なことはいっていなかった。
どうも焼き討ちにあうと資料が散逸あるいは消失して本当のところがわからなくなる。
|