分野別メニューへ戻る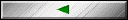
|
記事メニューへ戻る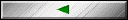
|
水産庁実験へ、 温暖化も防止
海の深いところにあり、栄養分が豊富な「海洋深層水」をくみ上げ、魚があまり取れない海域にまき、好漁場を人工的に造り出す−−。こんな研究実験が四月から、水産庁を中心に始まる。
海洋深層水は水深がおおむね200mより深く、太陽の光が届かないところにある海水。海藻や植物プランクトンの光合成が行われないため、海水中の窒素やリンなどの栄養分が消費されずに残っている。海面に波の力を利用した自家発電装置を備えたポンプを浮かべて、海底の取水口から深層水をくみ卜げる。水面上でプロペラなどでかき回し、表面の海水と混ぜる。海水は潮流で拡散し、広い範囲で植物プランクトンが増殖する。一年程度でプランクトンをえさにする魚が集まり好漁場ができる、というプランだ。
一日当たり数十万トンくみ上げるが、深層水は世界の海水量の95%を占めており、はぼ無尽蔵の資源だ。植物プランクトンは、光合成で大気中の二酸化炭素を吸収する役割もあることから、漁場造成のはか、地球温暖化防止も狙えるという。五年後の実用化を目指す。
米国の研究によると、魚がよく取れる海域は、栄養分が豊富な海洋深層水が水面に上がってくる「湧昇流水域」とされ、これは海の全面積の0.1%に過ぎないが、世界の魚の約半数がここで生まれるという。
国内では養殖場などで、深層水を利用している例があるが、水産庁は「深層水を利用して外海に大現模な漁場を形成する試みは、世界でも初めてではないか」 (整備課)と話している。
研究は水産庁と、大手鉄鋼メーカーや建設会社、県漁達、大学などでつくる農水省の外郭団体「マリノフォーラム21」が共同で行う。2000年度は約三億円をかけ、具体的な実験方法を決めるほか、室内プールを使った実験にも書手する。