過ぎし春より、太白(金星)が牛斗(牽牛星と北斗星)のあたりで鎮星(土星)を犯し、 天津(天の川に横たわる九つ星)を通過しました。
これは建安元年(196)年の記述の中の注として書いてある部分です。 過ぎし春ですから前に遡りますと、確かに牛宿で195年12/1〜12/3に金星が土星に接近します。 おひつじ座付近ですね。ただし「犯」には少々距離が離れています。
【】書きで牽牛とありますが、現在で言うわし座のアルタイル(彦星)ではなく、 中国星座の二十八宿の牛宿です。
牛斗の「斗」は、場所が南のおひつじ座付近ですので、北の北斗七星ではあまりに広範囲に なってしまいますので、恐らく南斗(いて座の南斗六星)である斗宿の事でありましょう。
次いで195年2月10日(興平2年正月中)に「犯=0.6度」以下となります。 過ぎし春と言う表現が当てはまりますね。(南極老人星さん訂正感謝)
但し場所的には反対の西側に位置してしまいますが、逃げる途中船に乗ろうかとする時 ですので、「過ぎし日」と年月日を特定していなかったり、場所が多少違うのは 記憶で話していたからでしょうね。
これは少々無理があります。天津はこぎつね座付近ですので、天の川の中にありますが、 黄道からは大きく外れ鎮星(土星)は通りません。侍従があんまり詳しくないか、 、記憶違いか、状況からして慌てていたかでしょうね。
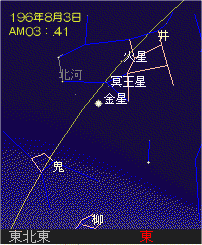 確かに火星は徐々に北河(ふたご座の上半身)まで近づきますが、逆行したり、
留になったりすることはないですね。
確かに火星は徐々に北河(ふたご座の上半身)まで近づきますが、逆行したり、
留になったりすることはないですね。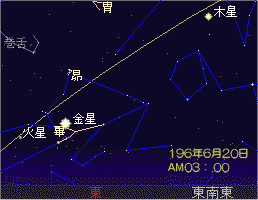 確かに金星と火星はおうし座で接近します。
確かに金星と火星はおうし座で接近します。 熒惑(けいわく)のケイ
熒惑(けいわく)のケイ 軹関(しかん)のシ
軹関(しかん)のシ