| ●黄道 |
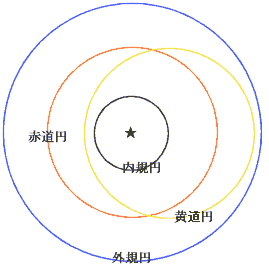 黄道は太陽の通り道のことで、赤道に対して約23.45度傾いています。大雑把に言えば、 黄道は太陽系の面で、赤道は地球の面と言い換えますと、そう!地球は傾いているのですね。 これを赤道座標・正距離方位図法で書くと左のような図となります。これがいわゆる天文図です。 左の図では赤道円と黄道円が2箇所交わったところがありますが、上側が春分点、下側が秋分点 となります。 この春分点・秋分点は「歳差」と言う地球のこま振り運動で動くことから時代を 割り出せないかと言うお話です。 |
| キトラ古墳2・黄道 |
| ●黄道 |
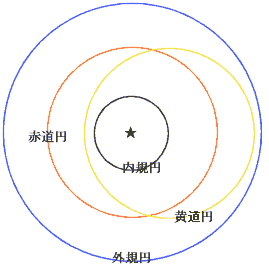 黄道は太陽の通り道のことで、赤道に対して約23.45度傾いています。大雑把に言えば、 黄道は太陽系の面で、赤道は地球の面と言い換えますと、そう!地球は傾いているのですね。 これを赤道座標・正距離方位図法で書くと左のような図となります。これがいわゆる天文図です。 左の図では赤道円と黄道円が2箇所交わったところがありますが、上側が春分点、下側が秋分点 となります。 この春分点・秋分点は「歳差」と言う地球のこま振り運動で動くことから時代を 割り出せないかと言うお話です。 |
| ●約16000年前? |
|
赤道の詳細は前ページを参照していただくとしまして、天球上では極軸に対して垂直な大円で あらわされますね。いわば地球が回転する面と言いかえられましょうか。 また別の言い方をすればお星様が沈む方向を表しているともいえます。(後述)問題にしている天文図では、この赤道の円が地球の円周と同じになるわけですね。
さて、黄道は太陽の通り道を表しています。 観測者が地球の中心にて地球と言うスクリーンに星が投影されている天球で考えますと、 赤道円と2点で交差(AとB)する大円となります。
言い変えますと、太陽と地球の面で、いわば一種の太陽系の面であるわけです。 赤道面と黄道面は地球の中心から見て、23.45度傾いて(角KOS)います。地球が傾いて自転しているとは このことですね。
赤道円と黄道円の2つの交点はそれぞれ「春分点」「秋分点」と言いまして、 地球がこの点を通過する日が「春分の日」「秋分の日」になります。太陽が南から北へ通りぬける交点を春分点(B)。太陽が北から南へ通りぬける交点を秋分点(A)と 言い換えることが出来ます。そしてこの交点は地球の自転とは逆の向きの 歳差運動により約2万4千年の年月をかけて天球を一周します。
ではどの星座の辺りに交点が描かれているかを見れば、観測した時期が特定できるかも しれませんね。
天文図の写真を見ますと、 昴(おうし座)と参(オリオン座)の間に春分点が通っていますので、 この辺りに春分点が来るのは紀元前約16000年・ 次に春分点が来るのは紀元後約8000年になっていましまいます。 どちらもね(^^;仮に天文図を裏返しに書いてしまったとなれば、秋分点が通っていることになりますので、 昴と参の間となりますと約紀元前4000年、或いは紀元後約20000年になっていしまいます。 これもね(^^;
黄道円は大雑把に言えば太陽系の面です。ですので星と黄道との関係は殆ど変化しません。 黄道円はおうし座のヒアデス星団(二十八宿:畢宿)とプレアデス星団M45(二十八宿:昴宿)との間を 通っていますが、キトラ星宿図ではオリオン座(二十八宿:参宿・伐宿)を通っています。つまりは黄道円自体大間違いと言うことですね。
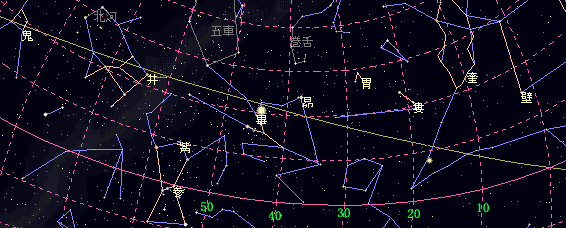
上記の図は西暦1年で、言わばキトラ星宿図の黄道修正版ですから、 春分点・秋分点も含めて全て約45度ずれております。これに付いては四神獣の項目でも少しお話します。
黄道と星座の位置関係は殆ど変化しないので、45度のずれがわかりましたが、 解かり易く、他の天文図と比較して見ましょう。
キトラ古墳の黄道円は、淳祐と比べますと南北を軸に対象になっています。 つまり、南北を軸にして逆さに写してしまったと言う事なのです。
ハハ早く言ってよね。計算しちゃったよ(^^;
学術報告書によりますと、下絵を使って星を天井に写した後、 コンパスで円を描くとき、地面に下絵を置いて方向を検討したので、 逆さまになってしまったのではないか。と言う事であります。