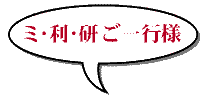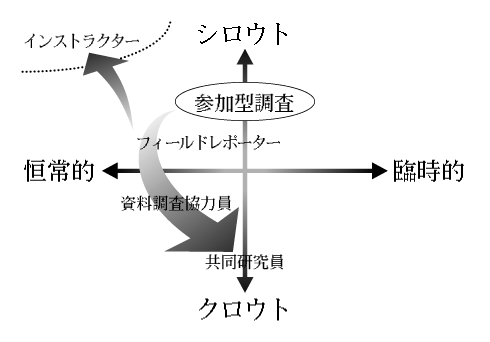その3
滋賀県立琵琶湖博物館で、企画調整課長・嘉田由紀子さんと面談!
20日 10:30〜16:40 滋賀県立琵琶湖博物館にて
-
京都の熱い夜があければ、翌日は開館半年目に入ってなお、多くの人々が来館する滋賀県立琵琶湖博物館へ!(弓場さんは不参加)
-
前夜、染川さんからおすすめされた通り、大津港から高速船に乗り琵琶湖博物館へ。「湖と人間」をテーマとするミュージアムを訪ねるにふさわしいアプローチでした。
-
日曜日。それにしても、という感じで多くの人がミュージアムに吸い込まれます。ミ・利・研一行は、まず、実態を探るため、思い思いに見学することに…。
-
ちょうど、企画展で「博物館のできるまで」(4月27日まで)が開催中でした。多くの時間をかけて、有名無名のたくさんの人々に支えられて博物館が創られて来たありさまが手にとるように分かります。
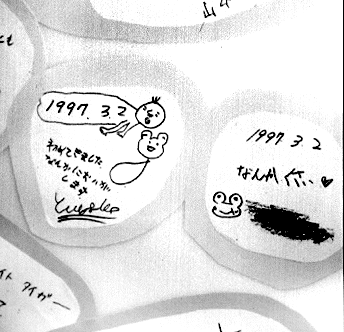
特に、展示制作にパソコン通信を駆使して、広く情報を収集したり、富江家(復元民家)に寄せられた利用者の声(左写真)に「なんかくさい」なんてつぶやきもあったり、つくづくこのミュージアムがフツーの人々の感覚を大切にしていることも感じられたモノです。

-
展示室には、揃いのユニホームを着た様々な年齢の男女の“インストラクター”がいます。その一人に、ミ・利・研の女性陣が質問をしています(右写真)。結構質問責めしているのか、長い間話し込んでいました。熱心すぎる利用者?といったところでしょう。
-
そして午後。企画調整課長 嘉田由紀子さんとの面談です。嘉田さんは、気さくな雰囲気で迎えてくれました。会議室でお話をうかがいます。
-
そこで、開館前からの市民との活動の状況、開館後の様々な変化やドラマッティックな出来事が、滑らかな口調で、語られました。
-
特に、我らミ・リ・研の最大の関心事である利用者との関わりを、開館前から開館後を通じてお話下さいました。いわく…。
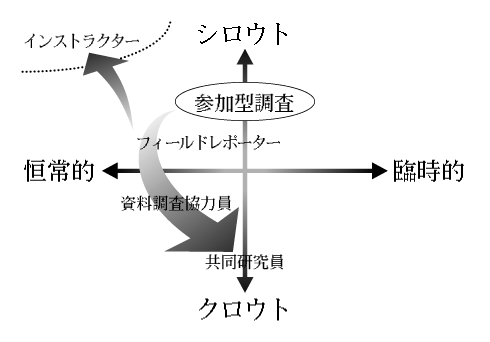
琵琶湖博物館の利用者には、ついでに来た「ついで様」と博物館に何かを求めてくる「その気様」がいる。アンケート調査によれば、琵琶湖博物館のリピーターは16%を数えますが、それらの人々の多くが後者だといいます。琵琶湖博物館では、開館準備段階から、市民が気軽に参加できる「参加型調査」を重ねて来ました。何の気なしに参加した市民もやがて、博物館の資料収集協力員や、人によっては学芸員と互角にわたりあえる程の共同研究員にまで成長するなど、幅広い利用者像をつくり出しています(左図参照)。
■一言のつぶやきに、嘉田さんから提案が…どうしましょうか?会員の皆さん!!■
-
このお話を聞いて、「これらの利用者たちがどういうきっかけで参加して、どんな経過で博物館活動に深く参加していったか興味がありますね…」という重盛のつぶやきに、「是非ともこの研究会でヒヤリング調査をして下さい!」と、嘉田さんがすかさず大胆な提案をされました。
-
あまりにも間髪を入れずだったので、「ハァ、ウー」と生返事。しかし、せっかくのご提案。会員諸氏にはかって検討しますと、即答せずにおきました。積極的なご意見をお聞かせ下さい。
-
ともあれ、2時間20分の平均滞留時間をはるかに越えて、6時間に及ぶ見学会でした。
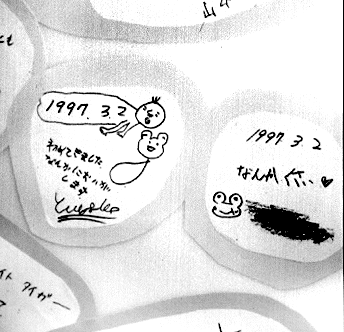 特に、展示制作にパソコン通信を駆使して、広く情報を収集したり、富江家(復元民家)に寄せられた利用者の声(左写真)に「なんかくさい」なんてつぶやきもあったり、つくづくこのミュージアムがフツーの人々の感覚を大切にしていることも感じられたモノです。
特に、展示制作にパソコン通信を駆使して、広く情報を収集したり、富江家(復元民家)に寄せられた利用者の声(左写真)に「なんかくさい」なんてつぶやきもあったり、つくづくこのミュージアムがフツーの人々の感覚を大切にしていることも感じられたモノです。