|
1月1日
※無断転載を一切禁じます
| スタジアム読者の皆様へ
あけましてめでとうございます。
21世紀がやって参りました。スタジアムの読者のみなさんと新年と新世紀を迎える喜びをかみしめたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、すでに私は国立競技場におります。そして2日、3日は箱根駅伝、夜は日韓選抜と世界オールスターに回ります。スタジアムの「三が日スペシャル」が、Sportsnavi.comに掲載されるそうですのでそちらでもお楽しみください。
さて、2000年を締めくくったシドニー五輪でもっとも注目を浴びた競技のひとつ、女子マラソンについて「Number」で連載を続け、シドニーから帰国後に取材をし、膨大なインタビューテープを再度おこし、さらにスタジアムに書いたその時々のレポートをまとめた「シドニーへ 彼女たちの42.195km」が1月10日、文芸春秋から発売されます。2000年の様々なアンケートでも女子マラソン、とりわけ高橋選手の金メダル「スポーツ感動のシーン」のトップに立つほど注目を浴びました。しかしこの本は、シドニーだけではなくて、そこに至るまでの1年間を追ったドキュメントです。マラソンという競技の持つ魅力と残酷さ、高橋、山口、市橋、小幡、弘山、有森ら世界的なランナーでもある彼女たちの競技者としての崇高さ、女性としての魅力、同世代を生きる力強さ、こうしたものに少しでも近いところで原稿を書こうとした結果、国内外で40ケ所、海外を含めると4万キロもの行程で取材をすることになってしまったようです。
本の最後に、リタイアしないよう私を引っ張ってくれた編集者の高木君と、後ろから押し続けてくれたカメラマンの山本君と出張した日程が書き込まれています。見開きに入らないのでかなり控え目にしたようですが、もう一度やれといわれればギブアップしそうな日程です。
それでも、彼女たちが自分たちの脚だけでシドニーまで積み重ねた練習での1万キロ、あるいはそれ以上を走りきったことを思うとまるでお遊びのようなものかもしれません。
歴史的な結末と、もしかするとそれ以上に重い1年となった女子マラソン2000年を、時間がありましたらどうぞ読んでみてください。
前書きから少し引用します。
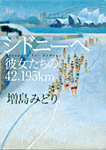 思い出すのは不思議なことに、彼女たちが颯爽と走る姿よりも立ち止まった時の姿のほうである。 思い出すのは不思議なことに、彼女たちが颯爽と走る姿よりも立ち止まった時の姿のほうである。
連載の中間点少し手前となった2000年3月、選考会の大阪国際女子マラソンで2時間22分56秒をマークしながら代表に漏れた弘山晴美(資生堂)の夫でコーチの勉氏から、こんな便りが届いた。
「ここボルダー(米国)に入ってから、様々な意味で疲れが一気に出て来たようです。晴美が昨日、もう走れない、走りたくないと口にしました。夫婦とはいえ、軽々しくまた走ろうと言うことは彼女のがんばりを一番良く知っているからこそできません。黙って見守ることしかできないことがとても辛い。彼女が心の底から走りたい、と口にするまで待とうと思います」
連載は当初、一体誰が代表になるのか、誰がもっとも速く走れるのか、そして、3人の代表が決定してからは誰が金メダルを獲得できるのかといった興味に答えることを目的とした。しかし、このボルダーからの便りを読んだとき、これが彼らの職業であることは当然としても、「走る」とは一体どういう行為なのかを深く考えなくてはならなかった。なぜ42.195kmを、もっと言えば、練習ではこの何百倍もの距離を走ろうとするのか、誰もが抱くであろうこの素朴な疑問について考えるスタート地点ともなった。
|
第80回天皇杯全日本サッカー選手権大会
決勝
鹿島アントラーズ×清水エスパルス
(国立競技場)
キックオフ:13時33分、観衆:53,501人
天候:晴れ、気温:10.6度、湿度:20%
| 鹿島 |
清水 |
| 3 |
前半 1 |
前半 1 |
2 |
| 後半 1 |
後半 1 |
| 延長前半 1 |
延長前半 0 |
41分:小笠原満男
49分:鈴木隆行
91分:小笠原満男 |
オリバ:41分
伊東輝悦:81分 |
 |
交代出場
鹿島
56分:本田泰人(根本裕一)
82分:本山雅志(平瀬智行)
清水
66分:平松康平(澤登正朗) |
Jリーグのスタート以来初のリーグ戦、カップ戦(ナビスコカップ)、天皇杯のタイトル3冠を狙った鹿島は、前半41分、フリーキックのチャンスから相手が壁を作っている間にチャンピオンシップでもMVPを獲得し波に乗っている小笠原満男が右足で直接蹴り込み、これが入って先制した。しかし直後の前半ロスタイムには、清水のサントスからオリバにつないだロングパスをうまくゴール前で合わせられ同点。3冠に向けては産みの苦しみを味わうことになった。後半開始直後の4分には、ゴール前の混戦で、清水のDF市川大祐が後頭部を打って倒れたが鹿島は攻撃を続行。市川が倒れていたことでオフサイドラインが下がってしまった清水の守備を逆手にとって、熊谷浩二がシュート。清水GKの真田雅則の弾いたボールを鈴木隆行が決めて2-1と再び清水を引き離した。
後半36分には中盤の上がり目に入った清水の伊東輝悦に、ゴール前の連携ミスもあってこぼれ球を押し込まれ同点とされたが、後半終了間際には清水の戸田和幸が2枚目のイエローカードを受け退場となり、鹿島は数的な優位をもって延長戦を迎えた。その延長1分、クリアボールをビスマルクが小笠原へ浮き球でパスし、それを右足で落ち着いて決め、鹿島が3-2のVゴール勝ちをものにした。
鹿島は終始主導権を握り続け、後半、延長と、早い時間に攻守が集中して得点をもぎ取るなどチャンスに対する攻守のまとまりと、試合巧者ぶりを存分に見せつけた。決勝ゴールを決めた小笠原は、この試合でも最優秀選手に選ばれ、チャンピオンシップに続いての活躍となった。
敗れた清水は、天皇杯決勝進出は2年前の対横浜フリューゲルス戦以来となったが、またも涙を飲む結果となってしまった。
トニーニョ・セレ-ゾ監督(会見から要旨抜粋)「互いの持ち味を見ている人たちも堪能できた試合になったと思う。来年以降、海外からのオファーはきているが、これだけの成績を残したんだから、今季(2001年)を含めて鹿島に残りたいと思っている。鹿島でチームを受け継いだとき、フロントからは『世代交代をして欲しい』と言われたが、スポーツにおいて世代交代とは若い選手のもので、その点で私の仕事は若い才能に磨きをかけることだった。そのために数多くの人材を持たなくてはならなかった。特に若手の体力面、──日本選手は持久力がないので、こうしたものを鍛えた。不満を言う選手もいたが、今は乗り越えるべき壁だったとわかっていると思う。若い選手にはもっともっとやって欲しい。
(秋田をはじめ選手に)髭を剃られてしまったが、楽しい気分を味わったし、チーム一体となっている気がする」
清水・ゼムノビッチ監督「いい内容で両方にとっても見ているほうにとっても魅力的な試合になったのではないか。天皇杯に入ってから、攻撃が非常に速く展開できるようになっており、それが決勝進出の理由だろう。(2失点目の場面のジャッジについて聞かれて)私は見ていません(皮肉もこめて)。見ていたみなさん(報道陣)が判断して欲しい。今後は補強のこともあるが、とにかく素早いサッカー、早い攻撃ができるようにチームを作っていくつもりだ」
秋田豊「まだ新しい年が始まったばかり。これからもっと気持ちを新たにしてがんばって行きたい。3冠は若い人たちのがんばりで自分たちベテランは仕事に集中することができたと感じた。両方がうまくかみ合わさってゲームができるようになった。シーズンの終わりなので確かに疲れもあるが、僕らには3冠を絶対とろうという強いモチベーションがあってそれがここまで来られた一番の理由だと思う。今後はチャンピオンにふさわしい、21世紀の鹿島を目座してがんばっていきます」
ビスマルク「思えば苦労の多い1年でもあった。イエスの支えでここまで来ることができた。チームは特に後期になってからまとまりというのを持ち始めたと感じている。1つ1つのプレーに明るさ(明確さ)が出て来て、互いの連携が取れるようにもなった。きょうの1勝は20勝くらいに等しいし、これからさらにレベルアップしたい。色々な意味で、戦っている本人にしかわからないような、本当に厳しい1年でした。これからも気持ちを大事にしてがんばろうと思う」
小笠原満男「追いつかれたときには苦しいと思ったが、もともと逃げ切れるなんて思わなかったし、自分自身、逃げきろうなんて考えるのは好きではなかった。こういう厳しい試合には今シーズンで随分慣れてきたので最後まで攻めようと思っていた。チャンピオンシップに続いて自分がMVPなんて……。悪い気がします。でも自分がチームの中心になれたとは全然思ってないんです。まだまだアントラーズは強くなると思うし、その中で置いていかれないようにしなければ」
鈴木隆行「今季はこうした厳しい試合がずっと続いていたので慣れていたし、少しも負ける気はしなかった。2点目は、自分がたまたまつめていただけで、何もすることはなかった。(清水の)市川が倒れていたので、あのポジションでもオフサイドにはならないと判断してあそこに出て行った。熊谷の位置もオフサイドではなかった(市川が倒れていたのを見て判断したという意味)。中盤でつないだために、清水のDFにてこずったが、ロングボールを後半少なくしていきながらうまく展開できた。3冠が取れてほっとした」
試合データ
| 鹿島 |
|
清水 |
| 11 |
シュート |
12 |
| 11 |
GK |
7 |
| 0 |
CK |
5 |
| 15 |
直接FK |
24 |
| 5 |
間接FK |
4 |
| 4 |
オフサイド |
3 |
| 0 |
PK |
0 |
ファビアーノ「市川が倒れていたのは逆サイドだったので全然気が付かなかった(実際は自分のサイド)。きょうは両方の守備にとって厳しい試合だったと思う。短気をおこしてはならない試合で我慢比べでもある。3冠はうれしいが、これも色々な条件やチャンスが重なってできることなので、今回をものにしたいと思っていた。清水は退場者を出した時点で、流れを逃がしたかもしれない」
熊谷浩二「(市川が倒れていたシーンについて聞かれ)ボールを外に出しても(市川が倒れていて危険なのでプレーを切って)良かったかもしれない。もしかすると(清水から)クレームがつくような場面だとは思った。でも、チームの中では誰もそういう指示をしていなかったし、これもしたたかさというプレーなんだと思う。相馬さんなど、怪我人が出たこともあったがチームに動揺はなかったし、層が厚く誰もが信頼しあえるところが鹿島の強さだと思う」
中田浩二「小笠原がMVP2回ですか。いいな、車(副賞)が欲しいです。3冠のピッチに立てたことは幸せでした。来シーズンは試合にすべてでることを目標としたい。代表で出られない試合をのぞいて90分すべてピッチに立てるように。代表での課題は、服部さん(年宏、磐田)に追いつくことです。試合に出ていなければならず、今の状態では差がありますから」
高桑大二朗「風と光とに苦しめられました。多分、相手の真田さん(清水GK)もそうだったと思いますが、ピッチ上の風がものすごく強かったし、それも方向が一定ではなくて苦労した。きょうは、飛び出さないことというか、出過ぎないことを心がけていた。緊張感でしびれる試合でしたが、それでもうちの守備陣が冷静に試合をコントロールしていたので安心できた。3冠で印象的なのは、自分が一度も負けるとか、点を取られるとか思わなかったこと。それほど鹿島の守備が安定しているということだと思う。これだけの結果を持っているのだから、ここで満足はしない。代表を狙っているし、そこでも戦いたい」
岡野俊一郎日本サッカー協会会長「日本のサッカー界にとって最高の1年になるよう、みんなで力を合わせて代表をバックアップして行きたい。目標としては、日本が常に世界のベスト10に入れるようなレベルになることだ」
トルシエ監督「鹿島は3冠でJでもっとも実力のあるクラブだということを名実ともに証明した。シーズン最後の試合まで、モチベーションを維持するのは困難で、本当にすばらしいと思う。鈴木がすばらしかった。よく回りも見えている(視野が広い)上、動きが速い。小笠原も2試合でMVPを獲得するなど、自信をつけている。私のチームへの復活を待っていた」
「かなり満足してます」
延長戦を終え、セレモニーでサポーターと喜びを分かち合い、ようやく長かったシーズンが終えた鹿島の選手たちが真っ先に駆け寄ったのは、トニーニョ・セレーゾ監督の元だった。正確には、監督の「髭」の元というべきだろうか。
電気カミソリを手にした秋田が、うれしそうに監督のホホにビーンとスイッチを入れながら刃を当てる。選手それぞれもうれしそうにそれをとり囲んで「儀式」が終了。大騒ぎする選手と監督の輪には、苦しかった一年を乗り越えて最高の結果を手にした満足感、連帯感といったものが、言葉の助けを一切借りずに漂っていた。
シドニー五輪女子マラソンで金メダルを獲得した高橋尚子(積水化学)も、レース直後に縁起をかついで伸ばしていた小出義雄監督の髭を剃って喜んでいたが、秋田が剃り落としたのは「願かけ」ではなくて、「鹿島の世代交代」だった。
「監督の髭を剃ると約束したのは、ナビスコの前ですから、そもそも3冠どころか1冠さえ手にしていないときだった。監督に、もし3冠獲ったら髭を剃り落としてもいいか、と聞いたら、いいよ、と言われたんで。いや、3冠もうれしいですが、これもかなり満足してます」
秋田はうれしそうにはしゃいで、ロッカーの前でもらったビールを握り締めていた。清水にしてみれば、何をやっても必ずストップに入るこのディフェンダーが憎たらしかったに違いない。
トニーニョ・セレーゾ監督が気楽に「髭剃り」を約束したのは、もちろん選手との一体感や動機を高めるためでもあろうが、一方で監督自身、秋田の言う3冠を心から信じていたわけではなかったのだろう。
「鹿島に来たときに世代交代をしている時期だ、と言われた。その仕事はどこの監督にとっても一番難しい仕事のたぐいだと言わなければならない」
監督は試合後のロッカー前でそう話した。勝てない時期もあった。個々で見れば何の不足もないはずが、若手の伸びと、ベテランの熟成がどうしても噛合わない時もあった。
監督は、それが勝利にどう結びつくかはともかくとして、フィジカルを重視した。特に若手からは「こんなに走っては、試合で疲れてしまう」と不満の声もあがった。しかし、持久力こそが試合に、もしかすると世代交代への強靭なエンジンになると決断した。
監督は「とことんまで絞り取らなければ、限界など見えない」と、スポーツのある部分における真実を貫こうとしたのだろうか。
今シーズン延長戦を6試合もものにした鹿島にとって、こうした「量をこなすこと」が無駄ではなかった。
この日観戦していた釜本副会長は、「清水も鹿島もやっているサッカーに大きな差はなかった。あるのは、ビスマルクや秋田がいるかいないかだった」と、小笠原を表のMVPに、秋田、ビスマルクをこの試合と3冠の裏のMVPに上げた。
ビスマルクは「どんなに苦しい1年だったかは誰にもわからない」と言ったが、Jリーグをも牽引してきた彼をもってしても、伸び盛りの若手を自分たちのステージに引き上げて、そこからさらに自信を持たせステップアップさせることがいかに困難か、やり遂げてみて初めてわかったということなのだろう。
ビスマルクの言葉はチームを機能させ結果を手にするために払った時間と犠牲の数々を指しているはずだ。しかし、これらは間違いなく若手への「肥料」となった。
秋田も「若手がすべてやってくれて、自分たちは(自分の)仕事に集中すれば良かった」と、こちらもかなり満足した様子で笑みを浮かべ、若手を盛んに立てていた。
新陳代謝とは、世代交代とは、2つのグループの入れ替わりではなく、融合する時間の長さ、質にかかっているのではないか。だとすれば、Jリーグ開幕からプレーしている秋田がいて、若い小笠原がいるチームの新陳代謝を支えているのは、強硬な根ということになる。
彼らが3冠を決めた国立競技場の芝の養生もこれに等しい。冬と夏と、生える時期のまったく違う芝が、枯れてはまた伸び、伸びては枯れる。両者が季節によって互いの個性を存分に出しながら芝は結果的に一年中青く輝くことになる。
おそらく鹿島の黄金時代と呼称されるだろう。
しかし金の光よりも、踏まれても、はがれても、たとえ一時は枯れてなくなっても、何度でも青々と茂り継続する「二毛作の芝生」の輝きこそ、彼らの栄誉をたとえるにふさわしいのではないか。
「主審は何をジャッジするのか」
どちらを主語に置くかによって、鹿島と清水で「答え」は正反対になるだろう。
清水からすれば、この日、布施主審が下した2つのジャッジは「信じ難い」(サントス)もので、鹿島にすれば「勝つためにはしたたかさもいる」(鈴木)ということになる。
流したプレー2つは、この試合を象徴するものになった。
問題は鹿島の1点目となった小笠原のフリーキックであり、2点目、鈴木の得点に至るまで、清水DF・市川が脳しんとうで倒れていた場面だ。
1点目のフリーキックをセットする際、布瀬主審は壁を9メートル下げようと清水の選手に促していた。自身も、鹿島のフリーキックセットをおそらく(主審のコメントはでないので確認できない)見ていなかったはずだ。このため、主審からの注意に従って壁を交代させていた清水にとっては、主審の注意がまったく払われていない中で、鹿島がフリーキックを蹴り出して来たという状況である。
オンプレーを告げる笛が鳴ったかどうかは問題ではなく、そもそも、プレーを止めるために、つまり「アウト・オブ・プレー」中であることを主審が選手に宣告していたのかどうかを確認しなければならない。
もし何も「今壁を下げているので蹴るな」と宣告なり確認なりしていなければ、試合は続行しており、主審の不注意さに引っ張られた清水は気の毒だった、という話になってしまう。
清水の選手は「主審が時間をオンプレーではないとしているからこそ、背中を向けてこちらに下がれと指示している」(市川)と解釈するだろうし、鹿島にすれば「いつ蹴ってもフリーキックをするほうの話。世界中どこでもあるプレーだ。驚くことはない」(トニーニョ・セレーゾ監督)となる。
あえていうなら鹿島の「したたかさ」である。
さて2点目の市川転倒のままでのオンプレーはどうか。
市川はゴール前で空中戦の時に後頭部を打ち、ここで意識を一瞬失った。試合後、後頭部を激しく打ったこと、そのため意識がなかったこと、試合終了後も手がしびれていることを憤慨した(さらに大きなたんこぶを見せてくれた)。
この質問を受けたトニーニョ・セレーゾ監督は「見てなかった」と言った。自分の側で倒れたにもかかわらず、ファビアーノは「反対側で気がつかなかった」と言う。
2人とも見ていないはずはなく、これはやはりデリケートな場面だと十分自覚しての発言だろう。主審は基本的に出血と頭部の打撃があった場合にはすみやかに試合を止めるよう、医科学委員会との折衝で定められている。
鹿島があの場面で市川の危険性をどう考えたかよりも、布施主審は試合を止めなくてはならなかった。
これも確認できないが、市川がすぐに立ち上がったときでさえ意識がなかった可能性が高く、頭部強打が大事に至らなかったことは主審にとってラッキーだったのだ。
一方鹿島の鈴木は「市川が倒れていたので、オフサイドポジションにならない。ああいうしたたかさも必要」と、自ら冷静にポジションをあげていたことを明かす。
鹿島に対してこのプレー中にボールを蹴り出せなどとは言えない。フェアプレーではないとも言わない。しかし、これは彼が言う「したたか」とは別の行為で、サッカーではしばしば称賛される場合に使われる「ずる賢さ」であった。
いずれにしても主審の確認作業における怠慢は、ゲームそのものへの価値に関わる。昨年末、Jリーグ審判講習会を取材した際、高田委員長が「来年からはビデオシステムを導入して、ジャッジメントの反省会に使う。その中で互いの討論を徹底させて向上したい」と話していた。
この試合こそ、そのスタートにふさわしいと、審判委員会は認識するべきだ。
「市川のプレーの向こうに見えるもの」
この日、清水の2点目をアシストした市川の右サイドのプレーには、強豪国とのAマッチが続く2001年に可能性を感じさせるものがあったのではないか。
代表の課題は常にサイド攻撃である。
名波浩(磐田)、中村俊輔(横浜)が左サイドをこなし、明神智和(柏)、望月重良(京都)らが右サイドを受け持つシステムは機能はしている。しかし、市川が見せたようなスピードと正確な技術は、本来のアウトサイドでのプレーを予感させるものだった。
98年のW杯では最年少でチームに加入。最終メンバーからは外れたものの、チームには帯同し得がたい経験を許された、ある意味厳しい言い方をすれば2002年へ重責を担う選手だ。代表に入らねばならない。
「もうあれから3年経つんですね。もっとしっかりやらなくてはと肝に銘じて2001年を過ごします。きょうの試合、ジャッジに文句は言いませんが、悔しいとも言い切れない悔しさが残ってます。今年は代表に戻ろうと決心している」
試合後、3年前の、もしかするとすでに昨年の表情とさえまったく違う精悍な顔つきで市川は言った。フランスの後は、生真面目で手抜きのできない誇るべき長所ゆえに、心身の疲労が抜けなくなる「オーバートレーニング症候群」にもかかった。
そこから這い上がり、今度はベンチも経験し、ようやくレギュラーの座をつかんだ道のりは、クロス、センタリングの精度を磨くものだったようだ。
市川のようなスタイルでプレーできるアウトサイドの選手がいてこそ、代表の攻撃も一層の厚みで強化されるはずだ。
同じ病で苦しんでいる森島寛晃(C大阪)に「休んでください。それしか方法がないのは辛いんですが、それしかありません」と控え目にアドバイスを送った。
ほぼ2年かかかってのカムバックの意味と、時間をかみしめるかのように。
|
![]()
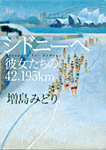 思い出すのは不思議なことに、彼女たちが颯爽と走る姿よりも立ち止まった時の姿のほうである。
思い出すのは不思議なことに、彼女たちが颯爽と走る姿よりも立ち止まった時の姿のほうである。
