Written by 中原 憬
| カテゴリ別 | |||
|
自殺・自死遺族の癒しに役立ちそうな本です。 | ||
|
犯罪被害者の遺族の癒しに役立ちそうな本です。 | ||
|
我が子を亡くした親の癒しに役立ちそうな本です。 | ||
|
家族を亡くした子どもの癒しに役立ちそうな本です。 | ||
|
伴侶を亡くした人の癒しに役立ちそうな本です。 | ||
|
カウンセラーや医療関係者に役立ちそうな本です。 | ||
|
広く、死別の悲しみに役立ちそうな本です。 | ||
|
悲しみを共感させ、心を温めるのに役立ちそうな本です。 | ||
| 書籍別 | |||
 「天国のお兄ちゃんへ〜なぜ、自殺したの?」 「天国のお兄ちゃんへ〜なぜ、自殺したの?」
|
著者は、兄を自殺で亡くしました。自死遺族である妹の壮絶な悲しみと立ち直りへの記録です。 | ||
 「生きかたを変える聖書のことば60」、「人生に効くサプリメント―聖書のことば240」 「生きかたを変える聖書のことば60」、「人生に効くサプリメント―聖書のことば240」
|
聖書の中から心に響くことばを集めた本です。聖書のエッセンスが味わえます。 | ||
 「死別の悲しみを癒すアドバイスブック」 「死別の悲しみを癒すアドバイスブック」
|
米国のカウンセラーの書いた非常に役に立つ書籍です。 | ||
 「生きることば あなたへ」 「生きることば あなたへ」
|
仏門に帰依した瀬戸内寂聴さんの包み込むような優しい言葉。人生の悲しみや苦しみに。 | ||
 「いま、会いにゆきます」 「いま、会いにゆきます」
|
病気で先立った妻が、突然に昔のままの姿で戻ってきた。涙の止まらない、切なく美しい物語。 | ||
 「よく生き よく笑い よき死と出会う」 「よく生き よく笑い よき死と出会う」
|
「死生学」の大家にして上智大学名誉教授のデーケン先生の「死」を乗り越えるためのヒント。 | ||
 「死後の世界が教える「人生はなんのためにあるのか」」 「死後の世界が教える「人生はなんのためにあるのか」」
|
退行催眠によって得られた、死後の世界に関する情報を集めた1冊です。 | ||
 「世界の中心で、愛をさけぶ」 「世界の中心で、愛をさけぶ」
|
世の中で最も大切なアキとの出会いと、彼女との死別が切なく描かれる青春恋愛小説です。 | ||
 「誕生死」 「誕生死」
|
出産前後に赤ちゃんを亡くした11家族のありのままの悲しみが綴られた本です。 | ||
 「心に残るとっておきの話」 「心に残るとっておきの話」
|
人と人との感動的な触れ合いの実話が集めてあり、凍て付いた心が温められる本です。 | ||
 「白い犬とワルツを」 「白い犬とワルツを」
|
妻に先立たれた老人が、他人には見えない不思議な白い犬と出会う物語です。 | ||
 「十二番目の天使」 「十二番目の天使」
|
交通事故で妻子を失った男性が、絶望のどん底から立ち直るまでを描いた小説です。 | ||
 「いつでも会える」 「いつでも会える」
|
飼主の女の子をなくした犬のシロが悲しみを乗り越える物語。小さな絵本です。 | ||
 「「死」って、なに?」 「「死」って、なに?」
|
小学生の子供にも分かりやすく、「死」の受け止め方を教えてくれる絵本です。 | ||
 「千の風になって」 「千の風になって」
|
世界中の人を感動させた死と再生の詩が、講談社からも発売されました。 | ||
 「あとに残された人へ 1000の風」 「あとに残された人へ 1000の風」
|
詠み人知らずの一篇の美しい詩が、写真と共に構成されています。 | ||
 |
感動的なホスピス・ボランティア物語です。連載漫画です。 | ||
 「生きがいの創造」 「生きがいの創造」
|
退行催眠によって得られた死後の世界の情報から構築された「生まれ変わりの生きがい論」。 | ||
 「生きがいについて」 「生きがいについて」
|
ハンセン病の施設で、精神科医として一生を尽くした女性の、深い人間愛に満ちた生きがい論。 | ||
 「夜と霧」 「夜と霧」
|
ドイツ強制収容所への収容という絶望から問われた人間の在り方。絶望の中でも人間らしくあるために。 | ||
 「犠牲(サクリファィス)」 「犠牲(サクリファィス)」
|
息子を自殺で喪った作家の柳田邦男氏が、愛する息子の生と死を綴った一冊。 | ||
 皆さんからのお勧めコーナー 皆さんからのお勧めコーナー
|
皆さんからメールで頂いたお勧めの作品を紹介しています。 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|

「忘れることなんてできません。」 「無かったことにもできません。」 「『兄の生きていた証』を残したい・・・」 「誰かひとりでも良いから『私の大好きで大切なお兄ちゃん』という、かけがえのない存在が、確かにこの世で生きていた、ということを示したい」
* * *
著者の兄は、2002年の冬のある日、18歳の若さで自殺しました。 この本には、兄の自殺という出来事を妹である著者がどのように感じ、受け止めてきたのかという6年間の心の軌跡が描かれています。突然の家族の自殺によって生活が一変し、深い悲しみに突き落とされた著者が、絶望と苦悩の果てに、乗り越えていける希望が見えるまでの心の葛藤が綿々と綴られています。自分を支えるために毎日のように書いていたという兄への手紙も何通も掲載されています。 兄への純粋な思慕とその兄を失った深い喪失感、自分が兄を殺したという強い罪悪感。襲ってくる悲しみや苦しみに対する辛抱強いまでの忍耐。自己嫌悪や劣等感、そして孤独や心の病との闘い・・・・。悲しみ、苦しみの嵐の中で翻弄され、惑い悩む内面を持ちながらも、同時に、これらの感情を封じ込めたり、克服しようと頑張ることで、強く家族を支えていこうという外面の姿・・・。 この本は、自死遺族の悲しみ、苦しみがありのままに表現されており、一般の方にも「自死遺族の本音」がどのようなものであるか十分に理解してもらえるものになっていると思います。自殺という行為がどんなに残酷で悲惨な結果をもたらすものなのかを広く世間に訴えることができる本です。
* * *
私も自死遺族の一人ですが、過去の自分の考えや想いとあまりに似通っていたので、正直なところ、深く入りすぎてしまってゆっくりとしか読み進めませんでした。愛する人を亡くしたときに、同じ高校1年生だったという境遇のせいもあるでしょう。舌の奥に当時の苦い想いを感じながら、心を揺さぶられながら読みました。 自死遺族は、絶望の闇のすさまじい苦しみ、悲しみの中で、生の意味を見据えながら生きるのです。実際、愛する家族の自殺以上に心を砕かれる出来事は世の中に存在しないでしょう。それは、魂の試練ともいうべき、過酷な体験です。極寒の絶望の中で、愛と死という対極のものに正対しながら、自分が生きていくための答えを探し求めながら歩んでいくことなのです。 むろん、それは簡単に答えが見つけられるものではないし、悲しみ以外に、後悔、無念、絶望、恐怖、怒り、憎しみ、怨み、妬み、恥、劣等感、不安、焦燥などの暗い情念が絶えず襲ってくる狭く険しい道です。道の両側には、底の見えない深遠が広がっています。 自死遺族は、特有の罪悪感から後追い自殺の誘惑に駆られることもあります。 そのとき、遺族は、故人と同じように世界を見ていることに気づくのです。同じ位置に立っていることに気づくのです。しかし、ぎりぎりのところで、遺族は持ちこたえていくのです。それは、愛するものを自殺で喪う悲しみを身に染みて知っているからです。 この本の著者も、鬱がひどいときに自殺未遂をしたあとに「私は、本当にバカでアホな最低最悪な親不孝者だね」と家族のことを思って後悔する場面が出てきます。 この章の注意書きに「(※私がした行為、絶対に真似をしないで下さい。自分を傷つけないで下さい。)」とも書いてあります。 好むと好まざるにかかわらず、塗炭の苦しみの中で、遺族は多くのものを失いながらも、多くのものを得ていきます。
* * *
作者の哀澤 かすみさんは、自身の体験をまとめたこの本を自費出版しました。 お兄さんへの深い尊敬と愛情の込められた本です。この本を読めば、お兄さんが決して弱い人間でも、卑怯な人間でもない、むしろ優しくて尊敬すべき人ということがよくわかります。 作者にとって、この本はお兄さんの生きた証であり、また、お兄さんと自分の絆でもあることでしょう。 この本で、人の命の「存在の大きさ」や「大切さ」を読者に感じてもらうことを著者は願っています。一人でも多くの人が、残酷な死に方を選ぶことがなくなってほしい、と。 この本には、一人の自死遺族が体験してきた凄まじいまでの悲しみ、苦しみが描かれています。精神的にボロボロになったどん底の時期もさらけ出しているのだけれども、それでもこの本は、一途な兄への想いのこもった美しい本だと思います。そして、多くの人たちを自分と同じ目に遭わせまいという想いのこもった優しい本なのです。 飾り気のない文体はとても読みやすいし、作者の率直な想いに共感できます。 作者にそのようなつもりはないかも知れませんが、生と死、愛と人生について多くを考えさせられる本です。 ぜひ、一読をお勧めいたします。 |

|

死別の悲しみに沈む人にとって、本当に素晴らしい書籍が出版されました。
死別の悲しみに沈む人に、ぜひ手にとって読んでいただきたいと心から思う本です。 適切な心理学的なアドバイスと、温かな思いやりに満ちた言葉に溢れた本です。内容は私が保証します。 この本の著者は、アメリカで死別の悲しみについて30年以上の実績のある女性の臨床心理学者(カウンセラー)です。 この本は、「私の死別体験」というプロローグから始まります。 そこには愛する家族を続けて失ったこと、特に、17歳の息子ジムを事故で失ったことが、母親としての視点から綴られています。そうです、この著者は愛する者を失った遺族の耐えがたい痛みを身をもって知っているのです。そこから、この著者は、臨床心理学者として、愛する人との死別から人がどのようにして立ち直るのかを研究してきたのです。 本書は、心理学的に評価しても類を見ない適切なアドバイスに満ちています。著者は、自身の体験のみならず、臨床心理学者としてのセラピー体験や、配偶者や子供、親を亡くした人への聞き取り調査と追跡調査も行っています。このような多くの情報と著者の深い洞察により、悲しみには「五つの段階」というプロセスがあることを著者は示しています。 本書の目次を見てましょう。 読者は、どのページを開いてみても、自分が抱えている悲しみや苦痛が適切な言葉に言い表されていることにまず驚き、その悲しみや苦痛に対して明確なビジョンを示してくれることに驚き、さらに、非常に具体的で分かりやすいアドバイスを与えてくれることに驚きます。 なお、この本は、特定の宗教に拠ったものではなく一般の平易な心理学の本なので、愛する人を喪って苦しんでいる人が身近にいてどうにかしてあげたいというときに、さりげなく貸してあげると喜ばれると思います。(通常、慰める言葉をうまくかけてあげることもできず、周りの人の善意は空回りしがちです) 本当に素晴らしい本です。このホームページを見にくる人全員に配りたいぐらいです。 この本の帯にこうあります。 「悲しみに沈むあなたの心に小さな明かりをともします。」 そのとおりになるでしょう。 |

著者は、まえがきで優しく語りかけます。
この本は、瀬戸内 寂聴さんの過去の全著作の中から、テーマ別に選んだ短い文章を、詩集のように読みやすく一冊にまとめ直したものです。 一章は、「わかれ」 二章は、「さびしさ」 三章は、「くるしみ」 四章は、「いのり」 五章は、「しあわせ」 どれも胸に響く言葉ばかりです。 あなたの心の苦しみ、悲しみをじんわりと癒してくれることでしょう。 一章が「わかれ」であり、「愛する人を亡くした人の為の100の言葉」と雰囲気が似ています(不思議なことに本の装丁も似ています)。 言葉も、とても似ているものもあったりします。 100の言葉が気に入った人なら、この本もきっと気に入ると思います。 (この本を紹介してくださった方、ありがとうございます)。
| ||||||||||

久しぶりに、本を読むことの素晴らしさを再認識させてくれた小説です。 心から他人にお勧めしたいと思う本に出会えました。 妻を病気でなくし、5歳の子供と二人で暮らすシングルファーザーの元に、ある日、突然に死んだはずの最愛の妻が現れます。記憶を亡くした状態で。 主人公と妻と子供は、再び三人で暮らし始めます。主人公は記憶を無くした妻と、もう一度最初から恋を始めるのです。別れの予感を秘めながら−−−。 ブックカバーの帯にはこういう感想のコピーがあります。 「とにかく、この小説を早く読んでください。一刻も早く。早ければ早いほどより多く人生は豊かになります。感涙度100%(個人差はあります)」 この感想を書いた人の気持ちはとてもよくわかります。同感です。1人でも多くの人にこの本を紹介しないと、という思いに駆られるくらい素敵な物語です。 本当に、「愛している」ということだけが書かれているのです。 何気ない会話に含まれた、思いやりや優しさで、心が満たされ、清々しい気持ちになります。 この本には、人を純粋に愛することの美しさ、切なさがぎっしりと詰まっています。読み終わるのがもったいない気持ちになる本です。 そして、驚くべき感動の結末が用意されています。 この手の物語は、つじつまの合わない弱いラストシーンが多いものですが、この本の結末は、感動できるとともに、納得できるものでした。どこにも伏線がなく進展していて、物語がきちんと収束するのかな?という心配は感動とともに吹き飛びました。 読み終わって、胸が熱くなり、じわじわと涙が止まらなくなりました。 同じ境遇にある人にとっても、癒される物語だと思います。 文体は、とても読みやすく、小説というよりも、どこかのホームページの日記のようで、リアリティがあります。ぜひ、読んでください。お勧めします。 映画も10月30日から全国東宝系ロードショーです。 竹内結子、中村獅童、武井証ほか(竹内結子さんて、こういう物語によく主演しますよね)。 楽しみです。(^_^) 公式サイト 『いま、会いにゆきます』 [補足] 映画もよかったですー。優しい雨に心を洗われたような気持ちになりました。本を読んで筋がわかっているのに、それでも泣けて泣けて・・・。心が疲れてしまっている人にもお勧めです。人生に大切な思い出がひとつ増えた気がします。 私は、本を読んでから映画を観るのをお勧めします。自分の中の「澪」像や「たっくん」像や「佑司」像が先に描けるから(もちろん、映画の役者さんもグッドです。特に竹内結子さんは、素敵ですねぇ)。それに、複雑なストーリー構成を自分の納得できるスピードで読み進めていって感動を味わってほしいので(この本の、あの手紙を何度読み返したことか)。 [補足] 現在放映しているTVの方の連続ドラマは、まったくお勧めできません。 生き返った「澪」に対して、「佑司」が傷つくから出て行ってくれ、と「たっくん」が言うなんて信じられません。(-"-) 本当にひどい作品です。TVドラマは粗悪な贋物です。 |


上智大学を定年退官され名誉教授となられたアルフォンス・デーケン氏は「死生学」を四十年教え続けてきたこの分野での大家です。 この本は、最終講義をベースに、先生の今までの研究をわかりやすくまとめた本であると同時に、先生の波瀾万丈の生涯を交えた感動的な内容の本です。 身近で大切な人を亡くしたとき、自らの死に直面したとき、一体どうすればよいのか?自らの体験も交えやさしく語りかけてくれます。ここには、「死」を乗り越えるための大切なヒントがたくさん詰まっています。 アルフォンス・デーケン氏は、下にあるように生と死を見つめた優れた著作を数多く上梓なさっています。 キリスト教に基づいた信念は、どれも温かく、愛情に溢れたものです。
[補足] 出版元の新潮社のサイトでこの本「よく生き よく笑い よき死と出会う」に対する柳田邦男氏による書評が読めます。 http://www.shinchosha.co.jp/shinkan/nami/shoseki/462501-9.html |


この小説は、中学時代につきあいはじめたアキという名の少女との恋愛と死別が、主人公である「ぼく」の目を通して語られる小説です。 物語は、こんな書き出しで始まります。 「朝、目が覚めると泣いていた。いつものことだ。悲しいのかどうかさえ、もうわからない。」 この物語は、愛と死別について、まっすぐに描かれた小説です。愛や幸福と同じぐらい、死別や悲しみについて語られています。 淡々とした筆致で、同級生である「アキ」との出逢いや、ごく普通の、しかし振り返れば胸が締め付けられるような瑞々しい青春の恋愛の思い出が、鮮やかに描写されていきます。やがて彼女は白血病を発病し、短い命を閉じます。 読者は、「アキ」とともに過ごす幸福の絶頂の日々と、病魔が「アキ」の体を蝕んでいく絶望や不安と、「アキ」を喪失してしまった深い悲しみと失意を主人公の「ぼく」の視点から体験します。 人が生きて、愛して、死んでいくということは、一体何なんだろうな、と考えさせられます。高校時代を舞台とした、あまりに切ないシンプルな物語に、鳥はだが立つような感動とともに泣かされます。 若くして恋人を亡くした人に一読をお勧めします。 [補足] 主人公を慰める祖父の言葉に、100の言葉と同じ台詞がありますね。 「おじいちゃんはどうやって乗り越えたの?」という質問の次です。 祖父の人生の美しさに関する言及も同感するばかりです。 [補足] いよいよこの本もメジャーになってきました。あちこちの本屋で山積みの光景を目にするようになってきました。映画化も決定したようです。 トレンディドラマにはない、シンプルで純粋な愛の形が人々の心にストレートに響くのでしょうね。 |


この本には、流産、死産、新生児死などで出産前後に赤ちゃんを亡くされた13名の父母のありのままの体験と想いが実名で載せられています。 この本のタイトル「誕生死」とは、流産、死産、新生児死などの幼い赤ちゃんの死をすべて含めて呼ぶ言葉として、つくられたものです。 それぞれの母親のお腹に宿った新しい命は、どんなに小さな体だったとしても、どんなに短い生涯だったとしても、間違いなく存在し、母親のお腹の中で一体となって命を育み、我が子として確かに誕生したのです。 それぞれの手記に綿々と綴られた悲しみに、涙を禁じえません。親の愛し、慈しむ気持ち、我が子に対する限りない愛情−−−そして、それが満たされない深い悲しみ。 親は、思いがけない赤ちゃんの喪失に、ショックを受け、深く傷つきます。 周囲の人たちは、慰めるつもりで、「早く忘れなさい」という、より深く傷つける言葉を掛けてしまったりします。そうではないのです。たとえどんな短い命であっても、いつまでもその子の親なのです。その子のことを想っていたいのです。その子のことを堂々と語りたいのです。 −−−この本は、そんな親の気持ちの結晶です。 親の子に対する想いが心に沁みる本です。親の愛情の深さに打たれ、命の尊さを感じずにはいられません。 同じように大切な赤ちゃんを亡くし、心の行き場がなく、どうして自分だけがという、いい知れぬ孤独感にもがいている人たちにとっては、悲しみに寄り添ってくれる本となることでしょう。 |


愛する人との死別は、人の心を冷たく凍えさせてしまいます。 凍えた心には、温かな言葉や触れ合いが必要です。もし、そのまま放っておくと、人生を信じたり、人を愛したりすることが難しくなることもあります。なぜなら、凍えた心は負の感情と結びつきやすいからです。 あのとき、ああすれば、という後悔が、恨み、怒り、憎しみとなどと結びついて自分を含めた誰かを責めたり、恨んだりすることで心がいっぱいになりがちです。 そんなふうに心が冷え切ったとき、ほんの一言でも、温かい言葉を掛けられると、心に温かさが沁み渡ることがあります。本書は、まるで温かい言葉を掛けられたかのように、凍りついた心がじんわりと溶けていく良書です。人との人との触れ合いに心が共感し、熱くなるのです。 この本は、ごく短い実話が並んでいて、どこからでも読みやすく、どれも胸に響く話ばかりです。ぱらぱらと拾い読みをするだけでも、心を洗われたような清々しい気持になれます。 心が、冷たく固く凍り付いているときに、是非読んでください。温かなものが流れて、少し楽になれます。
|


長年連れ添った妻に先立たれた老人のもとに、ある日驚くほど真っ白な犬が現われました。犬は次第に老人になつき、老人も犬を可愛がるようになります。 ただ、とても不思議なことに、老人以外にはこの犬の姿が見えないのでした。老人は、妻との死別の悲しみの中、不思議な白い犬との触れ合いに、ささやかな生きがいを見出します。 この物語は、一人の素朴で実直な男性の人生の晩秋の姿をきめ細かく描いています。そこには、彼を心配し見守る子供や友人達との触れ合い、人生を共に過ごした愛する妻との思い出、そして不思議な白い犬との交流が淡々と描き込まれています。 主人公の老人の堅実な人柄と、喪失感を持ちながらも、白い犬を心の支えに毅然と余生を生き抜く姿が、読者に示されます。そして、やがては老人自身も、病を得て、従容と死を受け入れていきます。 老人の姿を通じて、人生と愛について考えさせてくれる、大人向けの童話です。
|


この物語は、主人公の男性が自殺をしようとする場面から始まります。 主人公は、突然に最愛の妻と一人息子を同時に交通事故で喪ったのです。 それまでの主人公の人生は順風満帆で、コンピュータ業界大手の会社の新CEOとしてヘッドハンティングされ、テレビや雑誌でも紹介されるような輝かしいものでした。故郷に戻ったことで、町をあげての歓迎セレモニーに家族そろって出席したばかり後のことでした。 愛する家族を喪ったことで、主人公の人生は暗転し、絶望のどん底に陥りました。 葬式以来、主人公は家に閉じこもり、失意の中、やがて拳銃を手にします。 「さあ、これでいい。準備は整った。弾丸を込めた弾倉を拳銃に戻す。さあ、急ぐんだ!もう何も考えるな! やるんだ! 私は拳銃を持ち上げ、撃鉄を起こし、銃口をこめかみに押し当てた。この物語は、実際の天使が登場する訳ではなく、奇蹟が起こる訳でもありません。 登場するのは、ただ私達人間だけです。絶望と混乱の中から、主人公がさまざまな人たちの触れ合いとスポーツ(野球)を通じて、次第に夢と人生をあきらめない姿勢を取り戻して立ち直っていく過程を綴った物語です。 特に少年−−−絶対にあきらめないという信念を持つ少年−−−との触れ合いを軸としてストーリーが展開していきます。人がどんなふうに死別という人生の壁を乗り越えていくのか、成功哲学を下敷きにして理想的に描いた物語といえます。死別の悲しみに直面した人に掛けてあげる言葉もいくつも出てきて泣かされます。 友情と愛情に満ち、感動を呼ぶ物語です。よくできた良心的なアメリカ映画を観たような読後感が残ります。 |


若い女性から圧倒的に支持される小さな絵本があります。 菊田まりこさんの「いつでも会える」です。 こんな物語です。 シロという犬が、みきちゃんという女の子に飼われて幸せいっぱいに暮らしていました。 ・・・でも、突然にみきちゃんは死んでいなくなってしまいました。 シロは、死が受け入れられずに、どうしてかな、なんでかな、と呆然とします。 それから、さみしくて、悲しくて仕方ありません。 シロはみきちゃんに会いたくて、会いたくて、あちこち探し回ります。 でも、シロはみきちゃんが見つけられずに涙を流します。 そんな、ある日、シロはみきちゃんと夢の中で再会し、みきちゃんがいつも近いところにいることを知ります。 1999年度ボローニャ児童賞・特別賞受賞だそうです。 「子供に死という非常にデリケートな問題を教えるためにもこの本は秀逸である」との評がありました。 死を体験してしまった小さな子供達に贈りたい一冊です。 |

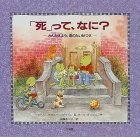
小学生くらいの子供は「死」って何だろう?と強い興味を持つ年代だと思います。 しかし、大人でさえこの質問は難しすぎて答えられないため、大切な人を失った子どもたちはあいまいな説明のまま、「死」とその悲しみをうまく受け止められずにいるのではないでしょうか? この絵本には、子供たちが生活の中で直面する「死」にまつわる疑問について答えようとする絵本です。 小学校低学年くらいの年代に合わせた適切なレベルで作られており、漫画的な恐竜のキャラクターが登場して非常に親しみやすい絵本です。しかし、その内容は専門のカウンセラーが答えたような、バランスのよい健全なものであり、子供の心の傷を丁寧に包み込むような優しさに溢れています。 ・生きているって、どういうこと?子供の心はデリケートです。 死別という体験ときちんと向き合うことで、不安と悲しみを乗り越え、人の命の大切さを学んでいくのではないでしょうか? そのような境遇の子供達に是非読んでほしい、優れた絵本です。 |


世界中の人々を感動させた、詠み人知らずの英語の一篇の詩があります。 その詩は、ごく短い詩ですが、多くの残された人の心を慰めてきました。 その詩を翻訳し美しい写真を付けて仕立てたのが本書です。 なお、この本は、ほぼ同じスタイルの本が、ほかの出版社から先に出版されています。 その本は、このすぐ下にある紹介文の「あとに残された人へ 1000の風」(三五館)です。詠み人知らずなので、著作権を主張する人がいない訳です。 (どちらを買うか迷ったら、訳者の問題から、この本ではなく、下の本を買うことをお勧めいたします。) ご参考までに、この本の翻訳とは無関係に英語の原詩を私が翻訳してみました。
英語の原詩は、下の紹介文にあります。 |


一篇の詩が、美しい写真と共に構成された本です。 タイトルは、1000の風―あとに残された人へ 。 この詩は、ごく短いものですが、愛する人を亡くした人にとって、胸に沁みる詩です。透明感と優しさに満ちています。写真も、本当に美しいものが選ばれており、心癒されます。 この本は、天声人語で紹介されたことで大きな注目を集めています。 この詩のオリジナルは、次の英詩です。本書ではこの英詩が日本語に翻訳されて、詩にふさわしい写真とともに構成されているハードカバーの小さな本です。
この詩はもともと詠み人知らずの詩で、人気コラムニストが大好きな詩として新聞に紹介したため、作者探しもあったそうですが、いまのところ人間のかたちでは姿を現していないと書いてあります。 美しく、思いやりに満ちた本なので、愛する人を亡くした人へのプレゼントとしてお勧めいたします。 |

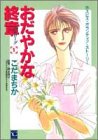
末期がん患者のホスピスでボランティアをする主婦を描いた感動のコミックがあります。 こだまちかさんの作品で、「おだやかな終章−エピローグ−」というシリーズ作品です。 主人公は、親を亡くした心の痛みを持つ主婦、鈴木瑞穂です。彼女の視点から、さまざまな患者の生と死のヒューマンドラマ描かれています。 とても質の高いコミックであり、人のこころがきちんと描かれています。リアリティのある描写に、きっと、主人公にあなた自身を重ね合わせてしまうことも多いでしょう。また、実際のホスピスの先生に監修してもらってあるなど、背景がきちんと描きこまれています。また、物語中にさりげなく語られる言葉も本当に深いものがあります。 このシリーズの単行本は次の3冊が既刊です。本屋で探す価値がありますよ。
なお、こだまちかさんは、ダウン症児と共に生きることをテーマにした作品や、不妊治療をテーマにした作品、小児救急をテーマにした作品など社会派の作品も発表されています。こちらも感動的な物語です。
|


人に奨められてこの「生きがいの創造」という本を読み、とっても気に入りました。ぜひ多くの人に読んで欲しいと思いました。 この著作は、前半では、世界中の退行催眠から得られた死後の世界と生まれ変わりの研究結果が集められており、後半では、それらの知識から導き出した生きがい論が書かれています。著者の立場は、人は生まれ変わりの科学を知ることで、この人生の生きがいを創造することができる、というものです。自らの意志でいまの人生を選んでこの世で魂の修行を積んでいることや、死後には愛と光に包まれた平和な世界があることや、死別した人と再会できることなどが、豊富な証言の引用で説明されています。 思わず引き込まれてしまうような、魂に響く内容です。 読後、善き人生を生きよう、などと思いました。 内容からして宗教的な色彩がないことがないのですが、著者は別に特定の神を信じている訳ではなく、あくまでも科学的な立場を貫いていると言っています。何よりも、この本の魅力は、人生の生きがいを見出すという観点から、人の生まれ変わりの真実について真摯に誠実に伝えようとしていることです。 この本は、1997年度のビジネス書分野第6位です(トーハン調べ)。40万部を超えるベストセラーで、5か国語にまで翻訳されています。そして続々出版された「生きがい論」シリーズの第1作にあたります。著者は福島大学経済学部助教授であり、出版社も信頼のある松下幸之助のPHP出版であることを考えれば、うさんくさい同種の本とは一線を画している良書であると言えるでしょう。 なによりも、感動的で、心打たれる本です。 この本を紹介することで、何度も感謝のメールを頂いています。 生と死について悩んでいる方は、心の拠りどころを得られるかも知れません。 |


この本は私が最も尊敬する人物である、神谷美恵子さんの著作です。 著者は、ハンセン病の施設に精神科医として勤め、世の中から隔離され心まで病んでしまった患者達を支えることにその生涯を尽くしました。彼女は、ハンセン病の施設で、生きがいを見いだせないために多くの患者さん達が虚無感に悩み、かなりの神経症にも陥っている事実に心を痛めていました。 彼女は、鋭い洞察力と奥深い知性によって、この人生の根源的な問題に真摯に取り組み、多くの示唆に満ちたこの名著「生きがいについて」を書き上げました。心理学の論文の形をとりながらも、クリスチャンである彼女の言葉はどこまでも温かく、平易で分かりやすく、静かに語りかけられるような謙虚な優しさを持っています。 この本のテーマは、「生きがい」についてであり、つぎのような言葉で始まります。 本書には、苦悩や絶望に陥ってしまった人達がどのようにして、人生のいきがいを見出して行けばよいか、多くのヒントが含まれています。また、数多の豊富な引用文献の中には、心理学の分野の論文のほかに、文学者や詩人、哲学者の言葉も含まれ、人生の真実について、さまざまな角度から考察がなされています。 どのページを開いても、人生に対する深い考察が的確にまとめられており、ただただ圧倒されるばかりです。多くの人々の魂の拠りどころとなってきた、いぶし銀のような名著とされる所以です。 「苦悩の意味」という章から引用してみます。 悲しみや苦しみという重荷を背負っている人達に、一人でも多く読んでほしいと願う一冊です。なぜ、こんな人生を生きなければならないのか、と日々煩悶している人にこそ、手にとってもらいたいのです。苦しみの意味、悲しみの意味、そして、生きることの意味−−−この不可解な人生というものの手がかりが見つかるかも知れません。 私は、この著作と出会い、これほど豊穣な著者の魂を垣間見る機会を得たことに、湧きあがるような喜びを感じます。この紹介文が、彼女の著作に少しでも関心を持ってもらえる機会となれば大変嬉しいことです。 |


この本は、第二次大戦中にドイツの強制収容所に収容されたユダヤ人の心理学者の体験記録です。 人類史上最悪の地獄とも言えるドイツ強制収容所の描写は悲惨を極めます。人の命の尊厳をかけらとも思わない所業がこれでもかというほど記述されています。収容所での虐殺、虐待、飢え、寒さ、病気、という条件の中で、人の命がぼろくずのように扱われ、実に多くの無辜の命が失われました。 本書の前半は、資料編として強制収容所内で何が行われたのか、戦後明らかになっていった想像を絶する事実が詳細に記録されています。人類の残虐性と愚かさに暗澹たる思いに沈みます。人類はこれだけの深い闇を作りうるのです。 しかし、一縷の光もあります。本書の後半に書かれた心理学者の行動が、たとえばそれです。このような身体的、精神的な極限状況に直面しても人間らしい優しさや尊厳を失わなかった勇気ある人々がいたという事実を本書は伝えています。この点において、本書は「評する言葉もないほどの感動」(朝日新聞の書評より)と絶賛されており、語り継がれる名作として知られています。 人間の良心についてはさておき、この欄で紹介したいのは、深い絶望の中で人はどう在るべきか、述べられている点です。 「八 絶望との闘い」という章から少し難しいですが一部を引用します。 苦しみと悲しみに直面しながらも、未来の視点を維持し続け、困難な外的状況こそ自らを超えて成長する機会と信じ、人間の尊厳と自由を追い求めた人たち。その人たちにとって、過去の愛する人との思い出は、永遠で確実なのものだったのです。 この本におけるクライマックスは、極度の疲労と絶望との中にいる大勢の収容者に対して、彼が自己放棄による自殺を防ぐために呼びかけるところです。多くの示唆に満ちた勇気と愛の溢れるものです。ぜひ、一読をお薦めします。 [補足] ある人を救ったというフランクルの言葉です。 「人間は誰しも心の中にアウシュビッツを持っている。 でもあなたが人生に絶望しても、人生はあなたに絶望しない」 アウシュビッツとは、生死を分かつような人生の苦悩のこと、だそうです。 |


息子を自殺で喪った作家の柳田邦男氏が、愛する息子の生と死を綴った一冊。 ある夏の日、25歳の青年が自殺を図りました。 救命センターに移送されましたが、救命医療の甲斐なく昏睡状態に陥りました。その青年は作家の柳田邦男氏の息子でした。氏は、愛する息子の突然の出来事に愕然し苦悩する中、何か息子のためにできることをと、脳死後に息子の腎臓をドナーとして提供することを申し出ます。 やがて、最期の時がやってきて、臓器提供がなされました。 そして、「なぜ」という問いが心に残りました。 なぜ、息子は、現代に生きられなかったのか? なぜ、息子は心の病に苦しんだ上に、自殺しなければならなかったのか? この本では、本人が書き綴っていた文章から、彼が生きた25年間の心の軌跡がありありと示されます。 彼の遺した日記には、対人緊張に悩み、社会にうまく自立できない焦りに苦悩する、繊細な内面が書き綴られていました。 彼の遺した短編作品には、実存の根源的な不安が色濃く示されていました。 氏は、息子の自殺に直面し、その激しい挫折感と敗北感から、一時は絶筆まで考えます。その悲しみと絶望の深さは、容易にはかり知れるものではないでしょう。 しかし、「息子は鈍感な通常人には見えないものを見てしまった。人間存在の根源的な孤独の世界とか。それを息子に代って書き残さなければ」という思いや、「洋二郎の魂の救済のためには、まず自分が再生しなければどうしようもないではないか」という考えのもと、執筆活動を再開し、この一冊の追悼記ができあがったのです。 この本は氏の愛惜に満ちた言葉で、彼の思い出が多く語られています。そして、彼の内面世界を綴っていた文章も多く載せられており、氏が読者に分かりやすいように解説を付けています。 読者は彼の生の姿をありありと感じ、その内面を見るでしょう。 彼は、こうして、孤独ではなく人々に忘れられない存在となりました。 さらに、脳死後に行った腎臓の臓器提供により、彼の望んでいた自己犠牲的な行為は成就しました。 この本の帯には、こうあります。「父と子の魂の救済の物語」。 息子がどのように生き、どのように逝ってしまったのか、その痛切な想いを書きまとめたレクイエムでもあると同時に、親の立場から見た脳死と臓器提供の記録でもあります。著書の後半には、脳死患者の遺族の心のケアについて論じた文章があります。 氏は、その後、いのちに関する著作を次々と上梓し、講演もしています。 日本におけるグリーフケアの分野で広くその名を知られ、氏は多くのご活躍をなさっています。 |
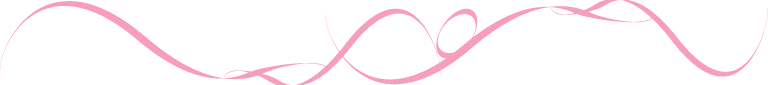
|
|||
|
|
||
|
 |
||