水質試験方法について。いずれ充実させませう。
| 作成者 | BON |
| 更新日 | 2003/08/17 |
ここでは各種水質試験に関する情報を用の場所です。
|
各種水質試験 水質試験方法について。いずれ充実させませう。 |
【備考】
先ずは場所から。
環境測定技術一般については以前特許庁のサイトなどがあったのですが...いずれさがします。。
| 【特許庁】 詳しい解説があったのですが...また探さないと。 |
ここでは,一般的な水質測定技術について設置する場所です。でもこの分野は充実に時間がかかりますし,ここに掲載する程度の情報では試験そのものを実施するには全く不十分です。よって,ここでは,どんな試験をどのような目的で行っているのか,概要を示すにとどめます。実施する人は,各種専門教育を受け,必要資料を入手してくださいませ。
水質試験の各種手法については,上水試験法に準拠します。ただし,細かい実験手法や計測結果の適用には,土木学会のマニュアルの方がわかりやすく,かつ詳しいです。学生実験用のマニュアルなどもこれに準拠しているようです。
(1)汚泥沈降試験
汚泥沈降試験は,上水汚泥の沈降,分離性を把握するための実地試験です。汚泥は,希薄な状態では沈降,濃厚な状態では圧密と呼ばれる状態変化を示し,清澄な水と汚泥部分とに分離されます。そこで,汚泥をメスシリンダーなどにとって静置し,その沈降状態を観察するとともに,界面=水と汚泥が分離していると認められる面の沈降速度を算出することで,サンプルとなった汚泥の分離性を把握します。併せて,汚泥の性状に関する試験(濃度等)を行うことで,どのような沈降条件の汚泥を扱っているのかを把握することができます。
![]()
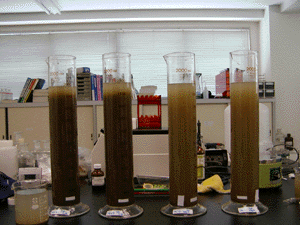 汚泥沈降試験状況
汚泥沈降試験状況
非常に単純な試験であることは右を見てもらえればわかるかと思います。このGIFは1分ごとの撮影で約10分間=10コマとなっていますが,大体48時間程度は最低でも試験を継続します。ただし,圧密過程に入ってしまえば,そんなに界面の検索頻度は必要ありません。右の画像は,高濁時のかなり濃い汚泥です。三脚とかを使ってないので,あまり長いこと見ていると酔いますので,気をつけてください。気分が悪くなっても,当サイトでは責任を負いかねます。m(_ _)m
(2)汚泥/SS濃度試験
汚泥沈降試験と併せて汚泥の濃度を測定します。まず,蒸発皿を洗浄,乾燥機とデシケータを使用して乾燥し,平熱で秤量します。あらかじめ洗浄済みのろ紙を使って規定量の供試水をろ過,ろ紙上に残留した懸濁物にいて,ウォーターベッドで湯煎乾燥したのち乾燥機,デシケータで乾燥,秤量して差分の従量を計測します。
なお,汚泥のような濃度の大きい供試水が対象であれば,ろ過工程は省略してもかまいません。
【備考】
とりあえず最近実施した試験から。