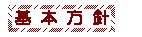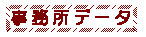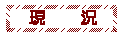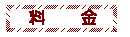内容工事中 |
*** 付 録 ***   左の各項目欄をクリックすると、一応の説明が出ます 左の各項目欄をクリックすると、一応の説明が出ます これ以上、特許関係の資料を加える予定は当面ありません これ以上、特許関係の資料を加える予定は当面ありません ご質問があれば、下記のメール先へご連絡下さい ご質問があれば、下記のメール先へご連絡下さい |
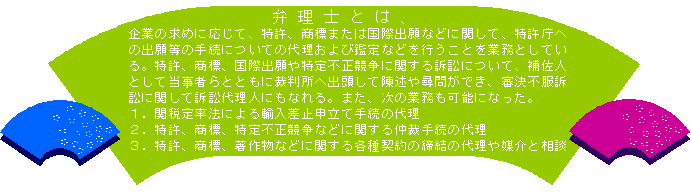
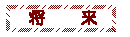 |
|||
| 【 弁 理 士 の 仕 事 】 | |||
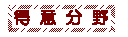 |
|||
| 【 パ ソ コ ン 歴 】 | |||
| 登録(公告)数 | 拒 絶 数 | 不審査請求(放棄、未審査を含む) |
|---|---|---|
| 45件 | 11件 | 44件 |
| 登録(公告)数 | 拒 絶 数 | 不審査請求(放棄、未審査を含む) |
|---|---|---|
| 64件 | 57件 | 50件 |
| 成 功 数 | 失 敗 数 | 未確定数(取下げを含む) |
|---|---|---|
| 23件 | 4件 | 3件 |
| 勝 訴 数 | 敗 訴 数 | 回答書段階で終了 |
|---|---|---|
| 3件 | 0件 | 15件 |
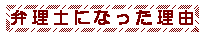 |
|||
| 【 プ ロ フ ィ ー ル 】 | |||
| 項 目 | 手 数 料 | 謝 金 | |
|---|---|---|---|
| ①特許出願の代理 ②実用新案登録出願の代理 ③(要約書作成) ④(請求項毎の加算額) ⑤(書面加算額:枚数毎) ⑥(図面作成) ⑦商標登録出願の代理 ⑧意匠登録出願の代理 ⑨意見書の作成(特許出願、補正書作成を含む) ⑩意見書の作成(商標、意匠出願) ⑪拒絶査定に対する不服審判の請求 ⑫他人の特許に対する特許異議の申立 ⑬無効審判の請求 ⑭鑑定書の作成 ⑮補佐人として裁判所へ出廷(特許侵害訴訟) ⑯刊行物の提出(情報提供) ⑰外国特許出願 ⑱特許調査(簡易) ⑲優先または早期審査に関する書類の提出 ⑳審査請求または出願公開の請求 各種料金の納付 | 170,000円 160,000円 5,000円 加算せず 2,500円 実 費 60,000円 80,000円 70,000円 30,000円 190,000円 270,000円 400,000円 300,000円以上 訴額の5%(原則) 120,000円 相 談 10,000円以上 130,000円 10,000円 10,000円 | 100,000円 な し - - - - 45,000円 65,000円 - - 190,000円 270,000円 400,000円 - 左欄と同額 - な し な し - - - | |