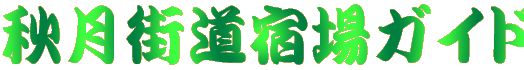

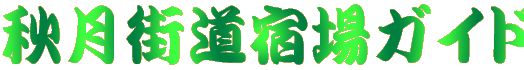

| 猪 膝 (いのひざ) | ||
|
福岡県田川市猪位金2区 | |
| 明治になって炭坑で田川市の伊田や後藤寺が発展するまでは、ここ猪膝が豊前の南の宿場町として大いに繁栄していました。江戸前期は参勤交代などでここを利用する大名も少なくありませんでした。 町並みの中央にある公民館には江戸時代の宿場猪膝をイラストで紹介する案内板があり一見の価値があります。 写真は猪膝宿の北側にある構口近くの白鳥神社です。仁和3(887)年に現在の場所に移ったと伝えられ、元禄年間に小倉藩主小笠原氏によって再建されました。国道322号から分かれる旧道が白鳥神社の前を通っており、往時の雰囲気が感じられます。 |
 |
| 香 春(かわら) | |
| 現在の行政区域 | 福岡県田川郡香春町香春 |
| 最寄の交通機関 | JR日田彦山線 香春駅より徒歩15分 |
 |
鬼ヶ城 慶長6(1601)年に豊前国に入国した細川氏の支城として、忠興の弟忠之が城主として整備しました。この城は、中世の戦乱の舞台となった香春岳城を背負う形で新たに造られました。三の丸〜一の丸の跡が確認できるほか、一部に石垣なども残っています。しかし存続した期間は短く、元和の一国一城令(1615年)によって廃城となりました。城の麓には秋月街道沿いに領主の館や武家屋敷が配置されて、殿町という字名が残っています。 香春中学校向かいの須佐神社から、香春町郷土史会の皆さんが作った階段などをたどって急斜面を登ると、20分ほどで天主台(写真)に着きます。そこからの眺めは、北と東側がすばらしいです。 |
| 採銅所(さいどうしょ) | |||
|
福岡県田川郡香春町採銅所 | ||
| JR日田彦山線 採銅所駅より徒歩3分 | |||
 |
街道沿いに町が形成され、現在も旧宿場町の名残が感じられます。 金辺(きべ)峠の麓の宿として、細川藩時代には藩主の茶屋(本陣)が設けられました。 採銅所の名前からわかるように、銅鉱山の町としても知られています。 さらに江戸時代初期には金鉱山も開かれました。写真は金辺川で、この場所でかつては砂金の採取がおこなわれました。 |
| 呼 野 (よぶの) | |
| 現在の行政区域 | 福岡県北九州市小倉南区呼野 |
| 最寄の交通機関 | JR日田彦山線 呼野駅 |
| 旧国道322号が旧街道を利用してつくられており、宿場の面影はあまり残っていませんが、通りに面して大山祇神社や大泉寺などの神社仏閣が建っておりかつての繁栄がしのばれます。江戸時代には小倉藩の本宿として人馬継ぎ立てをおこなっていました。 写真はお糸池(稗の粉池)です。宿場の東に位置し、享保3(1718)年にこのため池を築くにあたり、14歳のお糸が人柱となったと記録されています。 写真のように堤防がうねうねと長く続き、難工事であったことが伝わってきます。地元の呼野では毎年お糸の霊を慰めるための盆踊りがおこなわれています。。 |
 |
| 小 倉 (こくら) |
|
| 現在の行政区域 | 福岡県北九州市小倉北区 |
| 最寄の交通機関 | JR鹿児島本線 小倉駅・西小倉駅 |
 |
長崎街道のシンボル常盤橋の東端より西を臨んで撮影しました。橋の東端には江戸時代東勢溜という広場がもうけられていました。付近には各藩の本陣(正式には藩指定の宿所となる旅籠)が集まっていたました。海岸近くの皿屋は柳川・平戸藩の本陣で、常盤橋のたもとには福岡藩の本陣鍋屋がありました。また勢溜に面して建てられた大坂屋は広い敷地をもち長崎奉行の常宿となっていました。 |