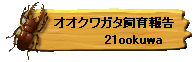 丂丂僆僆僋儚僈僞帞堢曬崘 丂丂僆僆僋儚僈僞帞堢曬崘丂丂侾俋俋俈擭偺僑乕儖僨儞僂傿乕僋偐傜僆僆僋儚僈僞偺帞堢傪巒傔丄柌偺亯俉侽倣倣堢惉傪 丂丂栚巜偟偰帞堢偟偰偄傑偡丅摉弶偼暉壀嶻偺傒偺帞堢偱偟偨偑丄嵦廤偟偨傝峸擖偟偨傝 丂丂偟偰崱偱偼偡傋偰嵦廤僨乕僞晅偒屄懱傪庬恊偲偟偨暉壀嶻丒嵅夑嶻丒孎杮嶻傪帞堢偟 丂丂偰偄傑偡丅戝偒偔側傞偐偳偆偐偼傑偢寣摑偑嵟廳梫場巕偲側傝傑偡丅 丂丂俀侽侽俀乣俀侽侽俁擭丂俀侽侽侽擭搤偵嵽妱嵦廤偟偨嵅夑嶻儁傾梒拵偺帞堢 丂丂俀侽侽侽乣俀侽侽俀擭丂椙寣摑傪扵偡偨傔偵俇宯摑偺梒拵傪帞堢拞偱偟偨偑丒丒 丂丂侾俋俋俋乣俀侽侽侽擭丂孎杮偱嵦廤偟偨撲偺梒拵偨偪偺帞堢 丂丂侾俋俋俉乣侾俋俋俋擭丂弶傔偰偺嬠彴價儞帞堢偱亯俈俈倣倣堢惉偵惉岟 丂丂侾俋俋俈乣侾俋俋俉擭丂弶傔偰塇壔偝偣偨僆僆僋儚僈僞亯俆俀倣倣 丂丂帞堢拞偺僆僆僋儚僈僞幨恀廤 丂丂-------------------------------------------- 丂丂Copyright(C) 1997-2002 21ookuwa All rights reserved. 丂 丂 |
|
僆僆僋儚僈僞帞堢曬崘丂俀侽侽俀乣俀侽侽俁擭 亅帺暘偱嵦廤偟偨嵅夑嶻偺梒拵傪帞堢亅 |
|
俀侽侽侽擭侾俀寧俁擔偵偵暉壀導偺僆僆僋儚僈僞柤恖j巘彔茓蓫虖W偟偨嵅夑嶻梒拵偺塇壔 屄懱偺儁傾傪庬恊(亯俇侾倣倣亊亰係侾倣倣偲係侽倣倣)偲偟偰嶻傑傟偨梒拵傪帞堢拞偱偡丅 丂仛帞堢曬崘偼偙偪傜仛 (侾侽寧俁擔峏怴)  庤慜懁偵偼俈係倣倣戜偺亯俀摢傪帞堢丄墱懁偵嵅夑嶻俥侽亯亰傪儁傾儕儞僌帞堢拞丅 |
|
僆僆僋儚僈僞帞堢曬崘丂俀侽侽侽乣俀侽侽俀擭 亅椙寣摑傪扵偡偨傔偵俇宯摑偺梒拵傪帞堢亅(搑拞拞抐) |
|
俀侽侽侽擭偺弔偐傜壞偵壓婰帞堢儁傾孮偐傜嶻傑傟偨梒拵傪堢偰偰偄傑偟偨偑丄廐偵巇帠偱揮嬑偲 側偭偨偨傔梒拵傪慡晹偄傠傫側恖偵偁偘偰偟傑偄傑偟偨丅傛偭偰俀侽侽侾擭弔偺塇壔屄懱偼側偟偱偡丅 傑偨俀侽侽侾擭偺壞偼梒拵傪嶻傑偣偰偄側偄偨傔俀侽侽俀擭弔偺屄懱傕帞堢偟偰偄傑偣傫丅 <嬨廈嶻> 仛嬨廈嶻俙僔儕乕僘(庬恊丂彎懢亯俈俈倣倣亊亰係俉倣倣) 丂嫟偵偦偺孼掜偡傋偰偑俀俇倗埲忋偵堢偭偨屄懱摨巑偺儁傾儕儞僌丅亰偼嶳岥導偺倀巵偐傜偺棦巕丅 仛嬨廈嶻俛僔儕乕僘(庬恊丂彎懢亯俈俈倣倣亊亰係俉倣倣) 丂彎懢巓亰偲嵅夑嶻亯偐傜嶻傑傟偨亰偲偱儁傾儕儞僌丅 <孎杮嶻> 仛孎杮導媏抮孲仜仜嶻僔儕乕僘(俥侾)(庬恊丂亯俇俋倣倣亊亰係係倣倣) 丂庬恊偼亯亰偲傕偵嵽妱嵦廤偟偨梒拵偑塇壔偟偨屄懱(俥侽)丅嵦廤僨乕僞偁傝丅 <暉壀嶻> 仛暉壀導媣棷暷巗嶻僔儕乕僘(俥侾)(庬恊丂亯俇侾倣倣亊亰係俀倣倣) 丂庬恊偼亯亰偲傕偵嵽妱鲏t嵦廤偟偨揤慠屄懱(俥侽)丅嵦廤僨乕僞偁傝丅 仛暉壀導嶰鄈孲嶻僔儕乕僘(俥侾)(庬恊丂亯俆俉倣倣亊亰係俇.俆倣倣) 丂庬恊偼亯亰偲傕偵庽塼嵦廤迠剛祩綋V慠屄懱(俥侽)丅嵦廤僨乕僞偁傝丅 <嵅夑嶻> 仛嵅夑導嶰梴婎孲仜仜挰嶻俙僔儕乕僘(俥侾)(庬恊丂亯俇俀倣倣亊亰係係.俆倣倣) 丂庬恊偼亯亰偲傕偵嵽妱嵦廤偟偨揤慠屄懱(俥侽)丅嵦廤僨乕僞偁傝丅 仛嵅夑導嶰梴婎孲仜仜挰嶻俛僔儕乕僘(俥侾)(庬恊丂亯俆俉倣倣亊亰係侾.俆倣倣) 丂庬恊偼亯亰偲傕偵嵽妱嵦廤偟偨揤慠屄懱(俥侽)丅嵦廤僨乕僞偁傝丅嵅夑嶻俙僔儕乕僘偲摨挰丅 仛嵅夑導嶰梴婎孲仜仜挰嶻倂僔儕乕僘(庬恊丂亯俈俁倣倣亊亰係俇倣倣) 丂嵅夑嶻俙a僔儕乕僘偲偼暿挰丅庬恊偼俥俀丅嵦廤僨乕僞側偟丅棃擭儁傾儕儞僌梊掕丅 丂 |
|
僆僆僋儚僈僞帞堢曬崘丂侾俋俋俋乣俀侽侽侽擭 亅孎杮偱嵦廤偟偨撲偺梒拵偨偪偺帞堢亅 |
|
仠偼偠傔偵 嶐擭(侾俋俋俉擭)壞偵泎壔偟偨梒拵傪嬠彴價儞偱帞堢偟丄亯俈俇.俈倣倣傪嵟崅偵亯俈俆倣倣僆乕僶乕 傪俁摢帞堢偡傞偙偲偑偱偒(傑偩侾摢偼梒拵偺傑傑)戝曄枮懌偺偄偔寢壥偱偁偭偨丅偨偩丄俀俉倗掱搙 偵側偭偨梒拵傪偆傑偔鍖壔偱偒側偐偭偨偲偄偆壽戣偑巆偭偨丅 偦偙偱崱擭偼丄戝偒偔側偭偨梒拵傪偆傑偔鍖壔偝偣傞偨傔偵嘆壏搙愝掕偺偱偒傞壏幒偱帞堢偡傞丄 傛傝戝偒側屄懱堢惉偺偨傔偵嘇椙寣摑屄懱孮摨巑偺妡偗崌傢偣偐傜嶻傑傟偨梒拵傪帞堢偡傞丄 偙偲偵偟偨丅 仠帞堢曽朄偲寢壥 暉壀嶻亯俈俇.俈倣倣亊嬨廈嶻亰係俉.侽倣倣 侾俋俋俋擭俈寧丄暉壀嶻亯俇係倣倣亊亰係係倣倣偐傜嶻傑傟偨俆寧塇壔偺亯俈俇.俈倣倣偺彎懢偲嶳岥 導偺倀巵偐傜捀偄偨暉壀嶻偲嵅夑嶻偺僴僀僽儕僢僪屄懱偺亰係俉.侽倣倣偲偺儁傾儕儞僌傪奐巒偟偨 (暉壀偲嵅夑偲偄偭偰傕嵦廤抧偼俆侽侽倣傕棧傟偰偄側偄)丅 偙偺亯亰偼丄偲傕偵偦偺孼掜偺偡傋偰偑俀俇倗埲忋丄暯嬒俀俈.俆倗埲忋偵傑偱堢偭偨屄懱孮偺拞偺 侾摢偱丄亯亰偲傕偵戝偒偔側傝堈偄椙寣摑屄懱偩偲峫偊偰偄傞丅摉弶偼亯亰偲傕偵戝宆側偨傔惉弉 偡傞偺偵敿擭偼偐偐傞偩傠偆偲巚偄丄崱擭偺嶻棏偼掹傔偰偄偨偑丄俋寧偵擖傝亯亰偲傕偵塧傪怘傋 妶摦傪偡傞傛偆偵側偭偨偺偱丄偙傟側傜嶻棏偱偒傞両偲敿暘柍棟栴棟偵丄岎旜偟堈偄傛偆偵彫働乕 僗偵堏偟偨傝丄僇僽僩儉僔偺梒拵傪塧偲偟偰梌偊偨傝偟偨偲偙傠丄侾侽寧偵擖偭偰偡偖偵嶻棏傪奐巒偟 侾侽寧侾侽擔偵棏係屄傪庢傝弌偡偙偲偑弌棃偨(偦偺屻偼婥壏偺娭學偱嶻棏偼偟側偐偭偨)丅  丂丂丂 丂丂丂  妱傝弌偟偨棏偼暿梕婍偵偰侾侽寧侾俈擔乣侾俉擔偵柍帠泎壔偟偨丅偦偺侾廡娫屻偺侾侽寧俀係擔偵泎 壔偟偨弶楊梒拵係摢傪嬠彴價儞(俋侽侽們們)偵搳擖偟丄偦偺屻壏幒偵偰俀俆亷慜屻偱帞堢傪奐巒偟偨丅 泎壔屻侾廡娫偱偼憗偡偓傞偲巚傢傟傞偐傕偟傟側偄偑丄幨恀偺捠傝丄偡偱偵梒拵偼塧傪怘傋扙暢 傕偟偰偍傝丄廫暘嬠彴撪偱惗偒偰偄偗傞偲敾抐偟偨丅傑偨偙偺帪婜丄偮傑傝側傞傋偔憗偔嬠彴帞堢傪 偡傞(偄偄塧傪怘傋偝偣傞)曽偑戝偒偔側傞偲峫偊偰偄傞丅偨偩偟丄嬠偑妶敪偡偓傞偲嬠偵傑偐傟偰巰 朣偡傞棪偑崅偔拲堄偑昁梫偱偁傞丅  丂丂丂 丂丂丂  泎壔偐傜偪傚偆偳侾廡娫屻偺弶楊梒拵偨偪(嵍偼妱傝敘) 嬠彴價儞偵搳擖偟偰係俋擔屻偺侾俀寧侾侾擔偵俀杮栚(亯侾俆侽侽們們丄亰俋侽侽們們)傊岎姺偟偨丅係摢偺偆 偪俁摢偑亰偱偁傝丄塧岎姺帪偺懱廳偼弴偵俥俫侾丗侾侾倗丄俥俫俀丗侾侽倗丄俥俫俁丗侾侽倗丄俥俫係丗侾俆倗偱偁 偭偨丅 偦偺屻侾寧侾俆擔偵俥俫係(亯)偺塧岎姺(懱廳偼俀俀倗)丄俀寧侾俇擔偵俥俫侾(亰)偺塧岎姺(懱廳侾侾倗)丄 係寧侾侾擔偵俥俫係(亯)偺塧岎姺(懱廳俀俁倗)傪幚巤偟偨丅係寧偵擖傝俥俫侾丒俥俫俀丒俥俫俁偺俁亰偑丄俆寧 俀俆擔偵俥俫係(亯)偑鍖壔偟偨丅偟偐偟巆擮側偑傜丄亯偺俥俫係偼嬠彴價儞偺掙偵鍖幒傪嶌偭偨偨傔巹 偺敾抐儈僗偱寢壥揑偵塇壔晄慡偱巰朣偝偣偰偟傑偭偨丅俁摢偺亰偼偦傟偧傟係俉倣倣丄係俆倣倣丄 係俁倣倣偱塇壔偟偨丅 仠峫嶡 庬恊亯傕庬恊亰傕偲傕偵偦偺孼掜偑俀俇倗埲忋偲偄偆椙寣摑摨巑偺儁傾儕儞僌偱偼偁偭偨偑嵟廔揑 側梒拵懱廳丄塇壔僒僀僘偲傕偵慡偔枮懌偺偄偔寢壥偲偼側傜側偐偭偨丅偨偩崱夞偼丄帞堢摢悢偑係 摢(摿偵亯偼侾摢偺傒)偲彮側偔丄傑偨泎壔帪婜偑侾侽寧拞弡偲偄偆偙偲傕偁傝丄偙偺寢壥偐傜偩偗偱 偼椙寣摑摨巑偺儁傾儕儞僌偑幐攕偟偨偲偼尵偄偒傟側偄丅傑偨丄嵟嬤孼掜摨巑偺儁傾儕儞僌(僀儞 僽儕乕僨傿儞僌)偵傛傞屄懱偺曽偑戝宆壔偟傗偡偄偲偄偆寢壥傕弌偰偍傝丄嵞搙泎壔瑨穾瀶鷤饙l 椂偟偰嵟掅侾侽摢埲忋偵傛傞帞堢傪幚巤偟専摙偡傞傋偒偩偲峫偊偰偄傞丅 仠偦偺懠 侾俋俋俋擭俉寧壓弡丄婜懸偟偰偄偨椙寣摑摨巑偺儁傾儕儞僌偑偆傑偔偄偐偢丄偙偺傑傑偱偼崱擭帞堢 偡傞梒拵偑慡偔偄側偄忬嫷偲側傞偨傔偦傟偼庘偟偄側偲偄偆偙偲偱丄僋儚僈僞帞堢偺愭攜偱偁傞倂 巵偵偍婅偄偟偰嵅夑嶻梒拵傪暘偗偰傕傜偭偨丅帞堢搑拞偺宱夁偼徣偔偑丄嵟廔揑偵亯俈俁倣倣丄 亰係俉倣倣偑嵟崅僒僀僘偱塇壔偟偨(偨偩俈俇倣倣慜屻偺屄懱偑塇壔晄慡偱巰朣丅搑拞僾儗僛儞僩 偟偨梒拵偼亯俈係倣倣傗亯俈俀倣倣偱塇壔偟偨偦偆偱偡)丅傑偨尰嵼丄俀寧侾俇擔偺塧岎姺帪俀俁倗偲 俁侽倗偩偭偨梒拵偑枹偩梒拵偱偄傑偡丅  嵅夑嶻梒拵亯俁侽倗(2/16) 侾俋俋俉擭俈寧偵泎壔偟偨梒拵偑鍖壔偣偢偵偄偨偑丄俋俋擭侾侾寧偵嵟崅俁侾倗傑偱惉挿偟偨屻丄 俀侽侽侽擭俆寧偵嵟廔揑偵鍖壔偡傞偙偲側偔巰朣偟偨丅梒拵婜娫偼幚偵俀俁儢寧娫偵媦傇丅 侾俋俋俋擭侾侽寧偵孎杮導偱戜晽偱搢傟偨僋僰僊偺棫偪屚傟晹暘偐傜撲偺梒拵傪俋摢嵦廤偟偨偑丄 俆摢偑僆僆僋儚僈僞偱偁偭偨(亯丗俇俋倣倣丄俇俆倣倣丄俇侽倣倣丄亰丗係係倣倣丄枹偩侾摢梒拵)丅 揤慠孎杮嶻僆僆僋儚僈僞傪僎僢僩偡傞偙偲偑偱偒偨偙偲偼戝曄偆傟偟偐偭偨丅堦弿偵嵦廤偟偨拠娫 偵姶幱偟偨偄丅 丂 丂 |
|
僆僆僋儚僈僞帞堢曬崘丂侾俋俋俉乣侾俋俋俋擭 亅弶傔偰偺嬠彴價儞帞堢偱亯俈俈倣倣堢惉偵惉岟亅 |
|
仠帞堢曽朄 俋俉擭俆寧偵暉壀嶻僆僆僋儚僈僞(俥侾)亯俇係倣倣亊亰係係倣倣偺儁傾儕儞僌傪奐巒偟丄俇寧壓 弡傛傝嵽妱傪偟偰弶楊梒拵媦傃棏傪嵦庢偟偨丅弶楊梒拵偼捈偪偵嬠彴價儞傊丄棏偼暿梕婍偱泎 壔偝偣丄泎壔偟偨弶楊梒拵傪嬠彴價儞傊搳擖偟偨丅嬠彴價儞傊搳擖偟偨梒拵偼慡晹偱侾係摢(搑 拞俀摢傪棦巕偵弌偟偨)偱丄搳擖婜娫偼俇寧壓弡偐傜俈寧拞弡偱偁傞丅  丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂 僆僆僋儚僈僞偺棏丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂泎壔屻偺弶楊梒拵 俁庬椶巊梡偟偨(侾杮栚偲俀杮栚偲俁S杮栚偱暿乆)丅俈乣俋寧偼僋乕儔乕偵傛傞壏搙(俀俆亷)娗棟丅 侾侽乣侾侾寧偼幒壏(俀俁乣俀俇亷)娗棟丅侾俀寧乣係寧偼帺嶌壏幒偵傛傞壏搙(俀俆亷)娗棟丅俆乣俇寧 偼嵞傃幒壏偱娗棟偟偨丅  丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂 鍖幒傪嶌傝巒傔偨亰梒拵丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂俋侽侽們們嬠彴價儞丂丂 仠帞堢寢壥 帗梇偺敾暿偼侾夞栚(俀杮栚傊)偺岎姺帪偵妋擣偱偒偨丅亯俇摢丄亰俇摢偱偁偭偨丅 塇壔屄懱偺僒僀僘 丂亰偼侾寧壓弡乣俁寧偵偡傋偰塇壔(僒僀僘應掕偼塇壔屻侾乣俁儢寧屻偵應掕) 丂丂丂係俇.侽丄係俈.俆丄係俈.俆丄係俈.俆丄係俉.侽丄係俉.侽倣倣 丂亯偼俆寧忋弡乣俈寧偵塇壔(僒僀僘應掕偼塇壔屻俀廡娫乣俀儢寧屻偵應掕) 丂丂丂俈俁.俆丄俈係.侽丄俈俆.侽丄俈俇.侽丄俈俇.7倣倣丄梒拵侾摢(俆寧塧姺偊帪俀俋倗) 搑拞巰朣媦傃塇壔晄慡偼亯亰偲傕偵柍偟丅  丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂 嫄戝梒拵亯俀俉倗丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慜偺壠偱偺帞堢扞 仠峫嶡媦傃壽戣 <亰偵偮偄偰> 亰偼摿偵戝偒偝傪婜懸偟偰偄側偐偭偨偨傔丄俁杮栚(係俆侽們們)傊偺岎姺屻丄嬠彴價儞偑儃儘儃儘偱 梒拵偑傕偑偒嬯偟傫偱偄偰傕偦偺傑傑曻抲偟丄柍棟栴棟鍖壔偝偣偨丅偦偺偨傔懱廳偑侾俁倗慜屻 偁偭偨傕偺傕弅傒丄寢壥揑偵係俇乣係俉倣倣偲暯杴側僒僀僘偲側偭偨丅傕偆侾夞塧岎姺傪偟偰鍖壔偝 偣傟偽係俋倣倣傗俆侽倣倣傕塇壔偝偣傞偙偲偑偱偒偨偺偱偼側偄偐偲巚偭偰偄傞丅偟偐偟偳偺屄懱 傕懢偔娵傒偑偁偭偨偺偱廫暘枮懌偺偄偔寢壥偱偁偭偨丅  彎懢俈俇.俈倣倣偲亰係俉倣倣 嬠彴價儞帞堢偼崱夞偑巒傔偰偱偁偭偨偑丄壏搙娗棟偺偍偐偘偐梒拵偼弴挷偵堢偪丄堦帪偼嵟 廔應掕懱廳偑俀俇丒俀俈丒俀俈丒俀俉丒俀俉丒(俀俋倗)傑偱偄偭偨丅偙偙傑偱堢偭偰偔傟傟偽偡傋偰俈俆倣倣 僆乕僶乕偱塇壔偝偣傞偙偲傕壜擻偱偼偁偭偨偑丄幚尰偟側偐偭偨丅幐攕偺尨場偼偦偙傑偱堢偭 偨梒拵傪偦偺忬懺偱偆傑偔鍖壔偝偣傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偨傔偱偁傞丅偪傚偆偳侾俀寧壓弡偐 傜侾寧忋弡偵偐偗偰嵟屻偺嬠彴價儞岎姺傪偟偨丅偙傟偱鍖壔偡傞偩傠偆偲巚偭偰偄偨偑丄壏搙偑 俀俆亷偱偐偮掕壏忬懺偱偁偭偨偙偲傗梒拵偑偁傑傝偵傕嫄戝偱偁偭偨偨傔偐偡偖偵鍖壔偟側偐偭 偨丅偦偟偰俁寧崰嬠彴價儞偑楎壔偟丄梒拵傕摦偒夞傝巒傔丄岎姺偟偨曽偑偄偄偺偐側偲巚偭偨偑 丂 嘆偙偙偱岎姺偟偰偟傑偆偲偦偺塭嬁偱弅傫偱偟傑偆偺偱偼側偄偐偲偄偆晄埨丄 丂 嘇梒拵偑嬠彴價儞撪傪朶傟傞偺偼鍖壔慜偺偄偮傕偺峴摦偱偁傞偲巚偭偨偙偲丄 丂 嘊堷墇偟傗寢崶幃摍偱戝曄朲偟偔僋儚僈僞偳偙傠偱偼側偐偭偨偙偲 偙傟傜偺棟桼偱偟偽傜偔曻抲偟懕偗偰偄偨偨傔丄悢摢偺梒拵(俀俇丒俀俈丒俀俉倗)偑嬠彴價儞撪傪朶傟 懕偗梒拵偼俀俁乣俀俆倗傑偱弅傫偱偟傑偭偨丅寢嬊丄柍揧壛枹敪峺儅僢僩偵堏偟懼偊鍖壔偝偣傞偼 傔偵側偭偰偟傑偭偨丅偙傟傜偺梒拵偼嵟廔揑偵俈俁.俆丄俈係.侽丄俈俆.侽倣倣偱塇壔偟偨丅偙偺嬠彴價 儞偑儃儘儃儘偵側偭偨帪偵朶傟偢偵鍖壔偟偨梒拵(俀俈倗)偑彎懢偱尰嵼俈俇.俈倣倣丄傑偨朶傟偢鍖 壔傕偣偢偠偭偲偟偰偄偨巆傝偺俀摢偺偆偪侾摢(俀俉倗)偼俈俇.侽倣倣偱塇壔偟(偪傚偭偲婜懸奜傟)丄傕偆 侾摢偼傑偩梒拵(俀俋倗)偱偄傞丅懱廳偺妱偵僒僀僘偑怢傃偰偄側偄偺偼丄偳偺屄懱傕懢偔娵傒偑偁 傞偨傔挿偝傛傝傕懢偝偺曽偵孹偄偨偺偱偼側偄偐偲巚偆丅  丂丂丂丂丂 丂丂丂丂丂 嬠彴價儞帞堢偼傗偼傝壏搙娗棟偑戝曄廳梫偱偁傞偲擣幆偟偨丅傑偨弶傔偰偵傕娭傢傜偢俈俆mm 僆乕僶乕偑俁摢帞堢偱偒偨(俇摢拞梒拵娷傔係摢))偙偲偼戝曄枮懌偱偒偨偑丄戝偒偔堢偰偨梒拵傪 偄偐偵弅傑偝偢偵鍖壔偝偣傞偐偲偄偆壽戣偑巆偭偨丅 丂 丂 |
|
僆僆僋儚僈僞帞堢曬崘丂侾俋俋俈乣侾俋俋俉擭 亅弶傔偰塇壔偝偣偨僆僆僋儚僈僞亯俆俀倣倣亅 |
|
侾俋俋俈擭俆寧係擔丄僕儏儞僌儕傾儞僴儉僗僞乕偺塧傪攦偄偵嬤偔偺儁僢僩僔儑僢僾壆乽俀係亷乿傊峴
偭偨丅揦撪傪曕偄偰偄傞偲儗僕嬤偔偺捖楍扞偵丄愄僨僷乕僩側偳偱侾摢悢廫枩墌偲偄偆偲偰偮傕側 偄抣抜偱攧傜傟偰偄偨僆僆僋儚僈僞偺梒拵偑攧偭偰偄偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 側傫偲乽侾摢係俋俉侽墌両乿丅
崺拵傗惗偒暔偵慡偔嫽枴偑側偄恖偵偲偭偰偼丄婥帩偪埆偄偨偩偺堭拵侾摢偑側偤係俋俉侽墌傕偡
傞偺丠丄傑偟偰傗側偤偦傫側傕偺偵崅偄偍嬥傪弌偟偰攦偭偨傝偡傞偺丠偲晄巚媍偵巚傢傟傞偐 傕偟傟側偄偑丄梒彮偺帪戙丄挬偐傜斢傑偱崺拵傪曔傑偊偰梀傫偱偄偨昅幰偵偲偭偰偼崅椾偺壴 偱偁偭偨摬傟偺僆僆僋儚僈僞偑偨偭偨偺係俋俉侽墌偱攧傜傟偰偄傞側傫偰柌偺傛偆側偙偲偩偭偨丅 摉慠偡偖偵峸擖偟偨丅偨偩偟侾摢偩偗丅偲偄偆偺傕梒彮偺崰偐傜傑偲傕偵僋儚僈僞偺梒拵傪柍帠偵 塇壔偝偣偨偙偲偑側偐偭偨偨傔丄傑偨巰側偣偰偼傕偭偨偄側偄偲巚偭偨偐傜偩丅偟偐偟丄堦斢偦偺 梒拵傪挱傔偰偄傞偲丄乽傕偟柍帠偵塇壔偡傞偙偲偑弌棃偨偲偟偰傕亯偐亰偺偳偪傜偐偩丅偣偭偐偔 偩偐傜亯偲亰偺儁傾偺曽偑偄偄丄俀摢攦偊偽亯偲亰偵側傞偐傕偟傟側偄乿偲丄崱巚偊偽偲偰傕抪 偢偐偟偔梒抰偱埨堈側棟桼偱丄師偺擔偵傕偆侾摢攦偄偵峴偭偨丅摉帪偼傑偩僆僆僋儚僈僞偵偮偄 偰偺抦幆偼慡偔偲尵偭偰偄偄傎偳側偔丄偦偺梒拵偑亯側偺偐亰側偺偐慡偔傢偐傜側偐偭偨(崱偱 偼偍怟偺棏憙偺桳柍偱傎傏帗梇偺敾暿偑偱偒傞)偺偱丄丂俀摢攦偭偰偒偰傕偦傟偑亯偲亰偺儁 傾偲偼尷傜側偐偭偨丅巹偼偙傟偑偒偭偐偗偱梒彮帪戙偺崺拵擬偑傛傒偑偊傝丄僋儚僈僞帞堢傊 揢偭偰偄偭偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂  丂僆僆僋儚僈僞偺梒拵 丂僆僆僋儚僈僞偺梒拵亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅
僋僰僊傗僫儔側偳偺棊梩峀梩庽偺媭偪栘傪暡嵱偟偨栘孄(儅僢僩)傪媗傔崬傫偩摟柧僾儔僗僠僢僋 偺墌摏梕婍偺拞偵梒拵偑侾摢擖偭偰偄傞偺偩偑丄晛抜偼壗傕偟側偔偰偄偄丅偨偩梒拵偑偦偺儅 僢僩傪堦惗寽柦怘傋偰戝偒偔側傞偺傪懸偮偩偗偩丅偮傑傝帞堢偲偄偭偰傕偲偰傕戅孅側偺偩丅 摉慠丄梒拵偼尯娭偱傎偭偨傜偐偟偺忬懺偵側傞丅偨偩僆僆僋儚僈僞偵偮偄偰偺嫽枴偼偳傫偳傫 憹偟偰偄偒帞堢曽朄傗惗懺偵偮偄偰傕偭偲抦傝偨偔側偭偨丅恾彂娰偵峴偒恾娪傪挷傋偨傝偟偨丅 恾彂娰偵峴偔偺傕妛惗埲棃偱偁偭偨偑丄偦偙偺嶨帍僐乕僫乕偱乽寧姧傓偟乿偲偄偆側傫偲傕儅僯 傾僢僋側崺拵帍傪尒偮偗偨丅巹偼愭傎偳弎傋偨傛偆偵梒彮偺崰偐傜崺拵傪偼偠傔偄傠傫側惗偒 暔偵嫽枴傪帩偭偰偄偨偨傔丄幁帣搰戝妛偱悈嶻惗暔壔妛傪妛傫偱偄偨崰傕傛偔恾彂娰偵捠偄 惗暔丒壢妛宯偺嶨帍傗彂愋偵偼栚傪捠偟偰偒偨偑丄戝妛偺恾彂娰偵傕幁帣搰巗棫恾彂娰偵傕 偙傫側嶨帍偼抲偄偰偄側偐偭偨丅偝偢偑嬨廈偼嵟戝搒巗暉壀偺巗棫恾彂娰偱偁傞丅嫽枴捗乆  丂暉壀巗棫恾彂娰 丂暉壀巗棫恾彂娰偵儁乕僕傪傔偔偭偰偄偭偰巹偼偝傜偵嬃偄偨丅嶨帍偺姫枛偵側傫偲僆僆僋儚僈僞偺斕攧傪拞怱偲
偟偨偍揦偺峀崘偑悢傌乕僕傕嵹偭偰偄偨丅悽偺拞偼偡偱偵僆僆僋儚僈僞偺帞堢斕攧偑宱嵪 妶摦偲偟偰惉傝棫偭偰偄偨偺偩丅惉拵偺斕攧丄儅僢僩偺斕攧丄儅僢僩偵揧壛偡傞塰梴慺偺斕攧 嶻棏栘偺斕攧摍丅巹偼偦偺擔丄恾彂娰偱乽寧姧傓偟乿偺嵟怴崋偺傒側傜偢丄僋儚僈僞摿偵僆僆 僋儚僈僞偺帞堢偵偮偄偰偺婰帠偑徯夘偟偰偁傞僶僢僋僫儞僶乕傪慡晹撉傒偁偝偭偰帺戭偵婣偭 偨丅 亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅亅 乽寧姧傓偟乿傪撉傓偙偲偵傛偭偰偁傞掱搙僆僆僋儚僈僞偺抦幆傪摼傞偙偲偑偱偒偨丅偦傟偵傛傞偲丄 梒拵傪僋僰僊側偳偺媭偪栘偱堢偰傞(嵽帞堢)偲懢偔戝偒側屄懱偵側傞傜偟偄丅僆僆僋儚僈僞偼柤 慜偺捠傝丄擔杮偱偼堦斣戝偒側僋儚僈僞偱偁傝丄戝偒偔側傟偽側傞傎偳敆椡傕偁傝偐偭偙傛偔丄傑 偨偦偺壙抣傕崅偔側傞丅巹偼偣偭偐偔帞堢偡傞偺偱偁傟偽彮偟偱傕戝偒偔堢偰偨偄偲偄偆巚偄偐 傜丄憗懍捙戼嵧攟偵巊傢傟偨屻偺儂僟栘傪峸擖偟丄俀摢偺偆偪侾摢傪嵽帞堢偟偨丅偨偩嵽帞堢傪 偡傞偲梒拵偼栘偺拞偵擖偭偰偄偔偨傔丄摟柧側梕婍偱帞堢偟偰偄偨偲偒偲偼堘偄拞偺梒拵偺條 巕偑慡偔傢偐傜側偄丅埬偺掕嵽帞堢偟偨梒拵偼尯娭偺扞偺拞偱傎偭偨傜偐偟偺忬懺偲側偭偨丅 僆僆僋儚僈僞偺抦幆傕朙晉偵側偭偨俉寧弶弡丄嵽帞堢偟偰偄偨梒拵偑偳偆側偭偨偐抦傝偨偔偰嵽 傪妱偭偰拞偺條巕傪妋擣偡傞偙偲偵偟偨丅嵽傪庤偵偡傞偲儃儘儃儘偺偣偄偐偲偰傕廮傜偐偄丅  丂塇壔偟偨亯俆俀倣倣 丂塇壔偟偨亯俆俀倣倣偦偺偨傔嵽偼娙扨偵恀偭擇偮偵妱傞偙偲偑偱偒偨丅偳偺偔傜偄戝偒偔側偭偰偄傞偺偩傠偆偐偲偄偆 婜懸偲傕偟偐偟偨傜巰傫偱偄傞偺偱偼側偄偐偲偄偆晄埨側婥帩偪偱嵽偺拞傪尒偨丅崟偄屌傑傝偑 嵽偐傜儅僢僩偵揮偑傝棊偪偨丅巹偼堦弖巰傫偱崟偔側偭偨梒拵偑棊偪偨偲巚偭偨偑偦偺崟偄屌傑 傝偼摦偄偰偄傞丅乽偁偭丄塇壔偟偰偄傞丏丏丏乿丅偦偆梒拵偼偡偱偵塇壔偟偰偄偨偺偩丅晄埨側婥 帩偪偼悂偭旘傃丄婌傃偲姶寖偱嫽暠偟偨丅柌偵傑偱尒偨偁偺僆僆僋儚僈僞偺惉拵偱偁傞丅偦傟傕 僆僗丅塇壔偟偰娫傕側偄偺偩傠偆丄傑偩慡懱揑偵懱偑愒拑怓偱偁傞丅僆僆僋儚僈僞偺抦幆傪偐側 傝摼偰偄偨巹偵偼偦傟偑寛偟偰戝偒側屄懱偱偼側偄偙偲偑傢偐偭偨偑丄弶傔偰尒傞偦偺俆俀mm 偺僆僆僋儚僈僞偼偲偰傕戝偒偔尒偊偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 丂 |
|
摉僒僀僩偼IE5.0埲忋丄XGA(1024亊768)丄昞帵僼僅儞僩偱偺娐嫬傪慜採偵嶌惉偟偰偄傑偡 |