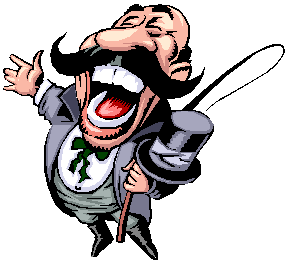|
�����ҥ��S�֎҂̒D�җ��@100���@
|
|
�@
�P�A���S���҂́A�ŏ�����Ō�܂ň�l�B�@ �Q�A�l���̐��́A�Ɛl�̐���茸�炵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@ �R�A��l�ł���Q����������̂Ȃ�A��̌����ɑł���B |
|
�@
�����փ^�u�[������
�����̎�@��
|
�@
�Q�A�Ɛl�Ƃ̐M���W�́A����ł̋�̓I�ȁu�|�������v �R�A���邽�߂̵���ݸ����݂́A�ŏ����ɂƂǂ߂�B�@ �@ |
�@
�@
 �@������w�
�T�_
�@������w�
�T�_
�@�����w�Ƃ́A�w��̈�ł͐S���w�Ɩ@���w�̊w�ۂɈʒu�Â�����Ǝ��̊w��ł����A�l�ԊW�̂������ʂɂ����ĕK�v�Ƃ����ėp�Ȋw��Ƃ��]���܂��B���������āA���̊w��ɂ����闝�_��Z�p�́A�����������s�����l�ɑ��āA�L���ɋ@�\����ł��傤�B
�@���������ӂ��ׂ��́A�r�W�l�X���w�ł́A�e�����ʗ��_�ł́g�ܔ��h���d�v�ȃv���X�v���ɂ��Ă��܂����A�^�̐M���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���\�̐����w�ɂ����ẮA�����̓}�C�i�X�v���ɂ����Ȃ�Ȃ��ȂǁA�T�O���`�ňقȂ�_�������A���̐����w���A�ߔN�̐S���w�u�[���ő���������r�W�l�X��̏����p���k���i��\�͂荞�ނ��߂̕����I�ꎞ�I�����p(���ȂɗL���Ȍ������l�����肷�邽�߂̌��p)�l�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@����́A�����̖{�����A�l�Ԃ̋��������̂���Љ�~���ɑ������邽�߂̏������Ƃ��āA�܂��A�l�Ԃ��Ƃ��Ă̑�������邽�߂̖��`�̏��Ƃ��āA�K�v��s���ȃR�~���j�P�[�V�����̓��屢Z�p�ł��邱�Ƃ���A���̊w��I�̌n�Ƃ��ẮA����(����ꂽ��ԥ�����̒��ŋ��ɐ�����)�ɕK�v�ȑΊO�I�g�M���h�āA�����傫����āA�g����(���ȋ]���̊o��)�h�Ƃ��Čł߂邽�߂ɁA�S�l�i�������Đ����Ɍ��t��s����s����(����Ɂg��������h�̂����玩�ȕېg�ł͐������Ȃ�)�Ƃ����w�\�̐����w�x�ƁA���Ɍ���Ă��Ĉ��������Ă��܂��������l�ԊW�������邱�Ƃ�ړI�ɁA�g����h���c�ݕώ����g����(���ȋ]���̑㏞�v��)�h�ɕς���Ă��܂����l�̐S�̋S���u���t�̖��p�v�ɂ��Â߁A����Ɏ����Ƃ̊W��������ɂƂ��ĉ��l�̂Ȃ������l�Ȃ��̂ƔF��������w���̐����w�x�Ƃ̓�̒��𒆊j�Ƃ��Đ����Ă��܂��B���̎�@�Ƃ��ẮA�����̐S������Z�p�ł͂Ȃ��A�S�l�i�`���ւ̒����Z�p����e�Ƃ��Ă��܂��B
�@�܂��A�Տ��S���m��J�E���Z���[���ƑΔ䂷��Ȃ�A�S���Ö@�m���܂߂������́A���k�҂�Ώێ҂̐S����Ԃ₻�̊W���̌������݂͂̂��s���A���k�҂̎��ȉ��P�⎩�ȗU������̏���ⳂƂ��܂����A�����w�ɂ����Ắu�����Ƃ͕ω����邱�Ƃł���A�l�̐S�E�l�i�͎��ʂ܂Ő�������v�Ƃ������Ƃ����ɂ��Ă���A���k�҂����łȂ����̑Ώێ҂����A�����̑ΏۂƂ��Đl�i�I����(�P�s�ւ̕ω�)���ʂ����Ă��炤���Ƃɂ���܂��B
�@���̂悤�Ɂw�����w�x�́A�S���w�ɂ����錻�����͂Ɏ~�܂�Ȃ��u�����̓�������v�Ƃ����N�w�I�e�[�[���܂ދɂ߂Đ[���Ȃ�w��Ƃ��Ĉʒu�Â����A����̕��G�Ȑl�ԊW�ɂ����ẮA�K�{�̗��_�̌n�ł���Ɖ]����ł��傤�B
�T�D�w���xnegotiation, bargaining
���D�����^[���a(�m����[���T��)]�E�����I����(All Win)
| ���ԕ�(Give and Take)�^�_���X���_���F�m�I��ѐ�(Cognitive consistency)�̌����� |
[�ړI]�@�o���̗v�������A�o���ɍő�̔z�����v�Ɩ�����(���l�]���̏C��)��
�@��
[����]�@���݈ˑ��W(�q�ςƎ��)�̗L���A�S�I�����̒��o�����(�e���ڂ��Ƃɑ��ݑ��v�ɂ�鋤�ʗ��v�ƑΗ����v���v��)�A���݂̋��͉\������BATNA(Best
Alternative To No Agreement)��\���v��
�@��
[�v��]�@���D�ʂȑË��_�Ɍ������邽�߂̎�i�I��----ex.�����I�����@(Door in the face)�A�������Ƃ��Ă̗��ʒ@(�����ƐM���̋��n�����)
�@��
[���s]�@�o���̒�ĂƏ����ɂ���̍��ӌ`��(���茋��)
����
��[�ĕ��͂ƍČv��]�@�����ɂ��BATNA�͈̔͌��艻�ƌ��ߒ��ł̏_��Ȍ����������ȃR�~�b�g�����g(�����ʂ̖�����)
�@�@(�) ���ʂ̍���----���`���܂߂��ŗǂ̗��v(�ŏ��̔�p�Ɗ댯)�ł̑��ݔ[���̎擾�������Ԃ�(�����ύX)�̋֎~
���D�������z�^[��a(�[���T��)]�E���ݔr���I����(Only Win)
| ������(thread)�̗��_�������I��ѐ�(Attitudinal
consistency)�̌����� ���s��(anxiety)�̗��_���Љ�I�ؖ�(�펯)�^�D�Ӂ^���Ђ̌����� |
[�ړI]�@����݂̗̂v�������A�����ɍő�̕s���v�Ƌ��J��(����ɂ�閞����)��^����
�@��
[����]�@�Ɨ���]���W�̗L��(���݈ˑ��̕s����)�A�Ώۂ̍ő哮�@�v���̔����A���@�v���̔r���s���Ɣ\�͂̐���
�@��
[�v��]�@�ő�e�����ʂ̎�i�I��(�����ݒ�Ƒԓx�ϗe�̕K�R�I���ʐ�)----ex.���ΐ��ɂ��Жʒ@
�@��
[���s]�@����̒�ĂƑ����̏��n�ɂ���̍��ӌ`��(���茋�ʂƌ��茋��)
�@�@(�)
��i�̍���----���m���̔�p�Ɗ댯���Î闧��Œ�̔[��----ex.�������A�A�������A��O�Ғ���
�@�@(�) ���ʂ̍���----�ő�̔�p�Ɗ댯�ł̔[��(����)�擾�������Ԃ�(��)�̗}�~
�@
�U�D�w�����xpersuade
| ���j��n���̗��_(Crush
and build)���l�i�I��ѐ�(Identity consistency)�̌����� ���e�a���̗��_(We Feeling)�^���̌����� |
[�ړI]�@�����̍K����Nj����A���Ȃ��܂߂��ő�̏������v�Ə[����(���l�]���̕ύX�Ǝ��Ȏ���)��
�@��
[����]�@�M���W�̗L���A�Ώۂ̐^=�q�ϓI���v�̒T�������A��ϓI�ő剿�l(�~�����v)�̔F�m
�@��
[�v��]�@�`�B�̎�@�E�^�C�~���O�̑I��----�l�i�ϗe(����)�̂��߂̖����@(���^�ƐM���̋���)�A�u�[���������ʂɂ���R�ƌ��p
�@��
[���s]�@�ЂƂ̍��ӌ`��(������@)�ƐM�������̊�����
�@�@(�) ��i�̈ꎞ����----���m���̔�p�Ɗ댯���Î�[���̎擾�������Ԃ�(�čl)�̋@���
�@�@(�) ���ʂւ̑��ݓw��
��A�������̈��ʗ�
�@�u�������v��"����"�s�ׂɂ���Đ��܂��"����"�́A�u�ԓx�ϗe�v�ł���B
�����́u�ԓx�ϗe�v��"�ړI"���ʂ����ׂɍs����u�������v��"��i"�́A��ł͂Ȃ��B
�@�����Ƃ́A���Ȃ���ё��҂̉��l�ςɉe����^���錴���R�~���j�P�[�V���� (�S���I�s���l��)�ł���B
�@���Ƃ́A���҂ƊW���\�z���悤�Ƃ���R�~���j�P�[�V��������(�Љ�I�s���l��)�ł���B�䂦�ɁA�W�̃t���[�~���O(�g�g�݉������Ɨ��v�̌Œ�R���g���[����)�ɂ��A�Q�[�����_�ł̊Ǘ����\�ƂȂ�A���̌��̐��ۂ́A�V���̏���(��������)�ƂR���̎��s(�O������)�Ō��܂邱�ƂɂȂ�B
�k���������l+�k���������l+�k���������l�ˁ@�ԓx�ϗe
��A�������̑Ώ�
�@������^����Ώۂ́A�u�l�v�^������҂̓��@�Â��@�\(Incentive)
�@ ���R(��)�I���݂Ƃ��Ă̐l
�@a. �{�\�I�~��(���v�E�m���̊l���{�\)���ڋߍs���k�����l���l�@
�@b. ���Ȗh�q(�O�I�댯�E���I����)������s���k�����l���l
�A �Љ�I���݂Ƃ��Ă̐l���l�̐��i��W�c�̈ʒu�Â�
�@a. ���Ȏ����~��(���ȉ��l�̑��ҕ]��)���ڋߍs���k�����l���l
�@b. �K���h�q(�����W�c�ւ̋A���~��)���ڋߍs���k�����l���l
�O�A�������̊�{�v�f
�y���̂P�z��l�̓��I�v�f�^�S�I�����v���̕���-------------
�P�A�ԓx(attitude)�̂R�v�f�ƐS���I���փT�C�N��
�@�`�D���m�E�Œ�̑ԓx���F�m(cognition)+����(affect)+�s��(behavior)
�@�a�D�ϗe����ԓx�ƘA������R�v�f
�@�@�@�@�v���X���l(value)�̃T�C�N���˲��ڥ�X�p�C����
�@�@�@�@���F�m(�ǂ�)������(�D��)�ˍs��(�ڋ�)
�@�@�@�@������(�D��)���F�m(�ǂ�)�ˍs��(�ڋ�)
�@�@�@�@���s��(�ڋ�)������(�D��)�˔F�m(�ǂ�)
�@�@�@�@���s��(�ڋ�)���F�m(�ǂ�)�ˊ���(�D��)
�@�@�@�A�}�C�i�X���l(value)�̃T�C�N�������ڥ�X�p�C�����^���l�̼���ρ@
�@�@�@�@���F�m(����)������(����)�ˍs��(���)
�@�@�@�@������(����)���F�m(����)�ˍs��(���)
�@�@�@�@���s��(���)������(����)�˔F�m(����)
�@�@�@�@���s��(���)���F�m(����)�ˊ���(����)
�Q�A�����̎��ƌ��̊�
�@�@��(����)�̐����@�@��(��)�̐����@�@�@���̊W(����)
�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�k�F�m(�������ǂ��l+�k����(�������D���l+�k�s��(������ڋ߁l �ˁ@�����l���̑ԓx�ϗe
�k�F�m(�ǂ��������l+�k����(�D���������l+�k�s��(�ڋ߁�����l �ˁ@�����l���̑ԓx�ϗe
�@�@�@�@�@�@���@�s��(�ڋ�)�Œ�ɂ�鋭���I���ȏ���
�y���̂Q�z�Όl�Ƃ̊O�I�v�f�^��ҊԂ̐����v���ƌ��W-------------
�P�A�ԓx�E���l�̉ϐ��Ǝ���(time)�E�Ԋu(distance)�̗Z�ʐ�
�@�� �����ȗZ�ʂ́A�w�͂̐������Ƃ������l�ϗe�������Ă��܂��B
���s�\�ȉ��l�����̎��_�o�߂ɂ��"����(�u��������)"
���i�K����(���݃��[��)�ɂ����������\��(����)
�����������̓S�����Ō�͈�������(��蓯��)
��j�ԓx�ϗe�̉ϐ��̔��f�Ƒ�^�Љ�f���_�ƃA���J�[���ʁ����Ғl
�@�@�@�@����(��D���̑匙��)�h���ƔF�m(�m��]���̕s�m��]��)�h��
�@�@�@�@�@�@�@�ア�h������W���_��T��
���������l�̃M���b�v���v�Z���ăA���J�[�W���_��ƂB
�k������(��D��)�l+�k�F�m(���]��) �l���A���J�[�M���b�v(��)�@�ˁ@�����l���̑ԓx�ϗe
�k����(����)�l+�k���F�m(�s�m��]��) �l���A���J�[�M���b�v(��)�@�ˁ@�����l���̑ԓx�ϗe
�k����(����)�l+�k���F�m(�m��]��) �l���A���J�[�M���b�v(��)�@�ˁ@�����l���̑ԓx�Œ�
�k������(�匙��)�l+�k�F�m(���]��) �l���A���J�[�M���b�v(��)�@�ˁ@�����l���̑ԓx�Œ�
�@�� �����̎O��e�N�j�b�N�ƌ����Ă������
�@�@�@�@�@Foot in the door
�@�@�@�A�@Door in the face
�@�@�@�B�@Low ball
ہj�e�v�f�̉ϐ��Ɠ��@�Â��@�\
�@�@�@�@�k����(�D��)�la�{�\�I�~����b���Ȗh�q�@�^����(�l)�I��ѐ�
�@�@�@�A�k�F�m(�P��)�l��a���Ȏ����~����b�K���h�q�^�O��(�Љ�)�I��ѐ�
ʁj�T�^�I�Ȍ��X�^�C���Ƃ̊W
�k�@�����̗\�h��p�@���@�����̉�p�@�l
�@�@�������́A��Βl(����)�ł͂Ȃ��A���Βl(����)�Ŕ��f����B
�@�@���������(�R���j���[�g��������)�̏d�v��
�@�@�����X�N���U(���|�[�g�t�H���I�헪)
���~�j�}�b�N�X�ƌ`�Ȑ���
�@�@�@�@�@���肪�A�ő��a�~��[���v]�ƍŏ���b�h�q[����]�������āA �ŗǂ�s�����O�����
�@�@�@�@�� �~�j�}�b�N�X�헪(Strategy)�^�ő�(mini)�̑������ŏ�(max)�ɂ���B
�@�@�@�A�@�������A�ő��a�~��[���v]�ƍŏ���b�h�q[����]�������āA �ŗǂ�s�����O�����
�@�@�@�@�� �}�L�V�~���헪(Strategy)�^���v�̍ŏ��l(mini)���ő�(max)�ɂ���B
�@�`�D���z�^����(Win-Lose)�̖ړI�Ǝ�i
�@�@�@�@���@�[���E�T���E�Q�[��(�u���b�N����)
�@�@�@�@�@�@�@�^�~�j�}�b�N�X�헪�ł̈Ƃ�"�����"��"���Ƃ�"��
�@�@�@�@�@�@�@�^���l�̃W�����}�Ɨ���(�ă��[��������د�"���")
�@�@�@�@����{�����Ƒ������ؕԂ�(�װ��p)
�@�@���@���ȓI�s���𗘑��I���ʂɓ����˖��̕���
�@�@�@�@�@�t���[�~���O(Framing)�Ƌ���(Threat & Penalty)
�@�@�@�@�@�@�@�^���l�̃W�����}(������ݹް�)��E�o����
�@�@�@�@�@�@�@�^�ă��[��(���ݹް�)���̌��Ƌ����̐�胋�[��(���ݹް�)��
�@
�@�a�D�����I����(Win-Win)�̖ړI�Ǝ�i
�@�@�@�@���@�i�b�V���ύt�ƃp���[�g�œK�l(BATNA)
�@�@�@�@�@�@�@�^�ϗ��ƐS���ɂ�鉿�l�̕ύX
�@�@���@�|�W���V���j���O(Positioning)�̏����ł��Ă̕ԕ�(Give and Take)
�@�`�D���m�E�Œ�̉��l�ł̌���i�����z�^����(Win-Lose)
�@�@�@�@�ԓx�ϗe(����)+�����̎���(���Ȃ�)+���s�̊Ԋu(�Z��)
�@�@�@�@�����ړI(����̉��l������ۂ�D������)
�@�a�D�ϓ����鉿�l�ł̌���i�������I����(Win-Win)
�@�@�@�@�ԓx�ϗe(����)+�����̎���(����)+���s�̊Ԋu(����)
�@�@�@�A�ԓx�ϗe(�_��)+�����̎���(���Ȃ�)+���s�̊Ԋu(�Z��)
�@�@�@�@�����ړI(�قȂ鉿�l������ۂ�����)
�Q�A�{�l�̑ԓx�ϗe(�����Ȑ���)�Ƒ���̑ԓx�ϗe(�����Ґ���)
�@�`�D����̍ő剿�l��D�����߂̎��Ȑ����Ƒ��Ґ���
�@�����z�^����(Win-Lose)
�@�@���@�k��i�l�����̃~�jϯ��(�ŏ���)���k���ʁl�����������ϯ��(�ő剻)
�@�@�@�@�^����̐�Η�ʏ���(��i)��o���̖����l������(�ڰѱ��)
�@�@�@�@�@�@��Nash�ύt�_�̔���
�@�������o�����X��(�������Y����)�ɂ�鉿�l�̑Γ�
�@�@���@�����~�j�}�b�N�X��p�ɂ�����D�ʏ����̊��Ǝ��s�̌��p
�@�a�D���݂̍ő剿�l�����邽�߂̎��Ȑ����Ƒ��Ґ���
�@�������I����(Win-Win)
�@�@���@����\��(Release)�Ɨ���Œ�(Persist)�^��ѐ�����
�R�A��ҊԂ̌p���I�W���ێ����鎖�O����(Commitment)�Ǝ������(Re-commitment)
�@�`�D���z�^����(Win-Lose)
�@�@���@�ꕔ���ϖƏ��̃K�X�������ʁ^�̗\�h
�@�@���@�͂ɂ�闝�z�Ì��_(Nash�ύt�_�������o���Ȃ����ȓ_)�̈ێ�
�@�a�D�����I����(Win-Win)
�@�@���@���͂ɂ����E�v���x(Shapley���ϒl���͏��ɂ�鑹������)��
�@�@�@�@�@���z�Ì��_(Nash�ύt�_)�ɂ�錋��(�ڋ�)�s���̊����ݒ�
�@�@���@�����ݒ肪�ł��Ȃ��ꍇ�A�J��Ԃ��̃t�H�[�N�藝�ɂ��
�@�@�@�@�@�C�����ꂽ����(�ڋ�)�s��
�����@�ᖡ�\�����f��(elaboration
likelihood model)
�@�ԓx�ϗe�̌����v�f�Ƃ��āA��̎�e�v�f���������āA�������ʂ̋��x��p�����f���闝�_�B
<�葤>
�T�D���̐[���ᖡ����k����"�K�v��"�̗L���^���@�Â�[�F�m�~��]�̋��x�^���w��[�����ʂ̐�����]�̒��x
�@�i�L)��Door in the face øƯ��^�A���J�[�W���M���b�v�̋��e�͈�(�L)
�@�i��)��Foot in the door øƯ��^�A���J�[�W���M���b�v�̋��e�͈�(��)
�@�i�L)���_���@�^�F�m�̕ϗe
�@�i��)���R��@�^����̕ϗe
�U�D����[���ᖡ����k������"�\��"�̗L��
�@�i�L)�����ʒ@
�@�i��)���Жʒ@
<�����葤>
�V�D��M�҂̊O���I���͂�M�ߐ�(����ݸ�)��ԕ̗L��[peripheral cue]
�����S���[�g[central
route]
�@�@�T(�L)+�U(�L)�ˏ��̋ᖡ����k���̎��s
�@�@���ԓx�ϗe������Œ艻�^������(��)���t�����̒�R��(��)
�����Ӄ��[�g[peripheral route]
�@�A�T(��)+�U(��)�ˏ��̋ᖡ����k���̕s���s
�@�@�T(��)+�U(��)+�V(�L)�ˏ��̋ᖡ����k���̎��s
�@�@���ԓx�ϗe������Œ艻�^������(��)���t�����̒�R��(��)
�@�B�T(�L)+�U(��)�ˏ��̋ᖡ����k���̕s���s
�@�@�T(�L)+�U(��)+�V(�L)�ˏ��̋ᖡ����k���̎��s
�@�@���ԓx�ϗe������Œ艻�^������(����)���t�����̒�R��(��)
�@�C�T(��)+�U(�L)�ˏ��̋ᖡ����k���̕s���s
�@�@�T(��)+�U(�L)+�V(�L)�ˏ��̋ᖡ����k���̎��s
�@�@���ԓx�ϗe������Œ艻�^������(��)���t�����̒�R��(����)
�����@�S���I���A�N�^���X���_(psychological
reactance theory)
�@�������S�����R�ȑԓx������ł����Ԃɂ���ƐM���Ă���҂́A�O�����玩�R��[�F�m��s��]����𐧌�����h������ƁA���ۂɐN�Q����O����A���R�ȐS�I��Ԃ��Ŏ�����悤�Ɠ��@�Â�����ԓx�ϗe[����]�̏�Q�@�\�͂������_�B
�@���@�S�I��R���ł��Ȃ��Ǝ��o�������ŁA�����I���ȏ������ʂ�������B
�T�D���������F�m��s���˕⋭�����l��(a.����h�q�@�\ + c.���l�\���@�\�̗~��)
�@�@���ړI���R�s�����w��s����ގ��s���̐ϋɓI�F�m��s��
�@�A�ԐړI���R�s��[���]���w��s����ގ��s���̐ϋɓI�F�m��s��
�@�B�����ɑ��銴��[����]���F�m����s���̒ጸ
�U�D���������F�m��s���˖����l��(d.�m��[�m�x���擾�~��]�@�\�̕���)
�@�@�������l�����u�[����������
�@�@���ړI���R�s�����w��s����ގ��s���̏��ɓI�F�m��s��
�@�A�ԐړI���R�s��[���]���w��s����ގ��s���̏��ɓI�F�m��s��
�@�B�����ɑ��銴��[����]���F�m(���̈�)�����(��)��s��(���)�̒ጸ
<�e���v���̋��x>
�@�@�N�Q����鎩�R�̏d�v�x[��]�^�F�m��s��
�@�A�N�Q����鎩�R�̊���[��]�^�F�m��s��
�@�B���Q���Ђ̑傫��[�����]�^�F�m(���̈�)�����(��)��s��(���)�̒ጸ
�y���̂R�z�Α�O��(�Љ�)�Ƃ̊O�I�v�f�^�O�ҊԂ̐����v���ƌ��W-------------
�P�A �o�����X(balance theory)�ƓK��(congruity
model)�̗��_
�k�����̎O�p�Ǘ��l
��(��O�ҥ�Љ�)
�^�@�@�@�@�@�_
�b(�{�l)�@�\�\�\�\�@��(����)
��j���@�Â��@�\�ƈ�ѐ��̉�����ԓx�ϗe
�@�@�k�F�m(�P�E��)�l��a���Ȏ����~����b�K���h�q�^�O��(�Љ�)�I��ѐ�
�@�@�@�@�@�@���o�����X���_�ɂ��O�p�Ǘ�
�@�A�k����(�D�E��)�l��a�{�\�I�~����b���Ȗh�q�@�^����(�l)�I��ѐ�
�@�@�@�@�@�@���K�����_�ɂ��O�p�Ǘ�
�����@�o�����X���_(balance
theory)�^�F�m�I�s���a���_
�@�O�ҊW�ł̑Η��̐ς��C���o�����X(�)��Ԃ��ƁA�ْ���s�����̃X�g���X���o������̂ŁA������������āu�F�m�I���a�̃o�����X(�������Ώ�symmetry)�v�����悤�ƁA�ł��X�g���X�̋����҂��A�ł��ω������₷���ӏ��Ɍ������đԓx�ϗe���|����B
���@�o�����X���(�ԓx�ϗe�̋N����Ȃ����)
�@�@�@���S��������
�@�@�@�����肪�����ŁA��O�҂��G���E����Ƒ�O�҂͓G��
�@�@�@�����肪�G���ŁA��O�҂������E����Ƒ�O�҂͓G��
�@�@�@������Ƒ�O�҂��G���E����Ƒ�O�҂͗F�D
���@�C���o�����X���(�ԓx�ϗe�̋N������)
�@�@�@������Ƒ�O�҂Ƃ������Ȃ̂ɁA���̗��҂��G���Ă���B
�@�@�@����O�҂ƓG���Ă���̂ɁA�����̑���Ƒ�O�҂��F�D�B
�@�@�@������ƓG���Ă���̂ɁA�����̑�O�҂Ƒ��肪�F�D�B
�@�@�@���S�����G������B��
���@���Ƃ��A�G�ł��鑊��̓G(��O��)�͖����Ȃ̂ɁA�����Ė{�l����O�҂ƓG����ƁA�l�I��ѐ���Љ�I��ѐ�(���a���Ώ̢����ذ��̒���)�����邽�߂ɁA����́A�{�l����O�҂̂ǂ��炩�e�Ղȕ��֑ԓx�ϗe���N�����B�����@�K�������_(congruity model)
�@�{�l�̑�O�҂ւ̑ԓx�Œ�[����]��m�邱�Ƃɂ��A�O�ҊԂ́u����I�K����(���������ɂ�鉿�l�̔���ƍĊ�)�v���͂��邽�߂ɁA����͖{�l�Ƒ�O�҂ɑ���ԓx�ϗe[����]���ɑ�������x�N�g���ŋN�����B
���@�K�����(�ԓx�ϗe�̋N����Ȃ����)
�@�@�@�{�l����O��(����)��
�@�@�@�@�����聨�{�l(����)
�@�@�@�@�����聨��O��(�D��)
���@�s�K�����(�ԓx�ϗe�̋N������)�@�^�����l��
�@�@�@�{�l����O��(�D��)��
�@�@�@�@�����聨�{�l(����)
�@�@�@�@�����聨��O��(����)
���@�s�K�����(�ԓx�ϗe�̋N������) �^�����l��
�@�@�@�{�l����O��(����)��
�@�@�@�@�����聨�{�l(�匙��)
�@�@�@�@�����聨��O��(��D��)
���@���Ƃ��A���肪�����������Ă���ꍇ�ɁA�D�ӂ����܂ł̑ԓx�ϗe���N��������ɂ́A���肪��D���ȑ�O��(����)����������D���ł��邱�Ƃ�`��������A����̑�O�҂ւ̊���(�D��)�𔖂������鎖���]���ɁA�����ւ̍D�ӂɊ����邱�Ƃ��ł���B�^�����̋Z�p�Ƃ��ĉ��p�Q�A���ɂ������O�҂̉��
�@���@�������̒S�ہ^�������(Hallo effect)�ƔF�m�I�ύt�̈ێ�
�@
�@������^���ɑ��k���Ă��A���ۂɐ���������s�����k�҂��A���̃A�h�o�C�X��N�`���[�����H�ł���Z�\���Ȃ���A�\�肷�錋�ʂ��o�����Ƃ͂ł��܂���B�����ŁA���H���錻��S���҂⑊�k�Ҏ��g�̐������\�͂����߂邽�߂ɁA�����c�[�}���̖������[���v���C�ɂ��u���t��I�сA�Ԃ��v��v���߂̃g���[�j���O�E�T�[�r�X��V�݂��܂����B
|
�����̃g���[�j���O(�Όl)
|
�@3���~�@�^30���`50���i�P���ɂ��j |
|
���̃f�B�x�[�e�B���O(�Ή��)
|
�@5���~�@�^30���`50���i�P���ɂ��j |