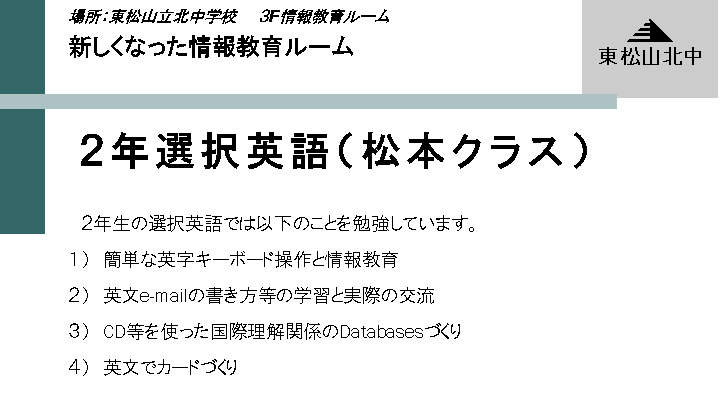Mediaと英語教育
99/10/13
MediaというとInternet、校内LAN、学習CD、ソフト等コンピューターがらみのCALL機材をすぐ思い起こされると思う。
しかし、実際にはラジカセ、ビデオ、ピクチャー、センテンスカード、バーコードリピーターなどの日ごろ使っているものもMediaである。古くから同じような使い方をしているそれらのTeaching_aidsには生徒はあまり興味を示さないだろう。
新しいMediaの方が生徒は興味を示す。だから、New-mediaは大切である。
根本的にInternetも新しいMediaのひとつとして言語学習に活用されようとしている。
しかし、まだ中学の設備段階は第一段階であって、日常的なものになっていない。だから、生徒にはFreshな印象がある。
さて、Global Educationでは「Media自体がMessageをもち、学習者と学習対象との間に介在するすべてのもの・ことがMedia」なのである。これは平成8年夏先よりこのWebでも言いつづけていることである。
つまり、教科書、ノート、筆記用具から教室環境教室内生徒間人間関係、教師と生徒の人間関係、教師の人柄などもMediaなのである。
コミュニケーション活動したいのなら、コミュニケーションの存在するMediaが必要である。私たち’外国語指導者というMedia’は「積極的にコミュニケーションを図る」存在になっているだろうか。その姿勢態度は学習者に少なからず影響していることは否めない事実であろう。
単に指導法だけ論じても、学習環境を無視しては良い授業は成立しないだろう。教科書だけを徹底してやれる先生などは、その先生自身の人柄、パーソナリティが生徒に多大に影響している。
逆も言える、Classroom_controlがうまくできない場合はMediaの改善・開発や学習環境整備をした方が良いと。
Mediaは常に進化し、流動的である。
ひとつのMediaに固執することなく、生徒学習者側のNeedsと実態を把握した上で上手に、柔軟的に、タイミング良く活用していきたい。
上で述べているように必要です。しかし、その流動的で進化する性質を見極めていないと多大な投資の割に教育的効果が少ないことがある。私流に言わせてもらうと、「労多くして功少なし」の効率の悪い指導法になる。かつてのLL教室はどうなったか?
Mediaは必要であるが、それらに引きずりまわされたらいけない。現在、生徒よりも先生や大人の方がInternetへの過大な期待をしていると同時に、興味関心が高くなっている気がする。
せっかくLANボードで40台をWebにつないでも、「さあ、みんなWebツアーしてみよう!」の先生の呼びかけに、「別に見たくナーイ!」の生徒の返答もよくあることである。
指導者のSuppliesと学習者のDemandsが一致していないのである。
周りがそうだからそのMediaというのではなくて、目の前の学習者に今必要とされるからそのMediaなのである。
今現在、英語科指導法が社会で問い質されている。「使えてナンボ」の英語だと言う。Mediaはそれゆえ、実体験場面を作り出せるものでなければならないだろう。よりAuthenticでReal_worldなものを提供できるものである必要がある。
New MediaとしてのInternetは今脚光を浴びている。Screenの向こうにRealな世界が広がると思うからである。それはまさに実践的なコミュニケーションの場面設定には打ってつけであろう。
だから、Internetを活用してあげたい、しかし、学習者はどう思っているのだろうか。コンピューター嫌いの生徒はいないだろうか。Screenの向こうに本当にRealな世界があるだろうか。Screenの向こうにコミュニケーションは本当に存在するだろうか。
実際に使用するには、予想以上のメンテナンスや準備に労力を要するのである。
New_Mediaを導入する際には、先見の目をもって現状を確実に把握しておく必要だけは絶対にある。
基本的にMediaはいつ如何なる時も、常に英語授業に関わっているだろう(上述の1のような考え方ならば(^.^;)。
下記の実践は私が過去実際に行ったものの一部です。
1) 一教室内授業で主に「導入の場面」や「言語活動・演習」として <一斉授業形態>
{VCRでのSKIT導入練習、TRでの音声練習やRepeating/Shadowing、Worksheet学習等}
2) 一教室内授業で「言語活動・コミュニケーション活動」として <一斉授業・グループ学習形態>
{WorksheetやPedagogical_Taskを使っての言語活動等}
3) 複数教室内授業で「言語活動・コミュニケーション活動」として <グループ学習・個別学習形態>
{学習環境スペースを広げ課題を複数設けることによるT-T、Interview、Recitation_Testing等}
4) 情報教育教室内授業で「英語への興味関心意欲付け(English
Needs)」として<一斉授業形態>
{異文化に関する画像等、個人の全体への英語プレゼンテーション、海外E-mail交流等}
5) 情報教育教室内授業で「言語活動・コミュニケーション活動」として<グループ学習・個別学習形態>
{校内英語/異文化掲示板への投稿等、校内E-mail交流等}
6) 情報教育教室内授業で「言語活動・調べ学習・文法、語彙学習」として<個別学習形態>
{百科事典CDを使ったDatabaseづくり、教科書準拠のCD活用、Study_netを活用した「みんなでStudy」等}
7) 複数教室及び情報教育教室併用授業で「完全個別学習」として<個別学習形態>
{情報教育ルームでの複数の文法・語彙ソフトを自分で選んで学習 と LL教室での自主学習の同時並行授業等}
すべて生徒実態や学習環境現状に合わせて形態を考える。現状を認識した上で、どのMediaが活用できるか考える。
当たり前だが、目的は英語力の向上に他ならない。さらに欲を言えば、英語力= 「実践的実用的英語力」であり、それは「英語への興味関心意欲」や「コミュニケーション能力」、さらに「国際人としてのGlobal_Perspective」を併せ持つ。
上記の目的に近づけるべく、日ごろのMedia活用の目標は:
1.授業のマンネリ化を防ぐべくNew_Mediaを使い、学習者のMotivationを高める
2.生徒の視野を広げるため、「教室から外へ」でて英語体験学習する
3.英語が実際に使用される場面を設定したり、見せたりする
4.英語を使ってRealな交流をする
5.英語を使ってNew InformationやMessageの送受信を行う
6.画像や音声を活用してAuthenticな英語を学習する
7.その他
英語が好きになるような活用がまず最優先されるだろう。
Media活用の課題はたくさんあるだろうが、ことNew Media
に関しては下記のようなものだろう。
1.Mediaの操作に熟練する
2.教育的効果を把握する
3.教科書との併用
4.Mediaの使用可能状況(常に使用できるのか、限られているのか)
5.Media活用のきまり(Internetの場合はネチケットと言われている)
6.Media活用にあたっての周囲の理解(参考;下記の文化祭での公開)
7.その他
地域への公開・発信(文化祭での展示)
< 校内LANが完成してから、初めての北中での文化祭公開 >
平成9年度から平成11年度ここ2年半の実践をStudy-Note_viewerやBrowserを使って文化祭第2日目に公開しました。
内容:
1) 平成9年からの海外e-mail交流の実践報告 2) 校内LANを使ったe-mail交流の実践報告 3) 異文化理解に関するDatabase
詳細: ここ
結果:
生徒はたくさんやってきて(エアコンが効いているせいもある(^^;)、展示作品を見た後はいろいろGAMEをやっていました。
ご父兄の方々も思った以上にご覧頂いてうれしかったです。ご父兄の方に操作を説明しながら現状のSYSTEMでできること、できないことなどをご説明したりしました。「へーすごいねー!」「楽しそうだねー」「あれなら飽きないねー!」という類のお言葉が多かったと思います。やはりまだ、情報化社会とは言っても、まだまだ各家庭へ浸透しているとは言えないような気がしました。
今ある設備で最大限に「生徒が国際化・情報化を知り、学ぶ」ことができるように指導していることをお分かりいただけたら幸いだと思いました。
学校格差が広がりつつある今日、地元地域の児童・生徒が遅れをとらないように、「今ある設備で最大限の努力」をしていくことはとても大切だと思っています。
課題:
来年度も、もし北中に勤務していたなら今年度をさらに発展させ、平常授業での「教科書準拠CDの実践」やLANを利用したPresentation、協同学習を選択英語といっしょに発表・公開したいと思います。
ただし、今年度の発表に刺激されて他教科でも発表をしたいとなると、情報教育ルームがひとつだけなので厳しいですが(^^;