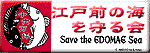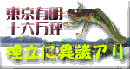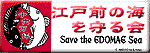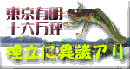資料集
日時:2000年6月10日午後1時より
場所:芝浦サービスセンター
= プログラム =
(1)有明北(十六万坪)のビデオ上映
(2) 工藤孝浩氏より基調講演
東京湾の魚たち―ハゼを中心にして
(3)パネラーからの発言
コーディネーター:鈴木康友氏(つり人社社長)
開発法子氏(日本自然保護協会)
東京湾開発―三番瀬をめぐって
安田進氏(屋形船・つり船晴海屋)
遊魚船として東京湾埋立てを考える
前田直哉氏(都政ウオッチャー)
臨海副都心開発と十六万坪の埋立て
(4)会場参加者とのディスカッション
(5)宣言文採択
資料説明
€参加団体一覧
工藤孝浩氏レジメ ¡月刊つり人99.9月号記事より
¤開発法子氏レジメ ¦日本自然保護協会(後援団体)紹介
©前田直哉氏臨海副都心問題資料
ª有明北事業計画(旧有明貯木場)のあらましと問題点
«有明北地区埋立問題を考える(月刊つり人記事より)
参加団体紹介
江戸前の海十六万坪(有明)を守る会、東京湾・十六坪の自然を守る会
内川と内川河口をよみがえらせる会、東京勤労者つり団体連合会
しのばず自然観察会、江戸川自然観察クラブ、いたばし野鳥クラブ
科学と社会を考える土曜講座、東京湾の浅海干潟に親しむ会
隅田川を愛する会、水郷水都全国会議東京大会実行委員会
高尾山の自然を守る市民の会、諫早干潟緊急救済東京事務所
FAネットワーク、市川緑の市民フォーラム、千葉の干潟を守る会
野鳥の会・三番瀬グループ、北限のトビハゼを守る会、三番瀬を守る会
三番瀬埋め立て案の問題点、三番瀬を守る署名ネットワーク、行徳野鳥観察舎友の会、小櫃川の水を守る会、
小櫃川源流域の自然を守り育む連絡会
海をつくる会、東京湾海洋研究会、川崎公害根絶・市民連絡会
横浜金澤地域総合研究集団(KYATS)
(後援団体)WWFJapan、日本湿地ネットワーク
®東京湾・ハゼサミット宣言(案)
*裏面の参加団体の追加
●横浜金澤地域総合研究集団(KYATS)佐治聖介(マサヨシ) 横浜市中区塚越96
電話&FAX:045(681)2614
基 調 講 演
東京湾の魚たち ―――ハゼを中心にして―――
工藤孝浩(神奈川県水産総合研究所主任研究員)
1.東京湾の魚類相
(1)魚類の分布構造
・平場の魚類・・・・・・・・・・水産資源として重要、海底の貧酸素化に影響
・浅海域の魚類・・・・・・・・・・・・・・内湾型グループと湾口型グループ
(2)生活史と生息場所
・周年定住種 ・・・・・・・・・・・一年中みられ、一生をその場で過ごすもの
・季節的定住種・・・・その場への依存度は様々、川と海を回遊するものを含む
・偶来種・・・・・・・・・・・・南方から、北方から、沖合いから、外国から
2.東京湾のハゼたち
(1) マハゼ・・・・・・・・・・・・・・・・江戸前の魚の代表格、感動ものの一生
(2) チチブ・シマハゼ類・・・・・・・天皇陛下の御研究、たくましきダボハゼたち
(3) アベハゼ・・・・・・・・・・・・・・最も劣悪な環境に耐える魚、尿素合成能
(4) ウロハゼ・・・・・・・・・・・西日本系の大型ハゼ、温暖化の影響か近年定着
(5) トビハゼ・・・・・・・・・・・・・・・・北限の個体群、快活な干潟の人気者
(6) エドハゼ・チクゼンハゼ・・・・・・局地的に分布、レッドデータブックに掲載
3.京浜臨海部のハゼ釣り場復元
(1) 金沢八景・平潟の環境改変・・・・・・・・・・・・・・野島水路の閉鎖と開放
(2) ハゼ釣りの衰退と復活・・・・・・・・・・・・・・・・お化けハゼから20年
(3) 都市河川と東京湾との関係・・・・・・・・・・・・・稚魚を育む汽水域に注目
(4) 京浜臨海部再編整備事業・・・・・・・・・海と水辺を活かしたまちづくり検討
4.魚類調査と私
(1) 愛するフィールドに人口島ができる!
(2) 一人ぼっちのモニタリング調査
(3) 人口海浜と魚類
(4) 横浜のイシガレイ復活か?
<参考文献>沼田眞・風呂田利夫編(1997)東京湾の生物誌、築地書館
海をつくる会編(1995)横浜・野鳥の海と生きものたち、八月書館
工藤孝浩・瀬能宏(1997)横浜の魚、オールプランナー
工藤氏のプロフィール
学生時代から首都圏の海に潜り魚や海の研究を続ける一方、山下公園の海底清掃や海・川・
森の活動団体のネットワークづくりを行う市民活動家、海の環境教育の実践者としての顔も
持つ。東京湾に失われた藻場や干潟を復元する夢に向かい、横浜・金沢八景を拠点にマハゼ
を中心とした都市河川汽水域の魚類の生態研究に取り組んでいる。
東京湾・ハゼサミット2000.6.10〜三番瀬の経験から
(財)日本自然保護協会 開発法子
暮らしの中に海とのつながりを取り戻し、東京湾の保全を
1. 干潟・浅瀬の重要性
・生物多様性を支える場(底生生物〜魚類・鳥類)
・魚類の餌場、稚魚の生育の場
・鳥類の餌場、休息の場(渡り鳥の国際的な中継地)
・水質浄化の場
……
・人が海の自然と触れ合う場(景観、レクリェーション、環境教育など)
2. 環境アセスメント(環境基本法に基づく環境影響評価法)
・ 海というみんなの共有財産の利用の仕方、管理の仕方を事業者が独断で決めるの
ではなく、まず、事業者が事業とその環境影響についての見解を自ら示し、市民、
NGO、専門家、行政が、それにかかわる有益な情報を提供しあって、よりよい環
境保全を実現するという機能を担う。
・ 開発行為は、本来、人の暮らしを豊かにするためのものであったはず。計画され
ている開発事業は、自然と共存した持続可能な地域づくりに寄与するものである
かどうか、事業を行うことで地域の文化や自然環境、将来はどうなるのかなど、
環境アセスメントにおいて地域の将来的なビジョンにそってチェックされなけれ
ばならない。
3. 計画の必要性は、十分説明されているか〜東京湾の視点
・ 「開発・利用の必要性、既存埋立地での代替可能性を十分検討した上で…」「既
存の埋立地に広大な未利用地が存在する現状では、新たな空間需要を満たすため
の埋立の必要性は極めて低い」「海面の埋立は抑止することを基本とする」
(東京湾水域環境懇談会中間報告,環境庁,1990)
・ 「水質改善には従来のような流入汚濁の削減だけでは不十分で、沿岸生態系の持
つ水質浄化機能を適正に保つことが重要」(中央環境審議会答申,2000)
・ 人工干潟は、水質浄化機能、生物多様性など自然の干潟・浅瀬の生態系を代替で
きるものではない。「干潟機能をもたせた護岸」の干潟機能とは?データは?
4.人と自然との豊かな触れ合い
・ 私たちの暮らしと東京湾とのつながりは?
・ 今、東京湾が抱えている問題点は?
・ かつての東京湾の姿は?
・ かつて、東京湾とどのようにつきあっていたか?
・ これから、子どもたちにどんな海との触れ合いを伝えたいか?
※ 以下は各団体より寄せられた文章です。
東京湾・十六万坪の自然を守る会
有明北(16万坪)水域の素晴らしさに魅せられ、今年3月に会を結成しました。
ゴミ問題、ダイオキシン問題、ダム開発、河口堰などの環境問題、地方自治体の無駄遣い問題などに取り組んでいる東京の市民が16万坪の問題で集まりました。
これだけ生物が豊かに生息する水域に対し、不十分かつなおざりな環境調査だけで埋立てようとする東京都の姿勢に、なによりも怒りを感じます。そして、新たな開発による財政的なつけを都民に負わせようとすることにも我慢できません。
有明北では運輸省が認可するか否かの段階まで来ていますが、認可をストップさせ、東京都に埋立て計画の見直しをさせる為に全力をあげて行動します。また、ハゼサミットを契機
に、東京湾全体を視野においた、自然の回復の為に努力していくつもりです。
活動:埋立て反対署名活動、16万坪の浅瀬に親しむ集い、東京都への住民監査請求、運輸省への請願などのアクションを起こしています。
連絡先:事務局 田巻誠
江戸川区清新町1−2−2−704
TEL&FAX:03(3878)7280
携帯:090(9106)8118
Email:makoto-tamaki@eva.hi-ho.ne.jp
団体名 日本湿地ネットワーク (JAWAN)
代表者 山下 弘文、辻 淳夫
連絡先
住所 長崎県諌早市小野町1100‐13 〒854-0034
電話 0957-23-3740
FAX 0957-23-3927
Eメールアドレス TAE04312@nifty.ne.jp
ホームページ / URL http://homepage1.nifty.com/wetland/jawanj/info/index.html
日本湿地ネットワークは1991年5月、長崎県諌早市で開催された国際湿地シンポジウムに
集まった全国各地の湿地保護団体により結成された、草の根の湿地保護団体のネットワークです。活動の目的は、内外の団体と協力してラムサール条約を推進し、国内の湿地の保護や回復、国際的な湿地保護連動の支援を行うことです。
1年数回の運営委員会によって活動方針などを決定し、活動を行ってきました。
毎年、各地持ち回りで国際湿地シンポジウムやフォーラム、ワークショップなどを開催しています。また、3年毎に開催されるラムサール条約締約国会議に日本のNGOとしてオブザーバー参加し、国内湿地の現状を知らせると同時に、国際的な協力活動を行っています。,
国際的な活動としては、アジア太平洋地域の「水鳥保全戦略」やシギ・チドリ類渡来地ネットワークの活動の中心として行動しています。また、ラムサール会議にはNGOの「ナショナルレポート」や「九州・南西諸島湿地レポート」などの英文版を作成しロビー活動を積極的に実施しています。さらに今年度から3年計画で、九州・琉球湿地ネットワークが中心となり、日韓のNGOが協力して韓国、特に世界最大の干拓計画が進行中のセマングム干潟の学術調査実施に協力しています。また、「国際協力によるハマシギの調査研究」を実施し、繁殖地であるアラスカと越冬地である日本・韓国・台湾の政府、NGOの協力によって保全に役立つ情報を集めています。
国内では、危機に瀕している各地の湿地保護活動の支援を行っています。
また、シギ・チドリ全国カウントを実施し報告書をまとめています。さらに、九州・琉球地
方干潟の底生生物調査を実施しています。この結果については九州・琉球湿地ネットワークが中心になり、ラムサール条約締約国会議の行われる3年毎に増補改訂版を出版しています。
日本湿地ネットワークには次のような事務所を設けています。
統括事務所 長崎県諌早市小野町1100‐13 〒854-0034
山下弘文Tel:0957-23-3740 Fax: 0957-23-3927
東京事務所 東京都日野市東豊田3-18-1-105〒191-0052
柏木実 Tel/Fax: 042-583-6365
国際担当事務局 香川県大川郡引田町黒羽27
鈴木マギー Tel: 0879-33-6763 Fax: 0879-33-6762
代表は、諫早干潟緊急救済本部山下弘文、藤前干潟を守る会辻 淳夫の二名です。
年会費は団体5000円、個人3000円です。年間6回程度の「JAWAN通信」を発行しています。現在、活動を強化するため、新たな会員の募集と組織強化策について論議を進めているところです。多くの方々のご参加をお待ちしています。
諫早干潟緊急救済東京事務所 活動のご案内
■諫早干潟を知っていますか?
かつてそこは「有明海の子宮」と呼ばれる生命の宝庫でした。独特のきめ細かい泥の中に、非常に多くの有機物やプランクトンを含む諫早干潟は、貝やカニ類、たくさんの稚魚や幼生を育んできました。多くの渡り鳥達が、長い旅路の中継点として諫早干潟で羽を休め、人々もその豊かな海の恵みとともに暮らしてきました。しかし、1997年4月、諌早干潟は巨大な堤防で閉め切られ、今や干潟はからからに干上がってしまいました。干し殺された数え切れない貝たちが、無惨な姿をさらしています。空を覆うばかりだった渡り鳥達もほとんど姿を見せなくなりました。そして干潟とともに失ったものは、私達人間にとっても計り知れないものでした。これほどまでの犠牲を払ってすすめられている「国営諌早湾干拓事業」とは、一体、何なのでしょうか。
■「国営諫早湾干拓事業」には重大な問題があります
「国営諫早湾干拓事業」(以下「干拓事業」)の目的は、(1)生産性の高い優良農地を作ること、
(2)防災機能(高潮・洪水・低地の排水対策)を強化すること、の2点です。しかし、実際の事業計画は、重大な問題をはらんでいます。
諫早干潟の「賢明な」利用法は、干潟として回復させることだと私たちは考えます。
■水門は閉め切られても諫早の問題は終わっていません
からからに干上がってしまった諫早干潟ですが、今ならまだ、やり直すことができます。
水門を開けて、有明海の潮流が流れ込めば、自然の力で元の豊かな干潟に回復するというのが専門家の一致した意見です。
自然の力の偉大さに、あらためて驚くばかりです。
■諫早干潟を回復させるためにあなたの力を貸して下さい
堤防が閉め切られてから、私たちが訴えてきた「干拓事業」の問題点が次々と現実になってきました。一日も早く「干拓事業」を見直し、干潟の回復に取りかからなければなりません。皆さんのご理解とご支援をよろしくお願いします。
■東京事務所のミーティングや活動にご参加ください。
諫早干潟緊急救済東京事務所では毎月2回、WWFジャパン会議室にて定例ミーティングを
行っています。どなたでも参加できますので、どうぞお気軽にご出席ください。
◎日時:毎月第1・3火曜日 午後7時〜9時
◎場所:(財)世界自然保護基金日本委員会(WWF Japan)会議室
〒105-0014 東京都港区芝3−1−14 日本生命赤羽橋ビル6F
TEL.03-3769-1715(担当:菅波)
東京事務所の会員としてご登録いただいた方には議事録や関連情報を送付いたします。
◎東京事務所年度会費(6月〜翌年5月):2000円
◎振込先:郵便振替口座 00140-3-402895
加入者名 諫早干潟緊急救済東京
(振込用紙の通信欄に「東京事務所会費」とご記入の上、お振り込みください)
*******************************************************
諫早干潟緊急救済東京事務所(干潟を守る日2000実行委員会)
〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3-7-3 ベルビュー目白701
TEL/FAX 03-3986-6490 E-mail isahaya@msj.biglobe.ne.jp
ホームページ URL http://www2s.biglobe.ne.jp/‾isahaya/
*******************************************************
科学と社会を考える土曜講座(略称:土曜講座)
新宿を拠点とした市民グループです。月1回、20−30人が集まり、主として科学の及ぼ
している社会的問題を勉強し議論し、問題によっては外部にも働きかけています。ごく一般
の素人の集まりですが、単に勉強に終わることなく他のグループとの連携も大切にしていま
す。
このほか機関紙による仲間150人、メーリングリストの仲間約50人がいて意見交換をし
ています。
環境問題・化学物質・核・医学・大学問題等テーマは多岐に亘っています。
干潟については、夏の合宿で博多湾の和白干潟を守る会で活躍している田中浩朗氏から話を聞き、我々もまず干潟に行って勉強し、実際に干潟を守る運動をしていらっしゃる方々から色々お話を伺いたいと、企画を建て始めたところです。是非このサミットに参加して勉強させて頂きたいと存じます。
代表者:上田昌文(うえだあきふみ)
横浜市港北区太尾町810ソフィア大倉山213
TEL&FAX:045(532)1958
市川緑の市民フォーラム
JR総武線で江戸川を越えると千葉県です。その千葉の玄関口に市川市があります。かって
の市川市は江戸川とクロマツ、雑木林と水田、遠浅で魚介類の豊富な東京湾など、自然豊かなまちでした。また、縄文遺跡や下総国分寺跡、万葉集に謡われた手児奈の里など名所旧跡も多く永井荷風や北原白秋などの文人もこの地に足跡を残す文化の香り高い落ち着いた雰囲気は高度成長期の急速な都市開発の中で失われていきました。
私たち「市川緑の市民フォーラム」は市川市にかっての自然と文化をとりもどし、緑豊かで住みやすくうるおいのある文化都市とするために発足した会です。いままでに市内の緑地保全や調節地に自然を復元する活動に成功しています。
今、埋立て問題で大きくゆれている三番瀬は市川の海の問題なので今まで千葉県内で活動する三番瀬保全グループと協力して署名やシンポジウムを行ってきましたが、今回は東京湾をとり囲む神奈川県・東京都・千葉県の市民の会が協力して「これ以上東京湾の埋立てはやめるべき、それよりもかっての豊かな東京湾の復元を考えるべき」を合言葉に、ハゼサミットを行うことになりました。私たちもこのサミットの成功のため実行委員会に参加させていた
だきました。
これを機会に東京湾全体の自然環境の保全を全国に力強くアピールしていきたいと考えています。
事務局長 さのさとみ佐野郷美
〒272-0832 千葉県市川市曽谷7−24−3
TEL&FAX 047−373−3219
トビハゼと北限のトビハゼを守る会
北限のトビハゼを守会 代表 田中 正彦
1.北限のトビハゼ
英名をmud-skipperといわれるトビハゼ類は,東京湾以南,朝鮮,台湾,中国,東南アジア
各地,インド,アフリカ東岸,オーストラリア,ミクロネシア各地など熱帯から温帯にかけ
ての干潟,特にマングローブ地域に広く分布している.千葉県にはトビハゼ
Periophthalmus modestusが,江戸川放水路や谷津干潟など東京湾奥部に残されたわずかな泥干潟に生息している.
東京湾奥部に生息するトビハゼは、トビハゼ属の世界的な北限個体群として知られており、
1999年2月18日環境庁から発表されたレッドリストで、「絶滅のおそれのある地域個体
群」に指定された。
2.北限のトビハゼを守る会
1991年2月、江戸川放水路河口の堤防補強工事に伴い、880mのトビハゼ生息地の干潟を埋め立て工事が始まりました。ここはトビハゼだけでなく、多くの干潟の生き物や野鳥などの宝庫としても知られており、工事に気がついた環境保護団体が工事の中止を求めました。
こうした中、この貴重な江戸川放水路の泥質干潟とそこに生息するトビハゼをはじめとする多種多様な生物達を残したいという主旨で「北限のトビハゼを守る会」を4月に結成し、干潟の保全活動に加わりました。その結果、工事主体であった建設省は大幅な工事計画の縮小とトビハゼの保護を約束し、実行されました。現在この場所は「トビハゼ護岸」という名称で呼ばれており、たくさんのトビハゼが生息しています。
3.一つの東京湾生物の多様性や水の浄化などさまざまな役割を持つ貴重な干潟をもうこれ以上失ってはなりません。干潟に生活するトビハゼも、仔魚のうちは干潟や沿岸部で生活します。そうした意味では、東京湾は生物的に一つの連続性を維持していかなければならない場所です。もし16万坪が埋め立てられれば、その影響は計り知れないものとなるでしょう。
隅田川を愛する会
私たちは昨年、江東区の鈴木康吉さんの案内で通称十六万坪を視察しました。懇切な説明を聞くほどに、怒りが涌いてきます。
私たちは、隅田川が悪臭を放ち魚が一匹もいない事を残念に思い活動をはじめました。現在とは隔世の感があります。言問橋付近でもハゼが釣れるようになり、台東区は環境調査と称して100万円の予算を組んでハゼ釣り大会を行っています。この大会には1000名の参加申し込みがあり盛大な年中行事となっています。
区民の要求や台東区議会の要望書によって、東京都は吾妻橋上流200Mにわたってコンクリート護岸ではなくアシなどの水生植物を植え、川の水が出入りする池も作りました。この池では流れ着いたメダカやテナガエビが子供たちを生み一つの風物詩となり、環境改善の例としてテレビでも放映させました。
このような自然保護・再生の大きな流れの中で、通称十六万坪を埋めてしまうとは、とんでもないことです。微力ではありますが、皆さんと連帯し十六万坪を守り、後世に残しましょう。
内川と内川河口をよみがえらせる会
設立年月 1989年3月5日
会員数 25名
代表者 木村真介 大田区大森東2−2−10(〒143)
電話(03−3764−0423)
FAX(03−3761−4717)
現在、東京には€三枚洲(江戸川区) 多摩川河口(大田区)¡森ヵ崎干潟(大田区)¤内川河口(大田区)の四ヶ所しか干潟が残されていません。
その内の三ヶ所が大田区に集中しています。その一方で1990年に「いつも光と水にあふれていた大田、よみがえる水辺」とうたい始め、1993年3月には「大森の海の復活」を掲げて「内川河口マリンプラザ計画」なるものを提案してきました。
しかしながら、それは自然保護とはかけ離れた、たった17仿程しか残されていない海を3分
の1も埋め立てて、人口的箱庭のように作り変えるという破壊そのものなのです。
そしてその中に道路・駐車場・バーベキューガーデン・レストラン・人口砂浜を作り、人を呼ぼうとす
るのです。
今この海は隣接する森ヵ崎干潟と一体となって、東京ではほかに比較する所が見当たらない
程のボラ・ハゼ・蟹・ゴカイそして鳥の天国となっています。
どれ程かというと、ボラは群れて海面がさざ波立つ程でハゼとゴカイは無数といえる程です。また、鳥では、特に冬鳥でカモ・カモメ類を主として、常時1500〜2000羽がこの海で越冬します。森ヶ崎干潟と合わせるとその数は3000羽にもなります。
この事は、すぐ近くにある、31億円もかけられて作られた、東京港野鳥公園に飛来する数の30倍程にもあたり、比較になりません。いかに自然の力がすばらしいかを見せつけてくれます。
内川河口と森ヵ崎干潟は、かっての遠浅の「大森の海」の名残として、ささやかに残されています。海を失い続けてきた我々は、川と蟹と貝に恵まれていた伝統あるこれらの海を、断固たる決意で守り抜くつもりでいます。そしてより親しめる水辺にと目指しています。
(1) 内川河口
面積17ha。三ヶ所の干潟と、三ヶ所の磯浜がある。最大干出面4ha。
ボラ、ハゼ、ケフサイソガニ、ゴカイが生息。
(2) 森ヵ崎干潟(モノレールからよく見える)
面積47ha。最大干出面積43ha。ボラ、ハゼが生息。特にゴカイは無数ともいえる程。
冬鳥、特にカモ類
が空港側から駆除される事がある。
上野からの発信
不忍池地下駐車場建設計画の教訓を伝えたい・ ・・
これは東京湾開発の台東区版!!・
1980年代半ば、突如として、不忍池地下駐車場建設計画が発覚しました。不忍池を干し上げて、地下に600台以上の車を収容し、水中レストランをつくり、コンクリートの上に水を溜めて池にするというもの。
さすがに世論の風当たりが強く、形の上では計画は二転三転、しかし収容規模は変えないというしたたかさでした。
《台東区の事業として推進を決定、採算性は当初から考えないのが当たり前》
当初は地域の商店街などの構想だったのが、やがて台東区の計画になり、工費120億円と試算され、インチキな環境調査(区は環境保全ではなく、建設のための調査だと認めた)の
末、第三セクターで駐車場公社を予算化。しかし応募する企業はなし。資金が集まらず、区は第三セクターを断念、区直営に切り替えました。区や与党の議員さんの言うには、「採算が合わず赤字がわかっているから、直営方式をとるのは当然だ。」とのこと。普段、福祉・環境・教育の分野について、「採算が合わないものは切り捨てだ、受益者負担だ!」と声高に叫んでいるのは誰だったのでしょう。
《将来の環境への配慮は責任を持つ部局が役所にはない》
建設計画は広範な市民の声と、内山前区長の英断で、不忍池の真下からはずらすことになりましたが、その後新区長の下で計画が固められ、池の外周道路に駐車場の出口が設計されています。また、地域では最高の建物である松坂屋デパートの高さの2倍分の深さに、鉄とコンクリートの塊が池のほとりに永久に埋められることになり、先々の地下水環境への影響ははかり知れません。区は、建設に当たっての調査はするが、未来については権限外だ、先のことは、そのときにならないと経済とか自然環境の見方が確定しないから、予測不可能だと言って責任を回避しています。
《都市計画決定直後に計画をすぐ変更、規模の拡大は自由にできる》
都市計画決定が決まるや否や、区は駐車場の収容台数を5割増しの300台にしました。
認可は平面図に基づいた地理的範囲で受けていること、同じ体積のコンクリートの箱の中を有効に生かして台数を増やすのだと言います。国や都からの補助の出る上限の規模にして認可を受け、その後、自己資金で増加分は賄うという、なにかペテンのような計画変更です。
《それでも建設できない、建設しなくとも意義がある?》
それでも3年経って、毎年関連予算が計上されるのに、まだ工事の具体化はありません。
それだけ不況の影響は深刻なのかも知れません。でも、なんとなく地元の商店に危機感が感じられません。これまでに環境調査だ、基本設計だといって使われた費用は数千万円とも億のケタだとも言われます。この段階ですでに、もうかった人がいたことになります。それは
地元の商店ではありません。
次々と税金を注ぎ込み、初めから赤字の建設工事を予定するやり方は、東京湾開発とまっ
たく同じです。ツケはすべて、私たち都民・区民と未来の納税者にかかってくるのです。
しのばず自然観察会のご案内
「しのばず自然観察会」は1975年9月に発足し、都市の自然を考えるというテ−マを掲げ、自然と歴史文化を生かした公園づくり・地域づくりをめざして活動しています。
メイン・フィールドの上野公園・不忍池の環境保全、自然と歴史文化を生かした地域づくりは私達の願いです。そのため、不忍池にあるカワウの集団営巣地保存、不忍池の浄化、周辺の地下水調査等に取り組み、また、不忍池の野鳥・上野公園の残存自然、文化遺産の分布・好まれる空間や快適性などの調査、ガイド・マップと研究報告書、ガイドブックの発行、一般の人々を対象にした公開野外観察会などを続けています。
不忍池地下駐車場建設計画が表面化してからは、広範な市民と共同して反対運動を広げ、台東区議会でも、「不忍池の環境に悪影響を与える建設には反対する」とい決議をあげる原動力となりました。
年間の活動は、月1回の野外活動を原則に、年間15回程度。1月と6月の公開野外観察会、それ以外の月には勉強のために他の公園や自然をたずねる緑地めぐり、遠足、また他の自然保護団体との交流もかさねています。
自然を愛するあなたの参加をお待ちしています。年会費2,000円(12月切換え)、他に行事
参加費。6月の活動は4日に上野公園の自然と歴史めぐりを、環境週間記念行事として実施しました。7月は、23日に高尾山の圏央道反対集会に参加します。なお、午前中、高尾山の自然観察を計画しています。
しのばず自然観察会 事務局〒110-0008東京都台東区池之端4-23-2-603(猪狩)
郵便振替 00100-8-84609 年会費2,000円 電話 03-3828-8775(小川)
〜自然と人との架け橋〜
Field Assistant Network
(F.A.ネットワーク)
私達、F.A.ネットワークは、自然保護活動を進めている学生のボランティア団体です。自然保護活動をしている学生達を結びつけ、自然と人、また人と人とのネットワークをつくろう、という目的で1989年に設立されました。
活動の基本的な考え方は、「現場(フィールド)での実践」を掲げています。机上の話だけではなく、実際の自然保護の最前線で取り組むことによって、現場への貢献と自分たち自身の勉強につながると考えているからです。活動場所も関東を中心に北海道まで幅広い場所で活動をしています。
メンバーは学生を中心としており、千葉大、日大、麻布大、東京農大等々、様々な学校から集まっています。このように多大学の学生と触れ合うことや、自然保護に関する情報が入ってくることも魅力のひとつです。
また、卒業して社会人となったメンバーは、NGOや行政、企業の自然保全、環境教育等の部署で活躍し、アドバイザー的な存在としてバックアップをしてもらっています。
<主な活動内容>
1、ワークキャンプ
・期間 :春(2月〜3月)と夏(8月〜9月)の年2回行っています。
自然保護の現場に行き、作業を通して、また現地の人々と触れることによって自然保護の現状や問題などを肌で感じ、学ぶことができます。北海道の大自然の中で行うので、都会では味わえない自然を楽しむことができます。期間は一週間から10日前後です。
・場所:ウトナイ湖サンクチュアリ、鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ、キナシベツ自然保護区等。
今年の夏から新たに霧多布湿原ワークキャンプが仲間入りすることになり、全部でワークキャンプ地は4つになります。
過去の作業内容 過去に行ってきた作業内容としては、看板作り、タンチョウねぐら調査、原生海岸へのステップづくりなどがあります。作業の他にも、一日、車に乗って現地の人から周辺の環境問題を学ぶ野外セミナー、夜には自然保護などについて考えるセミナーもあり、盛りだくさんの内容がつまっています。
2、NEC学生バードソン
「学生にできる自然保護」をスローガンに1988年に始めて学生の手で「学生対抗バードソン」が開催されて今回で12回目、「NEC学生バードソン」としては6回目を迎えます。 今年の「NEC学生バードソン2000」では、国内で3番目の広さを持ち、世界的にも重要な湿地である霧多布湿原の保全を応援するために、募金を集めます。集められた募金は、霧多布湿原の保全活動を進めている「霧多布湿原トラスト」に寄付されます。
<バードソンとは?!>バードソンはバードウオッチングと募金活動を合わせたチャリティーイベントです。参加者が4人一組のチームを組み、好きな場所で規定時間内に何種類の野鳥をみつけることができるかを競います。チームは募金者を集め、募金を集めます。見つけた鳥の種類数と、募金額で勝敗が決まります。
今年は7月2日(日)に開催予定です。学生をはじめ、社会人チームも受け付けています。*参加希望の方は6月22日までにご連絡下さい。
3、谷津干潟
千葉県習志野市にある谷津干潟では、月に1回「ソロモンの指輪」という子供向けの自然観察プロジェクトを行っています。
どんな生き物とでも話ができる指輪を持っているソロモン王。参加者はその指輪を王から授かるためにあらゆる問題を解かなくてはいけません。
その問題とは?そして問題を解いた証に指輪を授かることをできるのか?
毎月1回、第2日曜日に行っています。(予定変更あり)
4、その他
以上の活動の他に、総合学習を取り入れている神奈川県立大師高校との関わりや、機関誌
「FUN&FAN」も年に3回発行しています。
5、連絡先
住所:〒156-0051 東京都世田谷区宮坂1-22-10-102
TEL:03-3428-9086
FAX:03-3420-3239
URL:http://www03.u-page.so-net.ne.jp/xc4/fan/FAHOME.htm
E-mail:fan@xc4.so-net.ne.jp
東京湾海洋研究会(とうきょうわんかいようけんきゅうかい)
■東京湾海洋研究会とは
東京湾海洋研究会は、豊かな東京湾の姿を再生し市民が海と親しめる空間や生活環境を復活させるために、研究者、ジャーナリスト、マスコミ関係者、市民活動家、ダイバーなど様々な立場で東京湾と直接深い関わりを持っている有志が集まり1993年(平成5年)に結成しました。
1994年からは、次代を担う者たちへ東京湾の豊かな海と自然環境を引き継ぐための啓蒙活動の一貫として「江戸前の健康な海をみらいに」を合い言葉とする東京湾イベントを開催しています。このイベントは「知る・食べる・考える」という三つのテーマで構成されています。「知る」は体験教室や見学会などを通して東京湾の環境にふれ、「食べる」は豊かな東京湾の魚介類を食し、「考える」ではシンポジウムを開催し、東京湾問題を考え、語り合っていただいています。 東京湾イベントはこれまでに東京、横浜、川崎、横須賀、千葉等の沿岸各都市で合計五回開催しています。これらのイベントやシンポジウムを通じた提言、情報提供の他にも、会員それぞれの専門分野を生かした調査、研究、映像記録収集、環境保全活動団体とのネットワークづくり等も行っています。
■私たちが目指すこと
東京湾は昭和40年代の開発により海の生態系が変わってしまいました。 浅場が無くなったことによる魚の産卵場の消失、酸素不足、海を浄化してくれる底生生物の減少、汚水の垂れ流しによる汚染。それに伴い人々が気楽に接することが出来る海辺が無くなり、海岸が遠いものとなってしまいました。
現在では下水道の普及や大規模埋立の終了により、一時期よりは安定した状態になっていますが、浅海が無いこと、また赤潮、青潮の発生を見る限り、決してきれいになったとは言うことは出来ません。
グルメブームなども手伝って、江戸前の魚がクローズアップされている割には、東京、川崎、横浜などの市民は自分の住む町に海があるという意識が無くなってしまったのも事実です。これもすべて人々が海岸線から遠ざけられてしまった結果です。
私たちは、行政による湾岸都市開発、経済優先の構造を改め、水際の不要になった行政や企業の土地を市民開放し、立入禁止の水際線の構造を変えて行くべきだと考えています。
無機質なウォーターフロントと呼ばれるような場所ではなく、楽しく、びしょびしょになって、泥だらけになって遊べる浅場が人間にとっても様々な生きものにとっても大切なのです。魚の釣れない海釣り公園やフェンスが張りめぐらされた臨海公園ではなく、市民が気楽に入って水遊びが出来る、小魚や鳥などの生きものが集まるような浅海の海岸が必要です。
目の前に迫っている21世紀には、市民の目に見える場所の環境と構造を変えていきたいと考えています。それにより人々が水辺に集まり、楽しみながら人間と自然環境の結びつきや海洋環境の大切さを考えられるような海岸を回復できることを願っています。
■今後の活動予定
8月に「東京湾食(ク)ッチング」という江戸前の魚介類を堪能する会食会を横須賀市のティー・スリー横須賀で開催予定です。実際に豊かな東京湾の恵みを体感していただけます。
川崎市では「かわさき・海の市民会議」設立に協力しています。海の存在が薄い都市にも活動の輪が芽生え、市民や行政が一体となったまちづくりが始まろうとしています。これは7月20日の設立総会に向けて準備中です。
また、7月20日の「公開セミナー・どうしたら江戸前の海が復元できるか」(会場・牛込箪笥区民センター、同実行委員会主催)、10月7日の「第二回汽水域セミナー・東京湾の汽水域環境復元の世紀21」(会場・赤坂区民センター、同実行委員会主催)等のイベントへ開催協力をしています。
詳しくは当会のホームページをご覧ください。
http://www.yasumoto.com/tokyowan/
東京湾海洋研究会事務局 212-0004 川崎市幸区小向西町3-64 安元方
Tel/Fax:044-555-2208 Email:info@yasumoto.com
いたばし野鳥クラブ
2001年7月になると設立してから15年目に入ります。たのしく、おおらかにを基本にクラブは活動してきました。現在は、月1回の板橋区荒川河川敷の野鳥調査を続け、3年目に入り、それなりの成果もあります。このほか、月2回ほど、野鳥を見にあっちこっち出かけています。また、関係機関にも、自然環境について様々な働きかけを行っています。
連絡先: 栗林菊夫
電話:(3959)2072
FAX:(3959)8948
〒173-0024 板橋区大山金井町49−1
『いのちのゆりかごを埋立てるな』
東京湾の浅海干潟に親しむ会
代表 楠山忠之
「潮が引いても逃げおくれたアカエイが水たまりにいることがある。尻尾には毒のトゲが生えているから踏まないように」案内する人が注意する。5年前、はじめて三番瀬散策を体験、東京湾の干潟はいのちのゆりかごだと知った。以来、出かけるたびに出会える小さな生物たちの種類の多さに感動。
季節ごとに飛来する水鳥たち、マハゼ、ギンボ、ボラ、カレイ、ウナギ(最近みかけないが)などの幼魚、群雄割拠して賑やかなヤドカリやカニたち、砂の下を楽園とする貝やゴカイ。干潟を歩くたびに心は子どもの気分になって浮き立つ。開発破壊で無残なかたちになった日本の中で、東京湾に残った自然は誇れる美しさの一つだ。この感動を東京在住者にも、と集まってつくったのがこの会だ。
“ストップ・ザ・埋立て!”浅生干潟を守ろう。
※貴重なコメントと情報、有り難うございました。
掲載の許可確認はしておりませんので、訂正、削除等のご要望がありましたら、
管理者までお寄せ下さい。