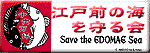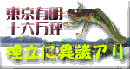このアサリという二枚貝について、興味深い研究結果がある。それは愛知県水産試験場漁場環境研究部の鈴木輝明さん(農学博士)が、三河湾の一色干潟においてアサリの生態について調査したものだが、一色干潟に生息しているアサリはもともと、湾奥部から潮流に乗ってきたものだというのである。
アサリという二枚貝は一般的に、底にいる生物ということからその場所で生まれ育つと考える人が多いことだろう。ところが実際は、卵がフ化すると10日から2週間くらいの間、その幼生は海の中を漂う。いわゆるプランクトンと同じ部類に入るわけだが、三河湾の一色干潟の場合、そこに生息するアサリは最初から一色干潟で生息していたのではなく、別の場所から流れ着いたことが分かったというのだ。
「一色干潟のアサリ、その幼生がどこから来るか、その流れを時間を遡ってシュミレーションしてみると、湾奥の埋め立てられた場所付近に行き着く。ということは、過去に埋め立てられた場所というのは、現在残っている干潟の浄化機能をも維持していた、それを高めていた可能性が高いということなんです」(鈴木さん)。
これはどういうことか。現在の一色干潟を、全く別の場所である湾奥部が支えているということであり、また、すでに湾奥部は埋め立てられていることから、しだいに一色干潟に何らかの影響が出てくる可能性も否定できないということだ。鈴木さんは続ける。
「たとえば、ある場所をなくしたから、そこに同じものを作ればいいという考え方ではなくて、湾スケールの中でここをいじることによってどこに影響が出るかということまで考えながら、埋め立てについての評価をしていかないといけないんです」
愛知県水産試験場の研究結果を三番瀬にあてはめてみると、101haの埋め立てを許し、人工干潟を造成するという考え方がいかに無意味であるかが分かる。この101haがもしかしたら、東京湾全体の干潟を支えているかもしれないからだ。
三番瀬と十六万坪の閥係
十六万坪についても同様のことがいえる。三河湾では湾奥部の埋立地付近からアサリの幼生が一色干潟に運ばれていることが分かった。十六万坪でもアサリは生息しており、また無数の稚魚が確認されていることからも「生命のゆりかご」になっていることは紛れもない事実である。それだけではなく、もしかしたら三番瀬や盤洲干潟のアサリでさえ、十六万坪など東京湾の湾奥から運ばれている可能性すら全くないとはいいきれないのだ。
鈴木さんも「その可能性もあるでしょうね、あると思いますよ」と、十六万坪の潜在能力に興味を示しながら、ゴカイなど底生生物が多い点に注目し、次のように付け加えた。「アサリなどの二枚貝のほうが、確かに懸濁(けんだく)物を除去する能力が高いといわれてますけども、どうもそうとは言い切れない。ゴカイなどでもアサリと同等の役割を果たしている可能性は高いと思いますが、残念なことに学問的な情報ということでは整理されていないんです」
鈴木さんの話を総合すると、三番瀬が東京湾全体の干潟を支えている可能性、そして十六万坪が三番瀬をはじめとする干潟を支えている可能性も、あながち否定することはできない。そして東京の片隅の小さな海域である十六万坪にも、湾奥にとって重要な浄化機能が備わっていることは間違いないのだ。
「どうも今までは、このくらいの埋め立てなんだから影響は軽微だという、面積的な規模論議だけが先行してますけども、その小さな面積が果たしていた役割の評価はほとんど今までされていないし、私どもの三河湾でもやっと今それに気が付いた段階です。個人的に言わせていただければ、どんな規模の埋め立ででも影響があることは間違いないんです」
十六万坪と三番瀬の埋め立て問題。ここに愛知県水産試験場の研究結果を照らし合わせると、これらの埋め立てという行為が、東京湾全体に甚大な被害を与えることを示唆している。有明海では諌早干潟の干拓によって、海苔の養殖に致命的ともいえる被害をもたらした。東京湾もそうなる可能性が極めて大きいわけだが、石原都知事と都議会自民党、そして公明党はあいも変わらず開発優先の立場を崩そうとはしない。千葉県のほうは今年3月の知事選が転機となるが、その結果いかんに東京湾全体の命運がかかっているといえるのである。