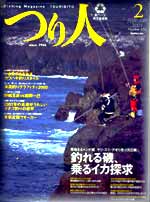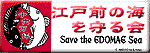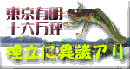有明北地区埋立事業のあらまし
ここーヵ月の報道で、初めて十六万押問題に関心をもたれた方もいるだろう。そこで、この事業の何が問題になっているのかについて、おさらいしておきたい。
有明北地区埋立事業は、昭和63年3月に基本計画が立案、平成12年9月13日に工事が着工され現在に至っている。臨海副都心開発の一環として旧有明貯木場の約85%、35.4haを埋め立て、住宅9000戸や業務・商業ビルを建設し、幹線道路および新交通システム「ゆりかもめ」を延伸させる計画だ。
埋立事業費は400億円(利息を含めると520億円)とされているが、民間企業9社(周辺の地権者)への補償に129億円、また関連の土地区画整理事業費やその他の道路整備を入れると、総額1300億円以上が投入されることになる。
財政難を理由に福祉予算900億円を切り詰めるほか、当初は銀行のみが対象だった外形標準課税も、今やホテルやパチンコ店などへの適用も検討しており、今後はより一般市民に関わりの深い業種への課税が予想される。
このほか"昼間都民"と呼ばれる部外からの通勤者に対し課税を検討するなど、横暴極まりないその行動によって、一般市民もようやく"石原都知事の本性に気づきはじめた”といったところだろうか。
その一方で、財政圧迫の原因となったはずの臨海開発には予算を湯水のごとくつぎ込み続ける。都の血税を利用してゼネコンを救済するかのようなその姿勢は、まさに旧態依然とした自民党執行部型の政治に酷似している。
にもかかわらず、いまだ都民の中には「石原都知事には我々の声が屈いていないだけではないか。いつか民意を聞き入れ、工事をストップさせてくれるはず」と、わずかな希望を抱いている人々もいることだろう。しかし、そのような幻想は、もはや捨てるべきである。
この事業を推進しているのは紛れもなく石原慎太郎都知事であり、その人気にあやかろうとする都議会の自民党および公明党なのである。この現実を見極めることこそが、工事を中止させる新たな一歩になる気がしてならないが、いかがだろうか。
|