 |
情報、其之弐 2000.6.3 [ 命 キラキラ 十六万坪 ] 東京新聞、6/1〜2 関連記事より。 |
|
東京都が埋め立てを決めている江東区・有明旧貯木場(通称.十六万坪)。 その”施工者”都港湾局が発表した県境アセスメント調査結果は、生息す るとされる生物の数も種類も少なすぎる。こんな疑問から、市民団体が独自 に調査に乗り出し、十六万坪に網をった。そうしたら都港湾局の調査では見 つからなかった?多種多様な生物が、初夏の太陽にキラキラと。 (野呂法夫、写真・石井裕之、五十嵐文人、稲岡悟) |
 |
| 「ドスン、バシャッ、バシャツ」同乗させてもらった”調査船”が十六方坪に入って間もなく、大きな魚が船に 飛び込んできた。体長40cm級のボラ。他のボラも船の周囲でポンポン跳躍を繰り返す。 初夏の今ごろは東京湾を浮遊する幼魚たちが成育のため十六万坪に来る時期。水深2-3mの浅瀬で投網を打つと、 一網で数え切れないほど多くのスズキの幼魚が採れた。 都港湾局の環境アセスを見ると、春季(調査=三月)から夏季(同“七月)にかけて魚類は、マハゼ、イッカク クモガニ、サッパ、ホラしか記載されていない。しかし、今回の市民アセスでは、この四種はもちろん、前述の スズキのほか、ニホンウナギ、メバル、イカなどが採取され、ハゼ科の魚は12種も確認された。 |
 投網を一回打っただけで採れた スズキとハゼの幼魚 |
「都のアセスを見せられた市民は『魚類がこれほど少ししかいないなら埋立てても』と 思ってしまいかねない。しかし実態は豊種(ほうじょう)の海なんです」。こう怒るの は市民アセスを実施した「江戸前の海十六万坪(有明)を守る会」の安田進会長。 同会は、都のアセスに納得せず、再調査を求めたが港湾局は応じないため、東京水産 大の丸山隆助手や東大海洋研究所の向井貴彦特別研究員らの協力を得て、自分たちで調 べ始めた。 調査にはダイバーも参加した。その一人、水中カメラマンの尾崎幸司さんは「海底は 良好な泥底が広がり、わき水も豊富。ゴカイ、カニ、エビなどが無数に存在し、魚影が 濃い。魚が濃く(わく)ような感じでキラキラし、生息密度は三番瀬を上回るのでは」。 |
| こうした実態を踏まえ、安田会長は、都のアセスを、こう批判する。「現地調杏は96年から年4回行っただけ。 調査の地点はわずか2カ所で、期間は八日間。魚類数も捕獲した数の多い優占三種の記載のみ。十六万坪はマハゼの 楽園だが、その生活サイクルも調査していない」 これに対し港湾局の小林伸好・開発技術課長は「調査は都の環境アセスの技術指針に基づいて行った。投網や刺し 網で捕獲した季節ごとの全種類数と上位三種の魚類名などをアセスに記載した」。 ではアセスの技術指針に問題があるのか。 都環境保全局の中村真一・事業アセス審査担当課長は「年間を通じた調査が好ましいが、原則として季節ごとに実施 するとあり、最低何回調査するなどは具体的に定めではない」・・・・。 前出の丸山さんは十六万坪を「東京港では貴重な」魚の”幼稚園”」という。 特に多いマハゼはこの域で成魚となり、本来なら隅田川や荒川に移動する。ところが、河口域はカミソリ護岸で、 生活場所が少ないいため、多くが引き続いて生活し、晩秋に深撮に移るまで居着いている。また三番瀬や多摩川河口域 では青潮や大水による酸欠被害があるが、十六万坪にはない-。 そして丸山さんは「市民版」環境アセス調査の意義をこう強調する。 「バブル的な発想のみで浅瀬を埋め立てる時代は終った。市民の手で十六万坪の価値を明らかにしていけば、都知事 や都民の判断材料となり、今後の方向性に英知を促せるはず」 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 東京、千葉、神奈川の約30に上る自然保護団体が一堂に集まるシンポ「東京湾・ハゼサミット」が、6月10日 午後1時から東京港芝浦サービスセンター(港区海岸3-26)で開かれる。この中で十六万坪の生物調査も中間報告 される。 問い合せは、シンポ実行委員の 田巻誠 さん(TEL: 03-3878-7280) |
|
|
|
|
|
|
 |
「江戸前ハゼの楽園」とされる江東区の有明旧貯木場(通称・十六万坪)を埋立てる都 の臨海開発に関連して、都港湾局は31日までに、浪越勝海港湾局長に対する市民団体の公 開質問状について回答した。 この中で同局は、十六万坪が秋のハゼ釣りシーズン中も「マハゼの生息数は少ない」と する調査データを示したが、市民団体側は「生物調査が不十分なのは明らか」と再調査を 迫った。 |
| 公開質問状を出していたのは「江戸前の海十六万坪(有明)を守る会」(安田進会長)守る会は、江戸前ハゼを 象徴とした十六万坪の浅瀬の価値をめぐって港湾局と論争を展開しており、特にマハゼが多い10月の調査内容を求 めた。 港湾局は平成8年12月から行った環境アセスの年間魚類調査(年4回、各2日間)の結果を示した。それによると、 個体数が多い上位3種の出現率では、マハゼが冬季(同年12月)74%、春季(9年3月)87%とダントツだった。 それが夏季(同年7月)と秋季(同年10月)はともに上位三種に入っていない。 この結果を基に、港湾局は「マハゼは東京港内にどこにでもいる魚で珍しくない」とあらためて回答した。 守る会は「10月にあれほどマハゼがいるのに少ないとは考えられない。多くの人が都の調査内容を疑問視し、 不十分なものだと思っている」と反論した。同局は埋め立て理由に良質な賃貸住宅の需要などを挙げつつ、公的 住宅について「都は将来も造らないとは言っていない」とのみ説明。現時点で都営住宅などの公的住宅建設の具体 的な計画がなく、計画の9000戸は民間デベロッパー頼みであることが明らかになった。 守る会世話人の中野幸則さんは「ほとんどが不十分な説明で、求めた質間の回答になっていない。 もう一度整理して意見をまとめたい」と話していた。 |
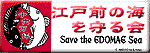 |
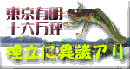 |