 |
情報、其之壱 2000.5.27 [”つり人”7月号より関連記事。] |
|
前半は、「江戸前はまだ生きている」のタイトルで、 現代に残る江戸前の食文化の検証というテーマの興味深いものです。 そちらはぜひ本誌をお読み頂くとして、 後半の埋立問題に直接関連する記事だけを抜粋いたします。 |
 |
| 三番瀬に匹敵する十六万坪の価値 ー 浦 壮一郎 ー 4月初句、十六万坪の埋立事業に一貫して反対を唱えてきた晴海屋店主・安田進さんから連絡が入った。荒川沿い の船着き場付近で、ごく普通の虫取り網を入れてみたところ、無数の稚魚が獲れたというのだ。 後日、私も同じように試してみたのだが、マコガレイやカタクチイワシ、スズキ、ハゼ類、そしてキンポやウナギ の稚魚まで捕獲することができた。それも、いとも簡単にである。これには正直いって驚いた。「三浦屋』の堀江さ んが昨年は全く手に入らなかったと言っていたキンポ、そして湾奥ではほとんど漁が行なわれなくなったウナギ、そ の稚魚が東京湾に戻ってきているのだ。 ウナギの稚魚はシラスウナギと呼ばれ、確かに最近はいくらか獲れるようになってきたと聞いてはいた。ただ、ま ったくの素人である我々にも獲れるのだから、江戸前のウナギが復活しつつある、そう信じたいという思いがつい先 行してしまう。さらに数日後、安田さんが十六万坪でも網を入れてみたところ、荒川と同じようにさまざまな種類の 稚魚が獲れたという。特にハゼ類とマコガレイの稚魚の数たるや、荒川の比ではないとのことだったが、これは予想 どおりといっていい。 小誌2月号で取材した水中映像専門のダイバー、尾崎幸司さんが十六万坪に潜ったところ、「あれだけ稚魚の数が多 い海域は珍しい、三番瀬に匹敵する」とまで言っており、あの海域が魚たちの保育園のような存在であり、成育場で あることは紛れもない事実なのだ。また、いかに荒川などの河川に稚魚が増えたといっても、一度大水が出てしまえば 大打撃を受けるのは間違いない。やはり、十六万坪のような閉鎖水域こそ、東京湾の再生に欠かせない存在であろう。 いずれにせよ、東京湾が豊かさを取り戻しつつあることは聞違いない。このまま回復し続けていけば、前述の佃島の 佃煮は、純江戸前産のものが復活することも夢ではないのではないか。そう感じさせるだけのカを、これらの稚魚は 持っている。 一方、江戸前の代表的な味覚として、今も人気が高いウナギはどうだろう。静岡など各地方の養殖ものではなく、純 江戸前ウナギの復活、それを望むことは早計なのだろうか。 |
 無数の稚魚、幼魚がすくえる。 |
豊かさゆえの漁法、ウナギの流し突き 日本に生息するウナギの生態は、つい最近になってようやく分かりか けてきたような状態にある。ウナギの産卵は6月頃、小笠原の南、赤道 近くのマリアナ海域であることが分かっており、ここでフ化した稚魚は レプトケファルス(葉形幼生〕になり、フィリピンに向かって東に流れ る北赤道海流に乗り、その後、北へ流れる黒潮の潮流によって日本沿岸 に近づくといわれる。 |
| 実に約3000Ɠもの距離を旅したのちに東京湾へ入ってくるわけだ。日本沿岸に近づいたあたりでシラスウナギにな るが、それでも遊泳カはたかが知れているため、湾内の潮流、その流れを借りて湾奥までやっとの思いでたどり着くの だ。 よって、いくら東京湾の水質が向上したとはいっても、これ以上の埋め立てや凌藻など、潮流に影響を与える工事を 行なうことは、ウナギのように潮流を利用して東京湾にたどり着く魚たちにとって、致命的な影響を与える可能性が非 常に高いと専門家は口をそろえる。逆にいえば、これら湾内で行なわれている工事、計画されている事業をストッブさ せることができれば、江戸前ウナギの再生も充分に可能ということだ。 その根拠として、昨年と今年、シラスウナギの漁獲は増加しており、一時、東京湾のニホンウナギは絶滅してしまう のではないか、とさえいわれていた時期と比較すれば、それは確実に好転しているからである。 束京湾でのウナギ漁は、昭和30年代まで盛んに行なわれていた。なかでも面白いのが流し突きと呼ばれる漁法で、 小型の船に十数人が横一列に並び、流し鈷という専用の漁具を用い、船を流しながら銛を絶えず海底に突き刺すという ものである。闇雲に突き刺すだけの単純な漁法だが・当時はそれでウナギが獲れたのだ。それだけ多くのウナギが生息 していた証拠で、いかに東京湾の自然が豊かであったかを如実に物語っている。明治時代には大森や砂町でも行なわれ たが、昭和以降に入っても続けることができたのは葛西や浦安であったという。 荒川河口の三枚洲も、流し突きが盛んな漁場のひとつであり、ウナギにとっても干潟が重要な役割を担っていた。 もちろん、流し突きが行なわれていた頃のレベルまで、湾奥の自然を回復させることは至難の業であろう。ただし、 行政も含めた人々の認識が向上すれば、次世代、またはその次の世代には、復活させることも不可能ではないのであ る。現状では夢のような話に聞こえるかもしれない。しかし、湾奥まで訪れるシラスウナギが増加していること、 そして荒川で見たあのシラスウナギこそが一筋の光明であり、環境への関心が高まったことで、東京湾再生、江戸前文 化復活を願うようになった沿岸の人々に対し、まるでエールを送っているかのように思えてくる。 東京湾の現状を熟知している前出の尾崎さんも、東京湾の可能性について次のように語っている。 「東京湾はまだまだ回復する力を持っています。かつての江戸前を取り戻すことは決して不可能なことではありませ ん」いつの目か、再び江戸前の海が漁師たちで賑わい、そして海岸で遊ぶ子ともたちの姿を、ごく普通に見られる時が 来ることを信じたいものである。(参考文献/「東京都内湾漁業興亡史。一東京都内湾漁業興亡史刊行会) |
| 環境庁は動くか? 十六万坪に絶滅危惧種「エドハゼ」がいる可能性 エドハゼという聞き情れない魚の存在がにわかに注目され始めている。 それもそのはず環境庁のレッドリストにも指定されている絶滋危慣種であり、それ が十六万坪に生息している可能性が高いのだ。発見されるのを待たずに、これまで だんまリを決め込んでいた環境庁が動<か否か.その動向に意点は移りつつある。 |
 |
| 焦点は東京都港湾局vs運輸省から、環境庁の動向へ 有明旧貯木場(十六万坪)はこれまで、マハゼの聖地として注目されてきた。前号でもお伝えしたようにマハゼが 大量に生息していることはすでに明らかであり、それはエサになるゴカイなどの底生牛物、カニやエビといった甲殻 類が豊富であることの証でもある。しかし、生態系豊かなその海域も、行政から見れば単なる埋め立ての対象でしか なく、「マハゼは東京湾のほかの海域にもいる」の一点張りだ。 マハゼのみならず、十六万坪が文字どおり生物多様性を維持していること、その価値を見出す能力が彼らには欠け ているといわざるを得ない。すでに計画は、東京都が今年3月に運輸省に埋立許可申請を行い、受理されていること から、焦点は運輸省がいつ認可するか」に移っており、国がどのような判断を下すかによって、十六万坪の命運が決 するといっていい。つまり、東京都港湾vs運輸省という構図が成り立つが、そこに環境庁の名が含まれないことにい らだちを感じる読者も多いだろう。 これまでも何度か述べてきているように、有明北地区埋立事業は埋立面積が35・4haであり、環境庁長官の意見の 聴取が必要とされるのは50ha以上であることから、環境庁としては関与できないというのが彼らの主張である。 しかし「環境保全上特別の配慮を要する埋め立てについては、環境庁長官が意見を述べることができる」ともあり 特に、稀少な生物が生息しているような場合は無視し続けることはできないことになる。ただし、これまではマハゼ が議論の中心であり、東京湾湾奥のハゼ釣り場は激減しているとはいえ、全国レベルで見れば確かに稀少と呼べるよ うな状態にはなかった。ところが、環境庁自らがレッドデータブックに記載する魚種が、十六万坪に生息している可 能性が高いのである。 絶滅危惧種・エドハゼの存在 環境庁のレッドリストには、絶滅のおそれのある野生生物の種が記されている。 その内容は、最も絶滅が危惧される「絶滅危倶1A類」に始まり、「絶滅危恨1B類」、「絶滅危倶ll類」、「準絶滅 危惧」、「危急種」、「希少種」の6段階(絶滅種、絶滅のおそれのある地域個体群を除く)にランク分けさられて いる。その中で、上から2番目にあたる絶滅危慎1B類に指定される魚種、ハゼ科ウキゴリ属のエドハゼと呼ばれる種 が、あの十六万坪に生息している可能性が高いという。ちなみに、レッドリストに載ったことで話題になったメダカ は絶滅危惧ll類の指定であり、エドハゼはそれ以上に危機的な種であると判断されていることになる。 また、東京都版レッドリストといえるのが、環境保全局が調査・作成する「東京都の保護上重要な野生生物種」で ある。こちらは3段階のランクが設けられており、A:国の絶滅危惧種に相当する種、B:国の危急種に相当する種、 C:(国の)希少種に相当する種、となっている(絶滅種を除く)。 これによるとエドハゼはAランクに相当し、東京都に生息する生物の中でも、最も絶滅のおそれのある魚類の一種と いえる。そのエドハゼは、環境保全局の調査によると湾奥の城南大橋付近、葛西沖人工なぎさ、さらにお台場海浜公 園で確認されている。十六万坪については未調査とされているが、江戸湾の趣を今に残し、マハゼのほかさまざまな 生物が他の海域よりも格段に多い海域だけに、エドハゼが生息している可能性は極めて高い。 ハゼの分類に詳しい東京大学海洋研究所の向井貴彦理学博士は、エドハゼの現状について次のように語っている。 「環境庁のレッドリストに入っているハゼの中には、ウキゴリ属という種類がかなり含まれています。エドハゼ、ク ボハゼ、チクゼンハゼ、みんなそうですね。あと準絶滅危惧種でもイサザとかがウキゴリ属になります。これらの魚 は数が減って危機的な状態にあるのです」 そのウキゴリ属にあたるエドハゼが、東京湾湾奥にはまだ生息しているのだ。「絶滅危惧種がいる可能性の高いと ころを、ちゃんと調査もせずに埋め立ててしまうというのは、少なくともいいことではないですよ」エドハゼという 魚はもちろん釣りの対象でもなく、また漁業など商業的に利用されている種でもない。よって、調査・研究は充分と はいえず、詳しい生態も分かっていないのが現状である。分からないからこそ、今後詳しい調査を進めるべきなのだ が、それをせずに東京湾は次々と埋め立てられてきたのである。城南大橋付近、葛西沖人工なぎさ、そしてお台場海 浜公園で確認されているというエドハゼ。この絶滅に瀕した種がこの3地点で見つかっているなか、十六万坪にだけ 生息していないと考えるのは、むしろ.不自然である。いずれ確認されることになると思うが、もし見つかった場合 埋立面積50ha以下としてだんまりを決め込んでいた環境庁も無視し続けることはできなくなる。環境庁自ららが指 定する絶滅危倶種、それが生息するにもかかわらず、意見を述べることさえしないのであれば、環境行政としてその 存在意義を間われることは必至だからである。 環境府はなぜ動かないのか |
 |
石原都知事人気に支えられ、 道理を失った東京部の役人たち 埋め立てを反対している保護運動力が、三番瀬や盤洲干潟 など、東京湾全体に広がってきていることは前号でもお伝え した。彼ら自然保護団体としても、絶滅危惧種のエドハゼが 生息している可能性が高いだけに、環境庁に対して少なから ず期待していることは事実である。彼らの口から環境庁への 落胆の声が聞かれることは当然のことだが、それは期待感の裏返しのようなものでもある。 |
| 一方、環境庁としても、エドハゼが発見されてから重い腰を上げるようでは、いささか対応が遅すぎるだろう。 その前に動いてほしいというのが自然保護団体関係者の願いであり、それは周囲の埋立面積にも関係してくる。 確かに東京郡の事業計画によれば埋立面積は35・4haだが、豊洲や晴海の埋立てを含めれば50haを超える事業に なるからだ。都側から見れば、それは確かに別事業ということになる。しかし、十六万坪と豊洲埠頭は目と鼻の先で あり、晴海運河を入れても。わずか約1・5Ɠにすぎない。事業が別であっても”同じ海”であることに変わりはな く、その同じ海に計画されている埋立面積は、、有明北35・4ha、豊洲14・5ha、晴海5・2haとされており、計 55・1haにも及ぶことになる。50haを超えるこれらの埋立計画を、東京都は。個別に事業計画を作成し進めてきた。 これまで小誌では、十六万坪の埋め立てに環境庁が無視し続けていると述べてきたが、環境庁が東京都に無視され ているといい替えることもできる。むしろ、軽くあしらわれてしまっているのは環境庁のほうなのである。もちろん 運輸省とて同様である。東京都港湾局が去る3月10日、運輸省に対して認可申請を行なったことはご承知のとおり。 それはすでに受理されており、いつ運輸省が認可するのか……という段階まできている。 ところが運輸省に提出した計画内容に対し港湾局は、認可後に変更を予定しているというのだ。計画を変更するな ら、改めて申請し直すのが道理のはずだが、横暴極まる港湾局はそんなことはお構いなしである。 まるで石原都知事の人気が高いことをいいことに、東京都港湾局は運輸省すらも足蹴にしようとしているように見 える。その前例といえるのが豊洲埠頭周囲の埋立計画である。こちらの計画はすでに運輸省から認可を受けている が、認可された内容では認められていない方法で、東京都は豊洲埠頭の開発を進めようとしている。豊洲埠頭の埋立 計画は、現在の護岸の外側を30…50m広げて緑地を造成するものであったが、実際には埋め立て後に区画整理を行な い、緑地だけでなく宅地造成することに計画を変更してしまったのだ。 これは有明北にもつながる環状2号線などの幹線道路建設にも関係している。道路を建設するために都は区画整理 事業を計画したが、周囲の埋め立ては”地権者の負担になる減歩卒を軽減することが目的”とも考えられるのだ。 (つまり埋め立てそのものが目的ではない)。道路を建設すれば地権者は持っている土地を提供する必要性が出てく る。これを減歩と呼ぶが、埋め立てを実施しない場合の平均減歩卒は約28%。埋め立てによって面積が広がることに なれば、当然のように減歩卒は下がることになる。豊洲埠頭の地権者は一般佳民ではなく、東京ガスや東京電力と いった大企業ばかりである。 早い話、一部の大企業の利益のために、豊洲埠頭の周囲は埋め立てられようとしているのである。 一方、有明北地区の埋立事業はどうだろうか。十六万坪の周辺もヤマト運輸や東武百貨店、昭和シェル石油などの 企業が地権者になっている。こちらも区画整理事業が進められることになっており、埋め立て前の滅多率は約18%と いわれている。しかし十六万坪を埋め立てたのち、それはひと桁にまで緩和されるというのだ。 埋立事業の名目には住宅建設が掲げられているが、実際は幹線道路用地を埋め立てによって捻出し減歩卒を緩和す ること、都民に負担を強いる一方で、民間企業の負担を軽減することが目的ともいえる。 そして運輸省への認可申請だが、現在の石原人気に支えられて有頂天になりつつある東京都が、「一旦は認可の通 りやすい内容にしておき、のちに変更するほうが埋め立て着工の近道……」と考えることは何ら不思議ではない。 逆にいえば、今や東京都にとっては運輸省や環境庁でさえ、単に踏み台的な存在でしかないのである。 民主党が模索する公共事業コントロール法とは なぜ、カニ護岸の実験を十六万坪で行なうのか? 埋立てが行なわれなかったことで、奇跡的に残ったハゼの楽園。その大半の海域を埋めて、
|
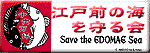 |
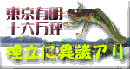 |