 |
情報、其之拾之弐 2000.7/20 [ 講演 マハゼから見た東京湾 ] 丸山 隆 (東京水産大学)P.2 |
 |
10 羽田沖合の埋め立てでは地元の研究所と して、自費で、羽田の埋め立て地の手前で 調査しています。 また、羽田沖合は、羽田空港の拡張工事でカレイやハゼの 産卵場所でしたから、沖合に房総半島の山にある粗砂を大量 に投棄しています。 |
| しかし、その埋め立てに使う泥が、本来細かい砂地であるところ、砂粒が大きすぎたために、ハゼを はじめ多くの魚が産卵できない状態で、結果として浅瀬が魚が使えない場所になって、死んだ状態にあり ます、 羽田沖でのマハゼの再生のためには、ゼロからはじめることになります。水域の生態系で最も重要なこと は分かっていることをやるべきだという事です。 11 酸素の供給源としては 民主党の議員等から質問として 質問1:(民主党議員)湾口に大きな石があります、それを取り除いたら微生物レベルで影響は? 回答: 護岸を取り除いたとしても、その技術的な手法が理にかなっていれば、微生物も幼生も稚魚も浮遊 していますので、羽田沖も同様ですが、翌年にはあっという間に回復します。しかし、手法が悪ければ永久 に回復しません。但し最も大切なことは、幼生や稚魚の供給源が豊かにあってのことです。 質問2:(民主党議員) 中央防波堤の中から風で散逸した大量のポリ袋が、東京湾内に大量に沈殿してい るのでは無いかとの質問があった。環境庁では全国で1万〜2万トン 回答:潮が入ると巻き上げられ、海流に乗って湾外の伊豆諸島の大島北東と相模湾の大磯を結ぶラインまで 流出して、台風後等は、長さ数キロのゴミのベルトとなって流れ、沈殿していく模様、湾内には少ないとの 回答がありました 質問3(安田さん)有明十六万坪にはハゼのみで10種類、稚魚は14種類も確認しています。他にこの様 な場所がありますか 回答: 調査情報がないので回答できません。湾口にはもっと多いと思います。しかし、湾奥での事例は貴 重です。しかし、私はエドハゼ等貴重な魚がいるから大切にするとの考え方は取りません。 当たり前のことですが、ごく普通な魚がまともに生きていけない湾奥が問題です。また貴重な魚がいるか ら入っては行けないと言うのは、かえっていじり回すことになって反対です。 稚魚の重要性に注意して下さい。稚魚がこの湾奥に吹き寄せられるにはいくつかの必然性があります。 種類毎に、ある特定の時期に浮遊して行かなければならない事情があります。 逆になぜ、この貴重なはずの場所を調査していないのか。調査しているのを実見している。出口を調査し ている。内部は調査していないのか。環境局との関連では、データが取れていない? マハゼ/エドハゼ 個体数は少ないが、生息地域/資源は増えつつあると考えています。 保存の考え方として、特定の種類がいるから保護するのではなく、絶対に生存権のために必要との考え方 にたつべきです。今後増えるのか減るのか?日本ではマハゼでは調査されている程度で、今後の調査待ち、 水生生物調査方法が必要です。 同一場所/投網等によって、葛西沖/城南大橋/何れもいいところで採取しています。 有明十六万坪でも投網等による生物調査を実施しているが、その情報開示がされていません。間違いなく 調査している(実見しているので)資料を早く公開すべきです。 神奈川県等に設置されている環境モニター制度が東京にはない。明らかに東京は立ち後れている、しかも データが無いならそれなりに理解できるが、私もデータを収集していることを実際に見て知っているので、 持っていて、ある意図で情報を公開しないとしか考えられない。情報を早く開示すべきであります。 神奈川県保全局の場合など、インターネットでも検索ででていますから。 質問4:(民主党議員)堤防手前の宅急便会社の敷地も買収、全体を公園にする構想はどうか。堤防側にテ ラスを置いて有明十六万坪を見せるアイデアは 回答:十六万坪の有明側に遊歩道は最善です。現在は、人が入っては行けない構造になっています。 上を編み線で覆ったテラス形式で空気が通りやすくする。網入りで海の底にも光のはいる、フランス・パリ のセーヌ川のテラスの形でお願いしたい。これであれば自然を損なわない。 質問5:(民主党議員)平井川で、自然環境として、蛇行を加えたらハゼが戻ってきました。 しかし、10年もかかりました。微生物との関係ですか。 回答: ハゼの回復は10年はかからないでしょう。問題は、ハゼの産卵場所が、比較的深く、細かい 泥地に穴を掘ります。しかも酸欠にならない場所と言うと、状況は厳しい。 川と運河は東京にはたくさん残っていますが、石済みの堤防が残っているところは意外に少ない これらが、潮が引けば浅瀬が少しでも残っていればマハゼには住み易い。決していい場所でなくても生き ながらます。 現在、中央防波堤沖等では、底に棲むべきメバル、ウミタナゴ、アイナメ、シマアジ等の小魚が、酸欠の ために、堤防の壁に添って上に棲んでいる。5m以下は真っ暗で、かつ酸欠のためです。 以上、2000.7/5 都議会民主党控え室にての 講演と質疑応答より。 |
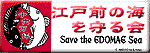 |
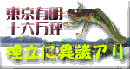 |