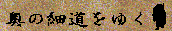
<日光2・裏見の滝>
(にっこう・うらみのたき)栃木県日光市
旅行日 '97/7
地図を見る(ここをクリック)
東照宮を参拝した翌日、芭蕉は、裏見の滝を訪れます。日光三名瀑のうちのひとつ(あと二つは華厳の滝と霧降の滝)とされ、滝の高さは18m。華厳の滝の5分の1程度で、それほど大きな滝ではありません。
 二十余丁、山を登って滝有り。岩頭の頂より飛流して百尺(はくせき)、千岩(せんがん)の碧潭(へきたん)に落つ。
岩窟に身をひそめ入りて、滝の裏より見れば、うらみの滝と、申し伝え侍るなり。
二十余丁、山を登って滝有り。岩頭の頂より飛流して百尺(はくせき)、千岩(せんがん)の碧潭(へきたん)に落つ。
岩窟に身をひそめ入りて、滝の裏より見れば、うらみの滝と、申し伝え侍るなり。
<現代語訳>
(東照宮から)二十余丁(注:2km強)ほど山を登ってゆくと滝がある。岩が洞穴のようにくぼんだところの頂上から百尺も飛ぶように流れて、たくさんの岩が重なり合っている青々とした滝壺に落ち込んでいる。岩屋になっているところに身をかがめて入り込んで滝の裏側から眺めるので、裏見の滝と言い伝えられているのである。
芭蕉が訪れて三百年。浸食が進み、滝も姿を変えているものと思われます。現在でも滝の裏側へまわり、「うらみ」ることが可能です。ただし岩肌の道は人ひとりがかろうじて通れるほどの幅で、しかも水しぶきを浴びて滑りやすく危険この上なし。高い所と滑る所と下り坂が怖い私にはとても行けませんでした。
続いて、芭蕉の句(↓)へ。
 <芭蕉の句>
<芭蕉の句>
暫時は 滝にこもるや 夏の初
(しばらくは たきにこもるや げのはじめ)

<句意>
- 折から、仏道の夏籠<げごも>りも始まろうととしているが、こうして裏見の滝の岩屋にこもり、しばらく清浄な気分で過ごすのも、いっそう精進の気持ちを高めることになるのだ。
NHK文化セミナー「おくのほそ道」永遠の文学空間(堀切実著)より
右写真は安良沢小学校内に建つ句碑。

 日光1・東照宮の頁へ
日光1・東照宮の頁へ
スタート頁(地図)へ
ホームページへ |「奥の細道」目次へ | メールはこちら
![]()
 二十余丁、山を登って滝有り。岩頭の頂より飛流して百尺(はくせき)、千岩(せんがん)の碧潭(へきたん)に落つ。
岩窟に身をひそめ入りて、滝の裏より見れば、うらみの滝と、申し伝え侍るなり。
二十余丁、山を登って滝有り。岩頭の頂より飛流して百尺(はくせき)、千岩(せんがん)の碧潭(へきたん)に落つ。
岩窟に身をひそめ入りて、滝の裏より見れば、うらみの滝と、申し伝え侍るなり。


 日光1・東照宮の頁へ
日光1・東照宮の頁へ