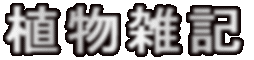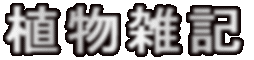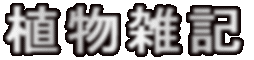
vol.2 「難物番付」 '04年11月15日
そもそもこのサイトは所謂「難物サボテン」の栽培レポートを掲載しようとはじめたものでした。難物サボテンとはどんな植物たちか、どこに魅力があるか、と云ったことは別項「難物道」に記したので割愛しますが、いったいひと括りに「難物」と呼ばれるなかで、どの種類がどのくらい難しいのか、それぞれの難しさのポイントはどこにあるのか、といったことをここでは書いてみたいと思います。今回はサボテン科植物のうち、アメリカ合衆国とメキシコに産する種に限って、わかりやすく「難物番付…ジャンル別格付けランキング」という形にしてみました。もちろん、個人的な栽培経験がベースなので、育てたことのない種は含まれていませんし、多分に独断と偏見に基づいています。栽培環境によってもかなり違ってくると思います(筆者の栽培場は関東首都圏の街なかで、日照通風など決して条件の良い場所ではありません)。他にもっと難しいのがあるよ、とか、これはこう育てればカンタンなんだよ、などなどご意見があれば是非お寄せ下さい。
<「北米サボテン」難物度総合ランキング>
| 属・種 |
総合 |
発芽率 |
成長速度 |
耐湿 |
耐暑 |
耐寒 |
耐腐敗 |
花つき |
| ペディオカクタス・天狼 |
AAA |
極低い |
極極遅い |
極弱い |
弱い |
極強い |
極弱い |
極悪い |
| スクレロカクタス・白紅山 |
AAA |
低い |
遅い |
極弱い |
強い |
普通 |
極極弱い |
普通 |
| ペディオカクタス・ブラディ |
AA |
極低い |
極極遅い |
極弱い |
弱い |
強い |
弱い |
? |
| スクレロカクタス・月想曲 |
AA |
極低い |
遅い |
極弱い |
弱い |
強い |
極弱い |
普通 |
| スクレロカクタス・黒虹山 |
Aa |
低い |
遅い |
弱い |
極弱 |
極強い |
極弱い |
良い |
| スクレロ・ナイエンシス |
Aa |
低い |
遅い |
弱い |
普通 |
強い |
極弱い |
普通 |
| スクレロ・プビスピナ |
Aa |
低い |
極遅い |
弱い |
極弱 |
極強い |
極弱い |
普通 |
| ペディオ・ウィンクレリ |
Aa |
低い |
極遅い |
弱い |
弱い |
極強い |
極弱い |
普通 |
| スクレロカクタス・彩虹山 |
A |
低い |
遅い |
弱い |
弱い |
極強い |
弱い |
良い |
| エキノマスタス・英冠 |
A |
普通 |
極遅い |
弱い |
強い |
普通 |
弱い |
普通 |
| エキノカクタス・大龍冠 |
A |
低い |
極遅い |
弱い |
強い |
普通 |
やや弱 |
? |
| ペディオカクタス・飛鳥斑鳩 |
BBB |
低い |
遅い |
弱い |
弱い |
極強い |
弱い |
良い |
| トウメヤ・月の童子 |
BB |
低い |
普通 |
弱い |
弱い |
極強い |
弱い |
良い |
| ペディオ・ニグリスピヌス |
Bb |
低い |
遅い |
やや弱 |
弱い |
極強い |
弱い |
? |
| スクレロ・グラウカス |
Bb |
低い |
遅い |
弱い |
弱い |
極強い |
弱い |
良い |
| ミクロプンチア・プルケラ |
Bb |
低い |
極遅い |
弱い |
普通 |
強い |
やや弱 |
普通 |
| ペディオ・パラディネィ |
B |
低い |
遅い |
やや弱 |
弱い |
極強い |
弱い |
良い |
| エキノマスタス・紅廉玉 |
B |
良い |
遅い |
弱い |
強い |
普通 |
やや弱 |
普通 |
| ペディオ・月華玉 |
CC |
低い |
遅い |
やや弱 |
弱い |
極強い |
やや弱 |
良い |
| エキノマスタス・藤栄丸 |
CC |
普通 |
遅い |
やや弱 |
強い |
普通 |
やや弱 |
良い |
| エキノマスタス・桜丸 |
CC |
良い |
やや遅い |
やや弱 |
普通 |
強い |
やや弱 |
良い |
| マミラリア・テトランシストラ |
CC |
良い |
普通 |
弱い |
普通 |
強い |
やや弱 |
良い |
| エキノカクタス・神竜玉 |
C |
やや低 |
やや遅い |
やや弱 |
強い |
普通 |
普通 |
普通 |
| 沙漠丸・アルバーソニー |
C |
良い |
やや遅い |
やや弱 |
普通 |
普通 |
普通 |
普通 |
| エキノマスタス・白栄丸 |
C |
良い |
普通 |
やや弱 |
強い |
普通 |
やや弱 |
良い |
| コリファンタ・精美丸 |
C |
普通 |
やや遅い |
やや弱 |
普通 |
普通 |
やや弱 |
普通 |
| アンシストロ・玄武玉 |
C |
良い |
普通 |
弱い |
強い |
普通 |
弱い |
良い |
| エキノマスタス・ワルノッキー |
C |
良い |
普通 |
やや弱 |
普通 |
普通 |
やや弱 |
良い |
| エキノマスタス・ラウィ |
D |
良い |
普通 |
やや弱 |
強い |
普通 |
普通 |
良い |
| オプンチア・バシラリス |
D |
やや低 |
やや遅い |
やや弱 |
強い |
強い |
やや弱 |
悪い |
| ツルビニカルプス・美針玉 |
D |
普通 |
遅い |
やや弱 |
普通 |
普通 |
やや弱 |
普通 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (以下 比較参考種) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ペレキフォラ・精巧丸 |
EEE |
普通 |
遅い |
普通 |
普通 |
普通 |
普通 |
普通 |
| マミラリア・陽炎 |
EEE |
普通 |
やや遅い |
やや弱 |
やや弱 |
普通 |
やや弱 |
良い |
| エキノケレウス・武勇丸 |
EEE |
普通 |
普通 |
普通 |
強い |
普通 |
普通 |
悪い |
| エキノカクタス・太平丸 |
EEE |
やや低 |
普通 |
普通 |
普通 |
普通 |
普通 |
良い |
| エスコバリア・ダンカニィ |
EEE |
良い |
やや遅い |
やや弱 |
普通 |
強い |
普通 |
良い |
| エキノケレウス・青花蝦 |
EEE |
良い |
やや遅い |
普通 |
やや弱 |
極強い |
やや弱 |
良い |
| アストロフィツム・兜 |
EE |
良い |
早い |
普通 |
強い |
弱い |
やや弱 |
良い |
| エピテランサ・小人の帽子 |
EE |
良い |
やや遅い |
普通 |
普通 |
普通 |
普通 |
良い |
| アリオカルプス・亀甲牡丹 |
EE |
良い |
やや遅い |
普通 |
強い |
普通 |
普通 |
良い |
| テロ・緋冠竜 |
E |
良い |
早い |
普通 |
強い |
普通 |
強い |
良い |
| アストロ・ランポー玉 |
E |
良い |
早い |
普通 |
強い |
普通 |
強い |
良い |
| ロフォフォラ・翠冠玉 |
F |
良い |
早い |
強い |
強い |
普通 |
強い |
良い |
| フェロ・紅鶴丸 |
F |
良い |
とても早い |
普通 |
強い |
普通 |
強い |
良い |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
こうして並べてみると、やはりペディオカクタス・スクレロカクタスが上位に並んでいます。比較的高緯度に自生する耐寒性の強い植物が栽培困難なのはなぜなのでしょうか。以下に私なりの考察を述べます。
上に、耐寒性「極強い」と書いた植物は、概ね日本の関東より高緯度でしかも標高の高い地域の産です。いずれも乾いた状態なら氷点下20度近くまでもちこたえることができます。耐寒性だけで云えば、日本国内ならたとえ北海道であっても軒下で越冬できるはずです。しかしそうした植物の自生地は内陸性の気候であり、はんたいに夏期は最高気温摂氏40度近くまで達します(もちろん夜間は激しく下がりますが)。こうした極寒と酷暑を経験する極端な環境に適応するために、ペディオ・スクレロ属や、一部のエキノケレウス、エスコバリア属の植物は肉質がたいへん柔らかく脆弱になっています。これが、季節変化にともなう球体サイズの大幅変更を可能にしているわけです。小さく縮むことで岩陰や地中に身を隠し、炎熱寒風をしのぎます。極寒には体液濃度を高め凍結をふせぎます。スクレロカクタス・グラウカスの自生地を調査した論文によれば、乾期には植物体の重さが雨期(成長期)の20%以下まで縮むことがあるそうです。またペディオのウィンクレリや飛鳥などは酷暑極寒期は縮みこんで完全に地表の下に潜って過ごします。まるで球根植物のような生態で、休眠期は自生地を訪ねても植物体を見つけることが出来ません。
この激しい「収縮」はまた、成長の遅さとも関わってきます。上記表記のなかで、成長が「極々遅い」というのが実際はどのくらいなのかというと、<ペディオ・ブラディ>は成球の径が3,4センチほどの植物ですが、私の栽培場では実生8年生が径1.5センチで未開花。同じく<ペディオ・天狼>は大型種にもかかわらず実生3年で径1センチ高さ2センチ。「遅い」と表記した<ペディオ・飛鳥>だと、実生5年で径1.5センチ。10年で2.5センチに達し花が咲く。「普通」と書いた<月の童子>が実生3年で径1センチ高さ4センチで開花、と云ったところです。そもそも、肉質が柔らかいなら生育は早そうですが、なぜそうでないのか。それは彼らの成長期が春先のごく短い期間に限られること(概ね1〜2か月くらい)。またせっかく成長しても、肉質が柔らかく休眠期には球体下部がぐっと収縮してしまうので、三歩前進二歩後退、といったスタイルであることによります。刺座は出ても、いっこうに径は膨らまない。私の栽培が極端に水が辛いことも一因になっているかも知れませんが、フィールドで観察を続けているひとの話だと野生下でもほぼ同様の成長速度のようです。
さて、今回は北米サボテンに限定しましたが、同じ傾向は南米産サボテンにも言えるようで、パタゴニアの寒冷地に産するアウストロカクタス属(Austrocactus)は、スクレロ類同様に難しいとききます。なんどか種子を入手しましたが、いまのところ発芽すら不可能で栽培経験がありません。またテフロカクタスや、ロビビア、オロヤ属など、アンデスの標高4000m級の高地に生育するサボテンもあり、これらはアルパインプラント的な性質を持ってます。一方ポピュラーなコピアポア属やエリオシケ属も、成長が遅く、微量要素欠乏による生育障害が出やすいなど、ある種の難しさがあります。…いずれ、別項で南米サボテンもとりあげてみたいと思っています。
なお、以上はいずれも、実生からの正木(実根)による栽培育成を念頭においたもので、接ぎ木になると事情はぜんぜん変わってくると思います。また開花のところに?がついているものは、筆者正木での花未見のものです。

スクレロカクタス・白紅山(白虹山)
Sclerocactus polyancistrus Aquerberry Point, Death valley, CALIFORNIA
”AAA”の難物とした白虹山ですが、それでも実生からの育成が不可能なわけではありません。この類としては比較的伸びが良いため、ほとんど成長しない天狼などよりは開花株育成の望みが持てます。もっとも、肉質がたいへん柔らかく、根もサクサク。ちょっとした過湿ですぐに腐ります。実生苗が何本もあっても、いつのまにか減ってゆきます。なので、10年近く育てて開花サイズまで行き着くのはごく僅か、というのが私の経験です。この個体、撮影場所はカリフォルニア・デスバレーエリアの山頂付近で、標高が1800mほど。同じカリフォルニアでも、Barstowあたりの標高5〜600mの場所にある巨大で刺のもの凄いタイプに比べると、女性的な感じ。ネヴァダの白紅山も似た雰囲気です。実生栽培するうえでは、これらやや北方系の小型タイプの方が丈夫に思えます。


BACK NEXT