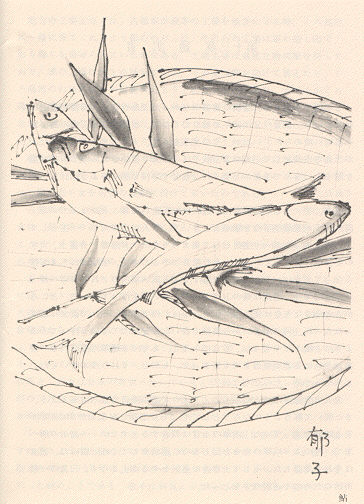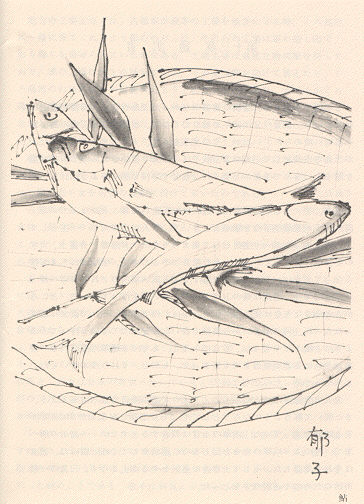
ミス高田は,世界一周の旅から帰国した。まだ日本では婦人が海外に留学することは珍らしかったので,新聞も彼女の記事を書いた。彼女はラジオで講演し,マダム・シューマンハインクとの珍らしい経験を話した。
帰国後間もなく,彼女の良き友であり,相談相手だったX氏が,脳溢血で亡くなった。この25年間,彼女の進路についてよく導いてくれ,また彼の広い知識がどれだけ我が身にとって役立っていたことかと,敏子は今更のように感じたのだった。彼なくしては,彼女の現在の仕事も何等生彩がないと思う程だった。
1930年,彼女は英語学校の仕事を再び始めたが,その頃日本人も日本の政府も,何故か以前のように,西洋の人々に対して,特にアメリカ人にはよい感情を持たなくなってきたように思われた。1920年代の始めには,日本人は西洋諸国に対して概して友好的であった。第一次世界大戦のヴェルサイユ条約によって,日本は旧ドイツ領の太平洋の島の委託統治をすることになり,これで日本は世界第三番目の海軍国となった。西欧的民主政治の受け入れというか,1925年にはいわゆる普通選挙が実施され,日本の男子は選挙権が与えられた。また西洋流にテニスやゴルフ,野球の競技が行なわれるようになった。日本の社会慣習も段々と変わってきて,婦人も会社に雇われるようになるし,ダンスホールのホステスとか,西洋風の料理店のウエイトレスとか,婦人の職場も増えてきた。洋服を着,洋楽を聞くことも徐々に普及してきたのである。
1923年の関東大震災の時には,アメリカは非常に同情的で,惜しまず援助の手をのばしてくれた。アメリカ艦隊は食料や緊急物資を積んで来航してくれ,義捐金もたしか百万弗を越えた額であった。日本人はアメリカの親切に感謝し,もちろん両国の友好的関係は増進していったと思われた。
しかし1924年,合衆国の上院は新しい移民法を上提した。それは移民の受け入れを年間15万以内に限定するというものだった。各国に対するその比例は,すでに米国内に住む同国人の数に応ずるというのである。この制限によると,日本人はたった146人が入国できるだけということになる。法案は成立し,結果としてアジア人はすべてしめ出されることになった。今まで長い間移住者を送り,その多くが立派なアメリカ市民となっている日本に対し,この屈辱的な決定がなされたのである。日本には昔から秀れた伝統と固有の文化があり,それはアメリカのニューイングランドにおけるそれ等よりも,千年も歴史の古いものであることが改めて思われるのである。
この合衆国の移民法は,日本の政府及び日本国民に,西洋の人々やその考え方に対する親愛の情を失わしめるものであり,同時に日本の発展の方向をアジア大陸と太平洋の島々へと向けさせることになった。こうした西洋の変化に伴ない,日本の人々の気持も段々とそれに対立的になっていったが,しかし高田敏子は東京の彼女の女子英語専門学校は止めなかった。それは日本の陸軍が満州を制覇した後も,また日支事変になってからも続いていた。
文部省はこれまで人々に大分普及してきた英語を,今度は使用を制限するよう指示してきた。しかし,海外在住の経験者などは無論英語への関心はまだ十分にあった。こんな頃,日本人の画家でかつ評論家である一人の人物が─この人は米国に40年もの長い間住んでいたのであるが─突然東京へ帰ってきた。彼は日本の新聞に銀座で見られるような婦人の服飾のスタイルや色などの傾向について評論を書いていた。そしてその記事は美術愛好の読者の間で大分評判となった。
丁度アメリカのレーディスホームジャーナルのような種類の日本のある雑誌社が,ミス高田にその人とのインタビューをしてそれを記事に書いて欲しいと依頼してきた。大方の読者は,彼は40年もの間日本を離れていたのだから,日本語は忘れてしまったのではないかと思っていた。敏子はその仕事は面白い仕事だと思って,彼の滞在しているホテルでインタビューしたのだった。
後年になって彼女は次のように書いている。“40年も経っていたのですから日本の国内はすっかり変ってしまい,彼自身も変ったことと思うのですが,しかし彼はきれいな日本語で話すのでした。見たところ彼は大変立派で威厳があり,また洗練された人だと私は思いました。彼の話によると,彼には女と男のきょうだいがあり,日本の西の地方に住んでいるのだが,消息は分らないとのこと。しかし彼は故里へ帰って調べてみようと言っていました。彼は友達もなく,たった一人大学教授をしている友人があって,その人が新聞社の人に紹介してくれたとのことでした。
何もかも変ってしまったので,彼はどんな風に生活していったらよいかも分らず,非常に淋しかったらしいのです。彼は私に,色々分らないことが多いから教えてくれと頼みました。彼はシカゴ大学を出て,ニューヨークである美術団体の指導をしていました。そして,私の学校で美術を教えてもよいと申し出てくれました。何も仕事がないのでとても退屈だったのです。
私が彼の申し出を受けましたので,週に一回来てくれることになりました。彼は生徒の間に人気があり,アメリカについて色々の話もしてくれました。
ある日私は彼を別荘へ昼食に招きました。それは和洋折衷の家で,東京方面をずっと見おろす丘の上の松林の中にありました。私は二人の大学生をそこに置いておりました。彼等は論文を書いていたのです。私はその二人をこの美術家の先生に会わせようと招待しておいたのです。ところがその人─ミスターNが来る少し前に,二人とも家から呼ばれて歌舞伎座に行くことになり,そちらへ行ってしまいました。
“そこで私達二人は,その日はアメリカの話をしたり,私のアメリカでの体験を話したりして面白く午後を過ごしました。彼はあちらで四十年間をどのように過ごしたか,またどうして急に帰国して来たのかなどの話をしました。状況は何やら大変ロマンチックになりましたが,でも私は彼は間もなく帰るだろうと思っていました。ところが,突然そこへ雷雨がやってきました。それが段々ひどくなり,とても表へ出られたものではありません。私達はやがて晴れるだろうと思って待ったのですが,とうとう台風となってしまいました。彼と二人だけであり,どうしてよいか分かりませんでした。
“彼は私よりずっと年上のことでもあり,そこで私は一体こんな場合どうしたらよいのでしょうと彼に尋ねました。彼を追い出すわけにはいかないし,そうかと言って彼を一人そこにおいて逃げ出すわけにもいきません。彼は微笑んでこう言いました。‘何処かへ置いて下さい。明朝早く帰りますから’と。
“私は別に彼のことを気にしなかったので,それから一緒に夕食を食べ,またひとしきり火のそばで話し込みました。話しているうちに彼はとてもセンチメンタルになってしまい,私に結婚のプロポーズをしたのです。その後数週間たちましたが,私は何の返事もしないでいました。そして,弟に会った時その話をすると,彼もN氏の評論を新聞で読んでいたので,大変心を動かしたようでした。弟は熱心に,私に人間として当然なすべき体験を持つべきだと言うのです。しかし私はずっと続けたい仕事があるし,西洋風の考えになれて,自主独立してやってきています。だから,適当な人を見つけることはむずかしいだろうと思っていたのです。でも弟は,N氏こそ丁度私に合う人のような気がすると言うのです。
“そこで,弟はある晩彼を夕食に招んだのです。私達は大型の屋形船を出して貰い,そこで夕食をとりました。二人の男の人は飲む程に,食べる程に話ははずみ,気の合ったのかすっかりお互いに気心も分ったようでした。そんなことで,弟はごく自然に私との結婚話を持ち出しました。私としてはごく冷静な気持であったし,むしろ冷淡だったようです。しかし一方,日支事変の進行してゆく時,私の将来は何やら不安が感じられ,仕事を続けていくことにも不安がないわけではありません。
“さて二ヵ月の後,私達は教会で結婚式を挙げました。その折の牧師は,伯父の尾島眞治でした。式はいたって簡単なもので,少しばかりの親しい友達と何人かの生徒を招待しました。結婚した後も、私は自分の従来の名前を名のることにしました。それというのも,学校は公に高田女学校として知られてきているので,その名前を変えることはできません。
“N氏は,婚約がきまって二,三ヵ月後から健康がすぐれなくなりました。多分それは長い間の淋しい孤独な人生の航路に疲れ,今やっと錨を降ろすべき場所を見つけたその安堵感からだったのかも知れません。
“私達はほんの二,三日の新婚旅行に出ただけで,もうその一ヵ月後には彼の病気が重くなってしまったので入院させなければなりませんでした。その費用を出すために,私は将来のためにと思って作っておいた私の別荘を売ってしまいました。容態は悪化する一方でした。病院のお医者さんが家の近くに住んでいました。夫がしきりに家に帰りたがるので,私たちはつれ戻すことにしたのです。そのお医者さんが,一日に二度往診してくれました。
“夏が来るとともに彼は何の苦しみもなく,静かに死んで行ってしまいました。彼は私が色々したことを感謝していました。私はこうした悲しみを通り過ぎ,しかも何も残るものは無く,空ろでした。私の結婚生活はわずか一年にも満たないものでした。本当に人生とは不思議なものです。彼は四十年をアメリカで過ごし,そして日本へ帰ってきた時はその四十年の間にまったくの異邦人となっていました。私は色々なことで彼の面倒をみなければならなかったし……お互い,物事がうまくいかない時には英語で話し合ったりしたものです。時が経つに従ってようやく私ももとの元気を取り戻しましたが。”
日本の政府は,新聞や雑誌に用いられている用語の中からすべて英語を排除し始めた。西洋流のものは何でも不可とされた。たとえば外来語のアナウンサーとか,レコード,ライターなど一連の英語はことごとく廃せられ,日本語に置き換えられた。こんな時,それは1940年の二月頃のころだが,文部大臣はミス高田を呼び出して,英語専門の彼女の学校を閉じるようにと命令した。
彼女は,その年の卒業予定の生徒に対しては,三月の卒業時期を一ヵ月程早めて卒業させることにした。しかし,その他の低学年の生徒達が問題だった。多くの父兄がやってきて是非英語教育を続けて欲しいと訴え,生徒もまた学校に留まりたいと言うのだった。彼女は教課を変更するために他の先生達を雇うということも出来かねたし,その為に大きな校舎を維持するというのも大変だった。父兄達は,もし学校を処分しなければならないのだったら,どこか小さい家を見つけるようお手伝いしましょうと申し出るのだった。彼女が思うには生徒達はやはり適当な学校で勉強する方がよいだろうということだった。
“このような問題に直面するのは,何とつらいことだったでしょう。”
と彼女は後になって言うのだった。“一体どうしたら生徒のために一番よいのだろうと色々に思い悩みながら銀座を歩いていた時,突然ひどい関節炎が私を襲ったのです。私は歩けませんでした。タクシーも見つからず,人力車も無し……でも幸運なことに私は男の連れと一緒だったので,その人が私を背負って家まで連れてきてくれました。それから,二,三ケ月入院した後,私は東北地方の,大変よい温泉のある療養所へ行きました。
私がそこにいる間に,戦争は段々と進行していきました。家に帰れなかったら大変なので,私は体が回復するよう一所懸命自分自身をはげまさなければなりませんでした。しばらくして私はようやくびっこをひきながら家へ戻ってきました。運よく私の家は無事でした。”
この時にはすでに日独伊枢軸が結成されており,第二次世界大戦がヨーロッパに始まっていた。日本国内の物資は,何でも戦争目的のために使わねばならなかった。そして,ある航空機製作所の社長がミス高田の所へ来て,学校の建物を彼の会社に売ってくれないかと言うのである。材木はそのまま工場建設に使用するとのことだった。
彼女は語る,“その時提示されたお金は,その後の私の生活を十分まかなってゆけるくらい多額のものでした。それだけのお金があれば,私は病気の養生をしながら暮らしてゆけたでしょう。しかしながら,そのうちにも貨幣価値は変化していきました。お金の値うちは下り,長くは続きませんでした。私は学校にあった種々の道具や家具を入れるのに大きな洋式の家を借りましたが,道具の中にはグランドピアノもあって,私はそれをいつかまた使う日があるかも知れないと望みをかけていました。”
第二次世界大戦は1939年,ヨーロッパに始まった。そして日本は1941年にいわゆる大東亜共栄圏を確立するために……それはインドシナからビルマ・マラヤ・フィリピン・香港そして太平洋の遠くハワイまで続く島々を含めた構想だったが,その軍事目的のために戦争に突入したのである。
日本はこの世界史上最大の統治圏を五ヵ月足らずで,わずか15000の兵と380の航空機と4隻の駆逐艦を失っただけで確保した。1941年12月の真珠湾奇襲は,日本のこの大東亜共栄圏と太平洋の制覇に対し,合衆国の太平洋艦隊が邪魔をしないうちに,それを破滅させようという意図で行われた。この奇襲は日本の意図した如くには成功しなかった。碇泊中の8隻の戦艦の4隻は沈み,他の4隻も大破されたが,3隻の航空母艦は港にはいなかったので,日本軍としてはそれが最大の目的であったにもかかわらず,難を免れた。日本機による爆撃も,火薬庫や修理ドックは破壊できなかった。
日本では,海軍の山本大将が宣戦布告の55分前に真珠湾爆撃が始まったことをきいて,こう言った。“我々のこの行為は眠っている巨人を呼び起こして,恐るべき決意へと追い込んだのではないか。”と。
山本大将は何年か前にハーバード大学を卒業した人である。彼はかつてワシントンで日本の大使館付武官として働いたが,そこで広くアメリカという国を理解し,大いに楽しんだものだった。後年彼が日本軍の幕僚の一員となった時,合衆国の戦争宣伝では彼を無責任な怪物として描き出していた。しかしながら,日本の参謀本部がアメリカ合衆国は国内の政治的分裂により無責任な怪物のようなものであり,強力な軍隊は持ち得ないと言ったとき,彼は決してそれに同意しなかった。彼はその反対を信じていた。彼は,日本が勝つことのできるのはせいぜい一年か二年で,その後は分からない,と言うのだった。
高田敏子は,日本軍が真珠湾で,またアジヤ地区で驚くべき成功を収めたことを聞きながらも,やはり山本大将と同じように疑い,そして憂えていた。かつて彼女が自分の眼で見てきたあの強大なアメリカを思ってみる時,日本がそのアメリカと戦って勝つことができるとは信じられなかった。そうした考えに悩みながら彼女は病の床にあり,しかも自分の生涯の仕事も放棄しなければならない世の状況であった。周りの人々の彼女を見る目も,今や排斥されている英語というものの教師として見る者ばかりだった。戦争が進むにつれて,周囲の人々の疑いと嫌悪の目は厳しくなるばかりだった。
日本軍の緒戦における勝利も追々敗退に変わっていった頃,アメリカ軍の空襲は太平洋の島伝いにようやく日本本土へと近づいて来た。ミス高田は,それ迄とっておいた学校の用具を友人のある校長先生に全部上げてしまった。彼女は家もたたんでしまい,弟と一緒に住むことにした。弟は東京の中心部で歯医者を開業しており,診療所の二階が住居になっていた。彼女は後にこう説明している。“弟は歯医者だったので,東京に残らなければなりませんでした。当時医師は,歯科医師も含めて負傷者の治療に当れるよう,市内に足止めされていたのです。彼の家族はすでに郷里三島の先の田舎へ疎開していました。”
東京が最大の空襲に襲われる二,三日前のこと,保険会社の人が来て,保険に加入することを勧めた。弟は姉に相談したところ,彼女も出来るだけ多額に加入するようにと奨めるので,その通りに契約したのだった。
1945年(昭和20年)三月九日の夜から十日払暁にかけての東京大空襲は凄まじいものだった。爆撃が始まると敏子は弟の寝ていた部屋へ走って行ったが,ぐっすり眠っていたのでその頬を叩いてやっと彼を起した。二人が家から逃れた時,家全体が火に包まれ,そのまま焼け落ちるばかりとなった。周りの建物もことごとく炎の中に燃えさかり,そして崩れていった。この東京に対する絨毯爆撃の被害は数量においても,またその犠牲者の数においても,広島の原子爆弾投下の時を上廻るものだった。
(電子入力者注・広辞苑によれば東京大空襲の死者は約十万人,広島の原爆投下は約二十数万の死者を出した。長崎は約十万人と言われている。もちろん正確な細部の数字はいずれも不明である。)
夜の十時に始まった爆撃は一晩中続いた。目撃者の話によれば,少なくとも300機以上の飛行機が,そうした家屋の密集地帯へ爆弾や焼夷弾を落としたのだった。
幾つかの大きなビルディングは大丈夫らしく見えたので,大勢がその地下室へかけ込んだ。敏子と弟も,他の人々と一緒に避難場所を探していたが,いつか二人ははぐれてしまった。彼女が地下室の階段から外を見ると,通りはすでに火の海となっていて,煙がビルの中へ襲ってきた。彼女は大声で窒息しないうちに早く出なければ危ないと叫んだので,一同はまたそこを逃げ出し,別の場所を探して去った。
敏子がそのビルを出た時,弟が自分の名を呼んでいるのが聞こえた。弟がいたと思ったその時の彼女の喜びは言いようもなかった。その時弟の最初の言葉は,我が家が診療所もろとも皆焼けてしまってよかったということだった。これでもう田舎へ行って家族と一緒に住めるということであった。その夜東京の大部分は壊滅し,一面の煙と灰燼とに化してしまった。
何とかして汽車に乗ろうとすると,そこまで歩くほかはなかったので,二人はほとんど一日中歩いた。敏子はびっこを引きながら弟の腕にすがって行ったのだった。食物と言えば,避難者が落としていったものをやっと食べる有様だった。二人は汽車の割れた窓から列車へ乗り込んだ。家族の者がラジオで東京のニュースを聞き,心配して駅まで来て待っていたのだった。
一方,伯父の尾島眞治のことであるが,彼は今では名の知られた牧師になっており,多くの著書も出していた。ところが,彼の本からは何等印税が入ってこないので,その方からの収入を期待することはできなかった。そのうち当局は遂に彼を投獄し、彼の本の多くは没収されてしまった。そこで彼の妻は産婆をして一家を支え,一家は何年もの間犠牲となったクリスチャンとして暮らしていったのである。尾島牧師は入獄中に看守達に説教をして,その何人かをクリスチャンにした。
焼け出された都会の人々は,それぞれ何等からの手掛かりを求めて田舎の方へ逃れて行った。だが農民達は,こうして焼かれた町から来た人々を“疎開乞食”などと呼んで,あまり親切にはしてくれなかった。町の人達は農民の人達に,食糧を売ってくれるようにと頭を下げて頼まなければならなかった。お金で買おうとしてもなかなか思うように売ってくれず,着物と交換した。町の人達は食糧やその他の必需品を手に入れるために,段々と着物を手離してゆき,いわゆる筍生活をしたのだった。
高田一家は,かつて高田女塾で教えていた女の先生の家に頼んで,一軒の小さな家を貸して貰った。先生をしていた娘さんはすでに亡くなっていたが,家の人は高田一家に大そう親切にしてくれた。敏子は関節炎のため,近くの小さな旅館に泊った。そこは温泉のある旅館で,彼女はよくなろうとして毎日その温泉に浸った。そして普通に歩けるようになるまでには,五年近くかかったのだった。
一家は何の食糧の貯えもなかった。時には山の畑へ行ってお百姓の掘り残したじゃが薯を拾ってきたり,時にはほうれん草の根っこを見つけたりした。ある日弟はボートを一そう都合して貰って釣りに出かけたが,なかなか腕がよく,その日は沢山の獲物を持って帰ってきた。彼はそれを農夫の野菜と交換する計画を立てていたので,姉にそれを頼んだ。 敏子は,それを条件をつけて交換するということには反対だった。別のやり方,つまりもっとクリスチャンらしいやり方があるのではないかと思った。彼女は魚を皆お百姓に上げてしまおうと決心すると,その通りに実行した。するとお百姓達は,野菜だの粉だのその他種々の品物を持ってきてくれたので一家は大喜びだった。弟はその後も釣りに行っては魚を沢山持って帰り,お百姓達はまた食糧を提供してくれるばかりでなく,非常に親しみを以てつきあうようになった。敏子は言った。“私達は仲好しになり,それが一番よいことだったのです。”と。農夫達は敏子への信頼を深め,子供達に教えてくれと頼むのだった。
戦争中日本の宣伝では,アメリカ人は血に餓えた野獣のようであり,子供なんぞ大きな手で押しつぶしてしまうような悪魔だと言っていた。彼等は皺くちゃな毛深い皮膚をした,丁度仏教でいう鬼のようなものだと言った。この山里の農夫達が,こうした宣伝を知っていたかどうかは分らないが,彼等はよく敏子の所へやってきて,戦争のこと,特に敵であるアメリカのことを聞きたがった。彼等は,“もし日本が負けたら,アメリカ人は我々を皆捕虜にして,日本から連れて行ってしまうのではないでしょうか?”と訊くのだった。
敏子は,アメリカはそんな酷いことをする国ではなく,むしろ宗教心の強い国だと言った。たとえ日本が負けたとしても,アメリカ人は日本を取ってしまうようなことはしないだろうし,日本は永久に日本の国として存在するだろうと言うと,単純で素朴な人達は安心して帰って行くのだった。そして,日本の軍部に押さえられて,いつまでも辛い生活をするよりは,早く負けてしまった方がいいかも知れないと言うのだった。
敏子の父は,トルストイの著書を読むのが好きだった。トルストイは消極的抵抗を唱えた人である。何年も前に,まだ日本が戦争をするような状態ではない時のことだが,敏子は父が若い学生や従兄弟の尾島眞治と議論していたのを思い出した。ある時,彼はこう言った。“神の眼で見れば,我々の国など一粒の米粒よりも小さな存在に過ぎない。国の亡びることも神の御心であるならば,それでよいと思う。しかし,この国を誰もかついで持っていってしまうことは出来ない。だから国土は永久にここにあるのだ。”と。その後敏子はこの田舎へ来て,その時の父の考えを,この片田舎のお百姓さん達に話したのだった。
やがて弟は借家の一隅に歯科の診療室を設けた。また,しばらくして高田一家は,温泉地に一軒の小さな家を手に入れた。こうして,いくらか生活も楽になっていった。
敏子の思いは,しばしばアメリカの友達の上に飛んだ。1929年から30年の彼女の在米中に,あんなに親しくなったお友達のことがいつも頭に浮んだ。彼女は何とかして自分が無事でいることを知らせたかったが,それは不可能だった。日本は,今その人達の国と戦っているのである。
ある日,非常に気持ちのよい朝であったが,桜の花が白く咲いている丘に少し霞がかかっているのを彼女は眺めていた。彼女の関心はその美しい風景の上になかった。後になって彼女はこう話した。“あの頃は何だか神が遠くなってしまったような気がしていました。”と。しかし景色を眺めているうちに段々と,その朝の静けさ,爽やかさ,そして雪を被って遠く望まれる雄大な富士の姿に,何か心に希望が湧いてくるのを覚えた。彼女は昔故郷の町で,この美しい山の姿を見て暮らした子供時代を思い出した。その朝,富士を見ながら思ったのは,たとえ世界中が戦争の渦中にあろうとも,神はやはり自然界を美しくして下さるということだった。山が,そう語りかけているように思われたのである。後に,彼女はその時のことをこう説明した。“突然私は,神はやはりいつも私とともにいて下さる。そして私を守って下さるのだということに気がついたのです。私は未来を神にゆだね,神の導きを待ちました。”
戦争はなお続いていた。生活は,ますます厳しくなるばかりだった。敏子の兄弟は,戦争中に二人とも亡くなった。そして一人の妹は空襲の傷がもとで死んでしまった。
ある時,一人の男が敏子の疎開先の住所を尋ね当てて訪れてきた。それは文部省からの人だった。どうやって住所を知ったのかは分からないが,その人の話はこうである。これからシンガポールに開く予定になっている女学校の校長として行ってくれないかと言うのである。そうした仕事には日本語と英語が話せる人でないといけないし,その点で彼女が最も適任なので是非この要請を承知して欲しいと彼は言った。彼女はそれを承諾したのだが,幸にもその学校は実現の運びにいたらなかった。というのは,戦争の状況からもはやシンガポールで学校を開くことは遅すぎたのである。
なおも戦争は続き,第二次世界大戦は世界史上最も烈しい消耗戦となった。身体的な惨害に加えて,道徳の低下は一般市民を,はたまた軍人をも苦しめた。爆撃と火災が,多くの国々の町や都市を次から次と破壊していった。飢餓,流行病,そして家を失った人々,そうしたものが世界中の戦争犠牲者の間に拡がっていった。そして,ついに戦争はみじめな終末に到達したのである。日本ではラジオや新聞や街頭のラウドスピーカーが,もしアメリカ軍が上陸したならば,彼等は軍人たちの首を斬り,女たちを強姦し,子供たちを連れて行ってしまうと警告していた。
やがて,今まで歴史上にかつてなかった天皇自身のラジオ放送が始まったのである。天皇は率直に日本の無条件降伏を告げ,アメリカ軍の占領を受け入れるべきことを話されたのである。その衝撃は,直ちに日本中に伝わった。