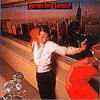
"Before The Daylight"
1988/02/05 release
■ショートコント(笑)から始まりドライヴ感タップリのイントロへと続くオープニングの<I Can Give You My Love>から角松ニュー・サウンド全開です。以下、デビュー当時には聞くことのできなかった大人の恋の物語が延々と歌われていきます。サウンドの劇的な変化に付いていけないファンも続出しましたが(笑)、個人的には大絶賛のアルバムであります。今聞いてもこのオープニングはゾクゾクします。
■時期的に考察して(大袈裟!)、たぶんこのアルバムのツアーと前後して、所属するビクター内に自身のレーベルを設立するという動きがあったに違いありません。ミュージシャンが自分のレーベルを持てる...それは一つの夢であり一つの到達点であるに違いありません。そんな夢の実現に向けて、自身の楽曲の創作というある意味ミュージシャンの根本的な活動がおざなりになっていく...まぁ仕方の無いことでしょうかね。翌年、その夢は遂に実現します。
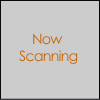
"Breath from The Season"
Tokyo Ensnmble Lab
1988/07/21 release
■そんな活性化のためのアプローチ第1弾がこれ。角松のツアー・メンバーとして参加していたホーン隊の数原晋、小池修らがが所属するTokyo Ensemble Labのソロ?アルバム。以前に自身のフュージョン・フリークとしての指向を満足させるだめに作った「She is A Lady」の隠れ第2弾的位置付けになります。アルバム全体はビッグバンド・ジャズ・アルバムですが、1曲目だけは角松フュージョン全開のナンバーが楽しめます。自身名義のアルバムではありませんが、ミュージシャン角松敏生の活動からすれば、このアルバムのリリースの意味は重要です。色んな楽曲の美味しいところだけ集めて外人さんにソウルフルに歌ってもらった<Mornibg After>は、相当笑えます(^^)。ボーカリストのテイストもほとんどJames Ingramみたいで、こちらも思わずニヤリ。
■この「オーン」の意味は宗教用語で最も神聖な単語なのだそうです。もともと大学で哲学科に在籍していた彼はこうした宗教関係だとかオカルト物?には居見があり、まだ学生だった頃に角松と「金縛りにあったら両手を親指から順番に閉じて、その後で逆に順番に開きながらオーンて言うと解けるんだよ」なんて会話をしたことがありました(本人は忘れていることでしょうけど)。彼が自身のレーベルにこの言葉をつけたと聞いた時に「おいおい」って思いました。で、あまり語られていないんですけど、あの悪名高いオウム真理教のオウムは実はこのオーンのことだったりして...。でも彼がこのカルト教団とは一切関係無いことは断言しておきます。でもオウムが話題になった時に内心「ヤバイ」と彼も思ったことでしょうけど...(汗)。でもこの話はちょっと宗教学をかじったことのある方には常識なんですよね、きっと。私はまるで興味ないですけど。
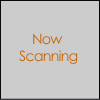
"S/T"
Nob Caine
1989/01/25 release
■80年代前半に終焉したかに思われていた日本のフュージョン・シーンに低迷していた業界に大いなるインパクトをもって受け入れられたと言えるでしょう。大キライ(ほとんど個人的な恨み)な斉藤ノブをフューチャーしているので複雑な思いをもって当時聞いていましたけど...(^^;;;;)。特段なオリジナル曲は収められていませんが、Parachute時代にも演奏されていた<Great Girl>やAllman brothers bandの名曲<Jessica>などの収録には懐かしく嬉しく思いました。ギターの松原氏の個性により、どうもParachute meets kadomatsuみたいなサウンドに聞こえてなりませんけどね...。後にフューチャーされる「はっぴぃえんど」の<そばかすのある少女>をオリジナル・メンバーの鈴木茂を迎えて再演するのは角松の拘りの一端を覗かせているように思います。繰り返しになるのですが、業界での斉藤ノブ氏の地位とか役割とか位置付けって詳しく知りませんが、あのズーズーしい横柄な態度は堪りません。このバンドにしたって、要は角松ツアー・バンドじゃないですか。自分の名前がついてますが、決して自分の手で作ったバンドじゃないと思いますけどね。このバンドのおかげで食っていけたのだから、何だかもっと違う態度というか対応というか、そういうもりがあっても良いと思うのですけど...。スミマセン、ほとんど個人攻撃ですね(^^;;)。ファンの方、失礼しました。でも本当に個人的で恐縮なんですけど、ノブ氏には公の場でものすごく無礼な態度で接っせられたことがあるもので...許してくださいませ。
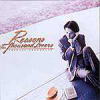
"Reasons for Thousand Lovers"
1989/09/06 release
■1988年4月にオープンした横浜アリーナ。このアルバムのツアーの一環?で角松としては初め(だと思うけど)てのアリーナ・コンサートが行われました。何せ現地からSystem本人を連れてきちゃったんだもの、そりゃお金かかるので大キャパシティの会場でやらないとモト取れませんよね。いやはや生Systemを見られるなんて角松サマサマではありましたが、が、が、何とも音のバランスが悪くて最低(泣)。横浜アリーナの柿落としはYumingのDSLKツアーでした。観客はもちろん音響スタッフだって初めての会場だけに一種異様な緊張感に包まれた雰囲気でしたが、音は最高!。まるでオーディオ・ルームで聞いているようなコンサート音響に愕然としたものでしたが、おいおい々会場かと驚くほどの音響の悪さに、「そりゃYumingとスタッフが違うもの」なんて無責任な感想が飛び交っていましたっけ...。パフォーマンスは負けてなかっただけに、とても残念な記憶があります。
■以前からミーハー的に海に出入りしていた(笑)角松ですが、この頃に至るとダイビングは彼の一部として完全に定着していたようです。沖縄のビーチにいる彼は仲間内にもさんざん目撃されてました。そんな彼が沖縄へのリスペクトとして作った<OKONAWA>。個人的には琉球音階による曲はあまり好きではなかったので、当時はほとんど無視してましたっけ(苦笑)。『After 5 Crash』で<Heart Dancing>なんて題してサブタイトル「あいらぶゆぅ音頭」なんて日本のダンスミュージックに挑戦なんてバカな企画がありましたけれど、ここでのアプローチはそんな軽薄さは感じられません。それでも随所に挿入される「」あいやぁ〜」との合いの手は、今でもやっぱり勘弁してくれって感じですネ。タイトル曲の<Reason...>は改めて聴くと、なかなか心に響きます。

"Special Live '89.8.26 〜more desire"
1989/12/06 release
■このライブで演奏された新曲<Desire>。同じメンバーでスタジオ録音したものとともに2バージョンが収録されています。彼がこの曲を作った背景などは、スミマセン当時のインタビューなどを調べ直して改めてコメントしたいと思います。絶対に何か深い意味があったはずですし...。あれ?角松が結婚して離婚したのっていつ頃でしたっけ??。そして新しい彼女への思いを募らせていったのって、この頃でしたっけ???。...なんでいきなりこんな彼のプライベートな話が突然でてくるかというと、実はこの彼の恋の遍歴(大袈裟...汗)が、実は彼の音楽活動に大きく影響するからだったりして。いずれ追記で...。

"Legacy of You"
1990/07/25 release
女性へのトリビュートも忘れずに押さえている辺りは、相変わらずって感じですね(笑)。
■で、ライナーを読み直しして気付いたのですが、「日本を再認識したい」みたいなコメントがありました。後にリリースされる名盤『インカナティオ』のことと合わせると実に興味深いコメントに読めました。三味線の高橋竹葉?とのコラボレーションなど、まさにインカナティオとの関連を意識せざるをえません。とは言ってもその間12年って、余りにかけ離れすぎていてどうも...って気もしますがね。