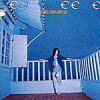
"SEA BREEZE"
1981/06/06 release
■待望のデビューアルバム。超豪華なバック・ミュージシャン。当時人気のParachute隊に村上ポンタ秀一、後藤次利、佐藤準、Epo、Buzz、Jake H Conceptionなど当時の一流どころを揃えてのレコーディングには本気で驚きました。曲調は当時流行のシティ・ポップ。山下達郎の二番煎じと揶揄されたけれど、達郎が60年代のフィラデルフィア・サウンドをバック・ボーンとしていたのに対して、角松は完璧80年代指向の7thテンション・コードとシンコペーションを多用したコンテンポラリー・サウンドと似て非なるテイストがあったことに気付く人は少なかったようです。さらに性質が悪いことに、当時聞いていた音楽が似ていたようで、同じアルバムに影響されて曲を作ったと思われるふしがあります。すると方や人気のポップ・シンガー、方やポッと出の新人としいうことで、世間は見方を誤ってしまいますよね。しかし夏・海・太陽...当時の学生はこんなことばかり考えていたって、今思えば懐かしい世相。<Wave>の前の波の音のSEに気恥ずかしさを感じつつも、私自身の趣味とバッチリ合う「こんなアルバムが聞きたい」って音を実現してくれた仲間の出現に心から応援したいと思った。
■実は角松はサークル内ではほとんど歌ったことが無かった。デビューが決まったとの話が伝わってきて、「ギターだけでデビューって?」とちょっと驚き、歌うと聞いて「角松って歌えるの!」と仲間は全員もっと驚いた。今から考えると笑えるけれど紛れもない事実。さらにもう一つ驚いたのは本人がレコーディングでギターを弾いていなかったこと。ご自慢のGibson335を抱えてスタジオ入りした角松は「君は良いギターを持っているね」の一言で片付けられてしまったとか(^^;;)。サークルのNO.1ギタリストがその程度の扱いだとは...プロの世界は厳しいなと実感しましたね。デビューのきっかけとなった名曲<Still I'm In Love With You>のデモテープはサークルの各パートNo.1ブレイヤーが揃えられて録音されたもの。この曲のモデルとなった娘の顔が浮かぶなんて...ちょっと複雑な気分(^^;;)。この曲を聴くとAirplayの<Should We Carry On>が聞きたくなるのは何故?(激爆)。当時仲間と吉祥寺で飲んでいて帰れなくなり角松家に深夜おじゃましたことがあった。夜中だというのに息子の友達が来たということで、つまみやお酒を出してくれた優しいお母様。当時はまだ珍しかったビデオで「歌う天気予報」に出演した時の角松の映像を見せてもらった。その間、角松の部屋ではきちんと整理されたビニ本に狂喜していた連中もいた(笑)。あまりレコードがたくさんあるって感じの部屋ではなかったような...。
■デビューのきっかけとなったビクターのオーディション大会。角松が参加した翌年の東京地区予選の決勝大会のゲストとして出演。アルバムが出てから中々ライブを見る機会が無かったので、サークルの仲間と高田馬場ビッグボックスのビクターのイベント・スペースに見に行った。アルバム1枚じゃステージが作れないと、まだ未発表だった<Office Lady>やサークルの先輩のオリジナル曲<小粋>などを含めて30分ほどのステージだった。サークルの発表会を見いてるって気分になりました。

"Weekend Fly to the Sun"
1982/04/21 release
■1stアルバムが大学生を含む若者全体を対象とした作品だとすれば、こちらは完全に社会人やOLをターゲットとしていると言えるでしょう。ライナーで角松自身が語っているように、青臭いけれどある意味で純粋な学生よりも、ある程度社会の裏表を見聞きしていきて、それでも自分の大切な何かを探すという、世代的には多少背伸びした感覚への憧れに溢れているということなのかもしれません。まぁ彼の制服好きは有名な話ですから、OLさんの制服姿にクラクラきても仕方ないかもしれませんけど(^^;;;)。
■肝心のサウンドは、時代のコンテンポラリー感覚満載。あれはこれ、これはそれと、元曲が続々と浮かぶのはご愛嬌(笑)。でも当時は本当にこんな感じの曲が流行っていたんですよ。そして一つ注目、2作目にして念願かなって1曲だけですがギタリストとして本人の名前がクレジットされています。でもどのフレーズだろうって感じで地味ですけど...。それと今でもバンドメンバーの中核をなすキーボードの友成さんもクレジットされています。しかし、インナーに写っているボーダー・シャツ着て指を咥えている本人の写真は何とかならないものでしょうか(笑)。時代といえばそれまでですけど...(^^;;;)。
■当時のセールスプロモーションの主流はCMタイアップ。今も健在な手法ですが、当時はまだその走りで、タイアップが付けばヒットは確実...そんな方程式が生きていた時代といえます。当時はまだ流行の最先端だったリゾートの雰囲気にマッチしたテイストからJALの沖縄キャンペーン・ソングに決定していたのにもかかわらず、羽田沖への逆噴射墜落事故による同社のCM活動自粛のアオリを受けて、敢え無くお流れ...。角松のメジャーへの道が閉ざされた瞬間でもありました。彼の沖縄へのリスペクトはまだ早いとの導きだったのかもしれません。後に壮絶なリベンジが行われようとは、神ですら思わなかったでしょうけど...。
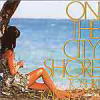
"On The City Shore"
1983/05/21 release
■そんな彼が、やっと自分の演りたい音を自分で作ることができた...それがこの『On the Cith Shore』です。もちろんセルフ・プロデュースで、自分で目にかけてきた日本の若手ミュージシャンを中心に、実力派スタジオ・ミュージシャン達で脇を固めた入魂の作という感じです。中でも後までも角松バンドの要となる青木智仁は、このアルバムから初参加です。青木氏を発掘したおかげで今後の角松の方向性は、シティポップスから和製ダンスミュージックへと傾倒していきます。いずれにせよ実際に「本当に演りたい音ができた」かどうかは別としても、そんな環境に自らを置くことができた...それは彼にとって幸せだったと思います。よき理解者に恵まれて....。彼のデビュー20周年記念ライブの幻となった初日のゲストの杏里の名前があったのは、特別な思いがあったものだと思います。
■時代の空気を敏感に感じていた彼に注目したのは音楽ファンだけでなく、シングル盤の<Sky High>は、当時はまだ元気のあった?ワーナー・ランバード社の髭剃り「Schick」のCMソングとして採用されてスマッシュ・ヒットとなりました。青い海原を飛ぶ真白のスカイダイバーの姿は爽やかそのもの。印象的なCMでした。悲劇的なタイアップ流れをたった1枚のアルバムで見事に挽回するのはサスガって感じ。でもこの雰囲気はまさに当時の時代性を感じますね。
■楽曲によっては特定の女性に捧げる...みたいなスタイルと、裏ジャケットでサーフボードを抱えた姿を見せるなど、「軟派なヤツ」との印象を徹底的に植え付けて(笑)、一部男性ファンからはひんしゅくを買ったものの、自身の音楽性を活かした和製ダンス・ミュージック路線は純粋な音楽ファンからは支持され始めたと言える気がします。ちょっとハネたシティ・ポップス...同種の音楽を聞かせていた山下達郎と、ルーツの部分では重なるものの、一線を画した指向は、実は現在の彼の音楽性にも見え隠れする部分だったりします。ラストを飾るバラード<Let Me Say...>などは、彼の敬愛するLuther Vandrossを彷彿とさせたかったと覗えます。
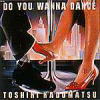
"Do You Wanna Dance
/ It's Hard to Say Goodbye
/ Fly-By-Day" (12inch Single)
1983/10/21 release
国分はその後数々のセッションで引っ張りだことなり、角松も所属していたAirレコードより数枚のソロアルバムをリリース。現在では山下達郎のツアーメンバーとして欠かすことのできない存在として活躍中です。またキリスト教関係のアルバムを旦那とともに制作するなど、充実の日々を過ごされています。この時期、角松と付き合っている?なんて噂も立ちましたが(笑)、この時に彼の毒牙にかからずに本当に良かったですね(爆)。After 5 Crashのツアーの時にゲストで彼女も来ていて、角松に紹介されて客席からスッと立ち上がり舞台に上がり、ベタベタのバラードを熱唱した後に、何事も無かったかのように背筋をスッと伸ばしたまま舞台袖に引いた彼女の姿は、強烈に印象に残っています。

"After 5 Crash"
1984/04/21 release
■先の12インチで参加した国分友里恵はこのアルバムでもコーラスで大活躍。中でも半インスト?で当時としてはまだ珍しかったRapを大胆に導入した<Step into the Light>やタイトル曲の<After 5 Crash>などでは、彼女の澄んだ美声が響いています。
■<Do You Wanna...>での話の続きですが、こうしたダンス・ミュージックへのアプローチを深めていった角松でしたが、まだこの時期は、その主体をまだシティ・ポップスに置いていて、あくまでアルバム全体のバリエーションの一環としてブラコン的な曲をおいている...そう感じます。こうしたある意味でのクロスオーバーな展開の中で、角松サウンドのオリジナリティが段々とカタチ作られている、まだまだ成長途上だけど期待度抜群...そんな感じでしょうか。
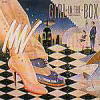
"Girl in the Box
/ Step into the Light" (12inch Single)
1984/11/21 release
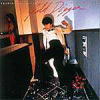
"Gold Digger"
1985/05/21 release
■そんなダンス系のサウンドに耳をとられていていはいけません。このアルバムでもっと注目しなければならないのは、角松ポップスがある意味で成熟期を迎えているという点です。<Melody For You>や<Mermaid Princess>、そして<No End Summer>の存在です。デビュー当初の角松は、しょせん達郎ポップスの二番煎じという地位に甘んじていました。それでもここにきて明らかにバックボーンの違う、角松ならではのポップスが見えてきます。<Mermaid...>などは曲調は3rdの砂浜の未亡人と同じですが、一味も二味も違うこなれたメロディ・ラインをこの曲では聞かせていますし、叶わぬ恋を壮大に歌い上げる<It's Too Late>、そして永遠の夏を歌う<No End...>。いずれも見事なほどの角松節です。次に向かうべき方向性が見えてきたからこそ、そんなオリジナリティ豊かな「自分の曲」が書けるようになってきた...そう思えてなりません。この時期のポップス曲は鳥肌モノの出来だと断言しましょう。
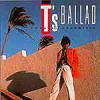
"T's Ballad"
1985/11/21 release
そしていきなりの<Still I'm in...>。この曲こそ彼のデビューのきつかけとなった曲だし、思い入れの一番ある曲。そしてそのオープニングを何と吉田美奈子にソロで歌わせるなんて...。初めて聴いた時に思わず嬉しくなってしまいましたよ。山下達郎と吉田美奈子の関係は、単にシンガー&プロデューサーと、コンポーザー&バックミュージシャンの関係ではありません。お互いがお互いを高め合い、深め合っているという傍で見ていて羨望の的。そんな美奈子の起用を、角松はジッと待っていたに違いありません。そして満を持して起用した曲が<Still I'm in...>だったなんて。デビュー仕したての頃に、こんなミュージシャンと一緒にアルバム作りたい...と言っていたNo.1とのコラボレーションがようやく実現した、納得の1曲といえるでしょう。
■例えばLPとシングル、オリジナル盤とコンピ盤。ファンからすれば、そのミュージシャンの出すアルバムは欲しいけれど、テイクもバージョンもまるで同じ曲を何曲も買わされては堪ったものではない...音楽ファンでもある角松自身は常々そんなことを言っていましたっけ。で、自分が出す場合も...当然、同じものは極力避けるという基本方針は貫かれていました。コンピ盤とはいえほとんどの曲を新録・リミツクス、パートの差し替えなど手を加えています。ある意味で、リリース時点では妥協したものを納得するカタチに直しておく作業...これって、達郎もよくやることなんですよね。
スチューワーデス(制服)好きな角松だけでなく(^^;;)、当時の日本を震撼させたJAL123便の乗客に捧げた<Ramp in>は何度聴いても涙を誘います。そういえば彼のデビュー20周年記念の野外ライブの折に、ちょうどこの曲を演奏する前にJAL機が上空を横切ったのには驚きました...。
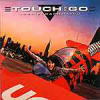
"Touch and Go"
1986/06/11 release
■次期角松サウンドの主流となるNYファンクに乗せる自分のメロディも見えてきて、<Lucky Lady...>や<Pile Driver>などはかなり余裕のスタンスでダンス・ナンバーを作っているように感じます。一方でホーン・セクションを効果的に用いた<1975>や<Best of Love>などは実に心地よいナンバー。ダンサブルでメロディアス...第1期角松ポップスが、ここに極まれりというところです。

"T's 12 inches"
1986/12/15 release
12インチ・シングルという新たな表現手段を究極まで追い求めていく当時の角松は、創作意欲に充ち溢れていた時期なのかもしれません。
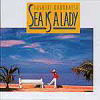
"She is A Lady"
1987/07/01 release
全編インストによる角松風フュージョン・アルバムの制作を遂に実現します。ギターは当然自分が演奏するとして(^^;;)、他のメンバーはまさに使い放題で、村上ポンタ秀一、ベースにはカシオペアの桜井哲夫と高水健ニ、キーボードに天才・佐藤博、他にホーンセクションも贅沢に導入するなど、まさに角松のイメージする究極のジャパニーズ・フュージョン・アルバムがここに完成します。
一連の「まとめアルバム」制作を受けて、角松の音楽的なキャリアもいよいよ第2ステージに突入か...そんな予感が広がる中で、期待を上回る新作が着々と準備されていきます。シンガー、コンポーザーとしてだけでなく、ギタリスト角松を120%アピールする1枚といえるでしょう。元々はギタリストなんですけどね...。