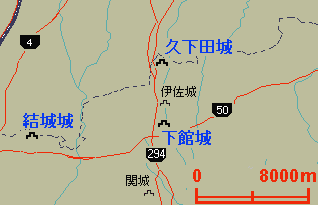
隣の茨城県の城です。 小山氏の分家であった結城氏の城は小山城と距離的にも近く、現在は栃木県と茨城県に別れているものの街道1本で両城が結ばれています。 結城の東隣にある下館は、藤原秀郷が平将門の乱の備えで下館、中館、上館の三館を築いた伝承があり、それぞれ下館城、伊佐城、久下田城へと変移します。(伊佐城は陸奥南朝の城2で紹介)現在では特記すべき遺構はありませんが、下館市の由来になった三館の存在には興味深いものがあるのだ。 下館城は、結城家再興の時に結城合戦の功により領地を分け与えられた水谷氏よる築城で、戦国時代の水谷蟠竜斎正村の手腕により、結城家から独立した大名の地位を確立します。
| 1つ前に戻る | ホームへ戻る |


