


 |
 |
 |
|
両脇の”文字ロゴ”をクリックすると、夫々詳しい説明のページが出ます。 | ||
◆5千円札でお馴染みの新渡戸稲造の、「武士道」が発刊して100年になり、郷土盛岡で「新渡戸基金」が
設立されているとの情報が友人相原氏よりあったので、本を借り調べて見ました。
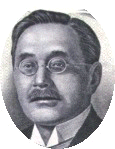
◆稲造は1862年江戸時代の南部藩の武士の子として盛岡で生まれた。
悲運に合いながらも、勉学にいそしみ、札幌農学校・東大などで勉強し、「太平洋の橋になりたい」
と言って、アメリカにわたり、大学で経済学や農政学を学んだ。
妻のエルキントンさんとはそのときに知り合った。
平和を願う国際学者として、国際連盟事務局長や太平洋問題調査会理事長として活躍し、
病気のため、カナダで72歳の生涯を閉じた。
◆渡米中に、ベルギーの法政学の大家ド・ラヴレーに「日本では宗教教育がなされていないのはなぜか、
道徳教育はどうしているのか」
◆少年時代に学んだ道徳教育は、自分の中で善悪・不正の観念を分析してみると、
武士の子として学んだ「武士道」であった、と述べている。

◆日本の「武士道」は桜と同じ日本固有のもので、道徳的な掟であり、それを守り、
行うことを徹底的に教育されてきた。武士は名誉と待遇を受けており、
その行動を律する理念であり、基準であった。
武士の教育はその品性を確立することに重点がおかれていた。
◆聖書のみならず、西洋の思想家などの説も縦横に引用し、日本人を理解してもらうため、
広く論述している。
◆38歳の時に英文で書かれたこの著書は、その後フランス語、ドイツ語など
10ヶ国語余に翻訳され、ベストセラーとなっている。
◆下記に相原氏のコメントや、小生がまとめた「武士道」の紹介が、
別ページにあります。ご覧下さい。
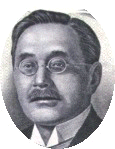

★新渡戸稲造博士が38歳で上梓した「武士道」が昨年発刊百年目を迎え、全くのロングセラーとなっている。
新渡戸博士は、「願わくは われ 太平洋の橋とならむ」として東西文化の交流に努力された
近代日本における国際派の一人であるが、その英文著書「武士道」・副題(日本の心)も、つとに有名である。
この著書は、武士道の淵源を中心としてその内的な規範・倫理の書となっているのだが、
その執筆のきっかけは、若き時代に会ったベルギーのある法学大家との対談の中で、
「日本の学校には宗教教育が無く、宗教教育無しでどうして道徳教育をすることが出来るのか」との問いに
答しえなかったことへの答えとしたものであると本人が述べている。
★そして、この本は多くの米国人にも読まれ、特に当時のルーズベルト大統領を感激させ、
日米協調の歴史的扉を開いた名著となったと言われており、広く各国語にも翻訳され世界の人々から読まれ、
一世紀にわたるロングセラーとなったものである。
★ところで今の日本は、贅沢で豊富な食、そして多くのモノに囲まれ暖衣飽食に明け暮れ気持ちが弛緩して
しまっている。 国家や民族としての将来に心を用いることが少なくなり、政治も外交も民間も無責任と無秩序に
囲まれてしまっており、 このままでは国家衰亡の兆しさえ予感させるものがある。
経済大国という国家としての一つの目標を達成したことが、結果して次なる国家目標を喪失させて
まったということだろうか。
★二十一世紀のわが国の将来を想い、経済活動にのみ意を用いるのではなく、次の世代のために
精神文化的遺産をもあわせ残すよう、軟弱化した我々国民の心の筋金を入れ替えるべく、先覚達が残してくれた
事績を改めて振り返ってみる必要があるのではないだろうか。今もう一度「武士道」を読み返してみることが
められていると思う。
★ところで、新渡戸博士の出身地盛岡市には、氏の遺徳を顕彰しその精神の継承を目的として
「新渡戸基金」が設立されいる。
ついでながら基金の宛先は、下記のとおりです。
財団法人 新渡戸基金
盛岡市内丸2−10 テレビ岩手 1F
TEL 019-654-3279