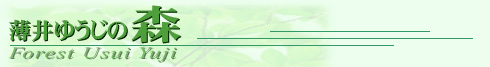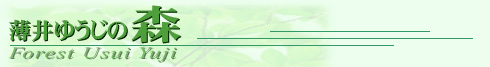|
ある豪雨の午後、僕は出来上がった仕事を封筒に詰めて郵便局へ向かった。今日じゅうにこれを速達で送らなければならないのだ。強い風雨のなか、傘をさして大通りを渡り、郵便局に着いたときには、びっしょりと濡れていた。セーターの下に隠し持った茶封筒は濡れずに済んだけれど、狭い郵便局内に入ったときは眼鏡は湯気でくもり、ズックはたっぷりと水を吸いこんでいた。
速達の料金を計測してもらい、宛名に抜けていた郵便番号を調べているときだった。ほかに客のいない局内に、誰かが入ってくる気配がした。顔を上げる前に、僕にはすぐにわかった。あのハイヒールの音だった。もちろん靴ははき替えるだろうけれど、歩きかたの癖は替えることはできない。彼女だった。
僕は無意識に時計を見た。一時四十二分。いつも彼女がここへ立ち寄る時間だ。そのことをさっきまでは覚えていたはずなのだが、郵便物を出すことで頭がいっぱいになり、つい忘れてしまった。この仕事は遅らすわけにはいかないのだ。誓って言うけれど、僕はわざと時間を合わせて郵便局で待っていたわけではない。
彼女は窓口で切手を買った。それを使って手紙を投函するわけでもなく、一枚の切手を手に持つと、そのまま郵便局を出ていった。僕は書き終えた封筒を窓口に預けて、すぐにそこを出た。彼女は郵便局の出口に立って、雨雲の空を見上げていた。
「ひどい降りね」
そう言ったのは、彼女のほうだった。まるでずっと以前からの知り合いに声をかけるみたいに、さり気ない言いかただった。
−−僕を待っていたのだろうか。
そんなふうにも感じたけれど、あり得ないことだ。見ると、彼女は傘を持っていなかった。淡いブルーのレインコートに、しっかりと身を包んでいる。レインコートだけのほうが、今日みたいに強い風雨の天候には有効なのだろう。そう思ったけれど僕は、彼女に声をかけた。
「傘に入っていきませんか」
彼女はにっこりと微笑んでから、首を横に振った。そして嵐など意に介しないというように、雨のなかへ。そのまま通りをゆっくりと東へ歩いていく。足音は遠ざかり、あたりは雨の音だけが支配している。彼女の姿は間もなく、吹きつける大粒の雨と水煙で見えなくなってしまった。それでも僕は郵便局の前にぼんやりと突っ立ったまま、はげしい雨音の合間からかすかにハイヒールの靴音が聞こえてくるような気がして、じっと耳を澄ませながら、さっき間近に見た彼女の顔をもういちど思い浮かべていた。
思った通り、美しいひとだった。 |
|