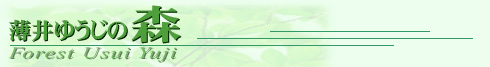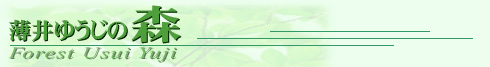|
その電話を朝からずっと待っていた。呼出音が鳴ったのは昼過ぎで、受話器をあげると男の声が興奮気味で言った。
「あなたがドードー鳥の飼育係に選出されました。おめでとうございます」
電話のむこうで何人かが拍手をする音が聞こえる。僕は緊張しながら、「謹んでお受けします」と答えた。
「つきましては明日、動物園まで来ていただけますでしょうか?」
電話の主は丁寧な口調で言った。はいお伺いします、そう答えながら僕は体が震えてくるのがわかった。ついに、ドードー鳥の飼育者に選ばれるという幸運に恵まれたのだ。
動物園は、地下鉄の駅からすこし歩いたところにあった。入口で名前を告げると、無料でなかに入れてくれた。象舎前の広場には紅白の幕が張られていて、そのなかで表彰式とパーティが行われた。僕は何人ものひとから、おめでとう、と声をかけられ、そのたびに握手を求められた。それは、とても名誉で晴れがましい瞬間だった。
パーティが終わったとき、ヤマシタナオミという女性が声をかけてきた。彼女は動物園の職員で、明日からはじめるドードー鳥の飼育について説明したいからと、僕をドードー舎の前に案内した。
「ここがあなたの仕事場です」
彼女は鳥の飼育に必要な用具の置き場所とその使用方法を丁寧に説明してくれたあと、ドードー舎の出入口のところへ行って、扉の開閉方法について話した。
「非常に臆病な鳥ですから、鉄扉の開閉は静かに。不用意に開けると逃げてしまいます。扉は薄めに開けて、その隙間から体を滑りこませてください」
そう言って彼女は、扉の隙間からケージのなかに入ってみせた。せまい隙間を横になって通るとき大きな乳房がすこし引っかかったが、彼女は見事にすり抜けてみせた。
「簡単でしょう?」
ケージのなかから得意そうに僕を見ている。ドードー舎は半円形で、広さはテニスコートくらいある。だが細い鉄柵に囲まれたケージのなかには砂が敷き詰めてあるだけで、何も入っていない。
「あの……。ドードー鳥は、どこにいるんでしょうか」
「え?」彼女はとても驚いたような表情をした。僕がものすごく猥褻な言葉を発したとでもいうように、ぽかんと口を開けてこちらを見ている。「あそこにいるでしょう。いま、草をついばんでる」
指をさすほうを見たが、そこは砂地にわずかの雑草がつんつんと生えているだけで、生き物の気配はなかった。
「見えませんけれど」
「そんな……」彼女は一瞬動きをとめると顔をこわばらせて、「いまそっちへ行く、何もしゃべっちゃだめ」と言った。
ドードー舎を出てこちらへ回りこんでくると、僕が掛けているベンチのとなりにすわって、彼女は諭すように言った。
「ドードー鳥が、絶滅した鳥だっていうことは知ってるわよね」
「もちろん」と僕は言った。「十七世紀にマダガスカルのマスカリン諸島で、船乗りの食料として乱獲されたために絶滅した。現在は、その標本さえ残っていない。ドードー鳥飼育者選抜試験の問題にも出ましたから」
「さすがに暗記してるのね。だったら、鳥が見えるはずでしょ」
「見えない」僕は正直に言った。「砂地と、それを囲った柵があるだけじゃないですか。ドードー鳥は飛べないから、天井は要らないんでしょうけど」
「あのねえ、イチハシくん」彼女は僕の名前を言った。僕と同じ三十歳くらいだろうか、不満そうに唇を突き出して、子供っぽい表情をしている。「絶滅した鳥を飼育するのは名誉でもあるけれど、とても難しいことなの。見えないなんてあなたが言えば、みんなは不安になる。じきにあなたにも見えるようになるから、心配しなくてもいいのよ」
「そうでしょうか」
「すこしずつ慣れていく以外にないわね。わたしがしばらくついていて、教えてあげる」
彼女は、ドードー舎のすぐ横にある飼育者用の小屋に僕を案内した。小屋のなかには事務机と清潔なベッドが置いてあって、とても快適そうだった。そこが僕のこれからの生活の場になるのだ。窓の外には、すぐそばにドードー舎の入口が見える。
「ここなら二十四時間態勢で、ドードー鳥の飼育ができる。がんばってね」
そう言ってナオミは小屋から出て行った。ひとりになって僕は飼育小屋の窓から、がらんとしているドードー舎をぼんやりと見つめた。飼育係に選ばれたのはとてもうれしいけれど、僕は自分がドードー鳥が見えない体質だなんて思いもしなかった。鳥が見えなければ、ただの空き地の管理者みたいじゃないか。いつかは見えるようになる、ナオミが言った言葉を信じる以外になかった。 |
|