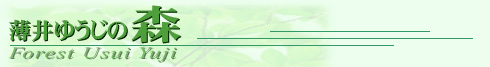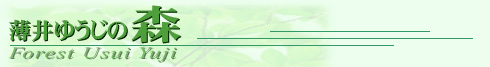|
ドードー鳥がいなくなってしまったのは、夏の終わりの暑い日だった。その日僕は朝から、なんだかむしゃくしゃしていた。何もいない鳥小屋の清掃なんかしていられるかという気持になって、掃除用のモップをぶんぶん振り回したり、散水器で思いきり水を撒いたりしていた。おかげでモップの柄は取れて、ドードー舎のなかは水浸しになった。
だけど誰が困るわけでもない、どうせ鳥なんかいないのだから。そういう気持が強くなっていた。つい昨日までは見えない鳥を見ようとし、聞こえない鳴き声に耳を傾けようとし、必要があれば見学者たちにドードー鳥の説明までしてあげていたのに、そういう一連の作業が、急に馬鹿ばかしくなったのだ。
僕以外のひとには鳥が見える、そのことを容認できないわけではない。みんなにとってドードー鳥はたしかに存在するのだろう。だが僕はいま、自分には鳥が見えないという事実さえ、誰にも打ち明けられない。そういう自分に対する怒りが突然噴出して、押さえきれなくなったのだ。なんだって見えもしない鳥を気にして、ケージの扉を薄目に開けてその隙間から体を滑りこませたりしなきゃならないんだ。僕は扉を大きく開け放しにしたままモップを振り回し、心ゆくまで砂地に散水した。いちど、やってみたかったのだ。
ドードー鳥が逃げたことに気づいたのは、午後になってからだった。たいていは朝のうちに掃除をすれば、昼過ぎには数枚の羽毛といくつかのふんが地面に落ちているのだが、午後になっても地面には何ひとつ落ちていないし、足跡も見あたらなかった。こんなことは、はじめてだった。考えられることはひとつ、ドードー鳥は逃げてしまったのだ。
幸い−−と言うべきだろうか、入園者たちはまだそのことに気づいていないらしく、ドードー舎のまわりに集まって、なかを覗きこんでいる。鳥がいないのを不審に思って騒いだりしないのは、どこかで眠っていると思っているのだろう。見物人はしばらくケージのまわりを歩いてから、あきらめたように立ち去っていく。誰も写真を撮ったり、指をさして歓声をあげたりしないところを見ると、やはり逃げてしまったに違いなかった。
困ったことになったと思った。ドードー鳥を逃がしたのは僕なのだ。しかも僕は、ドードー鳥の飼育者だ。鳥がいなければ、僕はここに存在する理由さえなくなってしまう。鳥と僕はそういう関係であることを、いまさらながらに思い知らされた。ナオミや動物園の管理者たちに見つからないうちに鳥を捜し出して連れ戻さなければならない。だが見えもしない鳥を、この広い動物園内で、いったいどうやって捜し出せというのだろう。
僕はドードー舎を離れて、とりあえず駝鳥のケージのところへ行ってみた。駝鳥を選んだことにさして理由はないのだが、なんとなく駝鳥はドードー鳥のイメージに似ている。もしかしたら仲間だと思って近くにいるかもしれない。だが駝鳥は大きな目で僕を不審そうに見るだけで、新しくやってきた変な恰好の鳥と話をしている様子はなかった。ほかの鳥舎もくまなく見てまわったが、鳥が闖入者に驚いたりしている様子はない。僕はさらに、絶滅しそうな動物を中心に見てまわった。絶滅という仲間意識が働いて、彼らにかくまってもらっているかもしれないからだ。だが、そこにもドードー鳥はいなかった。
僕は入園者の順路にしたがって、すべての動物小屋を見てまわった。二時間かけて園内をすっかりまわり終えたが、やはりドードー鳥の姿はなかった。もっとも、もともと見えもしないものを捜すのだから、やっかいな話だ。草むらに隠れているかもしれないと思って覗いたりもしてみたのだが、なにもそんなところに隠れていなくても、僕には見つけられないだろう。たとえドードー鳥が観覧車に乗って手を振っていたとしても、僕は気がつかないはずだ。こんなことで、よくいままでドードー鳥の飼育者が勤まったものだと思う。
「どうしたの、こんなところで」
オットセイのプールをぼんやりと覗きこんでいたとき、ナオミに声をかけられた。彼女は動物の世話もするが、日祭日は団体の入園者のツアーガイドをやっている。三十名ほどを引き連れて、動物の説明をして歩くのだ。いまも小旗を持って、そのあとに人びとがぞろぞろついてきている。
「みんなオットセイなんかより、早くドードー鳥のところへ連れて行けってうるさいの。
順番にまわりますからって言うのに。相変わらず人気なのねえ」
「それが……」と僕は口ごもった。どうせばれることだ。「今朝、逃げたんだ」
「ドードー鳥が?」
「しっ」みんなが、ナオミと僕を見ている。「さっきから捜してる、見かけたら知らせてくれないかな」
「騒ぎになるわ……。天然記念物が逃げたどころの騒ぎじゃなくて、絶滅したドードー鳥が逃げてしまったのよ」
「逃亡鳥、だな」
「つまらない冗談よして。よく平気ね」
「平気じゃないから、こうして捜しているんじゃないか。観覧車も捜したけど、乗ってないみたいだった」
「あきれた」彼女は声をひそめた。「とにかく注意しながらまわってみる。このひとたちには、ドードー鳥は病気だとかなんとかうまく説明しておくけど、ほかの入園者はどうするの。いまごろドードー舎の前は、大騒ぎになってるかもよ」
「僕がなんとかする」その場を離れようとして、僕は彼女に訊いた。「ドードー鳥の捕まえ方、知っていたら教えてくれないかな」
「知らないの?」彼女は冷たい表情で僕を見た。「全速力で追いかけて、手で押さえるのよ」
|