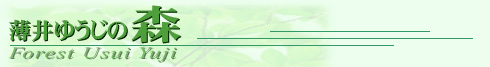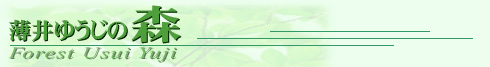|
落ちている羽毛とふんの量は増えつづけ、それに比例するようにドードー舎の前にやって来る見物人の数はすこしずつ増えていった。あの最初に来た家族を皮切りに、翌日は若い男女がやって来た。恋人同士とは、こうあらねばならないというように、ドードー舎の前で楽しげに語り合い、ドードー舎を背景にして記念写真を撮って帰っていった。そして一週間後には、近所の幼稚園児が団体でやって来た。彼等はスケッチブックを広げると、ドードー鳥の写生をはじめたのだった。昼下がりにドードー鳥の絵を描く。幼稚園児は、かくあらねばならない。ひとはなべて、ドードー鳥の前で楽しく時間を過ごすのだ。
僕は有頂天だった。ドードー舎のまわりには開園から閉門時まで、ひとが絶えることがなくなった。僕はこのときほどドードー鳥の飼育係になってよかったと思ったことはなかった。半年前、電話口で言われたあの言葉は、いまのためにあるのだ。おめでとう。僕は自分にねぎらいの言葉をかけた。絶滅した鳥の飼育という未知のものに取り組んでからわずか三箇月で、その成果が現われはじめたのだ。これは、快挙である。
「ずいぶんひとが集まるようになったわね」ナオミもドードー舎の人だかりを感心したように眺めている。「やっぱりイチハシくんには、ドードー鳥飼育の才能があったのね。わたし、はじめからそう思っていた」
「でも……。僕にはまだ、ドードー鳥が見えないんだ」
ナオミは驚いたように僕を見た。それからドードー舎のほうにちらりと目をやってまた僕に視線を戻すと、
「またあ」と言って笑った。「三箇月前なら本気にしたけど、だめよ。ドードー鳥はイチハシくんに、とてもなついているみたいね。ケージ内の掃除をしているとき、イチハシくんのあとを、ひょこひょことついてまわっているもの。ねえ、どうしたらあんなにドードー鳥を手なずけられるのか、こんどわたしにも教えてくれない?」
ドードー舎のほうで歓声が起きた。ドードー鳥が何か、面白い仕草でもしたらしい、みんなが一点にカメラを向けて、いっせいにシャッターを切っている。
「ねえ、見て見て。可愛いわねえ」
ナオミがケージのほうを見て声をあげた。僕は黙ったまま、何もない砂地をぼんやりとながめているだけだった。
|
|