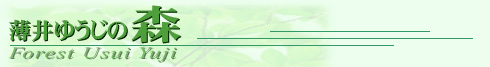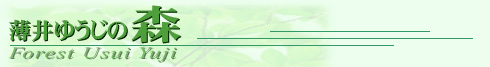| 『動物園内、ドードー鳥飼育係のお兄さんへ。お兄さん、こんにちは。ぼくはドードー鳥が大好きです。お兄さんは毎日ドードー鳥のお世話たいへんですね。ぼくも大きくなったらお兄さんのようなひとになりたいと思います。さようなら』
たどたどしい文字のファンレターが届くようになったのは、そのころからだった。僕はその手紙の、『お兄さんのようなひとになりたい』という部分を何度も読み返した。いったい僕はどんなひとなのだろう、そしてなぜドードー鳥の飼育などをはじめたのだろう。そういうことが皆目わからなくなっていた。手紙の主にとって僕は、何らかのあこがれの対象であるらしいことはわかる。それは僕への憧憬ではなく、ドードー鳥に対しての思いであることは間違いないのだが、僕もドードー鳥のあこがれの部分を、何パーセントか享受しているのだ。
ファンレターは、一日に二通くらいずつ舞いこんだ。宛名は、
『ドードー鳥飼育係のお兄さんへ』
『ドードー鳥のお兄さんへ』
『ドードー鳥さんへ』
と、変化していった。つまり、なんだか僕自身がドードー鳥になっていくみたいで変な気分だったが、僕は手紙のひとつずつに、丁寧に返事を書いた。
『お手紙ありがとう。ぼくは毎日元気に楽しく動物園で暮らしています。きみはどうかな。きみも元気でお友達と仲良く遊んだり、勉強したりしてくださいね。そしてときどき、ぼくに会いに来てね。待ってるよ。ドードー鳥より』
そんなふうにして、僕は毎日何通かのドードー鳥宛ての手紙を読み、ドードー鳥の代筆をした。そんなことをしているうちに僕とドードー鳥との境目がなくなってしまうんじゃないかと怖れたが、そういうことは起こらなかった。絶滅した鳥とこの僕が同化するなんて、とても考えられないことだからだ。
手紙の量は増えつづけた。鳥の世話と同時にファンレターの整理にも追われる忙しい日々がつづいたが、それはドードー鳥飼育の楽しい一面でもあった。
だが、相変わらず僕はドードー鳥の姿を見ることはできなかった。鳥は、いったいどんな姿をしているのだろう。もちろん飼育者選抜試験を受ける前に図書館で図鑑を調べて、その姿を確認したことはある。図鑑には、大きなくちばしの先が折れ曲がって愛敬のある顔をした、ずんぐりした鳥の絵が載っていた。翼はほとんど退化して、ころんとした胴体に太く短い足がついている。だがあれは、あくまでも想像図にすぎない。ドードー鳥は三百年以上も前に絶滅して、その完全な剥製は現在、ひとつも残っていない。図鑑の絵は当時からの言い伝えと、わずかに現存するドードー鳥の破片を寄せ集めて、それらしい鳥を再現したにすぎないのだ。いったい僕が飼育している「本物のドードー鳥」は、どんな姿をしているのだろう。
僕はケージのまわりで写生をしている幼稚園児たちの後ろにそっとまわって、そのスケッチブックを覗きこんでみた。そこには園児たちがクレヨンで描いたドードー鳥の姿があるはずだと思ったからだ。だが、彼らのスケッチブックにはケージの鉄柵と砂地と何本かの立木が描かれているだけで、ドードー鳥の姿はどこにもなかった。
保母さんが園児たちのあいだを忙しそうに走りまわって、「じょうずに鳥さんが描けているわねえ」とか、「あらドードー鳥さんのあんよは四本じゃなくて、二本でしょう」とか言っている。脚の数を指摘された子はケージのなかをじっと見てから、急いでスケッチブックの一箇所を白と茶色のクレヨンで修正した。脚を二本減らしたみたいだったが、僕には見えなかった。
動物園の入口に大きく飾ってある『ドードー鳥の写真』もケージと砂地が写っているだけだし、いつか地元の新聞に掲載された『春の陽を楽しむドードー鳥』という写真にも何も写っていなかった。もしかしたらこれは、みんなが僕をかつごうとしているのかもしれないと思うこともあるが、幼稚園児や動物園の職員、そして地方新聞社までを巻きこんだ悪い冗談なんて、とても考えられないことだった。
「ねえイチハシくん、何か悩みごとでもあるの?」とナオミが僕に訊いた。
「べつに」と僕は答えた。
|