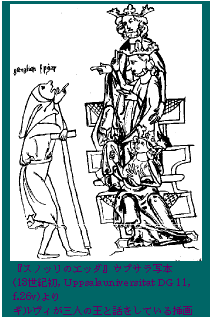
|
|
|
|
|
|
|
|
北ヨーロッパの神話
北ヨーロッパは、ヨーロッパ大陸とバルト海を挟んで北に延びているスカンジナビア半島と、その南側にあるデンマーク、そしてその周辺地域を広く指します。国でいうとノルウェー、スウェーデン、フィンランドのスカンジナビア半島の三か国、バルト海沿岸に縦に三つ並ぶエストニア、リトアニア、ラトビアのバルト三国。そして、ノルウェーの西に海を渡って行き着くオークニー諸島、フェーロー諸島、そして火と氷の国アイスランドです。けれども、この本で扱う神話は、この中でもゲルマン民族の国の神話です。バルト三国やフィンランドは入らないのです。それどころか、このゲルマン民族の、もっと南のドイツやオランダ、ベルギー、はてはもっと西のイギリスにまで広がる民族に共通の神話なのです。そんなにいろいろなところに、時代を超えて伝えられたために、場所や時代によって、神話の内容が若干異なってしまうこともあるのです。なかでももっともよくまとまった神話として書き残されたのは13世紀のアイスランドで、スノッリ・ストゥルルソン(ストゥルラの息子スノッリという意味)という人が書いた『エッダ』という作品です。これは普通『スノッリのエッダ』あるいは『散文のエッダ』と呼ばれます。その他に『詩のエッダ』と呼ばれる作品群もあります。これはスノッリが書いたのではなく、いろいろな神話詩を誰かがまとめたものです。その中には『スノッリのエッダ』の中に引用されている詩が、ほぼ完全な形で記されているのです。そこで、ここに、スノッリの書いた『エッダ』に書かれている神話の中を覗いてみたいと思うのです。まず始めに、私たちは北欧の神話を訪ねていった伝説の人々のことを御紹介致しましょう。
昔ギルヴィという男がいました。いまではスウェーデンと呼ばれる土地の王でした。あるとき彼のところにひとりの旅の踊り子の女が訪れたと言います。彼女は王を大変に楽しませたので、王は褒美に、自分の王国の中で、一晩と一昼のあいだ四頭の雄牛で耕せる土地を与えようと約束しました。さて、この女は名をゲフィユンと言い、神々(アィシル)の一族の一人でした。彼女は、北の巨人国から、彼女と巨人とのあいだにできた息子である四頭の雄牛を連れてきて、鋤をつなぎ、引かせました。しかし、あまり強く鋤を引いたので、土地が根こそぎになり、雄牛たちが進み続けたため、西の海の中にまで引っ張られてしまいました。牛たちはすこし音を立てて止まりました。ゲフィユンはそこに土地を定めて、シェランという名前をつけました(シェラン島はデンマークの首都コペンハーゲンのある島)。一方、土地が根こそぎになったところには湖が残りました。それがスウェーデンのメーラレン湖なのです。ですからメーラレン湖の岸の形は、ちょうどシェラン島の形にぴったりとはまるのです。それで、詩神ブラギはつぎのように歌っています。>メーラレン湖の写真です。
ギルヴィから ゲフィユンは喜びて 深き土地の輪(=鋤。但し「黄金/宝石」の解釈もあり)を引きよせり
それゆえ猛き引き手たちから 水煙は噴き出でたり
デンマークのひろがりなり
雄牛らの 自らの分捕りもの 広き牧場の島を引き寄せつつ
持ちえたるは 八つの額の星と 四つの頭
そのギルヴィ王は賢く、魔術にすぐれていました。彼は、神々が、ものごとを自分たちの思うがままに行うのを見て、愕き怪しみました――これは彼ら自身の能力によるのであろうか、それとも彼らの崇めている何かの神の力によるのだろうか。そこで彼は秘密裏に、自らの姿を老人に変えて、神々の土地アゥスガルズルに向かいました。しかし神々は予知能力を持っている点で、ギルヴィにまさっていました。ですからギルヴィがやってくる前に、彼の来るのを知っていたのでした。そこで彼らはギルヴィの目を欺くように備えました。ギルヴィが神々の町にやってくると、彼の目にはそこにそびえ立つ館が見えました。そのてっぺんはとても高く、目も届きません。その屋根は、瓦の変わりに黄金の楯が葺かれていました。歌に次のように歌われているとおり、ヴァルホルの屋根は楯で葺かれているのです。
感情の傷つきやすい男たち 兵士たちの背に
――彼らは石にて攻められているのである――
オージンの館の屋根瓦(すなわち楯)は輝けり
館の入り口で、ギルヴィは門番に出会います。彼は剣でお手玉をしているのですが、いちどきに七つの剣を空中に浮かばせながらなのです。この男がさきにギルヴィに話しかけます。おまえの名は何というのか、と。ギルヴィは答えてガングレリ(歩き疲れた者)だと名乗ります。自分は道なき道を越えてきたのだ、と。一夜の宿をお借りしたいが、この館は誰の者かと尋ねます。門番は、我らが王のものと答えます。
「王のところに案内するゆえ、王の名は、自分で訊くがよい」
男はきびすを返し、ギルヴィの先を歩くので、ギルヴィはあとをついていこうとしますが、扉のうちに入ったとたん、彼のかかとのところで扉がばったりと閉じるのでした。屋敷の中には多くの部屋があり、多くの人々がおりました。ある者はゲームをし、またある者は酒を飲んでおり、ある者は戦いの格好をして闘っているのです。ギルヴィは周りを見回し、目に映るのはとても信じられないものばかりだと思います。
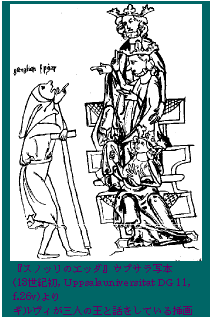
訊ねる者は立っていよ
答える者は腰をかける
という詩句を唱えるのでした。
こうしてガングレリとの問答が始まるのです。ところで、ガングレリが訪れたときとは別のある時、神々の館を訪れた人物がいると、スノッリは『エッダ』の別のところに書いています。その人物の訪問の様子は次のようなものでした。
昔アィギルあるいはフレールという名の人物がいました。彼は現在「フレールの島(フレースエイ)」と呼ばれる島に住んでおり、魔術の技に長けていました。彼はアゥスガルズルに向け出立しました。神々(アィシル)は彼のやって来ることを知ったとき、大歓迎をしましたが、多くのものは彼の目を欺いて見せた見せかけだけのものでした。そして夜になり、宴会が始まるときになると、[神々の長]オゥジンは何本もの剣を持ってこさせるのでした。剣から発せられる輝きは、宴会場にほかの明かりがいらないくらい明るかったのです。神々は宴の席を備えさせると、さばきつかさである12人の神々(アィシル)はそれぞれ自分の玉座につきました。彼らの名前は次の通りです。ソゥル、ニョルズル、フレイル、ティール、ヘイムダッル、ブラギ、ヴィーザル、ヴァーリ、ウッル、ハィニル、フォルセティ、ロキです。同様に、女神たち(アゥシニュル)も。フリッグ、フレイヤ、ゲフィユン、イズン、ゲルズル、シグン、フッラ、ナンナでした。アィギルにとって、そこにあるすべてのものは大変に素晴らしいものに思われました。壁板は、すべて見事な楯がはめ込まれていました。また、強い蜜酒があって、大勢の者がそれを飲んでおりました。アィギルの隣に座ったのはブラギでした。二人は共に飲み、言葉を交わし合いました。ブラギはアィギルに神々の関わった多くの事柄について語って聞かせたのです。
このようにして神々について聞くために、ギルヴィ王もアィギルも彼らのいた館に直接乗り込んだのでありました。皆さんは、そこで何が語られたか、是非、ともに座って耳を傾けてみたいと思うことでありましょう。残念ながら、その全てを此処で語り尽くすことはできませんが、その一部については、幸い紙数に余裕があるようです。それでは、話をギルヴィ王に戻し、そこで彼がどのようにしてヴァルホル(選ばれた者の館)で、神代の出来事について聞いたかを見て参りましょう。
ガングレリは言います。「始まりはどのようなものだったのですか? ものごとはどのようにして始まったのでしょう。それ以前にはなにがあったのですか?」
ハゥルが答えます。「『巫女の予言』の中で次のように言われている。
時のはじめにはなにもなかった
海辺もなく 海もない 冷たい波もなかった。
地はなく、空には天もなかった
力あるうつろ(ギンヌンガ・ガップ)があったが
しかし育つべき草もなにもなかった」
するとヤプンハゥルが言うのでした。「大地ができる遙か昔にニヴルヘイムができた。そこの真ん中にはクヴェルゲルミルという名の泉がある。
そしてそこから十一本の河が流れ出ている。11本目の河は
ヘルの入り口の門の脇を流れるギョッルという河である」
するとスリジが言います。「しかし始めは南の領域に世界があった。ムスペッルという名である。そこは明るくまた暑いところだ。その地域は炎があがっていて、燃えていて、その土地に生まれた者以外に、外の者には通り抜けることができない」
するとスリジが言います。「しかし始めは南の領域に世界があった。ムスペッルという名である。そこは明るくまた暑いところだ。その地域は炎があがっていて、燃えていて、その土地に生まれた者以外に、外の者には通り抜けることができない。その国の入り口にスルトと呼ばれる者がいる。彼はその国を守っているのだ。彼は燃える剣を持っていて、世界の終わりには彼はそこから出てきて戦いを挑み、全ての神々を討ち負かし、全世界を火で焼き尽くすのだ。それゆえ、『巫女の予言』の中で次のように歌われている:
スルトは南からやってくる 木を破壊する者を(炎)を持って
彼の剣からは殺戮の神々の太陽が輝く
岩壁も崩れ トロル女たちは去る 英雄たちはヘルへと続く
道を辿り行く そのとき天も裂ける」
ガングレリは尋ねます。「ものが生まれ、人が数を増やす前にはものごとはどのようであったのでしょう?」
ハゥルは言います。「幾つもの流れが集まって、エリヴァーガルという名で呼ばれる河があった。その流れが源流からはるか遠く離れたところにまできて、その流れに乗ってきた毒気のあるものが、まるで炉から金くそがでるように固まり始めると、ついには凍ってしまうのである。氷がそこに留まると流れもそこでとまり、固まった毒気が蒸気になって昇ると上で霜となって凍り付くのだ。霜はそのように積み上げられ、ギンヌンガ・ギャップを横断するほどになる」
するとヤプンハゥルが口を開きます。「ギンヌンガ・ガップの北側に向いている方は、その氷と霜の重さと重量によって満ちている。そこには蒸気と風が内に向かって吹いているのだ。しかしギンヌンガ・ギャップの南側は、ムスペッルの世界から飛んでくる火花や熔けてしまった飛沫に向かい合っているのだ」
そのときスリジが言います。「ちょうどニヴルヘイムから冷たさと全ての暗鬱なものが出てくるように、ムスペッルに向かい合っているものは熱く、輝かしいものなのだ。けれども、ギンヌンガ・ガップはまるで風のない空のように穏やかなのだ。そして霜と熱気の流れが出会い、霜が解け、滴り始めると、熱の源の力のために、この流れ出た滴に命が宿るのだ。そしてそれは人の形をとり、イーミルという名が与えられた。しかし霜の巨人たちは彼のことをオイルゲルミルと呼ぶ。霜の巨人たちは彼から生まれた子孫なのである。すなわち、『短き巫女の予言』の中で次のように言われている:
全ての巫女はヴィズオルヴルより、全ての知恵者はヴィルメイズルより、
全ての魔術師はスヴァルトホフジより、全ての巨人はイーミルより来たれり
また、「巨人ヴァフスルーズニルの言葉」にも次のように語られている:
巨人の子らとともに、かの賢き巨人オイルゲルミルは何処より来たのか。
「エーリヴァーガルから毒の滴が垂れ それから一人の巨人が形作られた
我らが先祖はみなその中にいた すなわち
全ての厄災は常にこのためにあるのだ」
すると、ガングレリは言います。「どのようにして生き物の子孫たちは彼から出たのでしょう。巨人以外の生き物が生まれたのはどのようにしてなのですか?それとも、あなた方はこの巨人が先ほど述べられた全てのものを作った神だと信じるのですか?」
するとハゥルは答えます。「私たちは彼を神だとは思わない。彼も彼の子孫も邪悪なものだから。我々は彼らを霜の巨人と呼ぶ。このように言われている。彼が眠っていると、彼は汗をかき、すると彼の左の脇から男と女とが生まれたのだ、と。彼の子孫はその二人から生まれ出たのだ。彼らこそ霜の巨人であり、その最古の霜の巨人を我らはイーミルと呼んでいるのだ」
するとガングレリが言います。「イーミルはどこに住んだのですか?またどのようにして生きながらえたのでしょう」
ハゥルは答えます。「巨人は塩の味がする霜の岩をなめた。そしてその岩をなめた最初の日、夜になって岩の中から人間の髪の毛が生えてきた。翌日、人の頭が出てきた。三日目には完全な人間がそこに現れたのだ。彼の名前はブーリという。彼はみめ麗しく、大きく、力強かった。彼は息子をもうけ、その名をボルと名付けた。彼は巨人ボルソルンの娘ベストラと結婚した。ボルとベストラには三人の息子がいた。一人はオージンという名で、二人目はヴィリ、三人目はヴェーといった。このオージンと二人の兄弟が天と地の支配者に違いないと私は信じているのだ。彼がそのように呼ばれるのは我々の私的意見にすぎないが」
するとガングレリが口を開きます。「どのようにして連中と巨人たちとはうまくやっていくのでしょうか?より強いのはどちらの方でしょうか?」
ハゥルは答えます。「ボルの息子たちは巨人イーミルを殺したのだ。イーミルが倒れたとき、あまりにも大量の血がその傷から流れ、それは一家族逃れた以外は全ての霜の巨人族はおぼれ死んでしまった。巨人たちはその逃れた者をベルゲルミルと呼んでいる。彼は箱船に自分の妻と共に行き、そこで生き残ることができた。霜の巨人たちの一族は全て彼から出たのだ。
すると、ガングレリが答えます。「あなた方がボルの息子たちを神々と信じるならば、いったい彼らがなにをしたというのですか?」
ハゥルが口を開きます。「それについて語ることは少なくはないぞ。彼らはイーミルの体を持ち上げ、ギンヌンガ・ギャップの真ん中へとそれを運んだ。そして彼から世界が、彼の血から海と湖ができたのだ。彼の肉体から大地が、岩は彼の骨から、石や小石は彼の歯や奥歯から、また彼の折れた骨からできたのだ」
するとヤプンハゥルが語ります。「彼の傷口から出た血は抑えが効かなかったが、そこから彼らは海を造り、大地を囲み世界の中に取り込んだ。そして大地の外側の周りに丸く海を配したので、ほとんどの人たちには海を越えることなどは不可能であるかのように見えるのだ」
そしてスリジが語りました。「ボルの子らは彼の頭蓋骨をとると、それから空をつくり、大地の上に置き、四つの地で空を支えた。そしてそのそれぞれの下に四人のドワーフを置いた。四人のドワーフの名前はオイストリ(東)、ヴェストリ(西)、ノルズリ(北)、スーズリ(南)である。それから彼らはムスペッルの世界から止めどなく飛んできた熔けている飛沫や火の粉をとり、天蓋の真ん中の上と下とに据え、空と大地とを照らす明かりとした。彼らはある明かりは空に据え、また別の明かりは空の下を動くように据え、特にその位置と進む道も定めた。そのようにして遙かな昔から、日々も年も数えられてきたのだと、古代の書物は告げているのだ。」
ガングレリは答えます。「今わたしが聞いたことは大変貴重なお知らせだと思います。これはまさに偉大で、優れた技の造ったものと言えます。この世界はどのようになっているのですか?」
ハゥルが答えます。「この世界は端が丸くされており、その周りに深い海がある。この海岸に沿った土地を、彼らは巨人の一族にそこに住むようにと与えたのである。しかし、大地のもっと内側には巨人族に対抗するための柵をはりめぐらし、世界を囲んだのだ。その柵を作るために彼らはイーミルのまつげを用いたのだ。その柵のことを彼らは人間界(ミズガルズル「中の囲い地」という意味)と呼んでいる。彼らはまた、イーミルの脳味噌をとり、それを空に投げ、そこに雲を造ったのだ」
それは神々が、自分たちの住まいを定めて、ヴァルホッルを建て、「中津国」(ミズガルズル)を据えた後、一人の工匠(大工職人)がやってきて、神々のために一年半で城塞をつくろうと申し出ました。それは山の巨人たち、霜の巨人たちに対して、彼らが「中津国」にやって来ても、信頼でき安心できるほど素晴らしい城塞なのです。しかし彼は、フレイヤを妻としてもらうことを条件としました。そしてまた、太陽と月ももらいたいと言いました。
神々は集い話し合い、次のように取り決めました。
工匠は半年でその城壁をこしらえられたら、報酬を手に入れられる;しかし、夏の初日になったときに城壁のことでなにかをし残していたならば、その報酬をあきらめなければならない、と。またその作業は誰の助けも借りてはならないというものでした。
彼らがそのように条件を話すと、工匠はスヴァジルファィリという自分の牡馬の助けを借りることをゆるしてくれるように頼みました。他の神々を説き伏せて、その条件を神々に認めさせたのは神々の中のロキでした。
工匠は冬の最初の日に城塞を建てる仕事を始めました。そして夜には馬で石を積み上げ始めました。神々(アィシル)にとって、この馬が運ぶ石の大きさといったら見るも驚くほどに思われました。しかも、この馬は工匠の働く二倍もの仕事をこなすのです。けれども、双方の間の約束は、力ある証人と誓いによって交わされたのでした。というもの、安全の保証がないのに神々の間にいることなぞ、ソゥルが戻ってくる以上、安心だとは巨人族には思われなかったからです。もっともその時にはソゥルはトロルたちを退治するために東の地域に行っておりました。そして冬が過ぎていくうちに、城塞建築はどんどん進んでいき、城塞はいまや非常に高くまた堅固になり、だれもそれを打ち壊すことなどできないようになりました。
そして夏の初日まであと三日になったとき、仕事はいよいよ城塞の門の所まできてしまいました。そのとき神々は裁きの座を設け、どうしようか、いったいフレイヤを巨人の国に嫁がせ、太陽と月を空から取って巨人にやってしまうなどと言うことを決めたのは誰の責任かを話し合いました。最悪の事態にいつも責任がある者がこの決定の責任を持つはずだ、すなわち女巨人ロイフェイの息子ロキであるということで、その場の全員の意見が一致しました。そしてあの工匠が報酬を受け取れないようにさせる計画を見つけることができないならば、ロキはひどい惨めな死を受けるにふさわしいという判決を下しました。それから神々はロキを懲らしめようと近づきました。ロキは恐れ、自分がどのようになろうとも、あの者が報酬を受け取れないようにするようやってみると誓いをたてました。その同じ夜、工匠がスヴァジファィリを駆って、石を運んでいたとき、ある森から一頭の牝馬が牡馬の方に飛び出してきて、彼に向かっていななきました。牡馬は、それがどんな牝馬か見て取ると、狂ったようになって、馬具を引きちぎり、牝馬の方に走り出しました。彼女は森の方に逃げ、工匠は牡馬を捕まえようとして二頭の後を追いました。二頭の馬はその夜中じゅうずっと走り回り、城塞の建築はその夜はとどこおってしまいました。次の日も、以前のようには仕事ははかどりませんでした。そして工匠が、これは約束の期日にまで仕事は終わらないとわかったとき、その工匠は巨人の怒りに達しました。しかし、神々(アィシル)はそこにいたのは確かに山の巨人だとわかると、例の誓いはそのとき顧みられなくなり、彼らはソゥルの名を呼びました。するとソゥルは瞬く間に現れ、次の瞬間にはミョルニルが高々と振り上げられたのです。
その時に彼への報酬が支払われたのですが、それは太陽でも月でもなく、巨人国で生き続けるのをやめさせられたことでした。そして最初の一撃で、彼の頭蓋は粉々に砕け、ソゥルは彼をニヴルヘイムへと送ったのです。しかしロキのスヴァジファィリのあしらい方は、次の結果となりました。すなわち、しばらくして、彼は子馬を産み落としたのです。それは灰色で、八本足でした。この馬が神々と人間との間で最も素晴らしい馬なのです。そこで『巫女の予言』には次のように言われているのです:
双方の間に交わされた 全ての神聖な誓いも 約束の言葉も退けられた。ソゥル一人がこのことをなした 燃える怒りをもって 彼がそのようなことを知りながら 何もせずにいることはまれだ
このように、神々の偉業についてガングレリが訊ねること全てにハゥルたちは答えることができたのです。このままではガングレリの方が負けてしまいますね。そこで、ガングレリは知恵を絞り、次のような質問を投げかけるのでした。
---
「ソゥル神は、力や魔法のおかげにより、自分で解決するのは無理だと思うような、力強い技や魔法の出来事に出会ったことはないのでしょうか?」
ハゥルは答えます。「ソゥルが困難な状況にあったことは何度もあったであろうが、お前が言うようなことについて話すことのできる人はほとんどいないであろう。しかし、仮にソゥルが撃ち破ることのできないほど強い何かがあったとしても、それについて語る必要はあるまい。なぜなら、ソゥルがもっとも力強いことは、信じるほかはないという証拠が多くあるのだからな」
するとガングレリは言うのでした。「どうやらあなた方のうちどなたも答えることのできない質問を尋ねてしまったように思えてきましたよ」
そこでヤプンハゥルが答えます。「私たちにはとても信じられたいように思えることで、真実であるかもしれないことを確かに聞いたことはあります。ここからそう遠くに離れていないところにいる人物が、あなたに真実の話をお聞かせできるでしょう。もちろん、これまで嘘をついたことのない人物が、今ここで初めて嘘をつくはずなどないことは信じられますね」
ガングレリは言います。「ここに私は立って耳を傾けています。このことの解決を誰がなさるのかを待っているのです。そして、これに答えることができなければ、あなた方の負けなのです」
そこでスリジが言います。「彼はなんとしてもこの話を聞こうと心に決めているのはよくわかる。けれども我々にとってそのことを語るのは愉快ではないのだ。そこでお前は黙っていなければならない。
「この話の始まりは、戦車のソゥルが自分の二匹の山羊の引く戦車を駆って出かけたことだ。彼と一緒にロキと名乗る神がいた。夕方になって、一人の農夫の家にやってきた。そこで一夜を過ごそうというのだった。夜になって、ソゥルは自分の山羊をとり、二匹とも屠った。そのあと皮をはぎ、ポットの中にそれを入れた。肉を焼いたとき、ソゥルとその連れは夕食の座についた。ソゥルは農夫とその妻、また子供たちを、その食事をともにしようと招いた。農夫の息子はシヤルヴィといい、娘はロスクヴァといった。ソゥルは山羊の皮を火の反対側に置き、農夫とその家族に、骨をその皮の上に捨てるようにと指示した。シヤルヴィは腿の骨を手の中に持つと、その骨をナイフでこじりあけ、髄までこそいでしまった。ソゥルはその夜はそこに留まったが、夜明けの少し前に起きあがると服を着て、ミョルニルという鎚をとり、それを振り上げると山羊の皮に祈りを念じた。すると山羊たちは立ち上がったが、そのうちの一匹は後ろ足がびっこをひいていた。ソゥルはこのことに気づくと、農夫か彼の家族の一人が、いたわりを持たずに山羊の骨を扱ったに違いないと結論をだした。ソゥルは例の腿の骨が折れていることを知ったが、そのことについて長々と話す必要はないだろう。だれでも農夫がソゥルが目を細めるのを見たときにどれほど恐ろしく思ったか想像するのはたやすいことだ。その両目になにが見えたかについて言うならば、農夫はその目を見ただけで体がバラバラになるのではないかと思ったものだ。ソゥルのハンマーを持つ手にさらに力がこもっていき、その拳が白くなってしまうほどだった。農夫はもちろん、彼の家族たちも激しく泣きながら、持っているもの全てを捧げるゆえ、命ばかりはお助けをとお慈悲を請い願ったのだ。ソゥルは彼らの恐怖を見ると、怒りが引いていき、静まると、贖いとして農夫の子供たちのシヤルヴィとロスクヴァとをうけとり、二人はそれ以来、ソゥルの召使いとなり、常に付き従ったのである。
ソゥルは山羊をそこに置いて行くと、東のヨトゥンヘイマルを目指して歩いていき、海にまで至った。その深い大海を渡ると岸に着いたので陸に上がった。ソゥルとともにいたのはロキとシヤルヴィとロスクヴァだった。しばらく行くと大きな森に行き当たった。彼らは暗くなるまで日がな一日歩いた。シヤルヴィはもっとも速く走ることができた。彼はソゥルの荷物をしょっていたが、通り道に泊まれるところは見あたらなかった。暗くなってくると、皆は夜を過ごせる場所を探していたが、あるとても大きな建物のところに来た。壁の一方には入り口があったが、建物の幅と同じ幅の入り口なのだ。ともかくもここに一晩泊まることにしたが、真夜中に大きな地震があった。地面は彼らのシダで激しく動き、建物も震えた。そのときソゥルは起きあがり、連れの者たちを呼んだ。彼らは周りを探ると、母屋の右の方、半分ほど下ったところに離れがあることがわかったのでその中に入った。ソゥルは入り口のところに留まり、ほかの者たちはもっと奥の方に行った。彼らは恐怖に震えていたが、ソゥルはハンマーの取っ手を強く握り、自分の身を守って闘ってやろうと待っていた。するとその時大きなガラガラ、ゴォゴォいう音が聞こえてきた。そして夜明けが近づいたとき、ソゥルが出ていくと、森を少し入ったところで誰かが寝ているのが見えた。その男は決して小さくはなかった。その男は寝ており、大きな音をたてていびきをかいていた。そのときソゥルは昨夜一晩中の騒音の原因を理解したのでした。彼は力のベルトを締めると神通力を増しました。しかしちょうどその時、寝ていた男は目を覚まし、すばやく立ち上がりました、その時ソゥルは、ハンマーで叩くのを恐れたのは最初で最後だったと言います。ソゥルはその男の名を尋ね、彼はスクリーミルだと答えます。
「しかしあんたが誰だか尋ねる必要はあるまい」とその男は言います。「あんたが神々のソゥルだとはわしにもわかる。しかしあんたはわしの手袋を持ち逃げしようとしていたんじゃあるまいな」
そういうとスクリーミルは自分の手袋を拾い上げてました。その時ソゥルは、自分たちが昨夜宿と思って使ったのはスクリーミルの手袋だと分かった。避難した離れは、手袋の親指の部分だった。
スクリーミルは、ソゥルに同行することを頼み、ソゥルは同意した。そしてスクリーミルは出てきて、背負い袋を下ろして朝ご飯の支度を始めた。ソゥルと連れの連中もそこから離れて同じようにした。するとスクリーミルが、食べ物は一緒に集めて保管するのがよかろう、と提案した。ソゥルはそれはよい、と言った。そこでスクリーミルは一つの袋の中に彼らの持ち物を全て詰め込むと背中に背負った。スクリーミルは昼の間先頭に立って歩き、その歩みはとても速かった。夜になると、スクリーミルは一本の大きな樫の木の下に、皆が一夜を過ごすための場所を見つけた。「だがお前さんたちはこの背負い袋を持っていって、自分たちの夕ご飯を取り出すがいい」
その後、スクリーミルは寝入ってしまい、大いびきをかき始めた。ソゥルは背負い袋を受け取ると、それを開けようとした。それは次のように言われているのだが、とても信じられそうには思えないのだ。ソゥルは結び目をひとつも解くことができなくて、ひもの端をどうやっても結び目がゆるんだようには見えなかった。いくらやっても埒があかないことがわかると、ソゥルは怒り、ミョルニルの鎚を両手で握ると、スクリーミルのところへたった一歩で飛んでいき、彼の頭を殴った。スクリーミルは目を覚まし、木の葉でも自分の頭の上に落ちてきたのか、と尋ねた。そしてみんなは食事を食べ終わって寝床に入る用意ができたのか、と尋ねた。ソゥルは皆もう眠るところだと言った。それから皆で別の樫の木の下に行ってしまった。実のところ、恐ろしさを感じずに眠ることなどできなかったのだ。
しかし真夜中に、ソゥルはスクリーミルがいびきをたてながら深く眠り、そのために森中がこだましているのをみて、立ち上がり、彼の方まで歩いていった。そこで素早くハンマーを振り上げ、思い切り彼の頭の真ん中に振り下ろした。ハンマーの先が頭の中にめり込むのを感じた。するとその時、スクリーミルが目を覚まし、こう言った。「今度は何だ?ドングリか何かが頭に落ちたのかな?ところでソゥル、お前は何をしているんだ」
しかしソゥルは素早く戻ると、俺は今目が覚めたばかりだ、と答えた。そしてまだ真夜中で寝ている時間だと言った。ソゥルはそのとき、もし三回目にミョルニルの鎚を打ち下ろすことがあったら、あいつは絶対目を覚まさせないぞと心に決めたのである。ソゥルは再びスクリーミルがぐっすりと眠るのを待ったが、夜明け前になってスクリーミルの寝息を聞くと、ぐっすり眠っているに違いないと思った。そこで起き上がり、彼のもとに走ると、ありったけの力を込めて鎚を振り回すとこめかみに向けて叩きつけた。その時鎚は取っ手のところまでめり込んだのだ。しかしスクリーミルは体を起こすとほっぺたのあたりを掻きながら、こう言った。「俺の上の木の枝に鳥でも留まったんだろうか。俺が起きるときに、枝の上から汚いものが落ちたようだぞ。ソゥル、お前は目が覚めたのか?もう起きて着替える時間だな。もうここからウトゥガルズルと呼ばれる城まではさほど遠くはないぞ。俺は、お前さん方が俺のことを決して小さくはないと言っていたのを聞いたが、もしお前さん方がウトゥガルズルに行くのなら、俺よりも大きな連中に会えるだろうよ。お前さんたちに一つ忠告してやろう。思い上がった行動をするんじゃないぞ。ウトゥガルズルのロキの部下たちはお前さんたちのような赤ん坊みたいなやつらに大きな顔をされるのがとても嫌いなのだ。そこに行かないなら、道を引き返すのがいい。その方がお前さんたちのためだ。だが、どうしても行くというのなら、東に向かうがいい。だが俺の行く道は北のあの山に向かっているのだ。」
第三章 ソゥルがウトゥガルザ・ロキの城を訪問すること
さて、スリジはソゥルの冒険についてまだまだ話を続けています。ガングレリは言われたとおり、一切口を挟むことはありません。
「ソゥルは連れの連中と旅を続けてお昼まで歩き続けた。すると開けた土地の中に城がひとつ立っているのが見えた。その城のてっぺんを見上げるためには自分たちの頭が背中に付くぐらい首を曲げなければならなかった。彼らは城に近づくと、入り口にはかんぬきの棒が渡されていた。ソゥルは入り口のところまで行ったが、かんぬきを持ち上げることはできなかった。しかしなんとかかんぬきとかんぬきの間を体をすり抜けて中にはいると、そこに大きな建物があった。近づくと扉は開いており、中に入った。二つの長椅子があり、多くの人々がそれに腰掛けていたが、ほとんどの体はたいしたおおきさだった。それから彼らはその人々の王であるウトゥガルザ・ロキのところにやってきて、挨拶をした。その男は彼らの方に向きをかえるのがやたら遅かったが、歯を見せて笑うとこう言った。『知らせというものは長い距離を行くのが遅いと見えるわい。しかし、間違っていなければ、この小さな御仁はソゥルではないかな? 実際に見えるよりも中身は大きいのは間違いないだろうな。おまえさん方がなにか人に見せるような特技を持っているかな? 我らの多くの者よりすぐれた業や特技を持っていなくては、ここに一緒にとどまることはできんのだぞ』
そこでソゥルの一行の一番しんがりにいたロキが言った。『俺は見せるべき得意な業を持っているぞ。この館の誰も俺よりも速く食べ物を食べ尽くすことができる者はおらんだろう』
するとウトゥガルザ・ロキがこう答える「もしそんなことができればそれこそ見物だぞ。試しにやってみようではないか。そこで長椅子に座っている者の中からロギと言う名前のものがロキと競うのがいいだろう」すると長皿が運ばれてきて、ホールの長さいっぱいに肉がもられた。ロキは片方の端に座り、反対側の端にはロギが座った。両者は全力で肉を平らげたが、ちょうど長皿の真ん中で二人がぶつかった。ロキはその時には肉を全て骨からそいで食べていたが、ロギは肉の全てを骨ごと食べたばかりか、木のお皿まで食べていた。そこで誰の目にもロキが負けたのは明らかだった。
するとウトゥガルザ・ロキは、そこの坊やは何ができるのかと尋ねた。シヤルヴィは答えて、館の主人が推薦するだれとでも走り比べをしてみたいのですが、と言った。ウトゥガルザ・ロキは、それは確かによい見せ物となるだろうが、ただし、得意と言うからにはお前は全力をあげてよっぽど速く走らねばならないぞ、と言った。それでもシヤルヴィはすぐに証明してみましょう、と言ったので、ウトゥガルザ・ロキは立ち上がり、外に出ていった。そこには平らでよい競走ができる場所があった。ウトゥガルザ・ロキはフギという名の小さな男を呼び、シヤルヴィと走ってみるがいい、と言った。まず第一回目の競走が行われ、フギはあまりに速く走り、ゴールして振り返ると、スタート地点のあたりにシヤルヴィがいたほどであった。するとウトゥガルザ・ロキが言った。『この走り比べで勝ちたかったら、もっと一生懸命に走らないとだめだぞ。だが、ここに来た者の中で、これほど速く走ったのを見たことは確かになかったがな』
それから彼らは二回目のレースを行った。そしてフギがゴールしてから振り返ると、シヤルヴィは槍を投げて届くくらいまだ後ろだった。するとウトゥガルザ・ロキが言った。『シヤルヴィは素晴らしく競い合ったな。だが、もう彼にはこの走り比べで勝てる見込みはありそうにもないとも思うぞ。だが、まあ三回目のレースを見てみることにしよう』
それからもう一度レースが行われた。フギがゴールしたときに振り返ると、シヤルヴィはまだコースの半分にも達していなかった。そこで皆が、この競走は決着が着いた、と言った。
するとウトゥガルザ・ロキがソウルに尋ねた。ソゥル自身は皆の前でどのような技を見せてくれると言うのだ? そこでソゥルは、飲み比べでなら喜んで誰とでも競ってみよう、と言った。ウトゥガルザ・ロキはそれはいいと言って館の中へ戻り、自分の家令を呼ぶと、家の者たちが飲み明かした古い角杯を持ってこいと命じた。再び家令がやって来たとき手には角杯を持ち、ソゥルにそれを渡した。するとウトゥガルザ・ロキは言った。『この角杯から一口で飲み尽くすことができたら、よく飲めた、と言えるのだ。二口で飲み尽くす者もいるが、三口で飲み尽くすことすらできなかったら、よく飲めるとはとても言いかねる』
ソゥルは角杯を眺めたが、すこし長いがそれほどまでに大きいとは思われなかった。それでも彼はのどが渇いていたので、飲み始め、ごくごくと飲み続けながら、しばらくの間は、二杯目を要求する必要もないかな、と思っていた。しかし息が続かなくなってきたので、杯を口から離し、どのくらい飲んだか見てみた。しかし、始めの頃と中身の位置がほとんど変わったようにも見えなかった。するとウトゥガルザ・ロキが言った。
『なかなか飲んだようだな。だが飲み過ぎというわけでもあるまい。神々(アィシル)のソゥルがもっと飲んだと聞いても俺としては驚かなかったと思うがな。それでももちろん次の一飲みで飲み干すつもりだろう』
ソゥルは返事をせず、角杯を口許に持っていくと、もっと大きな杯でも、息の続く限り飲み続けるぞと心を決めて飲み始めた。しかし、彼が思うよりも杯の傾きは大きくならないのであった。そして、口から杯を離したとき、中を覗いてみても、前の回よりも減ったとは思えないのだった。しかし今や杯をこぼさずに楽に運べるほどに、杯の中身は下がっていた。その時ウトゥガルザ・ロキは言った。
『どうしたというのだ、ソゥル? 軽く一杯飲み干す分をとっておこうとして、その分量を間違えたのか。しかし三杯目で飲み干そうと考えていたのだったら、それは今までで一番頑張らねばならぬぞ。しかし、この飲み比べの結果では、ほかの競技でもっと素晴らしい成果を出さない限り、神々の間で言われるほどお前さんは偉大な者だとはもう我々の間では認められなくなったな』
するとソゥルは大いに怒り、角杯を口に付けると、できる限り思いっきり、そして息の続く限り挑んで飲み干そうとした。しかし角杯の中を覗いてみると、今回は今までの中では一番中身が減ったように思えた程度だった。しかしソゥルはこれ以上はもう飲めないと思って角杯を返した。そこでウトゥガルザ・ロキは言った。『これでもうお前さんの力も思っていたほどではなかったことがわかった。ほかの競技に挑戦してみたいかね。この飲み比べではもう得るところはないのだから』
ソゥルは答えた。『もっと別の競技をなんとしてもやってみたいものだ。しかし、神々たちのところにいたとしてこれだけ飲んで何もならなかったら驚きだぞ。しかし今度はどんな競技をお望みなんだ』
するとウトゥガルザ・ロキは答える。『ここにいる若い連中がやることだが―もっともわしにとってはなんの意味もないことなのだが―わしの猫を地面から持ち上げるのだ。だが、先の競技で思ったほどの人物ではないとわからなかったら、こんなことを神々(アィシル)のソゥルに申し出るまでもなかったと思うがな』
すると一匹の灰色の猫が広間に走り込んできた。それはかなり大きい猫だったが、ソゥルはそいつを捕まえると、その腹の真ん中を片手で持ち上げた。しかし猫は背中をそりかえらせたので、ソゥルは腕を一杯に伸ばさなければならなかった。しかしソゥルがもうこれ以上は持ち上げられないというところまで来たときも、猫はただ片足を地面から離したに過ぎなかった。そしてソゥルはこの競技でも大した成果を上げられなかった。するとウトゥガルザ・ロキは言った。『まあ、こんな程度だろうと思っていたぞ。なんと言ってもソゥルはこの部屋のでかい連中と比べても小さい者だからな』
するとソゥルは言った。『俺を小さいと言ったな。さあ、誰でもいいから俺と闘ってみろ!俺は怒ったぞ』
するとウトゥガルザ・ロキは長椅子に座っている者たちを見回して言った。『お前さんと闘うなんて不名誉だと感じないものはここにはいなさそうだ。少し待ってくれ。ここにわしの伯母のエッリを呼んでこい。もしソゥルが望むなら、彼女と闘わせよう。ソゥルほど強く見える者と闘っても、彼女は負かしたものだからな』
そこで広間にやって来たのは一人の老婆だった。そしてウトゥガルザ・ロキは、彼女が神々(アィシル)のソゥルとレスリングをするのだ、と言った。そのことについては格別話すべきこともない。この試合がどうなったかと言えば、ソゥルが強く締め上げようとすればするほど、彼女はしっかりと立ち続け、その後で、彼女の方が技をしかけようとすると、ソゥルは足許がふらつき始め、力の入ったひと引きがあると、ソゥルが片膝を床に着けるまでにそれほどはかからなかった。するとウトゥガルザ・ロキがやって来て、戦いをやめろと宣言し、この広間の中で、これ以上ソゥルはほかの誰かに挑戦する必要はない、と言った。もうすでに時刻は夜も遅くになっていた。ウトゥガルザ・ロキはソゥルとその一行に、落ち着き場所を示し、彼らは手厚いもてなしとともに、その夜を過ごした。そして夜が白々と明けるやいなやソゥルとその連れは起き上がり、着替えると早速出掛けようとした。するとウトゥガルザ・ロキがやって来て、彼らのために食卓を用意した。楽しい話と飲み物と食べ物で欠けたところの何もないもてなしだった。そして彼らが食べ終わると、皆出発した。ウトゥガルザ・ロキも彼らと一緒に行った。そして城を出るまで、彼らと一緒だった。そして彼らは別れたが、そのとき、ウトゥガルザ・ロキはソゥルに尋ねて、お前さんの旅はどんなだったかと訊いた。そしてソゥル自身より優れた誰かに出会ったかと尋ねた。ソゥルは答えて、この出会いで自分の面目をかなり失わなかったとは言えないな、と言った。『しかもあんたはこの俺がたいした者ではないと言いふらすだろう。それが俺にはたまらないのだ』
するとウトゥガルザ・ロキが言った。『もうわしの城を出たからには真実を聞かせてやってもいいだろう。わしが生きていて、目の黒いうちは決してお前を城に入れることはないだろうからな。というのも、もしもお前がこれほどまで力を持っていたということや、お前がわしらを滅ぼすほどの危険に陥れるなどということをあらかじめ知っていたら、わしは決してお前を城に入れていなかっただろう。だが、わしはお前の目をだましていたのだ。だから最初にお前をわしが森で見つけたときも、その時にお前の目の前にいたのはわしだったのだ。例の背負い袋のひもをお前が解こうとしたとき、わしはそれを魔法のひもで縛り、どこを引っ張ればゆるめられるか見えなくしていたのだ。次にお前がハンマーで三度わしを打とうとしたとき、その最初の一撃は一番弱かったが、それでももし当たっていたら、わしの命はなかっただろう。しかし、わしの館の近くで一つの平山を見ただろうが、そこに三つの四角い谷ができていたはずだ。あれはお前のハンマーの痕なのだ。わしはお前が一撃を下ろすすぐ前に、お前が気がつかないように平山をそこに動かしたのだ。それと同じく、わしの手の者とお前たちが競ったときもそうだった。最初の競技はロキがやったものだ。彼はとてもおなかが空いてとても速く食べた。しかし、ロキの相手はロギ(つまり火)で、あれは野火だったのだ。そしてあれは木皿も肉と同じくらい速く燃やすことができる。そしてシヤルヴィが駆け比べをしたが、その相手はフギ(思考)というもので、わしの思考だったのだ。シヤルヴィはその速さにかてるはずはなかったのだ。そしてお前さん自身が飲み比べで角杯から飲んだが、あのときは本当に信じられないような奇跡が起こったのだ。角杯の尾っぽはじつは海に出ていて、お前さんはそれに気がつかなかったのだ。しかし今海に出てみれば、お前さんが飲んだことで、どれほど海の水が減ってしまったか、見ることができるだろう』」
そこで、スリジは話をとめ、「これは今は潮の満ち引きとして知られているのだ」と言いました。それからスリジは話を続けました。
「『それにお前が猫を持ち上げたときも、それに劣らず驚くべきものだった。本当のことを言えば、あれを見ていた者はみな、足が一本地面から持ち上がったのを見たとき、恐ろしさに震えたものだ。なぜかというと、お前さんにはあれは猫の姿に見えていたが、実はそうではない。あれは全地を囲んで横たわるミズガルズル蛇だったのだ。だからその頭としっぽでさえも、地面についていることができなくなったとき、お前は体を思いっきり伸ばして天に届くほど伸び上がっていたのだ。それに加えて、例のレスリングの組み合いをしたときも、偉大な奇跡を見たのだ。あれほど長く組み合っていながらお前はただ片膝をついただけだったが、相手はエッリ(すなわち「年齢」という意味)だったのだ。自分が老いたと思うほど年を取ってしまえば、誰も年齢に勝てるものはなく、みな齢に負かされて死んでしまうはずだったのにな。さあ、我々はこれで別れなければならないのだから、わしはお前に真実を話したのだ。お前がもう二度とわしと会わないというのは、お前にとってもわしにとってもずっといいことだ。わしは城を守るためなら、お前の力がわしを負かさぬよう、この次も同じような欺きの術かなにか別の技を使うつもりだ』
ソゥルは話を聞くと、ハンマーをつかみ、ぶんと振り回したかと思うと打ち下ろそうとした。しかしそのとき、ウトゥガルザ・ロキの姿はどこにも見えなくなってしまった。そこで、彼は再び東を目指してあの城を壊しに行こうとしたが、目に映るものは美しい風景ばかりで城はどこにもなかったのだ。さあ、ソゥルの味わったことについて、これ以上真実な話ができるものは決していないのだぞ」
アィギルとともに強い蜜酒を飲みながら、ブラギが語った次の物語について見ることにしましょう。
アィギルが尋ねます。「『かわうその支払い』が黄金を意味するのは何故なのでしょう?」
ブラギが答えます。「それは神々すなわちオゥジン、ロキ、ハィニルの三人が、この世を探るために旅をしていたときのこと。三人はある川に行き当たり、その川沿いに歩いているとある滝にたどり着いた。見ると、そこに一匹のかわうそが滝のそばにおり、鮭をつかまえて、薄目をあけながら、美味しそうに食べていた。ロキはそれを見ると、石を一つ拾い、かわうそめがけて投げ、石はかわうその頭に当たった。ロキは自分の成功に有頂天になった。たった一つの石を投げて、かわうそと鮭とをつかまえたのだから。神々はかわうそと鮭とを拾い上げ、その分捕りものを携えて旅を続けた。するとある農場に行き着いたので、そこに入っていった。そこに住む農夫はフレイズマルといい、権勢があり、魔術のわざにたけていた。神々は彼に一晩泊めてくれないかと尋ねた。自分たちは払うべきものには不自由していないのだから、と言って、先ほどの獲物をその農夫に見せた。フレイズマルが例のかわうそを見たとき、彼はファヴニルとレギンという息子二人を呼び、二人の兄のオッタル(かわうそという意味)が殺され、その犯人が誰かと言うことも伝えたのだった。いまやその農夫とその家族は神々に迫り、彼らを捕らえ、縛り上げると、そのカワウソについて真実を証し、それがフレイズマルの息子であったことを告げた。神々はフレイズマルの望むだけの報酬を約束して、自分たちの命請いをした。報酬について双方に合意が得られると、誓いを持って約束が取り交わされた。
そのあと、カワウソの皮が剥がされ、フレイズマルは、そのカワウソの皮の袋を黄金で満たし、外側も黄金で隙間なく埋めることを条件とした。そこでオージンはロキを黒エルフたちの世界へと使わした。ロキはアンドヴァリという名のドワーフに出会った。彼は湖の中の魚の姿をしていたが、ロキが彼を捕まえ、身代金として彼の洞穴にあるすべての黄金を要求した。彼らがその洞穴に行くと、アンドヴァリは持っている全ての黄金を運び出した。それはかなりの量であった。そのときそのドワーフは一個の小さな金の指輪を袖の下に滑り込ませた。しかしロキはそれを見て取り、それもよこせと言った。ドワーフはその指輪だけは自分から取り上げないでくれと頼んだ。それさえ手許にあれば、いくらでも富を増やすことができるからだった。ロキは、お前は一文だってやるものかと言って、その指輪も彼から取り上げ、立ち去った。するとドワーフはだれであろうとその指輪を持つものは身を滅ぼすだろうと呪いの予言を告げた。ロキはフレイズマルのところに戻り、オージンに取ってきた黄金を見せた。オージンはその中に例の指輪を見ると、それが美しいので、自分で取っておいた。それからフレイズマルとの賠償を始めた。フレイズマルはオッタルの皮に黄金をこれ以上できないというところまで詰め込むと、剥製のようにオッタルを立たせた。それからオージンはその外側を金で覆い始めた。そのあとで、フレイズマルに、皮が全て金で覆われたかどうか見てくれと言った。フレイズマルは丹念に調べながら眺めていたが、一本のひげが覆われていないと言った。これも覆われないなら、賠償は認められないぞと言った。そこでオージンは先ほどの金の指輪をとりだし、ひげに引っかけると、さあ、これでかわうその支払いは終わったぞ、と宣告した。そしてオージンは自分の槍を、ロキは自分の靴を取ると、彼らにはもう恐れるべきものは何もなくなった。その時ロキは言った。アンドヴァリの予言は今でも有効だ、金の指輪と黄金とはそれを持つものにとって死を意味するのだ、と。そしてその言葉はまもなく成就することになった。しかしこれで、なぜ詩の中で金が「カワウソの支払い」、「神々の強制支払い」、「争いの鋼」などと呼ばれるかがわかっただろう。
アィギルは言った。その金についてもっと語るべきことはないのですか?ブラギは答えた。
「フレイズマルはこのように黄金を自分の息子の命の償いとして手に入れたが、ファヴニルとレギンも自分たちの兄の命の償いとして幾ばくかを求めた。しかしフレイズマルは息子たちに一文もあげようとはしなかった。二人の兄弟は、黄金欲しさのためにその父を殺してしまうという恐ろしい所業を成し遂げた。そのときレギンはファヴニルに、黄金は二人の間で平等に分けようと言ったが、ファヴニルは答えて、自分の父親を殺しておきながら、自分の弟と黄金を分け合う筋合いはないと言い、レギンにここを去れ、と命じた。さもなければ、父フレイズマルと同じ運命をたどるぞ、と。ファヴニルはフレイズマルの持っていた兜を取ると、それをかぶり―それは「恐怖の兜」として知られていた。それを見てしまうと命ある者は全て恐怖におののいてしまうからである―、フロッティという名の剣を手に持った。レギンはレヴィルという名の剣を持ち、逃げ出した。しかしファヴニルはグニタヘイズルという荒れた窪地にいくとそこを棲み家とし、自らを蛇の姿に変え、黄金の上に横たわったのだった。
レギンはそれからテョーズという国のヒャルプレク王の許に行き、そこで鍛冶師となった。それから彼はヴォルスングの息子シグムンドルの息子であり、母をエイリミの娘ヒョルディスに持つシグルズルの養父となった。シグルズルは、全ての戦王の中で、血筋も力も勇気においても最も優れていた。レギンはファヴニルがどこに横たわるかをシグルズルに教え、そこに行って、その黄金を取ってくるように焚き付けた。その後レギンはグラムルという名の剣を鍛え、シグルズルに与えた。その剣はとても鋭く、流れる水の中に置き、上流から羊毛一筋を流すと、その剣に触れただけで毛は二つに分かれてしまうのだった。さらに、その剣はレギンの金床さえ根本まで真っ二つに切ってしまうことができた。その後シグルズルとレギンはグニタヘイズルに向かい、ファヴニルの通り道に、シグルズルは溝を掘りその中に入った。ファヴニルが水辺に降りていき、その溝の上を這って行ったとき、シグルズルは剣で刺し貫き、ファヴニルは死んだ。そのときレギンがやって来て、シグルズルが殺したのは自分の兄だと言い、その賠償としてファヴニルの心臓をもらい受けることで満足しようと言った。そこで心臓を火で焼いているとき、レギンは横になってファヴニルの血を飲み、そのうち眠ってしまった。しかし、シグルズルが心臓を焼いているとき、そろそろ焼けたかどうか確かめようとして、堅さを確かめるために指をその心臓につけると、指が焼けたので、すぐ口の中に入れた。そして心臓の血が彼の舌に付くと、シグルズルは自分が鳥の話し声が理解できることに気がついた。そしてすぐそばの木の枝でさえずる言葉の意味が分かったのである。一羽の鳥が言う:
ファヴニルの心臓を焼いている
もし指輪を授けるべき寛大な人物が 輝く命の肉塊である心臓を
食べるなら 私はその人を賢いと思うの
「あそこにレギンが寝そべっている」ともう一羽が言う
「心の中に欺きの計画
少年を一突きのつもり 怒りにまかせて
ゆがんだ話しぶりで近づき
災いの作り手は 兄の復讐を くわだてる」
するとシグルズルはレギンの許に行き、彼を殺した。それからグラニという名の自分の馬のところに行き、ファヴニルの棲み家まで乗っていった。そこで黄金を取り、ひとまとめにするとグラニの背に乗せた。自らも乗ると出発したのだ。これで黄金のことを詩の中で「ファヴニルの棲み家とか巣」と言ったり、「グニタヘイズルの鋼」「グラニの荷」と呼ぶ理由がこれでわかっただろう」
「それからシグルズルは山の上に立っている建物のところまで言った。その中には一人の女性が寝ていた。彼女は兜をかぶり、鎖帷子を身につけていた。シグルズルは剣を抜き、帷子を切り裂き、彼女から脱がした。すると彼女は目を覚まし、自分の名をヒルドゥルと名乗った。彼女は今ではブリュンヒルドゥルとして知られている女性だ。そしてかつてはヴァルキュリアだった」
ブラギはこのときは語りませんでしたが、このときシグルズルがどのようにブリュンヒルドゥルから隠された知恵を得、二人の間で愛の約束が交わされたか、また、どうしてオージンに使えるヴァルキュリアの一人である彼女が、このように寝ていたのかは、ヴォルスンガ・サガの中に語られています。しかしここでは先を進めましょう。
「シグルズルは馬をさらに進めた。そしてギューキという王の国に着いた。お后の名はグリムヒルドゥルといい、グンナル、ホグニ、そしてグズルーンが二人の子供たちだった。ゴットホルムルがギューキの養子だった。シグルズルはそこに長い間留まった。その後、彼はギューキの娘グズルーンと結婚し、グンナルとホグニはシグルズルと兄弟の誓いをした。その後、シグルズルとギューキの息子たちはブドリの息子アトリの許に行き、彼の妹のブリュンヒルドゥルをグンナルの妻にもらいたいと申し出た。彼女はヒンダ山に住んでおり、その館の周りは燃える炎で囲まれていた。彼女はその燃え立つ炎を越えて来る勇気ある男にのみ嫁ぐのだという誓願を立てていたのである。そこで、シグルズルとギューキの息子たち(彼らはその血筋からニブルングとも呼ばれていた)はその山に向かい、グンナルは炎の中に馬を駆って入ろうとした。彼の馬はゴティという名前だった。しかしその馬はどうしても火の中に入って行こうとはしなかった。そこでシグルズルとグンナルは名前と姿とを交換した。というのもグラニは自分にシグルズル以外の者が乗るのを許さなかったからである。そこでシグルズルはグラニに乗って燃えさかる炎の中に入っていった。その夜彼はブリュンヒルドゥルと婚礼をあげた。しかし二人が寝床に入るときに、彼は抜き身の剣グラムルを二人の間に置いた。そして朝になり彼は起きあがると、服を着て、きぬぎぬの贈り物としてブリュンヒルドゥルにロキがアンドヴァリから取り上げた指輪を与えた。そして彼女から記念として別の指輪を受け取った。シグルズルはそれからグラニを駆って自分の仲間のところに戻った。彼とグンナルは再び姿と名前とをとりかえ、ブリュンヒルドゥルを伴ってギューキ王の許へと帰って行った。シグルズルはグズルーンとの間に二人の子供、シグムンドゥルとスヴァンヒルドゥルをもうけた。
あるとき、ブリュンヒルドゥルとグズルーンが川に髪を洗いに降りていったときのことだ。二人が川に着くと、ブリュンヒルドゥルは土手から川に遠く入っていき、グズルーンの髪が浸かった水の中に自分の髪を一緒に入れたくはないわ、と言った。なぜなら自分の夫はずっと勇気があるのだから。するとグズルーンは彼女の後を追って水の中に入っていき、上流で髪を洗う権利があるのは私の方よと言った。なぜなら、自分の夫はグンナルよりも、また他の誰よりも勇気があるのだもの。彼はファヴニルとレギンを殺し、その二人の富を勝ち得たのだから。するとブリュンヒルドゥルはそれに応じていった。『シグルズルはあえてやろうとはしなかったけれど、グンナルは燃え立つ炎を越えたのだからそれこそずっと偉大なことではなくて?』
そのときグズルーンは笑って答えた。『あんなは燃える炎を越えたのがグンナルだと思っているの?あんたの横に寝ていた男は、この指輪を私に与えてくれたその人だと思うわ。そしてあなたがきぬぎぬの贈り物としてもらい、いまその指にしているその指輪は、アンドヴァリの贈り物と呼ばれている指輪ではないの? グニタヘイズルでそれを勝ち得たのはグンナルではないと私は思うわ』
するとブリュンヒルドゥルは押し黙り、家に帰った。このあと彼女はグンナルとホグニにシグルズルを殺すように促したが、シグルズルに対する誓いがあるので、彼らは義兄弟のゴットホルムルにシグルズルを殺すようにもちかけた。彼はシグルズルが寝ているときに剣で刺し貫いたが、シグルズルはその傷を負ったとき、グラムルをゴットホルムルに向かって投げたので、その剣は彼を真ん中で真っ二つに切った。こうしてシグルズルと、彼の三つになるシグムンドと言う息子は殺された。彼らが手を掛けたのである。その後ブリュンヒルドゥルは剣で自らを刺し、シグルズルと一緒に荼毘にふされた。一方グンナルとホグニはファヴニルの遺産とアンドヴァリの贈り物とを受け継ぎ、自分たちの国を治めていた。
その後、ブリュンヒルドゥルの兄でブドリの息子アトリはシグルズルの寡婦となったグズルーンをめとり、子どもを何人かもうけた。アトリ王はグンナルとホグニを招待し、二人は招きを受けた。しかし、二人は出立の前にファヴニルの遺産である黄金をライン川に隠した。その後、この宝物は二度と見つかることはなかったのだ。一方アトリ王は武装した兵と共に彼らを迎え、グンナルとホグニとの間に戦いが起こった。二人は捕らえられ、まだホグニが生きているときにアトリ王は彼の心臓を切り取ってしまった。これによりホグニは死に、アトリ王はさらにグンナルを蛇の穴の中に放り込んだ。しかし、グンナルにはこっそりと竪琴が与えられ、両手は縛られていたので、彼は爪先で竪琴を奏でた。あまりに見事に奏でたので、そこにいた蛇は皆うっとりと眠り込んでしまった。ただ一匹の毒蛇だけは眠らず、それは彼に襲いかかり、肋骨の下にかみつくと、そこの穴から中に頭を入れ、グンナルが息絶えるまで、肝臓にかみつきながらぶら下がっていた。グンナルとホグニはギューキング(ギューキの息子たち)あるいはニヴルング(ニヴルの一族)と呼ばれていたので、黄金のことを詩の中ではニヴルングたちの宝とかニヴルングたちの遺産と呼ぶのだ。
その後まもなくグズルーンは息子二人を殺し、その頭蓋骨で杯を二つ造り、金と銀とで装飾した。それからニヴルングたちの埋葬が行われたが、その宴会の席で、グズルーンはアトリ王に例の杯で蜜酒を注ぎ与えた。その蜜酒は息子たちの血が混ぜられていた。また心臓も料理してアトリ王に食べさせた。全てなし終わると、グズルーンは、汚れた言葉を彼の顔に浴びせかけながらことの次第を聞かせたのだった。蜜酒は強く、十分に振る舞われたので、ほとんど全てのものはそこで眠り込んでしまった。その夜、眠っている王のところへ、グズルーンはホグニの息子を連れていき討ち掛かった。そこで王は死んだのであった。二人は館に火をつけると、中にいた人々を焼き殺した。その後グズルーンは海辺まで行き、そこに身を投げて死のうとした。しかしフィヨルドの海を流された彼女はヨーナクル王の治める土地に流れ着いてしまった。王は彼女を見つけると彼女をめとり、ソルリ、ハムジル、エルプルという名の三人の息子をもうけた。三人はグンナルやホグニのようにニヴルング族の烏のように黒い髪の色をしていた。シグルズルの娘スヴァンヒルドゥルもその地で育てられた。彼女は全ての女性の中で最も美しかった。ヨールムンレックル大王は、そのことを聞き知ると、ランドヴェルという息子を使いに出し、彼女を后に迎えたいと申し出た。ヨーナクル王のところに到着した彼に、スヴァンヒルドゥルは委ねられ、ランドヴェルは父ヨールムンレックル王のところに彼女を送ることになった。父王の側近であったビッキ伯爵はスヴァンヒルドゥルをめとるのはランドヴェルこそふさわしいと言い出した。二人は若く、ヨールムンレックル王は年老いていたからである。若い二人はこの言葉をもっともだと思った。次にビッキはそのことをヨールムンレックル王に告げた。するとヨールムンレックル王は息子を捕らえ、絞首台に連れていった。するとランドヴェルは自分の鷹の羽を抜き取り、父王に献上するように命じた。それからランドヴェルは絞首刑になった。ヨールムンレックル王がその鷹を見たとき、その鷹が、羽もなく飛べないように、自分の王国も自らが年老い、なおかつ世継ぎの息子がいないので望みがないことを悟った。するとヨールムンレックル王はことを図り、自分の家来と共に森に狩に出かけた後、スヴァンヒルドゥル王妃が座って髪を洗っているところに馬で駆けていき、自分の馬の蹄で彼女を踏みつけ死に至らしめた。グズルーンはこのことを知ると、息子たちにスヴァンヒルドゥルの復讐をするように促した。彼らは出立の準備をし、彼女は丈夫で鉄でも刺し貫けないような帷子と兜とを与えた。それからグズルーンは息子たちにどのようにしてヨールムンレックル王を倒せばよいか指示をした。夜に王が寝ているときに襲撃し、ソルリとハムジルは王の両手両脚を切り取り、エルプルが頭を切り落とすのだと。しかし彼らが出発した後で、エルプルに二人の兄は尋ねた。ヨールムンレックル王のところに着いたら、お前からはどんな助けが得られると言うのだ?エルプルは答えて、腕が脚を助けるように助けるのだと言った。兄たちは腕によって脚が支えられることなどあるものか、と言った。自分たちの母親は自分たちを侮辱するような指示を与えてくれたものだ、と兄たちは怒り、母親がもっとも悲しむようなことをしてやる、と言い、エルプルを殺した。母親は弟を一番愛していたからである。少し後になって、ソルリが歩いているとき、足を滑らせたが、腕で体を支えて倒れなかった。その時ソルリは言った。『いま腕も脚を支えることがわかったぞ。今でもエルプルが生きていれば良かったのに』
そして彼らがヨールムンレックル王のところに夜になって着いたとき、王が眠っている間に二人は王の腕と脚とを切り落とした。すると王は目を覚まし、家臣たちを呼び、目を覚ませ、と叫んだ。そのときハムジルが言った。『エルプルが生きていたなら、いまごろは頭も切り落とされていたのに』そして王の家臣たちが起きてきて、二人を攻めた。しかし二人にはかなわないことがわかったとき、ヨールムンレックル王は石で打て、と命じた。二人は石で討たれ、ソルリとハムジルはそこで倒れた。このようにしてギューキの一族は今や滅んだのである」