|
|
 |
吉見町で発見された古代官道と思われる遺跡は以外にも低湿地帯を通っています。古代官道の遺跡としても低湿地帯は類例が少なく。研究者の間でも注目されているようです。ただ、従来想定されていた所沢市から坂戸市までのルートがほぼ直線でトレースできるの対して、今回発見された吉見町の遺跡にそれを繋げるとなるとどこかで方位の変更が必要になりそうです。
吉見町の遺跡の詳しい内容はこちらをご覧ください。 |
|
| 東松山市古凍のおくま山古墳(熊野神社古墳) |
|
|
 |
吉見町で発見された古代官道と思われる遺跡は以外にも低湿地帯を通っています。古代官道の遺跡としても低湿地帯は類例が少なく。研究者の間でも注目されているようです。ただ、従来想定されていた所沢市から坂戸市までのルートがほぼ直線でトレースできるの対して、今回発見された吉見町の遺跡にそれを繋げるとなるとどこかで方位の変更が必要になりそうです。
吉見町の遺跡の詳しい内容はこちらをご覧ください。 |
|
| 東松山市古凍のおくま山古墳(熊野神社古墳) |
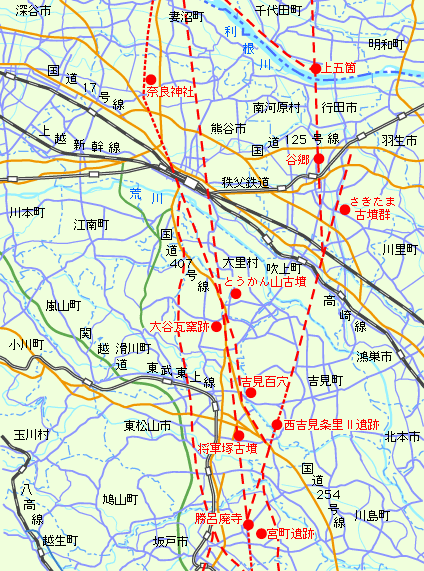 |
||
横塚山古墳 利根川の渡河点 刀水橋の南の妻沼町には、かって妻沼と男沼という二つの沼があったそうです。その間には「台」と称する微高地が伸びていて、台の集落付近が武蔵国府から数えて五番目の駅家があったと想定されているようです。 妻沼町の字境の道 |
|||||||||||||||||||
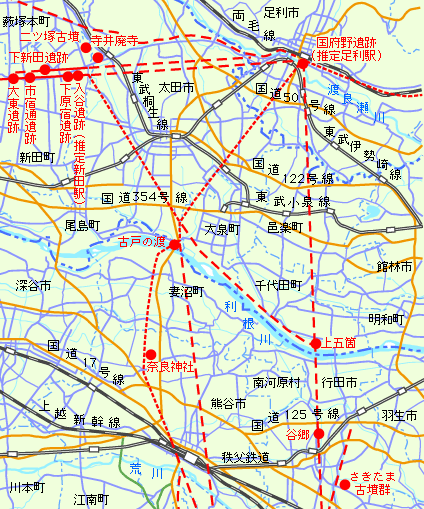 |
||
|
利根川に架かる刀水橋の群馬県側は西に石田川が北西から流れ込み、東には小河川が北東から流れ込んでいて、ちょうど逆三角形のように張り出した台地になっています。この台地の先端が群馬県側の渡河点と考えられています。その逆三角に突き出た台地の中央を北に延びる道が存在します。その道は太田市と大泉町の境になっていて、この道が東山道武蔵路ではないかと考えられているようです。 足利への道 この道は大泉町古氷までしか現在していませんが、この道の延長ライン上に近接して太田市竜舞の賀茂神社が存在し、この神社は『上野国神明帳』山田郡の従三位加茂明神に比定されています。 そしてこの道の延長ラインは足利市の国府野遺跡に達しています。国府野遺跡は足利郡家の可能性が高いと考えられている遺跡です。また遺跡の付近には東山道足利駅があったことも想定されているようです。
武蔵国は『続日本紀』の中で宝亀2年に東山道から東海道に所属替えされていることは何度も語ってきました。宝亀2年以後は東山道は武蔵国府へ向かう必要がなくなったわけです。そのことは上野国新田駅から下野国足利駅へ直接向かうようになったのです。 ここで上野国の東山道本路と推定される、牛堀・矢ノ原ルート以外の道路遺構を上げて置きます。新田町市で調査された下新田遺跡は牛堀・矢ノ原ルートの北500メートル付近に並走する道路遺構が検出されています。両側溝間の心々距離12メートルで硬化面も確認されています。この道路遺構の時期についてはハッキリしていないようですが、天仁元年(1108)の浅間噴火以前の遺構であることはわかっているようです。 この下新田遺跡のルートの東延長上に新田郡家に推定される天良七堂遺跡があり、その付近には新田郡寺と推定される寺井廃寺も存在します。この500メートル北の道路遺構と牛堀・矢ノ原ルートの関係はわかっていないようです。何故そんなに離れていない付近に幅12メートル前後の道が二つも存在したのでしょうか。今後の研究でその謎が解明されるのを待つのみです。 おわりに 鎌倉街道のホームページを作成している人間が、古代官道の旅を追いかけていたら、鎌倉街道に係わり深い生品神社に辿り付いたことは、何か因縁めいたものを感じないわけでもありません。私は生品神社の大きな鳥居の前で新田義貞が活躍した時代には東山道武蔵路は断片的にも存在していたのだろうかと、ふとそんなことを考えているのでした。 |
|||||||||||||||||||