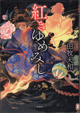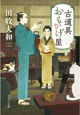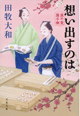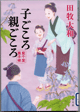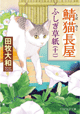| 「紅きゆめみし」 ★★ | |
|
2024年09月
|
時代小説版ホラー・ミステリ。 舞台となるのは、<八百屋お七>事件の後、間もない頃。 吉原の花魁=紅花太夫が稲荷神社で見かけた、禿と思える幼女、それは火刑に処せられたお七の亡霊なのか。 その紅花太夫の贔屓客の一人が、市村座の人気女形である「荻島清之助」こと新九郎。 新九郎、ちょうど立役者と揉め舞台から遠ざけられている処。紅花太夫から頼まれ、「七」と名乗る幼女の謎解きに挑みます。 「お七様」事件の謎解きはやがて、八百屋お七の事件に遡り、そして妖しい様相を見せ始めるのですが・・・。 探偵役を何故役者に設定したのか、というと、役者たる者、人の嘘を見破るのに長けているから、ということらしい。 役者、それも女形を主人公とした事件ものというと“濱次お役者双六”シリーズが思い浮かびますが、「長屋狂言」を最後にだいぶ時間が経っています。 今回、荻島清之助という新しい女形を登場させたのは、紅太夫に見劣りしない女形を主役に据える必要があったからでしょう。 田牧さんの上手さが冴えわたる斬新な時代ミステリ。お薦め。 序−燃える/太夫−紅い禿/幕間−芝居/女形−吉原漫ろ歩き/太夫−怪談/女形−朱華の帯/太夫−祟り/女形−狙われる/太夫−悋気/格子−幻/女形−思案/太夫−噂の矛先/女形−月桃の出どころ/太夫−太夫道中/女形−謎解き/結び |