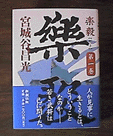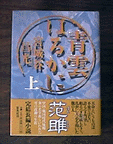|
|
|
|
|
2.晏子 3.孟嘗君 4.楽毅 5.青雲はるかに 6.太公望 7.華栄の丘 8.子産 9.沙中の回廊 |
|
|
|
三国志(第5~12巻)、孔丘 |
| 公孫龍(巻一)、公孫龍(巻二)、公孫龍(巻三)、公孫龍(巻四) |
|
●「重 耳」● ★ |
|
|
|
春秋時代の晋の文公・重耳の遍歴の物語。各国の興亡を綴った作品という
印象があります。 |
|
●「晏 子」● ★★ |
|
|
|
春秋時代の斉における晏弱・晏嬰父子の物語。 |
|
●「孟嘗君」● ★★☆ |
|
|
1995年
|
全5巻を熱中して読みました。 全5巻といっても、最初の2巻はこの風洪が主人公として活躍します。 ただ、ストーリイとしては、でき過ぎた印象のある田文より、はるかに風洪の方が魅力的です。人間としての成長プロセスの大きさ、行動範囲のきわめて広い風雲児、快男児的な部分。また、生身の人間としての魅力。 司馬遼太郎さんは「国盗物語」において、斉藤道三、織田信長という2人をひとつの流れとしてストーリィ化しましたが、本作品も、風洪、田文という2部からなる長編として読むのが良いのかもしれません。 |
|
●「楽 毅」● ★★☆ |
|
|
第1・2巻:1997.09 2002年4~5月
|
宮城谷作品の中でも「孟嘗君」と並ぶ傑作と言って良い作品だと思います。 本作品における面白さのひとつは、戦争の描写が豊富で、その駆け引きがすこぶる面白いこと、さらに楽毅の持つ戦術思想にあります。 一般に人がとらわれるであろう、国家とか人間関係、自己の利害というような枠を、楽毅という主人公は軽々と越えていきます。その発想・行動の自由自在な様は、まるで飛翔するかのようで、清々しい限りです。 なお、第1・2巻は、中国中原における小国・中山国の滅亡、その中で楽毅らが最後まで戦いを
貫く部分。そして第3巻は、第4巻へのつなぎとなる部分。 |
|
●「青雲はるかに」● ★ |
|
|
2000年12月 2007年04月
1997/12/27 |
時代・場所の設定は、孟嘗君、楽毅が舞台の中心から去った後の、魏、そして秦。前述の二人が退場したことから、再び諸国は乱立
しているという様相。 宮城谷節は相変わらず。ストーリィの中に吸い込まれるようにわくわくして読み進んでいきました。でも、読み終わった後にちょっと振り返ると、率直に言って、ちょっと物足りない感じ。宮城谷作品は、言葉によって登場人物、ストーリィを膨らませて読者を引き込んでいくようなところがありますから、読んでいる最中には感じる事なく面白く読んだのですが、読了後にそう感じました。 范雎についてのみなら、若い頃から辛苦を重ね、それと共に人間としての成長を重ね、ついに栄達を果たすという敬愛すべき人物の物語なのでしょう。でも、ちょっと離れて見るならば、所詮若い頃から自分の成功のみを考えて生きてきた人物であり、宰相の地位を得たものの、主君に抜擢の成果をもたらすべく攻略により領土の拡大をめざすこととなった。それは一国の利益でしかない。 貧民からの成功物語、というならば、確かに范雎の成功が精々なのかもしれません。 |
|
●「太公望」● ★★ |
|
|
2001年04月
1998/05/20 |
周王の功臣として商(殷)を倒し、斉の始祖となった太公望・呂尚の物語。 上巻はプロローグと言って良い。商(殷)王朝の説明と時代背景。この時代が、孟嘗君や、楽毅、呂不韋の頃と違ってはるかに遡る頃のことでしたから、ちょっと戸惑うところがありました。 中巻に至ると、望の動きは商打倒に向けての具体的な活動となります。商に反発する諸侯の間をめぐり、いろいろな献策を行うと共に自分の配下も増えていきます。 下巻は中巻の産物として、物語の決着具合を確かめるようなもの。太公望の伝承話を通過し、周王に招聘された後の望はもはや全知全能のスーパーマンの如き者。商が衰退し周が勝利するまでの展開は、望が描いた筋書きどおりに進む。読む興味としては、歴史の大転換の様を知るだけと言っても良い。 |
|
●「華栄の丘」● ★☆ |
|
|
2003年03月 |
春秋時代、「重耳」から少し後の小国・宋が舞台。 華元は、新君主・文公に召し出されて宰相の地位に就きますが、文公と共に善い内政を行う一方で、後半楚の外憂にさらされる、というのが本作品の主要な流れです。 華元という人物のイメージがぼんやりしている分、読み手によって随分とこの作品に対する評価は異なるように思います。私としては、楽毅の自由自在、迅速な行動に魅せられたばかりですので、華元については辛めの評価となりました。 |
|
●「子 産」● ★☆ 吉川英治文学賞 |
|
|
2003年10月 |
晏嬰、華元と同時期の春秋時代、鄭において“礼”により国・民に仕えた名執政・子産を描いた物語です。ちなみに、子産は、周公旦(周・武王の弟)と並んで孔子が尊敬した人物だそうです。 父子2代にまたがる物語という構成で思い出すのは、「晏子」の晏弱・晏嬰父子。父が武にて活躍した人物であったのに対し、子の側は宰相の地位を極めたという点で、両作品には共通するところがあります。 子産という人物からは、爽やかな印象を受けます。子産は武においても評価された人物ですが、広範な知識をもつと同時に、公平な見方ができ、言葉を飾らず率直にもの言う気概をもっていること、自家の利益に固執せず、真摯に国と民に尽くそうとした姿勢から、感じられるものです。 |
|
●「沙中の回廊」● ★☆ |
|
|
2003年01月 2004年12月 |
「重耳」亡き後の晋において、天才的な戦略家として名を馳せ、最後は宰相にまで登りつめた士会の生涯を描いた作品です。 ただ、この士会という人物は、出自が高くなかった所為もありますが、強引に自分を売り出すタイプではなかったようです。 その分本ストーリィも、士会中心というより、その殆どは重耳亡き後の晋の混乱の歴史であり、士会はその歴史の検証者として理解することもできます。 王位継承をめぐる晋の混迷から、士会は秦に亡命し、そこで戦略家としての名声を高めますが、その辺りが読んでいて快い箇所です。宮城谷作品をずっと読んでいて、爽やかな印象が残っている人物というと、風洪、孟嘗君、楽毅と、いずれも国という枠に嵌められていない人物。士会もそれに列なる人物のようで、そこに魅力を感じます。 また、士会は、礼と徳を重んじ、それを為政という大きな場で表現した人物であり、そうした人物は一世代後の子産しかいない、と宮城谷さんは作品中で語っています。ただ、士会がそれを発揮できるのは、漸く最後の方。 士会という人物に魅力はありますが、ストーリィは殆ど重耳亡き後の晋の混迷の経緯であり、春秋という時代、王・宰相の人物如何によって国の威勢がいかに変わるものか、ということがつくづく感じられる作品です。「重耳」の続編として読むのも良さそうです。 ※宮城谷作品お馴染みの人物の名が多く登場するのも、目を惹かれるところ。介子推、華元、子産、晏弱等。 |
宮城谷昌光作品のページ №2 へ 宮城谷昌光作品のページ №3 へ