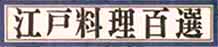魚河岸(うおがし、略して河岸『かし』)!
魚河岸を辞書で調べると、産地から送ってきた魚貝を競り売りする市場の事をいう。
現在、東京築地にあるのをさし、商売人の間では河岸という略称で今も呼ばれている。
江戸の魚河岸は、江戸初期から関東大震災までの間、日本橋北詰の東側と芝の海岸(芝浜)にあった。
江戸湾でとれた江戸前の魚介、押送(おしおくり)船という八丁櫓の高速輸送船で集められた魚介も、そこへ集められ、そこから江戸市中に売られていった。
小売商は、固定店舗の商人より多く、天秤棒の両側に桶を吊って売り歩く「振売り」と呼ばれる行商人が主流をしめ、一心太助のような威勢のいい魚売りが多く見られた。
この「振売り」は「棒手振」とも呼ばれ、いつも決まった時間帯に来るので時報の役割も兼ね、「売り声」は季節を感じさせる風物詩でもあった。
しかし、新鮮な生の魚を早く運送するにも、長く保存するにも難しかったので、干魚や塩魚の加工した商品がほとんど、江戸の近郊でも鮮魚が食べられるのは大変だった。ただし近くに川が流れていれば、汚染の心配もなく川魚は豊富にとれた。
魚の振売り!
いわし売り 「エ、いわしこい。エ、いわしこい」
しじみ売り 「しじみよー、しじみよー」
鯉売り 「コイやまい、コイやまい」
刺身売り 客は器を持ってくる。器のない者にはアワビの殻に盛った。
乾魚売り 「ひもの」または「ひうお」。塩魚や干魚を売った。
うなぎの蒲焼売り
上方では、うなぎを道路ばたでさいて焼き売る。江戸では焼きあげたものを岡持ちに入れて売り歩く。
鮮魚売り
秋刀魚売り
※引用:『たべもの江戸史』(永山久夫著)新人物往来社
魚のランク!
嘉永二年(1849)幕末の頃、千馬源吾・豊兆楼主人の著『年中番菜録』には、精進の番菜は上品、魚類の番菜は下品になりやすいと書かれている。当時茶の流行によって客にもてなす料理には生臭を避け、野菜の類も鰹節をけずって、味をととのえるのを上品と考えていた。
『和漢三才図会』(東洋文庫)にも、秋刀魚は下魚とされ「魚中の下品」とある。
この他にも下品な魚とされているのは、いわし、サバ、アジなどの「青肌の魚」、こはだ、まぐろ、鮫。ふぐ、あいなめ、むつ、ふな、どじょう、かき、あさり。
その中でも最たる下品はいわし、秋刀魚。兼好は鰹のことも下品とした。また下品な魚は、将軍様のお食事にはタブーとされた。
上品な魚とされていたのは、鯛、海老、鯉、鮎、すずき、きす、うなぎ、しじみ、赤貝などがある。
※参考文献:
『大江戸えねるぎー事情』(石川英輔著)講談社文庫
『古典料理の世界』(吉川誠次著)日本書籍
『落語にみる江戸の食文化』より『権力者と「食」の政治学』(小田晋著)河出書房新社
|