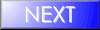
【本読み・読み合わせ】《本読み》「本読み」は、作家や演出が、役者やスタッフに台本を読んで聞かせるという儀式で、 へたをすると江戸歌舞伎なんかから継承した、伝統儀式かとも思ってしまう。 作家が自分の書いた戯曲を読んだって、一語一句その通り舞台でやるわきゃないし、またやれるはずもない。 それに自分の書いたものだって、絶対一言も間違えずに読めるという作家もいないだろう。 間違えたら「その間違えた通りにやれと言うのかい」と、つっこみを入れたくなるのは私だけではないだろう。 もし作家が、「舞台化するなら一語一句戯曲通りにやってくれ」というなら、一度自分で舞台を踏んでみれば良い。 毎日変わる舞台の中で、同じ芝居ができるわけがない。 そんなに同じ芝居にしたけりゃ、映像作品に脚本を売りなさいと言うまで。 役者が演出にしゃしゃり出て、演技指導か演出かわからないモノは別にして、 芝居の下手な演出が本をみんなの前で読んだって、屁のつっぱりにもならない。 本読みというのは止めにしよう。 しかし、第一回目には、演出が戯曲を通して読むことが普通になっている。 なぜなら、そのときまでに演出は、その劇の一番主要なものを知っているはずだし、 ポド・テキストもわかっているし、劇全体のリズムもわかっているからだ。 それらの特質を役者に伝えるためにこの本読みをする。 だからといって、演出は特別に意気ばって『演ずる』ようなことをしてはいけない。恥の上塗りになる。 ふつうにわかりやすく読み、正確に内容を伝えなければならない。いまは漢字の読みも演出の責任だ。 万が一、役者から質問があったら答えていくことも大切な仕事だ。 続いて、演出が戯曲についての構想を説明するのも大事な行事だ。 同時に戯曲について演出の研究したこと、作者のこと、時代のことなどを説明する必要がある場合もある。 また役者との間で戯曲の再検討をするのもよい。 演出が戯曲についてすべて分かっていることの方が少ない分けで、演出も本音は分からないことばかり。 役者と話し合って、戯曲の問題点を分け合って、個々に調べて報告した方が手っ取り早い。 演出ばかりではなく、役者もスタッフも戯曲の全体像がわからなければ、ただ台詞に声をつけたという結果に終わる。 戯曲の協同分析のやり方を取り入れて、課題、例えば登場人物の家の近所の様子とか、登場人物のこれまでの経歴とか、 この戯曲の書かれた時代の社会的事件とかの問題を、各人分け合って皆の集った席上で報告し、 それを皆で考えるようにすればいい。 そうすれば演出だけの説明によるテーブル稽古でなく、全員の意見が活発になる。 この戯曲はどういうテーマで書かれていて、そのテーマの中で登場人物はどういう役割りを持ち、 その人物たちのどういう行動によってこの戯曲のテーマは展開していくのだという目標をつけ、 その人物たちがおこす事件は、この芝居全体の展開のため、どういう役割りと位置を占めているかを明らかにしていく。 演出がこの戯曲をどのように演出したいかを詳しく述べてしまうと、後で実際の舞台化の際に演出が大恥をかくばかりでなく、 役者からの質問も少なくなり、創造の場として嫌な雰囲気になる時もあるから要注意。 演出の考えていたことが、役者の考えていたことと食い違っていることがあるが、それが当たり前。 演出は意地になって自分の主張を通すようなことをせず、いい点はどんどん取りあげ、変なところはよく説明して納得させ、 演出のイメージをもっと鮮明に明確にしていかねばならない。 大事なことは、演出は戯曲を読んだときの第一印象だけを大事にして、論争するということを避ける。 できるだけ戯曲に即して「ここにこういう台詞があるから」とか「こういうト書きがあるところをみると」とか確かめながら、 この戯曲にはどんなことが書いてあるか、どんな事件が起こっているか、そのためにどんな行動がなされているかを論議していくこと。 演出が自戒しなければならないのは、戯曲の第一印象と舞台化された後の印象とは、結婚前と結婚後のようなものだということ。 《読み合わせ》 一般に「読み合わせ」は、戯曲についての研究があらかた済み、戯曲の中心になっている行動がはっきりし、 各登場人物の占める位置と各人物の社会的な、また家庭的な環境も明確になり、 それぞれの人物の性格が各役者にのみこめたときに実施するものらしい。 戯曲の研究が済むのを待っていたら、何時稽古が始められるか分からない。 読み合わせそのものは、仮の配役で(演出にとってはこんなんかな?という配役で)本を持って、 座ったまま読み合わせていくもので、演出が漢字の読めない役者を虐められる楽しいひととき。 別段読んだ通りに芝居が仕上がるはずもなく、シーン割りやピース割りを、みんなに分かってもらうチャンスにする。 また、台詞ナンバーの間違いも(昔はひとり一人が自分の台本に番号を振っていたから、よく間違えた)チェックするいい機会だ。 もっとも読み合せでは、ただ単に台詞を声にしてみるというのではなく、作者の言葉を理解し、台詞を正しく言葉にする。 現代の話し言葉を書ける作家が少ないことと、作家の独りよがりの言葉が、 本来どういう会話を考えて書かれたかを推理するのも楽しみだ。 もっとも大事なことは、その台詞を口にしたときには、相手にその台詞が要求している刺激を与えるように話しかけること。 働きかけがない台詞は自分だけのひとりよがり。 侮辱したり、軽蔑したり、阻止したり、なぐさめたり、ほめたり、することを話し方で相手に伝える。 それがないと、劇の根本的な成立条件である対立ということがなくなって、二人が勝手に朗読しているのと同じ結果になる。 戯曲の言葉の内容やその前後から指し示す流れを正確に伝えるよう努力すべきだ。 そのためにもポドテキストの発見が大変重要な仕事になってくる。 《素立稽古》 台本を持たずに覚えている台本の流れ(時系列的な事件の数々や提示しなければならない事実)を、 俳優が自分の思い付いた言葉で、『事件を起こし事実を提示する』立ち稽古に入っていく。 これを「素立ち」と呼ぶ。 稽古日程に余裕のある時には、自分達の言葉で幕まで追っていく通しをし、ダイナミックな芝居を生み出せる。 やってみれば分かるのだけれど、台本の台詞を使わずに、自分の言葉で事件や事実を生み出すと言うのは、 丸ごと本を呑み込んでいかなければ、なかなか出来ない。 結局台詞を使った方が簡単なので、俳優に台詞の利用の仕方が十分に理解されるようになる。 つまり台詞と言うのは、台詞を言うために芝居をするのではなく、自分が芝居を作るために利用する道具だ。 時間が余れば、台本の稽古とは別に、台本の中の状況(事件と事実)を抽出してエチュードを試みる。 稽古日数が少ない時は、読み合わせを1回行ってから、本を持ったまま立ち稽古に入る。 稽古時間が20時間過ぎる迄には、本を持ったままでも、スムーズに通し稽古が出来る状態が望ましい。 《台詞を覚えて、通し稽古》 毎回の稽古で、最初に一度通し稽古をして、それから小返し稽古に入る。 特に、場面を動かす言葉や行為の前後や、登場人物の基本姿勢が表現されている言葉や行為を注意して観る。 そのうち、俳優の変な動きが感じられるようになる。 例えば怒るようなやりとりではないのに急に怒り出したり、立ち上がるような動機が生まれるはずはないのに 立ち上がったりするような過剰な対応、 あるいは台本上では泣いているのに泣けないやりとりなどの過小な対応など、 起きるべき事件が起きないで、提示されるべき事実がなにも明らかにされないという、表現の混乱に遭遇する。 演出は落ち着いて、起きない事件や提示されない事実を調べてみよう。 起きない事件や提示されない事実の時系列上数分前の事件や事実を確認すると、 もしそれが支障なく表現され展開されていたとしても、その結果が起きない事件や提示されない事実に繋がるとしたら、 数分前の事件や事実の表現が必ず間違った方向に行ってしまっている。 演技の事件と事実は因果応報の原則に則って、観客と共有するリアリティを構築していく。 それをご都合主義的になおざりにすると、観客の支持を得られない芝居ごっこになってしまう。 またよくあることで例えれば、「山田さん」とAに呼び掛けるBの台詞が「山村さん」になった時、 Aは「ハイ」と答えるべきかどうか。 既に交わされている会話の中で間違えたなら、「なに言ってンダイ、おれは山田だよ」「失礼、山田さん」と かえすのも一つの方法だろう。 台本から大きく脱線しても、起きてしまった事件と事実を、台本の軌道に戻す努力も必要だ。 《情動の整理》 実生活と言うのは、それほど感情豊かに過ごされている分けではないから、泣いたり笑ったり怒ったり、 30分の間にキラキラと情動の変化があるわけない。 しかし芝居の場合は、ピースごとに泣いたり笑ったり怒ったり忙しい話だ。 だからと言って、実生活に即したようなクソリアリズムはつまらない。 要はキラキラとした情動の変化が嘘っぽく見えずに、観客の支持を得られればいいのだから、 情動の変化する切っ掛けを俳優も観客も納得できるものにすればいい。 それを担うのが「ポドテキスト」だ。 台詞から推理した登場人物の心理と情動(感情の動き)が、具体的な行為としてあらわれる時、 「立ったり歩いたり、あるいは言葉として表面化する」のが、演技そのモノだ。 何の変哲もない言葉が怒りや悲しみを喚起するには、明瞭なポドをもった表現が必要になる。 ポドをしっかり表現できると、シーンの色合いをどのようにも変化させることができる。 キラキラとした芝居を創るためには、情動の喚起と整理の為のポドテキストを正確に理解し表現できることが必要だ。 《テンポリズムの整理》 どうも私達はナマケモノに出来ていて、一度成功したやり方や流れを中々改良することが出来ない。 俳優の演技も同じで、なんとなくうまくいった手ごたえがあると、そのテンポリズムから抜け出そうとしない。 大方の芝居は音楽と同じで、プロローグ・場面説明・情感の盛り上がり・エピローグと移っていく。 まさに音楽と同じように、様々なテンポリズムの変化が、芝居の起承転結・序破急をつくり出している。 テンポリズムをかもし出すのは俳優の仕事なのだ。しかしテンポリズムを変えたがらないのも俳優だ。 音楽的な用語で「追い上げ」という言葉がある。 機関車がゆっくりと走り出して全速力に至る過程を再現するかのような、テンポリズムの変化だ。 この追い上げがまさにぴったり来る場面が、オセロがイア−ゴと語りながらデスデモウナの不貞を確信する時だ。 芝居がドラマとして大きく展開(転回を使いたい。ドラマが広がるのではなく、ドラマの方向が激変する)する瞬間に、 これほどマッチする表現様式も少ない。 歌舞伎の台詞の「さあ!?」「さあ?!」「さあ?」「さあ!」「さあ?」「さあ!」という掛け合いと違って、 台詞とポドと行為が一体となって、登場人物のスーパーテーマがコペルニクス的転回をするような、 大きな表現に結びついている。 しかしこれは「物言いの訓練」を受けていると出来ないものだそうだ。 日本語は単音1拍で発声されるから、できるだけ単調なリズムで一定の音程で話す方が聞き取りやすい。 私はよく「アナウンスじゃないのだから」と、発声発音のうまい俳優に注意するが、台詞の聞き取りやすい俳優程、 演技が単純・単彩・モノクロになりやすい。 独特の言い回し(言葉の話し方)があって、それが一つの様式にまで固まっているらしい。 しかし、言葉は生き物で今の若者達の言葉を10年前の若者が理解できるかといえば、おそらく不可能だ。 私は女子高校生の会話が、宇宙人の会話のように感じる。なを、男子高校生の会話には、なんとかついて行ける。 言葉のテンポリズムもその時代のリアリティで大きく変わっている。 老人が創って老人が演じる老人の為の芝居なら、言葉のテンポリズムが変化しなくてもよいのだろうが、 時代を映す鏡としての現代劇・ストレートプレーならば、その時代のテンポリズムを使いこなす必要がある。 特に単彩化した演技には、大胆なテンポリズムの変化を取り入れるとまさに劇的に芝居が変わるから、 場面とタイミングさえ注意すれば新鮮な演技を保つための演出の技術としては有効な手段だ。 《ミザンスツェーナの整理》 舞台上の俳優達の行為の軌跡をミザンスツェーナと呼ぶ。そこには情動の軌跡も含まれる。 しかしここでは単に舞台上の俳優同士の位置関係を考えよう。 俳優の動きがどうもぎごちなくしっくりこない時には、大胆に様々な動きに挑戦してみよう。 稽古場でどれだけ試行錯誤をくり返しても、本番に俳優が肌にあう動きができれば一番なのだから、 演出は自分のプランにこだわらず、俳優とともに考えながら動きを研究してみよう。 上手に行く、下手に行く、座る、立つ、総てに理由がなければならない。 だから無理矢理椅子に座ってみる、立ってみる、下手へいってみる。 その結果、どうすれば椅子に座ることができるのか、立つことができるのか、下手へ行くことができるのか、 俳優は考えなければならない。これを行為の正当化という。 演技は目的を持った行為の集積だから、その行為を、目的を持った行為の結果でありかつまた 次の行為の原因ともしなければならない。 つまり必ず正当化する必要がある。「なぜ、椅子に座るのか、なぜ下手に行くのか?」。 結果として、その動きをするために事前に何をしなければならないかが判明する。 ひとつの新しい試行された動き・行為は、その行為の実施される前の芝居に影響を与えて変化させ、 さらにその行為の後の芝居も大きく変えていくから、行き詰まって打開の方法が見つからない時には、 ト書きやポドテキストや言葉の勢いを利用して、行為すわなちミザンスツェーナを変えてみる。 ところで、ミザンスツェーナを変えると、変えた所ばかりでなく、 もっと前の段階からそのミザンスツェーナのために布石を打たなければならない。 演出も俳優も次の稽古に注意しなければならない。 大抵、ミザンスツェーナを変えた日の稽古は、その変えたシーンで終わってしまうから、 その前のシーンの稽古は次の稽古日にまわされてしまう。 そうするとシーン同士のミザンスツェーナの整合性がとれないまま本番を迎えるような、 悲惨なことも発生しやすい。 演出は、自分の記憶力を当てにしないで、稽古予定帳に、何を注意して稽古するかを必ず書き留めて 稽古場に入るようにしたいものだ。 |
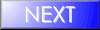 |
次へ |
| 隠居部屋あれこれ |
| 演劇ラボ |