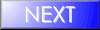
『あらためてスタニスラフスキー』高山図南雄 (たかやま・となお)演劇と教育 1995年No.475 1996年 No.479までの連載をまとめました。 日本の戦中・戦後のこと はじめに 「追っかけ」という言葉がはやっている。息せき切って追っかける。男を追っかける、 女を追っかける、芸人を追っかける、どこからか来た演出家を追っかける。 とにかくなにかを追っかける。ひょいと若者の手帳をのぞいてみた。持っているのは30分刻みの日程表のある能率手帳。 なんとその手帳がびっしりとスケジュールで埋まっている。トレンディな若者というわけだ。 「忙しいんだね」 「ええ。みんなそうですよ。でも忙しくしてないと不安なんです。とり残されたような気になって」 「ところで野暮な質問かもしれないが、スタニスラフスキーって知ってる?] わたしは若い俳優たちにきいてみた。案の定首をかしげると「さあ?」という答えがかえってきた。 でも、そのなかの一人がこう言った。 「あれ、もう古いんじゃないですか」 「ほう。それはまたどうして?」 「たまたま本を読んでいたら、スタニスラフスキーは自然主義的で、日常的なリアリズムしかやれない、 と書いてありましたよ」と一冊のトレンディな本をさし出した。 よく聞く意見だ。スタニスラフスキーがまだ若かった頃からくり返し吹聴されているのだから今さら驚くにはあたらない。 でも、そうした単純な結論でケリがつくのだったら、どうして世界が今日にいたるまでその業績を評価し、 これに学ぼうとするのか説明がつきかねるのだ。 でもまあそうした議論はいずれゆっくりやることにしよう。今は世界の文化遺産に対して抱く若者たちの軽ーい考えに答えて、 少しばかりスタニスラフスキーについて述べてみたい。 ★★ 戦後のスタニスラフスキーのブームは焼け跡の中から始まった。その頃若者たちはみな飢えていて狼のような眼をしていた。 彼らにあるものは唯、自由だけ。日本の新しい演劇を創り出そうという野放図な野望に燃えていた。 その指導者には岡倉士朗、八田元夫、下村正夫、三島雅夫など多くの専門演劇人がいた。 この人たちも若者たちに負けず劣らずエネルギッシュな活動を続けた。当時岡倉士朗の文芸助手だった牧原純(ロシヤ演劇研究家)は言う。 「いや、岡倉先生はすごい勉強家だったよ。ロシヤで出た新しい文献を、ぼくより先に知っていて、尻を叩かれながらつぎつぎに翻訳したものだ」 岡倉士朗といえば、どちらかというと感性派の温和な演出家というイメージが強いのだが、決してそれだけではないことを知らされた。 勉強家という点では八田元夫や下村正夫も同様だ。八田元夫の助手をしていたわたしも アメリカ占領軍の図書館から借り出したロシアの演技論の翻訳に追われていた。 スタニスラフスキー派の指導者たちは、一方で新しい理論を学習しつつ、 同時に現場での実践に移しかえるというおそろしく困難な離れ業を強いられた。 先駆者の宿命であろう。 スタニスラフスキーの方法が実践の現場に生かされたのは、たしかに戦後のことであるが、理論の一部はそれ以前にも紹介されていた。 昭和12年『俳優修業』の一部が杉山誠、山田肇の翻訳で雑誌『劇と評論』に発表された。 中断後山田肇訳で雑誌テアトロに連載されはじめたのが1938年(昭和13年)、ちょうどスタニスラフスキーが死んだ年だ。 当時の状況を岡倉士朗はこう述べている。 「演劇芸術の素材たる俳優とその演技の問題がぼつぼつとり上げられ始めた。 しかしスタニスラフスキーのいうような俳優が演劇芸術の中心であるとする考え方は片鱗もなかった。」(『昭和10年代の新劇』〈文学〉) 戦前のテアトロに連載された『俳優修業』を今読み返してみると、用語の問題をはじめいろいろと分かりにくい点もあり、 現場の演劇人にとっては、まだまだ縁の薄いものだったようだ。 それでも岡倉士朗をはじめ限られた演劇人の間にスタニスラフスキーについての関心が高まりつつあったことはたしかである。 岡倉士朗は1940年(昭和15)治安維持法違反で二度目の検挙にあうのだが、そのときの検事調書の中に次のような個所がある。 「脚本朗読ノ研究会ヲモチ私ガ中心ニナッテ真船豊作『小サナ町』、チリコフ作『町ノ家ニテ』ヲテキストトシテ研究致シマシタ。 研究ノ目的ハ技術二未熟ナ演技者ニ脚本ノ読ミ方、役ノツカミ方、ソノ表現ノ仕方等ヲ、 スタニスラフスキーノ演技術ニ従イ勉学スルコトデアリマシタ。」 スタニスラフスキーの研究会をやっても検事に詰問される時世だから、よほどの決意がいったことだろう。 ちなみに、1943年(昭和18年)までに治安維持法で検挙された人の数は、 司法省の発表で67,223名とあるが実数ははるかに越えていたであろう。 同じ頃、文部省は軍国主義教育の強化のために文部省訓令を出し、教師たちにその実行を強制している。そこではこう言っている。 「教育二関スル勅語ノ聖旨ヲ奉体シ皇国ノ道二則リテ国民ヲ練成シ皇運ヲ無窮二扶翼シ奉ル」ために 「教育ノ本義ノ徹底ヲ期シ……忠良ナル皇国臣民ノ練成ヲ主眼トスベキコト」をわきまえよ、というのだ。 戦後生まれの先生たちには正気の沙汰とは受けとれないかもしれないが、これが戦時中の教師の、芸術家の、そして民衆の置かれた状況であり、 天皇制ファシズム教育の実体だった。 戦後演劇とスタニスラフスキーについて述べるつもりが、少し戦時中のことを語りすぎたかもしれない。 しかし敗戦後の演劇人たちがどのような思いで演劇に向かいあったかということを一言述べておきたかったからだ。 ファシズムの鎖から解放され創造の自由を獲得した人々が、スタニスラフスキーとの出会いの中に、どのような接点を見出したのだろうか。 一言でいえばそれは「真実の創造」といえるだろう。形だけの、まやかしの劇ではなく「いのちをもった劇」である。 自然界のいのちをもつものは、一つの例外もなくいのちによってしか生まれることはない。 しかもいのちあるものが生み出したものには、どれひとつ同じコピーはない。だからこそ創造といえるのだ。 「いのちをもった劇」もまたいのちある俳優によってしか創造されない。 スタニスラフスキーが追究したものは、いのちある俳優によるいのちある劇だった。 といっても、スタニスラフスキーに馴染みのない読者には、彼の演劇観がどのようなものかなかなかつかみにくいと思う。 そこでそれを端的に物語っている記録の一つを紹介しよう。 一九〇八年九月モスクワ芸術座はメーテルリンクの『青い鳥』を上演したが、その稽古は前年の四月に始まっていた。 その頃、劇団内部は深刻な内輪もめで分裂状態にあったのだが、その危機を乗り切るためにスタニスラフスキーは最初の「本読み」のあと、 鈍感な俳優たちに向かってつぎのようなアピールを行った。 十数ぺージにわたる長文のものであるが、ここでは一部を紹介することにする。 ……人間のもつ野性は、野蛮で残酷で利己的なものです。自分の仲間を殺し、動物を滅ぼし、自然を破壊する。 しかも周囲にある一切は、自己の快楽のためにのみ創られたと信じています。人間は地球を支配し、宇宙の神秘を知りつくしたと思っています。 ところが実はなにも知っていないのです。 最も重要なものは人間の眼のとどかないところにあります。 物質に埋もれて生きている人間は、精神的な、思慮深い生活からますます遠ざかりつつあります。 今日では精神的な幸福をもつ人々は、ごく限られた人になりました。 その人たちは草の葉のさやさやという一瞬のそよぎにも熱心に耳を傾け、私たちには隠されている世界の神秘な姿を見ようと努めているのです。 そうした神秘を見つめかつ聴きながら、その人たちは、素朴な眼と皮肉な微笑で万物を眺めている民衆に、未知の世界の神秘をわからせてゆきます。 ……何百年もたつと、都市や村の騒音が、草々の奏でる微妙な音色をかき消してしまいます。 工場の煙突の煙は私たちからこの世の美を奪い、贅沢品の氾濫は人々に分別を忘れさせ、型にはまった天井は、空や星を人々から切りはなしてしまいます。 私たちは、自分たちが産み出したこの世の悪臭と埃のなかで、息をするために闘い、幸福をさがし求めるのです。 ほんのひととき、私たちは日光のあふれる広々とした原野でしあわせにひたることもあります。 だがそのしあわせは、青い鳥のように、ひとたび私たちが悪臭を放つ街角に一歩足をふみ入れたとたん、飛び去ってしまうのです。 子どもたちは彼らのものである自然から閉め出されたままになっています。子どもは私たちより自然に近いものです。 それは自然から生まれ出て日が経たないからです。……蟻や、樺の木や、小犬や小猫の生活に入りこんでゆきます。 そして大きな喜びやまじり気のない夢にひたることができます。……『青い鳥』という芝居は、十歳の子どものもつ純粋な空想でつくりあげねばなりません。 子どもの眠りのように素直で、単純で、明るくて、生命の歓びにあふれていて、しかも元気のよいものでなければなりません。 私たちの『青い鳥』を孫たちがみれば夢中になって血をわかせ、 一方おじいさん、おばあさんたちには人生についてのまじめな思索と深い感情の湧き起こってくるような芝居にしようではありませんか。 その晩年にあたって、人間らしい自然へのあこがれ、自然の美しさを楽しみたいというあこがれをふるいたたせてあげましょう。 その魂を曇らせている塵を払い落として、おそらくは生涯ではじめて手に入れた澄んだ眼で人間をみつめ、感謝の思いで見守るようにしましょう。 ……もし私たちがそうした観客の反応を、たとえわずかでも受けとれたとしたら、私たちの親しい友人である『青い鳥』の作者は、 心から喜んでくれるにちがいありません。 問題は、多数の観客からどうしたらそのような力強い反応を得られるかです。……幸い私たちは古いやり方とは全く違った新しい方法をもっています。 私たちの劇場は、すべての専門分野の人々の創造的な努力との結びつきを通じて、十分に強化されています。 ……全体のハーモニーの重要な鍵をにぎるのは、諸君です。劇団の淑女ならびに紳士諸君なのです。 ここで訴えている演劇への思いは、彼の生涯を貫くものだった。このスピーチはメーテルリンクにも送られ、1907年の7月15日にはフランスでも紹介された。 太平洋戦争の暗い谷間をくぐり抜けてきた戦後の演劇人が、スタニスラフスキーの人間的な思想に強く共感したとしても、むしろ自然な成り行きといえよう。 事実、スタニスラフスキーの方法を学ぼうとする数多くの集団が生まれた。 わたしは今、その代表的存在ともいえる「ぶどうの会」について述べてみたい。 この劇団は木下順二、岡倉士朗、山本安英を指導者と仰ぐ若い俳優の集団で、その俳優の中には久米明、桑山正一などがいた。 当時の岡倉演出による何本かの上演は、演技の古い約束事にとらわれた既成の演劇を見なれた観客には、全く新鮮な驚きとしてうつったのだ。 若い俳優たちの血の通ったみずみずしい演技を見ていると、魔術のような岡倉演出に強い興味をそそられたものだ。 『彦市ばなし』の彦市を演じた久米明さんに岡倉さんの稽古の模様を詳しく聞いたことがある。(拙著『芝居ばかりが芝居じゃない』) そのときも岡倉さんは、最初から俳優に台詞の勉強を強いることはなかった。 岡倉さんがやったことは、「戯曲によって与えられた状況のなかで、台詞(言葉)が出てくるにふさわしい身体行動とはなにか」ということを、 まず俳優に体でとらえさせるということだった。 久米さんによると『蛙昇天』(木下順二)においてもこの原則は貫かれていた。 『蛙昇天』は水の底の蛙の世界に状況が設定されている。したがって登場人物はみな蛙だ。そこに大きな岩石が突然落ちてくる。 それを契機に戯曲のなかの隠れているさまざまな要因が動き出す。俳優はなにより先に石が落ちてきたというショックを体の感覚で、 リアリティとして捉えなければならない。 人間界でいえば、多数の生命が奪われる大震災のようなものだ。 この事実との遭遇を決してまねごとのお芝居ではなく、真実の体験として肌身でとらえることだ。 岡倉さんは俳優たちの想像力を刺激しながら、何回も何十回も最初のシーンの稽古をくりかえした。 たまたまこの公演には岡倉さんが関係している大劇団の俳優が何人か加わっていた。 彼らはこの粘り強い、型破りの稽古に驚くと同時に、それよりも俳優の一人ひとりがリアリティをつかみ、 内側からはっきりと変わってゆく過程に目をみはったという。 稽古場は創造的雰囲気でみなぎっていた。大劇団での岡倉さんの演出にはみられない羨ましい光景だったとそのなかの一人は述懐している。 きっと、さまざまな制約が岡倉さんを窮屈にさせていたのだろう。 『俳優修業』という本は、内容は具体的だが、一、ニ度読んでもなかなかとらえにくいところがある。 そこで学者先生が出て来て、俳優たちに講義をするという風景があちこちで見られた。 しかし岡倉さんは全く斬新な方法を考察した。俳優たちと『俳優修業』を「あそぶ」のである。 「集中」「リラックス」「想像力」「舞台への信頼」「交流」等々のシステムの「要素」を「あそび」に還元することで、俳優たちに体で理解させるのである。 最近では同じ意図をもったシアター・ゲームのすぐれた本がいろいろ手に入るようになった。 しかし1950年代にそれがやられていたというのは驚くほかはない。 岡倉さんの個人的なメモには「ぶどうは間尺にあわないが、楽しい」と書いてあった。 蛇足だが、"間尺にあわぬ"というのは努力の割には報われない損な仕事のことをいう。 さりげない言い方だが「真実の創造」に賭けた岡倉さんの心意気が伝わってくる。こんなふうだから、 劇団は岡倉演出のときには上演時期を決めかねることもあったようだ。 しかしスタニスラフスキー派の演山家はみんな「間尺にあわない」稽古に没頭していたのである。 考えてみると、スタニスラフスキーも「間尺にあわぬ」稽古ばかりしていた気がする。 さきに述べた『青い鳥』の稽古のとき、彼は芝居の稽古というよりもアニマルエクササイズ〈動物練習〉を延々とやっていたようだ。 たまたま稽古を見たネミロビチ・ダンチェンコ(芸術座創設者の一人、演出家)が、妻への手紙(1907年8月21日)の中で、 皮肉をこめてそのときの様子を書いている。 それによると、俳優たちは全員、犬や描や鶏のまねをして、ワンワン吠えたり、ニャンニャン鳴いたり、コケコッコーと叫びながら、 ニコニコ顔のスタニスラフスキーのまわりを動きまわっていたというのだ。 スタニスラフスキーとネミロビチの複雑な関係についてはひとまず措くとして、実務家肌のネミロビチにはおよそ無意味なことに映ったことだろう。 それでなくてもスタニスラフスキーは稽古に時間をかけた。百回くらいの稽古はざらである。芸術座の首脳部はこうしたやり方を決してよく思わなかった。 このことも彼が自分の創造方法を追求するために、やむをえず劇団外のグループ、のちの第一研究劇場(スタジオ)を作らざるをえなかった理由の一つである。 岡倉さんが大劇団よりも「ぶどうの会」に情熱を傾けた理由もわかる気がする。 冒頭にも述べたように、若者たちはたえずなにかを追っかける。しかし息せき切って追っかけるのは若者だけではないようだ。 世の中全体が慌ただしく目先のことを追っかける風潮にあるのではなかろうか。 「問尺にあわぬこと」などやっておれないという価値観が定着しつつある。芸術界もまた例外ではなさそうだ。 そうなると岡倉さんやスタニスラフスキーは酔狂の部類に入るのかもしれない。 2「システム」の出発点 スイスの児童心理学者ジャン・ピアジェ(1896〜1980)が「反復された真理は半分の真理でしかない」と言っているのに非常に興味を覚えた。 彼によるとどんなに時間がかかっても、あらゆる障害を自分で切り抜け、自分の手で真実をつかむことを学ばせるのが教育だというのである。 核心を突く言葉だ。しかし教育だけではなくあらゆる創造行為もそうではなかろうか。 他人の発見した真理を反復するだけでは、つまり"He said"をくりかえすだけではなにも生まれない。 「時間をかけ」「障害に打ち克ち」「真実をつかむ」というピアジェの言葉が、私にはスタニスラフスキーのイメージと重なりあって響いてくる。 スタニスラフスキーはどうして「システム」つまり創造の法則を探究しようと思ったのだろうか。 俳優の経験のある読者ならよくご存知だと思うが、スランプというのはこわいものだ。 以前には芝居をやるのが楽しかったのに、スランプに陥ると舞台に立つのが恐ろしい。 でも我慢してやらねばならない。それも一時的なものならどうにか乗り切ることもできようが、長期にわたるともう重症である。 スタニスラフスキーも1906年、43歳にして突然深刻な挫折に襲われた。 当時の彼は、1898年モスクワ芸術座を創設以来、チェーホフ、イプセン、ゴーリキーなど数多くの作品を上演し、 ロシアはもちろん全ヨーロッパで広くその名をとどろかせた名優である。 しかし芸術的挫折は名優といえども容赦しなかった。いや正確に言うと、 名優といえども「出来合いの演技」に安住するかぎり容赦しないということであろう。 イプセンの『民衆の敵』の主人公ドクトル・ストックマンは永い間彼の当たり役だった。 そしていつも舞台に立つのが楽しかった。というのは役のイメージや感情が無意識のうちに、本能的に自分の中でよび醒まされたからだ。 自分の感情がストックマンの中に溶け込んでゆき、同時に役の身体的な特徴がひとりでにあらわれてきたものだ。 たとえば近視のために前かがみのせわしない歩き方、説得力を高めるために自然に前へさしのばされた人さし指と中指のしぐさなどである。 それが、ある時期からぱったりと途絶えてしまった。泉のように湧いていた創造的感情も涸れ尽きてしまったのだ。 焦りだす。しかし焦れば焦るほど結果は逆になる。台詞を言っても砂を噛むような空しさばかりだ。 そんなときの俳優は針のむしろに座らされているようなものだ。永年やりつけた役なので一応は「出来合いの演技」でとりつくろうことはできる。 とは言っても心の中のよろこびは苦痛に変わってしまった。 では他の俳優たちもみんなそうなのか。同じような舞台の危機に見舞われるのだろうか。 そこで、国内の、また外国からモスクワを訪れる名優といわれる人々の演技を見てみる。 ちがう。今の自分とは違う。エルモローワ、デューゼ、サルヴィーニ……彼らはスタニスラフスキーよりもこなした主役の数でははるかに多い。 それなのに舞台には花がある。 演じるたびに役は深められているではないか。この衝撃は大きかった。どうしたら立ち直れるか。 1906年の夏、劇団から休暇をとると、彼はフィンランドに向かった。 バルチック海の見渡せる断崖に座って、過去25年におよぶ舞台生活をつぶさにふり返ってみた。 一つ一つの役を吟味し、俳優日記の書き込みを読み返した。 徹底的な過去の分析をするうち、彼は一つのことに気づいた。 どうも舞台に立ったときの自分の精神状態にはひどく不自然なものがあるのではないか。 その不自然さが創造を妨げているのではないか、ということだ。 たとえば「崇高な」感情を表現しようとするとき、自分ではすこしも感じていないのに、そう見せかけようと紋切り型の表現をしているだけではないか。 「精神の創造的状態」……つまり、普通の人間が実生活でもっている自然な精神状態……を舞台で保つにはどうすればよいか。 そんなときにしかインスピレーションもよび醒ませないのではないか。そのためのいちばんいい状態を自由に創りだすにはどうしたらいいか。 もしいっぺんにそれが創り出せないにしても、少しずつでも訓練法をさぐり、いろいろな要素を組み合わせてゆくことで、 精神の創造的状態を生み出せないものか。 彼はものごとに熱中するタイプである。このときから文字通り寝食を忘れてこの大テーマに取り組むことになる。 こうしたいきさつから、1906年という年は後の「システム」の形成にとって記念すべき年だと私は考えている。 彼の試行錯誤の中からほんの一、二の例をあげてみよう。 今ではどんな若い俳優も「集中」や「リラックス」が演技の中の大切な要素だということを知っている。 そこでそれは当然昔からあった俳優の常識だと思っている。 しかしスタニスラフスキーが本当にその重要さを自覚したのは、少なくとも43歳以後である。 もちろんすでに名優だった彼は経験的にこれをつかみ、演技に生かしていたことは事実だろう。 また彼以前にいた多くの名優たちも、無意識のうちに、創造に必要なこの自然の法則を身につけていたにちがいない。 しかし「集中」や「リラックス」を俳優の創造のための不可欠な要素として、科学的認識に到達したのはスタニスラフスキーが最初である。 彼はフィンランドで少年時代のメモまでひっくりかえして読んでみた。リュビーモフカという田舎にいた頃の家族劇場時代のメモだ。 それによると、指を怪我して痛みがひどく、芝居は失敗だったが、どういうわけか日頃信頼していた客が、今日の出来をほめてくれたと書いてあった。 そんなメモはもうとっくに忘れていた。しかし今読み返すと気になってくる。 彼は舞台で試してみることにした。小指を紐で痛いほどキリキリ巻きにして舞台に出た。 そして自分の心と体の状態を観察し分析する。 そこでわかったことは、指の痛みに気をとられて、日頃は気になる客席のことをすっかり忘れていたということだ。 ……これはどんなことだろう。 もしかしたら自分の注意が指の痛みの一点にだけ向けられていたので、客席が気にならなかったのだろうか。 それから、自分の注意をどこかの一点に集中するということを、いろいろな条件の下で試してみた。 こんなふうに「集中」「リラックス」という重要な「要素」の一つを発見するだけでも長い年月を費やしたのだ。 もう一つ、失敗の例を紹介しよう。 フィンランドから帰ってくると、クヌト・ハムスンの『人生のドラマ』の稽古にとりかかった。 なにしろ「精神の創造状態」をつくり出そうと夢中になっていた時である。 もしこの状態が自分の中に呼び醒ますことができれば 他はすべて自動的にできあがるものと彼は思いこんでいた。 つまり、俳優が役に生きるためには「生きよう」という抽象的な、観念的な情熱さえあればよい、 だから役のもつ個性やもろもろの条件とは切りはなしても、「生きる情熱」はつくり出せる、と思っていたようだ。 どうもこの発想は当時彼が夢中になっていたイタリアの喜劇俳優ルイジ・リコボー二(1674〜1753)の演技論に影響をうけているようだ。 そのためにレオニードフ(後のモスクワ芸術座の名優)を稽古場の床にころがし、その上に演出助手が馬乗りになり、 力一杯彼を押さえつけ、「まだまだ!さあ!もっと!もっと力を入れて!」と叫びつづけた。 なんとかしてレオニードフが表現したいと思っている「特別な情熱」を彼から絞り出そうとしていたのだ。 結果については言うまでもないが、俳優の身振りを強制的にでもやめさせれば、注意は役の内面に集中しやすくなるのではないか、という素朴な誤解にもとづいていた。 少しでも自然を抑圧すれば、真実の感情はすぐに消滅するということを認識していなかったのだ。 このように膨大な時間とエネルギーをつぎこみながら試行錯誤を重ね、俳優の創造の原理となるべきものを、一つ一つ発見していった。 1936年、「システム」の研究を思いたってから三十年後に『An Actors Prepares』(『俳優修業』)としてアメリカで出版された。 ロシア語版はその二年後、1938年、彼が没する年に『俳優の仕事第一部』として出版された。 (第二部は没後弟子たちによってまとめられたが、主としてオペラ作品を手がける中で提起された身体技術への関心にもとづいている)。 『俳優修業』の目次をひらくと、「行動」「想像力」「注意の集中」「筋肉の緩和」……というように、彼が「要素」とよんでいる創造の原理が整然と並べられている。 そして各項目の訓練法が詳しく述べられている。 ただし、ここでは試行錯誤の過程はすべて省かれている。いわばきれいに盛りつけられた薬膳料理のようなものだ。 ところで日本の戦後の状況はどうだったか。 『俳優修業』第一部が突然現場の演劇人たちの手に渡された。 それも世界の「権威」ある書物として。 もしかしたら前号で述べた『蛙昇天』の、天上から水底に落ちてきた岩石のような衝撃だったのかもしれない。 この、読む前から「権威」であるということが、どうも不幸の兆しだったような気がする。 「権威」は「流行」に変わり、時代の表層を上滑りしてしまうからだ。 その後のブレヒト、グロトフスキー、ルコックなどもその点よく似ている。 本来なら「第一部」は身体的形象化をとり扱った「第二部」との一連のつながりとしてとらえるべきで、そうでないと「システム」への誤解が生じてくる。 だが両者の間の時間的空白は「第一部」だけを世界中にひとり歩きさせてしまった。 しかも試行錯誤についての情報もほとんど伝わっていなかった。 また「システム」が形成された当時の芸術座内部の状況、スターリン体制下でのソ連の社会情勢も詳しくはわからなかった。 そのなかでの真実は隠蔽され、伝わってくるのは作り話の美談だけだった。 権力はスタニスラフスキーを意図的に偶像化し、その創造理論を社会主義リアリズムの正当化のために徹底的に利用した。 他方彼の活動や人間関係については当局のきびしい監視の下に置かれていた。 これらのことが世界に明らかになったのは、80年代ロシアの「情報公開」以後のことであるから、戦後の日本の演劇人たちはもちろん知るすべもなかったのである。 しかし、今、あらためてスタニスラフスキーを見直すにあたって、この辺の事情にできるかぎり詳しく触れてゆきたい。 やむをえないこととはいえ、戦後の日本に伝わったスタニスラフスキーのイメージはあまりにも美化され、その理論は「聖典」化され、 その方法は修正を認めない「権威」となった。 このあたりは、スタニスラフスキーを深く尊敬しながらも、決して盲従せず、独自の道を歩いたアメリカの後継者、リー・ストラスバーグとの違いといえよう。 スタニスラフスキーが繰り返し言っているように、彼は「システム」の教条化を極度に嫌った。 彼は自分の「システム」を「権威」とも「聖典」とも思っていなかったし、ましてや修正を許さない完成品などとは考えていなかった。 それどころか「第一部」の出版が延びに延びたのも、ぎりぎりまで悩み、修正につぐ修正を重ねていたからだ。 とうとう彼の長年の協力者だったリュボフィ・グレーヴィチ女史も愛想をつかし、協力を断ったほどだ。 『An Actors Prepares』が出版された後もまだ書き直しにかかっていた。 しかしそんなこととはおかまいなしに、世界中の教条主義はスタニスラフスキーの思惑を越えて、手のつけられないところまで拡がってしまった。 晩年のスタニスラフスキーにとって「システム」の仕事はまだ道半ばだった。 しかも共に研究を続けてきた信頼すべき弟子たちはもういない。 スーレルジーツキイ、ワフタンゴフは若くして死に、ミハイル・チェーホフはとめるのをふり切って国外に亡命した。 信頼する唯一の同志は今やメイエルホリドを残すのみとなった。 一方では跡目を狙う弟子たちも現れてくる。 そんな中で彼の立場は実に孤独だった。 私にはスタニスラフスキーの心中が、どこか世阿弥に似ているように思えてくる。 世阿弥は観世一門のために能芸の秘伝を書いた。 当時、畿内を中心に各地に猿楽座がひしめいていた。是が非でも他座との競演に打ち勝たなければならない。 『風姿花伝』および数多くの伝書は世阿弥父子の切実な舞台経験に即した理論である。 一門にとってこれさえ学べば絶対に他座を圧倒することができる金科玉条だった。 必ず将軍のお抱えの座の獲得を保証するものだった。 しかし世阿弥が伝書の中で全体として言っていることとはなにか。 もしこの書物に書いてあることをそのまま行おうとする者は、そのまま行おうとすることによって滅びるだろう。 また、この書物に書いてあることに反抗しようとするものは、反抗しようとする行為によって滅びるだろう、ということである。 つまり教条主義でもだめ、原則を無視してもだめ、ということだ。 芸術というものはまことに恐ろしい。 スタニスラフスキーは世阿弥のことは知らなかったかもしれない。 しかし二人は似通った心境にあったのではなかろうか。 スタニスラフスキーは1933年1月10日のゴーリキー宛の手紙の中で、目分の複雑な創造体験を、 書物によって人にわからせることがどんなに難しいことか切々と訴えている。 個人的な接触でなら伝えられるものも「一旦筆をとると、自分の感じてることを定義づける必要な言葉が、私から飛び去ってしまうのです。 ……教えられるという受け身の形のシステムは、ただ俳優を片端にするだけのものです……」 スタニスラフスキー自身の「システム」に対する考えをさらに具体的に述べてみよう。 1931年アメリカの俳優ジョシュア・ローガンが、アメリカではどのようにシステムを学んだらよいのかと質問した。 それに対しスタニスラフスキーは「自分自身の道を探すように」と忠告している。 「アメリカの俳優が必要としているものと、ロシアの俳優のそれとはひどくちがうものです。 『システム』の各『要素』は正当かつ本質的なものであるが、『要素』のバランスと強調部分については、時と場所によって変化します。 個々の俳優はその資質と段階に応じて、『システム』のもつ多様な側面を発見するでしょう。 だからどんな時代にも、あらゆる俳優に対して演技を絶対的に法則化することは不可能なのです。 重要なことは結果です。『システム』は、真実にみちた上演のための手順を俳優に提供するためにのみ存在するのです」。 さらに繰り返し「それは道徳的義務ではない」と強調している。 ジョシュア・ローガンより以前に、マックス・ラインハルトが同じような質問をしたことがあった。 そのときもスタニスラフスキーの答えはおなじだった。「自分自身の道を探すように」というのだ。 |
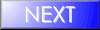 |
| TOPへもどる |
| 演劇ラボ |