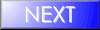
|
『あらためてスタニスラフスキー』 高山図南雄 (たかやま・となお) 演劇と教育 1995年No.475 1996年 No.479までの連載をまとめました。 チェーホフに学ぶ(1) 前回、スタニスラフスキーが、いわゆる「システム」についての、自覚を抱きはじめたのは、1906年であることを述べた。 そしてその「システム」を発展させる母胎となったものが、チェーホフとの仕事であったことはまぎれもない事実である。 スタニスラフスキーが仕事の上でチェーホフと関わったのは、 1898年12月、モスクワ芸術座の旗上げ公演となった『かもめ』から1904年1月の『桜の園』にいたる六年間である。 この短い間に『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』を含めて、四本の代表戯曲が上演された。 そしてチェーホフは『桜の園』が上演された年の7月2日、南ドイツのバーデンワイラーで死去した。四十四歳である。 したがってスタニスラフスキーにすれば、彼の30代後半から41歳までのかかわりということになる。 ここではっきりさせておきたいのは、チェーホフが生きている間には、まだスタニスラフスキーの「システム」は存在していなかったということである。 なぜこんなことを言うのかと言えば、「システム」というのは、俳優の内面的創造を重視し、そこを拠りどころとするのだが、 チェーホフ存命中のスタニスラフスキーには「内面的創造」という問題意識が十分に成熟していなかったからだ。 確かに『かもめ』以後の一連のチェーホフ劇の上演は大きな成功を収め、 劇作家としてのチェーホフ、俳優・演出家としてのスタニスラフスキーは世界的な名声を手に入れた。 しかしチェーホフとしては「これは私の戯曲ではない」とまで言いきるほどの不満、 戯曲の本質的部分において作者の意図が理解されていないという不満が消えなかった。 それでは芸術座が成功した理由はどこにあるのか。 一言で言うと、スタニスラフスキーの演出的才能によるものであり、それによって最高水準の自然主義演劇、 いいかえれば、外面的描写による圧倒的リアリティを創り出した結果にほかならない。 もしスタニスラフスキーがこの時点の成果に満足し、踏みとどまったとすれば、彼は後世「偉大な自然主義演劇の完成者」という評価をうけるにとどまっただろう。 しかし彼が絶えざる自己否定によって、創造の原理を追究することができたのは、チェーホフの「ノー」というきびしく暖かい忠告によるのではなかろうか。 彼がネミロビチ・ダンチェンコからはじめて『かもめ』の台本を受けとったとき、ほとんどこの戯曲を理解することができず、 「単調」で「演劇性に乏しい」ものという印象をうけただけだった。 これでは二人の関係がぎくしゃくするのは当然だが、そうした状態から、徐々にではあるが、どのようにして二人の人間的な信頼が培われていったのか。 その複雑微妙な関係について考察してみたい。 俗に、相性が良いの、悪いのという言い方をすることがあるが、初期の頃の二人は、この相性という点でどうもしっくりしなかったのではないかと思われる節がある。 芸術座における『かもめ』の初日は1898年12月17日である。まさに不安の幕あけだった。 第一幕が終わると俳優たちは身も凍る思いで舞台に立ちつくしていた。 それがなんと六回ものカーテンコールを受けたのだ。 第三幕のあと挨拶に出た共同演出者のダンチェンコに観客は熱烈な喝采序を送り、ヤルタにいるチェーホフに祝電を打つことを要求している。 ジャーナリズムもまた一斉にこの芝居を賞讃した。 それだけではなくチェーホフ自身もこの成功に気をよくし、翌1月25日には医学の同僚P・F・イオルダーノフに手紙を書いている。 「ぼくの『かもめ』が大入満員でモスクワで上演された。券は売り切れた。みんなこんなことは稀だといっている。」(書簡集) こうした流れからゆくと、次の作品『ワーニャ伯父さん』が芸術座に渡るのは至極当然のこととスタニスラフスキーも劇団員も期待していた。 ところがチェーホフはそうしなかった。 芸術座にではなく帝室劇場(マールイ劇場)に作品を渡す約束をしたのである。 一体なぜなのか。 もちろんチェーホフ自身はこうした自分の行為については一切説明を与えていない。 そこでいろいろな理由が推測されるが、その有力な一つとして、チェーホフは『かもめ』の演出が不満だったし、 また役者としてのスタニスラフスキーが好きではなかったのではないか、ということだ。 しかし、これもいささか奇妙なことである。だいいち、チェーホフは芸術座の『かもめ』公演を一度も見ていない。 したがってスタニスラフスキーの演技も見ていないのだから、判断の下しようがないのではなかろうか。 たしかにチェーホフは『かもめ』の稽古を見るために、メリホヴォからモスクワヘ来ている。 9月9日と11日の二度にわたって稽古をのぞいている。しかしこのときの稽古を取りしきっていたのはダンチェンコだった。 スタニスラフスキーは『かもめ』の残りの演出プランを急遽仕上げるために、ハリコフ近郊の、弟ゲオルギーの家に閉じ寵もっていて稽古場にはいなかった。 ある俳優がチェーホフに、スタニスラフスキーは田園風景をもりあげるために舞台裏で蛙をゲロゲロ、犬をワンワン吠えさせるのだといったのを聞いて、 チェーホフは「芝居は芸術です。そこでは人生の真髄を写し出す。だから余計なものは一切持ちこんではいけない」とたしなめたりしている。 そうはいっても、緊張と不安を抱いてやってきたチェーホフは、前回1896年ペテルブルグのアレクサンドリンスキー劇場の公演が惨めな失敗に終わったのに比べると、 今度は第一幕の稽古を見終わった時点ではあるが、演技者たちは作品を理解しているという印象を受け、ほっとしたことは確かである。 ダンチェンコはハリコフのスタニスラフスキーにこう報告している。 「あなたのミザンセーヌ(舞台上の動きのプラン)はとてもよかった。チェーホフが大喜びです。 トレープレフの解釈を、一、二だけ変えました。私じゃなくて、チェーホフが。 ……あなたの、ミザンセーヌがどれほど全体の印象を強めているか、彼はすぐに理解しましたよ。」 こうした事実を見るかぎり、チェーホフが芸術座に対して全面的に拒否反応を示したとはとうてい考えられない。 ましてやリハーサルの最初からチェーホフは、オリガ・クニッペルの美しさと演技に見惚れていた。 アルカージナを演じる28歳のこの女優は、知性に輝く眼をして、かぎりなく繊細な感覚でこの役を演じていた。 のちに熱烈な恋文のやりとりを経て、チェーホフの妻となるべき運命がこのときすでに決定づけられていたのである。 チェーホフがヤルタにひき籠って芸術座の『かもめ』の初演を見なかったというのは、一つには喀血のため健康状態がすぐれなかったということもあるが、 それ以上に彼は1896年のペテルブルグ公演での初日の失敗に大きく傷ついていたことは確かである。 観客の罵声と嘲笑が客席にいたチェーホフを居たたまれなくさせ、劇場をとび出すと深夜まで独りで街をさまよい歩いていたのだ。 彼は「もし七百年生きたとしても金輪際芝居は書かない」と心に誓った。 だから今度もそのときの二の舞を演じるのではないかという恐怖から逃れることができなかった。 見かねた妹のマリヤ・チェーホフは、兄の健康を気づかって、舞台稽古の当日になって公演中止を芸術座にたのみこんでいる。 もちろん芸術座としてはその申し出に応じるわけにはいかなかった。 ところで、マールイ劇場とチェーホフとの交渉は三月に入って決裂ということになった。 マールイの改訂要求をチェーホフが拒否したためだ。 この機会に芸術座はマリヤ・チェーホフを通して必死の巻き返しを図り、チェーホフは四月末になってようやく『ワーニャ伯父さん』を芸術座に渡すことにした。 どうもしぶしぶという印象はまぬがれない。 同時にチェーホフは、自分がまだ見ていない『かもめ』の上演を見たいと言いだした。 芸術座はチェーホフのために5月1日パラダイス劇場を借りて装置なしの『かもめ』の上演を行っている。 チェーホフとダンチュンコの関係が「きみ」「ぼく」というくだけた間柄だったのにくらべると、スタニスラフスキーとチェーホフは最初からどうもきしみが感じられた。 (2) スタニスラフスキーがはじめてチェーホフに会ったのは、『かもめ』の初演よりも9年ほど前になる。 1889年2月18日、「芸術・文学協会」の仮装舞踏会のときだ。 この頃彼はチェーホフが好きになれず、むしろ敵意さえもっていたようだ。 「チェーホフの思い出」の中に「チェーホフは自尊心が強く、横柄で一癖ある男だと思う」と書いている。 これにはいささか驚かされるが、たぶんチェーホフがスタニスラフスキーの文学的無知に気づき、彼一流の遠回しのやり方でからかいたくなったからではなかろうか。 スタニスラフスキーの方ではチェーホフの無意識の癖……頭を後ろにそらせたり、話し相手のどこか一点をじっと見つめたり、絶えず鼻眼鏡を調節する ……こうした癖からそう思いこむようになったのかもしれない。 「こうしたいろんなことが、私にはチェーホフの傲慢さにみえた。 実際は彼の内気のためであり、 当時の私にはそのことがわからなかったのだけれども」と後になって述懐している。 それから7、8年後にもまたスタニスラフスキーは気分を害している。 1897年1月4日、コルシ劇場で「文学と音楽の夕べ」が開かれ、彼はレールモントフの「詩人の死」という詩の朗読を頼まれていた。 もともと詩の朗読は得意ではなかったが、はじめての機会だったこともあって、大いに緊張した。 しかも朗読は惨めな失敗に終わった。 彼はほうほうの体で劇場を逃げ出そうとしたのだが、運悪くチェーホフにつかまってしまった。 チェーホフは彼に近づいて話しかけた。もちろん俳優の傷ついた虚栄心を慰めてやろうという心づかいからであったろう。 「あなたの演られた私の『熊』はなかなか立派だったそうですね。 ……ねえ、どうして再演しないのですか?そのときは私も出かけて行って拝見しますよ。なんなら新聞に批評も書きますよ。」 もちろんそれは全くの冗談だったが、おそらくそれが、「傲慢さ」にさえみえたのだろう。 スタニスラフスキーは黙っていた。 「それから上演料もいくらか頂戴しますよ」 スタニスラフスキーはなおも一言もしゃべらなかった。 「たとえわずかでもね」とチェーホフは言った。 スタニスラフスキーはかっとなった。本当に好意があるのなら、自分の朗読についてお世辞の一つくらい言ってもいいじゃないか。 しかるにこのあからさまな嘲笑はなんたる侮辱だろう。 スタニスラフスキーにはチェーホフが自分を励ますために言ってくれているのだということが理解できなかった。 おそらく内心では、「なんだあいつ、つい2か月まえに『かもめ』とかいう妙な題の芝居を書いて、 ペテルブルグでさんざん味噌をつけているではないか」と思ったことだろう。 それが2年後にはその『かもめ』によって、自分たちの運命も名声も切っても切れない間柄に結びつけられるのである。 いちばんびっくりしたいのは当の本人だったにちがいない。 (3) モスクワ芸術座の旗上げ公演の演目の一つに『かもめ』を入れたいと熱心に主張したのはダンチェンコだった。 かれはペテルブルグでの失敗にこりて嫌がるチェーホフを再三に渡って口説き、ついに納得させたのである。 他方、スタニスラフスキーに対しても、そのすぐれた文学的価値を説得し続けた。 もともとスタニスラフスキーは古典劇への関心が強かった。 それだけに古典劇とはあまりにも趣きを異にするこの現代劇を理解することは非常に難しかった。 とくに戯曲の内面的行動についての明確な理解がなかった。 「恥ずかしいことに、私にはその戯曲が分からなかった。 私がだんだん戯曲に溶けこんで、いつの間にか好きになっていたのは、その仕事の続いている間のことだった。 チェーホフの戯曲というのは、そういう性質のものだ。 ひとたびその呪文にかかると人はいつまでもその醍醐味を味わいつづけたくなるものだ」と書いたのはずっと後のことである。 ダンチェンコに説得されたスタニスラフスキーは演出プランの作成にかかるのだが、 ついでにダンチェンコはこの劇の「雰囲気」や「気分」についてもスタニスラフスキーに吹きこんだのだ。 「気の滅入るような」、「憂うつな」、「限りなく単調な」……こうした気分をスタニスラフスキーは演出プランの中に持ち込むようになった。 スタニスラフスキーによる『かもめ』の演出ノートの冒頭はこうなっている。 「舞台は暗い。(8月の)夕暮れ、うすぼんやりした角燈が柱の先にかかっている。遠くで酔っぱらいの声。犬の遠吠え。 蛙と水鶏(ヒクイナ)の鳴声。遠くの教会のゆるやかな鐘の音。 これらはすべて、この劇の登場人物たちのもの悲しく、味気ない生活感情に観客を溶けこませるためである。 稲妻。遥か彼方に微かな落雷の音。開幕後十秒の間。その間のあとで、ヤーコフが(劇中劇の舞台で)釘を一本金鎚でうちつける。 それから彼は鼻歌をうたいながら舞台を忙しそうに動き廻る」 これにくらべるとチェーホフが戯曲に書いているト書きは 「日没。ヤーコフと下男たちは幕を下ろした仮設舞台の上でいそがしそうに働いている。ハンマーの音。「咳」これだけである。 いささか過剰気味のスタニスラフスキーの自然描写に、ダンチェンコは批判的だった。 それに対しスタニスラフスキーはこう答えている。 「考えてみてください。静けさを出すためだけに、その場面に蛙を鳴かせているのです。 静けさというのは、舞台では、沈黙ではなく物音で表現されるものです。沈黙を物音で満たさなかったら、イリュージョンは生まれないのです」 たしかに、一般論としてはスタニスラフスキーの言う通りだろう。 しかしここではもっと別の、考えるべき重要な問題を含んでいるように思われる。 では重要な問題とはなにか。 演出家が戯曲の内面的行動を把握していないときには、不安のあまりどうしても瑣末主義(トリピアリズム)に走りやすいということだ。 一連の外面的、写実的技巧によって、観客を幻惑しようと試みる。 そうした外面的ディテールのみにこだわる演出家は、結局、独裁者の道を選ぶようになる。 彼が勝手につくりあげた外面的特徴から出発するために、個々の俳優のもつ創造的個性を簡単に無視してしまう。 そして、自分の思う通りにしゃべったり動いたりする人形になることを強要する。 この頃のスタニスラフスキーは、こうした独裁型の演出家という面を多分に持っていた。 今でもこのタイプの演出家は決して少なくない。 そして「様式性」という言葉がいつも隠れ蓑に使われている。 「簡潔さは才能と姉妹関係にある」というチェーホフの信条に照らすと芸術座の『かもめ』はまだそこに及ばなかったといえよう。 しかしそれよりもチェーホフを驚かせたのは、かつてのアレクサンドリンスキー劇場での『かもめ』の稽古だった。 そのあまりにも芝居がかった演技にすっかりうろたえたチェーホフは、演出家のカルボフに修正を要求している。 「芝居がかったことは、みなさん、一切不要なんです。まったく不要です。 いとも簡単なことですよ。登場人物というのは、実にさりげない人たちだし、普通の人たちなんですから。」 もちろんチェーホフの意見は全く受け容れられなかった。 彼は妹のマリヤにこう書いた。 「ペテルブルグにはうんざりしたよ。……だれもがぴりぴりしていて、けちくさく、インチキで、太陽が顔を出したかと思うとすぐに霧がかかってくる。 芝居は評判にもならず、みじめに終わるだろう。 」 このアレクサンドリンスキー劇場の演出家とスタニスラフスキーを同列に置くことはできないだろう。 しかし、外面から力でひっぱってゆこうとする点では共通していることを認めないわけにはいかない。 のちの芸術座の名優レオニード・レオニードフも当時のことをふりかえり、 「つまらぬディテールに凝りすぎるために、往々にして肝心なもの……思想や言葉……を忘れがちであった。」と述べている。 (4) チェーホフ劇をどう読みとるかということは、今もって難しい課題である。 一例として、チェーホフ研究会(日本大学)が調査したところでは、わが国でのチェーホフに関する著述は優に百冊を超えているし、 世界における上演数は、記録に残る有名なものだけでも二千を超えている。 いいかえれば、それだけの数のチェーホフ観があるということだ。 今も人々は「私のチェーホフ」を追究してやまない。チェーホフには無限の深みと同時に新しさのあることを各世代の人々はあらためて気づくのである。 それだけに、はじめて『かもめ』という戯曲を読んだスタニスラフスキーが、その内容を十分に把握できず、当惑したのも、無理からぬことであろう。 彼はひたすら外面描写の演出に力点を置き、それを手がかりとして中味に迫る努力を重ねざるをえなかった。 それでも上演は空前の成功をおさめている。その理由はなんだったのか。 そのことを考えてみようと思うのだが、そのまえに上演の実際の反響をいくつか拾ってみよう。 作家A・S・ラザリョフが1899年1月19日、チェーホフに宛てた手紙がある。 「初日を見ました。一幕はなにか変わった出だしでした。しだいしだいに観客が昂奮してゆく雰囲気をなんと表現すればよいか。 幕間にはほとんどの人が客席を抜け、感慨深い顔つきて通路に出ました。 まるでみんなの誕生日のような、まさしく(決して冗談じゃありませんよ)見ず知らずの婦人にまで近寄って、しゃべりかけることだってできたくらいです。 『いかがでした?え?』と。N・E・エフロース(演劇評論家)はどんな場合もいつも内気で『尊敬する』人ですが、一階正面の私の席まで駆け寄ってきました。 そして二幕のあとでは、庭園の入口で私を呼びとめて、感動のあまり大きな声で叫びました。本当に劇場中にきこえました。 『ああ、すごい芝居だ、すごい演技だ、すごい情熱だ!』」 また当時ロシアの代表的な文芸誌「ロシア思想」は1899年1月、次のような辛口の論評を掲載している。 「『かもめ』の成功は異常な現象である。われわれに多くを語り、多くの事柄についてわれわれの眼をひらかせた。 だが、この喜劇での芸術座の俳優の演技は、完全さからはほど遠いものだ。 作品の主役のひとり、トリゴーリン(注、スタニスラフスキー演じる)は理解することをはき違え、解釈を間違え、 「かもめ」のヒロインの役割をゆがめてしまったが、われわれは俳優たちの欠点を許した……。」 「誰もこのような芝居をすることはできない。人々は心の傷み、あるいは病気や苦痛へのじつに細やかな神経をもちえたとき、 はじめてこの世の中での一定の結びつきが破壊されつつあることを実感することができるのだ」 新聞もまた一致して賞賛した。 たしかに「ロシア思想」が言うように「『かもめ』の成功は異常な現象」といえるだろう。 とは言っても、この「歴史的」とも言える成功をどう考えたらよいのだろうか。 まず考えられることはこの上演がつくり出した「気分」である。 スラブ歌曲のもつもの悲しい「気分」がロシアの民衆の心をとらえるように、この劇の憂うつな「気分」は、 やがて訪れる1905年の動乱を前にして、知識階級の沈滞した気分にぴったりと反応した。 当時の統計によると、アーストロフ(『ワーニャ伯父さん』)のような地方医師の死亡理由のうち、なんと10パーセントが自殺によるものだという。 無数の有能な人々が逼塞した時代の情況の中で空しく頽廃し埋没してゆく。 チェーホフはその姿を醒めた眼で猫きつづけているのだ。 観客はこれこそ自分の姿だという実感をもったにちがいない。 わが国でいえば、中国との戦争直前に上演された『夜明け前』が、時代の暗い谷間に孤立した知識人の、 行き場のない心情に反応し、同時代人的共感をそそったのと相通じるもめがあろう。 つぎの理由としては、演出のおどろくべき新鮮さがあげられる。 当時の常識だった芝居がかった大げさな演技をすべて排除した。 それに独創的なミザンセーヌ(舞台上の動きのプラン)も注目をひいた。 たとえば第一幕の劇中劇のシーンでは、それを見ている俳優を客席に背を向けて坐らせた。 実際の観客と同時体験させることで、舞台と客席の眼に見えぬ仕切りをとり除くことに成功した。 さらに重要な特色として、舞台のアンサンブルがある。 舞台のリズムが自然のもつリズムと融合し、成果を際立たせたのだ。 とは言うものの、『かもめ』におけるスタニスラフスキーの演出構想は、まだ精密な外面描写から入っていたことはたしかである。 一例として、彼の演出ノートから四幕のマーシャのシーンを見てみよう。 原作の台詞はこうなっている。 マーシャ(ワルツを二まわり三まわり、ひっそりと踊る)大事なのはね、ママ、「去る者日々に疎し」ってことよ。 うちのセミョーンが転勤しさえすりゃ、むこうで、ほんとうよ、ひと月で忘れるわ。みんな、くだらないことよ。(松下裕訳) これをスタニスラフスキーは演出プランでこうふくらませている。 マーシャ(ため息をつき、ひとつまみの嗅ぎたばこを嗅ぐ。すばやく、力いっぱい瞼を閉じる)……〔台詞〕 ……(もう一度ため息、ワルツを踊りながら窓辺へ、脇に立ち止まる。闇に目を凝らす、ハンカチーフを取り出し、母親に知られないように、頬から落ちる涙を一、二度拭う。 ) この外面描写の演出プランが……というべきか、でさえもというべきか……観客につぎのような反応をよび起こしている。 観客としてのエフロースが見た舞台の印象はこうなっていた。 「一度見たら、忘れられない舞台となるだろう。深い悲しみと、衝撃、見る者の心にほとんど悲運を感じさせる。それは沈黙のせいだ。 マーシャはまるで機械的にワルツを踊る。コースチャの部屋から聞こえる遠い音楽をききながら深い絶望に沈む。彼女はただ聞いている。そしてリズムに合わせて二、三回廻る。 ……それだけだ。だがこのわずかな沈黙の間ほど、うちひしがれた彼女の存在が見る者の心をしめつける瞬間はない」 このエフロースの見た舞台上のマーシャ(リリナ)の演技と、最初のスタニスラフスキーの演出プランとの間には、明らかに質的なちがいのあることに気づくのである。 エフロースが見たマーシャは、単なる外面描写の域を越えている。 俳優のリアリチィ(内的真実性)に従って役を創造していることが感じられる。 ということは、スタニスラフスキー自身も、チェーホフ劇と取り組む過程の中で、最初に抱いていた演出意識が変化していったということではなかろうか。 その変化とは、外的なものから内的なものへ向かっていた自己の方法の逆転がはじまったことを示すものではないか。 事実、彼はしだいに外面的演出法を放棄して、世間の専制演出家が抱いている観念とは全く逆の演技の「システム」に向かってその一歩をふみ出したのである。 とはいうものの、この時期ではまだ「システム」の追究という発想は生まれていないし、「俳優こそ演劇芸術の焦点である」という認識にも至っていない。 彼の後半生の「システム」の追究は同時に専制演出家からの脱却の過程でもあったのだ。 (5) メイエルホリドは芸術座の『かもめ』の初演でトレープレフを演じている。 それから四十年ほどたって、彼の最晩年の「講話」の中で『かもめ』について回想している。 そのことに触れるまえに、メィエルホリドとスタニスラフスキーの関係について一言だけ述べておきたい(詳しくは連載の後半に述べる予定だ)。 世間ではこの二人は不倶戴天の間柄のように取り沙汰されている。 しかしその噂にはかなり意図的なものが仕組まれていたようだ。 たしかに二人の芸術観には大きな隔たりがあったことは事実だ。 しかし二人の間にはそれぞれの立場の相違を越えた芸術家としての深い信頼があったことも事実である。 メイエルホリドは芸術座をはなれたあと、芸術座に対しての鋭い批判の矢を向け続けた。 しかしその批判はむしろダンチェンコが完全に実権を握っている芸術座の体制的保守主義に向けられたものだった。 彼は芸術座とスタニスラフスキーを区別して考えていた。 とくに晩年の5年間は、二人は権力の監視の眼をくぐりながらひそかに会合を重ねていた。 (スタニスラフスキーは1938年に没し、メイエルホリドはその翌年に逮捕され、40年に銃殺された) そしてこれから創りあげるべきロシア演劇の未来について構想を練っていた。 スタニスラフスキーは世間に対して半ば公然とメイエルホリドを擁護し、1938年3月にはソビエト政府のメイエルホリドに対する憎悪が高まる中で、 あえてオペラ『リゴレット』の主席演出家の椅子を彼に与えたほどである。 メイエルホリドが『かもめ』について発言しているのは、こうした危機的状況の下であることを一応考慮に入れる必要がある。 「モスクワ芸術座の『かもめ』に自然主義の要素があったかどうかという質問ですが、それは裏のある質問ですね。 ……むろん、自然主義の個々の要素はあったでしょうが、それは重要なことじゃない。 大事なことは、詩的な神経中枢が働いていたということだし、チェーホフの散文のなかにかくれた詩情を表わしていたということです。 スタニスラフスキーが演出家として天才だったからです。 スタニスラフスキーが出現するまで、みんなチェーホフ作品のテーマだけを演じてきて、 作品のなかに描かれている窓外の雨音や樋から水の落ちる音、雨戸からもれる早朝の光、湖の霧といったものが、(散文にだけ明らかに見られるのですが) 人の動きと切り離すことのできないものだということを念頭に置いていなかったのです。 当時、これはすごい発見でした。自然主義というのは、月並みになったらおしまいです」 これはなかなか意味深い発言だ。 〈日常生活〉即〈自然主義〉……それは悪しきものという通念を抱く人々は、だからこそここで「テーマ」を強調すべきだという結論に向かいがちだ。 メイエルホリドが「みんなチェーホフ作品のテーマだけを演じてきて」と言っているのは、そうした流れに対する批判もこめていると思われる。 エルミーロフのチェーホフ論に象徴されるような、「革命的」解釈をむりに押しつけることで、芸術家を「統一見解」で縛ろうとする力への抵抗であろう。 1932年スターリンは社会主義リアリズムに従わない一切の文学形式を禁止した。 前年31年のプロレタリア作家同盟の大会では、メイエルホリドのみならずスタニスラフスキーも反革命的ブルジョア理論として攻撃にさらされた。 そのことを考えると、「自然主義」のレッテルを貼りつけようという隠れた意図に対して、メイエルホリドの切り返しは、あざやかである。 彼はレッテルをはぎとることで芸術の本質を擁護したのである。 ふたたび話を1899年に戻そう。 チェーホフとスタニスラフスキーの間に横たわる、とても埋められそうにもないと思われた溝も、少しずつ狭められてゆくきざしがあらわれてきた。 チェーホフ劇に対するスタニスラフスキーの理解の深まりもさることながら、二人は人間として、また芸術家としての親しみと信頼に気づきはじめた。 マールイ劇場が『ワーニャ伯父さん』の改訂をチェーホフにつきつけ、チェーホフはこれをきっぱりと拒否するというごたごたのあと、 作品はやっと芸術座に落ちつくことになった。 そうなると、多少唐突の感がないわけではないが、チェーホフの芸術座への関心は急速に高まりをみせた。 芸術座が『ワーニャ』の稽古に入ると早々に彼は稽古場に乗りこんできた。 5月24日、はじめの二幕までの稽吉の進行状態をつぶさに見たあと、「すばらしくよく流れている」という感想をもらしている。 同時にクニッペルヘの手紙では、スタニスラフスキーの演じるアーストロフについて注文を出したりしている。 スタニスラフスキーはエレーナに対して情熱的に演じすぎていたのだ。 「アーストロフは彼女が自分のことをなんとも感じていないことを知る……そして、この場面で彼女のことを語るのは、 まさにアフリカの暑さのことをしゃべるのと同じ調子だし、ほかにどうしようもないから、あっさりとキスをする……」と言っている。 『ワーニャ伯父さん』の初演は10月26日に開幕し好評だった。 しかしこのときもチェーホフは病気で見ることができなかった。 そこで芸術座はチェーホフのためにヤルタ公演を企画した。 「マホメット山へ行かざれば、山マホメットに来たらん」という意気込みだった。 モスクワでの初演を見たゴーリキーは非常に感動して、二回観劇したという手紙を1900年1月にチェーホフヘ送った。 チェーホフは早速返信で、4月には芸術座がヤルタに来ることになっているので、ゴーリキーも是非来てほしいという招待の便りを出している。 そして「もっとこの劇団に近づいてみてください。あなたも戯曲が書けるくらいに。」と芸術座への戯曲の執筆をすすめている。 それにしても前年『ワーニャ伯父さん』が上演された直後の11月に、チェーホフは自分の経験をふりかえり 「……浮き沈みの人生を航海するうちに、とうとうモスクワ芸術座というすばらしい島にたどりついたことを、神に感謝する。」と書いているところを見ると、 チェーホフにとっても芸術座は欠かせない生き甲斐だったといえよう。 芸術座の一行がヤルタにやって来たのは1900年4月14日だったが、この頃もチェーホフは喀血が続き、体調は決してよくなかった。 それでも4月10日にはセワストポリまで一行を出迎え、そこで『ワーニャ伯父さん』の一般公演を初めて観劇している。 皆に体の具合を尋ねられると、「快調です。とても元気ですよ。」と唇にゆがんだ笑いをうかべながら答えた。 ヤルタではチェーホフの招きで、作家や芸術家たちが芸術座を祝福するために駆けつけてきた。 イワン・ブーニン、マクシム・ゴーリキー、アレキサンドル・クプーリン、セルゲイ・ラフマニノフといった顔ぶれだ。 ヤルタ公演の間中チェーホフの家は、芸術家たちや劇団のメンバーで「お茶だ、食事だ」とごった返していた。 母親と妹はその応待で大わらわだった。 それでも妹マリヤによると、ヤルタに無理に「追放」されて過ごした時のなかで、チェーホフにとってはこの時がいちばん幸せだったという。 チェーホフは空いてる時間をたいがい劇場で過ごし、舞台画家を相手にこおろぎのまねかたを教えたりして楽しんでいた。 一方、スタニスラフスキーは昼食会での文学者たちの会話に魅せられ、とくにチェーホフの血の通った文学論には魂の洗われる思いだった。 またここで、生涯の友となる二人の男と知りあうことになる。ゴーリキーとラフマニノフである。とくにゴーリキーとは互いに深い親近感を抱くようになった。 チェーホフとスタニスラフスキーという二人のはにかみ屋にとって、こうした出来事は互いに打ちとけあういい機会となった。 後日、スタニスラフスキーは自分の性格のことをこう語っている。 「それまで、長い間アントン・パーヴロヴィチ(チェーホフ)を知ってはいたが、心を許すことも、気楽な関係になることもなかった。 私の前に誰か有名な人がいて、私は実際の自分以上に知性的に見せようとしてきたのだということをよく知っている。 こうした不自然な振舞がかえってアントン・パーヴロヴィチをがんじがらめにした。 彼はただ解放的なつきあいが好きなのだ。 最初からそうした単純なつきあいができた妻は、いつも私以上に気易さを感じている。……」 ヤルタでの公演は、確かに二人の間の溝を狭めてゆく足がかりとなった。 |
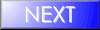 |
| TOPへもどる |
| 演劇ラボ |