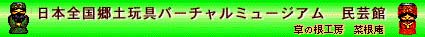
----福岡県篇・第7回----
---- FUKUOKA(7) ----
■柳川凧■
坂田信義さんは、レストランや土産品の販売、そして凧の製作をなどされています。レストラン「さかた」の裏に凧の工房があります。 坂田さんは伝統的な柳川凧の技術を受け継いで、八女の手漉和紙と真竹を素材に、7種類の手描きと印刷ものの両方を作っています。 「目返し面」は、「めん」と呼ばれ、代表的な柳川凧として親しまれ、柳川市のシンボルマークにもなっています。このどんぐり目は穴を開けて金銀の目玉が入っています。これを大空に揚げると、目玉が風に当りくるくる回りますので、「目返し面」と云われているのです。 「子守面」は、この目返し面を小型化したもので、1メートルほどの細長い竹が付いています。これは別名「おろろん凧」とも呼びます。「おろろん」はこの地方の子供をあやす言葉で、昔はこの凧の竹をかざして背中の子供に見せたそうです。 「から笠唐人」も、他では見られない形をした凧です。から傘・でんでん太鼓・向い鯛・扇子・酒徳利と、にぎやかに縁起ものが集まっていますので、祝いごとにも使われます。 この意表をつく意匠は、一説には、チベット仏教の「八吉祥文」に起源をもつといわれていますが、くわしいことはわかりません。 「むかで凧」は、実際は10〜20を連ねて揚げる「連凧」で、掲載のものはその1枚です。 掲載作品の他に、「えび尻(角凧にえびの尻尾のような尾がついている)」「奴さん」「とんび」「義経」があります。 製作者:坂田信義:柳川市筑紫町86..TEL: 0944-72-5123 (参考リンク)【CPH】→郷土玩具マップ→「福岡」→「坂田信義 : 柳川凧」の情報 ここに載っていない、連になった「むかで凧」と「義経」も掲載されていますのでご覧ください。 |

■山下仁三郎の諸玩具(廃絶)■
上の「柳川凧」はいつ頃からあったものかは不明ですが、「凧」やいろいろな郷土玩具を山下仁三郎という明治20年生まれの老人が作っていました。 山下仁三郎さんは、若いころは職が定まらず転々としていたようですが、仕事のかたわら凧作りを始めていました。 戦後も沖の端座で芝居の裏方をしていましたが、この頃から郷土玩具の注文が次第に増えて、晩年は「玩具作り」で生活するようになります。 昭和40年、78才で亡くなり、凧以外の玩具は後継者もなく廃絶しました。 この人の残した作品は、明治・大正時代をさながらに感じさせ「郷土玩具の原点をみる思い」がするといわれています。 その後、日本凧の会の人達により、山下さんの作った凧の復元などが行われましたが、その他の玩具は時代とともに忘れ去られようとしています。 --掲載作品-- 「紙の鯉:1月14日。戎(えびす)神社で売られていた」 「張り子の兎とだるま」「羽子板」「破摩矢」「鯉の滝上り」 |
| ▼‥[Next] 福岡県篇(8) | ▲‥[Back] 福岡県篇(6) |

|
(1999.6.26掲載)