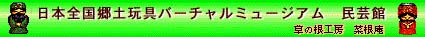
----島根県篇(2)ー1----
----SIMANE----
|
■出雲の灯玩具■ 「ジョーキ」:ジョーキとは蒸気船のことですが、この地方では明治の中頃、大型の船のことをすべてジョーキと呼びました。この玩具もジョーキと呼ばれていますが屋形船の形をしています。 竹と木で骨組みをして丈夫な八雲紙を貼り彩色してあります。屋形の内側に人の形の切り抜きが貼られていて、灯を入れると屋形の中で船遊びを楽しむ人物のシルエットが、浮かび上がるという仕掛けです。また、この玩具の絵付けの特徴は、温めたロウで模様を線描きして、その上から絵の具で彩色するという方法がとられていて、灯を入れたときに模様が美しく映えるようになっています。 「鯛堤灯」:上と同じように、竹と木の細工で、四角の台に大きな鯛が乗っています。鯛の両側のひれは内部で糸で吊り下げられていて、台の下の車を動かすとひれがゆらゆらと揺れる仕掛けです。 昔はこの地方の七夕や盆の行事に、各家庭の手造りのものを子供達が引いて歩いたそうで、大きいものは全長が1メートル位のものもあったそうです。 制作者:高橋至誠:出雲大社の門前町の「高橋屋」。前回掲載の大社の祝い凧も制作。 簸川(ひかわ)郡大社町杵築東720..TEL:0853-53-1553 |

|
■長浜人形(1)■ このページに掲載した作品は、江戸末から明治頃のものです。 この県の代表的な伝統のある土人形は、前回紹介の「白天神」とこの「長浜人形」ですが、同じ土人形でも、製法に多少の違いがあります。 鳥取の倉吉から出雲にかけての天神と、それといっしょに造られた土人形は、生土(なまつち)の上に胡粉をかけて彩色してあります。 長浜人形は、一般に見られる土人形の手法で、素焼きした人形に絵の具がほどこされています。 (次のページに現代の作品を掲載しています。)
|

|
(1998.11.29掲載)