ことばをめぐるひとりごと
その15
減少する「子名前」
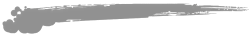
女の子の名前に、「〜子」が少なくなったと言われて久しい気がします。「〜子」の名前をもつ女の人にとっては、自分の仲間が減っていくような気がするんじゃないでしょうか。
明治生命では、自社の生命保険に加入した新生児の名前を調査して、その結果を毎年公表しています。昨年も12月下旬にマスコミで紹介されました。それによると、96年生まれの赤ちゃんの名前のうち、上位 100位以内に、「〜子」のつく名前はわずかに3つなのだそうです。
「子名前」は、古代は「蘇我馬子」「小野妹子」などのように男によく使われましたが、女性名にもありました。たとえば「万葉集」の石川郎女(いらつめ)は通称大名兒(オオナコ=漢字は宛字)といいましたし、藤原鎌足がめとった采女(天皇に伺候する豪族の娘)の名は安見兒(ヤスミコ)といいました。
平安時代中期からは上流階級で盛んに使われるようになります。清少納言が仕えた一条天皇の中宮「定子(さだこ)」、紫式部が仕えた「彰子(あきこ)」などの名が有名どころでしょう。
一般に広く使われるようになったのは明治後期になってからのようです。特に大正期から昭和20年代までは「子名前」の全盛で、先の明治生命の資料でも、この期間に生まれた女の人の名前の上位10位をまったく独占している状態です。「久子・文子・幸子・和子……」などといった具合。
昭和30年代には、「明美」さんなど「子名前」以外の名が人気を得てきましたが、依然「子名前」は健在でした。昭和50年前後に奈良・大阪・倉敷・鹿児島の高校を卒業した女の人9000人近くを調査したところ(つまり昭和30〜32年生まれが対象)、「〜子」は約71%、「〜美」は約11%、以下、「〜代」「〜恵」「〜江」などが続いていたそうです(寿岳章子『日本人の名前』大修館書店)。
高度成長期と軌を一にするようにして、「子名前」は減少していきました。明らかな変化があったとみられるのは昭和50年代後半、つまり1980年代に入ったころからです。「愛」ちゃんが台頭してきて、1983年には新生児の名前でトップになりました。以後、「愛」ちゃんは1990年まで連続して1位の座を保ち、翌年から現在までは「美咲」ちゃんがこれに取って代わっています。
保育園の坊ちゃんを持つ知人に以前聞いたところでは、0歳児〜5歳児クラスにいる35人の女の子のうち、「子名前」は5人で、いちばん多かったのは「〜み」(美・実・未・み……など)の6人ということでした。ほかには「〜か」(香・か……)の5人や、「〜奈」の4人などが多く、「〜子」と伯仲しています。「〜子」は一定の勢力を保ちつつも、今やワン・オブ・ゼムになってしまったようです。
(1997年記)
p.s. 女性の名前では権威である角田文衛著『日本の女性名』(教育社)がたいへん参考になりますが、残念なことに絶版です。古書店にもほとんど出回りません。
「復刊ドットコム」に復刊の声が挙がっています。あなたもご投票いただけませんか。
▼関連文章=「ナオミという名前」
|