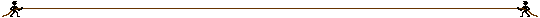
| �u���Ȃ����N�I�s�V�̔錍�I�H�v �@�@�Ƃ��V ���ǂ�œ����錒�N��� |
| ����ʈꗗ�ɖ߂� |
�y���肢�z
�@���쌠�̊W��Hyper�|Link�̐ݒ���s���Ă��Ȃ�����������܂��B���L���Ă�URL���𗘗p���A���Y�L�����������Ē�����K���ł��B
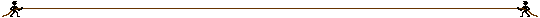
2006/09/03�������b�nj�Q�F�n���h�u�b�N�o�ŁA���J�j�Y���Љ�@
�@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/08/20060828ddm013100040000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/08/28�@�@�ߐH��^���s���̃��C�t�X�^�C������S�؍[�ǂ�]�����Ȃǂ̌��Ǖa�ǂ���܂ł́A���^�{���b�N�V���h���[���̕a�Ԃ��킩��₷���������A����20�N�x����̌��f�E�ی��w���`�����ɔ������A��Ï]���Ҍ����n���h�u�b�N�u���^�{���b�N�V���h���[�����H�n���h�u�b�N�v�i���V�C���ďC�A���f�B�J���g���r���[�����s�F�`�S��118�y�[�W�A3150�~�j���o�ł��ꂽ�B
�@�{���́A�E���ɑ���ی��w���Ő����K���a�\�h�Ɍ��ʂ��グ�����Ɍ����s�̎��g�݂Ɋ�Â��A���H�I�ȓ��e�ɂȂ��Ă���B�o�ŎЃR�����g
�@�P�j���s�s�����E���̐S�؍[�ǁE�]�������O�ɂ����ی��w���̌��ꂩ�琶�܂ꂽ���̂ł��B
�@�Q�j�ی��t���͂��߂Ƃ���S���̌��f�E�ی��w���ɏ]�����Ă�����X�����̎��H���B
�@�R�j�藣���Ă����g����ی��w���p�`���[�g���t���Ă��܂��B
2006/08/26���炾�Â���F����₷���Ȃ����̂͂Ȃ����ȁ`�@
�@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/08/20060823org00m100011000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/08/23�@�@�@�u�ŋ߁A�Ȃ�����₷���Ȃ����v�u�^�������Ă��A�v���悤�Ɏ��b�������Ȃ��v�u���N�A�����������Ă��Ă���B�v�Ƃ������A�K���̏��ł��B�@�Ȃ�����Ղ��Ȃ��Ă���̂��A���퐶���̒��̑̂Ɉ����K�����`�F�b�N�ł��܂��B���āA���Ȃ��́A�������Ă͂܂�܂����H
�y����z
�@��ɐ����s���ł���i�������Ԃ�5�`6���ԁj�^�n���ł��Ȃ��^�T�ɂS��ȏ�َq��H�ׂ�^�q���̍��i�c�����`15�Έʂ܂Łj�ɔ얞�ɂȂ����o�������� �^���H��H�ׂȂ��^��ɃG�A�R���������Ă��镔���ɂ���^���e���i���͌Z�킪�j�얞�ł���^����13�F00���܂łɐH�I���A�c�ƂȂǂŁA�[�т�21�F00�ȍ~�̓��������^35�ˈȏ�ł���^�X�g���X��������Ƒ�R�H�ׂĂ��܂��^�T��3��ȏ�A�܂݂�H�ׂȂ��炨�������ށ^�ߏ��̃R���r�j���Ԃňړ�����^�Ԓʋł���^���H���ł���^�P���̓��ŁA�[�H����ԁu��������v�H�ׂ�
�y�����z
�@��L�̎���ɑ��ē��Ă͂܂鐔���A�ЂƂȏゾ�ƁA�v���ӁB�R�ȏ�ł́A���Ȃ�댯�B�T�ȏ�́A��ςł��I�@
2006/08/20�m�肽���F�u�����L�Q�v���Ė{���H�@�h�{�w�I�ɂ͏����h�@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/08/20060818dde001040013000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/08/18�@�@�u���N�����v�̑�\�i�̋������u�L�Q�v�Ƃ���������Ђ�l�b�g��Ŏ��グ���A�g����L���Ă���Ƃ����b��ɂ��āB
�@�[���ƂȂ����̂́A�č��ݏZ�̈ݒ��������O�Ȉ�E�V�J�O�������ƂȂ�u�a�C�ɂȂ�Ȃ��������v�i�T���}�[�N�o�Łj�����A���҂̒��N�̗Տ��o�����瓱���o�����H�����̉��P�@���܂Ƃ߂����̂ŁA�����Ɋւ���L�q�����ɒ��ڂ���A�X�ɁA���z�������̊ϓ_����̗L�Q�����o�ꂵ�����삪�L���������́B
�@�����Ɋ܂܂��J���V�E���̐ێ挹�Ƃ��ċ����͗L�v�łȂ��Ƃ��鍪���̈���A���e���傤�ǂƂ̊W�B
- �������X�N�㏸
- �q���p���ނ̕s���R
- �H�Ɖ�����@�ɖ��
�����ێ�ʂ��������Ă̍���҂̑�ڍ��̍��ܗ��́A���{��荂�����߂Ɂu�����͖h�~��ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ�����ɑ��A�̌^�̍����Ƃ����������B�@�q���̐����𑣂������ɂ́A���_�G�X�g�������̏����z���������܂܂�Ă���A�����͕v�E�R����ȑ喼�_�����ɂ��A�u���_�G�X�g�����̓r�X�t�F�m�[���`�Ȃǂ̊��z���������������v�Ƃ����B����ɑ��A�R����_�w���̒����q�F�����i�b��w�j�́u��������z��������ێ悵�Ă��A�����̑̓��̃z�������̗ʂɔ�ׂ�Δ��X������́v�Ƌ^���悷�ӌ�������B
�@�L�Q�̈�Ƃ��āA�u�����͎q�������ނ��̂ŁA�l�����̚M�������̓������ނ͕̂s���R�v�Ƃ̍l����������B
�@���_�w�����w�@�̒���v�j�����i�������w�j�ɂ��A�ŋ߂̋��̎���@���H�Ɖ�����A���̐����ɍ���Ȃ��Ȃ��Ă����肪����Ƃ����B�u���^�{���b�N�nj�Q���点�I�v���f���̎w�������@
�@�@http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_06081827.cfm
�@�@�@�@�@YOMIURI ONLINE > �W���u�T�[�` > �j���[�X�@2006/08/18�@�@�����J���Ȃ�18���A�������b�nj�Q�i���^�{���b�N�E�V���h���[���j�̍L�����h�����߁A���N�f�f�̍ۂɎ��{�����ی��w���̂���������������j���ł߂��B
�@�ی��t�����f���ʂ܂��A��̓I�ȖڕW��ʐڂ�[���ŐϋɓI�ɒ��A���̌���p���I�Ƀ`�F�b�N���邱�ƂŁA�u���k�^�w���v����u����^�w���v�ւ̓]����}��B08�N�x������{������B
�@�V�����ی��w���́A���^�{���b�N�E�V���h���[���̎w�W�ƂȂ�E�G�X�g���͌a�⌌���A�����l�Ȃǂ̐��l�̉��P��ڕW�Ƃ���B
���f���ʂ����āA�ɉ����ĉ��L�������{����B
�@�q�P�r���͂⌌���Ȃǂɖ�肪�����A���P���s���ȏꍇ�́u�ϋɓI�x���v
�@�q�Q�r�ꕔ�ɖ��͂��邪����ێ��ł������ꍇ�́u���@�t���x���v
�g�E�K���V�ɐH��̍������\�h���ʂ��� / �����Ă���l�قnj����I�@
�@http://nh.nikkeibp.co.jp/nh/supli/2006/060815_02.shtml
�@�@�@�@���o�w���X�@ �u�T�v�����@�\���H�i�v�j���[�X 2005/08/15�@���̂قǔ��\���ꂽ�I�[�X�g�����A�ł̌����iAm.J.Clin.Nutr.;84,63- 69,2006)�ɂ��A�g�E�K���V�Ɋ܂܂��h�ݐ����u�J�v�T�C�V���v�́A�H�ׂ�����̓��ŔM�ɕς����p�������Ă���A�얞�ⓜ�A�a�̌����ƂȂ�H��̍�������}�����p�������Ƃ��킩�����Ƃ����B���̌��ʂ́A�얞�C���̐l�قǍ��������B
�@���̌����ł́A�`���\�[�X���g���Ă���A1���ɐH�ׂ��ʂ͐��̃g�E�K���V16.5g���Ƃ��Ȃ�̗ʁB�����g�E�K���V�̕����Ŋ��Z����ƃe�B�[�X�v�[��4�`5�t���ɂȂ�B���H���͔얞�̂��Ɓ@����O���[�v�����@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200608120369.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/08/12�@�@���É���̋ʍ��_�i�E�������i���O�q���w�j�A��w�@���̑�˗炳��炪�A���m�����ɏZ��35�`69�̒j��3737�l�A����1005�l�̐g���E�̏d�E�H�����e�E�^���K���̃f�[�^�͂������ʁA���H�������邱�ƂŔ얞�������Ղ��Ȃ邱�Ƃ��������Ƃ����B�@���H�����̂��̂��A�얞���������R�͂܂��悭�킩���Ă��Ȃ����A���H�����ƁA�G�l���M�[�̎�荞�݂𑣐i����z�������A�C���X�������ߏ�ɕ��傳���\���Ȃǂ��l������Ƃ����B
2006/08/03�w���V�[���|�[�g�F���N�C���t�H���[�V�����@�������b�ɍ��G����
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060729ddm010100213000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/07/29�@�@�T���g���[��5�����甭�������u���G�����v���H��̒������b�̏㏸��}����Ƃ������ƂŁA����ی��p�H�i�i�g�N�z�j�ɔF�߂�ꂽ�B
�@�Տ������͒������b����⍂�߂̐��l�j��20�l�Ŏ��{���A�H���Ɠ����ɍ��G����������ŁA���̈����ɔ�ׁA�H��̌����������b�̔Z�x����20���Ⴍ�Ȃ����B
�@�܂��A�j��12�l�E10���ԁA�H�����ɍ��G����������ŁA�ւɊ܂܂�鎉�b�ʂׂ���A���܂Ȃ����ɔ�ׁA���b�̔r���ʂ���2�{�������Ȃ����B
�@���̌��ʂ́A���t�̔����y�̉ߒ��łł���u�E�[�������d���|���t�F�m�[���v�̍�p�ɂ��Ƃ����B���T���g���[���j���[�X�����[�X�@No.9410 �i2006.4.4�j
�@�@�T���g���[�u���G�����v�i����ی��p�H�i�j�V�����@�\�@���b�̋z����}���A�H��̒������b�̏㏸��}������@�\
2006/07/23�����K���a�h���ɂ́c�@���J�Ȃ��^���ʂ̖ڈ��܂Ƃ߂�
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200607120327.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/07/12�@�@�����J���Ȃ̉^���w�j���ψ���A�����K���a�̗\�h�ɕK�v��1�T�Ԃ̉^���ʂ̖ڈ����������w�j�u�G�N�T�T�C�Y�K�C�h2006���15���܂łɂ܂Ƃ߂��A19���ɊJ����铯�Ȍ�����ɕ���B
�@�X�|�[�c�����łȂ��A���퐶���ł̊������Ώۂɂ��āA���e���Ƃɋ�̓I�Ȏ��Ԃ������āA�^���K���̂Ȃ��l�ł����p�ł���̂������B�@���^�{���b�N�nj�Q�̐l�����ɁA�ڈ��Ƃ���镠�́i�j��85cm�ȏ�A����90cm�ȏ�j��1cm�ׂ�����̂ɕK�v�ȃG�l���M�[����ʂ��u7000��cal�v�Ɛݒ�B�����̕��͂���l�ȉ��ɂ��邽�߂ɁA�P���ɂǂꂾ���G�l���M�[������������������悤�Ɏ������B
2006/07/02�w���V�[���|�[�g�F���N�C���t�H���[�V�����@�_�C�G�b�g�ɂ�����
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060702ddm010100145000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/07/02�@�@�J�c�I�߂ɂ̓A�~�m�_�̈��̃q�X�`�W�����܂܂�A���ꂪ�]�̖����������h�����ĐH�߂���h������������Ƃ����B
�@�l��Ώۂɂ��������ŁA�q�X�`�W���̐ێ�ʂ������قǔ얞�x��\���̊i�w���iBMI�j���Ⴍ�Ȃ����Ƃ���������B20��/�����x�̃J�c�I�߂����A�얞�\�h�̓�����������Ƃ�����B
�@�J�c�I�߂ɂ̓A���Z�����Ƃ����A�~�m�_���܂܂�A�A���Z����������Ă���^��������ƁA��J�̎w�W�ƂȂ錌�t���̓��_���Ⴂ�Ƃ�����������������A�^����̔�J�����y�����铭��������B�N���~�F�H�ׂČ��N�Ɂ^�����g�j���ōR����i���̂P�E�Q�j
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060628ddm013100002000c.html
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060628ddm013100125000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/06/28�@�@�N���~�́A���̂܂ܐH�ׂ邱�Ƃ͂��܂�Ȃ����A�ŋߓ����d���Ȃǐ����K���a�̗\�h���ʂ��Ȋw�I�Ȍ����ŕ�����A���ڂ���Ă���B
���u���A�悭�Ȃ���v�L�x
�@���̃i�b�c�ނɔ�ׂāA���i�A���t�@�j�|���m�����_�Ƃ����s�O�a���b�_���L�x
�����t�T���T��
�@�N���~�ɂ͓����d����h������A���ʃR���X�e���[�������炷���ʂ̂��邱�Ƃ��������Ă����B����l�̐H�����ŕs���������Ȃ��|�R�n���̕�[�ɃN���~���𗧂B
���R���X�e���[���ቺ
�@�č��e�c�`�i�H�i���i�ǁj�́A�Q�N�O�A�u42��/���i�k�t����7�`8���j�̃N���~�̐ێ�ŐS�������̃��X�N�����炷�v�Ƃ̌��N�����\����F�Ă���B���y�[�X�g����Ε֗��|�|�u�����X���z�\�ԁv���������E���c�����ɕ���
�@�N���~�ɂ̓z�������̈��ōR�_����p���������g�j�����܂܂��B
�@�ƒ뗿���ŃN���~���g���ꍇ�́A�y�[�X�g������Ă����ƕ֗��B
�@�u�N���~�̃y�[�X�g�͉��H�ɂ������B���W�u�T�v�����@�\���H�i2006�v�Ŗ��É���w��w�@�����̑��V�r�F�����u��
�@�@�@�@�A���R���̍R�_���E��Ő����̃G�r�f���X���Љ��@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426830
�@�@�@----���o�w���X�@ �T�v�����@�\���H�i�@2006/06/24�@�@�u�T�v�����@�\���H�i2006�v�̐��t�H�[�����Ŗ��É���w��w�@�����_�w�����ȋ����̑��V�r�F�����u�A���f�ނɂ���łƍR�_���v�Ƒ肵���u�����s�����B�@�d�����̔r�o�𑣂��悤�ȉ�Ń��[�g�����łȂ��A�̑��̃O���^�`�I��S�g�����X�t�F���[�[�iGST�j�Ȃǂ̉�ōy�f�ɂ��g�ł������h��Ń��[�g���̓��ŏd�v���Əq�ׂ��B
�@���̉�ōy�f�������U������|���t�F�m�[���̔z���̂Ȃǂ̐A���������Ƃ��āA�u�S�}�R���̃Z�T�~�m�[���z���́v�A�u�E�R���R���̃N���N�~���v�A�u�A�u���i�Ȗ�ؒ��o���v�A�u�p�p�C���A�A�{�K�h�A���ށA�����S�Ȃǂ̉ʎ��v�Ȃǂɂ��GST�������f�[�^���������B
�@�����J�����[�Łu��������i���S�̐H���v����A�u��E�ʕ����S�̐H���v�ւƐH�����e��ς����ꍇ�ɁA�A���ɔr�o������`�q�_������8-OHdG��1/3�Ɍ���������������B
�@�V���A�����K���a�A���ǂȂǂ�h�����߂ɁA�����_�f��t���[���W�J������������̓��̃��h�b�N�X�n���ێ����邱�Ƃ��d�v�B
�@�R�_�������A�R�_���r�^�~���Ȃǂ��A�����ێ悵�ă��h�b�N�X�n���ێ����邱�Ƃ��d�v�ŁA���̂��߂ɂ́A��ŁE�R�_���Ƃ��ɁA���ʎ��Ȃǂ̐A�������������ڂ����悤���B
2006/06/25���W�u�T�v�����@�\���H�i2006�v�ō������N�E�h�{�������������̓n粏�������u��
�u�T�v���͖�ł͂Ȃ��A���肷�����A�H���ɒ��ӂ�/�i�ރt�@�C�g�P�~�J�������A�Ǐ�Ɛ����̑��ւ����X�ɉ𖾁v�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426829
�@�@�@----���o�w���X�@ �T�v�����@�\���H�i�@2006/06/24�@�@�u�T�v�����@�\���H�i2006�v�ō������N�E�h�{�������������̓n粏�������u���H���s���A�u�H�v�ɂ��Ă̐������m���������Ƃ̏d�v����i�����B�@�H�����̂ɗ^����e���Ƃ��āA�t�@�C�g�P�~�J���i�|���t�F�m�[����J���`�m�C�h�ȂǁA�����K���a��K���\�h�ɖ𗧂Ƃ���Ă���A���������j�ɂ��Ă̍ŐV�����Љ�B
�@���ʕ��Ɋ܂܂��J���`����C�\�t���{���A�ܗ��������Ȃǖ�50��ނ̐����̐ێ�ʂƁA�얞�A���A�a�A�������A���a�Ƃ������a�C�Ƃ̑��ւׂ��B���֗�F
�E�J���`���ނ́A�Ƃ�قǔ얞�̃��X�N�����߂邪�A�J�e�L���͌��炷���ɓ����B
�E�P���Z�`���́A���a�̃��X�N�����炷�X��������B
�E�t�@�C�g�P�~�J���Ƃ����ǑS�Ăāg�����h�킯�ł͂Ȃ��A�ǂ�Ȏ��a�ɑ��Ă����X�N�y���ɗL���������̂́A�C�\�t���{�������������Ƃ����B�@��l��l��������������m���āA�H�����ɐ������āA�u100�܂Ō��C�Ő����āA�R�����Ƃ����v���Ƃ�ڎw�����ƌĂт������B
2006/06/18�t�@�C�g�P�~�J���F�u��V�̉h�{�f�v�@����\�h�A�A�����M�[���P�̗͔��
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060615ddm013100164000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/06/15�@�@���ʕ��Ɋ܂܂��A�������w�����u�t�@�C�g�P�~�J���v�́A�ŋ߂̌������炪��\�h��A�����M�[�̉��P�ɂ��𗧂��Ƃ��m�F����Ă���A�u��V�̉h�{�f�v�ƌ�����Ă���B�@�����t�@�C�g�P�~�J���̃p���[�ƐH�����ւ̏��Ȏ�������ɂ��Ẳ���L���B���W�F���ʕ��ɖ�P����
�@�]���A�h�{�f�Ƃ����^���p�N���A�Y�������A�����A�r�^�~���A�~�l�����̌܂��w�������A�H���@�ۂɑ����V�Ԗڂ̉h�{�f�Ƃ��āu�t�@�C�g�P�~�J���v�����サ�Ă���B
�@�L���x�c�A�^�}�l�M�A�_�C�R���Ȃǂ̒W�F���o�i�i�A�p�C�i�b�v���Ȃǂ̉ʕ��ɑ����܂܂�A��\�I�Ȃ��̂̓A���g�V�A�j���A�J�e�L���A�哤�C�\�t���{���ȂǂŁA��P����ނ���Ƃ����A�a�C���̂��̂�\�h��������P����͂��L�邱�Ƃ������Ă��Ă���B���������𑝂₵������
�@�������́A�̓��ɐN�������ٕ��₪��זE�A�E�C���X�Ȃǂ��E�������߂铭��������B�A���̒��ɂ́A���̔������̓��������߂鐬�����܂܂�Ă��邱�Ƃ������Ă����B
�@��Ƃ��ẮA�j���j�N��V�\�A�^�}�l�M�A�V���E�K�A�L���x�c�A���l�M�A�ʕ��Ƃ��ẮA�����S�A�L�E�C�A�p�C�i�b�v���A�������Ȃǂ����������𑝂₷�B
�@�L���x�c��i�X�A�_�C�R���A�z�E�����\�E�Ȃǂ̖�́A�������Ɋ܂܂���s�m�e�i��ᇉ��q�j�𑝂₵�A���̔Z�x�͍R����܂�C���^�[�t�F�������������Ȃ邱�Ƃ����������B
�@�ʕ����o�i�i�A�X�C�J�A�p�C�i�b�v���A�u�h�E�Ȃǂ�������������������͂�����B
�@�v�́A��E�ʕ����R�H�ׂ邱�ƂŁA�����������������āu����v�͖ܘ_�A�������ǂ⓮���d���A���A�a���̐����K���a��̑��a�A�A�����M�[�����ɂ����ʂ����҂ł���Ƃ������Ƃ̂悤���B
�@���ێ�ɕ֗��ȏ����
�@�t�@�C�g�P�~�J�����\���ɐۂ�ɂ́A�W�F�����ł����u�߂��肵�ĐH�Ղ����A�ێ�ʂ𑝂₷���Ƃ���B�܂��ʂ����łȂ��H�ׂ��ނ𑝂₷���Ƃ��d�v���B
�@��L�̋L���ɂ��Љ��Ă���u�t�@�C�g�P�~�J���v���A�����m���ɑ�R�ۂ邽�߂̔錍���Љ��Ă��܂��B
2006/06/03���^�{���b�N�V���h���[���F���点�I�������b�@�\���R����̐H����
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060601ddm013100055000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/06/01�@�@�얞�����ƂŁA�������ǂⓜ�A�a�A�������ǂȂǕ����̐����K���a�ɂȂ�댯��������A�����d���������N�����₷����Ԃ����^�{���b�N�V���h���[���i�������b�nj�Q�j�����A5���̌����J���Ȃ����\�ł�40�`74�Œj����1/2�A������1/5�����̊Y���҂Ɨ\���R�������B
�@���^�{���b�N�V���h���[���\�h�̂��߂̐H���́H�@�q���g�ƂȂ郌�V�s��H�����̍H�v���܂Ƃ߂Ă���B����J�����[�ł��H�v�Ŗ������|�|���ڐH�ނ̓A�[�����h�A�|
�@���^�{���b�N�V���h���[���̌����́u�������b�v�B�\���R�̐l�́A�������b�����炷�A��J�����[�̐H����S�|���邱�Ƃ��K�v�B
���v���̉h�{�m����������A�a���ÐH�̑�z�H�𗘗p
�@�����̍H�v�F
�@�@�����⋛�͏��ʂɂ��Ė�Ń{�����[�����o��
�@�@���M���𑽂����Č����ڂ����ɂ���
�@�@��������������Ǝ�����G�߂̏`����������
�@�@���V�N�ȐH�ނ��g���|�|�Ȃ�
�@�@���������̂Ȃ��ŗB�ꐧ���Ȃ��g���Ă����̂��|�B
�@���ڂ̐H�ނ��A�[�����h
�@�@���ʃR���X�e���[�������炷�I���C���_���L�x�ŁA�R�_�������̃r�^�~���d��H���@�ۂ������܂ށB
����ς�n���C�H�͂����I �n���C�H��O�ꂷ��ƃA���c�n�C�}�[�a�����Ȃ��Ȃ�@�@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426647
�@�@�@----���o�w���X�@ �T�v�����@�\���H�i�@2006/05/12�@�@�ăR�����r�A��w�������̃j�R���X�E�X�J�[�~�[�Y���m��̌����O���[�v���A�u�_�o�Ȋw�I�v�v�iAnnals of Neurology�j2006�N4�����ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A�j���[���[�N�̃}���n�b�^���ɏZ��2258�l��ΏۂɁA���N��ԂƐH���̓��e�ׁA�F�m�ǂɂ������Ă��Ȃ������m�F�������ʁA�I���[�u���A�i�b�c�Ȃǂ���I���C���_�Ȃǂ̕s�O�a���b�_�𑽂��ۂ�A��������i�͍T���ڂŖO�a���b�_�����Ȃ��ۂ�A���A���ށA���A�����ĉʎ����������Ղ�H�ׂ�Ƃ����n���C�X�^�C���̐H����O�ꂵ�Ă���l�́A�S���a�ɉ����A�A���c�n�C�}�[�a�̔��ǂ����Ȃ����Ƃ��������Ƃ����B
2006/05/27�u�a�H�̓w���V�[�v���@���k��A�l�Y�~�Ŏ����@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200605230391.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/05/24�@�@���k��̋{�V�z�v�����i�H�i�w�j�炪�l�Y�~���g���������ŁA���N�ɗǂ��̂͗m�H�����{�H�Ƃ����ʐ����Ȋw�I�ɗ������B
�@���Ă̍����h�{��������ɁA�ŋ߂̗����̑�\�I�ȂP�T�Ԃ̃��j���[�e21�H���i���{�H�͂����݂�G���A�I�����C�X�ȂǂŁA�č��H�̓n���o�[�K�[��t���C�h�`�L���Ȃǁj��I�сA���������������ɂ���3�T�ԐH�ׂ������B
�@�l�Y�~�̊̑��Ōv�P����ނ̈�`�q�̓������ׂ��Ƃ���A���{�H�̃l�Y�~�ł̓R���X�e���[���⎉�b�����镡���̈�`�q���A�č��H��1.5�{�ȏ�Ɋ��������A�̑����ɂ��܂����R���X�e���[���ʂ́A�č��H�̕����P���ȏ㑽�������B�������b�nj�Q�i���^�{���b�N�E�V���h���[���j �f�f��͑Ó��H�@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060522ik05.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2006/05/22�@�@���Ȃ��Ɏ��b�����܂�������b�nj�Q�i���^�{���b�N�E�V���h���[���j�̒����N���A�\���R�����킹��2000���l�ɋy�Ԃƌ����J���Ȃ����\���A�S�؍[�ǂ�]�����������Ƃ���A���J�Ȃ���ɏ��o�������A�f�f��̑Ó����⎡�Â̂����������ۑ�����サ�Ă���Ƃ����b��ɂ��āB�������N�j���̔����g�댯����h�@��܂�Ȃ���w�I�]��
�@�������b�nj�Q�����ڂ����̂́A
�@���ɁA�������b�����A�a�A�������A�������ǂ������N�������Ƃ������Ă������߂��B
�@���ɁA�얞�ƍ������A�������A�������ǂ�4���ڂ̑g�������A�S���a��]�����Ɩ��ڂɊւ���Ă���_�B���E�G�X�g�T�C�Y�A�Ă�102������
�@�E�G�X�g�T�C�Y�́A�č��ł͒j����102�������ƂȂ��Ă���̂ɑ��A���{�l�j����85�����ȏ�ƁA���Ȃ茵�����ݒ肳��Ă��锽�ʁA�����̊���A���{�l��90�����ȏ�ƕč��l�i88�������j���ɂ₩�Ȃ̂ƑΏƓI�Ȃ��Ƃɑ��āA����z��E���C���w�������͉��L�̎w�E�����Ă���B�q�P�r�����Ώۂ����S�l�ŏ��Ȃ�����
������ƊE�����S�@��̉ߏ�g�p���O
�q�Q�r�댯���q������ꍇ�̓������b�ʐς��Z�o���Ă���A�����̊댯���q�������̏nj�Q�̐f�f��f�[�^�Ƃ��ĕs�K��
�@�����A�����A�����l�������Ȃ邱�̏nj�Q�ł́A�~����A�����~����A�������ǎ��Ö�Ȃǂ��Ɏg�����Ƃ��ł��邱�Ƃ�A�ʂ��Ղ̐����K���w���ł́A�����Ȃǂ͗e�Ղɂ͉�����Ȃ����߁A���Ղɖ���o���ꍇ�����邽�߁A��̉ߏ�g�p�ɂȂ��錜�O������B������Ȃ����b
�@������������ł��A�̐S�̓������b�͌���Ȃ��B���Ȃ���肪�C�ɂȂ�l�́A�y���^������n�߂Ă݂Ă͂ǂ����낤���B���S���a�A�]�����c��Ô�}���֗\�h�ɗ͓_�@���J��
�@���J�Ȃ��������b�nj�Q�̑�ɗ͂�����w�i�́A�c������Ɨ\��������Ô�̗}�����B�V�l�ی��@���������A2008�N�x����40�Έȏ�̌��f��啝�Ɍ�������āA�V�������f�́A���nj�Q�̔������d������������B
�@�\���R�̒i�K�ł̕ی��w�����������A�K�v�ɂȂ�O�ɁA��f�҂̐����K����ς���悤�������A�ی��w�������Ő����K����ς���̂͊ȒP�ł͂Ȃ��B���nj�Q�͍��ۓI�ɂ͐f�f����قȂ�ȂǁA��w�I�ȕ]������܂��Ă��Ȃ��ʂ�����A�ی��w���ɂ��S�؍[�ǂȂǂ�\�h�ł��邩�ǂ����̃f�[�^�����Ȃ��A����̌������߂���B�m�肽���F�������b�nj�Q�i���^�{���b�N�V���h���[���j�@�ۂ����肨�Ȃ��A���p�S�@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/05/20060522dde001100005000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/05/22�@�@�����J���Ȃ́A���̑S�������ŁA40�`74�̒j���̂P/2�A������1�5���u���^�{���b�N�V���h���[���i�������b�nj�Q�j�v�Ƃ��̗\���R�������Ɣ��\�����B
�@���^�{���b�N�V���h���[���́A�����Ɏ��b�����܂�A�������⍂�����A�������ǂȂǂ̏Ǐ�x�ɕ����o�邱�Ƃ��w���A�V�����a�C�̊T�O���B�u���Ȃ����ۂ�����o�Ă��āA���N�f�f�̐��l�̂�����������l��菭�����߁v�Ƃ����l���Y������B���̍����̐f�f��́A���{���Ȋw��ȂǂW�w���N�S���ɒ�߂��f�f��́A���L�̂悤�ɂȂ�B�����^�{���b�N�V���h���[���f�f��F
�@�@�@�ɉ����A�A����ȏ�Y������ꍇ�ŁA�A���P���Y������ꍇ�͗\���R�@�@�E�F�X�g�@�j���@85�����ȏ�A�����@90�����ȏ�
�@�A�����@�@�@�ō������@130�ȏ�@���́@�Œጌ���@85�ȏ�
�@�@ �����l�@ ���Ɂ@110����/�����@�ȏ�
�@�@ �����@�@�@�������b�@150����/�����@�ȏ�A���́@HDL�R���X�e���[�� 40����/���� ����
2006/05/14�������b�nj�Q�A40�Β��j���̔����댯�@�]�[�ǂ̌����@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200605080242.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/05/08�@�@�����J���Ȃ��������N�E�h�{�����̈�Ƃ��āf04�N11���A����ׂɑI��20�Έȏ�̒j��1549�l�A����2383�l��Ώۂɐg�̌v���⌌�t�����Ȃǂ����{�����������ʂ\�����B
�@���̌��ʂɂ��A�S�؍[�ǂ�]�����Ȃǐ����K���a�̈������ƂȂ�u���^�{���b�N�V���h���[���i�������b�nj�Q�j�v�̋^�����������A���̗\���R�ƂȂ�l��40���߂���Ƌ}�����A40�`74�̒j���̖��ɏ��Ƃ����B�@���^�{���b�N�nj�Q�̔���́A�������b�̒~�ς������ڈ��Ƃ��ăE�G�X�g���j����85�����ȏ�A������90�����ȏ��K�{�����Ƃ��āA�X�Ɍ��������A�����A������2���ڈȏ�Ŋ�l����Ɓu�^���̋����l�i�L�a�ҁj�v�A�P���ڂŊ�l����l���u�\���Q�v�Ƃ��Ă���B
�R���X�e���[���⒆�����b�A�[�������ʓI�@���ꌧ�L�c���Z�����@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/OSK200605020051.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/05/02�@�@�����z��a�Z���^�[�̖k�����j�E�Տ������J��������ƁA���ꌧ�L�c���Ȃǂ������ŏZ����ΏۂɎ��{�����������ʂɂ��A�����̃R���X�e���[���⒆�����b�������l�ɂ͔[�������ʓI�Ȃ��Ƃ��������B�@�����A�����A�����A�얞�̂����ꂩ�̎w�W������47�`81�̒j��52�l�ɖ�P�J���ԁA���H��30���̔[�������I�ɐH�ׂĂ���������ʁA���R���X�e���[���Q�ł͕���7.7���A���������b�Q�ł͕���12.9���A�����Z�x���ቺ�����B
�w�Z�ŃW���[�X�̔��֎~�ց@�q���̔얞�h�~�ɍ��̏B���{�@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/JJT200605020001.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/05/02�@���B�ł�10��̎q����3�l��1�l���W���[�X�@2��/���@�ȏ����ł���A20�`25�����얞��Ԃ̂��߁A �@�I�[�X�g�����A�쓌���̃r�N�g���A�B���{�́A�����̏��E���E���Z�ɂ��锄�X�⎩�̋@�ł̃W���[�X�̔̔������N���ɋ֎~����Ƃ����B�����K���a�Ɨ\�h�@
�@�@http://www.oyappy.com/index.html
�@�@�@�@�@�~�c�J�@���E�X�P���^�c����{�����e�B�A�I�Ȑ����K���a�̉���y�[�W�@�Ꭹ�ȏЉ��
�@�����̃z�[���y�[�W�ɂ��Ă��ꂽ���ɐ����K���a�̕|���Ȃǂ����|�[�g��̌����܂Ƃ߁A
�@�@��Ȃǂ��݂ė\�h�ȂǂɎ�荞��ł����K���ł��B�@�Ƃ����A���́@40�H�̃��E�X�P���^�c���鐶���K���a��������A�֘A�T�C�g�̏Љ�����Ă���{�����e�B�A�I�ȃy�[�W�ł��B
2006/04/23�Β��E�R�[�q�[�ɓ��A�a�\�h���ʁ@�S���P���V��l�����@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200604190516.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/04/20�@�@40�`65�̓��{�l�j���ŁA���A�a�₪��A�S���a�ɂȂ��Ă��Ȃ�����17,413�l�ׂ������Ȋw�Ȃ̌�����ɂ���K�͒����̌��ʁA����̈锎�N�����i���O�q���w�j�炪�A18���t�̕č����Ȋw��̐�厏�ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A �Β���6�t/���ȏ���ސl�́A�P�t/�T�����̐l�ɔ�ׂē��A�a�̔��ǃ��X�N��33�����Ȃ��A�R�[�q�[��3�t/���ȏ���ސl���A�P�t/�T�����̐l�ɔ��42�����Ȃ��Ƃ����B
�@�R�[�q�[�̓��A�a�\�h���ʂ͉��ĂȂǂ̌����Ŏw�E����Ă������A����A�Β��̌��ʂ����炩�ɂȂ����B�Ăʂ��Ɍ����A�����A�����l�����鐬���@
�@�@http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200604/500226.html
�@�@�@�@�@���o���f�B�J�� �I�����C���EHot News�@2006/04/17�@�@���k��w�_�w�����ȐH�i�@�\���N�Ȋw�u����Ardiansyah���炪�AJ. Agricultural and Food Chemistry���d�q�ł�2006�N�P��27���ɕ����Ƃ���ɂ��A�Ăʂ��ɂ͑��l�ȍR�_���������܂܂�Ă���A�Ăʂ��R���̐�����Y�����������ɂ��A�]�����Ք��Ǎ��������R���ǃ��b�g�iSHRSP�j�̌����������邱�Ƃɏ��߂Đ��������B���������łȂ��A���������ʁA�����l�����������ق��A�_���X�g���X�̌���������ꂽ�Ƃ����B���_���̌���F�uRice Bran Fractions Improve Blood Pressure, Lipid Profile, and Glucose Metabolism in Stroke-Prone Spontaneously Hypertensive Rats�v
�i���œ��A�a���X�N������@
�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20060414hj001hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/04/13�@�ăA���o�}��w��w���������Ńo�[�~���K���ޖ��R�l�Lj�ÃZ���^�[��������Thomas Houston���m�炪�A�p��t��uBritish Medical Journal�v��4��8�����ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A�č��l�j��4,500�l��Ώۂ�15�N�̒ǐՌ������s�������ʁA�i�������A�a���X�N�傳����\�������邱�Ƃ������ꂽ�B
2006/04/02���Ă�S�����͐S�������A���A�a��얞�ɂ��Ȃ�ɂ�������@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/mdps/426457
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/03/31�@�@�ėՏ��h�{�w�G���iAm. J. Clin. Nutr.�j�ɕ��ꂽ�č��̌����ɂ��A���Ă�A�S�����̃p���Ƀp�X�^�����H�ɂ��Ă���A�S���a�ɂ����A�a�ɂ��Ȃ��Ƃ����B
�@�H���@�ہA�r�^�~����~�l�������L�x�Ȗ������̍�����H��ɂ����Ǝ����ꂽ�����悳�������B�_�[�N�`���R���[�g10g���̃J�J�I��ۂ葱����ƁA�S���ǎ��Ƃ����錴���ɂ�鎀�S���X�N����������@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/mdps/426213
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/03/30�@�@�I�����_�������O�q������������Brian Buijsse���炪�AArchives of Internal Medicine��2006�N2��27�����ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A15�N�ɂ킽�荂��҂̃J�J�I���܂ސ��i�̏K���I�Ȑێ�ƁA�����ƐS���ǎ��̊W�ׂ����ʁA�J�J�I���i�̐ێ悪�����������A�S���ǎ��ƁA�����錴���ɂ�鎀�̃��X�N�������邱�Ƃ��������B�����A�S���ǎ��A�����錴���ɂ�鎀�ƃJ�J�I�ێ悪�t���֊W�ɂ��邱�Ƃ��������u�w�I�Ȍ����͂��ꂪ���߂Ă��Ƃ����B�@���_���̌���F�uCocoa Intake, Blood Pressure, and Cardiovascular Mortality�v
2006/03/19���b�̗ʂ�}�������{�H�Ə��ʂ̃X�^�`�����^�ō����R���X�e���[���ጸ���ʁ@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/mdps/424555
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/03/13�@�@��t��w��w�����@�z�a�Ԉ�Ȋw����̒���h�ꎁ��̌����O���[�v�́A3��11������č��A�g�����^�ŊJ�Â��ꂽ�č��S���w��iACC�j�Ŕ��\�����Ƃ���ɂ��A���b�̗ʂ�Ⴍ�}�����H���Ö@�Ə��ʂ̃X�^�`�����^��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�X�^�`���P�Ƃ������҂�LDL�R���X�e���[���Ȃǂ����ʓI�ɒጸ�������邱�Ƃ����o�����Ƃ����B
2006/03/12�ʕ��Ɩ�͂���ς�G���C�A1��5�M�ȏ�Ŕ]������h���@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/mdps/424576
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/03/10�@�@�p���ł̑�K�͂Ȍ�����������w���u�����Z�b�g�iLancet�j�v�ɔ��\���ꂽ�Ƃ���ɂ��A���ʕ��̐ێ�ʂƔ]�����̔��Ǘ��Ƃ������f�[�^��������Ă���8�_���i�ΏۂƂȂ����l��25���l�j��I�яo���A�ێ�ʂɂ����3�O���[�v�ɕ����Ĕ]�����ɂȂ�댯�����r�������ʁA�u1�P�ʁv��0.5�J�b�v�Ƃ����Ƃ��A���ʕ��̐ێ�ʂ�3�P�ʖ���/���̐l�Ɣ�ׂ�ƁA5�P�ʈȏ�/���ł͔]�����ɂȂ�댯����26�����Ⴍ�A3�`5�P��/���ł�11���Ⴂ���Ƃ��킩��A���ʕ��̌��N���ʂ����߂Ċm�F���ꂽ�B�@���ʕ��ɑ����܂܂��J���E���ɁA��������h�����������邽�߂ƕ��͂���Ă���B
�R�R�A�ŐS�������S���A�I�����_�̒ǐՒ����@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060306ik07.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2006/03/06�@�@�I�����_�̌����`�[����1985�`95�N�ɂ�����65�`84�܂ł̃I�����_�l�j��470�l��ΏۂɌ��N�f�f�ƐH�����e�̕������ǐՒ����̌��ʂ�Ĉ�t��G���ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A�R�R�A������A�R�R�A�A�`���R���[�g�����̓������H�i��ێ悵���肷�邱�ƂŁA������������A�S���a�Ȃǂɂ�鎀�S������������\���̂��邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B
�@�R�R�A�ɂ��~����p�����łȂ��A�R�R�A�Ɋ܂܂��R�_�������Ȃǂ̗v�����l������Ƃ����B
2006/03/04�������A�|���͉����ԁH�@�����K���a�\�h�ɉ^����ā@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200602230396.html
�@�@�@----asahi.com ���N�@���N�E�����@2006/02/24�@�@�����K���a�̗\�h��Ƃ��āA�����J���Ȃ�23���A���N�Â���̂��߂̉^����̈Ă����A�L���҂̌�����Ɏ������B���i�^�������Ȃ��l�����ɂ��A���퐶���łǂꂾ���̂����Ηǂ�����̗�����j���[�Ŏ������B����A������ŋc�_���A3�����ɐV������߂�Ƃ����B�@�g�̊����Ȃ畁�ʕ��s20���A�낢����15���A�^���Ȃ瑬��15���ȂǂƋ�̗�������A���ꂼ��Ɂu1�v�Ƃ����P�ʂ����A�^���K���̂Ȃ��l�͐g�̊����̃��j���[����u3�`4��/���v�i�v23��/�T�j�A�^���K��������l�́A�^�����j���[����D�݂ɍ��킹�āu4��/�T�v����퐶���ɍ̂�����悤���߂Ă���B
�����J�ȁ@���N�� �@�^�����v�ʁE�^���w�j�̍��茟�����@���@��R��^���w�j���ψ����@���@���N�Â���̂��߂̉^���w�j�i�āj
2006/02/26�w���V�[���|�[�g�F�哤�H�i�Œ����@�閧�͊ܗL�����C�\�t���{���@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/02/20060225ddm010100102000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/02/25�@�@�S���a�ȂǏz�펾���ƐH�����̊W�𐢊E25�J���Œ��ׂĂ����ƐX�K�j�E���ɐ쏗�q��w�E���ی��N�J�����������i���s��w���_�����j�����哤�H�i�̂��炵�����Љ��C���^�r���[�L���B��������v�ɁA�����K���a�ɂ�����
�@�č��Ɣ�ׁA�J���V�E���̐ێ悪���{�͏��Ȃ��̂ɁA���e���傤�ǂ������ŋN�����ڕ��̍��܂̔������ł́A���{�͕č��̖�1/2�Ə��Ȃ��B
�@�哤�H�i�Ɋ܂܂��哤�C�\�t���{���ɂ̓J���V�E����������n���o���̂�}���邾���łȂ��A�������鍜��זE�𑝂₷����������A����̐H�����ł̑哤�C�\�t���{���̐ێ悪���邩��A���{�l�ɂ͂��̍��ܗ����Ⴂ�Ƃ����B�@�哤�C�\�t���{�����A�����z�������̕s���ŋN����X�N����Q�Ɍ��ʓI�Ȃ��Ƃ͂悭�m���Ă��邪�A����ɉ����A�C�\�t���{���̐ێ�ʂ��������قNj������S�����i�S���a�j�̎��S�����Ⴍ�A�哤�H�i���悭�H�ׂ���{�⒆���ŐS���a�̎��S�����Ⴍ�A�����⌌���̈��ʃR���X�e���[���l�������邱�Ƃ��������B
�@�C�\�t���{���́A�����z����������p�����e�̂���肵�Ăӂ������߁A�������鏗���z�������̓�����}���Ă����̂œ������\�h����B���ď����ő����j���̑O���B����̎��S�������{�ŒႢ�̂��哤�H�i�𑽂��H�ׂ邩�炾�Ƃ����B
�@�C�\�t���{���̓K�Ȑێ�ʂ́A���l�Ŗ�40�`50����/�������A�Ⴂ����ł�20�������x�������Ă��Ȃ��l�������B�T�v�������g�ŕ₤���A�H�i�ŕ₤�̂���{�B
�@���t�{�E�H�i���S�ψ���́A1�����ɓ���̐H���Ƃ͕ʂɐێ悷�����ی��p�H�i�Ƃ��Ă̑哤�C�\�t���{���̐ێ�̏����50�����Ƃ��钍�ӂ𑣂��]���� ���܂Ƃ߂����A����ɑ��ƐX����́u�[�����P�p�b�N�]���Ɏ�邾���ŏ�����Ă��܂��悤�ȕ]���͐������Ƃ͂����Ȃ��v�ƁA����ɉȊw�I�ȋc�_���K�v���Ǝw�E����B�@�ƐX����́A�u�C�\�t���{���𑽂��܂ޑ哤�H�i�̖L�x�ȓ��{�̓`���H�������E�Ɍւ�ׂ����z�I�Ȓ����H���v�Ƌ�������B
�ᎉ�b�{��ؖL�x�ȐH�����͐S���ǎ����A������A�咰���X�N�������Ȃ��A�č��̑�K�͉�������Ŕ����@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/mdps/423107
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/02/24�@�@Journal of American Medical Association�iJAMA�j��2006�N2��8�����Ɍf�ڂ��ꂽ�A�o������Ώۂɂ����č��̑�K�͉��������3�̘_���ɂ��A�ᎉ�b�̌��N�H�́A�S���ǎ����A������A�咰���X�N�������邩�ɂ��Ă͗L�ӂȌ��ʂ������Ȃ������Ƃ����B�@���̑�K�͉�������́A�팱�҂̐l��͗l�X��50�`79�̕o����48,835�l�i���ϔN��62.3�j�A���ێ�J�����[�ɐ�߂鎉�b�̊����i���b�M�ʔ䗦�j��20���ɂ��āA���ʕ��A���ނ�L�x�ɐێ悷��悤�w����������Q�ƁA�H���w�����s��Ȃ��ΏƌQ��8.1�N�ǐՂ������́B
�@���҂�́A�������獂���b�H���D�ޏ����Ȃǂ�ΏۂƂ���lj��������s���A�L�ӂȌ��ʂ�������\��������Ƃ��q�ׂĂ���A�������X�N�����炷���߂ɂ́A���C�t�X�^�C���S�ʂ����������Ƃ��܂��K�v�Ƃ̃R�����g����B
�@���e�����ɂ��Ă̘_���̌���F
�@�@�E�uLow-Fat Dietary Pattern and Risk of Cardiovascular Disease�v
�@�@�E�uLow-Fat Dietary Pattern and Risk of Colorectal Cancer�v
�@�@�E�uLow-Fat Dietary Pattern and Risk of Invasive Breast Cancer�v
2006/02/18��ƃt���[�c�������Ղ�ŁA�]�����ɂȂ��@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/422053
�@�@�@----���o�w���X �j���[�X�@2006/02/13�@�@����܂łɔ��\���ꂽ�A�H���Ɣ]�������ǂƂ̊W�ׂ�8�҂̌����_�����Č������Ă܂Ƃߒ������ʂ��A��w���u�����Z�b�g�v2006�N1��28�����ɕ��ꂽ�Ƃ���ɂ��A��ƃt���[�c���܂��܂��悭�H�ׂ�l�͂��܂�H�ׂȂ��l���A�]�������N������������11���������A�����ӂ�ɖ�ƃt���[�c��H�ׂĂ���l�́A���̊�����26�����Ⴂ�Ƃ����B��3���b�_�ێ�ł��ǂ͖h���Ȃ��A�@
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/421761
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/02/09�@�@����܂ł̉u�w�����Ń�3���b�_�𑽂��ێ悷��ƁA�����̂���ǂ�����Ƃ���������Ă���A�܂���3���b�_�̐ێ悪�A����̌`���Ƒ��B�ɉe����^����Ƃ������������̌��ʂ����钆�A�� Southern California Evidence-Based Practice Center��Catherine H. MacLean���炪�AJournal of American Medical Association�iJAMA�j��2006�N�P��25�����ɕ����Ƃ���ɂ��A������A�咰����A�x����Ȃ�10��ނ��邪��ɑ���n���I���r���[�ɂāA�c�O�Ȃ���A���X�N�ጸ�͖]�߂Ȃ��Ƃ����B�@���{�_���̌���F�uEffects of Omega-3 Fatty Acids on Cancer Risk�v
2006/02/05�I���K-3-���b�_�ɂ͂���\�h���ʂȂ��@
�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20060203hj000hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/02/03�@��Greater Los Angeles�ޖ��R�l�Lj�ÃV�X�e���i���T���[���X�j���E�}�`�����Catherine MacLean���m�炪�A�č���t��uJAMA�v1��25�����ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A���⋛���̕⏕�H�i�Ɋ܂܂��I���K-3-���b�_�́A�S���̂��߂ɂ͗L�p�ł��邪�A����̗\�h�ɂ͌��ʂ��Ȃ��Ƃ����B�哤����ς����ƃC�\�t���{���̌��������ቺ��p�͊��Ҕ�/�ĐS������iAHA�j���C�������\�@
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/421417
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/02/03�@�@Circulation���d�q�ł�2006�N�P��17���ɕ��ꂽ�Ƃ���ɂ��A�S���njn�̌��N�ێ��ɗL���Ƃ���Ă����哤����ς�����C�\�t���{���̗L�����ɁA�ĐS������iAHA�j�����̂قǁA�^�╄�������B�@�ŐV�̌������ʂ͂���AHA�h�{�ψ���́A�C�\�t���{�����܂ސH�i�܂��̓T�v�������g�ɂ��āA���ʂ������G�r�f���X�͕n��ŁA���S�����m�F����Ă��Ȃ����Ƃ���A�ێ�͐�������Ȃ��ƌ��_�����B
�@�哤����ς����ɂ��āA��ʂɐێ悷���LDL�R���X�e���[���iLDL-C�j�l��3���قǒቺ������̂́AHDL�R���X�e���[���A�g���O���Z���h�A�����Ȃǂɂ͗L�ӂȕω��͂Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�A���������댯���q�̉��P��ʂ����\�h���ʂ͊��҂ł��Ȃ��Ɣ��f���ꂽ���́B�@���{�_���̌���F�uSoy Protein, Isoflavones, and Cardiovascular Health. An American Heart Association Science Advisory for Professionals From the Nutrition Committee�v
�哤�C�\�t���{���F���߂��ɒ��ӁA�u�H���ȊO�v�ł�1��30mg���x�@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/02/20060201ddm002100069000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2006/02/01�@�@�H�i���S�ψ���V�J���H�i��咲����́A�哤�Ɋ܂܂�A�����z�������Ɏ�����p�̂��鉻�w�����u�哤�C�\�t���{���v�ɂ��āA�����J���Ȃ̓���ی��p�H�i�i���ہj�Ƃ��ē���̐H���Ƃ͕ʂɐێ悷��ꍇ�́A�P���̐ێ�ʂ�30mg/���@���x�ɗ}����ׂ����Ƃ���]�����Ă��ł܂Ƃ߂��B�܂��A�D�w�⏬���ɂ͐H�ו��ɏ�悹���Ă̐ێ�͐����ł��Ȃ��ƌ��_�t���Ă���B�@��ʂ̑哤�H�i�̈��S������ɂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���ۂƂ��ď�悹�ێ悷��ꍇ�̕]���ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�@�哤�C�\�t���{���́A������[���ȂǂɊ܂܂�A������⍜�e���傤�ǂ̗\�h���ʂ�����Ƃ��������ŁA�����ǂ�Ĕ����X�N�����߂�\�����l�����Ă���B�J�����[�����H�𑱂��Ă���l�̐S���͎Ⴂ�@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/420885
�@�@�@----���o�w���X �j���[�X�@2006/01/31�@�@�u�ĐS���w���v��1��17�����ɕ��ꂽ�Ƃ���ɂ��A�ă~�Y���[���B�́u�J�����[�𐧌������v�Ƃ����g�D�̃����o�[�́A41�`64�ŁA�����A�h�{�̃o�����X�������H�����A1400�`2000kcal�ɐ������ĐH�ׂĂ���A���̉�̃����o�[25�l�̐S���̓������A���ʂ̕č��l�Ɣ�r�������̂ŁA�J�����[�����H�N�����Ă���l�̐S���̋@�\�́A���N��̈�ʐl��蕽�ς���15�N�Ⴉ�����Ƃ����B
2006/01/29�����K���a��m�낤�@
�@�@http://www.stm-s.com/index.html
�@�@�@�@�@�T�J�m���^�c����{�����e�B�A�I�Ȑ����K���a�̉���y�[�W�@�@�����K���a�̂��낢��ȃW�������̂��Ƃ���`���m���Ē����A�����A�����A�y�������N�Ȑ����𑗂��Ē��������ł��B�Ƃ����A55�̃T�J�m���^�c���鐶���K���a��������A�֘A�T�C�g�̏Љ�����Ă���{�����e�B�A�I�ȃy�[�W�ł��B
2006/01/22��180g���H�ׂ�ƏT�P��ɔ�ׂĐS�؍[�ǃ��X�N�������@
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/419793
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/01/18�@�@����w�̈锎�N���炪 Circulation���d�q�ł�2006�N1��9���ɕ����Ƃ���ɂ��A 40�`59�̓��{�l�j��4���l����ΏۂɁA����ނ̐ێ�Ɗ��������X�N�̊W�ׁA����23g/����ېH���Ă���Q�ɔ�ׁA����180g/����ۂ��Ă���Q�ł́A�S�S�؍[�ǃ��X�N��53���Ⴍ�A��v���I���C�x���g�E���X�N��57���Ⴂ���Ƃ����炩�ɂȂ����B�@�����ł̌����ł́A�����T��1�`2��i�P��30�`60g�j�H�ׂ�ƁA�����������ƐS���ˑR���̃��X�N����������ƕ���Ă������A���{�l�̂悤�ɁA�������p�x�A��ʂɐH�ׂ�W�c��ΏۂɁA�������C�x���g�̃��X�N�Ƌ��ێ�ʂ̊W�ׂ������͂قƂ�ǂȂ������B
�@2003�N�̌��J�Ȓ����ł́A���{�l�̋���ސێ�ʂ́A40�`49�ŕ���93.2g/���A50�`59�ł�105.5g/���������B����́A����̏W�c�ł͑�2/5�Q�ɑ�������B���̌Q�ł́A���v�w�I�L�ӂȃ��X�N�����������Ȃ������B�h�g�P�ꂪ��15g�A���̐�g�P��͖�80g�A�ƂȂ�A�[�H�ȊO�ɂ����P�H�A��������H�ׂ邱�Ƃōō�5/5�ʌQ���肪�\�ɂȂ邪�A���Ɋ܂܂�鐅���_�C�I�L�V���A�����ɗp�����鉖���Ȃǂ̐ێ摝�ɂ͒��ӂ��������悳�������Ƃ����B
��Circulation��Web�T�C�g�F����́uIntake of Fish and n3 Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease Among Japanese. The Japan Public Health Center-Based (JPHC) Study Cohort I�v
�����T�W�H�A�S�؍[�ǂ̔���60�����c���J�Ȓ����@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060117ik08.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2006/01/17�@�@�A�W�A�C���V�A�T���}�A�T�o�Ȃǎ��b�̑������ɖL�x�Ɋ܂܂�Ă���d�o�`�i�G�C�R�T�y���^�G���_�j�A�c�g�`�i�h�R�T�w�L�T�G���_�j�Ƃ������b�_�́A���ǂ��l�܂�������ʂ�����B�����J���Ȍ����ǂ����A�H�c�A����A���ꌧ���ɏZ��40�`59�̒j����4���l��ΏۂɁA1990�N�����11�N�ԒǐՒ����������ʁA�����T��8�H�H�ׂ�l�́A1�H�����H�ׂȂ��l�Ɣ�ׁA�S�؍[�ǂǂ���댯�x��60���߂����Ⴂ���Ƃ��A���������Ƃ����B�A��������ς����̐ێ�ʂƌ����͋t���ւ���A�����p�Ă̍��ی����Ŗ��炩�Ɂ@
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/419727
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/01/17�@�@�p�����h����w��Paul Elliott���炪Archives of Internal Medicine��2006�N1��9�����ɕ����Ƃ���ɂ��A4�J����17�W�c�i���{4�A����-3�A�p��-2�A�č�--8�j�ɑ�����40�`59�̒j��2359�l�Ə���2321�l�A�v4680�l��ΏۂɁA�A��������ς����A����������ς����A������ς����̐ێ�ʂƌ����̊W�ׂ鉡�f�I�u�w���������{�������ʁA�A��������ς����̐ێ悪�����Ƌt���ւ��邱�Ƃ������A�A��������ς����̖L�x�ȐH���́A����������э������֘A�����̗\�h�ɗL���ł��邱�Ƃ�����Ɋm�F�����Ƃ�����B
�@����܂łɍs��ꂽ�u�w����������̌��ʂ́A����ς����̐ێ�ʂƌ������t���ւ��邱�Ƃ��������Ă����B�@�A��������ς����̐ێ�ƍ������ւ��������̂́A���@�ېێ�ʂƃ}�O�l�V�E���ێ�ʁB����������ς����ƍ������ւ��������̂́A�R���X�e���[���ێ�ʂ������B����ς����̑��ێ�ʂƌ����̊W�ɂ��āA�����ɂ͗L�ӂȊW�͌���ꂸ�A�j���ł͐g���E�̏d�Œ���������ł̂݊W�͗L�ӂ������B
�@�@�ߋ��ɍs��ꂽ�����̌��ʂƈ�v���Ȃ��������R�́A�������@��ΏۏW�c���Ⴄ���߂ƍl���Ă���B������F�uAssociation Between Protein Intake and Blood Pressure
2006/01/15�x�[�^�J���`���A�r�^�~��C��E�A������H���ł����Ղ�Ƃ�Ή�����ϐ����X�N��35����������
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/419102
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2006/01/10�@�@Journal of American Medical Association�iJAMA�j��2005�N12��27�����ɕ��ꂽ�A�I�����_Erasmus Medical Centre��Redmer van Leeuwen����̌����ɂ��A�I�����_��55�Έȏ�̒j���ŁA����Ƃ�������ϐ��iAMD�j�ł͂Ȃ������ǃ��X�N��L����5836�l��ΏۂɁA1990�`1993�N�ɐH���ێ�p�x�̒��������{���A2004�N�܂ŒǐՂ������ʁA����̐H������R�_����p�̂���4�̉h�{�f�ς�葽�߂ɐێ悷��AAMD���X�N��35���������邱�Ƃ��������B�@������ϐ��iAMD�j�́A�a�Ԑ����w�I�ȉ𖾂͐i��ł��Ȃ�������W���鑼�̕a�C�Ɠ��l�A���ǂɂ��_���X�g���X���ւ��ƍl�����Ă���A��i���ɂ����钆�r�����̍ő�̌����ƂȂ��Ă���B
�@���ɃT�v�������g�Ńx�[�^�J���`���A�r�^�~��C��E�A�����𓊗^����ƁA������AMD�̐i�s���}������邱�Ƃ��������ʂ��A������t��r�ΏƎ���AREDS�œ����Ă������A����̌����́A�ʏ�̐H���ɂ����邱���̕����̒���I�Ȑێ悪�AAMD���ǃ��X�N�ɂǂ��e�����邩�ǂ����ׂ����́B
2005/12/30�������̗\�h�ɂ͕����r�[�����т�P�{�A�T���Q�{�܂�
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/418323
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/12/20�@�@�������N�E�h�{���������N�E�h�{���������� �H���]���@���������̗R�c���m�����A�������N�E�h�{�������̋G�����u���N�E�h�{�j���[�X�@��14���v�ŕ����Ƃ���ɂ��A���A���R�[��300g�ȏ�/�T�A���{���Ɋ��Z�����13���ȏ���Ԉ���ł���l�ł́A�N������̌����㏸�̊������傫���A�V�N�ԂŖ�3 mmHg�������Ȃ��Ă��邱�Ƃ��A�j��3900�l��ΏۂƂ��������Ŗ��炩�ɂȂ����B
�@����܂ł�2�`3��/���@�i�T��14�`21���j�ȏ�̈������������ɊW����Ƃ����Ă������A�����菭�Ȃ�����ʂł������̌����㏸�x�����܂�\�����������邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B���������N�E�h�{�������@���@�u���N�E�h�{�j���[�X�@��14���v
�̂肪�₦���Ɍ����A�y�v�`�h�����ǂ��g���@�@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/416817
�@�@�@----���o�w���X �j���[�X�@2005/12/02�@�@�k�����������m��w�����������������̈ɓ��������A11��17���ɔ��q�i�����s�]�ː��j�Ɠ����������Â̍u����ɂĔ��\�����Ƃ���ɂ��A�C�ۗR���̃y�v�`�h�u�̂�y�v�`�h�v��1.2�`1.4���܂����������ނƁA�ێ��90���Ŏ��⑫��̌�����畆�����㏸����̂��m�F�����Ƃ����B�E�G�X�g�̂��тꂪ�Ȃ��Ȃ�̂��A�S���a���X�N�̑O���@�@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/414940
�@�@�@----���o�w���X �j���[�X�@2005/11/22�@�@�J�i�_�̃}�N�}�X�^�[��w�i�g�����g�j�̃T�����E���X�t�����i��ʈ�w�j���A��w���u�����Z�b�g�v2005�N11��5�����ɂĔ��\�����Ƃ���ɂ��A�@�u�E�G�X�g�^�q�b�v�v�䗦�́A�����ŕ���0.85�A�j���ŕ���0.95���������A���ϒl������ƁA�S�����njn�̕a�C�ɂȂ�Ղ��Ƃ����V�w�W����Ă���B�O�H�������q�ǂ��͕s���N�|�|�ĐS���w��Ŕ��\�@�@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/414730
�@�@�@----���o�w���X �j���[�X�@2005/11/21�@�@�ăE�C�X�R���V���B�ɂ���u�S�����nj����������v�iCardiovascukar Research and Education Foundation�j�̃J�����E�I���\�������炪600�l�ȏ�̎q�������A2005�N11��14���́u�ĐS���w��v�iAmerican Heart Association�j�Ŕ��\�����Ƃ���ɂ��A�O�H���邱�Ƃ������q�ǂ��́A��ɉƒ�ŐH�������Ă���q�ǂ��Ɣ�ׂ�ƁA�����������A�R���X�e���[���l�ɖ�肪����A�����̑�Ӌ@�\����������ȂNJT���ĕs���N�ł��邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B�L���x�c��u���b�R���[�ɔx����\�h���ʁA��������`�q�^�ɂ���ĈقȂ�@
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/411574
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/11/04�@�@��A���ɃA�u���i�Ȃ̃L���x�c��u���b�R���[���ɂ́A�C�\�`�I�V�A�l�[�g��L�x�Ɋ܂݁A���̃C�\�`�I�V�A�l�[�g�ɂ��ẮA���������Ŕx����ɑ��鉻�w�\�h���ʂ��m�F����Ă���B
�@�t�����X���ۂ����@�\�iIARC�j��Paul Brennan����́ALancet��2005�N10��29�����ɕ������ɂ��A�C�\�`�I�V�A�l�[�g�̔r�o�Ɋւ��O���^�`�I��-S-�g�����X�t�F���[�[�iGST�j�̈�`�q�^�ɂ��A�A�u���i�Ȗ�̔x����\�h���ʂ��قȂ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���{�_���̌���F�uEffect of cruciferous vegetables on lung cancer in patients stratified by genetic status: a mendelian randomisation approach�v
�L���x�c�ޖ�ɔx����\�h���ʁ@
�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20051104hj001hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/11/04�@�t�����X�̂������ۋ@��(������)��`�u�w��������Paul Brennan����́A�p��w���uLancet�v10��29�����ɁA�x����ɓ��ٓI�Ȉ�`�q�I����L���銳�҂��u�A�u���i�Ȃ̖�����Ȃ��Ƃ��T�P��ێ悷�邱�Ƃɂ���āA�����X�N���ቺ����\���̂��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�I���K-3-���b�_��L�x�Ɋ܂ސH�i���h���C�A�C��\�h�@
�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20051104hj000hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/11/04�@�ău���K���E�A���h�E�E�B�����Y�a�@�iBWH�A�{�X�g���j�\�h��w�����w����Biljana Miljanovic���m��́A��ɕK�{���b�_�̐ێ�Ɋւ���č��l�̐H�K���̕ω����������邱�Ƃ�ړI�ɁABWH�����S�ƂȂ���{���Ă���u�����̌��N�����iWomen's Health Study�j�v�̓o�^��3��7000��ȏ�̃f�[�^�͂������ʂ��A��w���uAmerican Journal of Clinical Nutrition�v10�����Ɍf�ڂ����Ƃ���ɂ��A�}�O���ȂǃI���K-3-���b�_�̖L�x�ȐH�i�̐ێ�ɂ��h���C�A�C�i�����p�������j���ǂ̃��X�N��68���ቺ���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�t�@�[�X�g�t�[�h�D���̕�e���琶�܂ꂽ�q���̓A�g�s�[���畆���ɂȂ�ɂ����@
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/405125
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/10/24�@�@10��22���ɐ����s�ŊJ�Â��ꂽ���{�A�����M�[�w��̈�ʌ����u�u�w�v�̃Z�b�V�����ŁA���������ÃZ���^�[�������Ɖu�A�����M�[�������A�����M�[�����������̏��{��������̃O���[�v�����\�����Ƃ���ɂ��A�D�P����Ǝ������ɗg������X�i�b�N�َq�A�t�@�[�X�g�t�[�h�𑽂��ێ悵����e���琶�܂ꂽ�q���́A�ێ悵�Ȃ�������e���琶�܂ꂽ�q���ɔ�׃A�g�s�[���畆���ɂȂ�p�x���Ⴂ�\���Ƃ����B
�@������ێ悵�����ƂŎq���̔畆�ɕی���ʂ�^���Ă���Ɛ�������Ă���B
2005/10/23�����u�H���ێ��v
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20051017ik08.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/10/17�@�@�H���ێ��́A�����J���Ȃ������K���a�A�h�{�s����ߏ�ێ�ɂ��a�C�\�h�̂��߁A�G�l���M�[�₳�܂��܂ȉh�{�f��ۂ��܂��Ȗڈ������������̂ŁA5�N���Ƃɉ�������Ă���B���N�x�������ꂽ�u�H���ێ��v���Q�l�ɁA��Ȗڈ����Љ��Ă���B
�ϋɓI�ɐێ悷�ׂ��h�{�f �h�{�f �ڈ��ƂȂ��
(1��������)��ȐH�i�̊ܗL��(���L���Ȃ����100g��) �H���@�� 26g ���S�{�E=5.7g���ł���1��(200g)=4g����V�C�^�P=3.5g n-3�n���b�_ 2600mg�ȏ� (EPA�ܗL��)���}�C���V=1380mg��E�i�M���ΏĂ�=860mg �J���V�E�� 650mg �����G�r10g=710mg��Ă��߂���=320mg�����=110mg �J���E�� 2000mg �o�i�i=360mg��W���K�C��=410mg���Ŏ}��=490mg ���炷�ׂ��h�{�f �H�� 10g���� �J�b�v�߂�=6.9g��~����1��=2g��t�����X�p��=1.6g ����ʂ���߂�ꂽ��ȉh�{�f �h�{�f �ڈ��ƂȂ��
(1��������)��ȐH�i�̊ܗL��(100g��) ����� �ߏ�ێ�ŋN���₷����� �t�_ 240��g ���z�E�����\�E=210 1000(��) �_�o��Q����M��畆�̔��](�ق�����) �r�^�~��A 750��gRE ���o�[=13000 3000 ���ɤ�̏�Q��َ���`(�D�P��) �r�^�~��E 8mg��-TE �A�[�����h=31.2 800 �o�����₷���Ȃ� �r�^�~��D 5��g �}�C���V�ۊ���=50 50 ���J���V�E�����Ǥ�t��Q �}�O�l�V�E�� 370mg ����ܶґf����=1100 350(��) ���� �S 7.5mg �A�T�����ϊʋl=37.8 55 �S������(�̑���Q�Ȃ�) ���� 9mg ���J�L=13.2 30 �n����P�ʃR���X�e���[���̒ቺ ���ڈ��ƂȂ�ʂͤ�������30�`49�Βj���̏ꍇ�g���O�����mg���~���E�O�������g���}�C�N���E�O�����RE���-TE�ͤ�r�^�~��A�E�̌v�ʒP�ʡ(��)�t�_�ƃ}�O�l�V�E���̏���̓T�v�������g�ȂǐH���ȊO����ێ悵���ꍇ��H������͏���Ȃ� �������J���Ȃ̃z�[���y�[�W���́u���ʁA�N��Ƃ̏ڂ�����v�F�@���{�l�̐H���ێ��ɂ���
�������l�u�����⍂�߁v��2�^���A�a�̍����X�N/ �얞�̎�N�j���ł͔��Ǘ����ő�8.3�{
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/403515
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/10/14�@�@�C�X���G���R��Ñ�������Amir Tirosh���炪�ANew England Journal of Medicine�iNEJM�j��2005�N10��6�����ɕ����Ƃ���ɂ��A�����̋������l�iFPG�j�̐������ł̍��l�́A���A�a�̓Ɨ������댯���q�ł��邱�Ƃ�������ABMI��g���O���Z���h�l�Ƒg�ݍ��킹��A�����A���A�a�ǂ���j��������ł���\�������炩�ɂȂ����Ƃ����B��NEJM��Web�T�C�g�F�uNormal Fasting Plasma Glucose Levels and Type 2 Diabetes in Young Men�v
2005/10/16�u��-GTP��⍂�߁v�͍������̉��M���A�č��̌���
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/402590
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/10/11�@�@�K���}- �O���^�~�� �g�����X�t�F���[�[�iGGT)�́A��GTP�̖��̂Ƃ��ĔF�m�x�������A�̋@�\�̎w�W�Ƃ��Ă悭�m���Ă���A�ߔN�A���b�̂ƍ������Ƃ̊W�ɂ����ڂ��W�܂�悤�ɂȂ��āA10��5���ɂ��A�S���ǎ������̓Ɨ������\�����q�Ƃ��ėL�p�ł���Ɣ��\���ꂽ����B
�@New York�B����w��Saverio Stranges����́A6�N�Ԃ̏W�c�x�[�X�̌������s���AHypertention���d�q�ł�2005�N10��3���ɕ����Ƃ���ɂ��AGGT�̐��������l�́A�����Ƃ͖��W�ɁA�����̍��������ǂƊ֘A���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���̊W�́A���ɓ������b�~�ς�����l�̏ꍇ�Ɍ������Ƃ����B��Hypertention���d�q�ŁF�uBody Fat Distribution, Liver Enzymes, and Risk of Hypertension. Evidence From the Western New York Study�v
��GTP�������ƐS���ǎ��S���X�N���㏸����A�I�[�X�g���A�̌���
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/401580
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/10/05�@�@�K���}- �O���^�~�� �g�����X�t�F���[�[�iGGT)�́A��GTP�̖��̂Ƃ��ĔF�m�x�������A�̋@�\�̎w�W�Ƃ��Ă悭�m���Ă���A�ߔN�A����GGT�l�ƁA�S�؍[�ǂ�S�����̃��X�N�̊W��������Ă���A�捠�A�]�����Ƃ̊W������Ă����B
�@�I�[�X�g���A Innsbruck��ȑ�w��Elfriede Ruttmann���炪�AGGT�ƐS���ǎ����iCVD�j�ɂ�鎀�S�Ƃ̊W���A16���l���̏W�c��Ώۂɒ��ׂāACirculation���d�q�ł� 2005�N9��26���ɕ����Ƃ���ɂ��AGGT�l�̏㏸�ɔ����S���ǎ��� ���̃��X�N���㏸���邱�ƁA��������GGT�l�͐S���ǎ������̓Ɨ������\�����q�Ƃ��ėL�p�ł��邱�Ƃ��������B��Circulation���d�q�ŁF�uGamma-Glutamyltransferase as a Risk Factor for Cardiovascular Disease Mortality. An Epidemiological Investigation in a Cohort of 163 944 Austrian Adults�v
��A�ʕ��������Ղ�H�ׂ�Δx�K����\�h�ł���@
�@�u�i�`�l�`�i�Ĉ�t���j�v�ɔ��\���ꂽ�e�L�T�X��wMD�A���_�[�\���K���Z���^�[�̌����ɂ��A1674�l�̔x�K�����҂ƁA���ʁA��ȂǓ����悤�ȏ�����1735�l�̌��N�Ȑl��ΏۂɁA��l��l�C���^�r���|���Ĕ�r���������������ʁA ��A�ʕ��������Ղ�H�ׂ�A�x�K���̗\�h�ɑ傢�ɖ��ɗ����Ƃ��������Ƃ����B
�@�����҂�́A��A�ʕ��Ɋ܂܂��z�������l�����ł���u�t�@�C�g�G�X�g���Q���v���x�K���\�h�ɖ��ɗ����Ă���ƌ��Ă���B
2005/10/02�A���G�X�g���Q���𑽂��H�ׂ�ƁA�x���X�N����������
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/399912
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/10/01�@�@Journal of American Medical Association�iJAMA�j��2005�N9��28�����ɕ��ꂽ�A�ăe�L�T�X��w��Matthew B. Schabath���炪�x���҂ƑΏƌQ�̌v��3400�l��Ώۂɍs���������ɂ��A�C�\�t���{����O�i���Ȃǂ̐A���G�X�g���Q���̐ێ�ʂ������l�́A�x����ǂ��郊�X�N���������邱�Ƃ��킩�����B��JAMA���ł̘_���F�uDietary Phytoestrogens and Lung Cancer Risk�v
�H���ƃ��C�t�X�^�C�������ł��O���B�K���͗ǂ��Ȃ�@
�@ �u��A��Ȋw�G���v�iJournal of Urology�j��2005�N9�����Ŕ��\���ꂽ���A�O���B�K���Ɛf�f���ꂽ�j�����A�����ɁA�ʕ��A��A�哤�ȂǓ��ށA�S�������A�𒆐S�Ƃ����H���ɕς��A�����āA�t�B�b�V���I�C���A�r�^�~���d�Ƃb�𑽂��ێ悷��悤�ɂ��A�X��30��/���E�T6���Ԃ̃E�I�[�L���O�A���K���x�[�X�ɂ����X�g���X�E�}�l�[�W�����g�i�X�g���b�`�A�ċz�@�A�����N�Z�|�V�����Ȃǁj��1����/���s���悤�ȁA���C�t�X�^�C���ɕς����Ƃ���A1�N�őO���B�K���̏Ǐ�������l�i�o�r�`�j�����P�����Ƃ����B��X�N�O���B����ւ̍����ʕ��ː����ÁA8���̊��҂�5�N�ԍĔ��Ȃ��A�č��̌���
�@�@http://medwave.nikkeibp.co.jp/regist/medi_auth.jsp?id=0/mdps/399912
�@�@�@�@�@MedWave�E�j���[�X�ꗗ�@2005/09/27�@�@Journal of American Medical Association�iJAMA�j��2005�N9��14�����ɕ��ꂽ�A�ăn�[�o�[�h��w��w����Anthony L. Zietman����̌����ɂ��A�����O���B����a���ɕ��ː�����萳�m�ɏW��������3D-CRT�ƁA�a���ɂ����肵���Ǝ˂��\�ȃv���g���E�r�[���𗘗p����A��X�N���҂ɑ��鍂���ʏƎ˂����S�ɍs�����Ƃ��ł��A�����ʂł����S���ɑ傫�ȕω��͂Ȃ��A�����w�I�Ĕ��� 49�����点�邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
�@�A���G�X�g���Q���ێ�ʂ̑����ɔ����x���X�N�̌����́A�i���̗L���ɂ�����炸�F�߂�ꂽ�Ƃ����B��JAMA���ł̘_���F�uComparison of Conventional-Dose vs High-Dose Conformal Radiation Therapy in Clinically Localized Adenocarcinoma of the Prostate�v
2005/09/25������40�Έȏ�̎����A����]���ǎ����A�S���a���M����
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/399029
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/09/21�@�@��Tulane��w��Jiang He���炪�ANew England Journal of Medicine�iNEJM�j��2005�N9��15�����Ŕ��\�����ɂ��A�����ɂ�����ߔN��40�Έȏ�̎����́A����]���ǎ����A�S���a����ʂ��߁A���W�r�㍑�̎����Ƃ��đ��������ǂȂǂ����̂����Ƃ����炩�ɂȂ����B
�@���̒����́AJiang He���炪�A�����ɏZ��40�Έȏ�16��9871�l�ɂ��āA1991�N�����10�N�ԒǐՂ��Ė��炩�ɂ������́B��NEJM���ł̘_���F�uMajor Causes of Death among Men and Women in China�v
�c���Ƀt�����`�t���C�𑽐H����Ɠ��K���̃��X�N���オ��@
�@���K���ɂ�����̂́A�����̈ꐶ�ɂȂ��ŗc���̐H�K���Ɛ[���֘A������Ƃ������������������A�u���ۃK���W���[�i���v�iInternationalJournal of Cancer�j�ɕ��ꂽ�A�{�X�g���̃u���K�������a�@�ƃn�[�o�[�h��w��w���̌����ɂ��A�q�ǂ��̂���A�t�����`�t���C�i�t���C�h�|�e�g�j���R�H�ׂ��q�ǂ��́A���K���ɂ����郊�X�N���傫�����Ƃ𗠕t�����Ƃ����B
2005/09/11�̓����v�F���߂���ς����A���Ԃ̂Q�O�{���E���b���~�ρ|�|������u��H�ׂ�Ƒ���v
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2005/09/20050909dde001040025000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2005/09/09�@�@�������Y�������ޑ̓����v�Ɋ֗^����u�a�l�`�k�P�v�ƌĂ�邽��ς������A�����̒~�ςɐ[����������Ă��邱�Ƃ���{��w��w���̐Y�t�ɋI��C�u�t�炪�˂��~�߂��B�@�������ʂ́A�ĉȊw�A�J�f�~�[�I�v�d�q�łɔ��\���ꂽ�B
�@���̂���ς����u�a�l�`�k�P�v�́A�c�m�`�Ɍ������A�̓����v������ɓ����悤���߂��铭��������A���b�_��R���X�e���[���̍����𑣐i���Ă���B
�@�̓��̂a�l�`�k�P�̗ʂ́A���ߌ�10���`�ߑO2�������ō��ŁA�ł����Ȃ��ߌ�3�����̖�20�{�ɒB����B��x���̐H���������Δ얞�\�h�ɂȂ���ƍl������Ƃ������́B
2005/09/04�g�����X���b���g���ȁ|�|�m�x�s�����X�g�����ɗv���@
�@�g�����X���b�Ƃ́A�A�������I�ɐ��f�����ČŌ`���������̂ŁA��\�I�Ȃ��̂̓}�[�K�����B�ȑO�͓������̃o�^�[���̖����������N�I�ȐH�i�Ƃ����Ă������A�ŋ߂̌����ŐS���a�̃��X�N�����܂邱�Ƃ��킩�茩������Ă���̒��A�j���[���[�N�s�̉q���ǂ�8��10���A�s���̃��X�g�����ɗ�����H�i�Ƀg�����X���b���g��Ȃ��悤�ɁA�ƈٗ�̗v�����s�����Ƃ����B�R�����w�F�ؗ�ɉ���@�\�h��w�̍ŐV���������ǂ��|�|���Е����Ώ�
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2005/08/20050822ddm013100143000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2005/08/22�@�u�a�C�������v�̂ł͂Ȃ��A�u�a�C�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���v�\�h��w�E�u�R����i�A���`�G�C�W���O�j��w�v�̍ŐV�������H����́A�R�����w��̐��オ�A�o�C�I�}�[�J�[�A�����x�A���ǔN��Ȃǂ��������ڍׂȎw��������V�����^�C�v�̐l�ԃh�b�N�E�u�A���`�G�C�W���O�E�h�b�N�v���S����100�J���̈�Ë@�ւŎn�܂�Ƃ����B ���a�C�ƘV���̌���
�l�̂�V�������A�a�C�������N���������̈���A�������_��������s����ȕ��q�́u�t���[���W�J���v�B���}�[�J�[��T��
�ċz�ɂ���đ̓��Ő��܂�זE��c�m�`�������邪�A�̓��ɂ͌��X�t���[���W�J�������ł�����u�R�_���y�f�v������B�ł�����Ƌ��Ɍ����Ă����B
�����₤�̂��A�r�^�~���b��d�ACoQ10���̍R�_�������B�R�����w�̊�{�́A�R�_��������ێ悵�A�K�x�ȉ^�������邱�Ƃ��Ƃ����B
�t���[���W�J���ɂ��זE�̑����́A�a�C�ɂȂ�O�┭�ǂ̂��������ɋN���A���̎��̑̂̒��̕ω����u�o�C�I�}�[�J�[�v�ƌĂԁB���̃}�[�J�[��������A�a�C�ǑO�ɖh�����Ƃ��\�ɂȂ�̂ŁA���܂��܂ȃ}�[�J�[�����E���ŒT����Ă���B����V�����Ȃǂ����
�H�i�̂��܂��܂Ȍ��\�̉𖾂��i�߂��Ă���A����\�h���ʂ�����Ƃ����Е��A�R���X�e���[����������Ƃ���钆�����A���b������Ƃ�����V�����ȂǁB����ֈ�Â̕]���ɂ�
�����̌����́A���N�H�i�⊿���A�I���A����Ö@���̑�ֈ�Â̌��ʂ��Ȋw�I�ɕ]������V�X�e���Â���ɂ��q���邱�Ƃ����҂����B�����O���J���̗Տ��������J�n
���[�J�[�{�_�C�G�b�g�̐����͂���ς����̐H�~�}���ɂ������@
�@�p���A�p�X�^�A���C�X�A�C���ނȂǁA�ł�Ղ̐H��������Ƃ������[�J�[�{�_�C�G�b�g�ŁA�̏d�����闝�R�ɂ��āA���V���g����w��w���i�V�A�g���j�̃f�[�r�b�h�E�E�G���O�����m�炪�A�u�ėՏ��h�{�w�G���v�iAmerican Journal of Clinical Nutrition�j�Ŕ��\�����Ƃ�ɂ��A���[�J�[�{�_�C�G�b�g���ɁA�ł�Ղ𑝂₷�ƕK�R�I�ɑ����邽��ς������H�~��}���āA���ʓI�ɐێ�J�����[�������āA���ʂɌ��т��̂��Ƃ����B�w�Z�ł̐��������̔��𐧌��@�Ĉ�������A�얞�ɔz���@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200508180111.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E ���N�E ���N�E�����@2005/08/18�@�@�č������w�Z����Y�_������W�����N�t�[�h����ߏo�����Ƃ����������e�n�ŋN���Ă��钆�A�����ƊE�c�́u�Ĉ�������v�i�`�a�`�j��17���A�q�ǂ��̔얞��Ƃ��āA�w�Z�Ŕ̔�������ݕ�������I�ɐ���������j�\�����B
�@����̂`�a�`�̑Ή��́A
- ���w�Z������100���W���[�X�̂ݔ̔�
- ���w�Z�����Ǝ��ԓ��́A�ȏ�̂ق��ɃX�|�[�c�h�����N��J�����[���T�����u�_�C�G�b�g�^�C�v�v�̈����̂ݔ̔�
- ���Z���̔�������ݕ��𑽗l�ɂ��A�Y�_�����͔����ȉ��ɗ}����\�\�Ƃ������́B
2005/07/31�w���V�[���|�[�g�F����߂��댯�A�ߐH��ߓK�x�ȉ^�����@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20050730ddm010100089000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2005/07/30�@�@�H�߂��ĉ^�������Ȃ��Ǝ��b���R�₳�ꂸ�ɂǂ�ǂ�~�ς��A�₪�č������ǂⓜ�A�a�ȂǂɂȂ�A�S���������Ȃǂ̃��X�N�������Ȃ�̂ŁA�̎��b�̍����l�͌��t���̒������b�l�������A�̑��ɑ�ʂ̒������b�����܂�A���b�̂ɂȂ�Ղ��B���L���X�g����w�i�����s�j�̔q�����i��t�j�́A�P�O��/�����x�̓꒵�сA�����ŕ����Ȃǂ��p�����H���邱�Ƃ��̎��b�̌����ɂȂ���Ɠ���I�ȉ^�������߂Ă���B�_�[�N�`���R���[�g�͍�������C���X������R�������P����
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/387576
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/07/22�@�@��L�fAquila��w��Davide Grassi���炪�AHypertension��2005�N�V��18 �����ɕ����Ƃ���ɂ��A�|���t�F�m�[���̈��ł���t���o�m�[����L�x�Ɋ܂ރ_�[�N�`���R���[�g�̐ێ�ɂ��A���N�Ȑl�̌����͉�����A�C���X������R�������P����A�X�ɖ{�Ԑ��������iEH�j���҂ɂ����l�̌��ʂ����邱�ƂƂ����B�@�t���{�m�C�h�́A�ʕ��A��A���A�ԃ��C���A�`���R���[�g�ɑ����܂܂��B���̃t���{�m�C�h�͊����������A���A�]�����ɂ�鎀�̃��X�N�����炷���Ƃ���������f�[�^���������A�t���{�m�C�h�̒��ł��A�J�e�L���Ȃǂ̃t���o�m�[���𑽂��܂ސH�i�ɂ́A�z��ւ̌��ʂ��\�z�����B
�@�������ʂ́A�ێ�J�����[�̑��ʂƉh�{�o�����X������Ȃ��悤�ɐH���ɑg�ݍ��߂A�J�J�I�R���̃t���o�m�[���͌��N���v�������炷���Ƃ������ꂽ���A����p����ꂽ�_�[�N�`���R���[�g�i���{�ł��A���̔�����Ă���Ritter Sport Halbbitter�j�ƁA���̃`���R���[�g��J�J�I���i�̐����͓����ł͂Ȃ��A�t���o�m�[���ܗL�ʂ����ɏ��Ȃ����i������ƒ��҂����͎w�E���Ă���B
���{�_���̌���F�uCocoa Reduces Blood Pressure and Insulin Resistance and Improves Endothelium-Dependent Vasodilation in Hypertensives�v
2005/07/16�哤�ɍ~�����ʁ@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20050714hj000hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/07/14�@�č����S�x���t�������iNHLBI�j��Jeffrey Cutler���m�炪�A��w���uAnnals of Internal Medicine�v7��5�����ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A �哤�H�i�̏�H���������̗\�h�������炷���Ƃ����炩�Ȃ����Ƃ����B�A���A�܂��\�������i�K�̌������тł��邽�߁A���������H�i�̐ێ�𐄏�����ɂ͎����Ă��Ȃ��Ƃ����B�@�哤�H�i�ɂ���Č������ቺ����@���͖��炩�ł͂Ȃ����A�哤�`�����̓��ł̌��������������A���ǂ��g�������邱�Ƃ��l������Ƃ����B
�������F�@Soy May Fight High Blood Pressure
�P����6�`7�t�̃R�[�q�[�łQ�^���A�a���X�N��2/3�ɁA���^���͂Ŗ��炩��
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/384926
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/07/08�@�@�I�����_Amsterdam���R��w��Rob M. van Dam���炪Journal of American Medical Association�iJAMA�j��2005�N6��6�����ɕ����Ƃ���ɂ��A�R�[�q�[�ێ�ƂQ�^���A�a���X�N�̊W�ׁA�P���Ƀh���b�v���R�[�q�[6�`7�t�Ń��X�N��35���������邱�Ƃ��������B�@�R�[�q�[�ɂ́A�O���R�[�X��ӂƂ̊W�����炩�ɂȂ��Ă��鐬���������܂܂�Ă���B�R�[�q�[�ێ悪�Q�^���A�a���X�N�ቺ�������炷�Ƃ����������Ă��钆�A15���̉u�w�����̌n���I���r���[�����݂����ʂł��邪�A�@�M�҂����́A�Q�^���A�a�̗\�h�ɃR�[�q�[�̓���I�Ȑێ�𐄏�����ɂ͎��@�����Ƃ����B
�c�i�ʂ́u�]�ɂ����v�|�|�ċƊE����L�����y�|���@
�@�I�����_�̃��g���q�g��w�A�}�|�X�g���q�g��w�̌����`�|�����A�Q�O�O�S�N�ɎG���u�_�o�Ȋw�v�iNeurology �j�ɔ��\�����������ʂɂ��ƁA �c�i�Ɋ܂܂��G�C�R�T�y���^�G���_�i�d�o�`�j�ƃh�R�T�w�L�T�G���_�i�c�g�`�j�̓����ŁA�L���́A�F�m�\�͂ȂǁA�]�̈�ʓI�ȓ������A�b�v�����邱�Ƃ��A�ƊE�c�̂ł���u�ăc�i����v�i�t�r�s�e�AUS Tuna Foundation �j���A�u�c�i�ʂ̏���𑝂₵�Ăق����v�ƁA�L�����y�|�����Ă���B�o�i�W�E���܂ޓV�R���ɓ��A�a���P�Ɍ��ʁA�A�T�q�����Ȃǂ��m�F
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/383612
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/07/01�@�@�A�T�q�����ƃA�T�q�r�[���A���{��ȑ�w�A������ȑ�w�ɂ�鋤�������ŁA�~�l�����̈��ł���o�i�W�E�����܂ޓV�R�������A�a�����P������ʂ������Ƃ��}�E�X���g���������Ŋm�F���ꂽ�B���̌������ʂ́A�U��30�����狞�s�ŊJ�Â�����16����{���ʌ��f�w��Ŕ��\�����B�@�Q�^���A�a���f���}�E�X�ɁA�x�m�R�̐���̒n������̐������o�i�W�E�����܂ޓV�R����3�J���Ԉ��܂����Ƃ���A�̏d�̑������}������A���b�g�D�̃C���V��������e�̐�����������ȂǁA����E�g�D�̕a�ς����P���邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��A���̓V�R�����Ԑێ悵�Ă��A�o�i�W�E��������̑���ɒ~�ς���悤�Ȍ��ۂ͌���ꂸ�A���S���ɂ����Ȃ����Ƃ��m�F���ꂽ�Ƃ����B
���A�T�q�r�[���O���[�v���v���X�����[�X�@2005/06/29
�@�@�u�o�i�W�E���ܗL�V�R���̓��A�a���P���ʂɂ�����@�\�E�`�Ԋw�I�l���v�ɂ����Β��Ɏ��ȖƉu�����̗\�h���ʁ@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20050626hj001hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/06/26�@�Β��ɂ���̗\�h��p�̂��邱�Ƃ͒m���Ă����A�V���Ȍ����œ���̎��ȖƉu������\�h������ʂ����邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B�@�ăW���[�W�A��ȑ�w�i�A�g�����^�j���w���y������Stephen Hsu�����A�č��߉����c��Â̊߉�������c��6��19�����\�����Ƃ���ɂ��A�Β����Ɖu�����������N���������Ƃ��đ̓��ŎY�������R���̔�����}������Ƃ����B
�@����̌����́A�Β��Ɋ܂܂��A���ǂ�}�����畆����ё��t�B�זE�ɑ��Č��ʂ�L���镨��EGCG�ɒ��ڂ������̂ŁAEGCG�͉��Ǘ}����p�̂ق��A���ȍR���ɑ��钲�ߍ�p���L����Ɛ�������Ă���B
2005/06/25�w���V�[���|�[�g�F �݂��`�Ō��N���i�@���A�a�ɗ\�h���ʁ^�������}�����@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20050625ddm010100125000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2005/06/25�@�@���{�̓`���H�̏ے��Ƃ�������݂��`�B�哤�y�E�n���������u�݂��v�ɂ́A�哤�Ƃ͈قȂ�w���V�[���ʂ����҂ł���Ƃ����B���̈�����F�̐F�f�u�����m�C�W���v�ɁA���������̐�����}������A���A�a�̗\�h���ʂȂǂ����҂ł���Ƃ����B�@�����m�C�W���ɂ́A����⓮���d���ȂǂɂȂ��銈���_�f�̓�����}����R�_����p������B����ɁA�l�̏����ǂɓ������Ƃ��A�����y�f�ɂ���ď�������Ȃ��Ƃ��������������Ă��邽�߂ɁA�H���@�ۂɎ�����p�����A�a�̗\�h���ʂ����҂ł���B
�o�����X��ꂽ�H���͂���/�����K���a�\�h�ɃK�C�h���\�@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200506210342.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E ���N�E ���N�E�����@2005/06/21�@�@�����J���ȂƔ_�ѐ��Y�Ȃ�21���A�����K���a�̗\�h�Ȃǂ̂��߂ɁA�����ǂꂾ���H�ׂ��炢���̂����������u�H���o�����X�K�C�h�v�\�����B�n���o�[�O��H�ׂ����́A����g���͉䖝����Ƃ��̋�̓I�ȗ��������Ƃ�1�����̐ێ�ʂ��C���X�g�ŕ\�����Ă���̂������ŁA���ނ͍T���Ė�₲�͂�𒆐S�ɂ����H�������߂Ă���B���_�ѐ��Y���@���@���\�����@2005.6.21�@���@�u�t�[�h�K�C�h�i���́j�̖��̋y�уC���X�g�̌���E���\�ɂ����v
�������J�����@���@���\�����@2005.06.21�@���@�u �t�[�h�K�C�h�i���́j�̖��̋y�уC���X�g�̌���E���\�ɂ����v
2005/06/19�t�H�[�~�����[�H�ɂ��J�����[�����ŃC���X�������E�ɐ���
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/381229
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/06/17�@�@��ʈ�ȑ�w�����w�̎c�Y�ꎁ���A6��10���A��5����{�R�����w���Ŕ��\�����Ƃ���ɂ��A�����ێ��ɕK�v�Ȃ���ς����A�����A���b�A�r�^�~���Ȃǂ̉h�{�f���܂�G�l���M�[�̃t�H�[�~�����[�H�𗘗p�����J�����[�����ɂ���āA���A�a�̖�ܓ��^�ʂ̌�����C���X�������˂���̗��E�ɐ�������Ǘ���o�������Ƃ����B���H�_���E���_�́A���H�͎q���̓��̂��߂ɗǂ�
�@�t�����_��w�h�{��������w���̃Q�C���E�����p�[�T�E�h����炪�A�ߋ��ɔ��\���ꂽ47�҂̉h�{�W�̊w�p�_�����Č������āA���H�̐���ɂ��ēZ�߁A�u�ĐH���w��G���v�iJournal of American Dietetic Association�j�Ɍf�ڂ����Ƃ���ɂ��A���H�������Ɛۂ�q�ǂ��́A�Ƃ�Ȃ��q�ǂ��Ɣ�ׂāA�u���̓����������v�u�w�Z�̏o�ȗ��������v�u�w�Z�̐��т��ǂ��v���Ƃ��킩�����Ƃ����B�X�ɁA���H��ۂ�ƁA���H�����̎q�ǂ��Ɣ�ׂ�ƁA����߂��̎q�ǂ������Ȃ����Ƃ��킩�����Ƃ����B�T���g���[�E�E�C�X�L�[���ɔA�_�����}��������
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/379744
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/06/15�@�@�T���g���[�́A�É�������w�Ɛ��}���A���i��ȑ�w�Ƃ̋��������ŁA�E�C�X�L�[���̃I�[�N�M�R�������̈�ł���G�O���_���A�_�����}�������邱�Ƃ��𖾂����Ɣ��\�B���̃G�O���_�́A�I�[�N�M�ɂ�钙���N���Ɣ�Ⴕ�ăE�C�X�L�[���ɑ����Ă����Ƃ����B���T���g���[���v���X�����[�X�i2005.06.03�j
�@�u�E�C�X�L�[���̓��A�a�����ǂ�\�h����\���̂��鐬���̒P���ɐ���
�@�@�T���g���[�E�É�������w�E���R��w�E���s�{����ȑ�w�������������{���A�a�w��Ŕ��\�v
2005/06/12����ݐ|�ɁA�����R���X�e���[���l�̉��P���ʂ��F�߂�ꂽ �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/379726
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/06/09�@�@�w���I�X�́A�u����ݐ|�v�Ɍ����R���X�e���[���l��ቺ��������ʂ����邱�Ƃ��m�F�����Ɣ��\�����B���̌����́A���{��ȑ�w��Ö�w�Ȃ̓n�ӑחY�����i�E���Êw�j�Ƃ̋��͂ōs���A2005�N8��6�A7���̑�7�p�V���|�W�E���ɂĔ��\�����\��B�@�����̃R���X�e���[���l�����߁i210mg/dL�ȏ�j�̒����N�̒j��12�l��ΏۂɂT�T�ԁA�P��60mL�����p�������ʁA�������̑��R���X�e���[���l���ቺ���A����l�ɋ߂��Ȃ�A�X�ɁA�ێ�I����T�T�Ԃ��o�ߌ���A���R���X�e���[���l���A����l�ɋ߂���Ԃ�ۂ��A���ALDL�R���X�e���[���̌������m�F����Ă���B
�@���w���I�X���j���[�X�����[�X�@2005�N6��6��
�@�@�@ �u�����А|�v�ɂ��R���X�e���[���l���P���ʂɂ������N�j����64�����J�����[�ߑ������o�A�R�J���ȏ�^���[����62���A�ԉ��̒����Ŕ��� �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/378446
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/06/02�@�@�ԉ������{����������2004�N11�`12���A��s���ݏZ��30�`50�Α�����j���T�����[�}����Ώۂɍs���A�A������V���Ԃ̓���s������ӎ��ɂ��āA323�l����L�������́B�@���̌��ʁA�S�̂�60�����H������^���K������l���āA�u����₷�������v�����o�B���o������l��43���́A�ŋ�5�N�Ԃɑ̏d���������Ă���B
�@�H�����ɂ��ẮA�S�̂�64�����A�J�����[�I�[�o�[��F�����A���ɑ���Ղ����������o���Ă���l�ł́A79�����J�����[�I�[�o�[���ƍl���Ă��邪�A�K���J�����[�ʂ�m��̂͑S�̂�10���ɉ߂��Ȃ��B
�@���̑��A�u���H���v�����o����l��72���A�u�H�����s�K���v��54���A�u�Q�钼�O�ɐH�ׂ�v��59���ɒB���Ă���B�@�^���ɂ��ẮA62���͒��߂R�J���ɑS���^�������Ă��Ȃ��B�^���s�������o���Ă���l�͑S�̂�69���ɒB����B�x�������Z���J�������ɁA�S�̂�57�����u�Ƃł��낲��v���Ă���B
�@���ԉ����v���X�����[�X�i2005.5.30�j
�@�@�@�w����T�����[�}���̑���₷�������s���x�����R���X�e���[����������ɂ͂����Ɩ��H�ׂȂ����@�@
�@�R���X�e���[���l�������ƁA�S�����njn�̕a�C�ɂȂ�Ղ��Ȃ邪�A��ȂǐA�����̐H���𑽂��܂H������ŃR���X�e���[���l��������Ƃ����f�[�^���u�ē��Ȋw�G���iAnnals of Internal Medicine �j�v5��3�����ɕ��ꂽ�B�u���[�x���[�̌��p�܂���|�|�S���a�\�h�ɂ��@�@
�@�ă~�V�V�b�s�B�I�N�X�t�H�[�h�ɂ���Ĕ_���Ȃ̉��w�ҁE�A�O�l�X�E���}���h���m���A���\�����Ƃ���ɂ��A�u���[�x���[�ɂ́A�R�_�������������܂܂�Ă���A�K���\�h��A���A�a�̍����ǂł��铜�A�a���Ԗ��ǂ̏Ǐ�ɘa�ɗL���ł��邱�Ƃ��m���Ă��邪�A�X�Ɉ��ʃR���X�e���[�������炵�ĐS���a��\�h������ʂ��A���b�g���g���������Ŋm�F�����Ƃ����B�����ۂ������Ɠ����d�����i�ށ@�@
�@�R�����r�A��w���O�q���w���̃��C�X�E�h�X�o�������m�炪�A�G���wCirculation�x �ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A���̒��ɍۂ������l�́A�����d���ɂȂ�Ղ��A�S���a��]�����ɂ����郊�X�N�������Ƃ����B
�@���ׂ�11��̍ۂ̂����A�����a�̌����ƂȂ�S��̃o�N�e���A�̑���l�����������l�قǁA���̔���̒��x�����������B
2005/05/21�ᎉ�b�H�ɑ哤�A�H���@�ہA�j���j�N�Ȃǂ̒lj��ێ�ł���Ɍ��ʁ|�|�č�����
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/375743
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/05/20�@�@��Stanford ��w��Christopher D. Gardner���炪�AAnnals of Internal Medicine��2005�N5��3�����ɕ����Ƃ���ɂ��A�ᎉ�b�H�ɁA��Ɖʕ��A���ށA�S�����ނ�������ƁA���R���X�e���[�������LDL�R���X�e���[���ቺ���ʂ����܂邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ����B
�@�h�{���x�̍����A�����̐H���A���ɑ哤�A�H���@�ہA�j���j�N�A�A���X�e���[���Ȃǂ𑽂��ۂ邱�Ƃ�����ɍv�������ƍl����Ă���B���_���̌���́uThe Effect of a Plant-Based Diet on Plasma Lipids in Hypercholesterolemic Adults�v
2005/05/15�咰����F ���Nj}���A�u���Č^�H��������v�ɋ^��@�u�a�H�v�ł����Ȃ��|�|���J�Ȓ����@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20050513ddm001100121000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2005/05/13�@�@90�N������A�H�c�A����A�����4���ɏZ��40�`59�̒j���v�S2,112�l�̃A���P�[�g�����Ɩ�10�N�Ԃ̒ǐՒ����ɂ������J���Ȍ����ǁi�S�������ҁ������E����������Z���^�[�Տ��u�w�������O���������j�ɂ���K�͒������ʂ��A���ۑ���A���̂����厏��12���A�f�ڂ��ꂽ�Ƃ���ɂ��A���⎉�b�𑽂��H�ׂ�u���Č^�v�̐H���ł��A�j���̏ꍇ�͑咰����̔��ǂ͓��ɑ����Ȃ��Ƃ����B
�@�����ł́A�u���Č^�v�≖�Ђ��H�i�𑽂��H�ׂ�u�`���^�v�̐H���ő咰����̈��̌����������Ă������A�咰����S�̂ł͖��m�Ȋ֘A�݂͂��Ȃ������B���{�ł��咰����̋}���́u�H���̉��ĉ�������v�ƌ����Ă������A����ɋ^��𓊂������錋�ʂƂȂ����B�@�j���ō����o�Ȃ������̂́A�H����������i���̉e�����傫���\��������Ƃ����B
��悭�H�ׂĂ��咰���u�卷�Ȃ��v�@���J�Ȍ����ǁ@
�@�@http://www.asahi.com/health/news/TKY200505090346.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E ���N�E ���N�E�����@2005/05/10�@�@���ʕ��ɂ͍זE�̂���h���R�_��������A�֒ʂ��悭����H���@�ۂ������܂܂�A��R�H�ׂ�Α咰����\�h�Ɍ��ʂ�����Ƃ���Ă������A��E�ʕ����悭�Ƃ��Ă��A�咰����ɂȂ郊�X�N�͑卷���Ȃ��Ƃ�����K�͂ȉu�w�������ʂ��A�����J���Ȍ����ǂ��o���B���������H�ׂĂ��@�咰����\�h�ɂȂ炸�@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050510so11.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/05/10�@�@�����J���Ȍ����ǂ̒ؖ�g�F�E���k�勳���i�u�w�j��ɂ��j����9���l�̖�10�N�Ԃ̒ǐՒ������A9���t�̉p���̂����厏�ɔ��\���ꂽ�Ƃ���ɂ��A���ʕ����R�H�ׂĂ��咰����̗\�h�ɂ͂Ȃ���Ȃ��Ƃ����B�@�����́A9���l����ʕ��̐ێ�ʕʂɂ��ꂼ��S�O���[�v�ɕ����A�咰����̔��������r�������ʁA��ł��ʕ��ł��A�ł��悭�H�ׂ�O���[�v�ƍł����Ȃ��O���[�v�Ƃ̊ԂŁA�咰����̔������ɍ��͂Ȃ��A��������ƒ�������ɕ����Ē��ׂĂ����͂Ȃ������Ƃ������́B
2005/04/24���m�X�^�C���̐H������A���R�[�������b�̉��̌����H
�@�@�O�a���b�_�������H���ŁA�}�E�X��NASH���@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/371662
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/04/22�@�@���B�̑��w��i4��13�`17���j�ŁA�x���M�[�̃��[�o���J�g���b�N��w�̌����҂炪���\�����Ƃ���ɂ��A�A���R�[�������܂Ȃ��A�܂��͏��ʂ������܂Ȃ��l�̎��b�̂ł��A�A���R�[�����̏�Q�Ɏ����̑��̉��ǂ��N����ꍇ�����邱�Ƃ��������Ƃ����B��A���R�[�������b�̉��iNASH�j�̌������A���������b�ɑ����܂܂��O�a���b�_�Ȃǂ𑽂��܂ށg�E�G�X�^���H�i���m�X�^�C���̐H���j�h�ɂ��邱�Ƃ���������}�E�X�����̌��ʂ\�����B�w���V�[���|�[�g�F �C�������ň݂��@�s�����ۂ����炷�t�R�C�_��
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20050421ddm010100042000c.html
�@�@�@�@�@�����V���E ��炵 �E ���N�@2005/04/21�@�@�u�݂��d���v�u�݂��ɂ��v�u�H�~���킩�Ȃ��v�ȂLj݂̕s��D�i�ɊC���̐����̈�́u�t�R�C�_���v�����ʓI�Ȃ��Ƃ��������Ă����B�݂���̌����ɂ��Ȃ���w���R�o�N�^�[�E�s�����i�s�����ہj�����炷��p�����ڂ���Ă���B��������҂ɂ����ʁ|�|�u�@�\���ݒ��ǁv�A���P�ᑽ��
�@�C���ނɂ́A�ʂ���Ƃ����������܂܂�Ă��邪�A���̃l�o�l�o�����̈�������ނ̃t�R�C�_���B���ł��I�L�i�����Y�N�ɂ́A�t�R�C�_�����L�x�B
�@�ݒ���i�g�Q�u���b�J�[�Ȃǁj�����ނƕ���p�̐S�z������l�ɂ��t�R�C�_���͍œK�B�@��������݂̒��q��������ƈ����Ƃ����l�́A�t�R�C�_�������p�����Ď����Ă݂�̂���̑I�����B�@�̐S�Ȃ̂͏Ǐ��P���邩�ǂ����ł��B����p�̐S�z���Ȃ��̂ŁA�C�y�Ɉ��߂�B�R���X�e���[���l�������l�͋L���́A�W���͂������@
�@�G���u�S�g��w�v �iPsychosomatic Medicine�j�ɕ��ꂽ�{�X�g����w�ł̌������ʂɂ��A�Ƃ������҈�������Ղ��R���X�e���[�������A���t���̃R���X�e���[���l�������l�i200mg/dl�ȏ�j�́A���Ⴂ�l�Ɣ�ׂ�ƁA�L���́A�W���́A �����̒��ۉ��A�g�D�I�Ɍn�����Ăčl����͂Ȃǂ̖ʂŁA�D��Ă��邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B
2005/04/17���茺�Ă̌����R���X�e���[���ቺ��p�̓X�e���C�h�ނȂǂ̔r����������/�����_�H��ƃt�@���P������
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/368895
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/04/08�@�@3�� 30���ɎD�y�ŊJ�Â��ꂽ���{�_�|���w��ŕ��ꂽ�A�����_�H��w�����̖���O����ƃt�@���P���Ƃ̋��������ɂ��A ���茺�Ă��_�`�_�̐����𑣐i���邱�ƂȂǂɂ���ăR���X�e���[���̔r���𑣂��A���ꂪ�����R���X�e���[���l�̉��P���������Ă���Ƃ����B���t�@���P�����j���[�X�����[�X�i2005/04/06�j���@�������\�u���茺�ẴR���X�e���[���ጸ�̍�p�@�\�v�ɂ��āiPDF)
2005/03/26�������̐��ŐS���a���X�N���\���ł���@
�@3��14���ɔ��\���ꂽ�u�ē��Ȋw�I�v�v�iArchives of Internal Medicine �j�ɂ��A�ă~�l�\�^�B�̃o�|�}���Տ������Z���^�[�̃J�����E�}�[�S���X���m���6��6000�l�ȏ�̏�����Ώۂɂ��������ɂ����āA���t���̔������̐��������ƁA�S���a��]�����ȂǁA�S�����njn�̕a�C�ɂȂ�Ղ��Ƃ������X�N�f�f���o����Ƃ����B�@�̂��a���ۂȂǂ̊O�G�Ɛ키�K�v��������ƁA��������������B���̍ۉ��ǂ��N�����A���̉��ǂɂ�茌�Ǖǂ�����������A���͌��ǂ��l�܂��āA�S���a��]�����̌����ɂȂ邱�Ƃ��A�S���a��]�����́A�̓��ŋN���Ă��鉊�ǂƊW���[���Ɖ]���Ă���A���̌����͂���𗠂Â��Ă���悤���B
�E�G�X�g�T�C�Y�����A�a�̖ڈ��@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050322so12.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/03/22�@�@�ėՏ��h�{�w��̍ŐV���Ɍf�ڂ��ꂽ�ăW�����Y�z�v�L���X��̖�3���l�ɑ���u�w�����ɂ��A�č����l�j���̃E�G�X�g�̃T�C�Y�����A�a�̊댯�x�̗L���Ȏw�W�ɂȂ邱�Ƃ��A�얞�x�̎w�W�Ƃ��Ă悭�g����a�l�h�l�����A�D�ꂽ�ڈ��ɂȂ邱�Ƃ��������Ƃ����B�@�E�G�X�g�ɂ�铜�A�a�̊댯�x�\�����L���Ȃ̂́A�����̎��b���A2�^���A�a�̔��ǂɋ����W���Ă��邽�߁B
�y���{�z��w��2005����z1��5�t�̗Β��Ō��ǒe�͐������P�@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/365712
�@�@�@�@�@���omedwave�E�T�v�����@�\���H�i�g�s�b�N�X�@2005/03/20�@�@����z��a�@�z����Ȃ̑���B���������{�z��w��2005�N3��19���̃|�X�^�[�Z�b�V�����ŕ����Ƃ���ɂ��A5�t/���A�܂���800ml�ȏ�/���̗Β���ێ悷�邱�ƂŁA�����ɊW����Ƃ���閬�g�`�d���x�iPWV�F Pulse Wave Velocity�j���L�ӂɉ�����A���ǂ̒e�͂�����FMD�iFlow Mediated Dilation�F�����̑����Ɉˑ��������NJg���j���L�ӂɌ��シ��Ƃ����B�@����̓��{�l�͍������ⓜ�A�a�A�����R���X�e���[���̑����Ƃ������S���ǃC�x���g���N���Ղ���Ԃł���ɂ��W�炸�A���Ăɔ�ׂĐS���a�Ȃǂ̐S���ǃC�x���g�̔��������Ⴂ�̂́A���{�Ɠ��́u�Β��v�����ǂɗǂ��e����^���Ă���Ƃ������������������̂Ƃ�����B
�s���̐l��6���́A�����K���a�����I�@
�@�v���đ�w��w�����_�_�o�Ȋw�����̓���������������̃O���[�v���A���N�T�����[�}���j��6084�l��Ώۂɍs�����A���P�[�g�����ŁA�s���Ɛ����K���a�̔Y�݂̊W����������ɂȂ����B�@�s���ɔY�o���̂���l�̂����A�����K���a�̗L�a�҂͖�60���B�s���Ɛ����K���a���W���Ă��邱�Ƃ��������킹�钲�����ʂƂȂ�A�X�ɁA�s���̔Y�݂�����������K���a���҂́A���a�ɂȂ�₷���X�����F�߂�ꂽ�B
���Ō���������������@
�@�u����ɂ͕�����v�Ƃ����������������ʂ��A�ĐS���w�� �iAmerican College of Cardiology�j�̉�ŕ��ꂽ�B
�@20�l�̐��l��ΏۂƂ��A�R���f�B�̏����Ăԕ����������W�߂��r�f�I�Ɛ푈�̐퓬�������������̑O��Ō��ǂ��ǂ��ω����������r�����Ƃ���A�R���f�B��������ł́A����������22���A�b�v�A�푈�f���������ł́A���������� 35���������Ă����B�P�ʃR���X�e���[���𑝂₷��œ����d�������P�@
�u�ē��Ȋw�G���v�iAnnals of Internal Medicie�j2005�N1��18�����ɍ������ǂɑ��铮���d�����P�̗Տ����ʂ����\���ꂽ�B
�@�u�W�F���t�B�u���W���v�igemfibrozil �j�A�u�i�C�A�V���v�A�u�R���X�`���~���v�̂R��̕������������킹���A�P�ʃR���X�e���[���ƌĂ��u�g�c�k�v�������グ���܂��J������A�����d���̉��P�ɐ��ʂ��グ�Ă���Ƃ������́B
�@���̎����ɎQ�������S�Ă̂��N��肪�A2.5�N�̊Ԃɑ̏d�𗎂Ƃ����Ƃ����B
2005/02/26�ꂪ�얞�@�q������₷���@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050221so16.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/02/21�@�@�ăy���V���x�j�A��Ȃǂ̃`�[�����܂Ƃ߁A�č��̗Տ��h�{�w�G���ɔ��\�����������ʂɂ��@�u�얞�C���̕�e�̎q�ǂ��́A�U���瑾��n�߂�\���������v�Ƃ����B�@2�ł͑̊i���͂Ȃ��������A4�ɂȂ�Ɣ얞�C���̕�e�̎q�ǂ��̕����A���̏d��������X���������A6�Ύ��̔�r�ł́A�얞�C���̕�e�̎q�ǂ��̕��ϑ̏d�́A�אg�̕�e�̎q�ǂ��̕��ϑ̏d��3Kg����A��23Kg�ƂȂ�A���b�ʂł����߂č������A�얞�x�ɖ��m�ȍ����o���Ƃ����B
���܂̐[���͔얞�̂��ƁH�@�č���������������
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200502200062.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2005/02/20�@�č����A���R�[���ˑ����������A97�`01�N�̍������N�ʐڒ����ɎQ�������j���̂����A�������ޖ�3��7��l�́u�P��̎�ʁv�Ɓu�����̕p�x�v�ׁA�u���݂��Ղ�v�Ɣ얞�Ƃ̊W��T�����������ʂ��A�č����ی��������i�m�h�g�j�����\�����Ƃ���ɂ��A���܂ɂ������܂Ȃ����Ő[������l�͑���₷���A���ʂ̔ӎނ��K���ɂ�����ݕ����Ƒ���ɂ����Ƃ����B�a�l�h�i�̏d��g���̓��Ŋ��������l�j�Ƃ̊W���݂�ƁA
- �P��ɂP�t�������܂Ȃ��j���@�F�@�a�l�h�̕��ς�26.5�B
- �P��ɂS�t�ȏ���ޒj�� �@�@�F �a�l�h�̕��ς�27.5�B
- �����̏ꍇ�@�F�@25.1�i�P�t/��j�@���@25.9�i�S�t�ȏ�/��j
- ����A�N�Ԃ̈�����������Ȃ��l�قǂa�l�h�̐��l���傫�������B
- ����ł������̂́A�P�t/�����܂��A�T��3�`7�����ސl�B
- ���܂̂����ŗʂ��߂����l���A�ł�����Ղ��B
�R���X�e���[���@��⍂�߂��������H�@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050220so12.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/02/20�@�@�R���X�e���[���������ƐS�؍[�ǂɂȂ�₷���Ƃ���A���l���C�ɂ��邪�A��⍂�߂̕����]�����Ȃǂ����Ȃ��A�������Ē������ł��邱�Ƃ������f�[�^���������ł���B�@���݂̊�l�́A�č��ł̒����ɂ����ăR���X�e���[���l220�ȏ�̏ꍇ�ɐS�؍[�ǂ����������A�Ƃ̌��ʂ���ɂȂ��Ă���B�����A�����30�`40�Α�̒j���̃f�[�^�ŁA������50�Έȏ�̒j���ł́A�S�؍[�ǂ�������̂͐��l��280���x�ȏ�̏ꍇ�������B
�@���C���w���̑���i���������j�z�ꋳ���́A�S���̌��f��f�Җ�70���l�̃f�[�^����A���N�I�ȏW�c��95���̐l�����܂�͈͂̏���l���Z�o���A��������R���X�e���[���̊�l�Ƃ���ƁA�u�����N�̏ꍇ�A�j����260��A�����ł�280��Ƃ��邱�Ƃ��Ó��v���Ƃ����B �@�č��́A�����̕��σR���X�e���[���l�̒ቺ�ɂ���ĐS�؍[�ǂ������Ă���B���{�͋t�ɐ��l���㏸�X���ɂ���A��l��ɂ���K�v�͂Ȃ��Ƃ����B
�@���R���X�e���[���ɓ��ɒ��ӂ��K�v�Ȃ̂�30�`40�Α�̒j���ŁA�S�؍[�ǂ̗v���Ƃ���钆�����b�������l��A�P�ʃR���X�e���[���Ƃ��Ă��g�c�k�R���X�e���[�����Ⴂ�l�������B���A�a�A�������ȂǗl�X�ȗv�f�𑍍����f���Ď��Â���K�v������Ƃ����B
2005/02/20�u�������ށv�R�[�q�[�A�̂����@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050217so12.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/02/17�@�@�����J���Ȍ����ǁi�ǒ����Ë�����Y�E��������Z���^�[�\�h���������j�����{������K�͒����̌��ʂ��A16���t�̕Ă����厏�Ɍf�ڂ��ꂽ�Ƃ���ɂ��ƁA1990�`2000�N�̖�10�N�ԁA�S��9������40�`69�̒j����9���l��ǐՒ����������ʁA�R�[�q�[�ێ�ʂƊ̂������̊֘A���킩�����Ƃ����B
�@�R�[�q�[�����ސl�́A�قƂ�Lj��܂Ȃ��l�ɔ�̂���ɂȂ闦��51�������Ȃ��A�u5�t/���ȏ���ށv�l�ł́u���܂Ȃ��l�v��1/4�B�������J�t�F�C���������܂܂��Β��𑽗ʂɈ���ł���l�ł́A�̂������̒ቺ�͂قƂ�ǔF�߂�Ȃ����A�ǂ̐��������ʂ��y�ڂ��Ă��邩�͔����Ă��Ȃ��B�R�[�q�[�Ǝ��̐����̉\���������Ƃ����B�̂��X�N�A�R�[�q�[�Ŕ����@��������Z���^�[
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200502160331.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2005/02/16�@�č��̂����厏�i�m�b�h�@16�����Ɍf�ڂ��ꂽ�A���{�̍�������Z���^�[�̌����`�[���ɂ��9���l����j����10�N�Ԃɂ킽���K�͒ǐՒ����̌��ʂɂ��A�R�[�q�[�����ޗʂ������قǔx����̃��X�N�ጸ�̌��ʂ�����Ƃ����B�@�R�[�q�[���̍זE�����\�h����ڂ����d�g�݂͕s�������A�R�_����p�̂��鐬�����R�[�q�[�ɑ�ʂɊ܂܂�Ă��邩��ł͂Ȃ����ƌ�����B�@�����A�����Ɍf�ڂ��ꂽ�č��`�[���ɂ��ʂ̌����ł́A�R�[�q�[��g���ő咰����Ⓖ�������\�h������ʂ͊m�F����Ȃ������Ƃ����B
�C���ނɓ�����̗\�h���ʁ@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20050210hj001hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/02/10�@�h�{�w�֘A���uNutrition�v2��2�����f�ڂ̃J���t�H���j�A��w�o�[�N���[�Z���O�q���w���̓ŕ��w��Christine Skibola���̌����́A���{�l�����͕č��l��������������̃��X�N���Ⴍ�A���퐶���ŊC���ނ̐ېH�ʂ��͂邩�ɑ������Ƃɒ��ڂ��A���J���Ȃǂ̊C���ނ̐ێ�ɂ��A������Ȃǂ̃G�X�g���Q���ˑ�������̔����Ɋ֗^���錌���G�X�g���Q�����ቺ���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ������̂ŁA�q�{�����ǂȂǂ̎����ɂ���Č��o�����ɋɓx�̕s�K�������݂鏗������3���ΏۂɊC���̕⏕�H�i��A���ێ悳�����Ƃ���A���o�������������K���I�ɂȂ�A���̂ق��A�G�X�g���W�I�[���i�G�X�g���Q���̈��j�̌����Z�x���ቺ�����Ƃ����B50�N�ɓn��ǐՒ����A�j���̋i����11�^�C�v�̊��ɂ�鎀�S�̊W������
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/358464
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/02/16�@�@�p��Radcliffe�����f�Ï���Richard Doll���炪�A�p���l�̒j����t��50�N�ԒǐՂ���11�^�C�v�̊��ɂ�鎀�S�Ƌi���̊W�ɂ��āABritish Journal of Cancer���d�q�łɂP��25���ɕ����B
�@���̕ɂ��A25�{/���ȏ�z���w�r�|�i���҂̎��Ґ��́A10���l������415.2�l�ŁA���i���ҁi��16.9�l�j�� 25�{�B�x�������̊��Ɠ��l�A�i���{���̑����ɔ����ă��X�N���㏸�B15�{/�������̃��C�g�i���ҁi10���l������130.6�l�j�ɔ�ׁA�w�r�[�i���҂̎��S����3�{�B�@��British Journal of Cance������F�uMortality from cancer in relation to smoking: 50 years observations on British doctors�v
2005/02/12�ᎉ�b�������ނƑ̎��b������A�E�G�X�g�ɃN�r���I�|�|���{�l�����Ŋm�F
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/358012
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/02/07�@�@�Ҋw���h�{���w�Z�����������̍L�c�F�q�������A2��3���ɊJ�Â��ꂽ�u��V�f�B�A�~���N�Z�~�i�[�v�i��ÁF���{���_���Ƌ���j�Ŕ��\�����Ƃ���ɂ��A�ᎉ�b���������ނƑ̎��b������A�ؓ��ʂ�������Ƃ����_�C�G�b�g���ʂ�����Ƃ����B�@�ᎉ�b�������ނ��Ƃɂ��A�J���V�E���̌����Z�x������āA���b��B�z�������Ȃǂ̓����Ŏ��b�זE���̃J���V�E���Z�x��������A����ɂ���Ď��b�̍������}������A�����͑��i����邽�߂ƍl������B
���P��1�`2�Ȃ�]������S���a�ւ̉e���Ȃ��A���������A�a�̕��͍T���߂Ɂ@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/358032
�@�@�@�@�@���omedwave�E�T�v�����@�\���H�i�g�s�b�N�X�@2005//02/07�@�@���i�{���j�Ɋ܂܂��R���X�e���[���́A100g�������400mg �ƐH�i�̒��ł����ɑ����A��1��300g�̃q���X�e�[�L�Ƃقړ����ܗL�ʂɂ��Ȃ�̂ŁA�����K���a�̖ʂ���H�ׂ�̂��T�����ق����ǂ����AUniversity of Medicine and Dentistry of New Jersey��Adnan I. Qureshi���炪�A�č��l1���l��16�N�ԒǐՂ�����������ɂ�����������A���N�Ȑl�Ȃ�1�`2��/���̗���H�ׂĂ�����������]�[�ǂ̔��ǂ͑����Ȃ����Ƃ����������Ƃ����B�@�A���A���A�a�ǂ��Ă���l�́A�S�؍[�ǂ̑����X�N�������̂ŁA�T�����ق����ǂ��Ƃ����B
�̂ɂ悭�Ȃ��n���o�[�K�[�A���q���x���ŗ��R�𖾁@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20050204hj000hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/02/04�@��w�֘A���uCell�v�@1��28�����Ɍf�ڂ��ꂽ�ăn�[�o�[�h��w�_�i�E�t�@�[�o�[���������̌����ɂ��A�n���o�[�K�[��g�������̂ɂ悭�Ȃ����R�����q�I�ɉ𖾂��ꂽ�Ƃ����B
�@�O�a���b�_����уg�����X���b�_�Ƃ������������b���ǂ̌����ƂȂ�LDL�i���ʁj�R���X�e���[���ɕϊ����镪�q�X�C�b�`���������ꂽ�Ƃ������̂ŁA���̕��q�́A�R�A�N�`�x�[�^�ɕ��ނ����PGC-1���i�x�[�^�j�ŁA�̑�ӂɊ֗^����B
�@���A�����i�ȂǂɊ܂܂�̂Ɉ����Ƃ��鈫�����b���̑��ɒB����ƁAPGC-1���������w�V�O�i���̃J�X�P�[�h���J�n�����A����ɂ���Ċ̍זE�����̕Ǖ����t�@�~���[�̃g���O���Z���h�i�������b�j�Ɠ��l�ɓ�����ǂ�����LDL�R���X�e���[�����Y�����邽�߁B
2005/01/30�t�_����������\�h�|�|15���l�̏����ׂĔ���@
�@�n�[�o�[�h��w�ƃu���K�������a�@�̌����҂炪�A15���l�̏�����27�`43�A44�`70��2�O���[�v�ɕ����A1990�N���8�N�ԁA�����̗t�_�̐ێ�ʂƍ������̊W���������ʂ��A�u�i�`�l�`�i�Ĉ�t��G���j�v�ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A�����t�_��ϋɓI�ɑ����ێ悵�������́A�ێ�ʂ����Ȃ������Ɣ�ׂāA�������ɂȂ����������͂�����Ə����������B
�@�N�z�̏����ł��A�t�_�𑽂��ێ悵���l�́A�ێ�ʂ����Ȃ������l���A�������ɂȂ����������������A�������\�h���ʂ��F�߂�ꂽ�B�A���A�Ⴂ�����قǂ͂�����Ƃ������͏o�Ȃ������B�t�@�X�g�t�[�h�Ɣ얞�A�[���W�@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050124so14.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/01/24�@�@�p��w�������Z�b�g�Ɍf�ڂ��ꂽ�ă~�l�\�^��Ȃǂ̌����ɂ��A1985,85�N��18�`30�������j����3000�l��Ώۂɂ���15�N�Ԃ̒����ɂ��A�č��l�ł͉^���s������������A�n���o�[�K�[�A�s�U�A�t���C�h�`�L���Ȃǂ̃t�@�X�g�t�[�h��p�ɂɐH�ׂ邱�Ƃ��A�č��l�̔얞�ⓜ�A�a�Ɩ��ڂȊW������Ǝw�E���Ă���B
2005/01/22�g�����X���b�_�ƖO�a���b�_�̐ێ挸�|�|�Ă̐V�H���K�C�h���C���@
�@�ĘA�M���{���A�T�N�Ԃ�ɉ��肵���u�H���K�C�h���C���v�ł́A�J�����[�����̂ق��A�g�����X���b�_��O�a���b�_�̐ێ���T����悤�������Ă���B
- �ێ�J�����[�F���l������2000Kcal/���A�j����2400�`2600Kcal/�����]�܂����B
- �h�{������������܂܂�Ă���H�i���A����ސH�ׂ邱�ƁF�A���A�O�a���b�_�A�g�����X���b�_�A�R���X�e���[���A�Y�����ꂽ�������≖���̏��Ȃ����̂�I�Ԃ��ƁB
- �t���[�c�Ɩ��L�x�ɐH�ׂ�F�t���[�c�͏o�������ۂ��ƐH�ׂđ@�ێ���ێ悷��B�t���[�c�Ɩ��4�`5�J�b�v/���A���b�[���Ȃ����ᎉ�b�̃~���N�܂��͓����i�����킹��3�J�b�v/���B
- �Y�������F�S�������̃p���A�I�[�g�~�[���A���ĂȂǁA�S�������̌`�Őێ悷�邱�ƁB
- ���b�F�g�����X���b�_�����炷���ƁB�O�a���b�_�́A���ێ�J�����[��1/10�ɗ}����B�R���X�e���[���̐ێ�́A300mg/���ȉ��B
���ʕ��ɓ�����̗\�h���ʔF�߂��@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20050121hj000hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2005/01/21�@�č���t��uJAMA�v1��12�����f�ڂ��ꂽ�I�����_�̌����ɂ��A�����̖��ʕ��ɂ͑��ʂ̑@�ہA�R�_���r�^�~����~�l�����A�����\�h���鉻�������܂܂�A�ߋ��̑����̌����͓����X�N�̒ቺ����Ă������A���ʕ��̐ێ�͓������\�h���Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ����B�@�������A���g���q�g��w��ÃZ���^�[�̌�����Petra Peeters ���m�� Carla van Gils���́A����̏����T�u�O���[�v�ŗ\�h���ʂ�������\���͏��O�ł��Ȃ��A�ƃR�����g���A�܂�����̌����ɂ��ẮA���B�ɂ�����h�{����т���Ɋւ���ő�̊r�������ł͂��������̂́A�ǐՊ��Ԃ�5.4�N�ԁi�����l�j�Ɣ�r�I�Z���������Ƃ��u�������\�h���Ȃ��v�Ƃ���s���ȓ_�Ƃ��ĔF�߂Ă���A����̒m���ɂ���Đl�X�����ʕ����d�v�����邱�Ƃ��~�߂Ȃ��悤�ɁA�ƌ���ł���B
2005/01/15�H�����K�C�h���C�����\�c�Č����ȁ@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20050114so13.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E ��ÂƉ���E ��Ãj���[�X�@2005/01/14�@�@������2/3���얞�ɔY�ނƂ����č��ŁA���������Ȃ�12���A�u�����̑唼�͑���߂��v�Ƃ��āA�����⎉�b�̑����H��������A���ĂȂǁu�S�������v�Ɩ�ؒ��S�̐H�����ɐ�ւ���悤�����H�����K�C�h���C���\�����B�@��̓I�ɂ́A�S���������g�����p����V���A������90���ȏ�A�A��Ɖʕ���5�`13�i��/���E�v4.5�J�b�v/���̐ێ悪�]�܂����Ƃ����B�^���s�������̂��߂ɂ�30��/���A���N�ȑ̏d���ێ����邽�߂ɂ́@1�`1.5����/���̕��s��P���ȑ̑��𐄏����Ă���B
�č����H���K�C�h���C���̐V�ł����\
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/353678
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2005/01/14�@�@2005�N�K�C�h���C���́u�̏d�R���g���[���A�拭�ȋ؍��`���ƃo�����X�̂Ƃꂽ�h�{�ێ�ɂ�閝�������\�h�v��B�����邽�߂̕��L����A�얞�̉��P�Ɨ\�h��ڎw�������́B�u�ێ�J�����[�����v�Ɓu�^���ʑ����v����������Ă���B�@��̓I�ɐ�������Ă���H�ނ́A�ʕ��E��A�S�����i�������̍����j�Ƌ����B
�@�ʕ��́A2�J�b�v����/���A���2.5�J�b�v����/����ێ悷��B
�@�܂��A����̉ʕ��E������H�ׂȂ��悤�Ɂu�Z���̖�A�Ԃ݂�тт���A���ށA�ł�Ղ�ɕx��A���̑��̖�v�S�Ă��P�T�Ԃɐ���ۂ�悤�w���B
�@�X�ɑS������85g�ȏ�/���̐ێ���A�����͖����b�܂��͒ᎉ�b�̂��̂��R�J�b�v/���@���ނ��Ƃ����߂Ă���B�^�o�R�ƃR�[�q�[�̑g�ݍ��킹�͌��ǂɈ����@
�@�A�e�l��ȑ�w�̃`���������{�X�E�u���`���v�[���X���m�炪�u�ĐS���w��v�iJournal of American College of Cardiology �j�ŋߍ��ŕ����Ƃ���ɂ��A�^�o�R���z���Ȃ���A�����ɃR�[�q�[�����ނ��Ƃɂ��A�哮�����ꎞ�I�ɍd���Ȃ�A���̍d���̒��x�̓^�o�R��R�[�q�[��P�ƂŐۂ����������A���҂�g�ݍ��킹���ꍇ�̕����͂邩�ɑ傫���Ȃ�̂ŁA���N���Ē����Ƀ^�o�R���z���ăR�[�q�[�����ނƂ����K���́A���ǂɈ����̂ł�߂������悢�ƌx�����Ă���B
2005/01/05�A���R�[���̔]�ւ̊Q�̓r�^�~���a�P�s��������Ɂ@
�@�u�_�o�Ȋw�W���[�i���v�iJournal of Neuroscience �j�Ɍf�ڂ��ꂽ�Ƃ���ɂ��ƁA�A���R�[���N���ݑ����Ĉˑ��ǂ��Ђǂ��Ȃ�ƁA�A���R�[���̈��e���Ŕ]�זE���j��āA�l�X�ȏ�Q���N�����B
�@���̒��́u�E�G���j�b�P�E�R���T�R�t�a�v�́A�A���R�[�����ł������Ƃ��鐸�_�ǂŁA���M�A�p���A���s�����A��}�q�A枖Ӂi��������j�A�����_�o���A���Y�ǂȂǂ��B���̕a�C�̓A���R�[�����ł̏�Ƀ`�A�~���i�r�^�~���a�P �j���R�ɂ��N���邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B
2004/11/27�O���B���ǂɂ���ς�m�R�M�����V��������
�@�n�[�o�[�h��w����o�ł���Ă���j�����N�G���u�n�[�o�[�h�E�����Y�E�w���X�E�E�H�b�`�v11�����ɁA�O���B���ǂɂ��Ǐ�̐i�s��H���~�߂邽�߂̍ŐV�m�����f�ڂ��ꂽ�B
�@���̋L���ɂ��ƁA�u�Z�C���E�m�R�M�����V�v���A��͂�ł����ʂ����肱��𗘗p���邱�Ƃɂ��A��Ԃ̔r�A������25���������A�O���B���ǂɂƂ��Ȃ��s���ȏǏ�28���y������Ă���A����p�����͂Ȃ��Ƃ� ���B�ԃ��C�������ނƔx�K���̗\�h�ɂȂ�@�@�@
�@�y�C���̃T���`�A�S�E�f�E�R���|�X�e����w�̃z�A���E�o���X�����炪�A�w�p���u���s�v�iThorax�j11�����ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A�ԃ��C�����x����̗\�h�ɂ��A���ʂ���Ƃ����B
�@�X�y�C���̃T���`�A�S�E�f�E�R���|�X�e���n��̔x�K������132�l�ƁA�x�K���łȂ����@����187�l��ΏۂɁA���C�������ޏK���ƕa�C�Ƃ̊W�ɂ��Ē��ׂ����ʁA�ԃ��C��������ł���l�́A�x�K���a���銄�����A�ԃ��C��������ł��Ȃ��l��菬�����A�����C��������ł���l�͔x�K���ɂȂ銄�����ނ��덂�������Ƃ����B�ԃ��C���Ɋ܂܂�Ă���^���j���ނ�X�x���g���[���Ȃǂ̍R�_�������ɂ����ʂ��Ǝv����B
2004/11/21�얞�F�Q�s���������H�@�đ匤���O���[�v�@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/medical/news/20041120k0000m040056000c.html
�@�@�@�@�@�����V���@�� �T�C�G���X�@���@��� 2004/11/19�@�Đ��{�̌��N�h�{�����̃f�[�^�͂����ăR�����r�A��̌����O���[�v���k�Ĕ얞������̑���Ŕ��\���Ƃ���ɂ��A�u�����s���͔얞�������N�����v�Ƃ̂��ƁB �@��������7�`9���Ԃ̏\���Ȑ��������l�ɔ�ׂāA�얞�ɂȂ闦���݂�ƁA
�@�@�@�@�S���Ԉȉ��̐l�F�@+73��
�@�@�@�@5���Ԃ̐l�F�@�@�@�@+50��
�@�@�@�@6���Ԃ̐l�F�@�@�@�@+23���ƁA�@�얞�ɂȂ闦�������B�N�������N�A�̏d�V�L�����@�S���a�ɒ��ӁI�@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20041115so11.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E��ÂƉ�� > �j���[�X 2004/11/15�@18�`30�̒j��2500�l�ɂ���15�N�Ԃɂ킽�萶���K���⌒�N��Ԃ�ǐՒ��������ăm�[�X�E�G�X�^����̖h��w�����`�[�����A�č��S���a�w��ŕ����Ƃ���ɂ��A�N�����璆�N�ɂ����đ̏d����VKg�ȏ㑝�����l�́A�قƂ�Ǖω����Ȃ������l�ɔ�ׁA�S���a�ɂȂ�댯�x���T�{�������Ƃ����B
�@15�N�ԂɂVKg�ȏ�̏d���������l��80�����������A���̓���20���ɍ������⍂�����ǁA����Ɍ����l��������z�������ł���C���X������������Ȃǂُ̈킪�����A���������ُ�́A�č��Łu��ӃV���h���[���v�ƌĂ�Ă���B��E�ʕ��͂���̃��X�N��ቺ�����Ȃ��@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20041112hj000hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2004/11/02�@�ăn�[�o�[�h��w���O�q����w�@�i�{�X�g���j�̌����҂�́A1970-80�N��ɊJ�n���ꂽ�����K�������N�ɗ^����e����]�������K�͂ȁu�Ō�t�̌��N�����v����сu��Ð��Ƃ̒ǐՒ����v�ւ̎Q���҂ŁA�����̐H���ōŒ�5�M�̖��ʕ���ێ悷���Ð���11���l�߂��ɑ��čs�����A���P�[�g���ʂ���͂��A����֘A��w���uJournal of the National Cancer Institute�v11��3�����Ɍf�ڂ����Ƃ���ɂ��A�]���̌��ʂƂ͈قȂ���̂ŁA�S���ǎ������X�N�͒ጸ������̂́A�����I�Ȃ��ǃ��X�N�͒ቺ���Ȃ��\������Ƃ����B�@�ߋ��̂��̂ƈقȂ闝�R�Ƃ��ẮA�L���̑z�N����ѕ̍ۂɃo�C�A�X�����������ƁA�܂��A����̔��ǂɂ͐S���ǎ����ɔ�ׂĒ������Ԃ��K�v�ł��邱�ƁA����̌����ł͐��l���ȑO�̐H�K���͌������Ă��Ȃ����Ƃ��l������B
2004/10/31�ق됌���̐l�]�[�ǂɒ��Ӂ@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20041025so11.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E��ÂƉ�� > �j���[�X 2004/10/25�@�@���{��ȑ�V�l�a�������i���s�j�ƍ���������ÃZ���^�[�������i���m����{�s�j���A�Ĉ�w���j���[�����W�[�ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A�A���R�[��������y�f�i�`�c�g�Q�j�̊������Ⴍ�ق됌���C�������������A�����݉߂��Ă��܂��X���̒j���́A�y�f�����̍����j�����2�{�ȏ���]�[�ǂɂȂ�Ղ����Ƃ�˂��~�߂��B
2004/10/10�ԃ��C���͑O���B�K���\�h�ɂ������@
�@�ăV�A�g���ɂ���u�t���b�h�E�n���`���\�������Z���^�[�v�̕ɂ��ƁA�����ԃ��C���P�t���x����ł���l�́A�O���B�K���ɂȂ郊�X�N��50���Ⴂ���Ƃ��킩�����B
2004/10/03�݂���\�h�����Ȃ�c��܂����Β�5�t��/���I�H�@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20040927so12.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E��ÂƉ�� > �j���[�X 2004/09/27�@1990�N�ȍ~�A�Œ�12�N�Ԃɂ킽��A�j����7��3000�l�̐H�K���ƌ��N��Ԃ̕ω���ǐՂ������ʁA�݂���\�h�ɂ́A������܂����Β���5�t/���ȏ���ނƗǂ��������Ƃ����������ʂ��A�����J���Ȍ����ǁi��C�����ҁ��Ë�����Y�E��������Z���^�[�\�h���������j���Z�߂��B�@�Β������ޏK���Ƃ̊֘A�ׂ�ƁA������5�t/���ȏ���ނƁA�قƂ�Lj��܂Ȃ��l�ɔ�ׁA�݂���ɂȂ�댯����3���Ⴉ�����B�j���ł́A���m�ȉe���͊m�F�ł��Ȃ������B
�@�݂���̂ł���ꏊ�ɂ���ėΒ��̉e�����傫���قȂ�B�݂̏o�����Ɍ���A���ł���댯���́A�قڔ����B����A�M�����ݕ��͐H������Ȃǂ̗v���ɂȂ肤�邱�Ƃ��m���Ă���A�Β��̏ꍇ���A�݂̓�����t�߂ł́A�\�h���ʂ͂قƂ�ǖ��������B�����̋��������������A�얞���^���s���c�ĂŒ����@
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20040927so11.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E��ÂƉ�� > �j���[�X 2004/09/27�@�ăt�����_��Ȃǂ̃`�[����1996�`2000�N��906�l�̏�����Ώۂɂ������C�t�X�^�C���S�ʂɂ킽�銈���̒ǐՒ�����č���t��G���ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A�����̐S���a��]�����ȂNj����������̔��ǂɂ́A�얞���u�^�����Ȃ��v�u���퐶���ő̂����Ȃ��v�ȂNJ������̒Ⴓ�̕��������֗^���Ă��邱�Ƃ��A�������B
�@�̏d�͐l���݂ł��A�^�������ڂ�Ƌ����������ɂȂ�Ղ��Ƃ�����B����3��/���ȏ���ސl�̈�Ô�A2���ȉ��ɔ�ő�6����
�@�@http://www.asahi.com/health/life/OSK200409210056.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/09/22�@���{���Ɋ��Z���ĕ���3��/���ȏ���ސl�̈�Ô�́A2��/���ȉ��̐l�ɔ�ׂčő��6���ȏ㑽�����Ƃ��A�㓇�O�k�E�����勳���i�����ی���w�j�Ȃǂ̒����ŕ��������B�]������S�؍[�ǂȂnjX�̕a�C�⎀�S���ɗ^����e���ɂ��Ă̒����͂��������A��Ô�Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ��������ŁA���݉߂��͉ƌv�����łȂ��A��Í����ɂ��}�C�i�X�ɂȂ邱�Ƃ������ꂽ���̂��B
2004/09/19�ŋ߂͑̏d���C�ɂȂ�̂ŃT���_����ς��܂����H�@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/colm04/331444
�@�@�@�@�@MedWave�E��t���˘f�����N����@2004/09/15�@�@�T���_�������ی��p�H�i�i�ȉ��g�N�z�j�ƂȂ��Ă���W�A�V���O���Z���[��(DAG)����̂��̂ɂ��Ă��A�̎��b�͌��邩���m��܂��A�̏d�͌���Ȃ��̂ɁA�W�A�V���O���Z���[������̐H�p����}���l�[�Y�̃e���r�R�}�[�V����������ƁA�����̏��i��ۂ�ΐۂ�قnj��N�ɗǂ����̂悤�Ɏv���Ă��܂��B
�@�����g�N�z�����B�̌��N�ɖ{���ɗǂ����ǂ������͂����肷��̂́A5�`10�N�Ƃ����������I�Ȑێ�ɂ��a�C���\�h�ł��邱�Ƃ�������鎞�ŁA����̓��[�J�[�ł͂Ȃ��Č��ʓI�Ɏ��ۂɎg������Ҏ��g�ɂȂ�̂ł́A�ƌx����炵�Ă���B���f�֕��A�u�₹�`�v�������œ��A�a�̊댯�@���J�Ȓ���
�@�@http://www.asahi.com/health/life/OSK200409110014.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/09/12�@�������l�ɔ�ד��A�a�ɜ���ƌ����鑉���`�̒j�����A�������ޏK��������Ɗ댯�����܂邱�Ƃ��A�����J���Ȃ̌����ǁi��C�����ҁ��Ë�����Y�E��������Z���^�[�\�h���������j�̒����ŕ��������B���{���Q�����x�ł��A���A�a�̜��Ղ����{�ɂȂ�Ƃ����B�����ł̊W�͕�����Ȃ������B
2004/09/13�����ł��₷���l�̓R�[�q�[�ɂ����Ӂ@
�@�A���̃J���V�E������A�A�_�Ȃǂ�������Č��������Ăł���̂������t�i����j�B���ꂪ�ł���ƁA���ݕ���ۂ藬���o���Ɨǂ��ƌ����邪�A���V���g���B����w�̃����_�E�}�b�Z�[���m�̌����ɂ��A�R�[�q�[�����ނƁA�A���ɔr�o�����J���V�E���̗ʂ������邽�߁A�����o���Ղ��Ȃ�̂ŁA�P���ɃJ�b�v�Q�t�ȓ��ɐ������ׂ����ƁA�G���u��A��ȃW���[�i���v�iJournal of�@Urology�j�Ŕ��\�����B�u���[�x���[�ŃR���X�e���[�������������@
�@�u���[�x���[�͍R�_����p�ɂ��A�a�C�̗\�h�ɗL���Ȃ��Ƃ��m���Ă��邪�A�Ĕ_���Ȃ̉��w�ҁA�A�O�l�X�E���}���h���m�ɂ��A�u���[�x���[���̉��w�����u�e���X�e�B�[���r�[���v���A���ʃR���X�e���[���u�k�c�k�v���������铭�������邱�Ƃ�˂��~�߂��Ƃ����B�I���K�R���b�_���A���c�n�C�}�[��h�����Ƃ��}�E�X�ŏؖ��@
�@�����ɑ����܂܂�Ă���u�I���K�R���b�_�in-3�n�����s�O�a���b�_�v�̌��N���ʂ́A�悭�m���Ă��邪�A�t�b�k�`��w���̐_�o�w�����A�O���b�O�E�R�[�����m�̃}�E�X���g���������ɂ��A�哤�ƃt�B�b�V���I�C���̉a�ɃA���c�n�C�}�[�a�ɂ��]�̑�����h�������Ɍ��ʂ����邱�Ƃ��m�F�B9��1���A�G���u�j���|�����i�_�o�זE�j�v�Ŕ��\�����B
2004/09/04�g�}�g�W���[�X�����A�a���҂̌��t�ÌŔ\��ቺ�@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20040827hj003hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X 2004/08/27�@�č���t��uJAMA�v��8��18�����Ɍf�ڂ��ꂽ�����ł́A�g�}�g�W���[�X��2�^���A�a���҂̌��t����߂��ċÌŔ\��ቺ�����邽�߁A�A�e���[���������d���ǂ�S������A�]�����Ȃǂ̐S���Ǐ�Q���X�N���ቺ�����āA�v�����̏�Q�̉���ɖ𗧂��Ƃ����炩�ɂȂ����B
2004/08/29�w���V�[���|�[�g�F �I���[�u�I�C���@�H�̌��N�ʂ�u�����̉t�́v�@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/medical/news/20040828ddm010100170000c.html
�@�@�@�@�@�����V���@�� �T�C�G���X�@���@��� 2004/08/28�@�A�e�l�ܗւŏ��҂̓������鏬�}�̊��̃I���[�u�̖́A�I���O����u�����̉t�́v�ގ��Ƃ��Ēm���A�ʎ�������Ƃ����I���[�u�I�C�������܁A���N�I�ȐH���ʂ�I�C���Ƃ��ĉ��߂Ē��ڂ���Ă���Ƃ������|�[�g�L���B�@���I���C���_���ʁA�R���X�e���[���ቺ�|�|�u���ʁvLDL�ɂ̂ݍ�p
�@�܂��g�R�t�F���[���ށi�r�^�~���d�j��R�_����p�̂���|���t�F�m�[���ނ������A����炪�畆�̃V���`����}��������A�V����h�������̂��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B���̂ق��A�I���[�u�I�C���͒_�`�̗�������������邽�߁u�_�Η\�h�ɂ����ʂ�����
�@���ō����G�N�X�g���o�[�W���A100Kg�̎�����7Kg�|�|�_�x�Ɛ��Ƃ̌����őI��
�@�I�C���̎�ނ̒��̍ō����̃G�N�X�g���o�[�W���́A�_�x�i�P���ȉ��j�Ɛ��Ƃ̊��\�����i���⍁��j�őI�ꂽ�I�C���ŁA100Kg�̎�����7Kg�O�サ���̎�ł��Ȃ��Ƃ����B
�@�����ō�������ɂ̍���|�|�s�G�g���E�R�����r�i
�@��肽�Ă̍��肽�I���[�u�I�C���̈���C�^���A�E�g�X�J�[�i�Y�́u�s�G�g���E�R�����r�i�v�i750mL�A5250�~�j�B�X�p�C�V�[�Ȑh�݂Ǝ�X�������肪�����ŁA�����ł͓����I�C���I���A���A�ʐM�̔�����ŗ\����t���Ă���B
�Â��\�t�g�h�����N�D���̏����͂��p�S�A2�^���A�a�Ƒ̏d�����̃��X�N�Ɂ@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/327403
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/08/26�@�@��Harvard��w���O�q���Z�\�h��w����Matthias Schulze����̌����ŁA�Ĉ�t���Journal of American Medical Association��2004�N�W��25�����Ɍf�ڂ��ꂽ�ɂ��ƁA�Â��\�t�g�h�����N�ɂ́A�ʏ�T�C�Y�P�ʁi350mL�j�ɁA50g�̔`���R�P�����ɕC�G�����33g���̍����i�V������ʓ��j���܂܂�Ă���A�����̈������P�{�ȏ���ݑ��������l�����ł́A�قƂ�Lj��܂Ȃ������ɔ�ׁA2�^���A�a���ǃ��X�N����1.8�{�����A���������Ԓ��Ɉ��ޗʂ��������Q�ł͑̏d���������ɒ��������Ƃ����������B�@�ʃr�[���P�ʁi350mL�j�̃G�l���M�[�ʂ��R�[���ނƂقړ����Ȃ̂ŁA�P���̑��G�l���M�[�ʂ𑝂₳�Ȃ��悤�ɓw�߂�K�v������ƌx�����Ă���B
�@���{�_���F�uSugar-Sweetened Beverages, Weight Gain, and Incidence of Type 2 Diabetes in Young and Middle-Aged Women�v
��֘A����
�\�t�g�h�����N�A���{�ł͒��n�������g�b�v�A�ÂݍT���߂��嗬�� �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/327754
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/08/27�@���A�a�ɂȂ�ƃA���c�n�C�}�[�a�ɂȂ�Ղ������č��Œ����@
�@�V�J�S�ɂ��郉�b�V����w��w�Z���^�[�̌����ҒB��1000�l�߂����N�����ɒǐՒ������A�G���u�_�o�Ȋw�v�iArchives of Neurology �j�ɔ��\�����Ƃ���ɋ���A���A�a�������Ă���l�́A�A���c�n�C�}�|�a�ɂȂ銄�����������Ƃ�������A���A�a�̂R�升���ǂƂ�����A����Q�A�Ԗ��ǁA�r�̖����_�o��Q�ɁA�A���c�n�C�}�[�a������邩������Ȃ��Ƃ����B �@�]�����͌��j���ɋN����|�|�t�B�������h�Œ��ׂ�@
�@�t�B�������h�������O�q���������W���R�r�G�r�b�N�E�f�B�~�g���[���m�炪�A12,801�l�̋L�^�����Ƃɒ��ׂ����ʂ��G���u�]�����v�iStroke�j�ŐV���Ŕ��\�����Ƃ���ɂ��A�A�������̔]�����́A�P�T�Ԃ̂����ŁA���j���ɒf�R�����N���Ă���A���j���ɍł����Ȃ��B����60�`74�̍���҂ł͌��j�����f�R�������A������ʂł́A�Ηj���������Ƃ����B
2004/08/22�₹�`�j��������ɂ����Ӂ@���J�Ȍ����ǒ����@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/medical/news/20040820k0000m040110000c.html
�@�@�@�@�@�����V���@�� �T�C�G���X�@���@��� 2004/08/19�@�����J���Ȍ����ǁi��C�����ҁE�Ë�����Y��������Z���^�[�\�h���������j��90�`01�N�ɂ����āA�S����40�`60��̒j����9���l���p������������K�͉u�w�����̌��ʁA���������{�l�j���́A�W���̌`�̒j���ɔ�ׂĂ��������ő�29�����������Ƃ����������B�얞�ł���̃��X�N�������Ȃ�댯���͐������w�E����Ă��邪�A�₹�`������ɂȂ�₷�����Ƃ��V���Ɏ����ꂽ���ƂɂȂ�B
�@�������ʂɂ��ƁA�̏d�iKg�j��g���im�j��2��Ŋ������l�ł���a�l�h���A23�`29.9�̒j���͂��������قƂ�Ǖς��Ȃ����A�₹�`�ɂȂ�ɏ]���Ĕ������͏㏸���A�������̍ł��ႢBMI=23�`24.9�Ɣ�r����ƁA�ł������Ă���BMI=14�`18.9�ꍇ�́A29���Ɣ������������Ȃ�B����A�ł������Ă���BMI=30�`39.9�ł���������22���ƍ������Ȃ�B�w���V�[���|�[�g�F����҂ɂ͂k-�J���j�`�����@
�@�@http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/medical/archive/news/2004/07/31/20040731ddm010070169000c.html
�@�@�@�@�@�����V���@�� �T�C�G���X�@���@��� 2004/07/3�@���H�����ɁA�A�~�m�_��r�^�~���b����̃\�[�Z�[�W�^�C�v�̐H�����i���o��A�l�C���Ă�ł���Ƃ����B���̗��R�́A�����͓d�q�����W�Ŗ�P���̊ȒP�֗��ʼnh�{�o�����X���ǂ��A����̊��͌��Ƃ��Ă��s�b�^���Ƃ������Ƃ���B
�@���ł����ڂ���Ă���̂��̎��b��R�₵����A�]�זE�̔j��X�s�[�h��}���铭�����������ŃA�~�m�_�̈��A�k�|�J���j�`������B���̂k-�J���j�`���̕s�����������ǂⓜ�A�a�Ȃǂ̐����K���a�A�s�ق��Ǐ�������N���������Ƃ��Ȃ��Ă��邩��B���֘A���F
�@�E�_�C�G�b�g�����̃J���j�`���A�q�b�g�̒����@�[���[�����A�y�b�g�����A�T�v���Ȃǂ����L���o��i2004.5.7�j
�@�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/306047
�@�E�ɓ��n���@�k-�J���j�`���A�r�^�~��C����u���̃t���b�V�� ���[�j���O�u���E���v
�@�@�@http://itoham.mediagalaxy.ne.jp/corporate/news/040420.html�@�E�T�v�������g�E���N�H�i�@>�@L-�J���j�`���Ŏ��b��R�āI
�@�@�@http://allabout.co.jp/fashion/supplement/closeup/CU20040416A/�@�E���b�R�Ăɕs����L-�J���j�`��������
�@�@�@http://health.biglobe.ne.jp/colum07/item72.html �@
2004/08/08�Β����E�[�����������ނƍ�������\�h�A1�t/���ȏ�ŁA���������ǃ��X�N��46���Ⴍ�|�|��p�̉u�w�����@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/324042
�@�@�@�@�@���o�w���X�E�T�v�����@�\���H�i�@�g�s�b�N�X�@2004/08/06�@�@�Ĉ�w���uArchives of Internal Medicine�v�ɔ��\���ꂽ�A��p�E����������w�ɂ��u�w�������ʂɂ��ƁA�Β����E�[��������120ml�i���݂̂P�t���x�j�A1�N�ȏ���ݑ����Ă���l�́A�������̔��ǃ��X�N���Ⴂ�Ƃ����B�u�Β��ň݂���\�h�v�����Ŋm�F�@���J�Ȍ����ǂ�����
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200408040179.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/08/04�@�Β��̂���\�h���ʂɂ��ẮA����܂ōm��A�ے藼���̕����������A�����J���Ȃ̌����ǁi�ǒ��E�Ë�����Y��������Z���^�[�\�h���������j�ɂ��S���V�n���40�`60��̒j����73000�l���A7�`12�N�ɂ킽���ĒǐՂ�����K�͂ȉu�w�����̌��ʂɂ��A�j���ł͌��ʂ��m�F�ł��Ȃ��������A5�t/���ȏ�Β����悭���ޏ����ł͈݂���ɂȂ郊�X�N���Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�o�i�W�E���������t���T���T���ɂ��ē��A�a��h�� �@
�@�@http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/kenkou/plus/320777
�@�@�@�@�@nikkeibp.jp�E���N�@2004/07/22�@�@�o�i�W�E�����܂ރ~�l�����E�I�[�^�[�i�o�i�W�E�����j���A�킸��80��g�i0.08mg�j/��������ł��A�C���X�����̌����ڂ����P�������A�a��h�����Ƃ��킩�����B����Ȍ������ʂ𒆑��w����w�̃O���[�v�����\���A�b��ɂȂ��Ă���B�@���A�a�����P���鎡�Ì��ʂ��m�F�ł������^�ʂ́A1�������萔�\mg�ł��������A��L�̌��ʂ́A���̐��S����1�̗ʂŗ\�h���ʂ����҂ł���Ƃ������́B
2004/07/25�Ă����͔]�����̌����u�S�[�ד��v��\�h����?!�|�|�č�CHS�������画��
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/320932
�@�@�@�@�@���o�w���X�E�T�v�����@�\���H�i�@�g�s�b�N�X�@2004/07/22�@�@�č��̍���Җ�4800�l��12�N�ԒǐՂ���CHS�iCardiovascular Health Study�j�����̌��ʁA���D���̐l�ɔ]���������Ȃ����Ƃ͊��ɕ���Ă������iJAMA�G285,304-12,2001�Ȃǁj�A�]�����̌����ɂ��Ȃ�u�S�[�ד��v�Ƃ����s�������A�Ă������悭�H�ׂ�l�͔��ǂ�����Ƃ����������ƕč��S������iAHA�j�����s����uCirculation�v���d�q�łŁA�V��19���Ɍ��J���ꂽ�B
2004/07/18�i�b�c�D���̏����ɂ͒_�����Ȃ��I �č��̑�K�͏����u�w�������画��
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/319777
�@�@�@�@�@���o�w���X�E�T�v�����@�\���H�i�@�g�s�b�N�X�@2004/07/15�@�@�č��̏����Ō�t���悻8���l���A20�N�ԒǐՂ����u�w�����uNurses' Health Study�v����A�ȑO�̓i�b�c�D�������ɂQ�^���A�a�����Ȃ����Ƃ�������傫�Șb��ɂȂ������A����i�b�c���悭�H�ׂ鏗���ɂ́A�Ђǂ��_�ΏǂɂȂ�l�����Ȃ��Ƃ������̂ŁA�_�Ƃ̊W�����炩�ɂȂ����̂͏��߂āB�������ʂ́uAmerican Journal of Clinical Nutrition�v���V�����ɔ��\���ꂽ�B�P�g���C�u���H�͖����v�͂U���@�����͂���s�ϒ���
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200407050435.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/07/06�@�_���ȂƔ_�������H�̕��y�����̂��߂ɑg�D���Ă���u�����͂���s�ψ���v���P�g���C�҂̒��H�ɂ��Ē��������Ƃ���A
�@�@�u�����K�����H��H�ׂĂ���v�l�́A59���A
�@�@�u���H��H�ׂȂ��v�l�́A13���������B�@���H��H�ׂĂ���l�̂����A�����ʂ��Ă��鎞�ɔ�ׂĒ��H��H�ׂ�p�x���u�������v�Ɠ������l��24���ŁA�u�������v�̂V����傫�������Ă���A�P�g���������H����ɂȂ��邱�Ƃ����������B
2004/07/11�����K���a��Ղ���������E�F�u�T�C�g�uLivita-Life�v�J�݂����
�@�@http://www.taisho.co.jp/outline/rls/htm/04_0707-j.htm
�@�@�@�@�@�吳�����E�j���[�X�����[�X�@2004/07/02�@�@�吳������Ђ́A�����K���a���킩��₷����������E�F�u�T�C�g�uLivita-Life�v��7��7�����J�݂��܂����B�@�uLivita-Life�v�̃R���e���c�́A���̂Ƃ���ł��B�@�l�ԃh�b�N�Ŏ�M�������ʂ��A��L�́u���N�f�f���ʂ̐����������v�̃y�[�W�Ń`�F�b�N���Ă݂ĉ������B�厖�Ȏ��������Ƃ����Ă��邩���m��܂����B
�@�Z���t�`�F�b�N�̃y�[�W�̒��ł́A�o�C�I���Y���̃`�F�b�N�o���܂��B
2004/07/04�u���[�J�[�{�E�_�C�G�b�g�v�ŁA������Q�����P
�@�Y�����������H�́A�i���R���v�V�[�̏Ǐ���y������|�|��Duke��w�����@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/315630
�@�@�@�@�@���o�w���X�E�T�v�����@�\���H�i�@�g�s�b�N�X�@2004/06/24�@�@�Y���������ɒ[�ɐ�������u���[�J�[�{�E�_�C�G�b�g�v�ŁA������Q�̈��ł���i���R���v�V�[�̏Ǐ��P����Ƃ����������ʂ��A�č�Duke��w�̌����O���[�v���� ���ꂽ�B�������ʂ́A�č��_�o�w��̊w�p���uNeurology�v��6��22�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B���N���Ȃ������A56���̐l���u�����K���v�@���J�Ȓ���
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200406180209.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/06/18�@�����J���Ȃ�18���ɔ��\�����A�S��1500�l��Ώۂɂ����������ʂ��܂Ƃ߂�04�N�x�̌����J�������ɂ��ƁA���A�a��S�����ɂȂ�������̐����K�����A�ł��������N��̃��X�N���ƁA��������l�������l���Ă��邱�Ƃ��������B���R���X�e���[����N��@���T�����A�W�N�Ŕ{��
�@�@http://www.asahi.com/health/life/OSK200406090020.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/06/09�@����ȑ�ƕl����ȑ傪�����Œj���v��9000�l���������ʂɂ��A���w�T�N�ŃR���X�e���[���l���������q���W�N�̊Ԃɔ{�����Ă���Ƃ����B�j�q�ł������Ă��āA���Ƃ͏����A�S�؍[�ǂȂǂ̑����ɂȂ���Ɨ\�z�B���̌��ʂ́A6���ɏo����{�u�w��̊w��ɔ��\�����B�P���P�������̈����Ŕ]�[�ǂS�����@�R���ȏ�͔]������
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200406070302.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/06/08�@�u���{����1������1�������i�r�[���Ȃ��r�P�{�����j���ށv�K���̒��N�j���́A �u���X���ށv�l�ɔ�ׁA�]�[�ǂ̔��Ǘ���4�����Ȃ����Ƃ��A�����J���Ȍ����ǁi�ǒ��E�Ë�����Y�E��������Z���^�[�\�h���������j�̒����ł킩�����B
2004/05/29�������m�[���_�iCLA�j�͊m���ɂ₹��I�@�m���E�F�[�̌����O���[�v�����̒��������Ŋm�F
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/310220
�@�@�@�@�@���o�w���X�E�T�v�����@�\���H�i�@�g�s�b�N�X�@2004/05/28�@�@�q�}�����̎�⋍���ȂǂɊ܂܂�Ă���u�������m�[���_�v�iCLA�j���Ƃ�ƁA�̎��b�������������Ƃ��A�m���E�F�[��Scandinavian�Տ��������ABetanian��ÃZ���^�[�Ȃǂ������ōs�����A1�N�Ԃ̃v���Z�{�ΏƎ����̌��ʂŖ��炩�ɂȂ����B�@CLA�ɑ̎��b�݂̂����炷���ʂ����邱�Ƃ́A�R�J���Ԃ̃q�g�����Ŋm�F����Ă������A�P�N�Ԏg���Ă����ʂ��������Ƃ��킩�����̂͏��߂āB
�@�������ʂ́A�uAmerican Journal of Clinical Nutrition�v��6�����Ɍf�ڂ��ꂽ�B
�J�t�F�C�����̏�Q��\�h�H�@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20040528hj001hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X�@2004/05/28�@�̏�Q�����������X�N�̂���l�́A�R�[�q�[�Ȃǂ̃J�t�F�C�����������ێ悷�邱�Ƃɂ���āA���̃��X�N��ጸ�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����������A�j���[�I�[�����Y�ŊJ�Â��ꂽ�č�������a�T�ԁiDDW2004�j�Ŕ��\���ꂽ�B�^���P��30���c�@WHO�A�����K���a��ɍ��ێw�j
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200405220332.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/05/23�@���E�ی��@�ցiWHO�j�����22���A�얞�ǁA�S�������A���A�a�Ȃǂ�\�h���邽�߂́u�H�����Ɖ^���Ɋւ��鐢�E�헪�v���̑������B����͐����K���a�ɑ��鏉�̍��ێw�j�ŁA�e���̎���ɍ��킹�ē��t������悤���߂Ă���B�@���N�I�łȂ��H�����Ɖ^���s�������A�a��S���a�A�ꕔ�̂���̌����ɂȂ��Ă���Ǝw�E�B
�@���K�x�ȉ^�����P���ɏ��Ȃ��Ƃ�30���ȏ�s��
�@�������A���b�A���̐ێ搧��
�@���ʕ��A��A���ނ̏���g��Ȃǂ����߂Ă���B
�q���C�r�u���t�T���T���v�ׂĂ݂܂��� �@
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200405180191.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/05/18�@���t�T���T���A�h���h���Ƃ������t���悭�����܂����A�э��ǂ̒��������̌��t�������l�q���^���̌��ł��鑕�u���J������A����������悤�ɂȂ��Ă���B ���̑��u�i�l�b�\�e�`�m�j�́A�Ɨ��s���@�l�H�i�����������i��錧���Ύs�j�̋e�r�C��̃O���[�v���J�����A01�N�A15�`77�̒j������563�l�̌��t��Ώۂɂl�b�\�e�`�m�̒ʉߎ��ԂׁA�����K���̈Ⴂ�ƑΏƂ������ʎ��̂悤�Ȃ��Ƃ��������B�@�j���Ƃ���Ƌ����D���Ȑl�͒ʉߎ��Ԃ��Z���A�����D���Ȑl�͒����A���ɏ����͂��̌X���������B�����́u�����������ށv�l�̗��ꂪ�ǂ��A�u�S�����܂Ȃ��v�l�͂������Ĉ��������B�^���� �u�����P���Ԉȓ��v���ł��ǂ��A�u�S�����Ȃ��v���Œ�B�����͋z��Ȃ��l�̕����ǂ������B
�@�h���h�����t�̕��Q�́A���ʃR���X�e���[���ɂ���ē����d�����N�����A�S�؍[�ǁi���������j��]�[�ǂւȂ���B
�q�������߂̐H�����r
�@�H�i�����������ɂ��ƁA�����̋ÏW��}����A���g�V�A�j�����܂܂�鍕���⎇�T�c�}�C���A�������̔S���⌌���̋ÏW��}����N�G���_���܂܂��~���������A�H�����̒��ɈӐ}�I�ɑ���������邱�Ƃ����A�������H�ׂ�̂͋t���ʁB
2004/05/16�}�[�K�����Ɋ܂܂��g�����X���b�_�ɈÉ_������� �u��R�ۂ�ƁA�{�P�₷���v�|�|�č�CHAP�������番��
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/307355
�@�@�@�@�@���o�w���X�E�T�v�����@�\���H�i�@�o�b�N�i���o�[�@2004/05/14�@�@�}�[�K������V���[�g�j���O�A���ŗg�����X�i�b�N�َq�ȂǂɊ܂܂�Ă���u�g�����X���b�_�v�́A�Ƃ�߂���ƐS���a�𑝂₷���ꂪ����Ƃ��āA2004�N�P������č��ŐH�i�ւ̕\�����`���t�����Ă��钆�ŁA �u�g�����X���b�_����������Ƃ邨�N���́A�ڂ��₷���v�Ƃ����A�X�ɂ�����C�|����Ȍ������ʂ��č��_�o�w����s����w�p���ANeurology���T��11�����Ŕ��\���ꂽ�B���_���F�uDietary fat intake and 6-year cognitive change in an older biracial community population�v
���č��H�i���i�ǁiFDA�j�̃T�C�g�F�uTrans Fat Now Listed With Saturated Fat and Cholesterol on the Nutrition Facts Label�v
�����������ސl�́A�]�̏�Q�ɂ����Ӂ@�@
�@�č��J���t�H���j�A��w�T���t�����V�X�R�Z�ł̌����ɂ��A�����̂悤�Ɏ�������ł���l�́A�A���R�[�����łœ��@���Ă��銳�҂Ɠ����x�ɔ]�̓����ɏ�Q���N���Ă���Ƃ����B�u�r�[���A�D�w�Ɉ��e���v
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20040511so12.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E��ÂƉ�� > �j���[�X �@2004//05/11�@�D�w��������̏������������ꍇ�A�ւ��̏�������ʂ��đَ���������A���R�[�������݁A����s�S�ɂȂ��鋰�ꂪ���邽�߁A���ɕč���؍��Ȃǂł́A�x���\�����`���Â��Ă��邪�A���{�̃r�[�����T�Ёi�A�T�q�A�L�����A�T�b�|���A�T���g���[�A�I���I���j��6���ȍ~�ɐ��Y����r�[���Ȃǂ̎�ސ��i�̃��x����ʕ\�ʂɁA�D�w�Ȃǂ��������ނƁA�َ�������̌��N�Ɉ��e����^���鋰�ꂪ����Ƃ̕\����V���ɕt����Ɣ��\�����B
2004/04/25����݂��H�ׂ�ƁA�P�J���Ō��ǂ̒e�͐������P�A�����d����h���@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/tpic/302535
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/04/19�@�@�č��̈�w�G���wCirculation�x��2004�N4��6�����Ɍf�ڂ��ꂽ�X�y�C���̃G�~���I�E���X��t��ɂ�錤���ɂ��A�I���[�u�I�C���A�g�}�g�Ȃǂ��ӂ�Ɏg���n���C�H�́A�S���a��\�h����ȂǁA���N�I�ȐH���Ƃ��Ă悭�m���Ă��邪�A���̒n���C�H�Ɏg���I���[�u�I�C���̈ꕔ���A����݂ɒu��������ƁA�������ǂ̐l�̌��ǂ��_�炩��������ʂ����邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B
2004/03/20�t�_�����̏��������]�����A�S���a��\�h����@
�t�_�́A�D�w�̏o�Y��Q��\�h���铭�������邽�߁A�č��ł́A�e�c�`�i�ĐH�i���i�ǁj�̎w���ŗt�_�������������A�P�X�X�U�N����o����Ă��邨��A���̗t�_�������������A�]������S���a�ȂǁA���njn�̕a�C��\�h���钘�������ʂ������Ă��邱�Ƃ��A�b�c�b�i�Ď��a�\�h�Ǘ��Z���^�[�j�̉u�w�ҁA�N�A���q�E�����O���m���A�ĐS������̏�œ��v�I�ɖ��炩�ɂ����B
2004/03/14�u��Ɖʕ������Ղ�H�v�͍�������h���|�|�Č����Ŗ��炩�� �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/med/leaf?CID=onair/medwave/tpic/295326
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/03/12�@�@American Journal of Epidemiology��3��15�����Ɍf�ڂ��ꂽ�����́Athe Chicago Western Electric Study�Ƒ肳�ꂽ���̂ŁA�A�����J���\����u�E��R�z�[�g�����v�̈�ŁA�č��̒��N�j��1700�l���V�N�ԒǐՒ��������������ʂŁA���ʕ��ɂ͍�������\�h������ʂ����邱�Ƃ��������Ƃ����B�@���ʕ��������Ղ���l�́A�N������Ă����������܂�オ�炸�A�t�ɁA�����R�H�ׂ�l�� �����̏オ������傫�������Ƃ����B
�@���̒ǐՒ�����40�N�ȏ㑱���Ă���A�u������������H�ׂ�l�͐S�؍[�ǂŎ��ʃ��X�N���Ⴂ�v�iNEJM�G336,1043,1997�j���ƂȂǁA���N�ɖ𗧂M�d�ȃf�[�^�����������Ă���A����͂��̖c��ȃf�[�^�̒�����A1950�`60�N��́u�����̃f�[�^�v�V�N���݂̂��g���āA�H�����ƌ����̊W�͂������́B
����������Ղ�H�ׂ�l�́A���܂�H�ׂȂ��l��茌���㏸����3���Ⴂ
�@��������Ղ�H�ׂĂ���l�́A���܂���H�ׂȂ��l���A��̌����̔N�ԏ㏸����3���Ⴍ�A�ʕ������l��17���Ⴉ�����Ƃ������Ƃ��������B
�@������r���Ȃǂ��R�H�ׂ�l�́A�������܂�H�ׂȂ��l���A�� �̌����̔N�ԏ㏸����4�����������B�ؓ���{���ł����l�ɁA���܂�H�ׂȂ��l��茌���㏸�������ꂼ��27����11�����������B
�@�Ȃ��A�����R�H�ׂ�l�́A�����㏸�����Ⴂ�X�����������Ƃ������A������������H�ׂ�K��������l���A�����J�ɂ͏��Ȃ��A�͂����肵�����Ƃ͂킩��Ȃ������Ƃ����B�@�@����ɔ��̒��肪���Ȃ��Ȃ�A�V�~��V�����ł��邪�A�̂̒��ł��������Ƃ��N�����Ă���A���ǂ̒e�͐����Ȃ��Ȃ�A���ǂ̓����Ɏ��b�Ȃǂ̘V�p�����\����A���ǂ��ׂ��A�d���Ȃ��Ă��邩��A�̂͌������グ�āA�K�v�Ȍ��t��̂̂��݂��݂ɓ͂��悤�Ƃ���B�����������Ӗ��ł́A���N���߂���ƍ������̐l��������̂́A���R�Ȃ��Ƃ��B
�@���{�l�ł��A�������̐l�̊����̑����́A30�Αォ��50�Α��r�ŁA�j����24����52���A�������V����43���ƂȂ��Ă���B�i�����J���Ȃ́u����11�N�����h�{�����v�ɂ��j�B
����̌��ʂ́A���̘̑̂V���ɂ��u���R�ȗ���v���A�H�������H�v���邱�ƂŒx���ł���\�����������́B
��M�҃R�����g�� �@2/9�ɂ����|�[�g�������e�i�������5�M���i350g�j�Ɖʕ�200g���`�u��t�H�[�����v�J�Áj�Ƃ��d�Ȃ�܂��B
�@�����K���a�̗��ɂ͊����_�f�̑��傪����A���̊����_�f�̉e�����ɗ͗}���邽�߂ɂ͖�E�ʕ�����R�H�ׂ�K�v������Ƃ������ƂŁA�����Տ��I�ɂ����t����f�[�^���A�ǂ�ǂ�o�Ă��Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@���̏��𑼎R�̐Ƃ��邱�ƂȂ��A��������Ƃ��킸��������A���Ȃ��̐H�������������āA�����Ɏ��s�Ɉڂ��Ă���������A����ɂȂ������ɕa�C�a����m�����啝�ɏ��Ȃ��A�a�C�m�炸�̌��N�I�ȘV�オ�����Ǝv���܂��B
�@�V��N���̎x���N������Ȃ錻��ł́A��Ô�̕��S��}���邽�߂Ɏ��Ȗh�q���邵���Ȃ��̂ł����A�F����͔@�����l���ł����H�@����Ȃ��ƌ��������āA�����̖Z���������̒��ŐH�������ǂ̂悤�ɂ���Ή��P�ł���̂��H�@���������^��������ꂽ���́A�������p����T�v�������g�����Љ�����܂��̂ŁA��������Ă݂Ă͔@���ł��傤���B�@�����Ƃ����ɗ��Ǝv���܂����E�E�E�B�@�ł����ꂪ���邾���̌������������ł���Ί��Ɏ��s����Ă��邱�Ƃł��傤�ˁB�@���炵�܂����Bm(_ _)m
�������̔錍�H
�����̌��N�s��
�����֔̕�����̕��@
���z�[���y�[�W�J�݂̔w�i
�댯�Ȕ얞�̒����BMI���E�G�X�g�T�C�Y�Ɍ���� �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/med/leaf?CID=onair/medwave/tpic/294564�@
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/03/08�@�@�J�i�_Queen's��w�� Ian Janssen���炪American Journal of Clinical Nutrition��2004�N3���P�����ŕ������e�ɂ��A�������A�������ǁA���^�{���b�N�V���h���[���̗\�m���q�Ƃ��ẮABMI�������́i�E�G�X�g�T�C�Y�j�̕����D��Ă���Ƃ���Ƃ����B
2004/02/29�u�H���@�ۂ̐S���a�\�h���ʁv�߂���u�w�����̃��^���͌��ʂ܂Ƃ܂� �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/med/leaf?CID=onair/medwave/tpic/292987
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/02/27�@�@�S���a���������Ăł́A30�N�ȏ�O����S���a�̗\�h�ɖ𗧂H�������Ɋւ��錤��������ɍs���Ă���A���̒��̐H���@�ۂɊւ��Ă��A��K�͂ȃR�z�[�g�ǐՌ����������s���Ă���B���̂قǂ����̕����̌����f�[�^����ɓZ�߂����^���͌��ʂ��AArchives of Internal Medicine��2��23�����Ŕ��\���ꂽ�B
�@�����̌����f�[�^����ɂ܂Ƃ߂郁�^���͂́A���K�͂Ȍ����ł͍s��������f�[�^�̂���̕��A��̌X�������މ�͂��s��������@�B
�@���̌��ʁA�H���@�ۂ̐ێ�ʂ������l�قǐS������S�����ɂ�鎀�S�����Ȃ����Ƃ������B�P���ɐۂ�H���@�ۗʂ�10g�����邲�ƂɁA�S�����͑��ΓI��14���A�S��������27��������̂ŁA�j�����݂͂��Ȃ������B
�@�H���@�ۂɂ̓y�N�`���Ȃljn���̂��̂ƃZ�����[�X�ȂǕs�n���̂��̂����邪�A�n���̐H���@�ۂ͏�������̓��E�����z����W���邱�ƂŁA���A�a�⍂�����ǂ̗\�h�ɖ𗧂Ƃ���Ă���A����̕��͂ł��A�n���̐H���@�ۂ̕����A�S������S�������̗\�h���ʂ��傫���Ƃ̌��ʂɂȂ����B���̒��ŁA�����[�����ʂ́A�ʕ��⍒���R���̐H���@�ۂ͐S������S�����������炷���A��ؗR���̐H���@�ۂɂ͌��ʂ��Ȃ��Ƃ����B�d���̒n��ł͐S�����삪���Ȃ��|�|�t�B�������h�@
�@�t�B�������h�n���������̃A���l�E�R�E�T���m�́A�t�B �������h�ł͒n�����ĐS������̕p�x������Ă��āA���̓����ɏZ��ł���l�́A�����A���̑��̒n��̐l��� ���A�S�����씭���̊������������ƂɋC�Â��A35�`�V�S�܂�18946�l�̏Z�l��3�N�ԒǐՒ����������ʁA����ł��鐅�̍d�x�������قǁA�S������̃��X�N���Ⴍ�A�����ȑ��֊W�����邱�Ƃ��������B�܂��t�b�f���܂މ������������قǁA�S�����삪���Ȃ������Ƃ����B���̎��b�������_�@�\�̒ቺ��h�~�@
�@�@http://health.nikkei.co.jp/hsn/news.cfm?i=20040208hj001hj
�@�@�@�@�@NikkeiNet �����������N�@�č����j���[�X�@2004/01/30�@�č��_�o�w��uNeurology�v1��26�����f�ڂ̃��g���q�g��w��ÃZ���^�[�ɂ�錤���ɂ��A�T�o�A�T�P�A�j�V���Ȃǎ��b���̖L�x�ȋ��Ɛ��_�I�ȏ_��A�q�����A�S�̓I�ȋ@�\�Ƃ̊֘A�����m�F����A�H���ɂ�����I���K�\�R�����s�O�a���b�_�̖L�x�ȐH�i����ю��b���̖L�x�ȋ��̐ێ�ʂ������l�́A�]�@�\����ѕq�����̒ቺ���X�N�����Ȃ��Ƃ����B
2004/02/22�H�����̍R�_�������Q�^���A�a��\�h�A�t�B�������h�̒����ǐՌ��������� �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/med/leaf?CID=onair/medwave/tpic/291795
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/02/20�@�@Diabetes Care��2�����Ŕ��\���ꂽ�t�B�������h�ōs��ꂽ�����N�̒j��4300�l��23�N�Ԃ̒����ǐՂ��������ɂ��A�r�^�~��E����N���v�g�L�T���`���Ȃǂ̍R�_������H������\���ɐێ悵�Ă� ��l�ł́A�Q�^���A�a�̔��Ǘ����Ⴂ���Ƃ����������Ƃ����B�H���ێ�͂P�����5.8g�Ɂ|�|�ĉȊw�A�J�f�~�[�@
�@�Q��11���A�č����Ȋw�A�J�f�~�[�i�m�`�r�j���甭�\���ꂽ�K�C�h���C���ɂ��A�č����͉��������߂��Ă���A�H���ێ�͌��N�Ȑl�ł��A�P���ō���5.8���ȉ��ɗ}����悤�ɂ��ׂ��Ƃ��B
2004/02/08�������5�M���i350g�j�Ɖʕ�200g���`�u��t�H�[�����v�J�� �@
�@�@http://www.health-station.com/n37.html
�@�@�@�@�@Health Net Media�@News & Topics 2003/12/01�@12��1���A�����z�[���i�����s�`��j�Łu�������5�M���i350g�j�Ɖʕ�200g���v���e�[�}�ɁA�u��t�H�[�����v���J�Â���A���̃��|�[�g�L�������Љ�����܂��B��1�l������̖�؏���ʁA���Ăŋt�]
�@���{�l��1�l������̖�̏���ʂ��������Ă���A����7�N�������ɕč���艺���悤�ɂȂ����B�����ȁu�ƌv�����v�ɂ��A���N��̍w���ʂ́A15�N�ԂŖ�5���������Ă���Ƃ����B
�@���Ɏ�N�w�̊ԂŒ��������A�����ȐH�ו��̏��10�i �ڂ̂���8�i�ڂ͖����߁A1���̖ڕW�ێ�ʂ�350g�ɂ��B���Ă��Ȃ��ɂ��W��炸�A�����ɂ���7���̐l�X������\���ɐۂ��Ă���ƔF�����Ă���Ƃ���������B
�@����ɕt�����邩�̂悤�ȁA���N����ƂȂ�A�����[���t�]���ۂ����Ă̎q�������̊ԂŋN���Ă���Ƃ����B����A�����_�f�̏d�v�Ȑ���Ɋւ��
�@�@�Ȃ���̐ێ悪�K�v�Ȃ̂�-----�B
��́A�����_�f����B�_�f��������邱�ƂŐ����Ă��邪�A���̊����_�f���ߏ�ɔ�������ƁA�g�̂������A�V���⓮���d���A����Ȃǂ̊e�펾���������N���������ƂȂ�B���̂��߁A��͊����_�f�̏d�v�Ȑ���Ɋւ���Ă���B
�@�A���͎��O���𗁂ѕ���Ȃ��߁A�A���͓�����芈���_�f��h�䂷��V�X�e���B�����Ă���A�����_�f�̊Q���玩�g����邽�߂ɁA����ɑR����r�^�~����R�_�������𑽂��L���Ă���B��90�N��ɓ���A�č��Ŗ�E�ʕ��̐ێ摝��ڎw�����u5 A DAY�v�^���W�J
�@�R�_�������𑽂��܂݁A���N�Ǘ��ɏd�v�Ȗ������ʂ�����̐ێ�ʂ������X���ɂ���̂͗J�����ׂ����Ԃ��B �č���'90�N��ɃK���̍������߂ɁA�č����K���������𒆐S�ɁA���N�ێ��̂��߂ɖ�E�ʕ��̐ێ摝��ڎw���u5 A DAY�v�Ƃ������ʕ���1�� ��5�M���ȏ�ۂ邱�Ƃ�ڎw�����^����W�J�������Ƃ��A����7�N�����A��̏���ʂ̋t�]���ۂ����ĊԂŐ������B
�����Ẵe�B�[���G�C�W���[�̃R���X�e���[���l���t�]
�@�u5 A DAY�v�^���ɂ��A��̏���ʂœ��ĊԂ̋t�]���ۂ��N���������A������A��N�w�̃R���X�e���[���l�̋t�]���ۂ����炩�ɂȂ��Ă����B'90�N�ォ��̐H�������P�^���Ƃ�������u5 A DAY�v�v���O�����ŁA���ʕ��ɉ����A���ނ�H���@�ۂ̏d�v���ȂǁA�H�����S�ʂ̌�����������ꂽ�B
�@���b�̉ߏ�ێ���T���A������H���@�ۂ̑����V���A���i�t���[�N�j�H�i�𑽂��ۂ邱�Ƃ���������A14�A5�N�قǑO����V���A���H�i���A�����J�l�̒��H�̔����ȏ���߂�悤�ɂȂ������Ƃɂ��A�R���X�e���[���l�ɂ��Ă����{�̎�N�w�̂ق��������Ƃ����悤�ȌX�����݂���悤�ɂȂ��Ă������B�������_�f���R���X�e���[���ƌ��т��ĉߎ_���������Y�����A���܂��܂Ȏ����������N����
�@���́A�R���X�e���[���̎��ŁA�ނ���R���X�e���[���S�̂ł͏��Ȃ����Ă��ǂ��Ȃ��B ���ǂɗ��܂�ꕔ��LDL�i���ʁj�R���X�e���[�������ŁA�ނ���HDL�i�P�ʁj�R���X�e���[���͑����ق����ǂ��B
�@LDL�i���ʁj�R���X�e���[���������_�f�ƌ��т��Ǝ_��LDL�R���X�e���[���ɂȂ�A���Ǖǂ��j��₷���Ȃ�A������������Ȃǂ̏�Q��������B�X�Ɋ����_�f�͂��������R���X�e���[���ƌ������ĉߎ_���������Y�����A�זE�������A���܂��܂Ȏ����������N�����B����N���{�ł��A�u5 A DAY�v���O�����v�Q�l�ɖ�E�ʕ��̏���[�������s������c�̐ݗ�
�@���{�ł��A�ߔN�̎�N�w�̖�ؗ�����뜜���A�č��́u5 A DAY�v���O�����v�ɏK���A��N7�� �Ƀt�@�C�u�E�A�E�f�C����ݗ����ꂽ�B�܂���w�A�h�{�w���̊w���o���ғ��𒆐S�Ƃ����u��ؓ����N�H�������c��v���ݗ�����A��E�ʕ��̏���[�������ɖ{�i�I�ɏ��o�����B
�@���N�A�u��͂�����ǂ��܂ŗ\�h�ł��邩�v���e�[�}�ɁA�u��t�H�[����2001 ����Ɩ�v���J�Â���āA���E�̑�\�I�ȉu�w����������������ꂽ�B
���d�q�����W�⒲���ߒ��ŁA��Ɋ܂܂��R�_������������
�@���ʕ��̎��a�\�h�@�\�́A�܂܂��R�_�������̊����_�f�}���ɂ��Ƃ��낪�傫���B�������d�q�����W�⒲���ߒ��ɂ�����R�_�������̑����ł���B
�@�X�y�C���ōs��ꂽ�����ł́A�u���b�R���[��d�q�����W�ɂ�����Ɗ܂܂��R�_�������̃t���{�m�C�h��97�������邱�Ƃ��킩�����Ƃ����iJournal of the Science of Food and Agriculture'03/11�����j�B
�@�d�q�����W�����łȂ��A�ʏ�̒����ߒ��ł��A�t���{�m�C�h��60���قǔj���B�܂��A�h�{�����͔M�Ɏキ�A���������Ƃł��R�_��������20�`30����������B
�@�r�^�~��C��30���قǎ�����B�������ߔN�n�E�X�͔|�ɂ���̃r�^�~��C�ܗL���I�n���Ɣ���Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ�����������B ���̑��A�_��Ȃlj��w�엿��E���܂̎g�p�ŁA�t���{�m�C�h�����Ȃ葹������B�X�ɔ_��Ȃǂ̉��w�엿�́A�̓��ɓ����āA�����_�f��]�v���₵���˂Ȃ��Ƃ������Ƃ����O�Ă���B
�@���̋L���̓`����Ƃ���́A�����K���a�̗��ɂ͊����_�f�̑��傪���邪�A���̊����_�f�̉e�����ɗ͗}���邽�߂ɂ͖�؉ʕ�����R�H�ׂ�K�v������B�@�ŋ߂̃n�E�X�͔|���ꂽ��؉ʕ��́A�̂����h�{�����Ⴍ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ�A�����̉��M�ɂ��܊p�̃t���{�m�C�h�i�A�����y�f�j���j������c���_�̖����Ă��A�����_�f��͔��ɏd�v�ł���Ƃ������Ƃ��ĔF������K�v������悤���B�@���̂悤�Ȓ��ŁA���_�����ۂ��ƕ��������A�M�H�����o�Ȃ��������@�����u��؉ʕ��ۂ��ƐH�i�v�ł���u�t���b�V�F�����A�v�Ƃ����T�v�������g��I�肵�����̌��N����܂�ł͂Ȃ��Ǝv��������ł����B(^_^)v
�@����؉ʕ��ۂ��ƐH�i�E�u�t���b�V�F�����A�v�ɂ���
��Č��Y�̃J�C�A�|�C���A�Q�^���A�a�ւ́u�������ʁv���m�F �@
�@�@http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/med/leaf?CID=onair/medwave/tpic/288267
�@�@�@�@�@MedWave�E�g�s�b�N�X�@2004/01/30�@�@�č����A�a����iADA�j�̊w�p���ł���Diabetes Care���Q�����Ɍf�ڂ��ꂽ�I�[�X�g���AVienna��w��O���Ȃ�Bernhard Ludvik����̌����ɂ��A��Đ��܂�̔����T�c�}�C���i���Ï��j�Ƃ��Ēm����u�J�C�A�|�C���v���A�Q�^���A�a���҂̌����R���g���[�����A�����Ԃɂ킽����P���邱�Ƃ��킩�����B
�@�����錒�N�H�i���A�v���Z�{�ΏƎ����Ńw���O���r��A1c�iHbA1c�j�l�̉��P���ʂ𗧏����̂͏��߂āB����́A����K�́E�����Ԃ̎����ŁA�����I�Ȍ��ʂ���S���ɂ��ĕ]�����������B
2004/02/02���邩����Ȃ����͈ӎu�����A������̗ʁ@�@
�ăC���m�C��w�̃u���C�A���E�E�H���V���N���m��̌����ɂ��ƁA �u�l�Ԃ́A�������ꂽ���͓̂r���ŐH�ׂ�̂���߂�ꂸ�A�������������ƌ��ʓI�ɑ����H�ׂĂ��܂��v�Ƃ������Ƃ��A�{�E���ɓ��ꂽ�X�[�v��A�e��ɓ��ꂽ�|�b�v�R�[����H�ׂ������������ؖ������B
�@���̌������ʂ���A�얞������������ɂ́A�P��ɐ�����镪�ʂ����炷���Ƃ��Ƃ����u�L�_�f�\�́v�����قǁA���A�ɂȂ�ɂ���
�@�@http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news_i/20040120so13.htm
�@�@�@�@�@Yomiuri-Online�E��ÂƉ�� > �j���[�X �@2004/01/20�@�u�^���𑱂��Ă���Γ��A�a�ɂȂ�ɂ����v�Ƃ悭�����邪�A�����K�X���N�J���Z���^�[�̒����ł킩�����B �j���ł́A�̗̖͂ڈ��Ƃ����u�L�_�f�\�́v�i�_�f��̓��Ɏ�荞�ޔ\�́j�������قǁA���A�a�ɂȂ�댯���͒Ⴂ�X���ɂ��邱�Ƃ��킩�����B�T�J�i��H�ׂ�Ɓ\���S���X�N���@������Ȃǒ��������@
�@�@http://www.asahi.com/health/life/OSK200401190016.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/01/19�@ �����ȑ�̒����ۍK�������i�z����ȁj�炪�A80�N�ɋ������Ȃ����{���������h�{�����̑ΏێҖ�P���l�i30�`64�j�ɂ���99�N�܂ōs������K�͂Ȕ�r�����̌��ʂ��A�R�`�s�ŊJ�������{�u�w���22���ɔ��\�����B
���̓h�R�T�w�L�T�G���_�i�c�g�`�j��G�C�R�T�y���^�G���_�i�d�o�`�j�Ƃ������s�O�a���b�_�𑽂��܂݁A�����ɂ͓����d����h������������Ƃ���A�Q���ɂP��ȏ�Ƌ����悭�H�ׂ�j���ł́A�H�ׂ�̂��T�P���Ə��Ȃ��l�ɔ�ׂāA���S�̊댯�x���R���O�㌸�邱�Ƃ��A���炩�ɂȂ����B
�@���l�̒����́A�C�O�ł͊�����邪�A����̒������ʂŁA���������܂ސ����͌��N�ɗǂ�����������Ƃ���邪�A�����悭�H�ׂ邱�Ƃ��A���{�l�̒����̗��R�̈�ł��邱�Ƃ��͂����肵���Ƃ����B
�@�����ł͗L�ӂȍ��݂͂��Ȃ������̂́A���S�����j�����Ⴂ���߁B�����C���|�����Ɉ���ō��������P �@
�@�@http://www.asahi.com/health/life/TKY200401190101.html
�@�@�@�@�@Asahi.com�E���N�E���N�E���� 2004/01/19�@���|�𒆐S�Ɂu���ސ|�v�̐l�C����������A�|�ƌ��N�ɂ��Ẵ��|�[�g�L���B
�@���|�ɂ́A�l�X�Ȍ��N���ʂ��m�F����Ă���B�L���Ȃ̂����앐�F�E��B�喼�_�����i���N�Ȋw�j�炪�W�W�N�ɔ��\���������ŁA20cc/�����A�P�`�U�J���Ԉ��ނ��ƂŁA���t���̑��R���X�e���[���A �������b�A�������̌���������Ƃ������́B ����ɁA���������ł́A�����̏�Q��}�����p�����邱�Ƃ��킩�����Ƃ����B
���N���ʂɌl������A�|�̎�ނ�@�ɂ���ĈႢ�͂���̂��낤���H�@�|�ł���Ύ�ނɊW�Ȃ��A���҂������ʂ͓����Ȃ̂��H
�o�b�N�i���o�[�@No.6�i2003.12�`2003.01�j
�o�b�N�i���o�[�@No.5�i2002.12�`2002.01�j
�o�b�N�i���o�[�@No.4�i2001.12�`2001.01�j
�o�b�N�i���o�[�@No.3�i2000.12�`2000.01�j
�o�b�N�i���o�[�@No.2�i1999.12�`1999.01�j
�o�b�N�i���o�[�@No.1�i1998.12�`1998.01�j
| ����ʈꗗ�ɖ߂� |
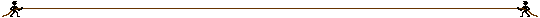
�bNews�b�H�i����b�n�N�֘A�b�����b�����bInfomation�bWhat's New�b
�b�����bHP�J�݂̖��bProfile�b�n�����bMy-Link�b
�b���Ȃ����N�I�s�V�̔錍�I�H�iHome�j�b
