| ●おうし座οξ |
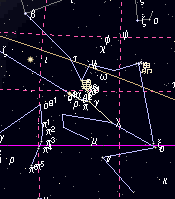 チョット気がついたのですが、おうし座ξ星とおうし座οの間に赤道が通っています。
これは紀元前約150年のことですね。
チョット気がついたのですが、おうし座ξ星とおうし座οの間に赤道が通っています。
これは紀元前約150年のことですね。去極度で年代を割り出したら紀元前65年になったと言いますので、 この方法でやってみましょうか。計算はメンドクサイので(^^;)大雑把の簡単のズルッコで、 ステラナビの視赤径と計測カーソルを使ってみます。 選んだ星は距星といって、星宿の中心となる星を使ったそうですが、 人の言うことを聞かないのが趣味な私は、まずはグレて一等星を使ってみましょう(^^; |
| キトラ古墳3・赤道 |
| ●おうし座οξ |
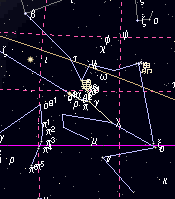 チョット気がついたのですが、おうし座ξ星とおうし座οの間に赤道が通っています。
これは紀元前約150年のことですね。
チョット気がついたのですが、おうし座ξ星とおうし座οの間に赤道が通っています。
これは紀元前約150年のことですね。去極度で年代を割り出したら紀元前65年になったと言いますので、 この方法でやってみましょうか。計算はメンドクサイので(^^;)大雑把の簡単のズルッコで、 ステラナビの視赤径と計測カーソルを使ってみます。 選んだ星は距星といって、星宿の中心となる星を使ったそうですが、 人の言うことを聞かないのが趣味な私は、まずはグレて一等星を使ってみましょう(^^; |
学術報告書って割には、小さくてボケボケでサッパリわからん(^^;
ま!取り敢えず3つ解かったのでやって見ますか。
名前 計算視赤径 ステラので該当年代 ベテルギウス 4.7cm*(180/9.83)=86.063 BC200 シリウス 5.35cm*(180/9.85)=97.7664 BC600 アルデバラン 4.4cm*(180/9.85)=80.40609 BC40 えっと、まず、学術報告書の写真で中心(北極)からの長さを測って、該当星と中心とを結ぶ 赤道の直径を計り、計算した角度を、ほぼ何年台になるかソフトで計算したものですので、 大分誤差があるでしょう。
平均を求めると(200+600+40)/3でBC286年となります。やはり相当な誤差がありますね。 明かに違う星を除いて、なるべく数が多いほうが誤差が少なくなりますね。
写真が小さくてボケボケじゃなきゃな〜(^^;
と、気張ろうと思ったのですが、こりゃ〜大変です。例えばどうやっても北斗七星が キトラの位置には決してあるはずがない(^^;オマケに西暦2800年の位置にある星もある。これじゃ、どの星を使うかで結果がまるで 違ってしまいますね。ま、ま、どんでもないのを覗いて(^^;取り敢えず結果を。
星座 名前 計算視赤径 ステラので該当年代 オリオン ベテルギウス 4.7cm*(180/9.83)=86.063 BC200 オリオン 三ツ星左 5.4cm*(180/9.83)=98.68 BC700 おおいぬ シリウス 5.35cm*(180/9.85)=97.7664 BC600 おうし アルデバラン 4.4cm*(180/9.85)=80.40609 BC40 おうし γ星 4.32cm*(180/9.9)=78.55 BC410 おうし λ星 4.60cm*(180/9.9)=83.64 BC350 ペガサス α星 3.35cm*(180/9.85)=65.51 BC850 ペガサス β星 4.60cm*(180/9.85)=84.06 BC850 かに γ星 2.95cm*(180/9.85)=53.90 BC100 かに δ星 3.13cm*(180/9.85)=57.20 BC280 うみへび GSC6050.1449星 5.23cm*(180/9.9)=98.18 BC150 平均はBC411.82年。まあこのようなものは単純平均をとっても平均値としては使えないのですが、 一応の目安となりますね。何もしないとBC350年になったそうですから目分量の嵐作戦としては(^^; 良い結果かもしれませんね。
「どうやら北極の位置がずれていたらしい」とは、この事なのでしょう。 BC411年にしても、BC350年にしても歴史から見て、観測日時が古すぎますね。
結局は このやり方とは逆に、どこに北極を持ってきたら一番つじつまが合うかを算出して、 その北極位置と年代を比べれば推定年代はでそうですね。
う〜ん。報告書にはなんで計算過程が出ていなんだろう???
観測年代が古いのは別の原因があかも知れません。漢書律暦志の二十八宿の位置は 赤経の基準が−130年のものより-450年の赤経・黄経に近いものが多い事です。 -450年の牛宿の初点(やぎ座β)が、冬至点(α、λとも270度)にあった事が注意点でしょう。 暦の原点に−450年が置かれていた可能性がありますから「平均BC411.82年」は、 案外悪い数値ではないのかもしれません。