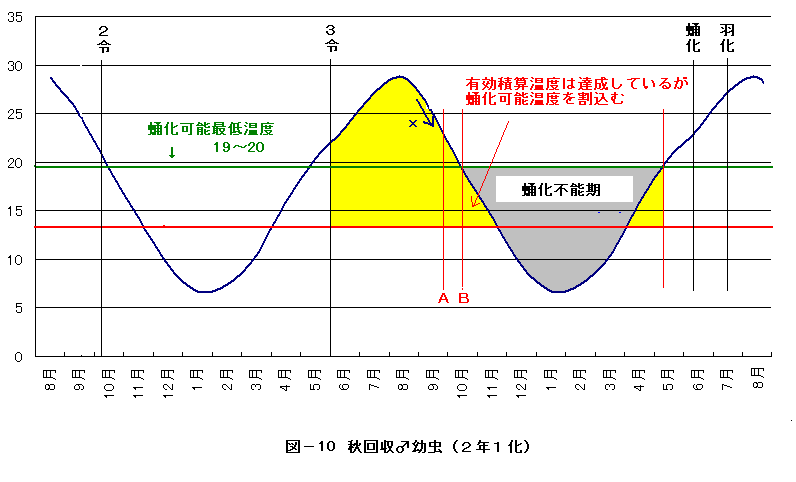2年1化のパターンさて、通常の室内飼育(空調なし)で、♂が2年1化となるのは、晩秋に若令幼虫で回収したもの だけです。この場合を検討しましょう。<図−10>
これが一番興味のある変態パターンです。図で示したA点付近で既に有効積算温度55度・月を達成していますが、通常、幼虫は蛹となりません。 ここで第2の条件「環境温度が摂氏19度以下では蛹化できない」が生きてくるのです。 また、まだ19度以上あるA点で蛹化しないのは、幼虫に温度変化の先行きを読む能力があり、図中の温度勾配xを感知して、蛹となるときに19度を下回らない様にコントロールしているのだと思います。 過去、筆者は1年を通して温度が約19度で一定している勤務先の地下2階のロッカー室を用い、飼育実験を行いました。実験の当初の目的は、出来るだけ夏場を低温で過ごさせて温度の積算を押さえることでした。実験材料として終令幼虫を使用したのですが、意外なことに、この温度では2年以上の長期に渡って、これらの終令幼虫は蛹化が出来なかったのです。また、体色は黄色となって成熟が進み老熟幼虫となりましたが大型幼虫とはならなかったのです。 このことから、三つのことがわかります。まずひとつは、第2の条件「環境温度が摂氏19度以下では蛹化できない」ということです。では、この蛹化できない上限の温度は何度でしょうか?1度刻みの飼育環境を整えることができないため確実な温度は不明ですが、小島啓史さんとの対話では、小島氏は20度ではないかと考えているようです。
これらの蛹化できない幼虫はその後25度の環境に移しましたがしばらくして蛹化、羽化しました。
|