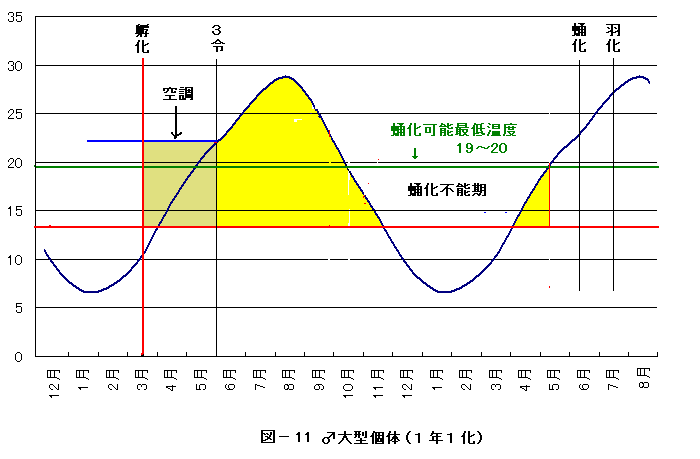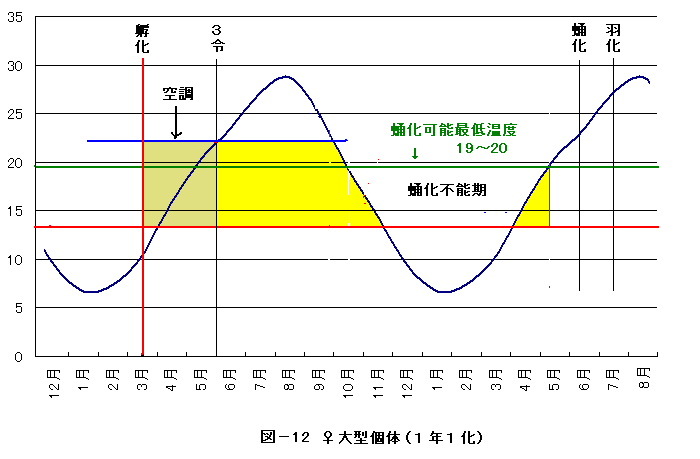変態パターンと成虫の大きさ
次に、変態パターンによる成虫の大きさについて検討します。 初夏回収1年1化の♂をA
<図−5>
初夏回収1年1化の♀をa
<図−7> 成虫の大きさは ♂の場合 C≧A>B ♀の場合 a>b≧c ♂のCとAの間には、それほどの差があるわけではないですが、Bとの間にはかなりの差が存在します。♀でもaとbの隔たりは大きく、これらのことから、終令で低温期を経験する前に相当の体重の蓄積がなければ、大型成虫にはなりにくいという仕組みがあるものと私は考えています。
では、この仕組みはどんなものでしょう? ♀ではcが小型個体となることも、この仕組みにあるのでしょう。終令幼虫は高温期に育ち越冬しないため、熟成に必要な時間が取れないことが小型個体になる理由だと考えます。 大きな成虫の育て方ここでは、温度変化にだけ注目して、出来るだけ短期間で大型成虫を羽化させるにはどうしたら良いかを考えてみましょう。先ほどまで述べてきたポイントをオスメス別まとめると ♂ ♀ 更に、できるだけ人の生活環境で飼育する(温室など極端な加温などはしない)という前提で考えると、♂では<図−11>のようなパターンが考えられます。これは2年1化モデル<図−10>をベースにしています。
次に♀ですが、上記の♂とおなじ変態パターンを辿れば45mm以上の大型となります。そのためには夏を比較的涼しい環境で過ごさせて積算温度の達成を遅らせる必要があります。これを<図−12>に示します。
考える楽しみ以上、オオクワガタの変態サイクルと積算温度の関係および個体の大きさについての、私のささやかな考え方を披露しました。 餌、いわゆる「マット」の質などについては意図して触れていません。これらを考え始めると複雑になりすぎて纏まらなくなるからです。ただ、乾燥気味の餌だと幼虫期間が長くなることは経験しています。元々私は考えるのは好きですが努力するのは大嫌いな性分です。データを取ることを目的に多数を飼育するようなことも楽しくないので嫌いです。(^^; 今後、餌による違いなどを追求しようとも思ってません。これ以上の研究は学究肌の方にお任せしたいと思ってます。さらに「材飼育」についてはほとんど経験がありませんので、材飼育での違いなどがあれば、それはその道の達人にお願いしたいと思ってます。 今回の積算温度のLOGICは月刊むし245号(Jul.1991)の「クロオオムラサキの越冬幼虫について」を読んでいるときに思い付いたものです。 この記事は、最近クワガタ標本がよく入ってくる中国四川省都江堰市(ドウジャンエン)産のクロオオムラサキについての研究ですが、日本産のオオムラサキと比較した内容で、偶々、四川省成都と東京の月別平均気温、平均湿度、平均降水量の表が載っていました。これとオオクワガタの飼育経過を重ねたとき、閃いたものです。 昆虫を飼育繁殖させるのは奥深く楽しいものです。産卵木を割って小さな幼虫を取り出すとき、蛹化、羽化を観察するとき、日常ではなかなか味わえない喜びがあります。そのなかで「なんでやろ?」と思うことが多々あると思います。その疑問が即座に解決するとは限りませんが、そのままにしないで考えてみることは昆虫の採集や飼育の楽しみ喜びを倍加させてくれることでしょう。 参考文献 |