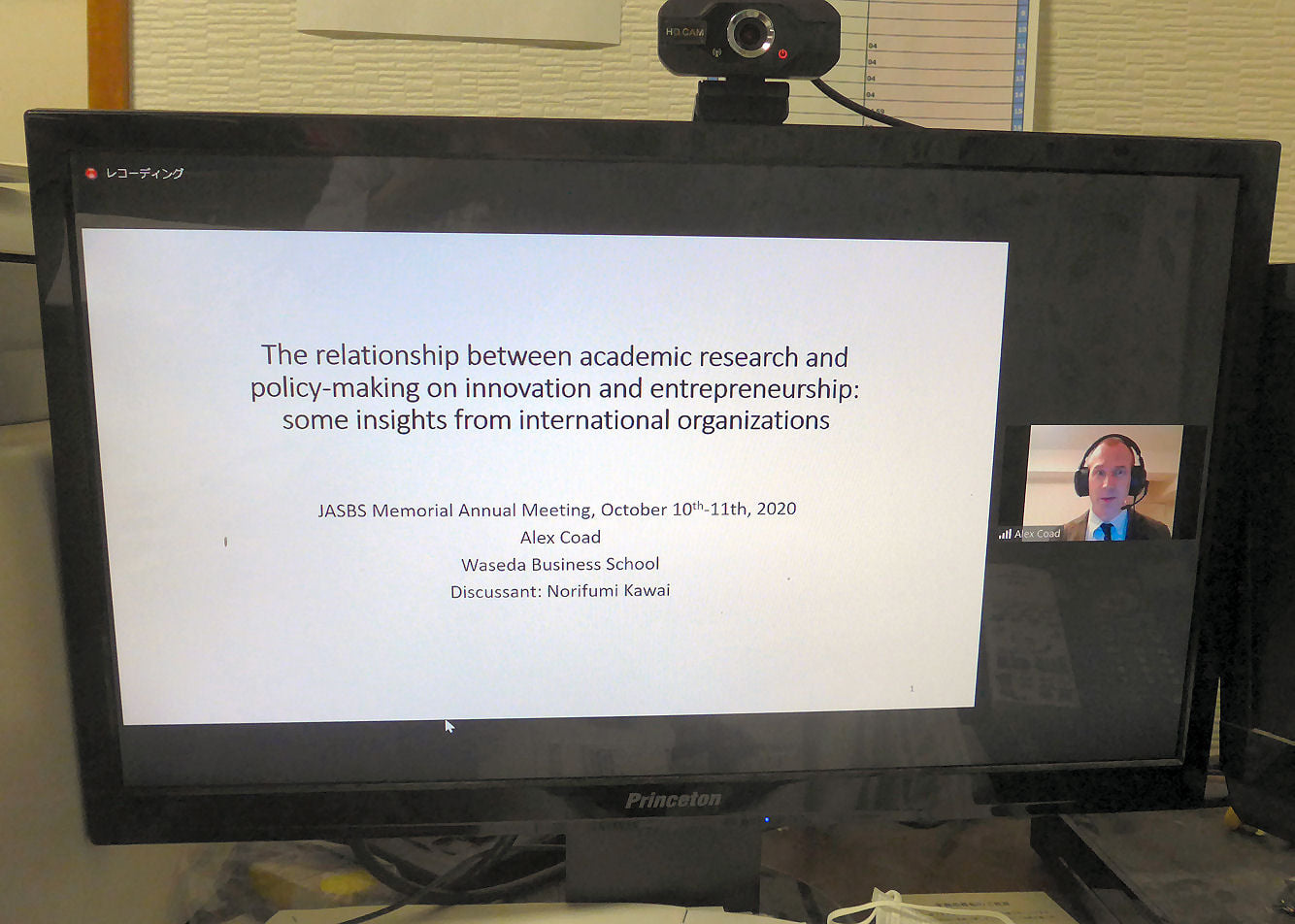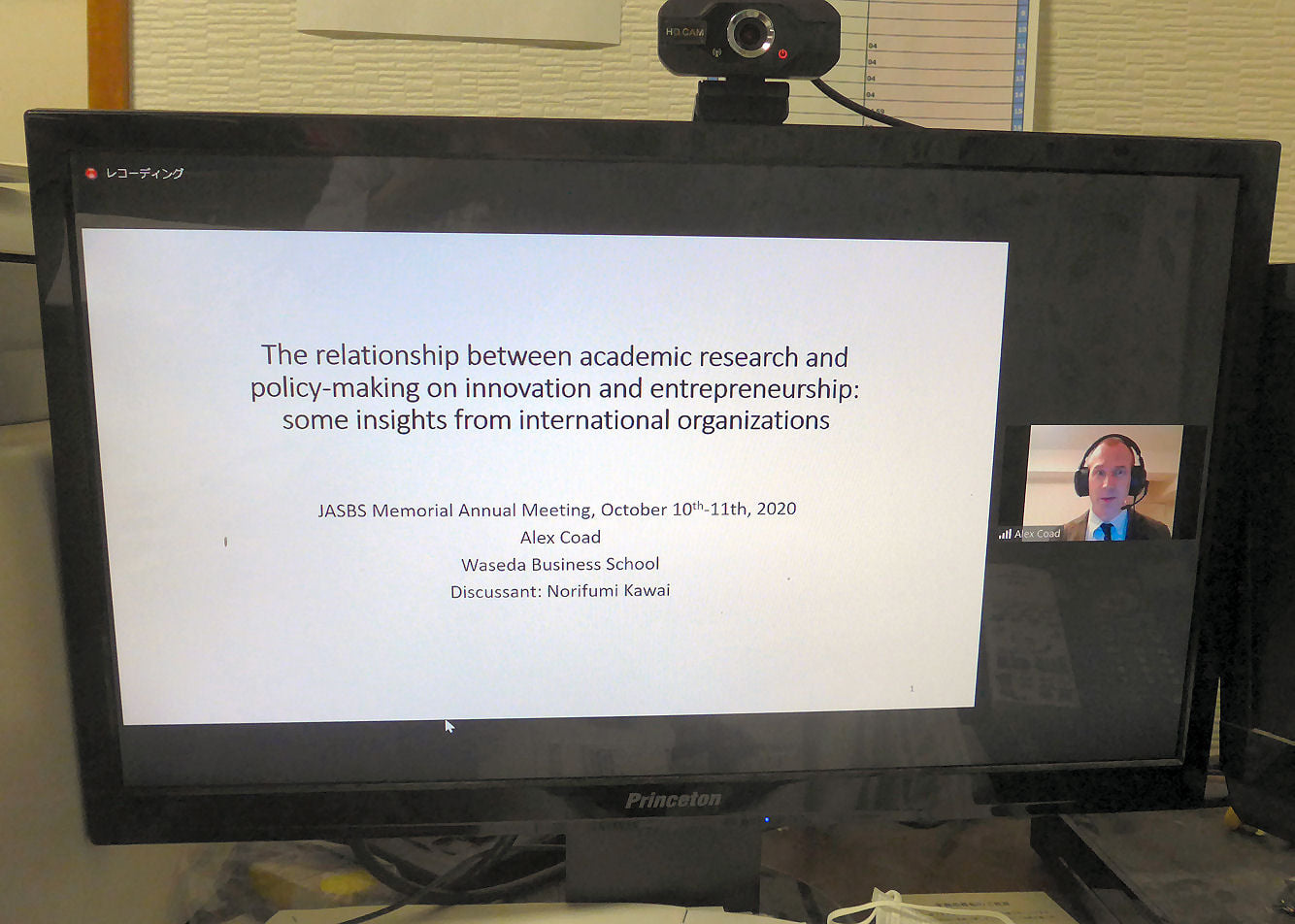idle talk57
三井の、なんのたしにもならないお話 その五十七(2020.10オリジナル作成)
日本中小企業学会の四〇年
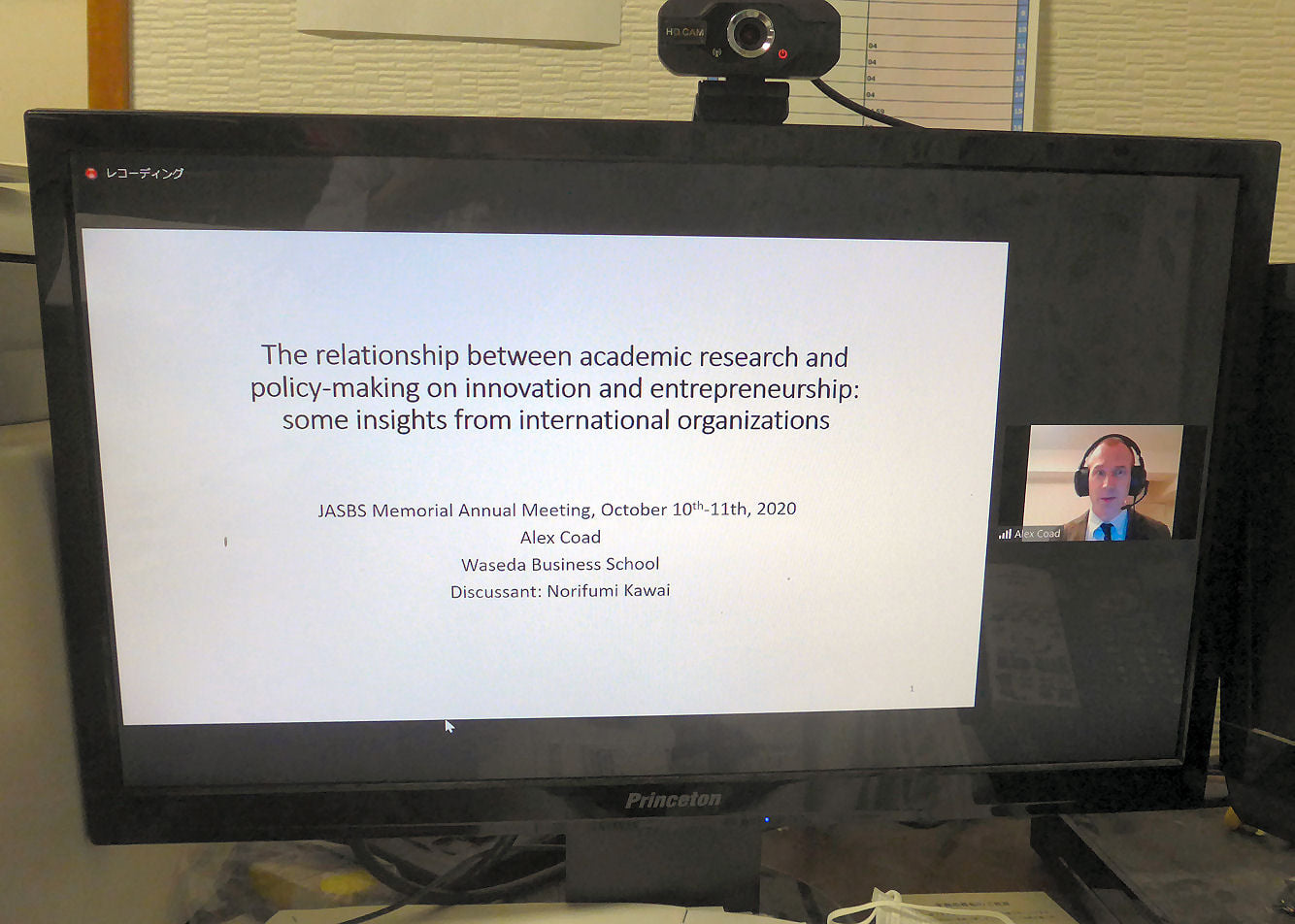
日本中小企業学会第40回全国大会(2020年10月10・11日)が、無事終わって「しまいました」。
先に、2002年から2019年まで、一挙10数年の学会の「歴史」と、わが歩みを継続的に
書き記しました。その掉尾は、2019年秋に学会役員を降り、次世代にバトンタッチするところでした。
けれども2020年秋、全世界のパンデミックという空前の状況の下で、「リモート大会」というはじめての形のうえに、開催直前に、学会の柱・顔である佐竹隆幸会長が急逝されるという、誠に大変な状況下でしたが、学会第40回全国大会がなんとか無事終わったという以上に、節目の年にふさわしいものになったと実感を致します。これもひとえに、堀潔大会プログラム委員長(副会長)、長山宗広準備委員長はじめ、関係者の皆さんの大変なご努力あってのことと、あらためて感謝の思いでいっぱいです。準備委員会にはこのほか、吉田健太郎、山本篤民氏ら、私のもとから研究者の道に歩んだ人たちが少なからず貢献しておられました。誠にありがたいことです。
大会のプログラムは、例年通りの自由論題研究発表多数の他に、統一論題がもう一つの柱をなしていましたが、今回は「中小企業研究の継承と発展 −日本中小企業学会40年関の軌跡」と題し、いわば研究史を振り返る形の企画が設定されました。もちろん、これは私を含め、ロートル組・「過去完了組」の横車でも何でもなく、あくまで、佐竹会長はじめ、学会現役員と今次大会プログラム委員会のご意向、企画であると理解しております。ただ、実際には、かつて学会会長、副会長を務められた諸氏、港徹雄、渡辺幸男、足立文彦、黒瀬直宏、太田進一、二場邦彦の各氏が登壇し、それぞれの思うところを語るという形態になり、私個人的には、「うーんな」ところもありました。これらの諸氏の主張を闘わせ、論点を探るというものではなかったので、自由討論の中では若干そういった「議論らしい議論」になったところもありましたが、概しては、それぞれの積年の主張を語っておしまいとなった観は否めないところです。
これにはもちろん、リモート大会という形の制約もありました。スピーカーが一堂に会し、司会者のもとで大いにやりとりを交わすというわけではなく、みんなそれぞれ自宅などにいたわけです。利点として、「帰りの足の便など気にする」ことなく、予定の時間を延長し、討論セッションに移ることができたものの、これも3パートに分かれて、となってしまったので、議論に火花散らす、とは行かなかった印象です。
私自身が参加した第一パートでは、渡辺幸男、港徹雄という、以前からの論客が並んでいたので、議論としてはそれなりに盛り上がり、過去・現在・未来に及ぶ闊達な議論が、それぞれの違いを示す形で展開され、それはそれなりに面白いものであったという印象です。でも、それは参加者全体で共有され、理解されたわけではないのが残念なところでした。また、1時間の討論時間も不足の感がありました。本来司会の役を務められたはずの佐竹会長がおられたら、どのような展開をリードされたのでしょうか。
さて、私自身は元会長ながらこの統一論題に参加するのではなく、第一日の「国際交流セッション」の中で、しゃべることになってしまったのです。これには若干込み入った事情があり、もちろん私自身がしゃしゃり出ようという意図など毛頭ありませんでした。
その辺を暴露してしまうと、もともと、大会準備委員会は国際交流の一環として、英国の研究者Robert Blackburnを招聘したいという意向を持ち、私が橋渡しを頼まれたのです。彼は記しましたように、2002年の第22回全国大会に招いておりますが、それから20年近くを経て、現在の中小企業研究などを語って貰うというねらいでした。
それで、早速に彼の快諾を得たものの、その後の世界的な新型コロナ禍、大混乱です。英国から来て貰うこと自体困難となり、やむなくお断りをせねばならなくなりました。けれどもさらには、日本国内での大規模な会合などが開催困難になり、「リモート開催」という形にならざるを得なくなったわけです。
リモート開催となれば、彼に英国から参加して貰うこともできたんじゃないのなどとも思いますが、ともかく成り行きで、プログラムを組み替えざるを得なくなりました。そしてプログラム委員会の出した新企画は、海外ゲストとして、在日中の研究者Alexander Coad氏(早稲田大学)を招聘する、そのほかに中小企業研究と政策の懐古的な内容を盛り込む、と言うものになったらしいのです。「らしい」というのは、もちろん私は企画者ではないので、詳しい経緯や議論はうかがい知るところではありません。
この「国際交流セッション」は、信金中金がスポンサーとなり、海外ゲストの招聘の費用を負担して貰う形で続いてきた企画なので、そこに私などがしゃしゃり出たのでは、お門違いも甚だしいことになります。その辺はおそらく、第20回大会や30回大会などで持たれたような、節目の記念企画と、国際交流とをセットにしようという結論に至ったのではないかと想像をします。第20回では小川英次元会長。第30回では渡辺幸男元会長がそれぞれ特別登壇をされておられましたから。
で、いったん確定されたプログラムでは、40回大会にふさわしく、この機会に、一方では2010年の日本版「中小企業憲章」閣議決定の立役者であった、長谷川榮一元中小企業庁長官と、その研究会メンバーの一人であった私とが並び、「中小企業憲章」と中小企業政策、研究の過去を語り合うような設定になったようです。長谷川氏は乗り気であったらしいのですが、大会前に首相交代、内閣改造という事態が生じ、首相官邸の幹部の一人であった長谷川氏の退任という、また大きな変化が生じてしまいました、それで最終的には、中小企業庁の関口訓央調査室長がビデオ出演し、最新の『中小企業白書』及び政策動向を説明するという、いささか無難な形に落ち着きました。私自身にはいろいろ勉強になったのは間違いないので、中小企業庁も今後の政策の目指すべきところに悩んでいる感がうかがえたのですが。
さて、それで私です。結局「中小企業研究と中小企業政策の展開 −日本と世界の視点から」という論題枠組みを頂いたので、なんとかそれに即する形で、「『世界の中の日本中小企業』(研究)の半世紀を考える」という、大胆不敵と言うべきか、身の程知らずな大風呂敷を広げました。これは実は、1989年の第9回全国大会(慶應義塾大学)の主題から頂いたものです。当時の、世界的な中小企業をめぐる議論、研究、政策等の盛り上がりを反映し、佐藤芳雄準備委員長のもとで、大胆に掲げられた主題でした。私にも、その前、1986-87年の在外研究の機会において、この流れを肌身に感じてきたところでした。そしてこの大会において、「最近のEC諸国における『中小企業政策』の展開」と題する研究報告を行い、翌年刊の『日本中小企業学会論集』第9集に掲載されております。
以来すでに30年、世界の流れはどのようであり、これに対する日本の位相はどうであったのか、そもそも「中小企業」という存在を見る視点、問題意識、さまざまな主張や研究方法の背景理論や枠組み、含意、そしてこれらを踏まえての政策や経営のありかたに対する提言、議論、そうしたものをどのように整理し、理解するかを、私なりに解く意図でした。限られた時間内でこういった大それた主題を扱うのは無茶承知のことでしたが、個人的には、これまでの自分の講義「中小企業論」「中小企業政策論」などの中で取り上げ、論じてきたものを踏まえるのであり、それゆえ「ネタ」は豊富に手元にありました。
そのせいか、私のpptを利用してのプレゼンは概ね好評であったようです。「なぜ中小企業(研究)なのか」、「それはどのような意義と必要性を持っているのか」、これを日本と諸外国の比較、その時間的変容と関係変化を追うかたちで説く、というのは、中小企業研究に多年関わってこられた方々などには、理解を得やすかったでしょう。さまざまな理論と研究方法、関心の変化を取り込みながら、です。
けれども、実は「本番用」に、別のpptを用意していたのです。字面だけのようなものをもっともらしく写すだけのプレゼンの限界も多々感じてきているので、私自身の体験中心にした画像をたくさん並べ、「受けねらい」で行こうと考えておりました。ところが、悪巧みの罰が当たったのか、いざ本番、私の出番となったら、私のPC上で起動していたこのビジュアル版のpptスライドを、zoom上で「画面共有」ができないのです。あらかじめのテストでは、長山さん設定下にうまく写ったのに、です。これは機械的トラブルというより、私の操作が間違っていたのかも知れません。
時間はどんどん過ぎる、焦っているとき、司会の岡室教授(前学会会長)が、「こちらで写しましょうか」と言ってくれました。公式pptファイルを事前に送っておいたので、備えがあったわけです。このバックアップを頼り、以後各コマを岡室教授に送って貰いながら、私が画面に向けスピーチをするという進行ができました。
このおかげで、まあかなりの時間の節約になったことも否定できないでしょう(それでもオーバータイムであったようですが)。まあ、画像ショーを繰り広げていたら、どれだけ時間を消費したことか。
正直、ねらいがはずれてしまい、個人的には残念な思いだったのですが、これは結果オーライと納得するしかないでしょう。また、これでもわかったのですが、このリモート開催ではpptなどのプレゼン材料を、かなりのスピードで送っていけるとわかりました。大きな会場や教室のスクリーンに投射している画面では、聴衆の皆さんに字面を追っていってもらえるのもかなりの面倒になりますが、それぞれの人の目の前のPCのスクリーン上なら、かなり素早く読んでもらえるものなのです。オンラインイベントも捨てたものでもないのでしょう。またその意味、プレゼン画面に文字ばっかしじゃあいかん、ビジュアル重視でいけという通常の実感的教訓も、少し違ってくるのかも知れません。
以下、簡単に私の用意したスピーチの項目のみ記します。
序 いま、世界の中での「中小企業存在」とは
−国連2017年総会決議と「中小・マイクロ企業の日」(MSMEDay)から
1 世界中で高まり広まる、中小企業をめぐる研究・議論と政策展開
2 戦後日本の中小企業研究と中小企業政策
3 1980年代以降の、世界的な研究と議論、新たな視点・方法・プラットフォーム
4 21世紀における到達点と課題はなにか
5 社会性・人間性と生態系を意識した研究と議論の可能性は?
さて、これで私めのお役目はおしまいとは行きませんで、開催直前に、第一日晩の「懇親会」の閉会挨拶をしてくれという依頼が来ました。まあ、こういうのは開催校の大先生とか、学会会長とかのお役目と思うのですが、リモート開催と言うこともあって、私にお鉢が回ってきたようです。
「なんで私に?」という問いにも理由がないことはないので、納得せざるを得ません。なにより、ちょうど20年前の第20回全国大会は同じ駒澤大学での開催であり、当時ここに勤務していた私は、実質的にその責任者でした(準備委員長は鈴木幸毅教授でしたが)。20回、40回という節目の年の巡り合わせは否定できません。この大会は前年の「中小企業基本法全面改正」を論じるものでもありました。しかしその翌年には駒澤大学を辞め、私は他に移ってしまったこと、以来はや20年が過ぎてしまったこと、今大会は私のもとから発っていった若いひとたちにになって貰っていることなど、こうした曰く因縁に言及し、学会の発展の軌跡と未来への期待を語り、急逝された佐竹会長への哀悼の思いを含め、私なりの「中締め」の言葉としたわけです。
まあ、正直にはバーチャルの「懇親会」というのもなにか隔靴掻痒どころか興ざめの感で、この機会での会話の相手を見つけるのも一苦労であり、主催側の大変なご苦労に比べ、かなりむなしい場であったのは否定できません。まさに、「ひととひととが交わり、対話交歓する」こと自体の真逆の状況なのですから。もちろん、「終了後、飲み直しと旧交を温めに二次会に行く」こともないわけですし、我が家の夕食直行です。
一年前の第39回全国大会(愛知学院大学名城公園校舎)の際には、私は司会の役も当たっていたのに、直前に体調を崩し、熱が出て行かれなくなってしまいました。この際には港、渡辺両元会長も欠席で、だいぶ物議を醸したようです。その「反動」で、今次大会では、私を含めたロートル連中が担ぎ出され、「まだ消えてないぞ」と示したようなどと申したら、年寄りの僻みもいいところで、せっかくの機会を設定くださった。現役員の皆さんに申し訳ないでしょうか。
おわりに、この記念大会のイベントとして用意された、さまざまな回顧資料の一環、各元会長のメッセージとして公開された、私の稿をそのまま添えておきます。
|
日本中小企業学会の40年に思う
第10期会長 三井逸友
日本中小企業学会の四十年の歴史にかかわってこられたことは、私の人生にとって大きな財産であり、誇りでもある。長い伝統を有する日本の中小企業研究を継承発展させる場としての学会の設立と活動展開にどれほどの貢献をなせたのかには自信はないが、その歴史とともにあったことは間違いない。
1980年の学会設立(慶大三田)の折りには私はまだ院生であり、「下働き」をしただけであった。以来、翌年の第一回大会での研究報告を始め、さまざまなかかわりを持ち、2007年から2010年には学会会長を務めることになった。学会と研究の伝統を築いてこられた諸先生方の名を汚すことのないように努めたつもりであるが、同時に時代の要請にこたえるべき課題にも取り組んだ。港徹雄、渡辺幸男会長時代に実現された、会則改正と査読制導入などの成果を踏まえ、「若手」の研究奨励、国際学会等での研究発表推進などがそれである。また、一方では研究と交流の機会の「地域化」として、北海道支部の基礎を築き、他方では国際組織との関係強化をすすめた。
後者に関しては、財政負担や参加機会の意義等から困難もあり、最終的には「JICSB中小企業研究国際協議会日本委員会」を、ICSBの支部組織として新たに設立するに至った。これらを含め、学会の活性化と役割強化にはいくばくかの貢献をなせたのではないかと考えるものの、他面支出の増加にもつながり、本来の使命たる学会の会員拡大と財政基盤強化は十分なしえず、のちの役員諸氏に宿題を残したのは心残りである。
初代会長山中篤太郎先生は、中小企業研究の活性化と発展に向け、「学会組織設立」、「研究レビュー刊行」、「研究奨励賞実施」という3つの柱を掲げられたという。「研究レビュー」に関しては、旧中小企業事業団中小企業研究所、のちの財団法人中小企業総合研究機構がこれを担ってこられ、これまでに四次にわたる刊行が行われ、私も第四次・2000年代版の編集代表を務めた。また、これには大阪経済大学中小企業・経営研究所から多大な貢献協力を頂戴している。「研究奨励賞」は、商工組合中央金庫、一般財団法人商工総合研究所が主催をしてこられ、すでに40年以上の歴史を重ねている。私も現在、審査委員の末席を汚している。
学会大会での国際交流セッションを支えてきて頂いている信金中金地域・中小企業研究所を始め、これらの諸機関諸団体のご協力あって、日本の中小企業研究は支えられてきた。そうした良き伝統が守られ、多様な視点・関心・対象・論理・方法・主張が中小企業に寄せられ、闊達な議論が高まり、研究のいっそうの発展が遂げられることを願ってやまない。 |
日本中小企業学会のwebサイトはこちら
第40回大会関連資料としても公開された、私の回顧録対談(『商工金融』誌掲載)はこちら
☆上記・学会大会報告「『世界の中の日本中小企業』(研究)の半世紀を考える」は、巻頭論文として、『日本中小企業学会論集』第40集(2021年・同友館刊)に掲載公刊予定です。
→ 2021年9月、刊行されました。
本書『日本中小企業学会論集第40号 中小企業研究の継承と発展』(同友館刊)の案内はこちら。
→ つぎへ