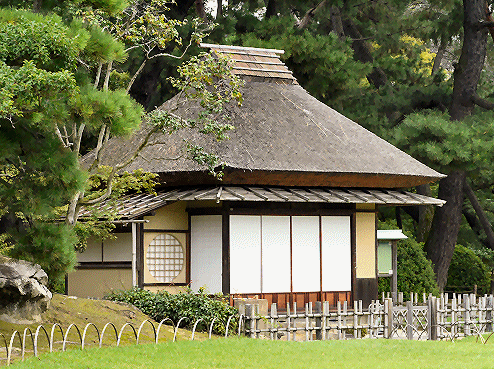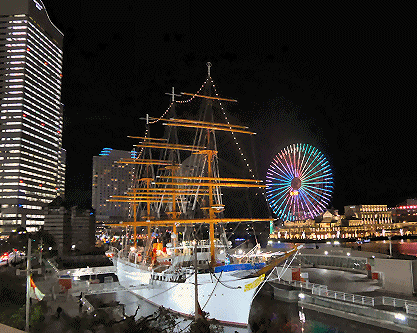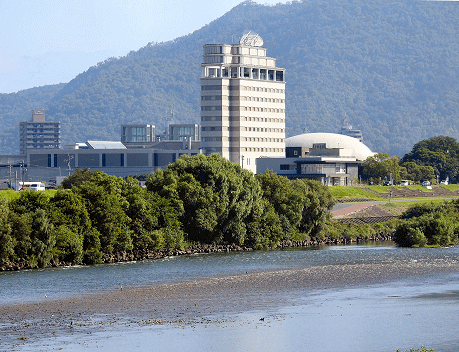これはいわゆる「高級コンデジ」ですが、2000年代に公費で買ったニコンP6000の後継機です。
いつも持ち歩き、簡単にしかし確実に撮れる「仕事で使うデジカメ」が主な位置づけで、私にとってこうした使い方は相当メインのデジカメの必要性そのものであり、この用途のものを何代かにわたって手にしてきたと考えています。キャノンIXY30、ニコンP50、ニコンP6000といったつながりでしょう。
公費で買える時代が終わり、すでに買ったのもお返しせねばならないので、ポケットマネーで後継機を買う必要があり、選んだのがこのキャノンG12でした。ニコンP6000のところで記したように、この機にはかなり満足できたものの、写りなどに不満が残ったうえ、後継機では図体ばかり大きく重くなり、しかもせっかく可動式になった液晶画面の動きがあまりに制約され、「新製品」として買う意味を見いだせなくなってしまいました。その後にはニコンが光学ファインダーを廃止、私の使い勝手からは完全に選択肢外になりました(最近また、EVFファインダー付を出していますが)。

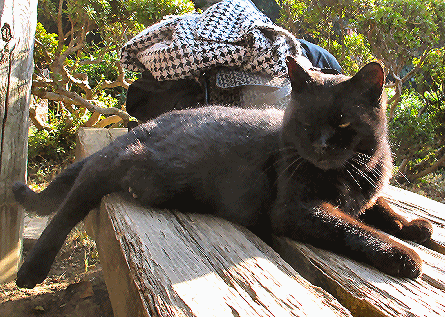
キャノンはこのシリーズをかなり前から出していたはずです。初代のPowershotG1は2000年に登場したとされます。基本的に、デジカメでも重量級で、特にストロボ用ホットシューを装備し、一眼レフなどと共通使用できることを特徴にしてきた模様です。いわゆる「サブカメラ」のポジションですな。また、はじめから液晶モニター画面の可動化を取り入れていました。
もっともG1は重さは420gもあったそうで、大きさこそ小振りでもとても「コンパクト」とは呼べません。以来、キャノンはこのGシリーズの改良新モデル発表を続け、私が手にしたG12にまで成長を遂げた次第です。そうした、明白な製品コンセプトを柱として息長く出される製品には、かなりの信頼が持てます。逆に言えば、デジカメを買おうという多くの方々はコンパクトさや操作の簡単さプラス見てくれの良さに惹かれそうなので、このキャノンGシリーズのようにちょっとごつくて、手にずっしり重く、操作するところもいろいろありそうなのは敬遠の対象になって不思議はありません。それでもシリーズが今に至るまで続いているのは、キャノンの確固としたポリシーと、このタイプを選ぶユーザー層の存在を示していたと考えられましょう。私もずっと横目で睨んできました。
それでG12は、SDカード使用、1/1.7型1000万画素CCD撮像素子、沈胴式のF2.8-F4.5/6.1-30.5mmズームレンズ(35mmで28-140mm相当)装備、重さは351gです。私は36,700円で買いました。手に取ると、多くのコンデジとは違い、厚みのあるボディが特徴、48mmというのはかなりで、ポケットに収めるにはいくぶん困難を伴います。まあそれで、二軸で自由に動くフリーアングル2.8型TFT液晶モニター画面も厚みのうちに収まっているので、大したものではあります。カメラ上面にはP・T・A・Mなどの撮影モード選択とISO感度選択の二重ダイヤル、プラスマイナス2までの露出補正ダイヤルが左右に控え、ガッチリとした構えです。ISO感度は100から3200まであるんですよ。外観の重厚さも相まって、こういった操作部や設定がいかにも「撮るためのカメラ」という構えです。ホールディングもいいですね、どうもすぐに落っことしそうな小さくて薄くてつるつるのコンデジの多くとはそこは違います(そういうのを使う際には、必ずストラップを手首に通しておきますよ)。もちろんRAW画像も撮影、動画撮影(MOV形式)も選択できます。
中央に鎮座するTTL制御ストロボ用のホットシューとその下の光学ズームファインダーがG12を特徴づけています。特に私には、ファインダーは必須の条件で、これがないものは買わない主義と、繰り返し書いてきました。もちろん光学ファインダーはズーム連動のほかは素通しに毛が生えたようなものなので、いろいろの表示データを読む、それで調整を図る、そして肝心のピントがどこにあっているか確認する等はできません。そのためには液晶画面を起動し、そっちを睨んで撮影をせねばなりません。もちろんそうしたじっくりとした撮影も必要な際はやりますが、私はコンデジで撮るのは多くの場合「早撮り」なのです。「仕事」として訪問面談や見学現場、会議などで撮りまくるなどとなれば、これしかないですね。そうなれば、目的・被写体や環境条件に合わせてモード設定などはしっかりやっても、「その瞬間」では素通し同様の光学ファインダーで、ともかくなにが画面に入っているか確認する(それもしないでヤマカン撮影も)、それしかできません。
それでも慣れれば、カメラの癖をつかめば、どこにピントが合っていそうかもおよそ想像ができます。もちろんAFのやることなので、みごとに外れてくれるのもあるのですが、確率的にやむを得ないとせねばなりません。
そういうわけで、私は通常は液晶画面を裏返しにしてしまって表示off、電池消費も節約し、目線に構えてどんどんシャッターを切っていきます。ともかく撮りまくるに向いたカメラで、動作も速いし、とりわけこのように液晶画面をオフにしておくと、電池の長持ちには驚嘆すべきものになります。まず交換電池の用意が要りません。背面の操作ボタンでストロボ設定、セルフタイマー、接写が表に出ているのも使いやすいですね。手ぶれ防止もよく効き、不安定な姿勢での撮影でもかなりいけます。これに外付けストロボを取り付けて撮るというのは実際にはやっていませんが、ともかく対応力の高い、使い勝手のいいカメラです。ズーム比はもうちょっとほしいですが、望遠サイドはともあれ、ワイドサイドが28mm相当であればかなり使い勝手がいいものです。撮れる画像も、代々高評価を得てきているだけのことはあり、期待通りの画質と色彩です。ただ、連写もできるけれど、通常の撮影画像とは異なるものになるので、そこはちょっと期待はずれ。
大変に使いやすいG12ですが、このごろ「いつでも持ち歩く」存在ではなくなってきてしまいました。期待はずれや限界ありだからではなく、電池等込みで400gを超える重量がちょっとこたえてきたからです。鞄の中でもかさばります。これに代わる、もっと小さく軽いコンデジで、私の望む機能と性能を備えるのが出てきたとなれば、やむない選択でしょう。
その一方、G12の後継であるG15、G16(13、14はなし)では画素数やレンズはじめ「いろいろ大幅性能アップ」とはされても、液晶モニター画面が固定式に戻ってしまう、それだけでもがっかりです。液晶画面はoffにしてるんなら関係ないだろというわけではなく、それを使う時にはフリーアングルが必要かつ便利と、P6000のときに痛感したわけで、実際にG12でも多々経験しました。なんでまた固定に戻っちゃうんでしょうか。
さらに「決定版」とされたG1xに至っては、1.5型CMOSセンサー採用という売りでも、図体がひとまわり以上大きくなり、厚さは65mm、重さは492g、液晶モニター画面が可動式にまた戻ったものの、もうどうにも「コンパクト」とは呼べないレベルです。だめ押しとして、2014年にはG1xMkⅡというのを発表、外観からして完全に「非コンパクト化」、重さも513gと大台載せ、そしてなによりファインダーレス化に踏み切ってしまいました。Gシリーズに一貫していた光学ファインダー採用はここに終焉を迎え、事実上まるで違う製品に化けたわけです。G1xMkⅡは別売EVFファインダーもつけられることになっていますが、それが33,000円もするんじゃあ。
ここ一、二年、キャノンはファインダーレス化の流れにしたがうか、「独自性」を保つか迷っていた様相が顕著でした。しかしこの「フラグシップ機」で「思い切っちゃった」ことは間違いないわけで、私も永久の別れを告げねばならなくなったようです。これをしてキャノンは「進化」と言う、私にはまったくの「退化」ですが。
貴重な存在にもなってきたG12はもちろん使い続けます、故障をおこさない限り。これも「予備機」を手に入れておきましょうか。
G10を買うの記
<2014.09>
それでも私は、画像プリントをつくる、何よりひとにあげる際にはということで、いまに至るまで使ってきている次第です。ところが参るのは、私の使ってきたキャノンのフォトプリンターが、PCのOSが上がるたびに対応しなくなる、特にWINDOWS7になったら、これなんですな。キャノンはプリンタドライバーソフトのバージョンアップサービスを続けてきているのですが、なぜかWIN7で多くが見捨てられてしまいました。むりやり、古いバージョンのドライバーをインストールしても、どうにも動いてくれないのでお手上げです。
おかげで、これまでにフォトプリンターを3台くらい見捨てねばならなくなりました。なかでも、CP-400なんてそんなに前のじゃないのに、です。このままにしておくのも忌々しいので、WINVistaのPCを、かなり調子が悪いのにだましだましまだ使っているくらいです。
詳しく言うと、CP-10用のカードサイズ用紙は前後にバリのついた、マスクみたいなかたちのHC-36IPというものです。ほかのフォトプリンター用のはKC-36IPというので、形状が全然違います。キャノンのフォトプリンターは基本、LサイズのKL-36IPまたははがきサイズのKP-36IPという用紙を使うことになっており、私も長年これらを使っていたのですが、そこで勘違いをしていました。
あっという間に時代に取り残されたCP-10だが、キャノンのほかのフォトプリンター同様に用紙はのちの世代のプリンターでもつかえるだろう、そうじゃなかったんですね。CP-10というのは、「専用の用紙にカードサイズのプリントをする」唯一の機械だったんですね。
それなりに満足できていたキャノンG12ですが、これより2世代も前のG10を中古で買うという事態になってしまいました。このアホみたいな選択には、ある込み入った事情が絡んでいます。
いまから10年以上も前に、キャノンのCP-10というフォトプリンターを買っていました。この頃から盛んにつくられ、いまも販売が続いている(ただ、どうも近ごろは消える寸前みたい)「昇華型熱転写方式」プリンターというヤツで、用紙とインクロール込みのランニングコストもちょっと高いけれど、印画紙へのプリントに似たクオリティ・外観の画像プリントができる(表面が保護されていて、印画紙同様に長持ち)ので、私も長年愛用しているタイプです。最近は、(複合型)インクジェットプリンターになんでもやらせる志向と、同じ昇華型熱転写原理で動いている、街中のプリントスタンド利用と、そして何よりプリントなんかつくらない、スマホのなかに画像があればいい、せいぜいネット上でやりとりや共有というひとの増加で、相当日陰の存在になってきている観です。おそらく、こうした画像プリントをつくらないのに比例して、「アルバム」というのも売れなくなっているんでしょう。
そういう「時代の流れ」ですから、CP-10なんていまのPCでは動くはずもない、そこは覚悟していました。ところが私が長年勘違いしていたのは、このCP-10に用いる用紙、これが専用の「カードサイズ」という、名刺よりひとまわり小さいクレジットカードサイズのもので、おそらく発売当時は大きめの用紙にプリントするにはコストが高かったこともあって、こういうのも出したのでしょうが、以来キャノンのプリンターはこれに対応をしないのです。なるほど、「通常の」キャノンフォトプリンターにも「カードサイズ」カセットというのがあり、それ用の用紙ももちろんいまに至るまで販売されているのですが、実はまったく違うものなのです。
CP-10を見捨てるのは可能でも(これ、発売が終わる直前くらいのタイミングで、2003年に店で投げ売りしているのを拾い上げたんですが)、問題は相当量のHC-36IP用紙です。当時、幸か不幸かこれを大量にストックしたのでした。別に「そのうち世の中から消えるだろう」というのを予想していたわけでもありません。しかし、ともかく「ある」のです。そしてこれでプリントできるのは、CP-10だけなのです。
そこでとれる究極の選択は、CP-10も大量のHC-36IPもまとめて見捨て、ゴミとするか、ともかくなんとかCP-10を動かしてみるか、これしかありません。うえに書いたように、CP-10が最近のOSのPCに対応するはずもないのはわかっていたので、そこはまず諦め、残された選択肢として、カメラメーカーが勧める、デジカメからの直接プリントを試みようとしました(このプリンターのインターフェースはUSBのはずなのですが、当時一部で使われていた独特の形状のコネクターで、いまのUSBとはまるで違うものです。ただ、いまどき風のUSBとつなぐケーブルもついているので、PCに接続できないわけではありません)。
キャノンのA530、お、プリントするじゃないですか、よかったよかった。しかしG12、だめです。うんともすんとも言いません。A1400も同じです。これはどういうことか、説明書やカタログなどさんざんひっくり返し、ようやくわかりました。CP-10はカメラとの接続に、キャノンの独自の規格とソフトを用いていたのです。「当社製カメラの専用プロトコル」と明記されているくらい(「DIRECT PRINT」というマークが記されている)なのでした。その後、各デジカメメーカーが共通のプリントの規格に合意、これがPictBridgeです。2002年にキャノンを含めた各社が定めたのだそうです。結果として、キャノンの「専用プロトコル」はガラパゴスに島流しになってしまいました。
キャノンとしては、「ユーザーサービス」のために、以後発売のデジカメにも基本的に両規格を搭載してきたらしいのですが、「この辺でいいじゃろ」と、2000年代末からPictBridge一本にしてしまったようなのですな。それを一概に責めるわけにもいきません。「共通規格」に向かったんだから、ということにもなります。ですから、2010年発売のG12ではCP-10には対応しないのでした。しかし、もうお蔵入り状態のA530で、このCP-10をなんとか動かそうというのも気が滅入ります。ほかのデジカメで撮った画像データのあるSDカードをA530に入れ、プリントしようという「裏技」も試みましたが、そうは問屋が卸しませんでした。
再度の究極の選択は、「CP-10を動かせる、キャノンの古いデジカメを入手する!」でした。詳しく調べると、Gシリーズでの境目は、G10とG11の間であることがわかりました。そうなれば一も二もありません。「G10を買う」、これだけです。
G10は外観や性能もG12とそんなに異ならないし、当時比較的評判のよかった製品です。2008年発売、同じようなF2.8-4.5/ 6.1-30.5mmレンズ搭載、1470万画素CCD、液晶画面が固定なのをのぞけば、G12とあまり大きな違いもありません。バッテリーも同じなのは有り難いところです。
これを、あちこち中古の店頭で探し回ろうかと思った矢先、M店で見つけてしまいました。価格が1万8千円もするので、私の予想よりはかなり高かったのですが、見たところ状態もよく、前の持ち主はほとんど使っていなかったようです。ですから、敢えて買ってしまいました。
かくして、「古いプリンタを動かすために、カメラを買う」という珍妙な事態になり、以後G10を持参、そして現地でCP-10で撮った写真のカードプリントをつくり、あちこち撒くという、ひとが見ればなにやってんだろと思う所行を重ねております。
言うまでもなく、これはいま人気のフジ「チェキ」のパロディです。デジカメ時代が逆に、フィルムカメラでのインスタントプリントの価値を見直させた、それならデジカメでインスタントプリントもできるんですよ、と「自己主張」している次第。その意味、CP-10がバッテリー駆動してくれればもっといいんですが、これは不可能な話しです。
もちろん、いまどきデジカメといま売られているキャノンのフォトプリンターを持っていったっていいわけだし、最近のはバッテリー駆動もできるんですが、なによりCP-10は小さくて軽い(本体510g)んですよ。2001年の発売当時、「写プリしよ!キャンペーン」と称し、CP-10とデジカメを持ち運べるキャリングバッグまで出すほど、キャノンはカードサイズ専用プリンターの需要は大いにあると考えたのでしょうが、見事からぶりだった、しかしまだまだ価値はあると思うんです、私が勝手に。少なくとも、HC-36IPのストックがなくなるまで、頑張りましょう。
2007年に買ったDXフォーマットデジイチD80の買い換えです。4年間相当に使ったんだからまあいいじゃろというところ。もちろんかなりの性能アップではあります。
D80下取りで、これも中古品を48,800円で入手しました。2008年の発売当時、12万円くらいの実売価格だったので、中古とはいえ値下がり急です。極端に「個性的」でもなく広く売れそうな製品は、それだけ値も下がる、状態のよいものが中古でいくらでもある、だからお買い得とも言えましょう。


使い勝手はD80とほぼ同じの、いかにも後継機らしいものです。外観も大差ありません。撮像素子が高性能化されたこと、動画撮影あり、また例によってライブビュー機能を取り込んだことなどが、2000年代末製品としての「先端」だったのですが、以来5年余、もうごく並の性能機能になってしまいました。だからといって、焦ってまた「最新製品」に買い換える気もしませんが。
SDカード使用、1230万画素のCMOSセンサー、1/4000~30secシャッター、連写4.5コマ/sec、ISO200~3200対応、AVI動画撮影、ペンタプリズムファインダー、11点測距位相差検出AF、3型ポリシリコンTFTモニター画面、コントラストAFによるライブビュー撮影可、重さ620gです。ニコンらしくちょっと重いのを別として、いかにも標準的なスペックですね。ライブビュー機能を取り込んだからといって、液晶モニター画面が動くわけではないので、私的にはあまりメリットを感じず、ほとんど用いたことがありません。
前にも書いたように、D80を買い換えたくなった最大の理由は、ダスト除去機能のなさでした。結果的にはこれはデジイチには不可欠の機能だと思えます。レンズ開口部からゴミが入り込むのは避けられず、それが画面のローパスフィルターにくっついて容易にとれない、大問題です。撮影画像に見事に写り込んでくれます。オリンパスなどがいち早くダスト除去メカを取り入れたのに、なぜかニコンはなかなか腰を上げなかった、ようやく踏み切ったのがこれらD90などでのことだったのですから。
いまはニコンのデジイチも完全に次世代に入り、D二桁シリーズは姿を消し、四桁と三桁と一桁に分解、D90の存在も過去のものになってしまいました。しかし私としては不満もなく、よく撮れるデジイチとして重宝しています。ちょっと重いですが、出張や旅行に持っていくことも多いですね。
<2016.09.10>
D90ももう5年以上使っているし、だいぶ旧式にはなってきたしというところですが、別に流行を追い、新製品に目がくらむというわけではなくても、目移りがすることには理由があります。最新のテクノロジーの結晶であるデジカメでは、(メーカーの方針もあってか)実際にどんどん新しい技術や機能が取り込まれてくるので、フィルムカメラの時代のように、「古くていいもの」を愛用するという意味が薄れ、むしろ「あれもこれもできないのか」という、旧製品への失望感ばかりが先立つのは否定できません。ビンテージもの、クラシックものの「味」や「写り」にも期待が薄で、悩ましいところです。しかも、どうも現代のデジカメは10年持たないようなつくりになっているんじゃないのという疑いも出てきます。まあ、電子部品の塊のようなものですから、メカが丈夫で長持ちなんていうだけでは無理で、どっかがいかれますと、もうアウトになる公算も大です。
そのへんの実態は、どれだけ実際に持ち出しているか、撮っているかによっても自覚させられるのです。D90、今年大きいイベントに持ち出しました。まあなんとか期待通りではあったと思いますものの、図体の大きい割にできることが限られているなあという実感はします。
そのD90には、直系の「後継機」というのがありません。もちろんD100ははるか前の、ニコンのデジイチ黎明期の製品(いまでも愛用者は少なくないですが)、そこを飛び越えて、いっぺんにD7000系列になってしまいました。撮像素子画素数など大幅強化されたものの、D90とのさしたる開きもなく、そんなに魅力的なものとも感じられませんでした。
このD7000も、さらにD7100、D7200と「進化」してきてはいますが、D90を100g以上も上回る重さに耐える必然性を感じさせないままです。高速連写向上してますよとか、ISO25600まで対応しましたとか、wifiで画像送信できますとか、それらはその用途を求める方々には新たな魅力でしょうが、AFの向上を除けば、私にはあまり関係ないところです。
私として、実はDX機にもほしいのはバリアングルモニター画面なのです。これについては、私が手にしたオリンパス機やパナソニック機で十分にそのお役立ちぶりを経験しました。昔はそんなものが要るのかなどとも考えていたのですが、一眼レフレックスファインダーや位相差検出AFが気にくわないのではなく、要するにファインダーをのぞけないような構えで撮ることもよくある、特にデジカメではその自由さがほしいと実感するようになりました。座ったまんま、頭上にカメラを構える、ひとの群れの上から見おろす、地面近くで接写する、そういった撮り方では、フィルムカメラ時代にはヤマカンで狙うしかなく、よくはずしたのですが、それが容易にできるのは、AFでもあるデジカメのつよみなのですね。そういう無理線の構えでも、画像を見ながらシャッターを押せるのですから。
ところがなぜか、ニコンはここにかなり消極的です。2016年現在でも、モニター画面を可動式にした機種は数えるしかないのですね。そのなかでも、別に記したように、FX機であるD750はチルトモニター採用で、完全バリアングルではないにせよ、使ってみればそれなりに便利です。
「そういう機能をお求めならば、D5000系を使ってください」というのがニコンのポリシーなんでしょうが、これはいささか違和感ありです。D5000系ははじめからバリアングルモニター画面を売りにしてきたのはたしかですが、これはどう見てもD40に発する、小型軽量化・安価化の路線上のもので、D90の位置づけには該当しません。
そこに投入されたのが、話題を呼んだD500です。「D5相当のDX機最強モデル」とうたい、値段もあっと驚く25万円以上、意表を突く製品コンセプトですが、容易に手が出ません。そんだけ払えるのなら、フルサイズFX機を探すよというのが並みの反応でしょう。けれどもこのD500には、チルト式モニター画面が採用されているのです。超強力153点AFとか、ISO51200対応とか、10コマ/秒の高速連写とか、4K動画とか、こわもてラインの並んでいる中、液晶モニター可動というのはぜんぜん強調されていませんが、たしかに入っているのです。
そうであれば、ニコンさんよ、あまりに選択肢が狭いんじゃありませんか。25万円も払って、電池込み860gの図体を抱えて、それでもDXフォーマットにこだわるという方がどれだけいるのか、私のようなビンボー暇なし人間には想像もできませんが、それならせめて、D7200の後継D7300として、バリアアングルモニター画面付きのを出してくれないでしょうか。
|
(2017.4.12) てなこと言ってたら、やはりニコンは出してくれましたですな。カメラ売れなくて経営が傾いているなどの評判下での、英断か危うい賭か、惰性かいずれでしょうか。ただ、D7300ではなくてD7500でした。規則性なく飛んだと言うより、D500やD750を意識したナンバリングなのでしょう。チルト液晶モニター画面付きの、D7200後継・ペンタプリズムSLRのDXサイズ機です。D500じゃあちょっと高すぎ、重すぎの実感にこたえる、2088万画素、ISO51200可、8コマ/秒連写、4K動画撮影、それで重さ720gと、いかにもD500手前のスペックが並び、チルト画面でのタッチ操作も売りです。2017年6月発売予定、予想販売価格が15万円前後と、これもいかにもですが、正直には、D90の後継と言うにはちょっと高いですね。 |
別のところに書いたように、このような「安いコンデジ」を新しく買う必要性は乏しかったのですが、あえては「ファインダーレス化」に抗する新製品を手に入れたい、応援したいという思いからでした。A530やP50での失望を経験しているので、こういった製品には期待はしていなかったものの、使ってみると結構いいものでしたね。12,980円也です。その後は一万円以下に落ちていましたが。

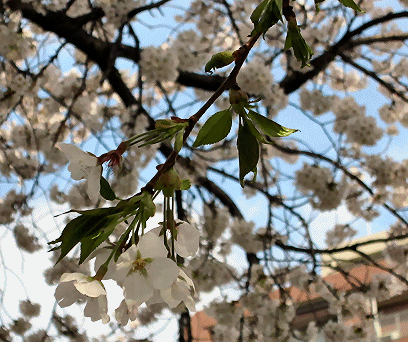
PowerShotA1400はSDカード使用、1/2.3型1600万画素CCD撮像素子、F2.8-6.9/5-25mm(35mmで28-140mm)沈胴ズームレンズ、2.7型TFT液晶モニター画面、電池込みで重量174gの軽量機です。厚みも29.8mmとなっていますが、これは電池収納部のふくらみで、それ以外では20mm程度と超コンパクトです。電源が単三電池2本であるのもいまどき珍しいところ、それでもかなり持って、13年前のフジFP2300とは大違い。基本的にはプログラムAEとAUTOしかできませんが、もちろんストロボ内蔵、動画(MOV)撮影可能です。G12同様にファンクションセットボタンにストロボ設定モードが出ていること、同じボタンリングでディスプレイのオンオフも設定できること、さまざまな設定変更をするメニューボタンがこれと別にあることも、ちょっとした特徴でしょう。露出補正やISO感度変更はいくぶん面倒なのは、この種の簡単なコンデジでは仕方ないところでしょうか。セルフタイマー起動も表に出てなくて、セットボタンでたどらねばならないのは、不便なところでもあります。
こういったシンプルなデジカメだし、「写り」にこだわるところで使うものではないと自覚はしていますが、見本画像にあるように、バックをぼかして桜花に焦点なんていう撮り方もできますよ。ファンクションセットの中にマクロもあるので。なにより実像式光学ズームファインダーですよ、「顔前腕のばし画面睨み撮影」をしなくても使えるんですよ。この花の絵だって、液晶画面を睨んでピント位置を捜したのじゃありません、ボディ上部の素通し状ファインダーで撮ったんです。
最近のデジカメは、ともかく値段を抑えるためか、付属品等も最小限、そのいきおいで説明書もシンプルなのしかついておらず、詳しくはCD中の説明書(ユーザーズガイド)を自分でプリントしてくれという構えです。A1400は専用電池も使わないので充電器などもなく、箱の中は本当にシンプルそのものでした。まあ、たしかに私を含めていまのユーザーは、説明書読まなくたって一通りは使えるものではありますが、詳しい説明を読んでいるうちに大発見ということも多いんですけれど。せっかくメーカーがいろいろ盛り込んでいるのに、「発見されず」に使われないというのももったいないように思います。
こう書きながら、「目つむり検出警告」とか、「顔セルフタイマー」とかの機能があることを初めて知りました。「デジタル手ブレ抑制」というのも入っているのですが、選択機能の一つで、しかも画素数限定、人がいないと「連続撮影になって画面が合成」なんていう、訳のわからない存在、これでは使えません。つまり、手ぶれ防止はないと考えるべきでしょう。
A1400の前に、もうキャノンもファインダーレス化に走ったと考え、すでに型落ちした、ファインダーつきながら旧タイプのA1200というのが「逆輸入品」か、ネット通販で販売されているのを見つけ、買ってしまいました。やはり単三電池使用です。ですからA1400とあわせ、同じようなものを2台持つことになってしまったのですが、まあ邪魔にもなりませんし、そんなに高い買い物でもなし。実際、恐れたようにキャノンはこの辺の迷いもさっさと捨て、ファインダーレス化の道から戻ることはなさそうです。
これを買ったのは、私にとってかなりの贅沢でした。
常時持ち歩き用、調査等訪問用にはキャノンG12を使ってきて、ちょっと重さもこたえてきたので、性能はだいぶ落ちるけどキャノンA1400に交代、それでまあ満足しているのに、また半年でコンデジ買うなど無理しすぎとなりましょう。しかし、つまるところはそうした私の用途に対しほぼ理想的なものが出てきて、しかもレンズはライカのvario-summicron、泣かせます。買う気をくすぐります。
もちろん、こうしたコンデジの世界で絶滅に瀕していたファインダーをパナソニックがあえて復活させた、それだけで泣けてくるではありませんか。光学ファインダーではもはやなく、EVFですが、ともかく「しっかり構え、覗く」撮り方のできるカメラなのです。パナソニックはあえて書きました、「被写体と向き合えるファインダー」「しっかり構えて被写体を狙える」と。そうですよ、顔前腕のばし遠目画面睨みで、しっかりなんか撮れるわけないでしょう。
高級コンデジを謳っているので、各性能も相当なものになっています。SDカード使用、1/1.7型1710万画素MOSセンサー撮像素子、ISO80~6400設定、F2.0-5.9/6.0-42.8mm沈胴ズームレンズ(35mmで28-200mm)、250-1/4000secメカ・電子シャッター、連写最大60コマ/sec、AUTO・P・A・S・M切り替え、マクロ可能なAF/マニュアル切り替え、AFロック、AEロック可、OIS手ぶれ補正つき、オートストロボ内蔵、RAW画像撮影、AVCHD動画撮影、3.0型TFT液晶モニター画面、0.2型LVFファインダー(視度調整つき)等々、よくこの小さな図体に盛り込んだと思うほど。EVFファインダー内には多くの情報が同時に表示されるので、これは光学ファインダーでは比較になりませんし、もちろんピントや明るさ状況もわかります。
ボディ上面はスイッチボタン、シャッター・ズームボタンダイヤル、撮影モードダイヤルのみでシンプルですが、背面メニューボタンの周囲に露出補正、ストロボ設定、マクロ/MF、セルフタイマー/連写の各ポイントが出ていて、操作しやすいだけでなく、レンズまわりのリングがダイヤルの役割を持つという、コロンブスの卵的発想をしています。キャノンG12は、レンズまわりのリングがなぜか外れやすく、なんでこのようなつくりにしたのかよくわからないのですが、LF1はまったく違う発想ですね。
それで、これだけのものを詰め込んだボディが重さ170gなのです。電池やカードを入れても、200gに届きません。厚さも約28mmなのです。wifi付は私にはどうでもよくても、動画をAVCHD出力するとなると、食指も動きます。「動画撮れます」のデジカメが主流になってきても、動画ファイルの形式が制約多いとなれば、その変換処理だのの手間を考え、使う気がおこりません。しかし、この世界でのデファクトスタンダード化してきているAVCHD形式対応となれば、これはもういまのデジタルビデオカメラに匹敵します。
かくして、日常携帯カメラはLF1に一挙交代してしまいました。EVFファインダーですがあまりタイムラグもなく、光学実像ファインダーに近い感覚で覗いていられます。画面内のデータ表示はさすがに小さすぎの観があるものの、必要な際には役に立ち、特にあとであげるISO感度変更、Pモードの場合これをレンズまわりリングで動かすのがそのままリングダイヤルを見ているような画像で、ファインダー内で見られるのはとても便利です。ファインダー覗いたままの状態で操作できるんです。もちろん、A優先やS優先時の絞りやシャッター速度変更も同じ操作と表示で、いかにも「撮るためのカメラ」ですね。
画像にはパナライカレンズの味が出ていて、フツーのコンデジとは段違いに感じられるし、また使っていてさすがと思うのは、ISO感度を相当に上げても、なんとかものになる画像を撮れるという点です。ISO1600設定で十分使えます。暗部に若干ノイズもあるし、大きく拡大したり画像処理を重ねたりすると、問題も出てきますが、コンデジの世界でここまでやれるという感動です。添付の絵も夜間にISO1600で撮っています。
不満なのは、専用リチウムイオン充電池を使うのに、充電器が付属していないどころか、オプション市販もされていないのです。これはどういう考えなのでしょうか。他方でボディ本体にも電源プラグはなく、充電はUSB接続を通じてやるしかありません。それを考えてか、USB接続で使う小さなAC100~240Vの外部電源アダプターがついています。これがあるからいいんじゃないという考えかも知れませんが、予備電池や外部の充電器はほしいですよ。もっとも、これだけのものを詰め込んでいるのに、電池の消費は意外に少なく、電池切れに瀕したことはまだありません。EVFはかなり電気を食うと思うのですが。
これの電池DMW-BCN10というのは買えば相当の値段であるものの、すでにサードパーティの「互換品」も出ているようです。それに合わせた充電器まで売られているらしいのですな。ちょっと怖くて手が出せませんけれど。あと、さすがにこれだけのレベルのもののせいか、Lサイズjpg+RAW画像で撮っていると、撮影後処理が終わるのにちょっと時間がかかるようで、シャッター押したあとすぐにスイッチを切ろうとすると、反応してくれません。なにかトラブルかと一瞬焦るに、やがてレンズ収納でoffになるという流れです。仕方のないことでしょうが。
おっと忘れました。私はLF1を33,800円で買いました。実はLF1はじめ、最近のデジカメは店頭価格が激しく乱高下するのです。それに悩まされた話しは別途記しましたが、LF1にして、私の買ったのちでも上がったり下がったりしています。アベシンゾー氏のおかげで、税金がはね上がったせいだけでもないようで、不思議ですね。この私の購入価格はお値打ちの方ではありましょう。
ちなみに、パナソニックのデジカメのかなりのものはドイツライカと共同、ないしはOEM供給用でもあります(マイクロフォーサーズ「ミラーレス」は違いますし、L10にはライカは乗ってくれなかったようですけど)。その際、前にも書いたように、ほぼ確実に、Leicaブランド品はPanasonicブランド品の倍以上の価格で売られるのです。「ライカ独自の機能やソフトが入っている」とか、なんだとか勿体がつくのですが、レンズを含めてどう見ても基本同じですよね。このPanasonicLF1も、LeicaCという名になると、途端に8万円以上もの値がつきます。ライカの製品としては安い方だろという、熱狂的ライカマニアの理解もありましょうが、私の理解は超えております。これぞ究極のブランド戦略とも、私はよく例に使うのですけれど。ま、機体の色はたしかに違うのですが(LeicaCはブラウンとゴールド)。
D26 ニコンD750 <2016.2購入>
別のところに書いたように、2010年購入のD700を今ごろながら買い換え、D750を入手しました。
自分の体力財力と、「撮る」意欲から申して、これは最後の大きい買い物かも知れません。とは言いながら、D700よりはだいぶ小ぶり、軽量化しています。D700後継ではないという言い方は正しいのでしょう。「フルサイズデジイチだ」という、身構えたところが少なくなりました。もちろん、LF1のようにいつでもどこにでも携えていけるということとは対極にあるのは間違いないのですが。
スペックは、35.9×24.0mm2493万画素 CMOS撮像素子、1/4000~30secフォーカルプレーンシャッター、最高速6.5コマ/sec連続撮影、TTL位相差検出方式51点AF、ライブビュー時コントラストAF、マルチパターン/中央部重点/ハイライト重点/スポット測光各切替AE、ISO感度100~12800、H.264/MPEG-4 AVC・MOV形式動画撮影、ペンタプリズム一眼レフファインダー・視野率100%、チルト式3.2型低温ポリシリコンTFT液晶モニター(123万ドット)付属、SDHC/SDXCメモリーカード2枚使用、総重量約840g(本体750g)、こんなところであります。最新のデジイチの性能を備えています。だいぶ軽くなったのに、本体の造りはモノコック構造の新技術でがっちりしているようです。
早速に試し撮りといきたいのですが、ここのところ所用多いうえ、寒いので、なかなかいい機会がありません。
下記の画像は、そういう中で所用先で収めたものです。
慣れないというか、しばらくきちんとカメラそのものをいぢっていなかった報いというか、出かける前にマニュアルレンズをつけて試しをしていた、そのままの設定で出先でD750を用い、AE露出もAFも外したままでシャッターを切るというへまをやらかしました。若い頃から変わらない、いい加減なところ丸出しです。それでピンぼけは仕方ないとしても、完全露出不足も撮ってしまいました。モニターに映る(映らない)撮影画像で気がつきそうなもの、これは機体に慣れぬところで、モニターをつけていないように勘違いをし、しばらく気がつかないという失態、お粗末なところです。
ただ、さすがD750なのか、完全アンダーで真っ暗のような画像も、ソフトでいじってみたら、結構見られるものになったには唖然です。
それでも一応「まともに」写ったようなのが、下にあげたのです。やはりフルサイズの余裕がここでもうかがえますね。
D27 ニコンP900 <2016.8購入>
これが人生最後の買い物などと言った舌の根も乾かぬうちに、また買いました。
まあ、D750に比べれば1/3以下の値段なので、後ろめたさもいくらか軽く済みます。
別のところでも記したように、2015年におけるニコンの「思いもかけない」ヒット製品、35mm換算で2000mm相当の超望遠、そんなの手にしたこともないでしょ、と悪魔のささやきが耳元に聞こえてきます。実際すごいことですよね。
思いもかけないヒットだったせいか、店頭でも長く品切れ、予約入荷待ち状態でした。それだけ割高感もありました。それが2016年もなかば過ぎ、ボーナス商戦時期を終えて、店頭でも「予約待ち」に代わり、「在庫あります」の札が付く、そして小売価格もかなり下がった実感のところでさっと買いました。その後またずいぶん値上がりしているので、私めもようやく「こつを習得した」というところでしょうか。あるいはニコンももう、これは製造販売終了とするのかも。
で、2000mm相当はすごいんですが、さすがにこれはなかなか撮るものがありません。いくら強力手ぶれ防止付きといっても、手持ちではやはりかなり無理そうです。だいたいこのくらいの望遠となると、それこそ月を撮る、鉄道やヒコーキ、スポーツを超遠距離で撮るというような状況になり、当然三脚に乗せてじっくり構えるのが定番なのでしょう。そういう撮り方を滅多にしない私としては、そこはやはり無理でした。
では空振りか、と言えばそうでもありません。2000mm相当はそう使えなくても、1000mm以上くらいなら手持ちでもこなせるし、かなりおもしろい画像を構成できます。さるイベントの機会に持ち出し、出席者の皆様方をかなり悪趣味に収めました。そういう人物像を撮るには向いているとも思うのです。相当の距離から、カメラを意識させずに表情をおさめる、こうしたねらいに向いているのですね。私は、いかにもという「カメラ目線」の人物像というのが好きではないので、あくまで私の見たまま、印象に残る表情を記録したいのですね。しかし「撮られる」側には不本意で、悪趣味に感じられるようです。困ったものです。かといって、ユーメー写真家のように、「モデルと対話しながら」いい表情を撮るなんていうのは、私の日常生活のうちでは無理なことですから。
そうした際には、やはり強力なVR機能が効きます。100%手ぶれなしとかピンボケなしともいかないですが、相当に信頼を置けます。狙った瞬間をおさめられますね。
ことのついでに申せば、ここのところ、私の顔写真入りのインタビュー記事などがいくつか載る機会もありました、そこでは、写真係氏とそれこそ「対話しながら」、撮られた画像が選ばれているはずですが、当の私には、愕然とするような老けぶりのみ印象に残ります。もっともそれは実物がそうなんですから、非はひたすら我が身にあるわけです。
P900の諸元は、1/2.3型1676万画素CMOS撮像素子、4.3~357mm/F2.8-6.5ズームレンズ(35mm換算24~2000mm相当)、コントラスト検出AF、デュアル検知レンズシフトVR(5.0段補正効果)、0.2型92万dotLCDファインダー、3型TFTモニター92万dotバリアングルモニター画面、AutoPSAM露出、ISO100~6400対応、1/4000~15秒メカニカル・電子兼用シャッター、7コマ/秒連写可、TTL制御フラッシュ内蔵、重さ899g、こんなところです。撮影画面は16M[4608×3456]、8M[3264×2448]、4M[2272×1704]、2M[1600×1200]、VGA[640×480]、16:9 12M[4608×2592]、16:9 2M[1920×1080]、3:2 14M[4608×3072]、1:1 12M[3456×3456]と、9種類もあって、選択に困るほどですが、意外なのはJPEGのみ、ちかごろデジイチのみならず高級コンデジなどでも多いRAW画像記録を切っていることです。なにか思うところがあったのでしょうか。私はRAW画像であとからいじることもしないことはないですが、やり出すとあまりに手間がかかるので、滅多にしません。その分メモリを食っているのみという観もあります。画面の画素数は、画素数競争も一段落したいまどき、2000万以下では少ないような印象も持たれそうですが(P900の後継ではないが、2016年10月発売のB700というのは24~1440mm相当のズームレンズだが、2029万pix)、特に不満を感じるほどでもありません。
これの動画はMOV規格(H.264/MPEG-4 AVC)で、相変わらずAVCHDには背を向けているニコンですが、イベントの記録に動かしていた、持参したパナのビデオカメラが、再スタートしたら突如「データ調整」表示になってしまい動きません。焦るに、急遽P900の動画撮影を用いることを思いつきました。これのスタートはボタン一つで簡単なのです(再生がわかりにくい、モニター画面上で動画のアイコンがスチルと一緒に並んでいるのを捜さないといけない)。まあうまく撮れました。問題はこの動画ファイルをAVCHDに変換記録すべく、MP4形式を経由させる大作業でした。
ワイド端での再近接距離は50cm、マクロAF設定で1cmなので、近写に不満を感じることはありません。P900は顔認識AFも効いています。でも、当然ですがカメラ任せだと、狙ったものでないところにピントが行くことも頻繁なのですな。それはファインダー画面上でわかるので、留意すべきところでしょう。
かなりごろごろする図体なので、いつでも持ち歩くには向かないものの、超望遠ぶりは別としても、出かけるに持参して、損な気分はありません。けっこういろいろ撮れます。当然ながら、デジイチを持ち、さらに500mmもの望遠レンズも持つといったら、えらいことですよね。
P900もフルに使ってみて、若干の問題に気づきました。
この図体の割に、1/2.3型撮像素子というのは、いかにもレンズの見かけ焦点距離を稼ぐやり方で、どうかなという気もしますが、同じような重量級ズーム機では以前からよく用いられているところです。他社製品でもよくあります。スタンダードなコンデジ並みだというのではがっかりの観はぬぐえないものの、まあそういうものと割り切って使っていれば、特に不満は覚えません。また、前記のようにjpegしか記録しないというのも、用途限定なのだと考えれば、これまたわからないではなし、です。
いちばんの問題は、実は動画撮影機能なのです。これも前記のように、MOV形式であるものが、再生画面上ではスチル画像と同じように出てくるので、再生を試みる際、さらに転送をする際にうっかり見落とします。それも道理で、スチル画像と同じDSCファイル名で記録されているのです。インデックス用にjpg画像も作成しているのか、動画ファイル名を同じにする積極的な意味があるのかわかりません。
しかし実は困ったのは、この動画撮影がボタン一つで簡単に起動できる、そのこと自体でした。これを間違ってやるのです。ボディバックの上部で、親指がかかるところのすぐそばに、動画撮影ボタンがあるのです。ですから、ぜんぜん意識しないままに押してしまう、するといとも簡単に動画撮影に入ってしまう、これがよく生じることに気がつきました。カメラをアイレベルで構えていれば、指先がどこに行っているのかほとんど考えていないので、この動画ボタンが赤に塗られていても、意味はありません。もちろん動画撮影に入ってしまえば、画面下部に赤い表示も出るのですが、容易に意識しないですね。
間違って起動してしまった「勝手に」動画撮影の画像も、あとから消去をすればいいわけでもあるものの、ともかくあっという間にSDカード内のメモリを食ってくれますので、うれしくない仕掛けです。私はもちろん動画を撮るのが主用途じゃないので、もうちょっと「面倒に」してくれなかったか、せめてロックをかけてほしかったところです。まあ、こういう経験はほかの動画撮影付きデジカメでも初めてのところなので、メーカー考えすぎの結果でしょう。
超望遠でひとの顔など撮る、その際かなりシャッター速度が遅くても、手ぶれ防止が相当に効き、期待通りです。もちろんそれでも手ぶれすることもあるし、それ以上に、被写体自体が動いてしまう、こればかりはどうにもならないですね。あるいはまた、それを考えて動画撮影を重視したのかも、というのは勘ぐりすぎですが。
ちなみに、ほかの機種などと比較してみると、多くのものは撮影モード選択ダイヤルの中に、動画撮影モードが入っている形です。そこに合わせ、さらにシャッターボタンを押すと、動画を撮り始めるとなるわけです。この方が間違いがおこらないのは当然ですが、二段構えで面倒ではあるし、動画撮影をよく使っていないと、モード選択ダイヤル上の記号が動画モードだということを忘れてしまう、その危険もありましょう。
パナのLF-1は最近の機種のせいか、P900と同じような赤塗りの動画撮影ボタンが付いています。でも、バック上部の端っこにこのボタンがあり、またそれをカバーするような突起もうえにあるので、間違って動画撮影にしてしまったという経験は一度もありません。ニコンにもここは再考を求めるべきものでしょう。
あと、これは余計なことながら、ニコンのおすすめもあるので、口径67mmの大きなフィルターを買ってつけ、さらにゴム製折りたたみ型の円形フードもつけました。フードの使用は、外光時ではなるべく意識した方がいいと、私の経験も教えます。取ったり付けたりは面倒なので、つけっぱなしでいい折りたたみゴムフードにしたのですが、これをくり出したままで24mm相当のワイド端で撮ると、みごとに円周のけられが生じます。穴の中から撮ったようになります。もちろん、注意して伸ばしたり引っ込めたりしていればいいわけですけど。
このゴム製円形フードでは、別の問題も生じました。P900はかなり電気を食うのか、ちょっと押していないとすぐスリープモードになる、さらにはシャットオフしてしまうのですが、その際にはレンズ胴が原位置に戻るため、ワイド端状態でもちょっと引っ込むのです。するとレンズ先端につけたフードも戻る、これがかなりの口径サイズであるため、置いていてたまたま下に紙片や布片などあると、ゴムの摩擦でもろに巻き込んでしまうのですな。これもニコンの責任ではありませんが、もうたびたびやりました。
月が、撮れました
恐ろしいほどに撮れちゃうんです。もちろん一定の工夫は要ります。ISO感度は最大の6400に設定、また「オートでピントが合う」はずはないので、ダイヤルで「風景」に合わせ、ズームを一杯に伸ばしてみる、すると満月がなんと画面からはみ出すのです。ちょっと戻し、なんとか画面内に月をおさめ、シャッターを押す、それもがっちりした三脚上にしっかり固定し、狙いを定めてじゃなく、たまたま手元にあった、おもちゃみたいな折りたたみ簡易三脚をつけて、ともかく固定を確保しながらもなかば手持ち状態でシャッターを押す、こんなんじゃブレブレモヤモヤだろうと思いきや、なんとなく丸く写っていますね。その画像をPC上で再生してみれば、鳥肌立つような、これまで図鑑やなんかでしか見たことのない、あばただらけの月面画像がみごとに再現されているのです。しかもはじの方を見やれば、クレーターの山と谷のでこぼこがそのまま見えている、まん丸い月じゃない実相、写っているのですよ。なんか、遠くの山脈風景見ているような生々しさなんですよ。

望遠鏡もない私として、生きているうちにこんな画像を自分の手で簡単に収められるなんて、これは感激です。それだけでもたしかにP900の値打ちがあります。やはり2000mmです!!
| L10 | 岡山後楽園 |
| G12 | 三渓園の野良 |
| D90 | シドニーオペラハウス |
| A1400 | 花小金井の桜 |
| LF1 | みなとみらいの帆船日本丸 |
| D750 | 三田山上の早咲き桜 |
| P900 | 長良川国際会議場遠望 |
D28 ニコンD5200! <2017.3購入>
このへんで正真正銘打ち止めの意図だったのですが、なぜかニコンのD5200というのがあるのです(D500じゃない)。シリーズではもうD5600が現行機で、同じ番号系でD5000、D5100、D5200、D5300ときて、その後は飛んでD5500、さらにD5600という展開でしたから、三世代も前のです(ただ、ニコンのwebサイトではD5500というのが消えています)。
どうしてこれが手元にあるのか、いくら歳でも、呆けて買ったものも記憶にないのではことですが、記憶が怪しいのには理由がありました。買った記録だけはあるので、今年の3月のことだったのです。そのあと、あまりに大きな出来事があり、打撃があり、ただでさえ諸事ある年度替わりの間に、記憶から飛んでしまったと言わざるを得ません。
だんだんに思い出します。まさしくその年度替わりの時期、某量販店がどういう加減か、三世代前の旧式機などの在庫一掃販売を(残台数を表示して)広告した、その中にこのD5200を発見し、web上でひょいと発注してしまった、そういう経過だったはずです。2012年末という新発売時には、ボディで9万円ほどの値札がついた、それが4年あまり後には18-55mmVRズームレンズ付きで4万5千円足らずでした。レンズキットの値段としても約半値以下です。大投げ売りというほどじゃないけれど、いまだメーカー保証付きのれっきとした新品提供です。近ごろのコンデジ機よりも安く、「みらーれす」なんか目じゃないですね。そこにプチッといってしまったのでした。

先にも記しましたが、DXフォーマット機の代わりがほしいというのはずっとありました。でもニコンが推すD500なんて値段も重さも常軌を逸している、他方またどうせならバリアングルフル回転のモニター画面付きがほしい、これはあれば便利、そこにマッチしているからというのが値段以外での主な理由だったでしょう。うえに書いたように、今年出てきたD7500も重すぎ高すぎで、DX機の意味を減じています。手を出したくはなくなります。他方で、D40からの流れのD3200は安さと軽さ小ささの勝負(プラス安値の勝負)でしたが、オートフォーカスの加減など、限界も日々感じておりましたし。D5000系の売りがバリアングルモニターだったのは意識していましたから。
でもね、せっかくこれを手に入れたのに、あとあとになって、なんでD5200が置いてあるのと自分で首をかしげるとは、誠にカメラに申し訳ないことです。それだけ、2017年のうちにもまだ活躍の機会をつくっていません。
D5200は、23.5×15.6mmサイズ2471万画素CMOSセンサー、感度ISO 100~6400、シャッター1/4000~30秒、最高速5コマ/秒連続、AFフォーカスポイント39点/1点を選択、ペンタミラーファインダー・視野率95%、3型TFT液晶モニター約92万ドット(VGA)・バリアングル方式、コントラストAFライブビュー機能、MOV動画撮影、こういったところで、重さは555gです。ニコンとしては、まあまだ軽くて小さい域でしょう。性能機能はいまどき標準以下になりますが、4年前のモデルじゃ我慢するしかありません。そんなに悪くもないでしょう。ともかく「新品」なんですから。

D5200 2017年初夏のHiroshima
番外編
実は意図あって、ここに掲載していないけど、いま持ってるカメラが何台もあるのです。
「日陰の身」におとしめる意図でもないものの、身辺整理で売ったり捨てたりするなか、名前も挙げないのでは恨まれましょう。カメラの恨みのたたりは怖いかも。
というわけで、名のみあげていくと、
ニコンD600
パナソニックDMC-FZ200
パナソニックDMC-FZ1000
こんなのが手元にまだあるのです。
D600はD700、D750と同じフルサイズデジタル一眼レフ、だから両方持つ意味があまりないし、しかも中国でクレームをつけられ、「改良型」マークⅡになったいわく付きのものです。ともかくフルサイズデジイチ二台持つ意味もあまりないので、手放してもいいんですが、このいわくのおかげか、中古市場でもやたら安いんですな。
FZ200は失敗でした。またもパナの中途半端な「中型大レンズ機」です。FZ8で懲りたはずなのに、また似たようなのを手にしてしまっているのです。
実際、そんな目を見張るほどの強力ズームでもないうえ、あきれたのは近接限界が驚くほど制約され、かなり離れて被写体に向きあわないとオートフォーカスの範囲に収まりません。がっかりでした。センサーも1/2.3型1280万画素で、大したことはないですから。そのくせ、本体500g以上もあるのです。
そんなこんなで、FZ50の代わりは出てこないなと思いつつ、代わりを務めさせたのに、富士X-S1というロケットみたいな名のもあったのです。これは悪くない製品で、ズームカメラとして、仕事記録関係などでかなり働いてもらいました。癖もありましたが。ちょうどFZ50の電池がみなへたってきて、それにワイド系の制約も気に障るようになっていたので。
そのX-S1は、7年間に及ぶ「お仕事」の機会も終わり、富士系のシステムも手元に乏しいので、ひとに譲ってしまいました。専用ストロボ込みで。
だから、中途半端すぎのFZ200なんて出番もないまま、引き出してふて寝をしていたのに、なにを間違ったかパナ同系のFZ1000に手を出したのです。正直、ニコンP900の影響でもあります(意味不明)。
FZ1000は中古で買いました(5万円あまり)が、悪くありません。ようやくにFZ50の後継にたどり着いた感です。P900程の強力望遠ではなく(35mm換算25~400mm)、見かけではFZ200以下の数字(FZ200は35mm換算25~600mm)であるものの、1型MOSセンサー・2000万画素はワンランク上、もちろんRAW画像も撮れます。そして、ライカバリオエルマーズームレンズの威力は生きています。だからこれは結構使っているのです。そうなると、電池その他共用部分もあるため、FZ200も生き延びているという、妙な理屈。
なお、一度市場から消えたFZ1000ですが、いまはFZ1000M2として再登場しています。4k動画どころか、4k連写ができますという、パナのいまの4Kへの入れ込みはNHK並み。でも、そこまでして買う意味分からないし、これいま新品だと15万円以上もするんですぞ。お手頃コンデジがほぼ消滅し、市場にはかなり値の張るデジカメしか残っていない観です。そうでなくっちゃ、須磨輔に対抗できないという危機意識ゆえですが、そんなに払えるひとどれだけいるんだろ。
→ 続編へ