

(2013.06�I���W�i���쐬/2024.3�T�[�o�[�ڍs)
 |  |
�@U2�́u���_�v�ƌ�����̂��A�t�B�����U����Ƃ�������Ԋ�������Ă��܂��A���ꂩ��V���b�^�[���������тɈ�R�}���u�����߂��Ă����v�Ƃ��������݂ł��B�����I�[�g���C���_�[�̐ݒ�Ȃ̂ł��傤���A����ԎB��I���Ă���u�����߂��v�K�v�Ȃ��A���łɃp�g���[�l�Ɏ��߂�ꂽ�t�B���������̂܂��o�������Ƃ����u�����b�g�v�ȊO�A���ɈӖ�������̂Ƃ��v���܂���BF100�ɂ͂����������d�|���͂Ȃ��A�ق��̎蓮�J�������l�ɎB��I�����犪���߂��{�^���������āA�p�g���[�l�Ƀt�B����������Ԋ����߂��Ă�����o�������Ȃ̂ŁA�Ȃ��U2������Ȏd�|���������̂��A���C���_�[�̋@�\���ȗ��ɂ����������̂ł��傤���B
�@�B��Ƃ��ɂ͂��܂�ӎ������Ȃ��d�|���ł����A���Ƃł��ƂɂȂ�܂��B�t�B���������Ă���A�܂����܂̎��̂悤�ɃX�L���i�[�ɂ�����A���������ۂɁA�t�B������̃R�}�ԍ��Ǝ��ۂ̎B�e�����^�t�ɂȂ��Ă���킯�ł��BU2�ł̎B�e�t�B���������������Ȃ��Ă���̂ł�����A�͂Ȃ͂��˘f���܂��B�f�[�g�ʂ����@�\��������炢������Ȃ��A�Ƃ������肾�����̂ł��傤���B
�摜����ւ��@(2013.9.2)
�@�����ɓ���Ă������AU2�ł̎B�e�摜�ł����A�J�����ƃ����Y�ɂ͔��ɍ��ȁA����t���̏����ł̕��i�ŁA������ƃJ�����ɋC�̓łȂ̂ŁA�J�����̉摜�ƂƂ��ɕʂ̂ɓ���ւ��܂����B
 |  |
 |  |
 |  |


�@�ł����ǂ��܂Ɏ���܂ŁA�R���^�b�N�X�����Ƃ͂���܂���ł����B���҂ɔ����A���Âł��e�Ղɒl��������Ȃ��������Ƃ�����܂��B������Z����2005�N�ɂ̓J������������S�ʓP�ނ��Ă��܂������Ƃ��s���ޗ��ł͂���܂����B����ȏ�ɂ́A����܂ł̂�������ɔ�����A���i�̏o���̈�����g���u���̑��������Aweb���ɏ��Ȃ��炸�ڂ���悤�ɂȂ������Ƃ��e�����Ă��܂��B�C���^�[�l�b�g����̋��낵���ł���A�������Ȃ��ɂ̓K�Z�l�^�A���ӂ̃f�}�Ȃǂ�����̂����m��܂���B�������A����܂ł̢�D�]��L���̐��X�⍂�������̂��̂̂悤�Ȑ��]�Ƃ͂܂��������������X�o�Ă���ƂȂ�A��͂肱��͂Ǝv�킴��܂���B
�@���ł��������̃R���^�b�N�X���i���A���Îs��ň떜�~�䂩�琔���~���x�Ŏ�ɓ���܂����A����Ȃ碊O�ꣂł����X������߂������̂́A���̂���͕����قǂ̍��l�������Ă����̂ł��B����Ȃ̕|���Ĕ����Ȃ�����Ȃ��ł����B����Ȃ�A���܂܂Œʂ��FF1s�Ƃ�ML�ʼn䖝�ł��邶��Ȃ��ł����B
�@���ǎ�ɂ��Ȃ������J�����̂��Ƃ����ꂱ�ꌾ���͎̂ד��ł����A����Ȏ��i���Ȃ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł����A���̢�ꐢ���r������A���@�̎����̂悤�ȃR���^�b�N�X�J�����ƃc�@�C�X�����Y�ւ̂�������Ƃ����̂͂Ȃ�����ł��傤���ˁBCONTAX�̃u�����h���l�������������̂͗��j�I�����Ȃ̂ł��B
�@�����Ƃ��A�����Ă����̂͗v����ɋ����V�J���Ƃ��A�����Y�͕x�����w���Ƃ��A��Âɍl����A�ЂƂ��둛�������ł������悤�ɂ��v���܂����A�v�̓J�[����c�@�C�X�Ȃ���Ƃ��������́A���Ȃ��Ƃ������Y�ɂ͓��Ă͂܂肤��悤�ɂ��v���܂��B���̓J�����{�̂̂���ł������̂����m��܂���B���ɐ\���邱�Ƃ́A�R���^�b�N�X�����Y�͒m��Ȃ�����ǁi�c�@�C�X�����Y��p��������R�V�i�̂��m��Ȃ�����ǁj�A�h�C�c�ŊJ���v���ꂽ�����Y�ɂ͓Ǝ��̂��̂����邾�낤�Ƃ������Ƃ��炢�ł��B�ł�����A�a���R���^�b�N�X�����ǔ���Ȃ������̂͂�����Ǝc�O�ł͂���܂��B�������܂��A������uCONTAX�v�̖��̌䗘�v���Ƃ����Ă��A�����ł����A�J�����ɊS�̂Ȃ��l�����ł́A����ז�̒��Ԃł�������炢�ɂ����~�߂��Ȃ�������ł����ˁB����C�J�E�R���^�b�N�X�_����Ȃ�āA�E���S�N�O�̘b�Ƃ�����������Ȃ��ł��傤�B
�@�J�����}�j�A���������瑲�|�������Șb�́A��X�E�F�[�f���Ȃ�Ă������ł��A�J�������Ă���炵���ł��ˣ�Ƃ����������A��X�E�F�[�f�����n�b�Z���u���b�h��Ȃ�Ă����L�q���ǂ����Ō����āA�ɂ��ۂ��h�C�c�A�A�����J�A���`�Ȃǂł��Ȃ��A�J�����������Ă��钆�ɂ͂��蓾�Ȃ����ƂɃX�E�F�[�f��������A�����Ƙ\�ł��Ȃ��낯�ǂƂ������Q�Ԃ�ɁA�䂪�������������R�Ƃ��錻���ł��B��m���x��Ȃ�Ă����̂͂��̒��x�̂��̂ł��傤�A���̒��ł́B
�������Ⴂ�܂���
�@Bessa R3A�A�������Ⴂ�܂����B
�@���炽�߂Ċm�F��������A�Ȃ��5�N�O�̃t�B�������������܂܂ł����B����ȗ��A�V���b�^�[����Ă��Ȃ������킯�ł��BDPE�ɏo���āA�܂������ƌ����͂ł��܂������A�����ɂ��̃J�����̏o�Ԃ��Ȃ����A�^���X�̔�₵�ɂȂ��Ă��邩�A���炽�߂ď\�����o�������܂����B
�@�Ȃ�̂���̂Ƃ��炻���Ȃ��Ƃ����ɂ��Ă݂Ă��A���Ǔ��X�f�W�J�����g���Ă���킯�ŁA�t�B�����J�����̏o�Ԃ͂���߂Č����Ă��Ă��܂��B������A����Ⴀ�t�B�����ţ�ƂȂ�A���ꂱ�ꂠ��u���[�j�[�t�B�����@���g�����A�����������t�@�ł���܂��āA�����Ȃ����35ML��FF1s�̂悤�Ȓ����^��V���v���J�������A�@���B�e�p�ɉ��ɔE���邭�炢�ł��B�����Y�����̃����W�t�@�C���_�[�@�̃A�h�o���e�[�W�͂قƂ�ǂ���܂���B
�@������ƋC���������̂��Ă��܂��A���̈���ł��̍���������������A�茳�s�@�ӂɂȂ��Ă������Ƃ��ẮA��ނȂ����f�ł�����܂����B�قڗ\�z�ʂ�̔��l�ł������̂ŁA�s���͂���܂���B�{�̂ƃ����Y�̔��l���قƂ�Ǔ����������̂́A�������ނȂ������ł��傤�B
�@���ꂼ��̃����Y�̂�݂����悤�Ǝv���A�ǂ����Ă����t�ɗ���܂��B�����W�t�@�C���_�[�Ń{�P�������Ƃ��A��������������Ƃ炦�悤�Ƃ����̂͐_�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B���C�J�ȗ��A�����W�t�@�C���_�[�@�̓t�b�g���[�N�����X�i�b�v�����Ȃ̂ł��傤���A����͂��܂̎��ɂ͂قځA�R���p�N�g�f�W�J���̖����ł��B���̂����A���C�JM�����YL�����Y�ȂǂƂ����_�̗̈�̂������Ă��܂���AR3A�̓��ӋZ��p����@��͂���܂ł��A���ꂩ����Ȃ������ł��B
�@�Ƃ����킯�ŁAR3A�{�̋y�у����Y�W�Ȃǂ��܂Ƃ߂Ĕ����Ă��܂��܂����B��P�[�X��������A�����͔������܂���Ƃ����̂ŁA���������������Ă�A�P�[�X���������Ă��Ă����傤���Ȃ�����Ƌޒ�v���܂����B���̖{�̂̂��܂��ɃP�[�X������ł��鎟�̔�����͍K�^�ł��傤�B
�@�Ƃ����킯�ŁA35mm�����W�t�@�C���_�[�@����ɂ��邱�Ƃ͓�x�ƂȂ��ƒf���ł��܂��B������ƍ������Ɨ��A�Ӗ��Ȃ��ґ�ł���܂����B�����̎ʐ^�࢈�e��ƂȂ�܂����B
�@���̎����A���������ɢ�����Ă�������Ƃ́A���̈�N�Ԃɔ������䐔�Ƌ��z�������ƕ�����Ă��܂��B����ȂɃ[�j������͂��Ȃ��A�܂����X�ɃJ�������������͂����Ȃ��̂ɁA���������ǂ������Ƃ�����ł��傤���ˁB
 |  |
�@�����Ƃ��ے��I�Ȃ̂��A���̃j�R��FM3A�ł����B�����A�j�R���̓t�B�����J�����̐����ł���ɓ��ݐ�A�قƂ�ǂ̃��f�����s�ꂩ���������܂����B�f�W�J�����̓{���̗��������A�������Ȃ����f�ł��傤�B���̂��߁A�j�R����SLR�@�̉��i�͒��Îs��ő����ɗ��������Ă����̂ł����A�l�C���W�߂Ă����̂�����FM�ł����B�������AAF���̑O�̃}�j���A���@�AAE������̂��Ȃ��̂��Ƃ����悤�ȌÓT�I�ȃ��J�A�����������ďd���ď�v�ȃj�R���̈��t�Ƃ����n���̂����ł͗�O�I�ɏ��^�ŃX�}�[�g�A�������l�C�̑�������ł������̂ł��傤�B
�@���߂ɁA�ꎞ��FM3A�ȂǐV�i�̎���������Â̒l�̕��������悤�ȁA���@�v���~�A���̗l�������悵�܂����B����ŏ��X�ׂ����l�����������ł��傤�B
�@�����g�͂ƌ����AU2�Ńj�R����SLR�̋���ȉ������ɓ��荞��ł��܂����Ƃ͂����A�������AF�̐��E�ł��B�ł����炻�̂܂܂Ȃ�A�}�j���A���@�̗̈�ɓ��ݍ��ޗ��R������܂���B�����ă��g���ɑ���̂́A��͂�j�R���ւ̒��N�̑A�]����p���Ă����ƒf�����ׂ��Ƃ���ł��傤�B
�@���ÓX�̓X���ō����l�D�������Ă���FM3A�̈�Q�A����������Ȃ���܂����߂����Ă������X�A�������ɁA���X�l��������n�߂��^�C�~���O�ŁA�����������������Ă��ɔ����Ă��܂��܂����B���̒l�i��99,800�~�ł�����A�܂��V�i�̔̔����i�������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���܂���v���A���Ȃ�����Ȕ������ł��B�����Ă��܂ł͂��̔��l���x�ɉ������Ă���̂ł�����B
�@��������ɂ���A�����肷��{�f�B�A���ɂȂ��ނ������ƃo�����X�A�悭�ł����}�V���̎������`����Ă��܂��B�������j�R����Ai�����Y������Ȃ��Ƃ����܂��A�����Y�Q�͂��̍����瑊���ɖ\�����Ă���A1���~�ȉ��œ���ł����̂�����܂����B�����A�l�i�ɂӂ��킵�������̏�Ԃ͂悭����܂���ł������B
�@���ۂ̂Ƃ���A���̎g�����ł́A��͂�FM3A�̂悤��35mm���t�A�������}�j���A���@�̏o�Ԃ͂قƂ�ǂ���܂���B����ł��Ȃ��AFM3A�ւ̐M�̂悤�Ȃ��̂ŁA�����Y�����ł͂Ȃ��A�f�[�^�o�b�N�A���[�^�[���C���_�[�ATTL����X�g���{�Ȃǂ����ÓX���Ō����A�����Ă��܂��܂����B�ł�����AFM3A���t���Ɋ������鏀�������͐����Ă���̂ł����A���Ă��̋@�����Ă��Ȃ��̂ł��B����͂�́A���e���ł��ˁB
�@�j�R��FM3A�͓d�q���䥋@�B�����p�̏c���胁�^���t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�E8�`1/4000sec�ATTL�����i��D��AE�A�{�̂̏d����570g�ŁA�j�R���ɂ��Ă͗�O�I�Ȍy���ł��B���[�^�[���C���_�[������ƁA�����y���ɓ����܂��B
�@���ꂩ���N���炸�̂̂��A����܂������������Ŕ����Ă��܂����̂��A�j�R����F100�ł����B�����Ă���͑吳���A���܂Ɏ���܂ŁA�����Ă���35mm���t�@�ł��B
�@���ꂪ���̂Ƃ��A���ÓX�̓X����59,800�~�������̂ł���B1998�N�̔��������́A��]�������i190,000�~�������̂ł��B1/3�ȉ��ł��B��{�f�B�̃S�����l�`�����Ă��Ă͂��܂������A���܂��Ƀf�[�^�o�b�N�������Ă��܂����B
 |  |
�@�Ƃ������AF100��35mm�J�����̎��͂��ĔF�������Ă����}�V���ł����BAF�J�����ł�����ŐV��AF�j�b�R�[�������Y���f�W�C�`�Ƌ��p���邱�Ƃ�����܂��傤�B�摜�̎ʂ肪����܂ł�35mm�ƒi�Ⴂ�A�N�₩�Őꂪ���Q�Ȃ̂ł��B���邢�͂��ꂱ�����j�R���̓`���Ȃ̂ł��傤���BAF�A���C���_�[�����A���x�K�ȃ}���`�p�^�[��AE�E�V���b�^�[�D��A�i��D��A�v���O�����A30�`1/8000sec�t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�A1/250�ŃX�g�{�������A�����������e�@�\�͓������̃f�W�C�`�Ƃقړ����ł��B�ƌ������A��������f�W�C�`�ɈڐA�����̂ł����A�e����n��O���b�v���܂߁A�܂����������g������ł�����܂��B
�@F100�̂قڗB��̖��́A�d�����P�O�d�r�ł��邱�Ƃł��傤�B�啔���̃f�W�J���ƈႢ�A��p�[�d�r���g��Ȃ����Ƃ́A�ǂ��łł��d�r����\�Ƃ������ւ͂�����̂́A���̐}�̂ƃ��C���_�[������x����ɂ͓��R�����̓d�͂�����A���������ĒP�O��4�{�g�p�ŁA�Ȃ��Ȃ�̂��������̂ł��B���̕��d�����A�g�p�����d�r�̏��Ղ��C�ɂȂ�܂��B
�@�P�O�ȊO�A���`�E���d�r��p����z���_�[��j�b�P�����f�[�d�r���g����p���[�o�b�e���[�p�b�N���ʔ��ł���悤�ł����A���܂��딄���Ă��Ȃ����ǂ��ɂ��Ȃ�܂���B���̍��͂܂��A�s�̂̃}���K���d�r��A���J���d�r��p����̂��J�����ł��嗬�ł������Ǝv���̂ŁAF100�����̂��Ƃł͂���܂��A���܂ƂȂ�ƕ֗����ƌ��E�̗��ʂ�����ƌ��킴��܂���B
�@�j�R���͍Ō�̃t�B����SLR�̎���A����F�Ȃ����O���n�A�ꌅ�n�A������FM�n�Ƃ�������������Ă��܂����BF�ꌅ�n�������A�j�R��F�ȗ��̍Ŏ嗬���Ȃ��Ă����̂ł��傤���A���܂�ɑ傫���A�d���Ƃ������ׂ͂���܂����B�v�����[�X�̃w�r�[�f���[�e�B�[�}�V���ɓO���Ă����̂ł��傤�B��������A���^�y�ʉ���FM�n�����܂�A�����F�ꌅ��AF�����o�āA����̕��y�@���Ƃ��Ă�F�n���o�Ă����̂��Ǝv���܂��B���̗���̍ŏI���B�_�ł���F100�́A���̎����Ƃ��ėD�ꂽ�����`���Ǝ�������̂ł��B
�@�ł�����AF100�̓f�W�^������ɂ����Ă���r�I�����A���������Ă���Ǝv���܂��B����ŎB�������J�̍��ȂǁA�悩�����ł��ˁB
�@����Ȃ̂ɁA���Îs��ł͂���ɔ����ȉ��ɒl���������Ă���A�����܂ŗ���Ǝ₵������ł��B
�@�w���͑O�サ�܂��B�܂�A2007�N�ɂ͂����ɖ���������������ł��ˁB
�@������u���[�j�[�@�ł��B�����āA�v���Ԃ�̘Z�Z���A��{�̓����W�t�@�C���_�[�̌ÓT�I�ȃX�^�C���ł��B�}�~������̑�q�b�g�Ƃ����}�~��6�̌���łƂ����G�ꍞ�݂ł����A�����炪�X�v�����O�J�������̂��̂ł������ɑ��A������͒������̃����Y�������A���`�̃{�f�B����ۓI�A1989�N�ɐ��ɏo���j���[�}�~��6�A���̉��nj^��1993�N��MF�ł��BMF�́A�A�_�v�^�[��35mm�t�B�������g����A�}���`�t�H�[�}�b�g�Ƃ������Ƃ炵���ł����A�������͂Ȃ����A�K�v�����ʂɊ����܂���B
�@�}�~���͂��̃f�U�C���E�\�����D���Ȃ̂��A�̂��ɂ̓}�~��7���o���Ă��܂��B�}�~��7�͒������ł͂���܂��A�قƂ�Ǔ����O�ςł��ˁB���̓����́ASLR�ł��Ȃ��̂Ƀ����Y�������ɂ����Ƃ����Ƃ���ɂ���܂��B���̎d�|���������ɂ��}�~���ŁA�}�~���v���X�ȗ��̃M�~�b�N�̂悤�ł��B�j���[�}�~��6�ł̓����Y��50mm�A75mm�A150mm�̎O�{�����A������������������낦�܂����B
 |  |
�@��������Ǝv�����̂́A��ʂ肪�悢��Ƃ������]����ł����B����ɂ��ẮAF3.5/75mm�����Y�t����105,000�~�Ƃ����l�i�͂悷���A����Ȃɂ�����قǂ̂��̂��Ɨ����܂��傤�B����ɁA�v���X�`�b�N�ޗ��𑽗p���Ă���炵���̂ł����A�{�f�B������890g�Ƃ��Ȃ�d���̂ł���B75mm�������1.14kg�ł��B����������āA�����Ďg�����肪�����Ƃ͌����܂���B���ɂ̓����Y�����͊���Ȃ��Ɗ��������A����Ă���͂��ł������Y��Ă��܂����ŁA�Ȃ��Ȃ���J�������Ă���܂��B�����Y�V���b�^�[�@�̃����Y���ƌ������Ă��܂��̂ł�����B�t�B���������̂����Ȃ�ł��B
�@����ł��A�D���ȂЂƂ͌��\���܂��B����̂��ꂱ���������l����ɁA���܂�X�i�b�v�����ł��Ȃ��A���i�⌚�����B��Ɍ����Ă���ƌ�����̂����m��܂���B���ہA����ŎB���������ʐ^�ȂǐF�ʂƖ��Â̕`�ʂɗD��A���]�������܂��B�t�ɁA���傤�т̃f�W�J���̉摜�����Ⴟ������̂����m��܂���B
�@�����W�t�@�C���_�[�ł̏œ_���킹�͐������ɂ����ł��B���ɁA���������Y���g���ƌ����Ƀt�@�C���_�[������R����̂ɂ́A����Ȃ��l�͋����܂��傤�B�����}���邽�߂ɁA��p�t�[�h�ɂ͑����J�����Ă���قǂł��B
�@80�N��ȍ~�̃J�����ł�����A�I�o�v�A���̍i��D��AE�ɂȂ��Ă��܂��B�����A�t�@�C���_�[����SPD�Ȃ̂ŁA�I�o�̐��x�Ȃǂ͂��܂���҂ł��܂���B���������Y�Ƃ��W����܂���B�����������Ƃ����܂�C�ɂ��Ȃ��C�����ŘI�����Ԃ�i����l����悤�ȎB���������Ƃ������Ƃł��B��I�ɁA��������y���ރN���V�b�N�ȃJ�����ƌ����܂��傤�B����ɂ��ẮA90�N��̓o�ꂪ���������I�[�o�[�^�C���ł����B
�@�t�B�����J�����ւ̂������́A���肪���Ȃ��ƂɁu���Y�Ō�̓��t�v�}�~��C330�̓���Ƒ����Ȃ�܂����B�قƂ�ǂ̃��[�J�[�����t���炳�����Ǝ���������Ȃ��A���̉��j���[���C�t���b�N�X���u�������t�v�Ŋm�łƂ����n�ʂ�����Ă�������ŁA���ł̓}�~�����u�����Y�������t�v�ŌǗۂ��ێ��������Ă����̂ł��B�Ȃɂ��A����}�~��C�̓o���1957�N�Ƃ���Ă��܂�����A�ȗ������������j�ł����B������A1994�N�Ŕ̔��I���Ƃ����܂��B
 |  |
�@���t�͂����Ƃ��S��������}���A���{���[�J�[�̃h�����������̂ł����i�j�R����L���m���͂���܂���ł������j�A���t�̖u���A����35mm�t�B�����A�y���^�v���Y���g�p�̐����摜�t�@�C���_�[�A�N�C�b�N���^�[���~���[�̗p�ŁA��������ɓ��t���������Ɏ���A1960�N��ɓ��t�͑啔�������Ă��܂����̂ł��B�t�@�C���_�[�����Y�ƎB�e�����Y�̂������̃p�����b�N�X�Ƃ�������������܂������A��͂茈��I�Ȃ̂̓����Y�����̖�肾�����ł��傤�B�����W�t�@�C���_�[���낤�����t���낤���A�Ƃ������u�t�@�C���_�[�ƎB�e�����Y���Ⴄ�v�䂦�A�u�B�e�����Y��ʂ��Ďʂ�摜���̂����Ċm�F�ł��Ȃ��v�̂ɑ��A���t�ő�̗��_�́A�����I�ɂ͂ǂ�ȃ����Y�ɂ��Ă��A���̉摜���~���[�łق��̕����ɓ����t�@�C���_�[�Œ��ڌ��Ă��邱�Ƃɂ���܂��B
�@���t�͎B�e�����Y�ƃt�@�C���_�[�����Y���ʁA������������Ă��t�@�C���_�[�������ʂ����Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�����ꏏ�Ɍ��������Ⴈ������Ȃ����Ƃ����̂��A�}�~��C�̔��z�ł����B���R�����Y�����ɂ́A���̊Ԃ̎Ռ��̖��A�V���b�^�[��i��Ȃǂ̃��J�̘A���̖��A�������������Y���ӂ̌��R��̖��Ȃǂ�����܂��B������\���Ƌ@�\�Ɛ��x�ʼn������Ă��܂����Ƃ����̂������ɂ��}�~���I�ł��B�����悤�Ȕ��z�������Y�V���b�^�[�J�����ɂ��������̂ł�����B�����āA�p�����b�N�X����J���t�@�C���_�[�Ɏ����ꂽ�Ƃ����킯�ł����A������̓����Y�̌J��o���ɂ��킹�ăt�@�C���_�[��ʏ�ɖ_�������A���ۂɎʂ���E�����������݂Ƃ��������Ȃ̂ŁA���܂芴������قǂ̂��̂ł�����܂���B���̃t�@�C���_�[�������\�Ƃ����A�V�X�e���J�����̋ɒv�ł��B
�@�����������J�ɂ͐���������Ă݂����Ȃ�܂��B�g���āA�g���āA���܂��l���������݂����̌����Ă݂����Ȃ�܂��B�����������ʂɂ���A���ǂ��A�����Y�������t���g���Ӗ��͉ʂ����Ăǂꂾ������̂��A�ǂ��l���Ă��傢�ɋ^��Ȃ̂ł����A�����܂ł����Ƃ܂����������Ĕ����ٓI�u��v�̈���o�Ȃ��ł��傤�B���ۂɂ��̂����@�̂�������@��͂���܂���B
�@�Ȃɂ����Ȃ̂́A�悭�l����ꂽ�����݂����ɁA���R�ɑ傫���d���@�̂ɂȂ��Ă��܂������Ƃł��B�܂��t�B�����̕��ʐ��m�ۂ̂��߂ɁA�t�B���������L���^�ɋȂ����A�����ɂ����̂ŁA�]�v�Ƀ{�f�B���傫���Ȃ�܂����B��123mm�~����171mm�A80mm�����Y�t�ŏd��1.65kg�ł�����B�������r���[�t�@�C���_�[���J���A�w�͂����ƍ����Ȃ�܂��B���t�͂��܂��₱�������J��d�����i���Ȃ��̂ŁA��r�I�y���A���ۃ��V�JMat124G��1.08kg�������̂ł��B�Ō�܂Ő����c�������[���C�t���b�N�X�̏d��������Ȃ��̂ł��B���������Y�Ȃǎ����Ă����A����ɏd�������������܂����A���̂��������Y�����̑���͂��Ȃ��ςł��B�菇��������x���G�ŁA��߂�ꂽ�悤�ɂ��Ȃ��ƃV���b�^�[���~��Ȃ��A���삪��i�߂Ȃ��A�������Ռ����Ȃ��܂܃����Y�����O�ꂽ��A�A�E�g�ɂȂ����Ⴂ�܂�����A�����Ă悢�o�l�̗͂œ�{�̃����Y�����������Y�����{�f�B�ɌŒ肵�Ă���̂ŁA������O���ɂ͂��Ȃ�̗͂�����܂��B�t�b�g���[�N�y���g�����ɂ͌����Ă��܂���B
�@�����̓��t�ƈႢ�A�s���g���킹�ɂ̓����Y���������O�S�̂��A�֕����g���A���b�N�s�j�I���őO�ɌJ��o�������ŁA���̃M�A�����{�f�B�O�������̃m�u�_�C�����̉�]����ʑ̋����Ɉ�v�Ƃ��������ɑ�ςȂ�肩���A���̂Ԃ�K�^���Ȃ��A���m�A�����đ傫�ȌJ��o����80mm�����Y��35cm�܂ŋߐڎB�e�ł���ȂǁA��ςɋÂ�������ł��B�������A���������ߐڎB�e������̂͂������t�̓ƒd��ł������킯�ŁA���t��C330�������܂ł�����Ăǂ�����̂��A���܂�Ɏ�I�Ȃ���ł������Ɛ\������܂���B�}�~���͔w�L�т��āA���̃V���[�Y�Ƀy���^�v���Y���t�@�C���_�[�A�|���~���[�t�@�C���_�[�܂ŒA����ɘI�o�v�����������ȂǁA�����u�ǂ����A���t�ɕ����Ȃ����v�Ƃ����C���������ӂꂩ�����Ă��܂����B������Ƃ˂��B
�@���̃��J�̂����܂�ɖ������Ă��A�����Ƃ��}�~��C330�₻�̊ȈՌy�ʉ���C220�͒��ÃJ�����X�̓X���������\�I��ŁA���������Y��e��p�[�c�����ꂱ�����ł������̂ł����B�܂����ꂾ���A������l�Ԃ����������Ƃ������Ƃł��傤�B�Ȃ��Ȃ��g�����Ȃ�����̂ł�����܂���B�߂���͂���ȂɌ��Ȃ��Ȃ�܂����B�ΏƓI�ɁA���[���C�t���b�N�X�͈ˑR�X���̖ڋʏ��i�Q���\�����A���C�J�ƂƂ��Ɍڋq�̗�����U���Ă���܂��B
�@����C330S�́A�Ō�̂���̃��f���ł��B�{�f�B�Ƀv���f�ނ����A�y�ʉ���}�����i����ł��j�A�s���g���킹�m�u�_�C�����Ƀ��b�N�@�\�������Ȃǂ����邻���ł��B1993�N�̍Ō�̂���ŁA�{�f�B��]�������i��66,000�~�ł����������ȁB����2008�N�ɔ������̂́AF4.5/180mm�̖]�������Y���t���Ă���59,800�~�ł����B�������A�Ō�܂ŘI�o�v�͓��������܂���ł����̂ŁA����C330S�̂��߂ɁA�����ȃV���[���t���̂��܂����B���̌�AF3.5/105mm�����Y�i����̓t�@�C���_�[�����Y�ɂ��i�肪����j�AF4.5/55mm�AF3.7/80mm�i����͎��͌Â���ŁA�V���b�^�[�̃Z���t�R�b�L���O���Ȃ��A�蓮�Z�b�g�j�̊e�����Y���������낦�܂������A�o�Ԃ̕������Ȃ����ł��B
�@���܁A���t�ɂ������A������̂悤�ȃ��[���C�t���b�N�X���A���͓��ł��������A�i���������Ȃ��ƌ�����V�[�K���i�C���j���炢�����V�i�ł͂���܂���B���ƌ����āA�������͓��X�Ƃ��Ă�����̂́A����ς�}�~��C330S�ł͋C�y�ɎB��ɂ��o���܂���B����ȊO�̓��t�݂͂ȑ����̃��[�g���@�ŁA���Âœ��肵�Ă��ʂ����Ďʐ^���B���̂����܂��S�z�ł��B�܂����������ĔY�߂�Ƃ���ł��B
�@������Ⴂ�܂����A�Ƃ����Ƃ���ł��B�}�~���ւ̋`�����Ă���Ȃ�����ǁA���N�̃}�~��645�g����Ƃ��ẮAAF�������̂����ڂŌ��߂�������ɂ͂ǂ����Ă��䖝�ł����A��������o���Ă��܂��܂����B
�@�������A����͂��Ȃ��葽�����̂ł����B�����Ďg���Ă݂Ă悭�킩�����̂ł����A�]���̃}�~��645�Ƃ͊�{�I�ɓ������C����̂��̂ł͂Ȃ��Ƃ����⌵�Ȏ����ł����B�Ȃɂ��A645�̃Z�R�[���}�j���A�������Y�������I�Ɏg���Ȃ��̂ł��B�������A�J�^���O��͉\�ƂȂ��Ă��邵�A�}�E���g�������Ȃ̂ł����A�ЂƂd��Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B645AFD�ɔ�AF�����Y�����t����ۂ́A�t�@�C���_�[�̃t�H�[�J�V���O�X�N���[�����u�^�C�vC�v�Ƃ����̂Ɍ������˂Ȃ�܂���B���̂����ōi��D��AE�ōi�荞�ݑ�������Ƃ����͉̂䖝�ł��Ă��A���̃X�N���[������肵�A����������Ă݂�ƁA���炢��ƂłƂĂ�����Ȃ����p�ɂɎ��݂�Ȃǂ��蓾�܂���B�����Y�J��������w�����A�s���Z�b�g�Ȃǎg���āA���ܕt���Ă���̂������Ɏ��O���A���̂�K���ɑ��U�Œ肵�悤�Ǝ��݂�A�����Q��܂��B�܂�A�����I�Ƀ{�f�B��AF�����Y�A��AF�����Y�Ɏg��������ȊO�����Ƃ������ƁA����Ȃ�645Pro���g�������̂ŁA645AFD��AF�����Y��p�ɂ����Ȃ�Ȃ������݂ł��B
�@�}�~����AF�����Y�����Âł��Ȃ�l���ꌃ�����������̂́A�ŋ߂͊O�������Ő��i�헪���]���A�����Y�����`���������f�����C���ɐ�ւ��Ă��܂��܂����B�������AF�����Y�̓}�j���A�������Y�ȏ�ɏd�����̂ł��B�����645AFD�ɃY�[�������Y�Ȃ��邩�A��p�Əd���̗����ł����낢�ł��܂��܂��B
 | 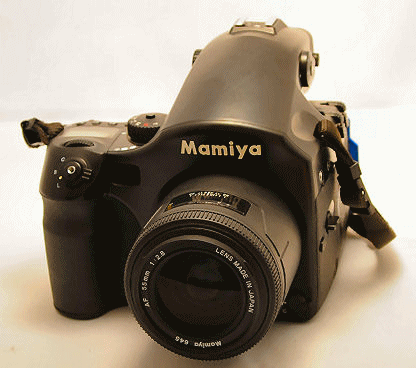 |
�@�ȉ����[�J�[�̐ӔC����Ȃ��̂ŁA����������Ă��؈Ⴂ�ł����A���̂悤�ɂ��낢��ȑ��삪���݁A�܂��\�������Ȃ�f�W�^�������Ă���{�f�B�ɁA���ÓX�Ő��������t���Ă��Ȃ������̂ł��B�߂���͂��낢��ȃ��[�J�[���A�Ƃ��ɐ������~�̕i�܂Ő������ނ�web�T�C�g����_�E�����[�h�\�ɂ��Ă���̂ŁA�������Ȃ��̒��Õi�ł������Ďg���ɕs�����Ȃ��̂ł����A�}�~�������͈���Ă��܂��B����ȁu�e�ؐS�v���Ȃ��A�Ȃɂ���Ǝ��̂��s���`�A����ł�����}�~����web�T�C�g�͂��e�����̂��̂ŁA���炭�͔��������V���i�̏���ڂ�Ȃ��قǂł����B�ł����疳�_�A645AFD�̐������Ȃ�������܂���B
�@�������������̐��X���ɏ��z���A645AFD���g���Ă����ׂ����A�Y�݂܂��B�������}�~����645AFD�U�A�V�Ƒ������Ŕ����AAFD�iAF�̂��Ƃ̓��ڂł����j��ꡂ��ȋ������f���ɂȂ��Ă��܂��������A�O����Ƃ̎P���ŁA645�V���[�Y���̂��������悤�A�f�W�^���o�b�N�ƈ�̉�����645DF�i�܂�PHASE ONE P21+645AF�j�̕��Ɋ��S�Ɏ������ڂ��A����ɍ�����AF�����Y�����āA�v���̕��X�g���ĉ������Ƃ����p���ł��B���Ⴀ645DF�����܂��傤���Ƃ��������āA�����Y�t�Ŏ���100���~�߂������ł���B
�@���ɂ�645AFD����ɂ��邱�ƂŁA�}�~��645�̃��C������AF���A�f�W�^�����ɃV�t�g�����悤���Ƃ����l��������܂����B�������A���̃}�~����645�̃}�E���g��@�\���g���A���ɏo�����u�����v�f�W�C�`ZD�͊��S�Ȏ��s��ƌ����A�J�������̍���甭�����啝�ɒx��A�}�~���̌o�c��@���������������łȂ��A�l�i�͔n������100���~�ȏ�i���݂͎���125���~�A�������������I�I�I�j�A�������r���g���ɂ������̂̂悤�ŁA�}�~���{�Ђ�645ProTL�̏C�����˗������ۂɁA���łɂ���ZD�̂��Ƃ����ɂ�����A�u�V���[�g����ɂ͂����߂ł��܂���v�ƌ����Ă��܂��܂����B645AF�̃��C������o�Ă���DF�������̒l�i�ł��B����Ȃ甃���������645AFD�Ƀf�W�^���o�b�N������Ƃ��������āA������Œ�100������500���~���炢�܂ł����ł��B�V���[�g�ɂ͎�������o�܂���B�������������͖̂{���v���p�Ȃ̂ŁA���Îs��ɂ����߂����ɏo�܂���B
�@��������645�̃f�W�^�����͊��S�ɖ����Ƃ킩��A���̃��C���͑��H�ɓ����Ă��܂��܂����B��������ȐF�C�͎̂ĂāA�f�p�Ƀu���[�j�[�t�B�����ɂ�������Ă���������Ƃ����Ƃ���ł����A�������f�W�J���Ɋ��ꂽ�g���A645�ł�AF�̕����g���₷���Ȃ��Ă���͎̂����ł��B������645AFD�n������ȏ�u���W�v������C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����W�����}�ł��B����ł��A�t����80mm�̂ق��AAF�����Y150mm��55mm�������܂������ǁB
�@�}�~��645AFD�́A�y���^�v���Y���t�@�C���_�[�����A�d�q����c���胁�^���t�H�[�J���v���[���V���b�^�[�E30�`1/4000sec�A�������[�h�ύX���I�o�v�����E�i��D�楃V���b�^�[�D��E�v���O�����ؑ�AE�ATTL�ʑ������o��AF�ATTL�X�g���{����A���C���_�[�O���b�v�����ł��B�t�B�����o�b�N�͎��O�����ł����A645Pro�Ƃ̌݊����͂�����Ȃ��悤�ł��B�d����1.7kg������̂ł����A�O���b�v���t���Ă��邹�������܂�C�ɂ͂Ȃ�܂���B����ɂ��t�B�����ɎB�e�f�[�^���ʂ����ގd�g�݂����Ă��܂����B
�@645AFD��AF F2.8/80mm�����Y�t��92,000�~�Ŕ����܂����B2001�N�̔��������A��]�������i286,650�~�����������ł��B���`���ł��ˁB�����͂���܂荂�����̂Ȃ��A�f���C�Ȃ��{�f�B�ł��B�܂������Ă���Ă��܂��B�������}�~�����@�̕������߂��̂Ăė����������悤�Ȏ����ł��B
�@�Ӑ}�������āA�t�B�����J�����̐V�i���w�������̂�����ł����B
�@���܂���t�B�����J��������Ȃ����낤�Ƃ��������������ĐU���A�������z�̂����Ƃ����̂͂����\�����̂��̂ł������A�u�t�B�����J�����Ō�̂��������v�ɂȂ邾�낤���A����d���ł܂Ƃ܂��������������̂����������ɁA������Ă��܂�����킯�ł��B�������A�u���܂ǂ��v�ɃX�v�����O�J�������̂��̂��o�����Ƃ����x�m�t�B�����̢�p�f��ւ̌h�ӂ�����܂��B��z�����m�̣�X�v�����O�J��������ɂ��邱�Ƃ̂Ȃ��������Ƃ��ẮA�~����������ł���ˁB�������A����܂����܂܂ł����������Ƃ̂Ȃ��Z�����Ȃ̂ł��B
�@�m��l���m��A�����g���ȍ\�z�̑㕨���f�W�J���S���A�t�B�����J������Ő��O��21���I�ɏo�����̂́A�قڗB��ƂȂ����t�B�������[�J�[�E�t�W�Ȃ�ł͂���܂����A���Ђ͈ȑO�ɔ�����GA645Zi�̂悤�ɁA�u���[�j�[�t�B�����g�p�J�������p���I�ɏo�������Ă��Ă��܂����B���̃}�j�A���킸���Ȃ��炢��A�܂��c�Ǝʐ^�̕��������A����������c���ꂽ�j�b�`�Ȏs�꣑���̂��Ƃł��傤�B�Â��l�ԂƂ��Ă͗L��������܂��B�������A�����Ȃ��炢�ɃX�v�����O�J�������̂��̂Ȃ�ł��B���܂ǂ��֕��g�p�̃J�����Ȃ�Ă����̂��A���ꂪ���[�J�[�ɂ͍ő�̕ǂ������悤�ŁA�֕��̑f�ށA�����Ă�������H�ł���E�l�{���ɋ�J�����炵���ł��B
�@���������̋t�]�̔��z�͂������ł��ˁB�֕��̗p�̂������ŁAGF670�͘Z�����Ȃ̂ɐM���������قnjy���A�܂��܂肽���߂Όg�тɂ��s�ւ���܂���B���̏d��1kg�A����67mm�������ł��B�X�v�����O�J��������ɂ͋�J�̎킾���������ȁA�����W�t�@�C���_�[�ƃ����Y���̃s���g���킹���J�Ƃ̘A�����y���N���A�[���Ă���A�Ȃɂ���肠��܂���B�B�����������̂́A����������������ɍ��킹�Ă����Ȃ��ƃt�H�[���f�B���O������Ȃ����ƂŁA�Ȃ�ł������̃f�W�J���Ɋ���Ă��܂��Ă���ƁA���X�˘f�����Ƃ�����܂��B
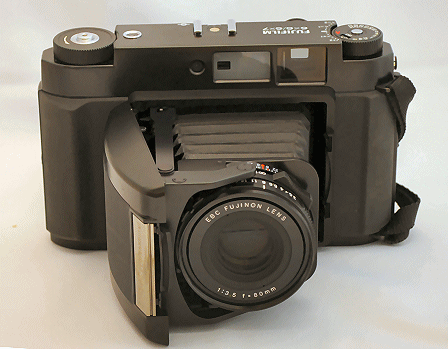 |  |
�@�B���Ă݂�A�������Z�����ŁA�摜�̔��͂��܂���i��ł��B���̃t�B�����摜���X�L���i�[�ŃX�L�������ăf�W�^��������A�t�Ƀf�W�J���摜�Ƃ̊i�̈Ⴂ�������������܂��B�ׂ����Ƃ���܂Ţ�l�H�I��Ȃ��炢�Ƀ����n������f�W�J���摜�قǂ̔��ׂ��͏o���Ȃ����A������ƊÂ߂ł͂�����̂́A��ʑ̢̂���ݣ�A���Â̕`�ʁA�F�̐[�݂Ƃ��������̂ł̓t�B�����Ȃ�ł͂Ə\�����������Ă����̂ł��B�f�W�J���͎��ɂǂ����A�Z�������ƞB���ł͂Ȃ��Ă���Ƃ肪����A����ς�ʐ^�炵���ʐ^�Ƃ����̂ł��傤���B�֕��͓������˂��y�����A�摜�̃N�I���e�B���グ�Ă����̂������ł����A�����͎��̗͂Ƌ@��ł͔������������Ƃ���ł��B
�@���������킯�ŁA����GF670�͂��Ȃ芈�Ă���Ă��܂��B�����Ƃ��A�B�����t�B�����œ��v�����邱�Ƃ͂قڂȂ��Ȃ��Ă��܂��܂����B��p�����łȂ��ADPE�̎��Ԃ������邱�Ƃ�����܂��B�����ς�t�B�����̂����ŃX�L���i�[�ɂ����܂��B���ꂶ�Ⴀ�t�B�����̗ǂ��������Ƃ����̂��킩��܂����A�X�L���i�[�œǂݍ��f�W�^���摜�f�[�^�Ƃ����̂��A�f�W�J���B�e�̂Ƃ͂܂��Ⴄ�A�����������Ƃ���ł�����܂��āB���́u�J�������v�̎B�e�摜�Ƃ����̂����ׂāA���ꂼ��̃J�����ŎB�����t�B�������X�L�����������̂ł��B
�@GF670�̎�_�́A��̓Z���t�^�C�}�[���Ȃ����Ƃł��B����͂��������L�O�ʐ^���B��̂ɂ������Ă���Ǝv�����̂́A�����������z�̓��[�J�[�ɂ͂Ȃ��悤�ŁAGF670�̂��Ƃɏo���A55mm�����Y�̃��C�h��GF670W�ɂ��^�C�}�[�͂����Ă��܂���B�������A�O�r�ɍڂ��Ē����ԘI���B�e����ɂ��^�C�}�[�g�p�Ƃ����������͂��ł����A�l���Ă��Ȃ��̂ł��傤�BGF670���Ԃ牺���Ă����āA�݂�ȂŋL�O�B�e�Ƃ����V�`���G�[�V�����͂��蓾��悤�Ɏv���̂ł��B�d���Ȃ��A�ÓT�I�ȃX�v�����O����O�t���Z���t�^�C�}�[�����݂Ă݂܂������A�������̕����������Ă��ăA�E�g�ł����B���ÓX�ł��������̂͂Ȃ�����������A���b�Ȋ������Ă����܂��ł����B�P�[�u�������[�Y�p�̌��͂����Ɨp�ӂ���Ă���̂ł����B
�@�����ЂƂ́A��x��炩�����A�d�r��ŃV���b�^�[����Ă��Ȃ������Ƃ����g���u���ł����B�ÓT�I�ȊO�ς⑀��̊��ɁA�V���b�^�[�͘I�o�v�A���̍i��D��AE�Ȃ̂ł��BAE�͕֗��ł͂�����̂́A����Ȃ�d�r��̍ۂɂ̓V���b�^�[�����삵�Ȃ��悤�ɂ��Ăق��������Ƃ����Ƃ���B��������GF670�̃V���b�^�[�͓��삵���̂��S�z�ɂȂ邭�炢�A�����ɏ��A���슴���Ȃ��̂ł��B���ꂪ�����Ƃ����Ƃ��������̂����m��܂��A�d�r��ł������悤�Ȃ̂���ˁB���ꂾ���̂��̂Ȃ���g���ۂɋC������A�t�@�C���_�[���̕\���ɋC��z��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B
�@�t�B���������グ���V���b�^�[�{�^���Ɠ����̃_�C�����Ȃ̂͑��ʐ����̂ĂĂ���A�Z���T�C�Y������]�v�����グ�ɓ���Ǝ��Ԃ�������Ƃ������Ƃ͔ے�ł��܂���B�������A35mm�J�������l�̃��o�[�����グ�̃j���[�}�~��6�ɂ��āA�X�g���[�N���傫���A���\��ςȂ̂ŁA�_�C���������グ���s�ւ��Ƃ������܂���B�J�����ɖڂ������܂܁A�t�B���������ƃV���b�^�[����𑱂���悤�ȎB����͖{���l���Ă��Ȃ��A�X�v�����O�J�����͂����������̂ȂƂ��������Ȃ̂ł��傤�B
�@�����W�t�@�C���_�[�͌����ׂ����s���g���킹�ɂ͌����ĂȂ����A�{�P���m���߂邱�Ƃ��ł��܂���A���������͈̂��t�ɔC���A�����Y��F3.5�Ȃ̂��܂߂�GF670�͊�{�I�ɕ��i�ʐ^�����ȂƂ������Ƃ͔[�����˂Ȃ�܂���B����ł�����̃t�@�C���_�[�\���͌��₷���A�s���g�����킹�₷���悤�ɂ͊����܂��B�����Y�����Ƃ��������Ƃ�x�O�����Ă���̂ŁA���̕��d�g�݂��ȒP�Ȃ̂ł��傤�B
�@GF670�̐��\�́A�����Y��F3.5/80mm�A�V���b�^�[��B�4�`1/500�̓d�q���䃌���Y�V���b�^�[�A�X�g���{�S�������i�z�b�g�V���[�j�ASPD����f�q���{�f�B�ɂ����i��D��AE�A��ʃT�C�Y�͘Z�Z�A�Z������ւ��\�i�t�@�C���_�[���u���C�g�t���[���A���j�Ƃ������Ƃ���ł��B�Z�Z���ɂ��Ă͂ق��Ƀ{�f�B�������Ă�����̂ŁA�g�������Ƃ�����܂���B�t�B�����̓I�[�g���[�f�B���O�ł͂Ȃ��A�X�^�[�g�}�[�N���킹���Ȃ̂ŁA120/220�t�B�����ɂ�鈳�ؑւȂǁAGA645Zi���́u�ޕ��v���Ă���܂��B�����192,000�~�ł����B
�@
�@�����̕��̂��Q�l�ɁA��L11��̃t�B�����J�����w�����z���v���o���Ă݂܂����B�u897,600�~�v�I�I�ł��B
�@3�N�قǂ̊ԂɁA�����g����������Ƃ������ƁB�������A���̂ق��Ƀ����Y�Ȃǔ�������������킯�ł�����A100���~���y��������̂͊ԈႢ����܂���B
�@�F�j�ł��S�R�Ȃ��̂ɁA����Ɨͣ�͂Ȃ����Ƃ��\���Ɏv���m�炳�ꂽ�E���\�N�̐l���𑗂��Ă������߂��A����Ȗ��ʌ������ł����̂́A��Ȃ���s�v�c�ł�����܂��B�܂��A������������߂̐l���̎��Ƃ��ẮA�����ʂ袈ꐶ�Ɉ�x��̂₯���ς���������邱�Ƃ����肩�A�_�l�������������邩�ȂǂƁA�����ł�����Ɍ��߂Ă���킯�ł��B
�@�ł��A����Ȃ��ƐŖ����ɖڂ������鋰������邩���B���͖��N���N�A���ɐ����Ɋm��\�����A���̂ǁA�t�c�[�̃T�����[�}���̈ꃖ���̋����ɂ��Ȃ肻���Ȋz��lj��[�ţ���ĎQ���Ă���܂��B�����Ȃɋ��������������Ȃ����ǁA�ǂ����āH��ƐS���Q���B�ł�����A30�N���������Ă���A���̂��炢�̒����������A���̐��Ɏ��Q����J�l�͗v��Ȃ�����A�₯���ς��Ŏg��������������A����̋ɒn�A���������Ŕ[�������Ă���܂��ł��B
�@���������A��ł��A�ق��Ƀf�W�J���ɂ��g�������룂ĂȁA�V�̐����������Ă��܂��B�����Ȃ�ł���ˁB�v�Z���邾�ɋ��낵���āA�悤���܂����ȁB
�@���������l�Ԃ��₦�Ȃ�����A���ÃJ�����₳���܂��Ɏ���ł���ˁB�����Ƃ��A���̐�������10�N���炢�Ŕ����قǂɌ����Ă��܂��������ł��B���ɒ��Ãt�B�����J�����̐��ނ͖ڂɌ����邭�炢�ŁA�m���ɂقƂ�ǐV�i�����Y�̔�����Ă��Ȃ��A�ł����碃T�v���C�T�C�h����җ�ɏk�����Ă���A�����Ţ�f�}���h�T�C�h����A���̂悤�ȃ��[�g�����炢�������炸�A���܂�20��30��̂ЂƂł��ƁA���������t�B�����J�����Ȃ�Č������Ƃ��G�������Ƃ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��傤�B��J�����̒��ɂ́A�t�B�������g�����̂����飂ĂȁA������k�Ő��N�O�ɋL������\���I�L�q��������́A�����ɓ������Ă��鍡�����̍��Ȃ̂ł��B���ꂶ�Ⴀ�A���ÓX�������ɂȂ�킯������܂���B�f�W�J���̒��Â�������x�̎s����`�����Ă��Ă��܂����A�V���i���i�����ł܂��l�����范�����������ł́A���ÓX���Ȃ��Ȃ�����܂���B
�@���ÃJ�����₳������Ȃ��A�t�B�����ŎB���Ă��A���܂ł͌����ɏo��DPE��t���ő��Ɍ��Ȃ��Ȃ�܂����B���͎����Ō�������悤�Ȕ\�͂����Ԃ��Ȃ��̂ŁA�X�ɏo���킯�ł����A�₵�����炢�ɏ��Ȃ��A�܂������Ă��Ћ��ɒǂ�����Ă���̂ł��B����͌����̔��f�ł���ȏ�d���Ȃ��Ǝv���Ă��A���܋���Ă���̂́A���܂�̎��v�̌����ŁA�������{���啝�����l�グ�����Ă��Ȃ����Ƃ������ƁB�ꎞ�͎����̃A���o�����X����ADPE��͂����Ԃ����Ă��܂����̂ł����A���ꂩ��͋t�]���ۂ������邩���m��܂���B�����Ȃ�����A��������Ă��Ȃ��A�t�B�����J�����͊��S�ɔ����ٓ���ɂȂ��Ă��܂������B
�@
| U2 | ���l�x�C�V�F���g���z�e�� |
| 645Pro | �ߔe�q�u�s��̋����� |
| 645ProTL | ���s�E�r |
| GA645Zi | ���R�s�ݐ��� |
| R3A | ���l�X�^�W�A�� |
| FM3A | ���l�Ս`�p�[�N�̕d |
| F100 | �ۂ̉Y |
| New6MF | ���������̖��� |
| C330s | ���l���{��� |
| 645AFD | ���������� |
| GF670 | �ˉB���r |
�@�f�W�J�����̋����ƍ����Ԃ�́A���ł��B���ڂ��邩�́A�킩��܂��B
�@�i2013�N7���A�ڂ��܂����j�B
���̌܂��@�@